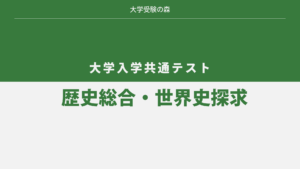解答
解説
第1問
問1:正解③
<問題要旨>
この問題は、19世紀のオスマン帝国で実施された西洋化改革(タンジマート)の内容と、その時代背景に関する理解を問うものです。資料の会話文にある、礼拝の際に邪魔にならない「トルコ帽」をヒントに、改革の性質を読み解く必要があります。
<選択肢>
①【誤】
アは正しいですが、イが誤りです。トルコ帽がつばのない帽子である理由は、イスラームの礼拝(額を地面につける)の邪魔にならないようにするためであり、西洋化を進めつつもイスラームの伝統に配慮したことを示しています。「急速な世俗化政策」という記述は、この配慮と矛盾するため、誤りです。
②【誤】
アが誤りです。「ドイモイ」は、1980年代後半に始まったベトナムの刷新政策であり、19世紀オスマン帝国の改革ではありません。
③【正】
アの「タンジマート」は、19世紀のオスマン帝国で実施された行政、社会、教育など多岐にわたる西洋化改革の総称です。また、イの「イスラームの儀礼に配慮しつつ西洋化を推進」という記述は、本文の「礼拝の邪魔にならないよう、つばが付いていません」というトルコ帽の特徴と合致しています。したがって、この組合せが正しいです。
④【誤】
アが誤りです。「ドイモイ」はベトナムの政策です。
問2:正解①
<問題要旨>
この問題は、図1に描かれた場面(辮髪の使節と洋装の日本人)から、その会談が行われた時期を推定する方法と思考過程の妥当性を問うものです。二つの異なる文化(清と明治日本)の歴史的特徴を結びつけて時期を特定する力が求められています。
<選択肢>
①【正】
方法あ:図1左側の人物がしている「辮髪」は、清が支配下の男性に強制した髪型であり、清の時代(1644年~1912年)の官吏に見られる特徴です。したがって、この風習が見られた時期を調べるのは有効な方法です。
方法い:図1右側の日本人が公式の場で「洋装」をしているのは、明治政府が近代化政策の一環として西洋の服装を導入したためです。したがって、この慣習が始まった時期を調べることも有効な方法です。
時期W:清は辛亥革命(1911年~1912年)で滅亡するため、辮髪の風習はそれまでの時期となります。これは方法あと対応します。
時期Y:明治維新(1868年)以降、近代的軍隊の創設などとともに洋装化が進みました。会談はそれ以降の出来事と考えられます。これは方法いと対応します。
両方の条件を満たすのは、「明治維新(1868年)以降」かつ「辛亥革命(1912年)以前」となりますので、この組合せが最も適当です。
②【誤】
時期Zが誤りです。日本の第一次世界大戦参戦は1914年であり、この時点では既に清は滅亡しているため、辮髪の使節団は存在しません。
③【誤】
時期Xが誤りです。満洲国は1932年に建国された国家であり、清が滅亡した後の出来事であるため、時期設定として不適切です。
④【誤】
時期XとZが両方とも誤りです。理由は②、③と同様です。
問3:正解③
<問題要旨>
この問題は、1860年代のプロイセン(後のドイツ)と日本の関係に関するメモの内容を検討し、当時の国際情勢や国内状況についての記述の正誤を判断するものです。19世紀半ばのヨーロッパと日本の歴史知識が問われています。
<選択肢>
①【誤】
ヴィルヘルム2世がドイツ皇帝として積極的な対外政策(世界政策)を進めたのは、19世紀末から20世紀初頭にかけてです。1860年当時のプロイセンの指導者は、後のドイツ皇帝ヴィルヘルム1世(当時は摂政)であり、記述の時代が合いません。
②【誤】
1860年当時、シンガポールはイギリスの海峡植民地の一部であり、アジアにおける重要な貿易拠点でした。ドイツ(プロイセン)の植民地ではありません。
③【正】
メモにあるプロイセン使節団の来日は1860年です。日本(江戸幕府)は、それ以前の1858年に、アメリカ、オランダ、ロシア、イギリス、フランスの5か国と修好通商条約(安政の五か国条約)を締結していました。したがって、プロイセンとの条約以前に、他国と修好通商条約を結んでいたという記述は正しいです。
④【誤】
安政の五か国条約をはじめ、幕末期に諸外国との条約締結交渉にあたったのは江戸幕府です。朝廷(天皇)は、当初、条約勅許を与えず、外国との交渉の主体ではありませんでした。
問4:正解④
<問題要旨>
この問題は、1890年から1910年にかけての日本と中国における機械製綿糸の生産量と自給率を示すグラフを読み解き、綿糸生産に関する知識とグラフの情報を正しく結びつけるものです。統計資料の読解力と、近代産業史の基礎知識が問われています。
<選択肢>
①【誤】
文あが誤りです。綿糸の生産量を推計する直接的な指標は、糸を紡ぐための「紡績機」の錘(すい)数です。「力織機」は糸を使って布を織る機械であり、綿糸生産量の指標にはなりません。
②【誤】
文あが誤りであるため、この組合せは誤りとなります。
③【誤】
文Xが誤りです。グラフによると、1910年時点の中国の自給率は50%を下回っています。自給率が100%未満であることは、国内生産量が国内消費量を下回っていることを意味します。したがって、この記述はグラフの内容と一致しません。
④【正】
文い:綿糸の生産能力は、紡績機の錘(スピンドル)の数によって測られるため、この記述は正しいです。
文Y:帝国議会が開設されたのは1890年です。グラフを見ると、日本の国内生産量は1890年に21千トン、その10年後の1900年に128千トンとなっています。128÷21≒6.1倍となり、「5倍以上増加した」という記述はグラフから読み取れる事実として正しいです。したがって、この組合せが正しいです。
問5:正解②
<問題要旨>
この問題は、1920年代から1930年代の東アジアにおける「モダンガール」という文化現象を通して、当時の社会状況を考察するものです。パネルに書かれた情報を基に、この時期の東アジアの政治的・文化的な多様性を理解しているかが問われています。
<選択肢>
①【誤】
モダンガールは、欧米の最新の流行を取り入れており、その髪型は一般的にショートカット(ボブカットなど)が特徴とされました。ロングヘアーという記述は誤りです。
②【正】
パネルには、モダンガールの装いが「東京や大阪」だけでなく、植民地であった朝鮮の「京城(現ソウル)」や、外国の支配が及ぶ租界が存在した中国の「上海、天津など」でも見られたと記されています。これは、国や地域の政治的地位(独立国、植民地、租界)に関わらず、都市部を中心に新しい文化が受容されていたことを示しています。したがって、この記述は正しいです。
③【誤】
統監府は、第二次日韓協約(1905年)に基づき、日本の韓国に対する保護国化を進めるために1906年に設置された機関です。韓国併合(1910年)によって朝鮮総督府が設置されると、統監府は廃止されました。したがって、モダンガールが闊歩した1930年代の京城に統監府は存在しませんでした。
④【誤】
女性誌『玲瓏』が創刊された1931年当時の中国は、中華民国です。中華人民共和国が建国されるのは1949年のことであり、時代が異なります。
問6:正解②
<問題要旨>
この問題は、1920~30年代のファシズム体制下のイタリアにおけるファッション政策を扱った資料を読み解くものです。資料から、国家による統制とナショナリズムの強化というファシズム体制の特質を読み取れるかが問われています。
<選択肢>
①【誤】
文いは誤りです。資料には「フランスびいきの消費者がイタリア製品に下す過小評価に対抗」とあり、フランスからの影響を排除し、国産品を奨励する意図が読み取れます。フランスからの影響を歓迎していたわけではありません。
②【正】
文あ:資料は、政府が設立したモード公社が「衣服産業の国内市場の制圧」を目標とし、国産品を支援する必要性を説いています。これは、ファシズム体制という思想・言論統制下で、経済においても国家主義的な政策(国産奨励)が進められたことを示しており、正しいです。
文い:資料の内容から、イタリアのモード公社はフランスのファッションの影響力に対抗しようとしていたことが分かります。フランスの影響を歓迎していたわけではないため、この記述は誤りです。
したがって、文あが正、文いが誤りの組合せが正しいです。
③【誤】
文あは正しいですが、文いは誤りです。
④【誤】
文あは正しいです。
問7:正解④
<問題要旨>
この問題は、20世紀後半のイランで起きたイラン=イスラーム革命前後の社会の変化を、小学校教科書の挿絵という資料から読み解くものです。服装や教室の様子の変化から革命の性質を理解し、正しい時系列と歴史的意義を判断する力が求められています。
<選択肢>
①【誤】
うが誤りです。イラン=イスラーム革命は、国王が進めていた西洋化政策に反対し、イスラームの教えに基づく国家体制を目指したものでした。したがって、「西洋化が推進された」という記述は革命の方向性とは逆であり、誤りです。
②【誤】
あが誤りです。挿絵1では、教師も生徒もヴェールなどで髪を覆っており、男女別学の様子が描かれています。壁にはホメイニ師らの肖像画が見えます。これはイスラーム革命後の様子です。挿絵2では、教師はヴェールを着用せず、男女が同じ教室で学んでいるように見えます。壁には国王(パフレヴィー朝)の写真が掲げられています。これは革命前の様子です。したがって、時代の古い順は「挿絵2→挿絵1」となります。
③【誤】
い、うの両方が誤りです。
④【正】
い:挿絵2は西洋的な服装で男女共学の革命前の様子、挿絵1はヴェールを着用し男女別学の革命後の様子を示しています。したがって、古い順に並べると「挿絵2→挿絵1」となり、正しいです。
え:イラン=イスラーム革命は、パフレヴィー朝の君主制を打倒し、シーア派の指導者ホメイニを最高指導者とするイスラーム共和制を樹立した革命です。「イスラームの教えに基づく共和国が成立した」という記述は正しいです。したがって、この組合せが正しいです。
問8:正解⑥
<問題要旨>
この問題は、第二次世界大戦後の女性の社会的地位向上に関する三つの出来事(ウーマン・リブ、男女雇用機会均等法、SDGs)を、年代順に正しく配列するものです。戦後世界の社会運動や国際的な取り組みの時系列に関する知識が問われています。
<選択肢>
①【誤】
配列が誤っています。
②【誤】
配列が誤っています。
③【誤】
配列が誤っています。
④【誤】
配列が誤っています。
⑤【誤】
配列が誤っています。
⑥【正】
三つのメモを年代順に並べると以下のようになります。
メモⅢ:女性解放運動(ウーマン・リブ)は、アメリカの公民権運動などと連動して1960年代後半から1970年代にかけて高まりました。
メモⅡ:日本の男女雇用機会均等法が制定されたのは1985年(施行は1986年)です。
メモⅠ:「持続可能な開発目標(SDGs)」が国連サミットで採択されたのは2015年です。
したがって、古いものから順に「メモⅢ → メモⅡ → メモⅠ」と並べるのが正しいです。
第2問
問1:正解④
<問題要旨>
この問題は、14世紀半ばに地中海世界で起きた出来事に関する資料を読み、都市名とそこで流行した疫病の名前を特定するものです。資料中の「スルタン」や「アズハル=モスク」といったイスラーム世界のキーワードと、疫病の流行時期から判断します。
<選択肢>
①【誤】
ア、イともに誤りです。
②【誤】
アが誤りです。
③【誤】
イが誤りです。「梅毒」は15世紀末以降にヨーロッパで広まったとされる病気であり、14世紀半ばの疫病ではありません。
④【正】
ア:資料にある「アズハル=モスク」は、エジプトのカイロに現存する有名なモスクです。また、当時のカイロを支配していたマムルーク朝の君主は「スルタン」を称しました。これらの情報から、都市アは「カイロ」であると特定できます。
イ:14世紀半ばにヨーロッパからイスラーム世界にかけてパンデミックを引き起こし、多くの死者を出した疫病は「黒死病(ペスト)」です。資料の「罹患するとすぐに死に至る」「通りや市場が死体で埋め尽くされていた」といった描写は、黒死病の猛威を伝えています。したがって、この組合せが正しいです。
問2:正解③
<問題要旨>
この問題は、前の問題で特定した都市カイロを、14世紀半ば(黒死病の流行時期)に支配していた王朝の特徴を問うものです。マムルーク朝に関する知識が問われています。
<選択肢>
①【誤】
ベルベル人が中心となり、北アフリカとイベリア半島を支配したのは、ムラービト朝やムワッヒド朝です。マムルーク朝はエジプトを拠点としました。
②【誤】
北アフリカに興ったシーア派の王朝で、カリフを称したのはファーティマ朝です。ファーティマ朝はカイロを建設しましたが、14世紀には既に滅亡していました。
③【正】
マムルーク朝は、アイユーブ朝のトルコ系奴隷軍人(マムルーク)出身であるバイバルスらによって建てられた王朝です。13世紀半ばにはアイン・ジャールートの戦いで、当時破竹の勢いであったモンゴル軍の西進を阻止し、イスラーム世界を守ったことで知られています。これが14世紀半ばのカイロを支配していた王朝の説明として正しいです。
④【誤】
クルド系の軍人サラディンが創始し、十字軍からイェルサレムを奪回したのはアイユーブ朝です。マムルーク朝は、このアイユーブ朝を倒して成立しました。
問3:正解④
<問題要旨>
この問題は、準備メモの内容から、都市ウ(サンクトペテルブルク)の歴史に関する発表内容として最も適当なものを選ぶものです。ロシア史における各時代の出来事と、その背景を正確に理解しているかが問われています。
<選択肢>
①【誤】
君主がギリシア正教に改宗し、聖堂が次々と建てられたことで繁栄したのは、10世紀末のキエフ公国(都市はキエフ)です。ウラジーミル1世の改宗が知られています。
②【誤】
初めて公式に「ツァーリ」の称号を名乗ったのは、16世紀のモスクワ大公国君主イヴァン4世です。彼が拠点としたのはモスクワであり、サンクトペテルブルクではありません。サンクトペテルブルクは18世紀初頭にピョートル1世によって建設されました。
③【誤】
1918年に首都がサンクトペテルブルク(当時はペトログラード)からモスクワへ移されたのは、ドイツとの戦争(第一次世界大戦)を背景に、首都が国境に近すぎることを懸念したソヴィエト政権(レーニン指導)による決定です。臨時政府は既にロシア革命で倒されています。
④【正】
1991年に都市の名称がレニングラードからソ連以前のサンクトペテルブルクに戻されました。これは、当時のソ連の指導者ゴルバチョフが進めたペレストロイカ(改革)とグラスノスチ(情報公開)によって自由化が進み、ソヴィエト時代の歴史や名称を見直す動きが活発になったことを背景としています。この記述は正しいです。
問4:正解①
<問題要旨>
この問題は、17世紀から20世紀までのヨーロッパや中国における文化・技術史上の出来事について述べた文の中から、誤っているものを一つ選ぶものです。幅広い時代の知識が問われています。
<選択肢>
①【誤】
地球球体説を唱え、コロンブスに影響を与えたとされるフィレンツェの天文学者トスカネリが活躍したのは、15世紀です。17世紀には科学革命が進行し、地動説などが広く知られるようになりますが、トスカネリの活躍時期は17世紀ではありません。したがって、この文は誤っています。
②【正】
18世紀のフランスでは啓蒙思想が隆盛し、その集大成としてディドロやダランベールらが中心となって『百科全書』が編纂されました。これは正しい記述です。
③【正】
19世紀には科学技術が大きく発展しました。アメリカのモース(モールス)が実用的な電信機とモールス符号を開発したのは1830年代であり、情報伝達技術に革命をもたらしました。これは正しい記述です。
④【正】
20世紀初頭の中国では、文学革命が起こり、胡適らは難解な文語文(書き言葉)を批判し、口語文(話し言葉)に基づく白話文学を提唱しました。これは文化を通じて社会全体の変革を目指す新文化運動の一環であり、正しい記述です。
問5:正解①
<問題要旨>
この問題は、会話文中の空欄エに入る、ラタナコーシン朝が首都バンコクの防衛を強く意識した歴史的背景として、最も適当なものを選ぶものです。18世紀後半の東南アジア大陸部の情勢、特にタイと周辺国との関係についての知識が問われています。
<選択肢>
①【正】
ラタナコーシン朝(バンコク朝)は、1767年にビルマのコンバウン朝によって首都アユタヤを徹底的に破壊され、アユタヤ朝が滅亡したという記憶も新しい中で、トンブリー朝を経て1782年に成立しました。首都をチャオプラヤ川対岸のバンコクに移した際、アユタヤ朝滅亡の悲劇を繰り返さないよう、防衛を強く意識したのは自然なことでした。したがって、この記述は正しいです。
②【誤】
阮福暎(げんふくえい)が西山(せいざん)政権を滅ぼして阮朝を建てたのはベトナムでの出来事であり、タイの首都防衛意識の直接的な原因ではありません。
③【誤】
イギリス=ビルマ(ビルマ)戦争は19世紀の出来事であり、ビルマがインド帝国に併合されたのは1886年です。ラタナコーシン朝が成立した18世紀末とは時代が異なります。
④【誤】
フランス皇帝ナポレオン3世によるインドシナ出兵は19世紀後半の出来事であり、ラタナコーシン朝成立の直接的な背景ではありません。
問6:正解②
<問題要旨>
この問題は、図1(19世紀初頭)と図2(20世紀初頭)のバンコクの地図を比較し、20世紀初頭の状況とその背景に関する記述の正誤を判断するものです。地図から読み取れる情報(施設の配置、交通網の変化)と、タイの近代化の歴史を結びつける必要があります。
<選択肢>
①【誤】
文いは誤りです。図2では、道路網(陸上交通)が整備されていますが、同時に運河・河川(水上交通路)も依然として市街地を縦横に走っており、衰退しているとは読み取れません。東南アジアの都市では、近代化後も水上交通は重要な役割を果たし続けました。
②【正】
文あ:図2を見ると、城壁外の南東部、チャオプラヤ川沿いに外国領事館(●の記号)が集中しています。これは、19世紀半ばに欧米諸国と不平等条約(ボウリング条約など)を結び、本格的な外交関係・貿易関係が始まった結果、外国人居留地や領事館が設置されたことを示しており、正しいです。
文い:図2では道路も発達していますが、水上交通路が衰退したとは言えないため、誤りです。
したがって、文あが正、文いが誤りの組合せが正しいです。
③【誤】
文あは正しいですが、文いは誤りです。
④【誤】
文いは誤りです。
問7:正解④
<問題要旨>
この問題は、生徒がまとめた二つのメモ(佐藤さん、中原さん)の内容について、授業で取り上げられた都市(バンコク、カイロ、サンクトペテルブルク)の歴史を踏まえて正誤を判断するものです。各都市が関わった国際的な出来事や、その歴史的性格についての正確な知識が求められます。
<選択肢>
①【誤】
佐藤さんのメモ、中原さんのメモともに誤りです。
②【誤】
中原さんのメモは誤りです。
③【誤】
佐藤さんのメモは誤りです。
④【正】
佐藤さんのメモ:第一次インドシナ戦争の休戦協定が締結されたのは、1954年のジュネーヴ会議であり、バンコクではありません。したがって、このメモは誤りです。
中原さんのメモ:バンコクが対外貿易で発展し、都市ウ(サンクトペテルブルク)が西欧との結びつきを意識して建設されたという点は事実ですが、「一方は…、他方は…」という記述は、それぞれの都市の歴史を単純化しすぎています。サンクトペテルブルクもバルト海交易の重要な港として発展しましたし、バンコクも国際関係の中で防衛を意識して建設されました。両都市の歴史を単純に二分している点で、このメモは不正確であると判断できます。
したがって、「二人とも誤っている」が正しい評価となります。
第3問
問1:正解②
<問題要旨>
この問題は、古代ローマの「アクティウムの海戦」に関する後世の記録を読み解き、歴史記述が勝者の視点によっていかに形成されるかを理解するものです。文章の内容から、劇作家の名前と、勝者が作り上げた敗者(アントニウス)のイメージを正しく特定する力が求められています。
<選択肢>
①【誤】
Yは正しいですが、Xが誤りです。クレオパトラはプトレマイオス朝エジプトの女王であり、セレウコス朝シリアの女王ではありません。
②【正】
ア:『ハムレット』などで知られ、16世紀末から17世紀初頭のイングランドで活躍した劇作家は「シェークスピア」です。
Y:資料文には、アントニウスが「クレオパトラの飾り物になっていた」「司令官として、あるいは戦士として行動しているのではない」と記されており、これは勝者であるオクタウィアヌス側が、アントニウスは指導者としての能力や資格を失っていたという否定的なイメージを流布したことを示しています。
したがって、この組合せが正しいです。
③【誤】
アが誤りです。「ラブレー」は『ガルガンチュワとパンタグリュエル』などで知られるフランスのルネサンス期の作家です。
④【誤】
ア、Xともに誤りです。
問2:正解③
<問題要旨>
この問題は、文章のテーマ(女性の政治参加への反感)に関連して、世界史上の有力な女性君主である中国の則天武后とオーストリアのマリア=テレジアの事績に関する記述の正誤を判断するものです。
<選択肢>
①【誤】
文あが誤りです。則天武后は官僚登用に科挙を積極的に利用し、貴族層を抑えて皇帝権力の強化を図りました。「九品中正(九品官人法)」は、それ以前の魏晋南北朝時代に主流だった官吏登用制度であり、則天武后の時代には科挙が中心となっていました。
②【誤】
文あが誤りであるため、この組合せは誤りとなります。
③【正】
文あ:上記の通り、官吏登用制度の記述が誤っています。
文い:マリア=テレジアは、オーストリア継承戦争でプロイセンにシュレジエン地方を奪われました。その後、プロイセンに対抗するため、長年の宿敵であったフランスのブルボン家と同盟を結ぶ「外交革命」を実行しました。これは正しい記述です。
したがって、文あが誤、文いが正の組合せが正しいです。
④【誤】
文いは正しいですが、文あが誤りです。
問3:正解④
<問題要旨>
この問題は、唐代における儒学経典の注釈事業『五経正義』の編纂について、その中心人物と目的を問うものです。唐王朝が科挙制度と結びつけて思想・学問の統一を図った歴史的背景を理解しているかが問われています。
<選択肢>
①【誤】
イ、Xともに誤りです。
②【誤】
Yは正しいですが、イが誤りです。「董仲舒」は前漢の武帝に儒学の国教化を献策した人物です。
③【誤】
イは正しいですが、Xが誤りです。「金属活字」による印刷が本格化するのは後の時代であり、唐代の印刷は木版印刷が主でした。
④【正】
イ:資料文の内容と唐代の歴史的事実から、『五経正義』の編纂を主導した中心的な儒学者は「孔穎達」です。
Y:資料文には「学問に多くの学派があり、経書の解釈が煩雑なので」「五経の注釈を制定させた」とあります。これは、官吏登用試験である「科挙」において、評価の基準となる統一的な解釈を定める目的があったことを示しています。したがって、この組合せが正しいです。
問4:正解③
<問題要旨>
この問題は、明代に刊行された『礼記註疏』という書物の構成(本文・注・疏)を理解し、この書物がどの時代の研究史料となりうるかを判断するものです。一つの史料に、異なる時代の情報が重層的に含まれていることを認識できるかがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
研究例いも可能であるため、この選択肢は不適切です。
②【誤】
研究例あも可能であるため、この選択肢は不適切です。
③【正】
研究例あ:「註」の部分には後漢代の儒学者である鄭玄の注釈が記されています。したがって、これを用いれば漢代の儒学や経書解釈についての研究が可能です。
研究例い:「疏」の部分には唐代の儒学者である孔穎達らの注釈が記されています。したがって、これを用いれば唐代の公式な経書解釈や学問のあり方についての研究が可能です。
以上より、二つの研究例はどちらも可能であると言えます。
④【誤】
二つの研究例はどちらも可能であるため、この選択肢は誤りです。
問5:正解①
<問題要旨>
この問題は、文章中の空欄ウに入る中国人巡礼者(玄奘)がインドを訪れた7世紀前半のインドの状況について、最も適当なものを選ぶものです。同時代のインドの王朝や文化に関する知識が問われています。
<選択肢>
①【正】
7世紀前半に北インドを支配していたのは、ヴァルダナ朝のハルシャ=ヴァルダナ(ハルシャ王)でした。玄奘は彼の保護を受け、ナーランダー僧院などで仏教を学びました。したがって、この記述は正しいです。
②【誤】
パータリプトラを都とするマウリヤ朝を建てたチャンドラグプタは紀元前4世紀の人物、グプタ朝を建てたチャンドラグプタ1世は紀元後4世紀の人物であり、いずれも7世紀ではありません。
③【誤】
インドの古法典である『マヌ法典』の成立は、紀元前2世紀から紀元後2世紀頃とされており、7世紀ではありません。
④【誤】
大乗仏教の「空」の思想を大成したナーガールジュナ(竜樹)は、2~3世紀頃の人物です。
問6:正解④
<問題要旨>
この問題は、19世紀のイギリスによるインド史研究の文脈を理解し、空欄補充と、それに合致する研究手法の例を選ぶものです。オリエンタリズムや植民地主義が歴史研究に与えた影響を読み解く必要があります。
<選択肢>
①【誤】
エ、Xともに誤りです。
②【誤】
エが誤りです。
③【誤】
Xが誤りです。「死者の書」は古代エジプト人が残した文献であり、外国人による記録ではありません。カニンガムの手法は、当事者(インド人)以外の第三者(中国人巡礼者)の記録を用いる点に特徴があります。
④【正】
エ:文章には、イギリスの研究者が「ヒンドゥー時代(古代)」「イスラーム時代(中世)」「イギリス時代(近代)」という時代区分を導入し、「イギリスがインドの人々を エ から救い出し…支配を正当化しようとした」とあります。彼らが暗黒期と位置づけた「イスラーム時代(中世)」、すなわち「ムガル帝国の下でのムスリムによる支配」から救い出す、という文脈が最も自然です。
Y:ルブルックは13世紀にモンゴル帝国を訪れたフランス人の修道士です。彼が残した旅行記は、ヨーロッパという外部の視点からモンゴル帝国を記録した貴重な史料です。これは、カニンガムが中国人(玄奘)の旅行記を用いてインド史を研究する手法と共通します。したがって、この組合せが正しいです。
問7:正解⑥
<問題要旨>
この問題は、20世紀初頭から前半にかけての中国を舞台とした、外国人(スタイン)による文化財調査に関する公文書(資料4)を読み解くものです。資料から読み取れる現地政府の考えと、その文書が書かれた時期の中国の政治的背景を正しく結びつける必要があります。
<選択肢>
①【誤】
あ、Xともに誤りです。
②【誤】
あ、Yともに誤りです。
③【誤】
あが誤りです。
④【誤】
Xが誤りです。
⑤【誤】
Yが誤りです。改革開放政策は1970年代末からの中華人民共和国の政策であり、時代が異なります。
⑥【正】
い:資料4には、スタインの発見は評価しつつも、敦煌文書などは「国家の貴重な宝物である」「盗み去ることは不法行為である」と記されています。これは、現地政府が文化財の国外流出を危惧し、自国で保護する必要性を感じていることを示しており、正しいです。
Z:資料4は「今日までの30年にわたるスタイン氏の調査」に言及しており、最初の調査(8か国連合軍の北京占領時、つまり1900年頃)から約30年後、すなわち1920年代後半から1930年頃に書かれたと推測できます。この時期、中国では国民政府が国内統一を目指して「北伐」(1926~28年)を進めていました。したがって、この政治的背景は時期的に合致しています。
第4問
問1:正解①
<問題要旨>
この問題は、19世紀後半のイギリスにおける綿花輸入量の推移を示すグラフを読み解き、その変化と歴史的背景を正しく結びつけるものです。グラフの読解力と、産業革命期の世界経済に関する知識が問われています。
<選択肢>
①【正】
あ:グラフを見ると、1850年の輸入総量は約750百万ポンド、1880年は約1500百万ポンドであり、「2倍以上に増加しています」という記述は誤りではありません(約2倍です)。
X:18世紀後半から続く産業革命により、マンチェスターなどを中心とするイギリスの綿工業は飛躍的に発展し、原料である綿花の需要が急増しました。これが輸入量増加の大きな背景です。
したがって、この組合せが正しいです。
②【誤】
Yが誤りです。「囲い込み」は、農地を牧羊地などに転換する動きですが、綿花の需要増の直接的な背景ではありません。特に第一次囲い込みは毛織物工業に関連し、時代もより古いです。
③【誤】
いが誤りです。アメリカからの輸入量は1850年が約600、1880年が約1100であり、3倍には達していません。
④【誤】
いが誤りであるため、この組合せは誤りとなります。
問2:正解②
<問題要旨>
この問題は、前の問題のグラフ(イギリスの綿花輸入)について、二人の生徒がまとめたメモの正誤を判断するものです。特に1860年代の輸入量の変動(アメリカ南北戦争の影響)を正確に読み取れているかが問われています。
<選択肢>
①【誤】
木村さんのメモは誤っています。
②【正】
木村さんのメモ:1862~65年にアメリカからの輸入が激減し、インドからの輸入が増えている点は正しいです。しかし、「1860年の輸入総量の水準を維持した」という点が誤りです。1860年の総量は約1300ですが、1862年の総量は約500、1864年は約900であり、1860年の水準には達していません。
加藤さんのメモ:1862~65年にアメリカからの輸入量が激減していること、その減少がアメリカ南北戦争(1861~65年)の影響による一時的な現象であったと考えられること、いずれも正しいです。戦後、アメリカからの輸入は回復傾向にあることもグラフから読み取れます。
以上より、加藤さんのみ正しいです。
③【誤】
木村さんのメモは誤っています。
④【誤】
加藤さんのメモは正しいです。
問3:正解③
<問題要旨>
この問題は、中世ヨーロッパで広範囲に活動したヴァイキングの動向について、空欄に当てはまる適切な記述を選ぶものです。ヴァイキングの西ヨーロッパおよび東ヨーロッパでの活動に関する基本的な知識が問われています。
<選択肢>
①【誤】
イが誤りです。イングランドを征服(ノルマン・コンクェスト)したのは、ノルマンディー公ウィリアムであり、ロロではありません。
②【誤】
イ、ウともに誤りです。ブルガリア王国を建てたのはスラヴ系やテュルク系のブルガール人であり、ヴァイキングではありません。
③【正】
イ:ヴァイキングの一派(ノルマン人)を率いたロロは、10世紀初頭に西フランク王からフランス北西部の土地を与えられ、「ノルマンディー公国」を建国しました。これは正しいです。
ウ:ヴァイキングの別の一派(ルーシ)は、東ヨーロッパの河川を下って黒海方面へ進出し、コンスタンティノープルを都とする「ビザンツ帝国と接触」し、交易や傭兵活動を行いました。これも正しいです。
したがって、この組合せが正しいです。
④【誤】
ウが誤りです。
問4:正解④
<問題要旨>
この問題は、北米で発見されたヴァイキングの遺跡について、それがアメリカ大陸外部から来た人々のものだと判断する根拠として最も適当なものを選ぶものです。コロンブス以前のアメリカ大陸には存在しなかった物品や技術は何か、という知識が問われています。
<選択肢>
①【誤】
ジャガイモは、アメリカ大陸原産の作物であり、ヴァイキングが到達する以前から先住民によって栽培されていました。したがって、これが外部から来た証拠にはなりません。
②【誤】
アメリカ大陸には、ヨーロッパ人が到達するまで牛や馬は生息していませんでした。しかし、会話文に「家畜を飼っていた形跡がない」とあるため、この選択肢は文脈と矛盾します。
③【誤】
トウモロコシも、アメリカ大陸原産の作物であり、先住民の主要な食料でした。
④【正】
アメリカ大陸の先住民は、ヨーロッパ人が到達するまで鉄を精錬・加工する技術を持っていませんでした。したがって、遺跡から「鉄の釘」が見つかったことは、鉄器文化を持つヨーロッパ(この場合はヴァイキング)から人々がやって来たことを示す強力な物証となります。
問5:正解②
<問題要旨>
この問題は、ヨーロッパ人の海外進出に関する三つの事柄(ポルトガルのアフリカ西岸進出、アカプルコ貿易、コロンブスのアメリカ大陸到達)を、年代順に正しく配列するものです。大航海時代の主要な出来事の時系列を正確に把握しているかが問われています。
<選択肢>
①【誤】
配列が誤っています。
②【正】
三つの事柄を年代順に並べると以下のようになります。
Ⅰ:ポルトガルによるアフリカ西岸への探検航海は、エンリケ航海王子の下で15世紀前半から始まりました。
下線部(コロンブスのアメリカ大陸到達):1492年の出来事です。
Ⅱ:アメリカ大陸の銀を、メキシコのアカプルコから太平洋を越えてフィリピンのマニラへ運ぶ航路(アカプルコ貿易)が成立したのは、スペインがフィリピンを領有した後の16世紀後半(1571年以降)です。
したがって、古いものから順に「Ⅰ → 下線部 → Ⅱ」と並べるのが正しいです。
③【誤】
配列が誤っています。
④【誤】
配列が誤っています。
⑤【誤】
配列が誤っています。
⑥【誤】
配列が誤っています。
第5問
問1:正解④
<問題要旨>
この問題は、朝鮮半島の扶余で出土した7世紀初頭の木簡に関する解説シートと考察を読み、空欄を埋めるものです。木簡の内容(5割の利息を伴う穀物貸付)と出土地、そして同時代の東アジア(朝鮮半島、唐、日本)の律令制度に関する知識を結びつけて考える必要があります。
<選択肢>
①【誤】
ア、イが誤りです。
②【誤】
イが誤りです。
③【誤】
イ、ウが誤りです。
④【正】
ア:木簡が出土した扶余は、7世紀当時、朝鮮半島南西部に位置した「百済」の首都(泗沘)でした。
イ・ウ:考察部分では、木簡に見られる「返済時に5割の利息」という制度が、日本の律令の規定と共通点があると指摘しています。一方で、唐の律令には同様の明確な規定が見つかっていないため、比較ができないとしています。したがって、イには日本の律令と比較対象である「朝鮮半島」(の百済の制度)、ウには比較ができない「唐」が入るのが文脈に合います。この組合せが正しいです。
問2:正解①
<問題要旨>
この問題は、16世紀イングランドにおける漁業奨励策の歴史的背景を読み解くものです。パネルに書かれた情報から、当時の宗教的、軍事的、経済的な状況を推測します。
<選択肢>
①【正】
パネルには、漁業奨励の目的として「戦時に利用できる船員と漁船を増やすことで、海軍力を強化する目的もあった」と記されています。これは、漁業者が平時は漁に従事し、戦時にはその技術や船をもって海軍力の一部を担うことが期待されていたことを示唆しており、正しいです。
②【誤】
ヘンリ8世やエリザベス1世の時代は、イギリス国教会を確立し、カトリックから離脱した宗教改革の時代です。肉食を禁じる布告は、あくまで漁業奨励という経済的・軍事的目的のためであり、「カトリックを復活させようとする狙い」は、彼らの宗教政策と完全に矛盾します。
③【誤】
エリザベス1世は、スペインからの独立を目指すオランダを支援しており、スペインとは敵対関係にありました。イングランドとオランダが対立するのは、後の17世紀、航海法をめぐる英蘭戦争の時期です。
④【誤】
航海法は、17世紀半ばのイングランド共和国時代に、護国卿クロムウェルが制定した法律です。16世紀末のエリザベス1世の時代ではありません。
問3:正解②
<問題要旨>
この問題は、北米先住民の料理「フライブレッド」の起源について、その歴史的経緯を正しく理解し、空欄を埋めるものです。19世紀アメリカの西漸運動が先住民の生活に与えた深刻な影響を読み取る必要があります。
<選択肢>
①【誤】
オが誤りです。伝統的な自給自足の生活を破壊された結果生まれた料理です。
②【正】
エ:19世紀のアメリカ政府は、武力や不平等な条約によって先住民を土地から追いやり、特定の「保留地」に強制的に移住させる政策をとりました。したがって、「保留地に隔離」が正しいです。
オ:保留地での生活や、バッファロー乱獲による食料難の結果、先住民は連邦政府が供給する小麦粉やラードといった食材に頼らざるを得ない状況に追い込まれました。その中で生まれたのがフライブレッドです。したがって、「供給された食材に依存」が正しいです。
この組合せが、フライブレッドが生まれた歴史的文脈を正しく説明しています。
③【誤】
エ、オともに誤りです。自営農として公有地を無償供与する(ドーズ法など)政策も存在しましたが、それは伝統的な共同体生活を解体する同化政策の一環であり、フライブレッドが生まれた直接の経緯である「隔離と食料支援」とは異なります。
④【誤】
エが誤りです。
問4:正解①
<問題要旨>
この問題は、第一次世界大戦中のドイツにおける食料価格のデータ(表2)と、戦時下の社会状況に関するメモを読み解き、記述の正誤を判断するものです。総力戦体制が国民生活に与えた影響を多角的に考察する力が求められています。
<選択肢>
①【正】
あ:メモには、軍需生産優先、労働力不足、海上封鎖による食料不足に対し、政府が価格や供給量を統制する「配給制」を導入したとあります。これは、国家が経済や国民生活のあらゆる側面を戦争遂行のために動員・管理する「総力戦体制」構築の一環であり、正しいです。
う:表2で値上がり率を計算すると、ライ麦粉は0.15→1.85で約12.3倍、牛肉は1.00→2.80で2.8倍となります(闇市価格ではなく小売価格で比較します)。したがって、「牛肉よりもライ麦粉の方が、値上がり率が大きい」という記述は正しいです。
両方とも正しいので、この組合せが正解となります。
②【誤】
えが誤りです。メモには「配給された切符の分だけ、政府が決めた価格で、食料を購入できた」とあり、無料で入手できたわけではありません。
③【誤】
い、うが両方とも正しいわけではありません。ドイツ革命の結果、皇帝は退位し、ヴァイマル憲法に基づく共和制が実現しました。「立憲君主制が実現した」という記述は誤りです。
④【誤】
い、えともに誤りです。
問5:正解③
<問題要旨>
この問題は、第5問の各班の活動内容(穀物貸付、漁業と海軍力、保留地政策、食料配給制)を参考に、これらを包括する主題αと、その主題をさらに追究するための事例を選ぶものです。各事例の歴史的背景を理解し、主題との関連性を判断する力が求められています。
<選択肢>
①【誤】
あは主題として適切ですが、Xは不適切です。バイオテクノロジーを用いた品種改良は、産業や科学技術の発達が食料事情に与えた影響の事例(主題い)であり、政治権力の影響とは少しずれます。
②【誤】
Yは主題として不適切です。気候変動による凶作は自然現象であり、政治権力が直接与えた影響ではありません。
③【正】
あ:問1~4の事例は、律令(百済、日本)、国王の布告(英)、連邦政府の政策(米)、政府の配給制(独)など、いずれも「政治権力が食料事情や食生活に与えた影響」という主題でまとめることができます。
Z:中国の「大躍進政策」(1950年代末)は、毛沢東の指導の下、政治権力が非科学的な増産計画を強行した結果、数千万人規模の餓死者を出す大飢饉を引き起こした典型的な事例です。これは主題あと完全に合致しています。
したがって、この組合せが最も適当です。
④【誤】
主題い(産業の発達)は、各班のテーマを包括するには少し狭いです。
⑤【誤】
主題いが不適切であり、事例Yも主題から外れています。
⑥【誤】
主題いが不適切です。