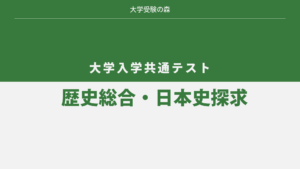解答
解説
第1問
問1:正解③
<問題要旨>
18世紀から19世紀にかけての東アジアにおける伝統的な国際秩序(冊封体制)と、近代的な主権国家体制との違いについて、理解を問う問題。
<選択肢>
①【誤】
文「あ」は中国王朝中心の秩序(冊封体制)を、港「a」は18世紀末に唯一開港されていた広州を指し、それぞれ正しい記述です。しかし、パネル全体が冊封体制と、それとは異なる「主権国家からなる国際秩序」を対比して説明している文脈です。この問題は、下線部⑧の冊封体制と対比される概念である主権国家体制(文「い」)を正しく理解しているかを問うています。したがって、この組み合わせは最も適当とは言えません。
②【誤】
港「b」は上海付近を指します。18世紀末の段階では、清は広州一港のみを開港しており、上海は開港されていません。したがって、港の選択が誤りです。
③【正】
文「い」は、ウェストファリア条約以降にヨーロッパで形成された、各国の主権が対等であり、領土内の統治権が認められる「主権国家からなる国際秩序」を正しく説明しています。パネルでは、下線部⑧の「中国王朝を中心とする世界観」と、この主権国家体制とを比較し、両者が異なる秩序であることを論じています。港「a」は、18世紀末のイギリスが唯一、清との貿易を公認されていた広州港を指しており、正しいです。したがって、この組み合わせが最も適当です。
④【誤】
港「b」は上海付近を指します。18世紀末には開港されていなかったため、港の選択が誤りです。
問2:正解②
<問題要旨>
資料文とパネルの内容を基に、19世紀後半の東アジアの国際関係(特に日・清・朝鮮の関係)について、歴史的背景を正しく理解できているかを問う問題。
<選択肢>
①【誤】
資料中の「我が国と貴国との条約」は、その後の「台湾出兵」(1874年)や朝鮮での「事件」(江華島事件、1875年)の文脈から、1871年に締結された日清修好条規を指します。下関条約は、日清戦争(1894~95年)の講和条約であり、時期が異なります。
②【正】
資料中の「事件」とは、1875年に起こった江華島事件のことです。清仏戦争は、ベトナムの宗主権をめぐって清とフランスが争った戦争で、1884~85年に起こりました。したがって、江華島事件は清仏戦争の前のできごとであり、この記述は正しいです。
③【誤】
「事件」が起こった1870年代の日本では、不平等条約により外国人の居住は条約港の居留地に限定されていました。外国人が国内のどこにでも自由に住めるようになる(内地雑居)のは、条約改正が達成された1899年以降のことです。
④【誤】
江華島事件を契機に1876年に締結された日朝修好条規は、朝鮮の関税自主権を認めず、日本の領事裁判権を認めるなど、日本側に有利な不平等条約でした。「ともに領事裁判権を認め合う対等な条約」ではありません。
問3:正解②
<問題要旨>
19世紀半ばの国際衛生会議における、検疫に対する各国の姿勢とその背景にある思想(自由貿易主義)についての理解を問う問題。
<選択肢>
①【誤】
空欄アの国が検疫に反対した理由が、空欄イです。イの「コレラの国内侵入を水際で阻止」することは、検疫に賛成する理由であり、文脈に合いません。
②【正】
会話中の「穀物法を廃止した」というヒントから、自由貿易を推進したイギリスがアの国であることがわかります。イギリスは、国家による過度な介入を嫌う自由貿易の立場から、検疫が船の入港や通行を妨げ、貿易の障害になるとして反対しました。したがって、アにイギリス、イに貿易を妨げるべきではないという趣旨の文が入るこの選択肢が正しいです。
③【誤】
アの国は、穀物法廃止の史実からイギリスと判断できます。スペインではありません。
④【誤】
アの国はイギリスです。スペインではありません。
問4:正解④
<問題要旨>
両大戦間期(1919~1939年)において、「政治的対立」がありながらも「国際保健協力」が進展した事例を的確に指摘できるかを問う問題。
<選択肢>
①【誤】
イギリスの「光栄ある孤立」は、主に19世紀後半の外交政策を指す言葉であり、第一次世界大戦後の国際連盟に創設時から参加したイギリスの状況とは異なります。
②【誤】
イスラエルの建国は第二次世界大戦後の1948年であり、問題で設定されている「両大戦間期」の出来事ではありません。
③【誤】
日本が国際連盟を脱退したのは1933年で、その直接の原因は満州事変をめぐるリットン報告書への反発です。盧溝橋事件(1937年)が直接の原因ではありません。
④【正】
第一次世界大戦の敗戦国であったドイツは、当初、国際連盟への加盟を認められませんでした(加盟は1926年)。これは明確な「政治的対立」の事例です。しかし、国際連盟の専門機関であった国際保健機関(LHO)などは、加盟国・非加盟国を問わず協力活動を行っていました。したがって、政治的対立を乗り越えた協力の事例として最も適当です。
問5:正解①
<問題要旨>
1858年のコレラ流行に関して、地図に示されたミシシッピ号の寄港地と各地の流行時期から、感染拡大の経路を合理的に推測する力を問う問題。
<選択肢>
①【正】
メモ1は、関東地方での流行が近畿・中国地方より早いことを指摘し、その原因を下田からの感染拡大と推測しています。地図を見ると、関東の流行は7月上旬からで、中国地方(8月中旬~)や近畿地方(8月下旬~)より早いです。また、ミシシッピ号が6月中旬に下田へ寄港していることから、この推測は地図の情報と矛盾せず、合理的であると考えられます。メモ2は、京都(9月流行開始)が、それより早い中部地方(8月中旬)や近畿地方(8月下旬)の流行の起点であるとしており、時間的な前後関係から明らかに誤りです。したがって、「メモ1のみ正しい」とするこの選択肢が正解です。
②【誤】
メモ2は、流行時期の前後関係から誤りです。
③【誤】
メモ2が誤りであるため、この選択肢は正しくありません。
④【誤】
メモ1は地図から合理的に推測できる内容であるため、この選択肢は正しくありません。
問6:正解③
<問題要旨>
アメリカへの移民数の推移を示したグラフを正確に読み取り、その内容と合致しない記述を見つけ出す問題。
<選択肢>
①【正】
グラフを見ると、1900~1929年の期間において、ヨーロッパからの移民(灰色の部分)の数が、他の地域(アジア、南北アメリカ)を圧倒的に上回っていることがわかります。
②【正】
世界恐慌は1929年に始まります。グラフの1930~1939年の期間を見ると、移民の総数はそれ以前の10年間と比べて急激に減少しており、恐慌による経済的苦境が移民の流れを停滞させたと読み取れます。
③【誤】
ベトナム戦争は1960年代から1975年にかけて続きました。グラフでアジアからの移民(黒色の部分)を見ると、この戦争の時期から戦後にかけて一貫して「増加」しています。特に1970年代以降の急増は、ベトナム戦争終結後の難民の流入などが影響していると考えられます。「減少している」という記述はグラフの示す事実と逆です。
④【正】
冷戦終結は1989年頃です。グラフの1990~1999年の期間を見ると、南北アメリカ(アメリカを除く、白色の部分)からの移民は、総数(約980万)からヨーロッパ(約120万)とアジア(約300万)を引いた数、すなわち500万人を超えており、「400万人を超えている」という記述は正しいです。
問7:正解⑤
<問題要旨>
20世紀後半の冷戦期とその後の出来事について、発生した年代を正しく理解し、順番に配列できるかを問う問題。
<選択肢>
・メモ I「チェコスロヴァキアでは、民主化を求める動きが…挫折した」は、1968年の「プラハの春」とワルシャワ条約機構軍による軍事介入を指します。
・メモ II「鄧小平が、『四つの現代化』を…決定した」は、1978年に開始された中国の改革開放政策を指します。
・メモ III「カストロが、社会主義政権を樹立した」は、1959年のキューバ革命を指します。
これらの出来事を年代順に並べると、III (1959年) → I (1968年) → II (1978年) となります。この順序に合致するのは⑤です。
問8:正解④
<問題要旨>
提示された探究の「問い」に対して、その問いを考察する上で最も適切と考えられる「学習活動」を正しく結びつけられるかを問う問題。
<選択肢>
①【誤】
問い「あ」はベルリンの壁崩壊(1989年)後の影響を問うていますが、活動「W」のドイツ関税同盟は19世紀の出来事であり、時期が全く異なります。
②【誤】
活動「W」が問い「あ」に対して不適切です。
③【誤】
問い「い」は明治期の技術導入が人々の生活に与えた影響を問うていますが、活動「Y」の第一次世界大戦期の外交方針は、テーマ・時期ともに問いと関連性が低いです。
④【正】
問い「あ」のベルリンの壁崩壊(1989年)の影響を調べるには、活動「X」のように崩壊前後(1988年と1990年)の人口流動を比較することが極めて有効です。また、問い「い」の明治期の技術導入と生活の変化を調べるには、活動「Z」のように、技術指導にあたったお雇い外国人が関わった産業施設(例:富岡製糸場)の労働環境を調べることは、直接的で適切な学習活動です。したがって、この組み合わせが正しいです。
第2問
問1:正解②
<問題要旨>
江戸時代中期の田沼時代に書かれた工藤平助の意見書(資料1)と、その背景となる時代の特徴を正しく理解しているかを問う問題。
<選択肢>
①【誤】
選択肢「う」が誤りです。資料1には、江戸で消費される中白砂糖150万斤のうち、菓子屋用は「四~五百斤」とあり、ごく一部であることがわかります。「ほとんどが菓子屋で消費されている」という記述は、資料の内容と反します。
②【正】
選択肢「あ」は田沼意次が印旛沼・手賀沼の干拓を計画した史実、「え」は資料1で工藤平助が「下賤の者が異国の物を日用の食物とすることはあってはならない」と主張していることから、いずれも正しい記述です。
③【誤】
選択肢「い」は誤りです。株仲間などの同業者組織を解散させたのは、天保の改革を主導した水野忠邦です。田沼意次は逆に株仲間を公認・奨励しました。
④【誤】
選択肢「い」と「う」が誤りです。
問2:正解①
<問題要旨>
第一次世界大戦期頃の菓子の輸出に関する記事(資料2)と新聞広告(図1)を読み解き、当時の社会状況を推測する問題。
<選択肢>
①【正】
選択肢「あ」について、資料2には「欧州製菓の輸入途絶し」とあり、これは第一次世界大戦でヨーロッパ諸国がアジア市場への輸出をできなくなった状況を示唆しています。その結果、日本製菓の需要が高まり輸出が増加したと推測でき、正しいです。選択肢「い」について、図1の広告文には「小児の常用」とある一方、「事務家、読書家、運動家」とも書かれており、子どもだけでなく大人もターゲットにしていたことが明確に読み取れ、正しいです。
②【誤】
選択肢「い」も正しい記述です。
③【誤】
選択肢「あ」も正しい記述です。
④【誤】
両方とも正しい記述です。
問3:正解②
<問題要旨>
平安時代の貴族文化に関する記述の中から、不適切なものを見つけ出す問題。
<選択肢>
①【適】
最澄が開いた天台宗や空海が開いた真言宗などの密教は、加持祈祷による現世利益を重視する側面があり、平安貴族社会に広く受け入れられました。
②【不適】
違い棚や付書院は、室町時代に発達した武家住宅の様式である「書院造」の特徴です。平安時代の貴族の邸宅は、間仕切りの少ない「寝殿造」が主流でした。
③【適】
平安時代前期には『凌雲集』などの勅撰漢詩集が、中期には『古今和歌集』などの勅撰和歌集が編纂され、漢詩文が和歌に先行しました。貴族にとって漢詩文や和歌の素養は必須でした。
④【適】
貴族の日記には、儀式や政務の前例(有職故実)を子孫に伝えるという目的がありました。藤原道長の『御堂関白記』などがその例です。
問4:正解④
<問題要旨>
中世の禅宗寺院で砂糖を用いた菓子が普及した背景として、最も関連の深い歴史的事実を選ぶ問題。
<選択肢>
①【誤】
長崎に唐人屋敷が設けられたのは、江戸時代の1689年であり、中世ではありません。
②【誤】
大輪田泊(現在の神戸港)を修築し、日宋貿易の拠点としたのは平安時代末期の平清盛です。
③【誤】
鑑真が日本に戒律を伝えるために来日したのは奈良時代の754年です。
④【正】
室町時代、幕府と明との間の勘合貿易では、五山の禅僧が外交文書の作成を担うなど、外交顧問として重要な役割を果たしました。彼らが日中間の交流に深く関与したことで、砂糖を含む中国の進んだ文物や文化が日本にもたらされやすくなり、禅宗寺院を中心に砂糖菓子が普及する背景となりました。
問5:正解③
<問題要旨>
古代から近代にかけての日本における砂糖の普及と利用の歴史について、最も正確に述べた記述を選ぶ問題。
<選択肢>
①【誤】
会話文にある通り、砂糖と甘葛は異なるものです。砂糖は奈良時代に薬として伝来し、甘味料として広く使われるようになったのは後の時代です。
②【誤】
カステラは、戦国時代にポルトガルから伝来した南蛮菓子であり、室町時代に中国から伝わったものではありません。
③【正】
本文にあるように、江戸時代には砂糖は輸入品であった一方、薩摩藩などで国産化も進められました。資料1からも、菓子原料や民衆の食料として様々な用途に用いられていたことがわかり、正しい記述です。
④【誤】
切符制(配給制)は、第二次世界大戦中の物資不足に対応するための消費制限策です。これにより砂糖の消費量は増加するのではなく、厳しく統制・減少しました。
第3問
問1:正解④
<問題要旨>
3世紀(弥生時代末期~古墳時代初頭)までに、中国大陸や朝鮮半島から日本列島にもたらされた可能性が「ない」遺物を特定する問題。
<選択肢>
①【可能性あり】
楽浪郡は前漢によって朝鮮半島北部に置かれ、後313年まで存続しました。したがって、3世紀までに楽浪郡で作られた土器がもたらされる可能性は十分にあります。
②【可能性あり】
「漢委奴国王」と刻まれた金印は、後漢の光武帝が1世紀に倭の奴国の王に授けたとされ、実際に福岡県の志賀島で発見されています。
③【可能性あり】
前漢は紀元前3世紀末から紀元後8年まで存在した王朝であり、その貨幣(半両銭や五銖銭)が交易によって3世紀までにもたらされる可能性はあります。
④【可能性なし】
新羅が国家としての体制を整え、特徴的な馬具などを生産し、それが日本の古墳の副葬品として見られるようになるのは、主に4世紀以降、特に5世紀代になってからです。したがって、3世紀までにもたらされた可能性は極めて低いです。
問2:正解③
<問題要旨>
古代日本の唐や新羅との外交関係、および人的交流について、最も正確に述べた記述を選ぶ問題。
<選択肢>
①【誤】
日本は遣隋使や遣唐使を派遣しましたが、中国王朝の皇帝から王として認められる「冊封」は受けておらず、対等な外交関係を志向していました。
②【誤】
日本は新羅に対し、自らを上位の国とみなし朝貢を求める高圧的な態度をとることがあり、関係はしばしば緊張しました。「対等な外交関係を望んでいた」とは言えません。
③【正】
吉備真備と玄昉は、遣唐使として唐に留学し、帰国後、橘諸兄が政権を握った聖武天皇の時代に重用されました。これは史実です。
④【誤】
8世紀に両国の公的な関係が悪化した後も、9世紀になると新羅商人の張宝高などが主導する民間交易はかえって活発化しました。「来航しなくなった」という記述は誤りです。
問3:正解②
<問題要旨>
複数の資料の中から、国名の「高麗」が「渤海」を指しているものを特定する問題。
<選択肢>
①【誤】
資料中に「宋の謀略か」とあります。宋の建国は960年で、この頃には渤海はすでに滅亡しています。ここでいう「高麗」は、918年に建国された王氏高麗を指すと考えられます。
②【正】
資料中に「高麗国王の大欽茂」「聖武天皇が亡くなった」とあります。大欽茂(文王)は渤海の3代目の王(在位737~793年)であり、聖武天皇の崩御は756年です。人物名と時期が一致するため、この「高麗」は渤海を指していると判断できます。
③【誤】
「隋の煬帝」が攻めた相手は高句麗です(7世紀初頭)。したがって、この「高麗」は高句麗を指します。
④【誤】
「雄略天皇」(5世紀)の時代の朝鮮半島の王朝は、高句麗・百済・新羅です。文脈上、この「高麗」は高句麗を指します。
問4:正解①
<問題要旨>
古代の九州北部(大宰府周辺)が担った軍事的重要性について、正しい記述の組み合わせを選ぶ問題。
<選択肢>
①【正】
文「あ」について、8世紀末の桓武天皇の時代に軍団・兵士の制度が改革され、多くが廃止されましたが、国防の最前線である九州(大宰府管内)と東北、佐渡では存続しました。正しい記述です。文「い」について、11世紀前半に女真族が九州北部を襲撃した「刀伊の入寇」を撃退したのは、大宰権帥であった藤原隆家です。正しい記述です。両方とも正しいため、この組み合わせが正解です。
②【誤】
文「い」も正しい記述です。
③【誤】
文「あ」も正しい記述です。
④【誤】
両方とも正しい記述です。
問5:正解④
<問題要旨>
遣唐使が廃止された後の日本の文化の展開について、メモの内容と図(仏画)が同じ時期のものかどうかを判断する問題。
<選択肢>
①【誤】
サクラさんのメモにある「大陸文化を踏まえつつも日本風に工夫された貴族文化」は、遣唐使が廃止された9世紀末以降に栄えた国風文化(平安中期)を指します。一方、タケシさんのメモにある「阿弥陀仏の信仰が隆盛し、極楽浄土に往生することが願われた」のは、平安時代中期から後期にかけて広まった浄土教のことであり、図の阿弥陀来迎図もこの信仰を反映したものです。したがって、タケシさんのメモと図は同時期です。
しかし、サクラさんの図は、メモの内容と一致しません。この仏画は、中央に阿弥陀如来、その左右に観音菩薩・勢至菩薩を配した「阿弥陀三尊来迎図」であり、平安時代中・後期の浄土教美術の典型です。サクラさんのメモが指す国風文化の美術としては、例えば日本の風景を描いた「やまと絵」などがより適切でしょう。したがって、サクラさんはメモと図の時期が一致しません。
②【誤】
タケシさんはメモと図の時期が一致しています。
③【誤】
サクラさんはメモと図の時期が一致せず、タケシさんは一致しています。
④【正】
サクラさんのメモ(国風文化)と図(浄土教美術)は、どちらも平安時代のものですが、文化の側面が異なります。一方で、タケシさんのメモ(浄土教の隆盛)と図(阿弥陀来迎図)は、浄土信仰というテーマで完全に一致しており、同時期(平安中・後期)のものです。したがって、「タケシさんのみ、メモと図とが同時期である」というこの記述が正しいです。
第4問
問1:正解③
<問題要旨>
鎌倉時代の御家人である笠間時朝の事例を手がかりに、鎌倉武士全般に関する記述として不適切なものを見つけ出す問題。
<選択肢>
①【適】
資料1で笠間時朝が中国で印刷された経典「唐本一切経」を奉納していることから、御家人が唐物(中国からの輸入品)を入手していたことがわかります。日宋貿易などを通じて、唐物は武士層にも広まっていました。
②【適】
評定衆や引付衆は、鎌倉幕府の最高政務機関・訴訟機関であり、有力御家人から選ばれて幕府の運営に参加していました。これは鎌倉時代の政治に関する基本的な事実です。
③【不適】
半済令は、荘園や公領の年貢の半分を軍事費として徴収する権利を守護などに与える法令ですが、これは鎌倉時代ではなく、南北朝時代の1352年に室町幕府によって出されたものです。時代が異なります。
④【適】
会話文にあるように、笠間時朝の和歌が後嵯峨上皇の勅撰和歌集に採録されていることから、地方の御家人も京都の朝廷文化とつながりを持ち、和歌をたしなむ文化的な側面があったことがわかります。
問2:正解④
<問題要旨>
『蒙古襲来絵詞』(図)とモンゴル襲来後の判決書(資料2)を読み解き、二度の元寇(モンゴル襲来)とその後の状況について正しく考察する問題。
<選択肢>
①【誤】
考察Xが誤りです。資料2には、異国警固や石築地(防塁)の費用について、「両方寄り合い、等分の沙汰をいたすべし」とあり、荘園領主(領家)と地頭の双方が負担を命じられています。荘園領主が免除されたわけではありません。
②【誤】
考察Xが誤りです。
③【誤】
図の説明「い」は二度目の襲来時(弘安の役)の様子として適切ですが、考察Xが誤りです。
④【正】
図の説明「い」は、『蒙古襲来絵詞』のこの場面が、防塁を築いて戦った二度目の襲来(弘安の役)における竹崎季長の奮戦を描いたものと解釈できるため、適切です。考察Yも、1324年の資料2に「異国警固ならびに石築地用途」とあることから、二度の襲来後も鎌倉幕府がモンゴルの三度目の襲来を警戒し、防衛体制を維持していたことが読み取れるため、正しいです。
問3:正解①
<問題要旨>
戦国時代の大内義隆の滅亡に関する日記(資料3)を読み、会話文の空欄に入る語句の正しい組み合わせを選ぶ問題。
<選択肢>
①【正】
日記の筆者である吉田兼右は、吉田神道(唯一神道)の家系の人物です 。したがって、アには「唯一神道」が入ります。また、大内義隆は宣教師フランシスコ・ザビエルを保護し、山口でのキリスト教布教を許可したことで知られています。神道を奉じる兼右の視点から、この外来の宗教が「魔法」と見なされたと考えるのが最も自然です。したがって、イには「キリスト教」が入ります。
②【誤】
黄檗宗は江戸時代初期に伝わった宗派であり、戦国時代の出来事とは時期が合いません。
③【誤】
アに入るのは、吉田兼右の家系から「唯一神道」が適切です。伊勢神道ではありません。
④【誤】
ア、イともに不適切です。
問4:正解②
<問題要旨>
戦国時代から安土桃山時代にかけて、統一権力が独自の貨幣を鋳造する必要があった歴史的背景・前提として、最も適切なものを選ぶ問題。
<選択肢>
①【誤】
藩札は、江戸時代に各藩が領内通用として発行した紙幣であり、戦国大名の事例ではありません。
②【正】
室町時代、日明貿易などで大量に輸入された中国の銅銭には、品質の悪い私鋳銭が多く含まれていました。そのため、商取引の現場では人々が良質な銭を選び、悪銭を嫌う撰銭(えりぜに)が横行し、経済を混乱させる一因となっていました。この混乱を収拾し、安定した経済活動を保証するために、織田信長や豊臣秀吉のような統一権力は、自らの権威で品質の保証された貨幣を鋳造する必要に迫られました。
③【誤】
貫高制は、土地の生産力を銭の額(貫文)で表示する制度で、貨幣経済の浸透を示しますが、貨幣を「鋳造する」直接の理由としては②ほど適切ではありません。
④【誤】
戦国時代、日本は石見銀山などの開発により世界有数の銀産国となり、銀を「輸出」する側でした。銀が大量に「流出」して問題となるのは、主に江戸時代の貿易構造です。
問5:正解④
<問題要旨>
中世(鎌倉時代~戦国時代)の武士のあり方について、総合的に理解しているかを問う問題。
<選択肢>
①【誤】
1150年代の保元の乱・平治の乱で武家の棟梁の地位を高めたのは平清盛などです。一方、勘合を用いた日明貿易を開始したのは、15世紀初頭の室町幕府3代将軍・足利義満であり、時代が大きく異なります。
②【誤】
鎌倉幕府が定めた御成敗式目は、あくまで武家社会内部の道理を中心とした法であり、朝廷の公家法(律令など)や荘園領主の本所法の効力を完全に否定して、それに取って代わるものではありませんでした。
③【誤】
南北朝時代(14世紀)になると、分割相続が進んで血縁的な一族の団結が弱まる一方、在地での利害を共通にする近隣の武士たちが地縁によって団結する「国人一揆」などが盛んになります。記述は逆の傾向を述べています。
④【正】
応仁の乱(15世紀後半)以降、室町幕府の権力が衰えると、それまで守護を補佐していた守護代や、在地の有力武士であった国人の中から、実力で守護を倒し、領国を独自に支配する「戦国大名」が登場しました。これは下剋上の時代の特徴を的確に説明しています。
第5問
問1:正解④
<問題要旨>
近世社会の基礎を築いた太閤検地と、その下での百姓の立場について、正しく理解しているかを問う問題。
<選択肢>
①【誤】
文「あ」が誤りです。太閤検地では、それまで領主ごとに異なっていた枡を、全国統一基準の「京枡」に定めました。
②【誤】
文「あ」が誤りです。
③【誤】
文「X」が誤りです。豊臣秀吉の刀狩令などで兵農分離が進められ、百姓が武器を持つことは原則として禁じられました。
④【正】
文「い」は、太閤検地が一地一作人の原則を確立し、耕作者を検地帳に登録して土地の所持と年貢負担を直接結びつけた点を正しく説明しています 。文「Y」も、百姓が石高に応じた本年貢の他に、小物成などの様々な雑税を負担していたという近世の税制を正しく説明しています 。
問2:正解③
<問題要旨>
江戸時代の村掟(村法)の資料から、近世の村における自治や連帯責任のあり方を読み解く問題。
<選択肢>
①【誤】
資料には、罪の重さに応じて「村から追放」や「1000文の罰金」、「300文の罰金」など、異なる処罰が定められています 。
②【誤】
資料の末尾に「定めた通りの処罰を村として行う」とあり、処罰の主体が領主ではなく村自身であったことがわかります 。
③【正】
資料には、罪を犯した本人だけでなく「その五人組には1000文の罰金を払わせる」といった記述があり、五人組という制度を通じて、連帯責任が課されていたことが明確に読み取れます 。
④【誤】
幕府は慶安の御触書(発布年次に諸説あり)に代表されるように、法令によって農民の生活全般にわたって細かく規制・統制していました。「法令を発布しなかった」という背景認識が誤りです。
問3:正解⑥
<問題要旨>
江戸幕府が実施した、百姓の経営や村を維持するための諸政策を、年代順に正しく配列する問題。
<選択肢>
・I「旧里帰農令」に代表される、江戸への人口流入を抑制する政策は、寛政の改革(1787~93年)や天保の改革(1841~43年)で実施されました。
・II「青木昆陽を登用して甘藷栽培を奨励」したのは、享保の改革(1716~45年)を主導した将軍徳川吉宗です。
・III 百姓の経営安定を主眼とする政策への転換は、17世紀後半の文治政治への移行期に見られ、代表的なものに1643年の田畑永代売買の禁止令があります。
これらの出来事を年代順に並べると、III(17世紀後半)→ II(18世紀前半)→ I(18世紀末~19世紀前半)となります。この順序に合致するのは⑥です。
問4:正解②
<問題要旨>
天明3年(1783年)の浅間山大噴火で被災した鎌原村に関する二つの時代の資料(メモ3)を比較・読解し、その内容と合致する記述を選ぶ問題。
<選択跡>
①【誤】
文「う」が誤りです。慶応2年(1866年)の時点でも、耕地・人口ともに被災前の状態には回復していません 。
②【正】
文「あ」は、メモ3冒頭の「火山の噴火による泥砂などが流れ込み」「村人597人中、生き残ったのは131人」という記述から、被害が甚大であったことがわかり、正しいです 。文「え」も、慶応2年の人口が199人と、被災前の597人には及んでいないことから、回復しなかったことがわかり、正しいです 。
③【誤】
文「い」が誤りです。慶応2年の資料に「荒地は年貢賦課の対象外となっている」とあり、実質的な年貢負担は軽減されていたことがわかります 。
④【誤】
文「い」が誤りです。
問5:正解③
<問題要旨>
グラフや資料から読み取れる情報をもとに、近世の村に関する記述として不適切なものを見つけ出す問題。
<選択肢>
①【適】
近世の村では、検地帳に登録され土地を所持する本百姓が正規の構成員(村方役人なども彼らから選出)であり、土地を持たない水呑百姓などの発言権は制限されていました。
②【適】
問4の資料で、被災した鎌原村の生存者を「他村の名主が世話している状態」とあることから、村同士の協力関係があったことがわかります 。
③【不適】
グラフを見ると、石高と年貢高は連動しているものの、その比率(年貢率)は一定ではありません。例えば、1745年の年貢率は約38%(170万石/450万石)ですが、1785年には約32%(140万石/435万石)に低下しています。年貢率が固定されていたという記述は、グラフの示す内容と反します。
④【適】
江戸時代前期には、幕府や藩の主導で大規模な新田開発が行われ、全国の耕地面積・石高が増加しました。グラフが示す17世紀から18世紀半ばにかけての石高の増加は、この史実と合致しています。
第6問
問1:正解①
<問題要旨>
西南戦争時に発行された「西郷札」に関する新聞記事(資料1)を読み解き、当時の歴史的背景と正しく結びつける問題。
<選択肢>
①【正】
内容「あ」について、『読売新聞』の記事に「西郷の札まで今は地に落ちて」とあり、西郷隆盛の敗戦とともに西郷札の価値が暴落したことが読み取れます 。政策「X」について、西南戦争が勃発した1877年、政府は地租改正に対する農民一揆の激化を憂慮し、地租率を3%から2.5%に引き下げました。時期・内容ともに正しいです。
②【誤】
政策「Y」が誤りです。政府が兌換紙幣である日本銀行券を発行し、銀本位制を確立するのは1880年代の松方財政によるものであり、西南戦争の時期とは異なります。
③【誤】
内容「い」が誤りです。資料1の『朝日新聞』の記事は1895年のもので、「総督府」とは日清戦争後に設置された台湾総督府を指すと考えられ、朝鮮ではありません 。
④【誤】
内容「い」、政策「Y」ともに誤りです。
問2:正解④
<問題要旨>
松本清張の軍隊時代(1944~45年)に関する自伝(資料2)とその時期の朝鮮半島の状況について、不適切な記述を選ぶ問題。
<選択肢>
①【適】
資料2には、軍隊での仕事が「飯あげ、使役、洗濯、掃除以外には仕事はなかった」とあり、単調であったことがうかがえます 。
②【適】
資料2には、英語の教科書を「こっそりとひろげているところを発見されると、どんな処罰をうけるか分らない心配はあった」とあり、敵性語とされた英語を学ぶことに危険を感じていたことがわかります 。
③【適】
1944~45年頃の朝鮮半島では、日中戦争の長期化に伴い、日本語の使用や神社参拝、創氏改名などを強制する皇民化政策が強化されていました。
④【不適】
朝鮮総督府による土地調査事業は、朝鮮併合(1910年)直後の1910年代に行われた政策です。1940年代の出来事ではないため、時期が全く異なります。
問3:正解⑥
<問題要旨>
日本のマスメディア史における象徴的な出来事を、年代順に正しく配列する問題。
<選択肢>
・III 『朝日新聞』などが100万部を超える発行部数となるのは、ラジオ放送が始まるなど大衆文化が花開いた大正デモクラシー期(1920年代頃)です。
・II 政府によるメディア統制が極度に強化されたのは、日中戦争から太平洋戦争にかけての戦時体制下(1930年代後半~1945年)です。
・I 手塚治虫に代表されるストーリー漫画が戦後の子ども文化を席巻し、今日の漫画・アニメ文化の礎を築いたのは、第二次世界大戦後、特に1950年代以降です。
これらの出来事を年代順に並べると、III → II → I となります。この順序に合致するのは⑥です。
問4:正解④
<問題要旨>
松本清張が『日本の黒い霧』で題材とした「占領期」(1945年~1952年4月)に起きた出来事として、適切でないものを選ぶ問題。
<選択肢>
①【適】
二・一ゼネストは1947年に計画されましたが、GHQの指令により中止に追い込まれました。占領期の代表的な労働運動です。
②【適】
社会党・民主党・国民協同党による中道連立の芦田均内閣が、昭和電工事件という汚職事件で総辞職したのは1948年のことです。占領期の出来事です。
③【適】
国鉄の初代総裁が謎の死を遂げた下山事件など、国鉄をめぐる一連の怪事件は1949年に発生しました。占領期の出来事です。
④【不適】
破壊活動防止法(破防法)が制定されたのは、1952年7月です。サンフランシスコ平和条約が発効し、日本が独立を回復した(1952年4月28日)後の出来事であり、厳密には占領期に含まれません。
問5:正解②
<問題要旨>
1971年に描かれた漫画(資料3)を題材として、そこから生じた疑問と、その解明に最も適した調査方法の組み合わせを選ぶ問題。
<選択肢>
①【誤】
調べ方Yが不適切です。「規制緩和・構造改革」は1971年当時の主要な政治課題とは言い難く、漫画の文脈とも離れています。
②【正】
疑問「あ」(女性の政治参加の程度)を調べるには、調べ方「W」(男女別投票率の調査)が、参加の度合いを示す客観的指標として最も適切です。疑問「い」(なぜ松本清張が登場したか)を調べるには、調べ方「Z」(当時の週刊誌などでの社会的評価を調査)が、漫画が描かれた同時代の大衆的なイメージや評価を知る上で最も有効な方法です 。
③【誤】
調べ方Yが不適切です。
④【誤】
調べ方XはWに比べて、政治参加の「程度」を調べる上でやや間接的です。