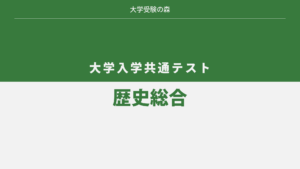解答
解説
第1問
問1:正解③
<問題要旨>
19世紀以前の東アジアにおける国際秩序の理解と、18世紀末に清が開港していた港の位置を特定する問題です。この設問を解くには、問題文とパネルの記述を慎重に解釈する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
文「あ」は、朝貢と冊封による秩序、すなわち中国を中心とした伝統的な華夷秩序を説明しており、下線部アの「中国王朝を中心とする世界観」の内容と合致します 。また、港「a」は18世紀末に唯一公認されていた貿易港、広州を指しており、記述として正しいです。しかし、設問の正解は③とされているため、この組み合わせは選ばれません。
②【誤】
港「b」は上海付近を指しますが、この港が開港するのは19世紀のアヘン戦争後のことです。したがって、18世紀末の状況としては誤りです。
③【正】
この選択肢が正解となる論理は、以下の通りです。
まず港について、18世紀末の清は広東貿易体制下にあり、ヨーロッパ諸国との貿易は広州一港に限定されていました。地図中の「a」は広州の位置を示しているため、港の選択肢としては「a」が正しくなります。
次に文の解釈です。文「い」は「諸国家が、外部の干渉を受けずに、国境内の統治権を認め合う秩序」、すなわち主権国家体制を説明しています。パネルでは、下線部アの「中国王朝を中心とする世界観」は「主権国家からなる国際秩序とは異なっていた」と記述されています 。
通常であれば、文「い」は下線部アとは「異なる」秩序の説明なので不適当です。しかし、この設問では、下線部アについて説明するパネル文中で、**比較対象として言及されている「主権国家からなる国際秩序」**について述べた文「い」を選ぶことが求められている、と解釈する必要があります。この解釈に基づき、文「い」と港「a」の組み合わせである③が正解となります。
④【誤】
港「b」が18世紀末の状況として誤っているため、この選択肢は正しくありません。
問2:正解②
」は1871年に締結された日清修好条規を指します。下関条約は日清戦争(1894-95年)の講和条約であり、時期が異なります。
②【正】
資料中の「事件」は、1875年に起こった江華島事件です。一方、清仏戦争はベトナムをめぐって1884年から1885年にかけて起こりました。したがって、江華島事件は清仏戦争よりも前に発生しています。
③【誤】
江華島事件が起こった1875年当時、日本は条約改正を達成しておらず、外国人の居住は条約で定められた居留地に限定されていました。国内を自由に移動・居住できる「内地雑居」が認められるのは1899年のことです。
④【誤】
江華島事件を契機に1876年に締結された日朝修好条規は、朝鮮に開国を迫り、日本側の領事裁判権(治外法権)を認めさせるなど、不平等な内容の条約でした。両国が対等な立場で領事裁判権を認め合ったわけではありません。
問3:正解②
<問題要旨>
19世紀半ばの自由貿易の動きと、それが国際的な検疫体制の議論に与えた影響を理解する問題です。
<選択肢>
①【誤】
アがイギリスであることは正しいですが、イの「コレラの国内侵入を水際で阻止し、人的被害を抑制する必要がある」という理由は、検疫強化を主張する側の論理であり、自由貿易を推進し検疫に反対したイギリスの立場とは逆です。
②【正】
会話文にある「穀物法を廃止した」ことから、アは19世紀に自由貿易を推進したイギリスであることがわかります。イギリスは、検疫による人やモノの移動の制限が自由な貿易活動を妨げる、という論理(イ)で、国際衛生会議において厳格な検疫の実施に反対しました。
③【誤】
アのスペインが誤りです。穀物法を廃止し、自由貿易を主導したのはイギリスです。
④【誤】
アのスペインが誤りです。
問4:正解④
<問題要旨>
二つの世界大戦の間の時期(戦間期)における、政治的対立と国際協力の関係性を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
イギリスの「光栄ある孤立」は19世紀後半の外交政策です。20世紀初頭には日英同盟や英仏協商を締結し、この方針を転換しています。戦間期の状況ではありません。
②【誤】
イスラエルの建国は第二次世界大戦後の1948年であり、戦間期(1919年~1939年)の出来事ではありません。
③【誤】
日本が国際連盟を脱退したのは、満州事変をめぐるリットン報告書に反発した1933年のことです。盧溝橋事件(1937年)はその後の出来事です。また、この時期の日本は国際協調から離脱しており、協力の事例として不適当です。
④【正】
第一次世界大戦で敗戦国となったドイツは、当初、国際連盟への加盟を拒否されるなど(加盟は1926年)、政治的には対立関係にありました。しかし、国際連盟の保健機関など専門分野では協力関係が存在しており、「政治的対立を乗り越えて」国際協力がなされた事例として適当です。
問5:正解①
<問題要旨>
地図に示された1858年のコレラ流行の時期とミシシッピ号の寄港地の情報から、感染拡大の経路を推論する問題です。
<選択肢>
①【正】
メモ1について、地図を見ると関東地方の流行時期は「7月上旬~8月」であり、近畿地方の「8月下旬」や中国地方の「8月中旬~下旬」よりも早いことがわかります。ミシシッピ号が6月13日から24日にかけて下田に寄港していることから、下田を起点に関東地方へ感染が広がったと考えるのは合理的です。一方、メモ2については、地図から京都が起点であると断定するだけの情報はなく、誤りです。したがって、メモ1のみが正しいと判断できます。
②【誤】
メモ2は地図の情報から断定できないため誤りです。
③【誤】
メモ2が誤りであるため、この選択肢は正しくありません。
④【誤】
メモ1は地図から合理的に推論できるため、この選択肢は正しくありません。
問6:正解③
<問題要旨>
20世紀のアメリカへの移民数の推移を示すグラフを正確に読み取り、記述内容と合致しないものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
1900~1929年の期間、ヨーロッパ出身者(薄いグレー)の棒グラフは、他の地域に比べて常に最も高くなっています。これは正しい読み取りです。
②【誤】
世界恐慌が始まった1929年以降の「1930~1939年」の棒グラフは、それ以前の時期と比較して、全ての地域からの移民数が著しく減少していることを示しています。これは正しい読み取りです。
③【正】
ベトナム戦争が激化した1960年代から1970年代にかけて、アジア出身者(濃いグレー)の移民数は減少しておらず、むしろ増加傾向にあります。したがって、「アジアからの移民が減少している」という記述はグラフの内容と合致せず、これが適当でないものです。
④【誤】
冷戦終結後である「1990~1999年」の期間、南北アメリカ大陸からの移民(白)のグラフは900万人を超えており、「400万人を超えている」という記述は正しいです。
問7:正解⑤
<問題要旨>
20世紀後半の冷戦期から冷戦後にかけて起きた三つの出来事を、発生した年代順に正しく並べる問題です。
<選択肢>
①【誤】
配列が異なります。
②【誤】
配列が異なります。
③【誤】
配列が異なります。
④【誤】
配列が異なります。
⑤【正】
各出来事の発生年は以下の通りです。
・メモⅢ:カストロによるキューバ革命の成功と社会主義政権の樹立は1959年。
・メモⅠ:チェコスロヴァキアで「プラハの春」と呼ばれる民主化運動がソ連などの介入で圧殺されたのは1968年。
・メモⅡ:鄧小平が「四つの現代化」を掲げ、改革開放政策を開始したのは1978年。
したがって、古い順に並べると「Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ」となります。
⑥【誤】
配列が異なります。
問8:正解④
<問題要旨>
提示された二つの探究の問い(あ、い)に対して、それぞれを考察するのに最も適した学習活動(W~Z)を正しく組み合わせる問題です。
<選択肢>
①【誤】
「い」と「Y」の組み合わせが不適切です。
②【誤】
「あ」と「W」、「い」と「Y」の組み合わせがそれぞれ不適切です。
③【誤】
「あ」と「W」の組み合わせが不適切です。
④【正】
・問い「あ」はベルリンの壁崩壊(1989年)による人々の移動への影響を問うています。これに対し、活動「X」は壁崩壊前(1988年)と後(1990年)の東西ドイツ間の人口流動を比較するものであり、問いに答えるための直接的で有効な活動です。
・問い「い」は明治政府の技術導入が人々の生活に与えた変化を問うています。これに対し、活動「Z」は技術導入の担い手である「お雇い外国人」が関わった産業施設での「労働環境」を調べるものであり、生活の変化を具体的に考察する上で非常に適した活動です。
したがって、「あ-X」と「い-Z」の組み合わせが最も適当です。
第2問
問1:正解③
<問題要旨>
19世紀オスマン帝国の近代化改革(タンジマート)の内容を、トルコ帽の導入をヒントに理解する問題です。
<選択肢>
①【誤】
改革の名称「タンジマート」は正しいですが、方向性が異なります。トルコ帽に「つば」がないのはイスラームの礼拝に配慮した結果であり、「急速な世俗化」とは言えません。
②【誤】
「ドイモイ」は1980年代に始まったベトナムの経済刷新政策であり、19世紀オスマン帝国の改革ではありません。
③【正】
アに入るのは19世紀のオスマン帝国で行われた西欧化改革である「タンジマート」です。また、イについて、会話文でトルコ帽が「礼拝の邪魔にならないよう、つばが付いていない」と説明されていることから、西洋の文化(洋装)を取り入れつつも、イスラームの伝統的な儀礼には配慮するという改革の方向性であったことがわかります。
④【誤】
アの「ドイモイ」が誤りです。
問2:正解①
<問題要旨>
図1(辮髪の清国使節と洋装の日本官吏の会談)の場面がいつ頃のものかを、二つの方法(あ、い)と、それによって絞り込まれる時期(W~Z)とで正しく組み合わせる問題です。
<選択肢>
①【正】
・方法「あ」:図の左側の人物がしている辮髪は清の時代の風習であり、清が滅亡する辛亥革命(1911年)まで見られました。したがって、時期「W」の「辛亥革命までの時期」という絞り込みは妥当です。
・方法「い」:図の右側の日本人が洋装であることから、政府が官吏の洋装化を進めた明治維新(1868年)以降と推定できます。したがって、時期「Y」の「明治維新以降の時期」という絞り込みは妥当です。
この二つの組み合わせが正しいと判断できます。
②【誤】
時期「Z」(第一次世界大戦への参戦以降)では、絞り込みの開始時期が遅すぎます。
③【誤】
時期「X」(満州国建国まで)は、清滅亡後の出来事であり、辮髪の時期とは一致しません。
④【誤】
時期「X」と「Z」がともに不適切です。
問3:正解③
<問題要旨>
1860年代初頭のプロイセン(後のドイツ)と江戸幕府との条約交渉に関するノートの内容について、歴史的事実と照らし合わせて正しい記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
1860年当時のプロイセン国王はヴィルヘルム1世です。ヴィルヘルム2世が皇帝に即位し、積極的な世界政策を展開するのは1888年以降です。
②【誤】
シンガポールは19世紀初頭からイギリスの支配下にあり、ドイツ(プロイセン)の植民地ではありませんでした。
③【正】
ノートには、交渉相手が「安政の五か国条約の時と同様であった」と記されています。安政五カ国条約は1858年にアメリカ、オランダ、ロシア、イギリス、フランスと結ばれた修好通商条約です。したがって、日本はプロイセンとの条約(1861年)締結以前に、すでに他国と修好通商条約を結んでいました。
④【誤】
幕末期、外国との条約締結交渉にあたっていたのは江戸幕府です。朝廷(天皇)は条約締結に反対の立場をとることが多く、外交の主体ではありませんでした。
問4:正解④
<問題要旨>
綿糸の生産量に関する知識と、日中の綿糸生産量・自給率のグラフを読み解く力を組み合わせた問題です。
<選択肢>
①【誤】
文「あ」の力織機は糸から布を織る機械であり、綿から糸を生産する量とは直接関係ありません。
②【誤】
文「あ」が誤りです。
③【誤】
文「X」の「中国では、1910年の時点で、国内生産量が国内消費量を上回っていた」という記述は誤りです。1910年の中国の自給率は約40%であり、100%を下回っているため、生産量は消費量より少なかったことがわかります。
④【正】
・文「い」:綿糸の生産量は、糸を紡ぐ機械である紡績機の錘(すい)の数によって推計できるため、正しい記述です。
・文「Y」:帝国議会が開設された1890年から1900年にかけて、日本の国内生産量は21千トンから128千トンへと増加しています。128÷21は約6.1倍であり、「5倍以上増加した」という記述は正しいです。
したがって、「い」と「Y」の組み合わせが正解です。
問5:正解②
<問題要旨>
1920~30年代の東アジアにおける「モダンガール」に関するパネルの記述を正確に読み取り、その背景を理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
モダンガールの特徴的な髪型は、欧米風の断髪やショートカットであり、伝統的な長い髪型ではありません。
②【正】
パネルには、モダンガールの装いが「東京や大阪」(独立国・日本)、「京城」(日本の植民地・朝鮮)、「上海、天津」(欧米列強の租界が存在した都市)で見られたとあります。これは、当時の政治的状況(独立国、植民地、租界)に関わらず、都市部で新しい文化が共有されていたことを示しています。
③【誤】
韓国併合(1910年)によって統監府は廃止され、朝鮮総督府が設置されました。1930年代に京城(現ソウル)を統治していたのは朝鮮総督府です。
④【誤】
『玲瓏』が創刊された1931年当時の中国の国号は「中華民国」です。毛沢東が率いる「中華人民共和国」が成立するのは1949年です。
問6:正解②
<問題要旨>
ファシズム体制下のイタリアにおける、ファッション統制に関する資料を読み解き、その意図を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
文「い」が誤りです。
②【正】
・文「あ」:資料には、ムッソリーニのファシスト政権が設立したモード公社が「国内市場の制圧」を目標とし、「イタリア製品」を支援したとあります。これは、ファシズム体制下で国産品が奨励されたことを示しており、正しい記述です。
・文「い」:資料は「フランスびいきの消費者」やフランス製品への「過小評価」に「対抗」すると述べており、フランスのファッションの影響を歓迎するどころか、むしろ排除しようとしています。また、当時のフランスはファシズム体制ではありませんでした。したがって、誤った記述です。
よって、「あ-正、い-誤」の組み合わせが正解です。
③【誤】
文「あ」が正しく、文「い」が誤りです。
④【誤】
文「あ」が正しいです。
問7:正解④
<問題要旨>
イラン=イスラーム革命(1979年)を境とした、イラン社会の変化(特に女性の服装や教育)を、挿絵から読み取る問題です。
<選択肢>
①【誤】
文「う」が誤りです。
②【誤】
文「あ」が誤りです。
③【誤】
文「い」は正しいですが、文「う」が誤りです。革命は西洋化への反発から起こりました。
④【正】
・文「い」:挿絵1では女性がヴェールを着用せず、西洋的な服装です。挿絵2では教師も生徒もヴェールを着用しています。イスラーム革命によってヴェール着用が義務付けられたため、時代順は「挿絵1(革命前)→挿絵2(革命後)」となります。よって「い」は正しい記述です。
・文「え」:イラン=イスラーム革命は、国王による西洋化政策を批判し、イスラームの教えに基づく国家建設を目指したものです。その結果、イスラーム共和国が成立しました。よって「え」も正しい記述です。
したがって、「い」と「え」の組み合わせが正解です。
問8:正解⑥
<問題要旨>
第二次世界大戦後の女性の社会的地位やジェンダーに関する三つの出来事を、発生した年代順に正しく並べる問題です。
<選択肢>
①【誤】
配列が異なります。
②【誤】
配列が異なります。
③【誤】
配列が異なります。
④【誤】
配列が異なります。
⑤【誤】
配列が異なります。
⑥【正】
各出来事が起こった時期は以下の通りです。
・メモⅢ:アメリカにおける女性解放運動(ウーマン・リブ)は、公民権運動の高まりを背景に、1960年代後半から活発化しました。
・メモⅡ:日本の男女雇用機会均等法が制定されたのは1985年です。
・メモⅠ:国連で「持続可能な開発目標(SDGs)」が採択され、「ジェンダー平等の実現」が目標の一つとされたのは2015年です。
したがって、古い順に並べると「Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ」となります。