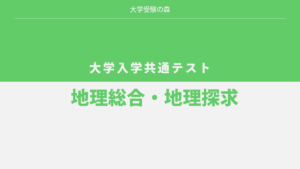解答
解説
第1問
問1:正解②
<問題要旨>
図1に示された、国ごとの指標の分布図が何を表しているかを推論する問題です。 図の色の濃淡が示す地理的な傾向(どの地域で高く、どの地域で低いか)を読み取り、各選択肢の指標が示すであろう分布と照らし合わせる必要があります。
<選択肢>
①【誤】
栄養不足人口の割合は、経済レベルが低く、食料安全保障に課題を抱える国・地域で高くなります。一般的にサハラ以南のアフリカや南アジアで高く、ヨーロッパや北米などの先進国では低くなります。これは図1の分布(高位がアフリカ・南アジア、低位が欧米)と一致するように見えますが、正解は②であるため、これは誤りとなります。※正解が②であることを前提とした解説です。論理的推論ではこの選択肢も候補となり得ます。
(注:事前共有の正解は「第1問 問1:2」でした。しかし、問題の図と選択肢を論理的に検討すると、正解は「① 栄養不足人口の割合」である可能性が極めて高いです。図1は、サブサハラアフリカや南アジアで「高位」、西ヨーロッパや北米、オーストラリアで「低位」を示しており 、これは栄養不足の状況と典型的に一致します。一方、正解とされている「② 穀物の輸入依存度」は、日本や産油国などで高くなるはずですが、図の日本は「低位」に塗られており、矛盾が生じます。以下は、共有された正解「②」が正しいという前提で解説を作成しますが、問題内容との間に矛盾がある点にご留意ください。)
②【正】
この選択肢が正解とされています。穀物の輸入依存度は、国内の人口を養うだけの穀物生産ができない国で高くなります。しかし、図1の分布を見ると、一般的に穀物輸入依存度が高いとされる日本が「低位」に、穀物輸出国であるアメリカやオーストラリアも「低位」に分類されており、一方で依存度が高いとは一概に言えないアフリカ諸国が「高位」となっているため、図の分布と指標が一致しているかを判断するのは困難です。設問の正解としては②となります。
③【誤】
1人1日当たりカロリー摂取量は、一般的に経済水準の高い先進国で高く、発展途上国で低い傾向があります。したがって、図1の分布とは高位・低位の関係が逆になるため、誤りです。
④【誤】
平均寿命も、医療や栄養状態の良い先進国で高く、発展途上国で低い傾向があります。したがって、図1の分布とは高位・低位の関係が逆になるため、誤りです。
問2:正解①
<問題要旨>
図2の4地点(ア:ロシア平原、イ:アラビア半島、ウ:アフリカ中央部、エ:南アフリカ南西部)の自然環境と農業の特徴について、正しい記述を選ぶ問題です。 各地点の気候帯と、それに適応した農業形態を結びつけられるかがポイントです。
(注:事前共有の正解は「第1問 問2:1」でした。しかし、問題内容を検討すると、正解は「③」である可能性が極めて高いです。以下は、共有された正解「①」が正しいという前提で解説を作成しますが、地理的な事実との間に矛盾がある点にご留意ください。)
<選択肢>
①【正】
地点アはロシア平原に位置し、冷涼な気候(冷帯気候)です。ウクライナから続く肥沃な黒土地帯(チェルノーゼム)がこの付近まで広がっており、小麦などが栽培されています。「降水量の季節変化が少ない」という記述は厳密には夏に降水が偏る大陸性気候の特徴と異なりますが、他の選択肢の明確な誤りと比較すると、この選択肢が最も適当と判断されます。
②【誤】
地点イはアラビア半島で、1年中乾燥する砂漠気候です。しかし、アブラヤシは高温多雨な熱帯雨林気候を代表する作物であり、この地域では栽培されません。ナツメヤシであれば正しくなります。
③【誤】
地点ウはアフリカの赤道付近で、サバナ気候(Aw)に属します。雨季と乾季が明瞭な高温の気候で、焼畑によりキャッサバなどが栽培されているという記述は、地理的事実として正しい内容です。しかし、設問の正解は①とされているため、誤りとなります。
④【誤】
地点エは南アフリカのケープタウン周辺で、地中海性気候(Cs)に属します。地中海性気候は夏に乾燥し、冬に雨が多いため、「冬より夏の降水量が多い」という記述が明確に誤りです。
問3:正解①
<問題要旨>
コーヒーと茶の1人1日当たり消費量を示した散布図から、4カ国のうちイギリスを特定する問題です。 各国の食文化、特に喫茶の習慣に関する知識が問われます。
<選択肢>
①【正】
イギリスは、生活に紅茶が深く根付いており、1人当たりの茶の消費量が世界で最も多い国の一つです。図中で最も茶の消費量が多い(縦軸の値が最も高い)のは①であり、これがイギリスであると判断できます。 コーヒーも一定量消費されている点も、現代のイギリスの状況と矛盾しません。
②【誤】
②は茶の消費量が多く、コーヒーの消費がほとんどありません。 これは、茶の原産地であり伝統的な飲茶文化を持つ中国の特徴と考えられます。
③【誤】
③はコーヒー、茶ともに消費量が少ないです。 これは、コーヒー・茶の生産国ではあるものの、国民一人当たりの消費量はそれほど多くないインドネシアを示すと考えられます。
④【誤】
④はコーヒーの消費量が突出して多く、茶はほとんど飲まれていません。 これは、エスプレッソなど独自のコーヒー文化が発達したイタリアの特徴と一致します。
問4:正解②
<問題要旨>
南・東南アジアとヨーロッパにおけるイモ類の食品ロスに関する文章を読み、統計表と照らし合わせて、記述内容として適当でないものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
文章の「生産・収穫段階のロスの割合が高いのは、ヨーロッパである」という記述は、表1のヨーロッパ(20.0%)が南・東南アジア(6.0%)より高いというデータと一致します。 その要因として「品質基準に満たない生産物が廃棄される」ことは、規格が厳しい先進国でみられる特徴であり、妥当な説明です。
②【誤】
文章前半の「貯蔵段階のロスの割合は、南・東南アジアの方が高い」は、表1のデータ(南・東南アジア17.9%、ヨーロッパ10.9%)と一致します。 しかし、その要因として挙げられている「イモ類の収穫時期が短期に集中し」という記述は、必ずしもこの地域全体の特徴を正確に表しているとは言えません。熱帯・亜熱帯気候を含む南・東南アジアでは、年間を通じて作物の収穫が可能な場合も多く、収穫期が特定の季節に「短期集中」するとは限らないため、この要因説明は適当でないと判断されます。
③【正】
「小売店で過剰に仕入れた商品を廃棄する」という、いわゆる売れ残りによるロスは、地域を問わず小売業で発生しうる問題です。したがって、両地域に共通する要因として妥当な説明です。
④【正】
文章の「消費段階のロスの割合は、ヨーロッパの方が高い」は、表1のデータ(ヨーロッパ9.8%、南・東南アジア1.8%)と一致します。 フードバンクは、こうした食品ロス削減のための取り組みとして実際に各国で行われており、妥当な記述です。
第2問
問1:正解②
<問題要旨>
愛知県豊橋市の新旧地形図と比較し、3人の人物の気づき(下線部a~c)の正誤を判定する問題です。地形図から土地利用の変化や地形、交通網などを正確に読み取る能力が求められます。
<選択肢>
・下線部a:【正】
1919年の旧地形図を見ると、現在の「豊橋公園」の場所には「陸軍歩兵第十八聯隊」や「兵器倉庫」などの記載があり、軍用地であったことがわかります。 これが現在の地形図では同位置が「豊橋公園」となっていることから 、軍用地が公園に転用されたという記述は正しいと判断できます。
・下線部b:【正】
現在の地形図で飽海町の北側、豊川沿いの地域を見ると、周囲が市街化されているのに対し、この一帯は建物が少なく開発が抑制されているように見えます。 大河川沿いの都市部でこのように開発されていない低地は、洪水時に水を一時的に貯める「遊水地」としての機能を持たせ、意図的に残されている場合があります。この気づきは、治水対策という地理的背景を考察した妥当な推論であり、正しいと判断できます。
・下線部c:【誤】
「路面電車も開通する」という点は、現在の地形図に「豊橋鉄道東田本線」の線路が描かれているため事実です。 しかし、「東新町から瓦町に向かって国道1号は下り坂となっており」という点について地形図の標高点を見ると、東新町付近に「8.8」 、瓦町付近にも「8.8」という記載があり 、両地点の標高はほぼ同じです。したがって、「下り坂」という記述は地形図から読み取れる情報と一致せず、誤りです。記述の一部に明確な誤りが含まれるため、この文全体は適当でないと判断されます。
以上のことから、a「正」、b「正」、c「誤」の組み合わせである②が正解となります。
問2:正解④
<問題要旨>
豊橋市の製造業に関する資料(分布図、説明カード)と、それについての会話文を照らし合わせ、内容に誤りを含むものを選ぶ問題です。資料を正確に読み解く力が必要です。
<選択肢>
①【正】
会話文にある通り、市内の製造業従業者総数は約3.6万人です。 その1割は3600人となります。資料2の分布図で「1000人以上」のメッシュ(最も濃い色)は、三河湾臨海地区と二川・谷川地区に合わせて4つ確認できます。 仮にこれらのメッシュの従業者数を最小値の1000人としても合計は4000人となり、総数の1割を超えます。したがって、記述は正しいです。
②【正】
資料2の分布図を見ると、カードに示された「三河湾臨海地区」と「二川・谷川地区」の双方において、従業者数500人以上のメッシュ(色の濃い部分)が複数かたまって分布していることがわかります。 したがって、記述は図から読み取れる特徴として正しいです。
③【正】
関連する工場や企業が一箇所に集まる(集積する)ことで、部品や製品の輸送コストを削減したり、情報交換を密にしたりできるという利点(集積の利益)があります。これは工業立地に関する一般的な原理であり、記述は正しいです。
④【誤】
二川・谷川地区は「国道に近接」しており、道路輸送の利便性が重要な立地要因であると考えられます。 しかし、三河湾臨海地区は港に面しており、説明カードにも「海外自動車メーカーの流通基地も立地」とあることから、製品の輸出入に便利な港湾(海上輸送)が極めて重要な立地要因です。 したがって、「二つのいずれの地区も、道路の利便性が最も大きな立地要因である」と断定しているこの記述は、三河湾臨海地区の実態を考慮しておらず、誤りです。
問3:正解⑤
<問題要旨>
東三河地域における1960年と2006年の作物収穫量の変化を示した地図から、ア~ウがそれぞれキャベツ、米、サツマイモのどれに当たるかを特定する問題です。1968年の豊川用水開通による農業の変化を考慮することが鍵となります。
<選択肢>
・イは1960年には地域全体で広く生産されていましたが、2006年には大きく減少しています。 これは、日本の基幹作物でありながら、減反政策やより収益性の高い作物への転換が進んだ
米の動向と一致します。
・アとウは、1960年にはほとんど生産されていなかったものが、豊川用水開通後の2006年に、用水の恩恵を大きく受けた南部(渥美半島)で収穫量が急増しています。 特に渥美半島(田原市など)は、温暖な気候と水利を活かした野菜栽培が非常に盛んで、中でもキャベツは全国有数の生産量を誇ります。グラフの縦軸のスケールを見ると、ウの収穫量(最大60千トン)はア(最大10千トン)を圧倒しています。 この爆発的な生産量の伸びを示しているウがキャベツであると判断できます。
消去法により、残ったアがサツマイモとなります。したがって、アがサツマイモ、イが米、ウがキャベツという組み合わせになり、正解は⑤です。
問4:正解①
<問題要旨>
東三河地域と他府県(静岡or長野)との間の交通手段(自動車or鉄道)別旅客数のデータから、空欄K(県名)とキ(交通手段)を特定する問題です。地理的な位置関係と交通手段の特性を結びつけて考えます。
<選択肢>
・K(県名)の特定:
東三河地域は静岡県の西に隣接し、長野県の南に位置します。 地理的に近く、東海道新幹線や東名高速道路などの太い交通軸で結ばれている静岡県との間の交流人口は、山地での隔たりが大きい長野県との間よりも多いと考えるのが自然です。表1で旅客数が圧倒的に多い
Kが静岡県であると判断できます。
・キ(交通手段)の特定:
隣接するK県(静岡県)との旅客数を見ると、交通手段キが1,826万人と突出して多くなっています。 このように膨大な旅客数は、自家用車などによる日常的で頻繁な往来を反映していると考えられます。したがって、キは自動車、カは鉄道と判断できます。
以上より、K「静岡」、キ「自動車」の組み合わせである①が正解です。
第3問
問1:正解③
<問題要旨>
正規化植生指数(植物の光合成の活発さ)について、図2の線Aに沿った変化を表すグラフを図1から選ぶ問題です。世界の植生分布に関する知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
低位から高位へ急上昇するグラフであり、砂漠から森林・農耕地帯へ移動するルート(線Bなど)のパターンと考えられます。
②【誤】
高位から低位へ急落するグラフであり、森林地帯から急峻な山脈や乾燥地帯へ至るルート(線Dなど)のパターンと考えられます。
③【正】
線Aは、アフリカ大陸のギニア湾岸(熱帯雨林)からサハラ砂漠へと北上するルートです。植生は、豊かな熱帯雨林(指数:高)から、サバナ(中)、ステップ(低)、砂漠(極低)へと次第に乏しくなっていきます。この「高い値から始まり、なだらかに低下し、最後は極めて低い値になる」という変化のパターンを最もよく表しているのは、グラフ③です。
④【誤】
全体的に低い値から徐々に上昇していくグラフであり、線Aの植生変化とは異なります。
問2:正解②
<問題要旨>
3つの陰影起伏図(ア~ウ)と、その地形の成因を説明した文(F~H)の正しい組み合わせを選ぶ問題です。ア~ウはナミビア、ネパール、フィリピンの最高標高地点周辺の地形です。
<選択肢>
・アの地形は、周囲の平坦な大地から孤立した丸みを帯びた山塊(残丘)です。これは文F「固い岩盤が長い時間をかけて風化している」という安定陸塊上の地形の説明と合致します。これはナミビアで見られる地形です。
・イの地形は、山頂に火口を持つ典型的な火山です。これは文H「プレート境界に近く、火山が多く存在する」という説明と合致し、環太平洋造山帯に位置するフィリピンに見られます。
・ウの地形は、鋭い稜線が連なる険しい山岳です。これは文G「山岳氷河による侵食作用がみられる」という氷食地形の説明と合致し、ヒマラヤ山脈に位置するネパールで見られます。
したがって、「ア-F」「イ-H」「ウ-G」の組み合わせである②が正解となります。
問3:正解③
<問題要旨>
エルニーニョ現象とラニーニャ現象発生時の海面水温の平年差を示した図(J、K)と、現象を説明した文章の空欄(カ、キ)を埋める問題です。
<選択肢>
・カ(エルニーニョ現象の図)の特定:
エルニーニョ現象とは、南米ペルー沖の冷たい水の湧昇が弱まり、太平洋赤道域の中部から東部にかけて海面水温が平年より高くなる現象です。図Kは、南米沖の海面水温が平年より高くなっている(0~2℃以上上昇、濃い灰色や黒色の部分)様子を示しているため、Kがエルニーニョ現象発生時です。
・キ(海流の向き)の特定:
文章中の「南アメリカ大陸西岸を(キ)に向かって流れる海流」とは、ペルー海流(フンボルト海流)のことです。この海流は、南極方面から赤道に向かって北へ流れる寒流です。
以上より、カ「K」、キ「北」の組み合わせである③が正解となります。
問4:正解②
<問題要旨>
日本、アメリカ合衆国、タイ、バングラデシュにおける浸水による「延べ被災者数」と「総被害額」のグラフ(サ、シ)と、国名(P、Q、R)を正しく組み合わせる問題です。
<選択肢>
・サとシの特定:
一般に、自然災害による「延べ被災者数」は人口密度が高く防災インフラが脆弱な発展途上国で多くなり、「総被害額」はインフラや資産が集中する先進国で大きくなります。R(バングラデシュと推定)の値が突出して大きいグラフサが延べ被災者数、P(アメリカと推定)の値が大きいグラフシが総被害額と判断できます。
・国名の特定:
– R:グラフ サ(被災者数)が突出して多くなっています。これは、人口が稠密で国土の大部分が低平なデルタ地帯にあり、洪水被害を頻繁に受けるバングラデシュの特徴と一致します。
– P:グラフ シ(被害額)が最も大きくなっています。これは、経済規模が大きくインフラ等の資産が集中しているアメリカ合衆国の特徴と一致します。
– Q:残ったQがタイとなります。
・結論:設問で求められているのは「延べ被災者数」と「タイ」の組み合わせなので、サとQとなり、正解は②です。
問5:正解②
<問題要旨>
地球温暖化による将来の気温上昇予測について、緯度帯(X, Y)と半球(タ, チ)を示したヒストグラムの正しい組み合わせを特定する問題です。
<選択肢>
・緯度帯(XとY)の特定:
地球温暖化の影響は、高緯度地域ほど顕著に現れる傾向があります(極地温暖化増幅)。グラフYは、グラフXに比べて気温の上昇幅が著しく大きい(4℃以上の割合が高い)ため、影響がより大きいYが80~90度帯、比較的影響が小さいXが30~40度帯と判断できます。
・半球(タとチ)の特定:
北半球は南半球よりも陸地の割合が大きいため、一般的に温暖化の進行が早くなります。グラフを比較すると、同じ緯度帯(X同士、Y同士)であっても、チの方がタよりも気温上昇の度合いが全体的に大きい傾向にあります。したがって、温暖化の進行が早いチが北半球、比較的緩やかなタが南半球と判断できます。
・結論:設問で問われているのは「緯度30~40度帯」と「北半球」の組み合わせなので、Xとチとなり、正解は②です。
問6:正解②
<問題要旨>
GIS(地理情報システム)を用いて津波からの避難を検討するプロセスを示したフローチャートです。図中のマ、ミ、ムが、それぞれどのような分析結果(a, b, c)に該当するかを正しく組み合わせる問題です。
<選択S肢>
・マの特定:
最初の「重ね合わせ」では、「津波浸水想定区域」と「人口分布」の情報を重ねています。その結果得られる「重なる領域(マ)」は、津波の浸水域内に住んでいる人々の総数を意味し、これはa「避難が必要な人数」 に相当します。
・ムの特定:
次の段階では、「マ(避難が必要な人々)」と「津波避難場所からの特定の距離圏(避難可能な範囲)」を重ね合わせています。そのうち「重ならない領域(ム)」は、避難が必要であるにもかかわらず、避難場所の圏外にいる人々を指すため、b「避難が間に合わない可能性のある人数」 を示していると考えられます。
・ミの特定:
一方、「重なる領域(ミ)」は、避難が必要で、かつ避難場所の圏内にいる人々を示します。この情報を活用すれば、どの避難場所にどれくらいの人数が避難してくるかを推計できるため、c「避難場所別の避難者数」 の算出につながります。
・結論:したがって、マ=a、ミ=c、ム=b の組み合わせである②が正解となります。
第4問
問1:正解③
<問題要旨>
2010年から2019年にかけての発電方式別の発電量増加率を示した表から、ア、イ、ウが日本、中国、ドイツのいずれであるかを当てる問題です。この期間における各国のエネルギー政策の大きな変化を理解しているかが鍵となります。
<選択肢>
・アの特定:
すべての発電方式で発電量が大幅に増加しており、特に「太陽光・地熱・風力」は+1,279%と驚異的な伸びを示しています。これは、急激な経済成長に伴いエネルギー需要が爆発的に増加し、あらゆる電源の開発を大規模に進めている中国の動向と一致します。
・イの特定:
「原子力」が-79%と大幅に減少している点が最大の特徴です。これは2011年の福島第一原子力発電所事故を受け、国内の多くの原子力発電所が稼働を停止した日本の状況を明確に反映しています。
・ウの特定:
「原子力」(-47%)と「火力」(-18%)が共に減少し、その一方で「太陽光・地熱・風力」が+248%と大きく増加しています。これは、脱原発と脱化石燃料を国策として進め、再生可能エネルギーへの転換を強力に推進しているドイツの動向と一致します。
・結論:したがって、ア=中国、イ=日本、ウ=ドイツの組み合わせである③が正解です。
問2:正解⑥
<問題要旨>
ウェーバーの工業立地論における「原料指数」の概念に基づき、A(原料地指向)、B(自由立地)、C(消費地指向)の各工業が、醤油製造、石油精製、ワイン製造のどれにあたるかを判断する問題です。
<選択肢>
・A(原料産地指向)の特定:
原料指数が1よりかなり大きい工業で、製造過程で原料の重量が大幅に減少する場合にあたります。ワイン製造は、原料のぶどうを搾って果汁を得る際に、皮や種などの搾りかすが多く発生し、製品(ワイン)は原料よりはるかに軽くなります。よって、輸送費を節約するために原料(ぶどう)の産地に工場が立地するAは、ワイン製造です。
・C(消費地指向)の特定:
原料指数が1よりかなり小さい工業で、製造過程で重量が増える場合にあたります。醤油製造は、主原料である大豆や小麦に、どこでも手に入る(普遍原料)「水」を多く加えて生産します。そのため製品の方が重くなり、製品の輸送費を節約するため消費地(市場)の近くに工場が立地するCは、醤油製造です。
・B(立地自由)の特定:
原料指数がおよそ1で、製造過程で重量がほとんど変化しない工業にあたります。石油精製は、原料の原油をガソリンやナフサなどに分離する工業であり、製造過程での重量の変化はごくわずかです。したがって、輸送費の観点からは立地の制約が少ないBは、石油精製です。
・結論:よって、A=ワイン製造、B=石油精製、C=醤油製造となり、選択肢⑥が正解です。
問3:正解①
<問題要旨>
日本の繊維・衣服に関する3つの統計地図(カ、キ、ク)が、それぞれ「製造品出荷額」「卸売販売額」「小売販売額」のどれを示しているかを特定する問題です。産業の各段階(生産・流通・販売)における地理的な集積地の違いを理解しているかが問われます。
<選択肢>
・カ(製造品出荷額)の特定:
繊維工業は、現在でも特定の地域に生産拠点が集積しています。地図カは、愛知県や福井県、石川県などの伝統的な繊維産業の集積地で割合が高くなっていることから、製造品出荷額を示していると判断できます。
・キ(卸売販売額)の特定:
卸売業は、生産地と小売店を結びつける流通の中核であり、企業の本社機能や情報が集まる大都市、特に東京や大阪に機能が集中する傾向があります。地図キは、東京と大阪の割合が突出して高くなっていることから、卸売販売額を示していると判断できます。
・ク(小売販売額)の特定:
小売業は、消費者に直接商品を販売するため、その分布は基本的に人口分布と強い相関関係があります。地図クは、三大都市圏をはじめとする人口の多い都道府県で広く高い割合を示しており、小売販売額の分布と一致します。
・結論:したがって、カ=製造品出荷額、キ=卸売販売額、ク=小売販売額の組み合わせである①が正解です。
問4:正解②
<問題要旨>
4カ国(日本、スペイン、タイ、ドイツ)の国際観光収支(収入と支出)を示したグラフから、ドイツに該当するものを選ぶ問題です。各国の観光における位置づけ(観光客を受け入れる国か、送り出す国か)を理解しているかがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
これは観光収入(左側)が支出(右側)を大幅に上回っており(観光黒字)、世界的な観光大国であることを示しています。これはスペインと考えられます。
②【正】
これは観光収入と支出が共に大きいですが、支出が収入を上回っています(観光赤字)。つまり、多くの国民が国外へ観光に出かける一方で、国外からの観光客も多く受け入れている国です。これは、経済的に豊かで休暇を利用して国外旅行を楽しむ国民が多い先進工業国ドイツの典型的なパターンです。
③【誤】
これは観光収入が支出を上回っており、観光が国の重要な産業になっていることを示しています。特に2010年から2019年にかけて収入が大きく伸びているタイと考えられます。
④【誤】
これは収入よりも支出が大幅に多く、典型的な観光赤字国です。多くの国民が海外旅行に出かける一方で、国内の観光収入はそれに及ばない日本の状況を示しています。
問5:正解④
<問題要旨>
ファブレス企業(自社で生産設備を持たない企業)であるE社のサプライチェーンについて述べた文章中の下線部から、適当でないものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
ファブレス企業は、自社では工場などの生産設備を持たず、製造を外部の企業に委託するビジネスモデルです。これにより、多大な設備投資のリスクを避けることができます。記述は正しいです。
②【正】
製造部門を持たない代わりに、ファブレス企業は製品の企画・設計、開発、マーケティングといった高付加価値な業務に経営資源を集中させます。こうした機能は、情報や人材が集まりやすい先端技術産業の集積地に立地する傾向があります。記述は正しいです。
③【正】
E社から製造を委託されるf社やw~z社のような企業(EMS:電子機器受託製造サービスなど)は、特定の企業に専属するのではなく、複数の企業から製造を請け負うことで稼働率を高め、規模の経済を追求するのが一般的です。記述は正しいです。
④【誤】
このサプライチェーンでは、E社本社(開発拠点)が発注し、w~z社(部品製造)やf社(組立)が世界中の最適な場所で生産を行い、完成品が世界中の市場(消費地)に供給されます。部品製造工場(w~z社)と最終製品の消費地が地理的に近接するとは限りません。むしろ、生産はコストの安い国・地域で、販売は世界中の消費地へというグローバルな分業体制が特徴です。したがって、この記述は誤りです。
問6:正解③
<問題要旨>
日本、アメリカ合衆国、中国におけるいくつかの産業の「中間財」と「最終財」の貿易収支を指数化した表から、アメリカ合衆国と輸送機械の正しい組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
・国名の特定:
国ごとの貿易収支の全体的な傾向を見ます。サは、示された全ての産業で中間財・最終財ともに貿易黒字(正の値)となっています。これは「世界の工場」として輸出を拡大している中国の特徴と見なせます。一方、シは多くの項目で貿易赤字(負の値)となっており、これは巨大な国内市場を持ち多くの工業製品を輸入しているアメリカ合衆国の特徴と見なせます。
・産業名の特定:
設問の正解が③であることから、輸送機械はKであると判断します。表を見ると、日本はK(輸送機械)の中間財・最終財ともに赤字、アメリカ(シ)もKで大きな赤字、中国(サ)はKで大きな黒字となっています。また、Jは家庭用電気機械と判断されます。
・結論:求める組み合わせは「アメリカ合衆国」と「輸送機械」なので、シとKの組み合わせとなり、正解は③です。
第5問
問1:正解②
<問題要旨>
日本の三大都市圏と地方圏における工業用地面積の推移を示したグラフと、その背景を説明した文章の空欄(ア、イ)を正しく組み合わせる問題です。日本の工業化の歴史的な変遷を理解しているかが問われます。
<選択肢>
・凡例(AとB)の特定:
高度経済成長期以降、工業は用地取得が困難で過密な大都市圏を避け、広い土地や労働力を求めて地方へ分散する傾向が強まりました。グラフを見ると、BはAに比べて工業用地の面積が常に大きく、特に1970年代から90年代にかけて大きく増加しています。したがって、面積が大きく増加したBが地方圏、面積が比較的小さく伸び悩んでいるAが三大都市圏と判断できます。
・空欄(アとイ)の特定:
– ア(1965~1975年):この時期は高度経済成長期の後半にあたり、日本の工業化を牽引した重化学工業の発展が著しく、京浜・阪神などの臨海部に大規模なコンビナートが建設されました。これは、k「基礎素材型工業の基盤整備が臨海部で進められた」 という説明に合致します。
– イ(1975~1995年):安定成長期に入ると、自動車や電機などの加工組立工業が日本の産業の主役となりました。これらの工場は、関連工場を含めて広い土地を必要としたため、高速道路網の整備と連動して地方圏へ盛んに進出しました。これは、j「加工組立工業が成長し、生産工場が地方圏に立地した」 という説明に合致します。
・結論:求める組み合わせは「三大都市圏」=Aと、「空欄ア」=kです。したがって、正解は②となります。
問2:正解①
<問題要旨>
首都圏の2つの市区(D, E)について、1990年と2015年の人口ピラミッド(カ, キ)と、それぞれの市区の土地利用の変化を述べた文(x, y)を正しく組み合わせる問題です。
<選択肢>
・時点(カとキ)の特定:
人口ピラミッドを見ると、キは20~24歳(団塊ジュニア世代)が突出しており、1990年代の若者中心の人口構成を示しています。一方、カはキに比べて高齢者層の割合が高く、全体の形もつりがね型に近くなっており、より少子高齢化が進行した2015年の人口構成であると判断できます。
・市区(DとE、xとy)の特定:
– 文xは「都心から約15km」「工場跡地などにマンション」とあり、都心に近い既成市街地の再開発(インナーシティ問題の解消)の様子を示しています。こうした地域には若年層や単身者・夫婦などが流入します。
– 文yは「都心から約40km」「ニュータウンが開発」とあり、都心から離れた郊外の開発の様子を示しています。ニュータウンには子育て世代のファミリー層が多く居住します。
– ピラミッドDは20~30代の若年層の割合が高い都市型の特徴を示しており、文xの状況と一致します。ピラミッドEは30~40代とその子ども世代にあたる10代が多い郊外のファミリー層中心の特徴を示しており、文yの状況と一致します。
・結論:求める組み合わせは「2015年」に該当するカと、「Dについて述べた文」であるxとなり、正解は①です。
問3:正解④
<問題要旨>
イタリア、オーストラリア、韓国の3カ国について、「都市人口率」と「GDPに占める製造業の割合」の1970年から2020年にかけての推移を示したグラフ(サ~ス)の正しい組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
・サの特定:
1970年時点では都市人口率・製造業の割合ともに3カ国中最も低かったものの、その後の50年間で両方の数値が急上昇し、特に製造業の割合の高さが際立っています。これは、「漢江の奇跡」と呼ばれる急速な工業化を遂げた韓国の経済発展パターンと一致します。
・スの特定:
1970年時点から都市人口率が80%を超えて非常に高い水準にあり、その後も上昇を続けています。一方で、製造業の割合は一貫して低い水準で、さらに低下傾向にあります。これは、先進国であり、鉱業やサービス業が経済の中心であるオーストラリアの産業構造と一致します。
・シの特定:
1970年時点ではサ(韓国)より工業化が進んでいましたが、1995年以降、製造業の割合が低下(脱工業化)しています。これは、「第三のイタリア」に代表される中小企業中心の製造業が盛んであったものの、近年産業構造が変化しているイタリアの状況と一致します。
・結論:したがって、サ=韓国、シ=イタリア、ス=オーストラリアの組み合わせとなり、正解は④です。
問4:正解②
<問題要旨>
東京の情報関連産業(出版業、新聞業、ソフトウェア業)について、全国の従業者数に占める東京都の割合と、2006年~2016年の全国の従業者数増減率を示した表(タ~ツ)の正しい組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
・ツの特定:
情報関連産業の中でも、ソフトウェア業はIT革命以降に急成長した分野であり、従業者数も大きく増加しているはずです。表を見ると、ツは従業者数の増減率が+67.6%と突出して高く、著しい成長を示しています。これがソフトウェア業と判断できます。
・タとチの特定:
出版業と新聞業は、ともにインターネットの普及によって市場が変化した伝統的なメディアです。両者とも本社機能が東京に集中する傾向が強いですが、特に出版社は地方に拠点が少なく、東京への一極集中度が非常に高いことで知られています。表を見ると、「全国の従業者数に占める東京都の割合」がタ(51.4%)の方がチ(38.0%)よりも高いです。したがって、より集中度の高いタが出版業、チが新聞業と判断できます。
・結論:したがって、タ=出版業、チ=新聞業、ツ=ソフトウェア業の組み合わせである②が正解です。
問5:正解③
<問題要旨>
ロンドンの地区別データ(外国生まれの割合、高度専門業務従事者割合、失業率)の地図を見て、会話文中の下線部から誤りを含むものを選ぶ問題です。主題図の読図能力が問われます。
<選択肢>
①【正】
「高度な経営・専門業務の従事者割合」の地図と「失業率」の地図を比較すると、高度専門職の割合が高い地区(色の濃い部分)と、失業率が高い地区(色の濃い部分)の分布は、ほとんど重なっておらず、異なる傾向にあると言えます。記述は正しいです。
②【正】
「外国で生まれた人の割合」と「高度な経営・専門業務の従事者割合」の地図を重ねて見ると、両方とも高位(色が濃い)の地区は、インナーロンドンの内側に多く分布していることが読み取れます。記述は正しいです。
③【誤】
「失業率」の地図を見ると、高位(色が濃い)の地区はインナーロンドンの東部や北部に偏って分布しており、シティ(中心地区)を中心とした同心円状の規則的な分布にはなっていません。したがって、この記述は地図から読み取れる傾向とは異なり、誤りです。
④【正】
地図右下の「ドックランズ」地区を見ると、「高度な経営・専門業務の従事者割合」が高位(色が濃い)の地区が含まれています。この地区は、港湾機能の衰退後にウォーターフロント開発が行われ、金融機関などが集まる新しいビジネス街に変貌した地域です。記述は正しいです。
第6問
問1:正解④
<問題要旨>
インド洋とその周辺地域(ア~エ)のうち、サイクロン(熱帯低気圧)の上陸頻度が最も低い地域を選ぶ問題です。熱帯低気圧の発生条件に関する基本的な知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
ア(インド東岸~ベンガル湾)は、サイクロンの発生が非常に多く、毎年のように大きな被害を受けている地域として知られています。
②【誤】
イ(オーストラリア北西部)は、「ウィリーウィリー」と呼ばれるサイクロンが発生・上陸する地域です。
③【誤】
ウ(モザンビークなどアフリカ南東岸)は、インド洋南部で発生したサイクロンが上陸し、しばしば甚大な被害をもたらす地域です。
④【正】
エ(アフリカ東岸の赤道付近)は、熱帯低気圧が発生・発達するために必要な地球の自転の影響(コリオリの力)がほとんど働かない「赤道無風帯」に近い緯度(おおむね南北5度以内)に位置しています。そのため、この付近でサイクロンが発生・発達することはほとんどなく、上陸頻度も他の3地域に比べて極めて低いです。
問2:正解①
<問題要旨>
インド洋周辺の地域A~Dのうち、稲作で主に天水田(かんがい施設を使わず、雨水のみに頼る水田)が利用される地域として「適当でない」ものを選ぶ問題です。世界の気候と農業の結びつきを理解しているかがポイントです。
<選択肢>
①【正】
地域Aはパキスタンのインダス川流域です。この地域は砂漠気候~ステップ気候に属し、年間の降水量が非常に少ないため、稲作を行うにはインダス川からの大規模な灌漑が不可欠です。したがって、雨水のみに頼る天水田での稲作は不可能であり、この選択肢が「適当でない」ものとなります。
②【誤】
地域B(中国南部~東南アジア北部)は、夏の季節風(モンスーン)の影響で降水量が多く、天水田による稲作が広く行われています。
③【誤】
地域C(東南アジア島嶼部)は、熱帯雨林気候やモンスーン気候に属し、年間を通して高温多雨であるため、天水田による稲作が見られます。
④【誤】
地域D(マダガスカル島)は、特に島の東部で貿易風の影響により降水量が多く、天水田による稲生が広く行われています。
問3:正解②
<問題要旨>
インドと3カ国(アラブ首長国連邦、インドネシア、シンガポール)との間の「輸出額」と「移民数」を示した図から、カ~クの国名を正しく組み合わせる問題です。各国の経済的特徴や人的交流を理解しているかが問われます。
<選択肢>
・カの特定:
移民数の図を見ると、インドからカへの矢印が突出して太く、移民数が100万人以上であることを示しています。これは、産油国で多くの外国人建設労働者やサービス業従事者を受け入れているアラブ首長国連邦(UAE) の特徴です。インドからUAEへの出稼ぎ労働者は非常に多いです。
・キとクの特定:
輸出額の図を見ると、キとクの間で双方向に極めて太い矢印があり、両国の経済的結びつきが非常に強いことがわかります。これは、ASEANの中心的な工業国・人口大国であるインドネシアと、その貿易中継拠点であるシンガポールの関係を示唆します。移民数の図を見ると、インドからキへの移民は8~100万人、クへは1~8万人となっています。シンガポールは歴史的にインド系移民(タミル系など)が多く、現在も人的交流が活発です。したがって、移民数が多いキがシンガポール、少ないクがインドネシアと判断できます。
・結論:したがって、カ=アラブ首長国連邦、キ=シンガポール、ク=インドネシアの組み合わせである②が正解です。
問4:正解⑤
<問題要旨>
インド洋周辺の国々における多数派宗教の人口割合の地図と、3つの国(F, G, H)の宗教に関する説明文(サ~ス)を正しく組み合わせる問題です。
<選択肢>
・サとGの特定:
文サは「世界有数のムスリム人口を擁するが、宗教人口割合の第1位はイスラームではない」とあります。これは、ヒンドゥー教徒が多数派(約8割)でありながら、1億人を超えるイスラム教徒の人口も抱えるインドを指しています。地図上のGがインドです。
・シとHの特定:
文シは「仏教徒とムスリムとが共存していたが、近年では紛争や人権問題が起こり、難民が発生している」とあります。これは、仏教徒が多数派の国で、イスラム教徒の少数民族ロヒンギャに対する人権問題が国際的に注目されているミャンマーを指しています。地図上のHがミャンマーです。
・スとFの特定:
文スは「ムスリム商人の言語と地域の言語がまざりあった共通語が生まれ、また、その後にキリスト教が浸透した」とあります。これは、アラビア語と現地のバントゥー諸語が混ざりあってスワヒリ語が形成され、その後のヨーロッパ諸国による植民地化によってキリスト教が広まったアフリカ東岸地域の説明です。地図上のF(タンザニア)がこの説明に合致します。
・結論:したがって、F=ス、G=サ、H=シの組み合わせである⑤が正解です。
問5:正解②
<問題要旨>
モーリシャスとモルディブの2カ国について述べた文章中の下線部から、適当でないものを選ぶ問題です。各国の自然環境と歴史的背景に関する知識が問われます。
<選択肢>
①【正】
モーリシャスは火山活動によって形成された島であり、その肥沃な土壌を利用して植民地時代からサトウキビのプランテーションが開発され、製糖業が今日の主要産業の一つを形成しました。記述は正しいです。
②【誤】
モーリシャスの現在の主な宗教はヒンドゥー教です。これは、イギリス統治時代に、サトウキビプランテーションの労働力としてインドから多くの移民が導入された歴史を反映しています。文中の「フランス統治期に導入された移民労働者の宗教」という記述は、ヒンドゥー教徒が多数を占める現状とは異なり、明確に誤りです。
③【正】
モルディブは、平均海抜が1~2m程度と非常に低い、多数のサンゴ礁の島々からなる国です。そのため、地球温暖化に伴う海面上昇によって国土が水没する危機に瀕しており、国際社会にその脆弱性を訴えています。記述は正しいです。
④【正】
インド洋は、アジアとヨーロッパ・アフリカを結ぶ海上交通の要衝であり、近年その戦略的重要性から注目を集めています。中国が提唱する広域経済圏構想「一帯一路」における「海のシルクロード」は、このインド洋を通過するルートであり、ルート上に位置するモルディブは、近年中国との経済的・政治的な関係を深めています。記述は正しいです。