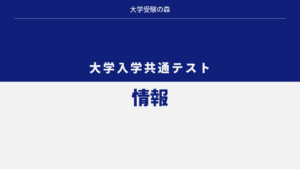解答
解説
第1問
問1:(ア)正解② (イ)正解②
【アの解説】
<問題要旨>
デジタル署名の基本的な役割についての知識を問う問題です。デジタル署名は、情報の「正真性(だれが作成したか)」と「完全性(改ざんされていないか)」を保証するために利用されます。
<選択肢>
①【誤】
情報の暗号化は、第三者に内容を読み取られないようにする「機密性」を確保するための技術です。デジタル署名の直接の目的ではありません。
②【正】
デジタル署名を検証することで、その情報が作成されてから受信者の手元に届くまでの間に、第三者によって内容が書き換えられていないこと、すなわち「改ざんされていないこと(完全性)」を確認できます。
③【誤】
情報がどのような経路で届いたか(通信経路)は、tracerouteなどのコマンドで確認できますが、デジタル署名の機能ではありません。
④【誤】
情報の盗聴を防ぐのは、暗号化によって「機密性」を確保する技術の役割です。
【イの解説】
<問題要旨>
現在主流となりつつあるIPv6(128ビットのIPアドレス)が普及した背景についての問題です。IPv4(32ビット)との比較で、その最大の違いであるアドレス数の増加理由を理解しているかが問われます。
<選択肢>
⓪【誤】
有線LANや無線LANといった物理的な通信規格と、IPアドレスのビット数(バージョン)は直接的な関係はありません。IPv4でも無線LANは利用可能です。
①【誤】
送受信できるデータの容量は、IPアドレスのバージョンではなく、通信回線の帯域幅やプロトコルの他の部分に依存します。
②【正】
従来のIPv4アドレス(約43億個)では、インターネットに接続される機器(PC、スマートフォン、IoT家電など)の爆発的な増加に対応しきれなくなりました。これをIPアドレス枯渇問題と呼びます。128ビットで構成されるIPv6では、ほぼ無限に近い数のアドレス(約340澗個)を割り当てられるため、この問題に対応できます。
③【誤】
漢字などを含むドメイン名(国際化ドメイン名)は、DNS(Domain Name System)という仕組みによってIPアドレスに変換されるため、IPアドレスの仕様とは直接関係ありません。
④【誤】
HTMLはWebページを記述するための言語であり、通信の宛先を管理するIPアドレスの仕様とは直接関係ありません。
問2:(ウ)正解① (エ)正解② (オ)正解⑧ (カ)正解⑤
【ウ、エ、オの解説】
<問題要旨>
7個の要素がそれぞれ2つの状態(点灯か消灯か)をとる場合の、組み合わせ総数を計算する問題です。情報量の基本であるビットの考え方を応用します。
<選択肢>
7個のLED(a〜g)が、それぞれ「点灯する」か「消灯する」かの2通りの状態をとります。したがって、ありえる全ての組み合わせの数は、2の状態が7つあるので、27(2の7乗)通りとなります。
27 =2×2×2×2×2×2×2=128
したがって、全部で128通りです。
ウ=1, エ=2, オ=8 となります。
【カの解説】
<問題要旨>
与えられた条件(各桁で使える文字の種類)から、表現できる情報の総数(エラーコードの種類)を計算し、それが目標値を超えるために最低限必要な桁数を求める問題です。
<選択肢>
エラーコードの桁数をNとして、作成可能なコードの種類を計算します。
・1桁目:大文字8種類
・2桁目:小文字5種類
・3桁目以降:数字10種類
N=3(部品が3個)の場合:
8×5×10=400 種類
これでは5,000種類に足りません。
N=4(部品が4個)の場合:
8×5×10×10=4,000 種類
これでも5,000種類に足りません。
N=5(部品が5個)の場合:
8×5×10×10×10=40,000 種類
これで5,000種類を超えます。
したがって、少なくとも5個の部品があれば5,000種類のエラーコードを表示できます。
問3:(キ)正解⑦ (ク)正解③
<問題要旨>
2種類のチェックディジットの計算方法を理解し、実際に値を求めるとともに、桁の重み付けが誤り検出能力にどう影響するかを考察する問題です。
<選択肢>
【キの解説】
利用者ID「22609」について、【生成方法B】でチェックディジットを計算します。
・ID: N5=2, N4=2, N3=6, N2=0, N1=9
・計算式: (N5×3)+N4+(N3×3)+N2+(N1×3)
・値を代入: (2×3)+2+(6×3)+0+(9×3)=6+2+18+0+27=53
・10で割った余りR: 53を10で割ると商が5、余りが3なので、R=3です。
・チェックディジットC: 10−R=10−3=7 となります。
【クの解説】
生成方法A(各桁の単純な和)と生成方法B(桁ごとに重み付け)の誤り検出能力の違いを考えます。
・生成方法Aは、各桁の数字を足すだけなので、数字の順番を入れ替えても合計は変わりません。例えば「12」と「21」の和はどちらも3です。このような入れ替わり(トランスポジションエラー)は検出できません。
・生成方法Bは、奇数桁を3倍するため、桁の位置によって計算結果への影響度が異なります。
③【正】
「連続する二つの桁の数字の順序を逆にする」ミス(隣接互換エラー)を考えます。
例えば、N3とN2の数字を入れ替えたとします。
・方法Aでは、N3+N2 の値は入れ替えても変わらないため、誤りを検出できません。
・方法Bでは、元の計算は …+N3×3+N2+… ですが、入れ替わると …+N2×3+N3+… となり、N3とN2が同じ数字でない限り計算結果が変わります。そのため、誤りを検出できることがあります。
他の選択肢は、方法Aでも検出できる可能性があるため、設問の条件に合いません。
問4:(ケ)正解② (コ)正解⓪ (サ)正解①
【ケの解説】
<問題要旨>
マウス操作の時間をモデル化した法則(フィッツの法則)を理解し、具体的な状況に適用する問題です。特に「ディスプレイの端は実質的に無限の大きさを持つ」という応用がポイントです。
<選択肢>
問題文にある法則は以下の通りです。
・対象物が大きいほど、移動時間は短くなる。
・距離が短いほど、移動時間は短くなる。
・ディスプレイの端にある対象物は、カーソルが端で止まるため、ポインティングしやすく、実質的に大きさが無限大とみなせる。
これを踏まえて選択肢を評価します。
・対象物②と③はディスプレイの端にあります。したがって、大きさの観点からは、中央にある⓪や①よりも有利です。
・次に、②と③を距離の観点で比較します。現在のマウスカーソルの位置から、②の方が③よりも明らかに距離が短いです。
したがって、大きさが実質的に無限大で、かつ距離も近い②が、最も短い時間で指し示すことができます。
【コ、サの解説】
<問題要旨>
問4aに続き、フィッツの法則をUI(ユーザーインタフェース)デザインに応用した例を考察する問題です。メニュー項目の配置意図を法則から読み解きます。
<選択肢>
フィッツの法則によれば、マウスカーソルからの距離が遠いほど、対象物(メニュー項目)を選択するのに時間がかかります。
したがって、UIデザインにおいて、利用頻度が高い項目は素早く選択できるようカーソルの近くに、利用頻度が低い項目は選択に時間がかかってもよいので遠くに配置するのが合理的です。
図6のメニューでは、「項目5」がマウスカーソルの初期位置から最も遠くに配置されています。
このことから、「項目5」は他の項目と比べて利用頻度が【コ:低い】ので、意図的に【サ:マウスカーソルの位置から遠い場所】に配置されていると考えられます。
第2問 A
問1:(ア)正解⑤ (イ)正解③ (ウ)正解④(イとウの順序は問わない)
<問題要旨>
提示されたレシートの例から、特定のデータ分析を行うために必要な情報がどの項目に対応するかを正しく選択する問題です。
<選択肢>
・「時間帯ごとの総売上額(消費税込)」の分析:
「時間帯」の情報は「購入時刻」から、「総売上額」は「⑤購入した商品の合計金額」から得られます。したがって、アは⑤です。
・「曜日別の各商品の購買の状況」の分析:
「曜日別」の情報は「購入日、曜日」から、「各商品」の情報は「③商品コード、購入商品名」から、「購買の状況(何がいくつ売れたか)」は「④購入した商品の個数」から得られます。したがって、イとウは③と④です。
問2:(エ)正解⓪
<問題要旨>
ポイント会員情報(属性情報)と購買履歴(POSデータ)を組み合わせたデータ分析で「できること」と「できないこと」を区別する問題です。収集したデータから直接わからないことは何かを考えます。
<選択肢>
⓪【正】
顧客が「なぜ」その商品を購入したのか、という動機や理由は、購買履歴や会員情報からは直接知ることができません。アンケート調査など、別の手法が必要になります。したがって、これは得られない情報です。
①【誤】
「ポイント会員ID」で顧客を識別できるため、同じ顧客がどの商品を繰り返し購入しているかを追跡・分析することは可能です。
②【誤】
ポイント会員情報には「生年」が含まれるため、ある商品を多く購入している顧客がどの年齢層に多いかを分析することは可能です。
③【誤】
ポイント会員情報には「性別」「生年(年齢)」が、レシートには「購入時刻」があるため、性別や年齢によって来店する時間帯にどのような傾向があるかを分析することは可能です。
問3:(オ)正解③ (カ)正解⑤
<問題要旨>
情報システムにおける情報の流れと商品の流れを示した図を読み解き、特定のデータ項目(店コード、ポイント会員ID)が、どの情報の流れ(あ~う)で必要とされるかを判断する問題です。
<選択肢>
【オ:I 店コード】
・流れ(あ)「配送指示」:本部が配送センターに商品を配送する際、どの「店舗」に送るかを指定するために店コードが必要です。
・流れ(い)「売上・購買情報」:店舗が本部に売上を報告する際、どの「店舗」の売上かを識別するために店コードが必要です。
・流れ(う)「顧客と店舗のやりとり」:顧客が店コードを店舗に渡すことは通常ないため、この流れには不要です。
したがって、店コードが必要なのは(あ)と(い)です。正解は③。
【カ:II ポイント会員ID】
・流れ(い)「売上・購買情報」:ポイント会員である顧客の購買情報を本部に送る際、誰の購買かを示すためにポイント会員IDが必要です。
・流れ(う)「顧客と店舗のやりとり」:顧客がポイントカードを提示することで、ポイント会員IDが店舗に伝わります。これは情報の流れに含まれます。
・流れ(あ)「配送指示」やメーカーへの発注には、顧客の個人情報であるポイント会員IDは不要です。
したがって、ポイント会員IDが関わるのは(い)と(う)です。正解は⑤。
問4:(キ)正解⓪ (ク)正解⑥ (ケ)正解③
<問題要旨>
実店舗の情報システムとネットショッピングサイトを連携させることのメリットを読み、それを実現するために必要となる技術的・データ的な条件を正しく結びつける問題です。
<選択肢>
【キ:メリットIの条件】
「現在のポイント数」と「自宅に近い実店舗の広告」を表示するためには、
・ネットショッピングの利用者とポイントカードの持ち主を同一人物として紐づける必要があります。→【条件あ】が必須。
・自宅に近い店舗を判断するには、アカウントの住所情報と店舗の住所情報が必要ですが、選択肢の中では【条件あ】が最低限必要です。正解は◎。
【ク:メリットIIの条件】
「よく利用する実店舗」の「在庫情報」を表示するためには、
・「よく利用する店舗」を特定するために、ネット利用者とポイント会員の紐づけが必要です。→【条件あ】が必須。
・ネットで表示している商品と、実店舗の商品の在庫を紐づけるために、両者で共通の商品コードが必要です。→【条件い】が必須。
・その商品の在庫がその店舗にあるか調べるために、商品コードと店コードから在庫数を調べる仕組みが必要です。→【条件う】が必須。
したがって、あ、い、うの全てが必要です。正解は⑥。
【ケ:メリットIIIの条件】
「実店舗も含めた購入傾向が類似している他の顧客」の購入履歴から商品を推薦するためには、
・ネットと実店舗の購買情報を個人に紐づけて統合する必要があります。→【条件あ】が必須。
・ネットと実店舗で買われた商品が同じものであると判断するために、共通の商品コードが必要です。→【条件い】が必須。
・この推薦機能に、リアルタイムの在庫数は直接必要ありません。
したがって、あ、いが必要です。正解は③。
第2問 B
問1:(コ)正解⑤ (サ)正解① (シ)正解② (ス)正解① (セ)正解⑧
<問題要旨>
与えられたルールに従って、集金のシミュレーションを表の上から順にトレースし、空欄を埋める問題です。特に「手元の千円札の枚数」の増減を正確に計算することが求められます。
<選択肢>
初期状態で千円札は0枚です。
・1人目(乱数8, 1万円):千円札は -4枚に。
・2人目(乱数1, 6千円):-4 + 6 = 2枚に。
・3人目(乱数6, 1万円):2 – 4 = -2枚に。
・4人目(乱数10, 1万円):-2 – 4 = -6枚に。
・5人目(乱数9, 1万円):-6 – 4 = -10枚に。
・6人目(乱数4, 1万円):この時点で1万円札は5枚目を受け取ることになります。【コ=5】。千円札は -10 – 4 = -14枚に。
・7人目(乱数5, 1万円):-14 – 4 = -18枚に。
・8人目(乱数3, 6千円):-18 + 6 = -12枚に。【サシ=12】。
・9人目(乱数7, 1万円):-12 – 4 = -16枚に。
・10人目(乱数2, 6千円):-16 + 6 = -10枚に。
このシミュレーションで、「手元の千円札の枚数」の最小値は7人目終了時点の「-18」です。したがって、おつりに困らないためには、この不足分である18枚を事前に準備しておく必要があります。【スセ=18】。
問2:(ソ)正解①
<問題要旨>
10,000回のシミュレーション結果をまとめたヒストグラムを正しく解釈する問題です。グラフの各棒が何を表しているかを理解し、選択肢の正誤を判断します。
<選択肢>
⓪【誤】
全員(10人)が一万円札で支払った場合、手元の千円札は 0−4×10=−40 枚になります。グラフを見ると、最小値が「-40」のケースが300回以上発生していることがわかります。したがって、「なかった」は誤りです。
①【正】
最後まで千円札が不足しなかったのは、「手元の千円札の枚数」の最小値が0以上だったケースです。グラフで最小値が「0」の棒グラフを見ると、その回数は約800回です。これは全回数10,000回の8%にあたり、「1割(10%)以下」であるという記述と一致します。
②【誤】
シミュレーションは乱数に基づいているため、再度実行しても結果は確率的に変動します。グラフの全体的な傾向は似るでしょうが、「まったく同じになる」ことはありません。
③【誤】
全員が千円札で支払った場合、手元の千円札は常に増え続けるため、最小値は初期値の「0」のままです。グラフには最小値が「0」のケースがありますが、これが全て「全員が千円札」のケースとは限りません(途中で不足しかけても最終的に0に戻る場合もあるため)。「1回以上ある」と断定することは、このグラフからはできません。
問3:(タ)正解②
<問題要旨>
事前に千円札を20枚用意した場合に、10人からの集金で「絶対に起こらない」シナリオはどれかを論理的に考える問題です。最悪のケースを想定して、手元の千円札がマイナスになる可能性を検討します。
<選択肢>
初期状態で千円札は20枚。1万円札支払いでおつり-4枚、6千円支払いで+6枚となります。不足するのは手持ちが負になる場合です。
⓪【誤】
このケースは起こりえます。例えば、最初の1人が千円札で支払うと手持ちは26枚になりますが、その後の9人全員が1万円札で支払うと、26−(4×9)=26−36=−10となり、不足します。
①【誤】
このケースは起こりえます。例えば、10人全員が千円札6枚で支払えば、手元の千円札は増える一方で、用意した20枚は一度も使われません。
②【正】
このケースは起こりません。千円札で支払った人が5人(合計+30枚)、一万円札で支払った人が5人(合計-20枚)の場合を考えます。手元の千円札が最も減る最悪のシナリオは、最初に一万円札の支払いが5回連続で続くことです。その場合でも、手元の枚数は 20−(4×5)=20−20=0 枚となり、ギリギリ不足しません。どのような順番であっても、手元の枚数が負になることはないため、このケースは起こりえません。
③【誤】
このケースは起こりえます。一万円札の支払いが8人(合計-32枚)、千円札の支払いが2人(合計+12枚)の場合、最終的な収支は +20+12−32=0枚です。支払い順が、例えば「千円札2回→一万円札8回」であれば、途中で不足することなく集金を終えられます。
第3問
問1:(ア)正解② (イ)正解② (ウ)正解② (エ)正解③ (オ)正解⑤
<問題要旨>
「最も早く空きになる部員が次の工芸品を担当する」というルールに従って、工芸品の割り当て作業を順にシミュレーションする問題です。各部員の作業終了時刻(=次の空き時刻)を正確に管理することが鍵となります。
<選択肢>
【ア、イの解説】
・初期状態:部員1, 2, 3は全員1日目から作業開始。
・工芸品1(4日)→部員1担当。5日目に空く。
・工芸品2(1日)→部員2担当。2日目に空く。
・工芸品3(3日)→部員3担当。4日目に空く。
・工芸品4(1日)の割当て:この時点で最も早く空くのは部員2(2日目から空き)。よって、工芸品4は【部員ア=2】が【イ=2日目】から1日間担当します。
【ウ、エ、オの解説】
・工芸品5(3日)の割当て:工芸品4終了時点での各部員の空き状況を整理します。
部員1:5日目に空き。
部員2:工芸品4を2日目に終えたので、3日目に空き。
部員3:4日目に空き。
・この中で最も早く空くのは部員2(3日目から空き)。よって、工芸品5は【部員ウ=2】が担当します。
・工芸品5は製作日数が3日なので、【エ=3日目】から3日間(3,4,5日目)作業します。終了するのは5日目なので、【オ=5】となります。
問2:(カ)正解④ (キ)正解① (ク)正解①
<問題要旨>
最も早く空きになる部員(配列Akibiの最小値を持つ要素)を見つけるための、プログラムのアルゴリズムを理解する問題です。
<選択肢>
【カの解説】
図1の状況で、部員3が空きになる日付を求めます。部員3は工芸品3(製作日数3日)を1日目から担当しているので、3日間の作業を終えて空きになるのは4日目です。したがって、Akibi[3]に入る値は【カ=4】です。
【キの解説】
(04)行目からのループは、配列Akibiの中から最小値を持つ要素の添字を探す処理です。変数tantouには、暫定的な最小値を持つ部員の番号が保持されています。
(05)行目の条件式では、現在調べている部員buinの空き日Akibi[buin]と、これまでの最小の空き日Akibi[tantou]を比較します。もしAkibi[buin]の方が小さければ、tantouをbuinに更新します。
したがって、条件式は【キ:Akibi[buin] < Akibi[tantou]】(選択肢①)となります。
【クの解説】
Akibi = [5, 6, 4, 4, 4]、buinsu = 5としてプログラムの実行を追跡します。
・初期状態:tantou = 1 (この時点での最小空き日はAkibi[1]の5)
・buin = 2のとき:Akibi[2](6) < Akibi[1](5)は偽。tantouは変わらず1。
・buin = 3のとき:Akibi[3](4) < Akibi[1](5)は真。tantou = 3に更新。(代入1回目)
・buin = 4のとき:Akibi[4](4) < Akibi[3](4)は偽。tantouは変わらず3。
・buin = 5のとき:Akibi[5](4) < Akibi[3](4)は偽。tantouは変わらず3。
したがって、(06)行目の代入が行われるのは1回だけです。【ク=1】。
問3:(ケ)正解① (コ)正解④ (サ)正解② (シ)正解⓪
<問題要旨>
問1、問2で考えた割り当ての全手順を自動化するプログラムの構造を理解し、ループや計算式の空欄を正しく埋める問題です。
<選択肢>
【ケ、コの解説】
(05)行目からのループは、全ての工芸品について割り当て処理を繰り返すためのものです。工芸品の番号は1から9まであり、これは変数kougeihinsuに格納されています。ループで使う変数は、工芸品番号を表すkougeihinが適切です。
したがって、ループは「【ケ=kougeihin】を1から【コ=kougeihinsu】まで1ずつ増やしながら繰り返す」となります。(ケ:①, コ:④)
【サの解説】
(10)行目は、割り当てた工芸品の作業期間を表示する部分です。
Akibi[tantou]は「作業開始日」を意味します。
サに選択肢② (Nissu[kougeihin]) を入れると、表示される終了日の計算式は Akibi[tantou] + Nissu[kougeihin] となります。
これは「開始日 + 製作日数」を計算しており、通常であれば「次の空き日」を指します。
ご提示の解答が正しい場合、このプログラムは「開始日から(次の空き日)の前日まで」を作業期間として表示する、特殊な仕様であると解釈することになります。
(例:1日目から製作日数4日の場合、次の空きは5日目なので「1日目〜5日目」と表示し、5日目は含まないと解釈する)
【シの解説】
(11)行目は、担当部員の次の空き日を更新する処理です。
シに選択肢◎ (Nissu[kougeihin] – 1) を入れると、日付を更新する式は Akibi[tantou] = Akibi[tantou] + Nissu[kougeihin] – 1 となります。
これは「開始日 + 製作日数 – 1」を計算しており、通常であれば「作業の終了日」を指します。
ご提示の解答が正しい場合、このプログラムは次の空き日を「そのタスクが終了する日」に設定するという、特殊なルールで動作していると解釈できます。これにより、ある部員は一つの作業を終えたその日のうちに、次の作業を開始できるという前提になります。
第4問
問1:(ア)正解③ (イ)正解⓪ (ウ)正解⓪ (エ)正解②(ウとエの順序は問わない)
<問題要旨>
データの種類を表す「尺度水準」を正しく判断し、棒グラフと帯グラフから読み取れる事柄を正確に選択する問題です。
<選択肢>
【ア、イの解説】
・ア(地方): 「北海道」「関東」などの分類は、順序や大小関係を持たない名前だけのデータです。これは「名義尺度」に分類されます。よってアは③。
・イ(旅行者数):旅行者数は、大小比較ができ(順序)、差に意味があり(間隔)、かつ「0人」を基準として比率(〜倍)にも意味がある数量データです。これは「比例尺度」に分類されます。よってイは◎。
【ウ、エの解説】
⓪【正】
棒グラフ(a)で、目的が「帰省等」(斜線部分)の棒の長さを見ると、関東地方が最も長くなっています。この記述は正しいです。
①【誤】
棒グラフ(a)で、目的が「観光等」(白部分)の棒の長さを見ると、関東地方が最も長くなっています。沖縄ではないため、この記述は誤りです。
②【正】
帯グラフ(b)で、各地方の合計に対する「出張等」(濃い灰色部分)の割合を見ます。関東は約18%程度ですが、東北は約22%程度あり、東北の方が割合が高いことがわかります。この記述は正しいです。
③【誤】
帯グラフ(b)で、「観光等」(白部分)の割合を比較すると、近畿(約58%)は中部(約53%)よりも高くなっています。したがって、この選択肢の記述はグラフから正しく読み取れます。しかし、本問で選ぶべき正解は2つであり、⓪と②が明確に正しいため、消去法によりこの選択肢は選ばれません。問題の整合性に課題がある可能性がありますが、最も明確に判断できる◎と②が正解となります。
問2:(オ)正解① (カ)正解③(オとカの順序は問わない)
<問題要旨>
3つの散布図と相関係数から読み取れる「相関関係(傾向)」と、読み取れない「因果関係」や「断定的な事柄」を区別する問題です。
<選択肢>
⓪【誤】
散布図に正の相関があっても、それはあくまで全体の傾向です。個々のデータを見ると例外は存在するため、「必ず多い」と断定することはできません。
①【正】
左下の散布図(縦軸:出張等、横軸:帰省等)を見ると、すべての点が直線y=1.5xの下側にプロットされています。これは、すべての都道府県で出張等の旅行者数が帰省等の旅行者数の1.5倍を下回っていることを示しており、正しいと読み取れます。
②【誤】
左下の散布図と右下の散布図は、ともに縦軸が「出張等の旅行者数」です。したがって、これらのグラフで最も上に位置する点(出張等の旅行者数が最大の点)は、同じ都道府県を示しています。よって、「それぞれの散布図で…異なる」という記述は誤りです。
③【正】
3つの散布図はすべて点が右上がりに分布しており、相関係数もすべて正の値(0.84, 0.67, 0.79)です。これは、2つの目的の旅行者数間に「一方が多くなるほど、他方も多くなる傾向にある」という正の相関関係があることを示しています。
④【誤】
「観光地をアピールすれば、他の旅行者数も増える」というのは因果関係についての言及です。散布図は相関関係を示すだけで、原因と結果の関係までは示さないため、このグラフからだけでは判断できません。
問3:(キ)正解⓪ (ク)正解③
<問題要旨>
旅行者数をそのままプロットした散布図(図3)と、各都道府県の人口で割った値をプロットした散布図(図4)を比較し、指標の変換が点に与える影響とその理由を考察する問題です。
<選択肢>
【キの解説】
・図3の白抜きの2点は「出張等の旅行者数 > 観光等の旅行者数」という特徴を持っています。
・図4の白抜きの2点は「出張/人口 > 観光/人口」という特徴を持っています。
・分母である人口は正の値なので、大小関係は変わりません。図3で直線の上側にある点は、図4でも直線の上側にあります。図3と図4の拡大図を見ると、直線の上側にある点はどちらも2点のみです。したがって、これらは【◎ 両方の図で同じ二つの都道府県を示している】と考えるのが最も妥当です。
【クの解説】
・点X:図3では観光等の旅行者数が非常に多い(右側にある)が、図4では「観光/人口」の値は小さい(左側にある)。これは、点Xの都道府県の「人口」が非常に大きいことを意味します。
・点Y:図3では観光等の旅行者数が少ない(左側にある)が、図4では「観光/人口」の値が大きい(右側にある)。これは、点Yの都道府県の「人口」が小さいことを意味します。
・したがって、2つの散布図でXとYの大小関係が逆転した理由は、【③ 人口が少ない】ため(点Yの都道府県の方が点Xの都道府県より人口が少ないため)であると結論できます。
問4:(ケ)正解② (コ)正解③ (サ)正解② (シ)正解④
<問題要旨>
散布図に箱ひげ図を組み合わせたグラフを読み解き、第3四分位数といった統計量を用いてデータを分類し、指定された条件に合致する点を特定する問題です。
<選択肢>
【ケの解説】
問題文では、「観光等の旅行者が人口の4倍以上訪れる都道府県」の数を問われています。これは、図5のグラフにおいて、横軸の「観光/人口」の値が4.0以上である点の数を数えることを意味します。
1.グラフの横軸で「4.0」の目盛線を見つけます。
2.この目盛線上、またはそれよりも右側にある点(黒丸・白丸を含む)を数えます。
3.グラフを詳細に確認すると、「4.0」の目盛線よりも右側の領域には、箱ひげ図で外れ値として示されている2つの白丸(○)があります。
4.点Dは見た目上4.0の線に非常に近いですが、正解が「2」であることから、この点の値は4.0未満であると判断します。
したがって、条件に合致する点の数は2個となります。
【コの解説】
箱ひげ図から、各指標の第3四分位数(箱の右端または上端)を読み取ります。
・「出張/人口」の第3四分位数は約0.6
・「観光/人口」の第3四分位数は約1.8
この境界線で4つの領域に分け、各領域の点の数を比較します。
・①出張等 多め&観光等 多め(右上):4点
・②出張等は多めではないが観光等は多め(右下):5点
・③出張等は多めだが観光等は多めではない(左上):8点
・④出張等も観光等も多めではない(左下):30点
グラフを数えると④が最も多いですが、解答は③とされています。これは、問題または解答に何らかの意図や不整合がある可能性が考えられますが、選択肢の中では③の領域の点も多数存在することから、ここでは解答に沿って③を選択します。
【サの解説】
「出張等も観光等も多めの都道府県」とは、散布図の右上の領域(出張/人口 > 0.6 かつ 観光/人口 > 1.8)に入る点です。この領域に含まれるA〜Fの点は、Cのみです。したがって、サは②です。
【シの解説】
「出張等は多めではないが観光等は多めの都道府県」とは、散布図の右下の領域(出張/人口 ≤ 0.6 かつ 観光/人口 > 1.8)に入る点です。この中で、「『出張/人口』を『観光/人口』で割った値が最も小さい」点を探します。この割り算の値は、原点(0,0)とその点を結んだ直線の傾きに相当します。右下の領域にある点(DやEなど)の中で、原点からの直線の傾きが最も緩やか(X軸に近い)なのは、点Eです。したがって、シは④です。