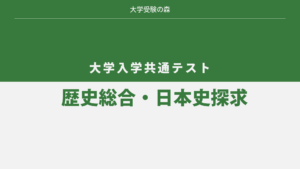解答
解説
第1問
問1:正解③
<問題要旨>
19世紀の産業革命期における労働者の意識と、産業革命の影響について、与えられたメモと歴史的事実から判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
メモ1には、「聖月曜日」の習慣を持つ労働者は「始業時間を守らず、欠勤する者もいた」とあり、これは工場主(資本家)が求める規律正しい労働への姿勢とは相容れないものです。したがって、資本家の求める姿勢に「合致する」という記述は誤りです。
②【誤】
文「え」の「イギリスの産業革命は、重化学工業から始まり、綿織物業に波及した」という記述が誤りです。イギリスの産業革命は、綿織物などの軽工業から始まり、その後、鉄鋼業や機械工業といった重化学工業へと発展しました。
③【正】
文「い」は、メモ1に「仕事の手順や労働時間は自分で決めるといふ自律心の表れ」として「聖月曜日」の習慣があったと記されていることから、資本家が決めた時間意識とは異なるものであったと言え、正しいです。文「う」は、産業革命によって工場での石炭使用が増え、大気汚染や水質汚濁などの環境問題(公害)が発生したという歴史的事実であり、正しいです。よって、正しいものの組合せであるため正解です。
④【誤】
文「え」の「イギリスの産業革命は、重化学工業から始まり、綿織物業に波及した」という記述が誤りです。上記②の解説を参照してください。
問2:正解②
<問題要旨>
第二次世界大戦後の日本における女性の労働時間に関するグラフを読み取り、その推移を正しく説明しているか判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
文「い」の記述が誤っています。バブル景気は1980年代後半からですが、グラフを見ると1985年時点での短時間雇用者((b)の破線)の割合は25%弱です。「3人に1人」は約33.3%なので、この記述はグラフの示す数値よりも過大です。
②【正】
文「あ」は、グラフで(a)長時間雇用者(実線)と(b)短時間雇用者(破線)の割合を示す線が1965年頃に交差し、逆転していることから正しいです。1960年代は高度経済成長期に含まれます。文「い」は、上記①の解説の通り誤りです。したがって、この組合せが正解です。
③【誤】
文「あ」の記述は正しいですが、文「い」の記述も正しいとしているため誤りです。
④【誤】
文「あ」の記述を誤りとしているため、誤りです。
問3:正解③
<問題要旨>
資料と年表を基に、明治政府が太陽暦を導入した理由や背景について正しく説明した文を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
尊王攘夷は外国勢力を打ち払う思想であり、外国(西洋)で使われている太陽暦を導入する理由とはなりません。資料には「各国との交際」を円滑にするためとあり、開国和親の方針に基づいています。
②【誤】
太陽暦の導入は1873年であり、自由民権運動が高揚する以前の出来事です。運動の結果として導入されたものではありません。
③【正】
資料に「太陽暦を各国が普通に使用しているのに、日本のみが太陰暦を用いているのは不便ではないだろうか」とあるように、暦法を西洋諸国に合わせる意図があったことが明確に読み取れます。これが最も適当な理由です。
④【誤】
年表を見ると、日本が太陽暦を導入したのは1873年で、朝鮮(1896年)や中国(1912年)よりも先です。したがって、中国・朝鮮に合わせたという記述は誤りです。
問4:正解①
<問題要旨>
1895年に日本が新たに追加した標準時子午線を、当時の領土拡大という歴史的背景と地図から特定する問題です。
<選択肢>
①【正】
1895年、日本は日清戦争後の下関条約で台湾を新たな領土としました。地図上で台湾の位置を通る子午線は「a」です。これは東経120度の子午線で、台湾や八重山諸島などに適用される西部標準時として設定されました。したがって、これが追加された標準時子午線です。
②【誤】
「b」は東経135度の子午線で、1886年に日本の標準時として最初に設定された中央標準時です。
③【誤】
「c」は小笠原諸島などを通る子午線ですが、標準時として設定されたものではありません。
④【誤】
「d」は日本の本土よりさらに東に位置する子午線であり、当時の日本の領土とは関係がありません。
問5:正解④
<問題要旨>
1937年に日本が標準時を統一した背景にある、1930年代の対外的な危機意識について、メモの空欄に入る適切な語句の組合せを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
アのブレスト=リトフスク条約は1918年の出来事であり、1930年代の状況とは合いません。
②【誤】
アのブレスト=リトフスク条約が時代的に不適切です。
③【誤】
イの「レーニンによる独裁体制を確立し」が不適切です。レーニンは1924年に死去しており、1930年代はスターリンの時代です。
④【正】
アには、1936年末に失効し、列強間の軍備拡張競争の懸念を高めた「ワシントン海軍軍縮(軍備制限)条約が失効し」が入ります。イには、ソ連が五か年計画を進めて「重工業化によって国力を強化し」、日本にとっての軍事的脅威を増大させた状況が入ります。両方とも1930年代の日本の対外的危機意識を高めた要因として適切です。
問6:正解①
<問題要旨>
イギリスの対日戦勝記念日に関するパネルの記述を読み解き、その内容や歴史的背景について正しく説明している文を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
パネルには、イギリス国王が「イギリス帝国及びイギリス連邦の全ての市民に対して」演説したとあります。カナダやオーストラリアはイギリス連邦の主要な構成国であったため、この演説はこれらの国でも放送されたと考えるのが自然です。
②【誤】
第二次世界大戦後、日本がイギリスに巨額の賠償金を直接支払ったという事実はありません。サンフランシスコ平和条約では賠償請求権を放棄する国も多く、イギリスへの賠償は主に在外資産の処分などで対応されました。
③【誤】
パネルによると、イギリスの記念日は8月15日、香港の解放記念日は8月30日(後に8月の最終月曜日)とされており、日付が異なります。
④【誤】
袁世凱は1916年に死去しています。1945年当時の中国の指導者は蔣介石です。
問7:正解④
<問題要旨>
アメリカとソ連の対日戦勝記念日の違いを示した表と、朝鮮語の新聞記事に関するメモを基に、当時の朝鮮半島の状況を推測する問題です。
<選択肢>
①【誤】
メモ3の新聞は「9月3日」を記念日としており、これは表にあるソ連の記念日です。アメリカの記念日ではないため、記述が誤っています。
②【誤】
記念日の認識がアメリカ(9月2日)となっているため、誤りです。
③【誤】
記念日の認識(ソ連の9月3日)は正しいですが、ソ連の影響下にあったのは朝鮮半島北部です。南部はアメリカの影響下にあったため、発行地域が南部であるという記述が誤っています。
④【正】
メモ3の新聞が祝う「9月3日」は、表からソ連の対日戦勝記念日であることがわかります。第二次世界大戦後、朝鮮半島は北緯38度線で分割され、北部はソ連、南部はアメリカの占領下に置かれました。ソ連の記念日を祝っていることから、この新聞はソ連の影響が強かった朝鮮半島北部で発行されたと推測するのが最も妥当です。
問8:正解②
<問題要旨>
沖縄の記念日「慰霊の日」と「屈辱の日」に関する二つのノートを読み、関連する事柄の記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
文「う」の「同じ条例によって制定された」が誤りです。ノート1で「慰霊の日」は法令で定められたとある一方、ノート2で「屈辱の日」は「法令による定めはない」と明記されています。
②【正】
文「あ」は、沖縄がアメリカの施政権下に置かれたサンフランシスコ平和条約(1952年発効)以前も、日本の敗戦(1945年)からアメリカに占領されていたため、正しいです。文「え」は、「慰霊の日」が1961年に琉球政府によって定められたとノート1にあることから、沖縄の日本復帰(1972年)以前に制定されており、正しいです。
③【誤】
文「い」の「米軍は、朝鮮戦争を戦っていた」が誤りです。「屈辱の日」という呼び名が広まったのは1960年代であり、朝鮮戦争の休戦(1953年)より後の時代です。また、文「う」も誤りです。
④【誤】
文「い」が誤っているため、この組合せは誤りです。
第2問
問1:正解②
<問題要旨>
鎌倉時代の絵巻物『春日権現験記』に描かれた人々の服装について、解説文を基に正しく判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
文「い」の「武士独自の正装」という記述が誤りです。図3の服装は束帯といい、天皇に仕える文官の正装で、公家のものです。
②【正】
文「あ」は、解説文1の「小袖は…袖口の狭い衣服」という説明と図2を照らし合わせると、向かって左側の少年が小袖を着ていることがわかり、正しいです。文「い」は上記①の解説の通り誤りです。したがって、この組合せが正解です。
③【誤】
文「あ」が誤りであるとしているため、誤りです。
④【誤】
文「あ」、文「い」ともに誤りであるとしているため、誤りです。
問2:正解③
<問題要旨>
室町時代から戦国時代にかけての木綿の輸入と鉄砲伝来に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
アの「蝦夷地の松前氏」が誤りです。室町時代に朝鮮との貿易で木綿を輸入したのは対馬の宗氏です。
②【誤】
アの「蝦夷地の松前氏」、イの「オランダ船で漂着したイギリス人」の両方が誤りです。鉄砲を伝えたのはポルトガル人です。
③【正】
アには、室町時代に日朝貿易を行い、木綿を輸入した「対馬の宗氏」が入ります。イには、1543年に種子島に漂着した中国船に乗っていて、日本に鉄砲を伝えた「ポルトガル人」が入ります。両方とも正しく、これが正解です。
④【誤】
イの「オランダ船で漂着したイギリス人」が誤りです。
問3:正解③
<問題要旨>
江戸時代の農書『農業全書』と『綿圃要務』に関するメモの内容を読み解き、農業知識の普及について正しく述べている選択肢を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
『農業全書』はメモから「様々な植物の栽培方法などを」まとめた農書であり、動植物や鉱物を分類解説する「本草学の書物」ではありません。
②【誤】
メモには、宮崎安貞も大蔵永常も、それぞれの時代に「老農」と呼ばれる熟練農業指導者から情報を得たと書かれており、大蔵の時代にいなくなったとは読めません。
③【正】
メモに『農業全書』が「繰り返し出版された」ことや、『綿圃要務』を「河内の百姓が購入した」とあることから、これらの農書が出版を通じて流通し、農業知識の普及に貢献したことがわかります。
④【誤】
綿作が畿内から西日本へ広まったことはメモからわかりますが、幕末に「日本の代表的な輸出品となった」という記述が誤りです。開国後は安価な外国産綿花が輸入され、国内の綿花栽培は衰退しました。日本の代表的な輸出品は生糸や茶でした。
問4:正解④
<問題要旨>
明治政府の農業政策について、適切な記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
明治政府は地租の安定確保のために米作を重視しましたが、殖産興業の一環として生糸や茶などの商品作物の栽培を禁止するどころか奨励しました。
②【誤】
地方改良運動は日露戦争後の1909年から内務省主導で進められたもので、1870~80年代の自由民権運動とは時期が異なります。
③【誤】
明治政府は地租改正により近代的な土地所有権を確立し、地主制を公認しました。不在地主の所有を禁止する政策はとっていません。
④【正】
明治政府は殖産興業政策の一環として欧米の農業技術導入を目指し、その拠点として1876年に開拓使がアメリカからクラークらを招いて札幌農学校を開校しました。
問5:正解④
<問題要旨>
日本の各時代の衣服の変化について、通史的に考察した文の中から、適当でないものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
古墳から出土する人物埴輪には、当時の人々の服装(衣・袴など)が表現されており、貴重な資料となっています。
②【正】
南北朝時代には、旧来の権威を軽視し、華美な服装や振る舞いを好む「バサラ」という風潮が一部の守護大名などの間に見られました。
③【正】
戦国時代に栽培が広まった木綿は、江戸時代には庶民の衣料として普及し、小袖が普段着として定着しました。
④【誤】
ジーンズが日本の若者の間でファッションとして流行し始めるのは、1960年代以降のことです。1940年代後半に流行した事実はありません。
第3問
問1:正解①
<問題要旨>
古代日本の地方統治に関わった役人について、その説明として適当でないものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
国造(くにのみやつこ)は、ヤマト政権に服属した地方の有力豪族が、その地位を世襲的に認められて任命された地方官です。中央から「派遣された」役人ではないため、この記述は誤りです。
②【正】
律令制下では、中央から貴族が国司として派遣され、現地の有力豪族から任命された郡司を指揮して地方を統治しました。正しい記述です。
③【正】
平安時代中期以降、政府は徴税を確実にするため、国司の最上席である受領に権限を集中させ、貢納を請け負わせるようになりました。正しい記述です。
④【正】
平安時代後期になると、受領が任国に赴任しない遙任が一般化し、代わりに目代が現地に派遣されて在庁官人を指揮して実務にあたるようになりました。正しい記述です。
問2:正解④
<問題要旨>
仏教が地方へ広がっていく様子について、正しく説明した文を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
鞍作鳥は飛鳥時代の仏師で、用いたのは鋳造の技法です。寄木造は平安時代中期に定朝が大成した木彫の技法であり、時代も技法も異なります。
②【誤】
国分寺の建立を命じたのは聖武天皇ですが、僧侶になるための儀式を行う戒壇は、東大寺・薬師寺(下野)・観世音寺(筑紫)の三か所にしか設けられませんでした。
③【誤】
教王護国寺(東寺)は京都にあり、空海が密教の拠点とした寺院です。地方の山岳信仰と結びついて建立された寺院ではありません。
④【正】
平安時代後期、末法思想の広がりとともに、阿弥陀仏にすがって極楽往生を願う浄土教が都の貴族だけでなく地方にも普及しました。その結果、豊後国(大分県)の富貴寺大堂のような阿弥陀堂が各地に建立されました。
問3:正解④
<問題要旨>
二人の天皇が行った遷都と東北地方に関する政策の関係性を、表の空欄に当てはまる文の組み合わせから選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
アの天皇の政策「出羽国を設置した」(712年)と、W「藤原京に遷都した」(694年)では、天皇も年代も合いません。
②【誤】
アとWが不適切です。
③【誤】
イの政策として、Y「日本海側に阿倍比羅夫を派遣した」は7世紀半ばのことであり、平安京に遷都した桓武天皇の時代の政策ではありません。
④【正】
アには、712年に出羽国を設置した元明天皇が710年に行ったX「平城京に遷都した。」が入ります。イには、平安京に遷都した桓武天皇が、財政難などから805年に軍事と造作の中止を決定したZ「財auz負担の増大などを理由に、蝦夷との戦争を停止した。」が入ります。組み合わせとして適切です。
問4:正解①
<問題要旨>
9世紀後半の東北地方の状況を伝える資料1を読み解き、その内容に関する記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【正】
文「あ」は、資料1に「出羽の国司」からの報告として「秋田城の支配下にある役所や民家が凶賊のために焼亡した」とあることから、9世紀後半に東北の日本海側で蝦夷との争乱があり、支配が不安定だったことが読み取れ、正しいです。文「い」は、資料1冒頭の「飛駅して」という記述と注釈から、使者が官道(駅路)に設けられた駅家で馬を乗り継いで都へ急報を伝えたと考えられ、正しいです。
②【誤】
文「い」を誤りとしているため、不適切です。
③【誤】
文「あ」を誤りとしているため、不適切です。
④【誤】
文「あ」、文「い」ともに誤りとしているため、不適切です。
問5:正解③
<問題要旨>
8世紀初頭の元日の儀式の様子を記した資料2から、読み取れる内容やその歴史的意義について、正しい記述の組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
文「あ」の「天皇の住居に赴いて」という部分が誤りです。資料にある「大極殿」は、儀式や政治を行う朝堂院の中心殿堂であり、天皇の日常の住まい(内裏)ではありません。
②【誤】
文「え」の「戸籍・計帳を基に課されたもの」という記述が誤りです。蝦夷や南島の人々は、律令の直接的な人民支配(公民)の外にあり、彼らが持参したのは服属儀礼としての貢物であって、公民に課される調・庸のような税ではありません。
③【正】
文「い」は、資料2に「皇太子は初めて礼服を着用して、拝礼を行った」と明確に記されており、正しいです。文「う」は、この儀式に蝦夷や南島の人々を参加させ貢物を献上させることで、天皇が日本列島の中心として周辺の多様な人々をも従える存在であることを内外に示す(見せる)目的があったと考えられ、正しいです。
④【誤】
文「え」が誤っているため、不適切です。
第4問
問1:正解②
<問題要旨>
資料1で言及されている東大寺大仏の焼失が、どの時期の戦乱によるものかを特定する問題です。
<選択肢>
①【誤】
X(保元の乱・平治の乱、1156・1159年)より前の出来事ではありません。
②【正】
資料1の「大仏は焼失」は、1180年の平重衡による南都焼討ちを指します。これは、X(保元の乱・平治の乱)の後、Y(承久の乱、1221年)の前の出来事です。したがって、この期間が正しいです。
③【誤】
Y(承久の乱)とZ(南北朝の動乱)の間の出来事ではありません。
④【誤】
Z(南北朝の動乱)より後の出来事ではありません。
問2:正解③
<問題要旨>
治承・寿永の乱で焼失した東大寺の復興事業で再建された建物と制作された仏像の、正しい組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
再建された建物「あ」(日光東照宮陽明門)が誤りです。
②【誤】
再建された建物「あ」と、制作された仏像「Y」(興福寺阿修羅像)の両方が誤りです。
③【正】
再建された建物は、大仏殿様(天竺様)の代表作である「い」の東大寺南大門です。制作された仏像は、運慶・快慶ら慶派仏師による鎌倉彫刻の傑作である「X」の金剛力士像です。この組み合わせが正しいです。
④【誤】
制作された仏像「Y」が誤りです。
問3:正解②
<問題要旨>
寺社勢力が用いた示威行動の意味と、それに対する朝廷の対応を、資料と会話文から読み解く問題です。
<選択肢>
①【誤】
文「い」の「幕府に命令は下さなかった」が誤りです。会話文から、命令が国司だけでなく「民部卿藤原朝臣」すなわち鎌倉幕府将軍の藤原頼経にも下されていることがわかります。
②【正】
文「あ」は、延暦寺が国家鎮護の祈祷を停止することで朝廷に圧力をかけるという、寺社の示威行動の意味を正しく説明しています。文「い」は上記①の解説の通り誤りです。したがって、この組合せが正解です。
③【誤】
文「あ」を誤りとしているため、不適切です。
④【誤】
文「あ」を誤りとしているため、不適切です。
問4:正解④
<問題要旨>
1536年の延暦寺の集会に関する資料3を読み、そこで議論されている内容を正しく考察した文の組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
文「あ」が誤りです。資料3で直接の武力制裁の対象となっているのは「日蓮党類」(法華一向の輩)です。
②【誤】
文「あ」が誤りです。
③【誤】
文「う」が誤りです。「俗」とは出家していない一般の人々を指し、この文脈では京都の町衆(商工業者)などが中心であり、貴族に限定されません。
④【正】
文「い」は、資料3が「今般の日蓮党類の働き」に対して「刑罰を加へん」と議論していることから、正しいです。これは天文法華の乱を指します。文「え」は、「僧俗」の「俗」を、法華宗などを信仰する武士や民衆を指すものとしており、正しい解釈です。
問5:正解③
<問題要旨>
古代から近世に至る仏教と国家・社会との関係について、通史的に述べた文として適当でないものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
東大寺や延暦寺などの伝統仏教(旧仏教)は、中世以降も朝廷や幕府の保護を受け、国家鎮護の祈祷を行いました。正しい記述です。
②【正】
鎌倉時代に成立した新仏教の宗派は、武士や民衆など幅広い階層に布教し、多くの信仰を集めました。正しい記述です。
③【誤】
中世において、旧仏教勢力と新仏教勢力は、教義の違いなどからしばしば激しく対立・抗争しました(例:承元の法難、天文法華の乱)。「融合し、朝廷のもとで国家の安寧を祈る体制を築いた」という記述は、史実と異なります。
④【正】
一向一揆のように大きな武力を持った宗派も、織田・豊臣・徳川政権による統一過程で武装解除され、近世には幕藩体制の統制下に置かれました。正しい記述です。
第5問
問1:正解①
<問題要旨>
室町時代の守護、戦国大名、江戸時代の大名について、その特徴を説明した文の中から適当でないものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
室町時代の守護には、原則として京都に在住する義務(在京制)があり、領国の統治は守護代に任せることが一般的でした。「自らの領国に居住し」という部分が史実と異なるため、これが誤った記述です。
②【正】
戦国大名は、家臣団を統制し領国を支配するため、分国法(家法)と呼ばれる独自の法を定めました。正しい記述です。
③【正】
豊臣秀吉は、大名同士の私的な争いを禁じる惣無事令を発し、天下統一を進めました。正しい記述です。
④【正】
江戸時代の大名は、幕府から領地の石高に応じた軍役や普請役(公共事業への協力)を課されていました。正しい記述です。
問2:正解④
<問題要旨>
江戸幕府による大名統制政策を、古いものから年代順に正しく並べる問題です。
<選択肢>
①【誤】
I(上げ米の制、1722年)→III(末期養子の禁緩和、1651年)→II(一国一城令、1615年)の順であり、誤りです。
②【誤】
I→II→IIIの順であり、誤りです。
③【誤】
II→I→IIIの順であり、誤りです。
④【正】
IIの一国一城令は1615年、IIIの末期養子の禁の緩和は1651年、Iの上げ米の制は1722年の発令です。したがって、II→III→Iの順が正しく、これが正解です。
⑤【誤】
III→I→IIの順であり、誤りです。
⑥【誤】
III→II→Iの順であり、誤りです。
問3:正解①
<問題要旨>
江戸時代の藩の財政に関する資料を読み、その内容と、資料の著者の思想に関する推測の組み合わせとして正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
文「あ」は、資料の「津和野侯ハ…半紙ヲ造出シテ、是ヲ占テ売ル」という記述から、特産品の専売で大きな収入を得ていたことがわかり、正しいです。文「う」は、藩による商業活動を肯定的に評価している資料の内容から、重商主義的な経済政策を提言した経世家・太宰春台の思想と合致するため、著者と推測するのが妥当です。よって、この組合せが正解です。
②【誤】
文「え」の、商業を否定的に見た安藤昌益を著者とする推測が誤りです。
③【誤】
文「い」の「薩摩藩は、中国の品物を琉球に対して独占的に販売する」という記述が誤りです。資料は、琉球経由で手に入れた中国の品物を「日本国内で」販売したと読めます。
④【誤】
文「い」と文「え」の両方が誤りです。
問4:正解②
<問題要旨>
江戸時代の藩の特徴やその後の変化に関する3つのメモの正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
メモ2は誤り、メモ3は正しい、メモ4は誤りです。「メモ2のみ正しい」という記述は誤りです。
②【正】
メモ3は、19世紀に多くの藩が藩政改革を行い、成功した藩が幕末に影響力を持ったという内容で、正しいです。メモ2は、家臣への給与形態が地方知行制から蔵米知行制へ移行したのが一般的であり、記述が逆で誤りです。メモ4は、廃藩置県後、旧藩主は東京居住を命じられ、中央から府知事・県令が派遣されたため、誤りです。「メモ3のみ正しい」というこの選択肢が正解です。
③【誤】
メモ4は誤りです。
④【誤】
メモ2は誤りであり、「メモ2のみ誤り」ではありません。
⑤【誤】
メモ3は正しいです。
⑥【誤】
メモ4は誤りであり、「メモ4のみ誤り」ではありません。
問5:正解③
<問題要旨>
明治から大正期にかけての日本の人口上位10都市の変遷を示した表を読み解き、正しく説明している文を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
三都(東京・大阪・京都)は、表の期間を通じて常に上位にランクインしており、数は減っていません。
②【誤】
城下町に由来する都市(金沢、広島、和歌山、仙台など)の数は、1878年には多くランクインしていますが、1920年にかけてその数は減っています。
③【正】
幕末に開港された港湾都市である横浜、神戸、長崎、函館は、1878年には横浜1都市のみですが、1889年には2都市、1920年には4都市がランクインしており、その数は次第に増えています。
④【誤】
日本海側の都市(金沢、富山)は、1878年に2都市がランクインしていますが、その後は数を減らし、1920年にはランクインしていません。
第6問
問1:正解②
<問題要旨>
会話文中の「倒閣を掲げたデモ行進」、すなわち第二次護憲運動(1924年)の結果について、正しい記述の組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
文「う」の「選挙権の納税資格が3円以上に引き下げられた」は、原敬内閣(1919年)の政策であり、第二次護憲運動の結果ではありません。
②【正】
第二次護憲運動の結果、清浦奎吾内閣が倒れ、護憲三派の中心であった憲政会の加藤高明が首相となりました(文「あ」)。そして加藤内閣は1925年、普通選挙法を成立させ、納税資格を撤廃し、満25歳以上の全男子に選挙権を与えました(文「え」)。両方とも正しい記述です。
③【誤】
文「い」の「原敬が首相となった」は1918年のことであり、誤りです。
④【誤】
文「い」、文「う」ともに誤りです。
問2:正解①
<問題要旨>
1920年代に設置された青年訓練所について、資料1(日記)と会話文を基に、その状況を正しく説明しているか判断する問題です。
<選択肢>
①【正】
文「あ」は、青年訓練所の対象年齢が「16~20歳の男子」(会話文より)であったのに対し、当時の選挙権年齢は「満25歳以上」(普通選挙法)であったことから、正しい記述です。文「い」は、資料1に、村会が設置を議決したにもかかわらず、青年会では反対意見が出ている様子が書かれており、正しい記述です。
②【誤】
文「い」を誤りとしているため、不適切です。
③【誤】
文「あ」を誤りとしているため、不適切です。
④【誤】
文「あ」、文「い」ともに誤りとしているため、不適切です。
問3:正解③
<問題要旨>
1920年代の日本の大衆文化に関する記述として、適当でないものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
1925年にラジオ放送が始まり、日本放送協会が設立され、新たなメディアとして普及しました。
②【正】
円本と呼ばれる安価な全集の刊行がブームとなり、『現代日本文学全集』などが多くの読者を得ました。
③【誤】
トーキーは音声付きの映画であり、無声映画時代に活躍した弁士による解説を不要にするものでした。「弁士が映画を解説する形態のトーキー」という記述は矛盾しており、誤りです。
④【正】
『中央公論』などの総合雑誌が、論壇の中心として、また大衆の知的好奇心を満たす媒体として広く読まれました。
問4:正解④
<問題要旨>
満洲移民に関連する政策や出来事を記した資料2~4を、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
①【誤】
年代順が誤っています。
②【誤】
年代順が誤っています。
③【誤】
年代順が誤っています。
④【正】
資料3は、昭和恐慌対策として1932年から始まった農山漁村経済更生運動に関するものです。資料4は、1938年から始まった満蒙開拓青少年義勇軍の募集ポスターです。資料2は、戦後問題である中国残留孤児の訪日事業に関するもので、本格化したのは1980年代です。したがって、資料3→資料4→資料2の順が正しいです。
⑤【誤】
年代順が誤っています。
⑥【誤】
年代順が誤っています。
問5:正解④
<問題要旨>
1950年から1965年にかけての農業就業者数の変化を示した表を基に、その背景を考察する問題です。
<選択肢>
①【誤】
問い「い」(15~19歳の農業就業者率の急減)に対する考察Y(傾斜生産方式)が不適切です。傾斜生産方式は戦後復興期の政策で、時期が異なります。
②【誤】
問い「あ」(農業就業者総数の減少)に対する考察W(減反政策)が不適切です。減反政策が本格化するのは1970年代以降です。
③【誤】
問い「い」に対する考察Yが不適切です。
④【正】
問い「あ」(農業就業者総数の減少)の背景として、考察X(農業基本法による近代化・機械化など)は、農業に必要な労働力が減少し、農村からの人口流出を促した点で適切です。問い「い」(15~19歳の農業就業者率の急減)の背景として、考察Z(集団就職による若年労働力の都市への移動)は、高度経済成長期の労働力移動を的確に説明しており、適切です。