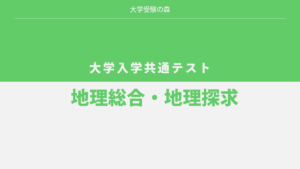解答
解説
第1問
問1:正解②
<問題要旨>
三大穀物である小麦、米、トウモロコシの生産量に対する輸出量の比率と、主な輸出元地域に関する統計データから、それぞれの作物を特定する問題です。各穀物の生産地域や国際的な流通量の特徴に関する知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
アを小麦、ウを米と判断するのは正しいですが、イをトウモロコシではなく米と判断しているため誤りです。
②【正】
アは、世界の生産量に対する輸出量の比率が24.4%と最も高く、主な輸出元としてヨーロッパが挙げられています。小麦は世界各地で生産される主要な輸出穀物であり、ヨーロッパ(フランス、ロシア、ウクライナなど)は主要な輸地域であるため、アは小麦と判断できます。
イは、中央・南アメリカが主要な輸出元地域となっています。トウモロコシはアメリカ大陸が原産で、アメリカ合衆国やブラジル、アルゼンチンなどが主要な輸出国であることから、イはトウモロコシと判断できます。
ウは、世界の生産量に対する輸出量の比率が5.7%と最も低く、自給的な性格が強い作物です。また、主な輸出元はアジアが78.2%を占めています。米はアジアのモンスーン地域で主に生産・消費され、生産国での国内消費が多くを占めるため輸出率は低くなります。したがって、ウは米と判断できます。
以上のことから、アが小麦、イがトウモロコシ、ウが米の組み合わせが正しく、この選択肢が正解です。
③【誤】
アを米、イを小麦と判断している点が誤りです。
④【誤】
アをトウモロコシ、イを小麦、ウを米と判断している点が誤りです。
⑤【誤】
アを米、ウを小麦と判断している点が誤りです。
⑥【誤】
アをトウモロコシ、イを米、ウを小麦と判断している点が誤りです。
問2:正解②
<問題要旨>
世界地図に示された4つの地点と、米を用いた4つの特徴的な料理を結びつける問題です。各地域の食文化と、料理の材料や調理法に関する知識が問われます。この問題では、地点C(インドネシア周辺)の料理を特定します。
<選択肢>
①【誤】
この料理は、説明文の「魚介類やトマトと一緒にオリーブオイルで炒めて炊いている」という特徴から、スペイン料理のパエリアと判断できます。パエリアは、地図中の地点B(スペイン)を代表する料理です。
②【正】
この料理は、説明文の「米をココナッツミルクで炊き、ゆで卵や野菜とともに盛り付けている」という特徴から、マレーシアやインドネシアで広く食べられているナシレマッ(またはその類似料理)と判断できます。ココナッツミルクで炊いたご飯は、東南アジアの食文化に特徴的です。したがって、地点C(インドネシア)の周辺でみられる料理として最も適当です。
③【誤】
この料理は、説明文の「醤油で味付けしたモチ米や豚肉を、笹の葉にくるんで蒸している」という特徴から、中華ちまきと判断できます。ちまきは、東アジアや東南アジアの中華系文化圏で広く食べられており、地点D(日本)の食文化にも関連しますが、地点Cの代表的な料理とまでは言えません。
④【誤】
この料理は、説明文の「ゆでたジャガイモと米に、鶏肉とトウガラシの入ったソースをかけている」という特徴から、南米の料理と考えられます。ジャガイモやトウガラシはアンデス地域が原産であり、この料理はペルーなどで見られるアロス・コン・ポヨなどに類似しています。地図中の地点A(ペルー沖)に対応する料理です。
問3:正解①
<問題要旨>
アフリカの2か国(X国:エジプト、Y国:チャド)の穀物収穫面積の割合と、稲作の方法に関する文章から、穀物名(小麦かモロコシ)と稲作で利用される水資源(灌漑施設か天水田)を特定する問題です。各国の自然環境(気候、水文)と農業の特徴を結びつけて考える必要があります。
<選択肢>
①【正】
まず、国を特定します。X国はナイル川下流に位置するエジプト、Y国はサハラ砂漠南縁のサヘル地帯に位置するチャドと判断できます。
Y国(チャド)は乾燥・半乾燥地域であり、乾燥に強いモロコシ(ソルガム)やミレットが伝統的に主要な作物です。図2のY国の円グラフではGが圧倒的な割合を占めているため、Gがモロコシと判断できます。
一方、X国(エジプト)では、ナイル川を利用した灌漑農業が盛んで、小麦などが栽培されています。したがって、消去法的にFが小麦となります。
次に、空欄カについて考えます。X国(エジプト)は国土の大部分が砂漠気候で、降水量が極めて少ないため、農業はナイル川からの灌漑に全面的に依存しています。したがって、エジプトでの稲作は「灌漑施設」を利用して行われます。
以上のことから、Fが小麦、カが灌漑施設の組み合わせであるこの選択肢が正解となります。
②【誤】
カを「灌漑施設」と判断している点は正しいですが、Fを「小麦」ではなく「G」と対応させているため誤りです。
③【誤】
Fを小麦と正しく判断していますが、カを「天水田」としている点が誤りです。エジプトの気候では天水による稲作は不可能です。
④【誤】
Fを小麦ではなくGとし、カを天水田としている両方の判断が誤りです。
問4:正解②
<問題要旨>
三大穀物と大豆の収穫面積と1ha当たりの収量(単収)の経年変化を示したグラフを読み取り、それに関する記述の正誤を判断する問題です。グラフから各作物の生産性の変化を正確に読み取り、その背景にある技術革新や需要の変化などの知識と結びつける能力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
図3の横軸(収穫面積)を見ると、大豆は1960年代の約25百万haから2000年代の約90百万haへと大きく拡大していますが、同じ期間の小麦の収穫面積(約210百万ha→約220百万ha)の絶対値には及びません。また、大豆の栽培面積拡大の主な要因は、食肉需要増に伴う飼料用需要の拡大や、植物油の需要増大であり、「気候変動によって栽培適地が拡大した」は主たる要因とは言えません。
②【正】
図3の縦軸(1ha当たりの収量)を見ると、トウモロコシは1960年代の約2トンから2000年代の約4.5トンへと約2.5トン増加しており、他の作物(米:約2トン弱の増加、小麦:約1.6トンの増加、大豆:約1.1トンの増加)と比べて最も増加量が大きくなっています。この著しい単収の増加の背景には、品種改良や化学肥料の普及に加え、近年では遺伝子組み換え技術の導入が大きく貢献していると考えられます。したがって、この記述は正しいです。
③【誤】
図3を見ると、米の1ha当たりの収量は1960年代の約2トンから2000年代の4トン弱へと、約2倍になっています。「3倍以上になった」という記述は、グラフの数値を過大に表現しており誤りです。「緑の革命」が単収向上に寄与したことは事実ですが、数値の記述が不正確です。
④【誤】
図3を見ると、小麦の収穫面積は1980年代から2000年代にかけて、微減ではなく、ほぼ横ばいから微増で推移しています。また、世界の人口増加に伴い食料需要は増大し続けており、「十分な小麦の供給が行われた」という背景説明も世界の食料事情の実態とは異なり、不適切です。
第2問
問1:正解③
<問題要旨>
愛媛県今治市の波止浜湾周辺の地図上の指定された地点から、どの方向を撮影した写真かを特定する問題です。地図の読図能力と、写真に写る特徴的な対象物(橋、建物など)から方角や位置関係を正確に把握する力が問われます。
<選択肢>
①【誤】
この写真は、湾の南側から北方向を撮影したものと考えられます。地点Bから南東方向を撮影した景色とは異なります。
②【誤】
この写真は、湾内に立地する造船所などを間近に見た景色です。地点CやDから撮影した可能性はありますが、地点Aからの眺めではありません。
③【正】
地点Aは波止浜湾の北西の入り口付近に位置し、矢印は南東方向を向いています。この方向には、湾をまたいで架かる来島海峡第三大橋が見えるはずです。写真③には大きな吊り橋がはっきりと写っており、この位置関係と合致します。したがって、これが地点Aから撮影した写真です。
④【誤】
この写真は、対岸に大きな船と造船所のドックが見える景色です。地点Dから西方向を撮影した写真と考えられ、地点Aからの眺めではありません。
問2:正解⑥
<問題要旨>
本州四国連絡橋の開通が、四国の各県への交通手段(バスと旅客船)に与えた影響を統計データから読み取り、県名を特定する問題です。各連絡橋がどの県と結ばれているかという地理的知識と、交通網の変化が人々の移動手段に与える影響を論理的に推論する力が必要です。
<選択肢>
①【誤】
Fを高知県、Gを徳島県、Hを愛媛県とする組み合わせですが、GとHの判断が誤りです。
②【誤】
Fを高知県、Gを愛媛県とする判断は正しいですが、Hを徳島県ではなく愛媛県と重複させているため誤りです。
③【誤】
Fを徳島県、Gを愛媛県、Hを高知県とする組み合わせですが、FとHの判断が誤りです。
④【誤】
Fを徳島県、Gを高知県、Hを愛媛県とする組み合わせですが、全ての判断が誤りです。
⑤【誤】
Fを高知県とする判断は正しいですが、Gを徳島県、Hを愛媛県としている点が誤りです。
⑥【正】
Gは1995年時点で旅客船の利用者が5,130人と圧倒的に多く、しまなみ海道開通(1999年)以前に広島との間に多数の航路があった愛媛県の特徴と合致します。Hは1995年の旅客船利用者が2,484人と多く、明石海峡大橋開通(1998年)以前に関西圏との航路が中心だった徳島県の特徴と合致します。開通後、両県とも旅客船が激減しバスが大幅に増加しています。Fは、G、Hに比べて1995年時点の旅客船・バスの利用者数が少なく、本州と直接結ばれていない高知県と判断できます。したがって、Fが高知県、Gが愛媛県、Hが徳島県の組み合わせが正しく、この選択肢が正解です。
問3:正解⑤
<問題要旨>
愛媛県内の市町村別の主題図から、人口密度との比較を通じて、J、K、Lがそれぞれどの統計指標(1k㎡当たり事業所数、第二次産業就業者割合、1人当たり農業産出額)を示しているかを判断する問題です。各産業の立地特性に関する知識が求められます。
<選択肢>
①【誤】
J、K、Lすべての指標の判断が誤りです。
②【誤】
Jを事業所数、Lを農業産出額と判断している点は正しいですが、Kを第二次産業就業者割合と判断できていないため誤りです。
③【誤】
Jを事業所数と判断している点は正しいですが、KとLの判断が逆になっています。
④【誤】
Jを第二次産業就業者割合、Kを事業所数、Lを農業産出額としており、JとKの判断が誤りです。
⑤【正】
Jは、人口密度が高い松山市や今治市といった都市部で値が高くなっており、人口や都市機能の集積と強い相関がある「1k㎡当たり事業所数」と判断できます。Kは、新居浜市や四国中央市など、瀬戸内海の沿岸部に広がる工業地帯で値が高く、「第二次産業就業者割合」と合致します。Lは、都市部で値が低く、みかん栽培などが盛んな県西部や南部で値が高いことから、「1人当たり農業産出額」と判断できます。したがって、この組み合わせが正解です。
⑥【誤】
Jを農業産出額、Kを事業所数、Lを第二次産業就業者割合としており、すべての判断が誤りです。
問4:正解③
<問題要旨>
今治のタオル産業に関する複数のグラフ資料を読み解き、地場産業の変化についての会話文の空欄(P、Q)に当てはまる語句を特定する問題です。資料解釈能力と、日本の産業構造の変化に関する知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
Pを「分業化」、Qを「先進国」としており、両方の判断が誤りです。
②【誤】
Qを「国内の他産地」としていますが、輸入品との競合がより大きな要因です。
③【正】
空欄Pを含む文は、1975年から1990年にかけてのタオル生産量増加の要因を問うています。左上のグラフを見ると、この時期、事業所数はほぼ横ばいであるのに対し、生産量は増加しています。これは、個々の事業所での生産性が向上したことを意味し、その要因として「ア 各事業所における生産設備の大型化」や技術革新が考えられます。
空欄Qを含む文は、1990年代半ば以降の生産量減少の要因を問うています。右下のグラフを見ると、この時期に「輸入品の割合」が急激に増加し、80%を超えています。これは、中国など人件費の安い「z 発展途上国の産地」からの輸入品との価格競争が激化したことを示しています。
したがって、Pがア、Qがzの組み合わせであるこの選択肢が正解です。
④【誤】
Qを「国内の他産地」としており、誤りです。
⑤【誤】
Pを「分業化」、Qを「先進国」としており、両方の判断が誤りです。
⑥【誤】
Pを「分業化」としており、誤りです。
第3問
問1:正解②
<問題要旨>
地図上に示された4つの地域から、文章ア(プレートの沈み込みに伴う地殻変動)と文章イ(最終氷期における氷河の影響)の両方の条件を満たす地域を選ぶ問題です。プレートテクトニクスと第四紀の氷河時代に関する知識を統合して考える必要があります。
<選択肢>
①【誤】
この地域(北米西岸)はアの条件を満たしますが、大陸氷河に広く覆われた地域ではないため、イの条件を完全には満たしません。
②【正】
この地域(南米西岸の南部)は、ナスカプレートが南米プレートに沈み込む場所にあり、海溝型巨大地震や火山活動が活発であるため、アの条件を満たします。また、南部のパタゴニア地方は、最終氷期に山岳氷河や大陸氷河に覆われ、現在も多くの氷河湖やモレーン(氷河堆積物)がみられるため、イの条件も満たします。したがって、両方の条件が当てはまるこの選択肢が正解です。
③【誤】
この地域(地中海周辺)はアの条件を満たしますが、イの条件で述べられているような広範囲な氷河地形は限定的です。
④【誤】
この地域(東南アジア島嶼部)はアの条件を満たしますが、低緯度に位置するため氷河の影響はほとんどなく、イの条件を満たしません。
問2:正解②
<問題要旨>
地図上に示された4つの火山の近年の噴火について、その影響を述べた文章の中から最も適当なものを選ぶ問題です。近年に起きた大規模な火山噴火の事例とその影響に関する具体的な知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
火山A(アイスランドの火山)の2010年の噴火で、火山灰によりヨーロッパの航空網が混乱したのは事実ですが、その期間は数週間の規模であり、「数年間にわたり」という記述が誤りです。
②【正】
火山Bは日本の南方にある海底火山「福徳岡ノ場」を指しています。2021年の噴火で噴出した大量の軽石が、海流に乗って数か月後に沖縄や日本の太平洋沿岸に漂着し、漁業や船舶の航行に深刻な影響を与えました。この記述は事実に即しており、正解です。
③【誤】
火山C(フィリピンのピナトゥボ山)の1991年の噴火は世界最大規模で、地球全体の気温を低下させる影響がありましたが、その影響が「数時間後に観測」されることはありません。気候への影響はより長期的な現象です。
④【誤】
火山D(トンガの海底火山)の2022年の噴火では、爆発により津波が発生し太平洋全域に到達しましたが、その到達時間は数時間から十数時間であり、「数週間後」ではありません。
問3:正解④
<問題要旨>
地図上の3つの都市群(F, G, H)と、3つの気候帯(カ, キ, ク)を示す降水グラフを正しく結びつける問題です。ケッペンの気候区分に関する知識と、グラフから降水パターンを読み取る能力が必要です。
<選択肢>
①【誤】
カをF、キをG、クをHとする組み合わせですが、すべて誤りです。
②【誤】
カをF、キをH、クをGとする組み合わせですが、カとクの判断が誤りです。
③【誤】
カをG、キをF、クをHとする組み合わせですが、キとクの判断が誤りです。
④【正】
まず、各都市群の気候を判断します。Fは地中海沿岸とチリ中部にあり地中海性気候(Cs)、Gは西アジアとチリ北部にあり砂漠気候(BW)、Hは日本とアルゼンチンにあり温暖湿潤気候(Cfa)です。
次にグラフを分析します。キは、2つの都市がいずれも最暖月・最寒月ともに降水量が多く、年間を通じて湿潤なH(温暖湿潤気候)に対応します。クは、2つの都市がいずれも最暖月(夏)の降水量が極めて少なく、夏に乾燥するF(地中海性気候)の特徴と一致します。
消去法により、残ったカがG(砂漠気候)に対応します。したがって、カ=G、キ=H、ク=Fの組み合わせが正しく、この選択肢が正解です。
⑤【誤】
カをH、キをF、クをGとする組み合わせですが、すべて誤りです。
⑥【誤】
カをH、キをG、クをFとする組み合わせですが、カとキの判断が誤りです。
問4:正解④
<問題要旨>
オーストラリアの1月と7月の林野火災の分布図と、それに関する文章の空欄(a、b)を埋める問題です。オーストラリアの気候(特に降水量の季節変化)と植生に関する知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
aを1月、bを湖沼の多さとする組み合わせですが、両方とも誤りです。
②【誤】
aを1月とする判断が誤りです。
③【誤】
bを湖沼の多さとする判断が誤りです。
④【正】
オーストラリア北部は熱帯気候区に属し、夏(1月頃)が雨季、冬(7月頃)が乾季となります。林野火災は空気が乾燥する時期に発生しやすいため、火災が北部に集中している図Kは、北部の乾季である7月を示していると判断できます。したがって、aには「7月」が入ります。
オーストラリアの内陸部は広大な砂漠やステップ(半乾燥草原)が広がっており、植生が非常に乏しいです。林野火災が発生するには燃えるべき樹木や草が必要ですが、内陸部ではその燃料自体が少ないため、火災の発生が少なくなります。したがって、bには「樹木の乏しさ」が入ります。
この組み合わせである④が正解です。
問5:正解⑤
<問題要旨>
3つの時系列グラフ(サ~ス)が、「北極の海氷面積」「東京の気温」「ハワイの二酸化炭素濃度」のいずれかを示しているかを特定する問題です。それぞれの指標が持つ季節変動と長期的傾向の特徴を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
シを東京の気温、スを二酸化炭素濃度としており、誤りです。
②【誤】
シを東京の気温、スを北極の海氷面積としており、誤りです。
③【誤】
サを東京の気温、スを二酸化炭素濃度としており、誤りです。
④【誤】
サを二酸化炭素濃度、シを東京の気温としており、誤りです。
⑤【正】
シのグラフは、規則的な季節変動を繰り返しながら、全体として一貫して右肩上がりの強い上昇傾向を示しています。これは、人間活動の影響で増加し続ける「ハワイの二酸化炭素濃度」(キーリング曲線)の典型的な特徴です。
サのグラフは、夏に最小、冬に最大となる大きな季節変動が見られます。また、長期的に見ると、最大値・最小値ともに少しずつ減少する傾向にあり、地球温暖化による「北極の海氷面積」の減少を示していると判断できます。
スのグラフは、夏に高く冬に低いという顕著な季節変動が中心で、他の2つに比べて長期的な傾向が明確ではありません。これは「東京の気温」の変動パターンに対応します。
したがって、サが海氷面積、シが二酸化炭素濃度、スが気温の組み合わせであるこの選択肢が正解です。
⑥【誤】
サを気温、シを海氷面積としており、誤りです。
問6:正解④
<問題要旨>
丘陵地を宅地開発した前後の地形図を比較し、造成された土地の種類(切土地・盛土地)と、地震時に災害リスクが高まる土地を判断する問題です。造成地の種類と防災に関する知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
Xを切土地、タを切土地とする組み合わせです。タの判断が誤りです。
②【誤】
Xを切土地、タを盛土地とする組み合わせです。Xの判断が本問の正解とは異なります。
③【誤】
Xを盛土地、タを切土地とする組み合わせです。タの判断が誤りです。
④【正】
まず、空欄タについて考えます。大規模な地震が発生した際に揺れが大きくなったり、地盤が崩れたりする危険性が高いのは、もとの地盤が固い切土地ではなく、土を盛って造成した軟弱な地盤である「盛土地」です。したがって、タには「盛土地」が入ります。
次に、凡例Xがどちらか判断します。本問ではXが盛土地とされています。開発前の地形図(左)で谷だった部分(標高が低い)を埋め立てて造成した土地が盛土地にあたります。
したがって、Xが盛土地、タが盛土地となるこの選択肢が正解となります。
第4問
問1:正解②
<問題要旨>
農業の生産性(土地生産性と労働生産性)を示したグラフから、3つの国群(A, B, C)と、それぞれの農業の特徴を述べた文章(ア, イ, ウ)を正しく結びつける問題です。世界の農業地域とその特徴に関する総合的な理解が求められます。
<選択肢>
①【誤】
BとCに対応する文章の判断が逆になっています。
②【正】
Aは、農民1人当たり生産額(労働生産性)が極めて高く、広大な土地で機械化を進めるアメリカ・カナダの企業的農業(ア)と合致します。
Cは、1人当たり生産額(労働生産性)は低いものの、耕地1ha当たり生産額(土地生産性)は比較的高く、多くの労働力を投入するスリランカ・フィリピンの集約的稲作農業(イ)に対応します。
Bは、労働生産性・土地生産性ともに中程度で、集約的な混合農業が行われるドイツ・フランス(ウ)と判断できます。
したがって、Aがア、Bがウ、Cがイの組み合わせであるこの選択肢が正解です。
③【誤】
AとBに対応する文章の判断が誤りです。
④【誤】
AとCに対応する文章の判断が誤りです。
⑤【誤】
BとCに対応する文章の判断が逆になっています。
⑥【誤】
AとCに対応する文章の判断が誤りです。
問2:正解⑥
<問題要旨>
3か国(アメリカ合衆国、ナイジェリア、フランス)における2種類の穀物(トウモロコシ、麦類)の用途別消費割合のグラフから、穀物名と国名を特定する問題です。各国の農業や食文化、産業に関する知識が必要です。
<選択肢>
①【誤】
麦類をE、アメリカ合衆国をカとしていますが、両方の判断が異なります。
②【誤】
麦類をE、アメリカ合衆国をキとしていますが、両方の判断が異なります。
③【誤】
麦類をEとしており、穀物の判断が異なります。
④【誤】
アメリカ合衆国をカとしており、国の判断が異なります。
⑤【誤】
アメリカ合衆国をキとしており、国の判断が異なります。
⑥【正】
まず、穀物EとFを特定します。グラフEでは「燃料用・その他」の項目がありますが、グラフFにはありません 。バイオエタノールの原料として大規模に利用されるのはトウモロコシであるため、
Eがトウモロコシ、Fが麦類と判断できます。
次に、国名を特定します。
キの国では、トウモロコシ(E)と麦類(F)のどちらも「飼料用」の割合が極めて高いです 。これは家畜の飼育が盛んな混合農業の特徴であり、
フランスに該当します。
クの国は、トウモロコシ(E)・麦類(F)ともに「食用」の割合が高いです 。これは、世界有数の農業大国であり国内消費量も多い
アメリカ合衆国に該当します。
消去法により、カがナイジェリアとなります。
問題では「麦類」と「アメリカ合衆国」の正しい組合せを問われています。したがって、麦類がF、アメリカ合衆国がクとなる、この選択肢が正解です。
問3:正解⑥
<問題要旨>
世界の森林資源に関する3つの指標(伐採量、輸出量、輸入量)について、上位5か国を示した表から、指標名(サ、シ、ス)を特定する問題です。各国の経済規模や森林資源の賦存量、木材貿易における役割を考える必要があります。
<選択肢>
①【誤】
サを伐採量、シを輸出量、スを輸入量としていますが、サとスの判断が誤りです。
②【誤】
サを伐採量、スを輸出量としていますが、すべての判断が誤りです。
③【誤】
サを輸出量、シを伐採量、スを輸入量としていますが、サとシの判断が誤りです。
④【誤】
サを輸出量、スを伐採量としていますが、すべての判断が誤りです。
⑤【誤】
サを輸入量、シを伐採量、スを輸出量としていますが、シとスの判断が誤りです。
⑥【正】
サは、1位が中国、2位がアメリカ合衆国と、経済規模が大きく木材需要の多い国が上位に来ています。これは木材の「輸入量」のランキングと判断できます。
シは、1位がロシア、2位がカナダと、広大な森林面積を持つ国が上位を占めています。これは木材の「輸出量」に対応します。
スは、インド、中国、ブラジル、アメリカ、ロシアといった、人口が多く国土の広い国々が上位に来ています。伐採量には産業用材だけでなく燃料用の薪炭材も含まれるため、発展途上国も上位に入ります。これは「伐採量」と判断できます。
したがって、サが輸入量、シが輸出量、スが伐採量の組み合わせであるこの選択肢が正解です。
問4:正解④
<問題要旨>
4か国の外国からの直接投資受け入れ額と国外出稼ぎ者からの送金額を示したグラフから、指標名(タ、チ)と国名(J、K)を特定する問題です。各国の経済的な特徴や、国際的な人の移動に関する知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
送金額をタ、フィリピンをJとしており、両方の判断が誤りです。
②【誤】
送金額をタとしており、誤りです。
③【誤】
フィリピンをJとしており、誤りです。
④【正】
まず、指標タとチを判断します。タは中国の額が圧倒的に大きく、経済規模に比例する傾向があります。これは「外国からの直接投資の受け入れ額」と判断できます。一方、チはインドの額が最も大きく、人口が多く国外で働く労働者が多い国の特徴を反映しており、「国外出稼ぎ者からの送金額」と判断できます。
次に、国JとKを判断します。フィリピンは「OFW」と呼ばれる海外出稼ぎ労働者が非常に多く、国への送金額が多いことで知られています。グラフでチ(送金額)が多いのはKであるため、Kがフィリピン、Jがロシアと判断できます。
問題では「国外出稼ぎ者からの送金額」と「フィリピン」の組み合わせを問うているので、チとKの組み合わせが正解となります。
問5:正解⑥
<問題要旨>
3つのサービス産業(インターネット関連サービス業、研究開発事業、社会福祉・介護事業)の従業者数が、日本の都道府県別にどのように分布しているかを示す地図から、業種名(マ、ミ、ム)を特定する問題です。各産業の立地特性を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
インターネット関連をマ、社会福祉・介護をムとしており、判断が異なります。
②【誤】
インターネット関連をマ、研究開発をム、社会福祉・介護をミとしており、すべての判断が異なります。
③【誤】
インターネット関連をミ、研究開発をマ、社会福祉・介護をムとしており、すべての判断が異なります。
④【誤】
インターネット関連をム、研究開発をマ、社会福祉・介護をミとしており、研究開発と社会福祉・介護の判断が異なります。
⑤【誤】
研究開発をマ、社会福祉・介護をミとしており、研究開発と社会福祉・介護の判断が異なります。
⑥【正】
まず、各地図の分布特性を分析します。
ムの地図は、従業者数の割合が東京都に極端に集中していることを示しています。他の道府県の円が非常に小さいのに比べ、東京の円だけが突出して大きいです。このような首都への一極集中が最も顕著なのは、情報通信技術や関連企業の本社機能が集積する「インターネット関連サービス業」です。
マの地図は、三大都市圏(東京、大阪、愛知)で割合が高いものの、それ以外の地方の県においても人口規模に応じて比較的均等に分布しています。これは、地域住民の生活に密着し、特に高齢化に伴い全国どの地域でも必要とされる「社会福祉・介護事業」の分布パターンと合致します。
ミの地図は、東京圏に集積が見られる一方で、筑波研究学園都市を擁する茨城県や、大企業の工場・研究所が集まる愛知県、大阪府など、特定の研究開発拠点にも顕著な集積が見られます。これは、大学や公的研究機関、企業の開発部門が立地する場所に集まる「研究開発事業」の特徴と一致します。
以上のことから、マが社会福祉・介護事業、ミが研究開発事業、ムがインターネット関連サービス業と判断できます。この組み合わせと一致するこの選択肢が正解です。
問6:正解⑤
<問題要旨>
日本の高速道路沿線の都府県における、工業出荷額第1位の業種の時代的変遷を示した表から、凡例P、Q、Rがどの業種(食料品、電気機械、輸送機械)に対応するかを特定する問題です。日本の工業化の歴史と、各工業の立地特性に関する知識が必要です。
<選択肢>
①【誤】
Pを食料品、Qを電気機械、Rを輸送機械としており、QとRの判断が逆になっています。
②【誤】
Pを食料品、Qを輸送機械、Rを電気機械としており、PとRの判断が逆になっています。
③【誤】
Pを電気機械、Qを食料品、Rを輸送機械としており、PとQの判断が誤りです。
④【誤】
Pを輸送機械、Qを電気機械、Rを食料品としており、すべての判断が誤りです。
⑤【正】
Qは、愛知県で一貫して第1位を占めています。愛知県は日本最大の自動車産業の集積地であることから、Qは「輸送機械」と判断できます。
Rは、東北自動車道が開通した1980年代以降、東北地方の各県で第1位になっています。これは、高速交通網の整備に伴い、IC工場などの「電気機械」工業が地方に進出したことを示しています。
Pは、特定の地域への集中度が低く、工業化の初期段階である1950年代から多くの県でみられます。これは、原料や市場が全国に分散している「食料品」工業の特徴と合致します。
したがって、Pが食料品、Qが輸送機械、Rが電気機械の組み合わせであるこの選択肢が正解です。
⑥【誤】
Pを輸送機械、Rを食料品としており、PとRの判断が誤りです。
第5問
問1:正解②
<問題要旨>
3か国(日本、アメリカ、インドネシア)の都市圏人口の規模別順位を示したグラフから、国名(A, B, C)を特定する問題です。各国の都市システムの特色(プライメイトシティ型か、ランクサイズ型か)に関する知識が問われます。
<選択-肢>
①【誤】
Bをアメリカ、Cを日本としており、誤りです。
②【正】
Aは、第1位都市(ジャカルタ)への人口集中が極端に著しく、第2位都市との差が非常に大きい「プライメイトシティ(首位都市)」の典型例です。これは発展途上国によく見られるパターンであり、インドネシアに対応します。
Cは、第1位都市(ニューヨーク)の人口割合が比較的低く、第2位以下の都市との規模の差がなだらかです。これは、国土が広く、機能の異なる大都市が各地に分散しているアメリカ合衆国の特徴(ランクサイズ・ルールに近い分布)を示しています。
Bは、AとCの中間的なパターンで、第1位都市(東京)への集中が見られるものの、Aほど極端ではなく、日本に対応します。
したがって、Aがインドネシア、Bが日本、Cがアメリカ合衆国の組み合わせであるこの選択肢が正解です。
③【誤】
Aを日本、Bをアメリカとしており、誤りです。
④【誤】
Bをアメリカ、Cを日本としており、誤りです。
⑤【誤】
Aを日本、Cをアメリカとしており、誤りです。
⑥【誤】
BとCの判断が逆になっています。
問2:正解③
<問題要旨>
日本の主要都市における大企業の本社数と支所数を示した表から、横浜市に該当するものを選ぶ問題です。各都市が持つ経済的な機能(中枢管理機能)の集積度合いに関する知識が必要です。
<選択肢>
①【誤】
本社数、支所数ともに東京に次いで多く、西日本の中心である大阪市に該当します。
②【誤】
本社数、支所数ともに大阪市に次いで多く、中部地方の中心である名古屋市に該当します。
③【正】
この選択肢が横浜市に該当します。
④【誤】
本社数、支所数から、九州地方の中心都市である福岡市に該当すると考えられます。
問3:正解④
<問題要旨>
東京大都市圏における3つの住宅関連指標(共同住宅、持ち家戸建て、単身世帯)の分布図から、指標名(E, F, G)を特定する問題です。都心と郊外における土地利用や居住形態の違いを理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
Eを共同住宅、Fを持ち家戸建て、Gを単身世帯としていますが、EとGの判断が逆になっています。
②【誤】
Eを共同住宅、Gを持ち家戸建て、Fを単身世帯としており、FとGの判断が誤りです。
③【誤】
Eを単身世帯、Fを共同住宅としており、EとFの判断が誤りです。
④【正】
Fは、都心部で割合が低く、周辺の郊外で高い分布を示しています。これは、地価が比較的安く、広い敷地を確保しやすい郊外に多い「持ち家戸建て住宅」の割合と判断できます。
Gは、都心部(特に中心区やその周辺)で割合が極めて高くなっています。これは、交通の便が良く、大学や企業が集まる都心に住む傾向が強い「単身世帯」の割合を示しています。
Eは、Gと同様に都心部で割合が高いですが、Gほど中心部への集中は顕著ではなく、周辺の市区にも広く分布しています。これは「共同住宅」(マンション・アパート)の割合と判断できます。
したがって、Eが共同住宅、Fが持ち家戸建て住宅、Gが単身世帯の組み合わせであるこの選択肢が正解です。
⑤【誤】
Eを持ち家戸建て、Gを共同住宅としており、すべての判断が誤りです。
⑥【誤】
Fを単身世帯、Gを共同住宅としており、FとGの判断が誤りです。
問4:正解②
<問題要旨>
長野県の人口動態(社会増減と自然増減)の推移を示したグラフとその背景を述べた文章から、誤りを含むものを選ぶ問題です。グラフから人口動態の長期的な変化を正確に読み取り、その時代の社会経済的な背景と結びつけて考察する力が求められます。
<選択肢>
①【正】
1960年代後半は、高度経済成長期にあたり、地方から大都市圏へ若年層が「集団就職」などで大量に流出しました。グラフでも社会増減(白棒)が大きなマイナスを示しており、この記述は正しいです。
②【誤】
「1970年代後半には…長野県の総人口は横ばい傾向となった」とありますが、グラフを見るとこの時期は自然増(黒棒)のプラス幅が社会減(白棒)のマイナス幅を上回っています。つまり、人口増減の合計はプラスであり、総人口は「微増」を続けていました。「横ばい」という表現は不正確であり、この記述が誤りです。
③【正】
1980年代から1990年代にかけて、大都市からのUターン現象や企業の工場誘致などにより、地方への人口還流がみられました。グラフでも社会増減がプラスに転じる期間があり、この記述は正しいです。
④【正】
2000年代以降、少子高齢化の進展により全国的に自然減が続き、長野県も例外ではありません。グラフでも社会減と自然減の「ダブルパンチ」で人口が減少しており、これにより地域によっては過疎化が進行したと考えられるため、この記述は正しいです。
問5:正解④
<問題要旨>
フランスとドイツの都市システム(中枢管理機能の分布)を比較した地図と、それに関する会話文から、誤りを含むものを選ぶ問題です。両国の国土構造や歴史的背景の違いを理解し、都市システムの長所・短所を考察する力が問われます。
<選択肢>
①【正】
フランスの地図を見ると、大企業の本社(星印)や主な中央官庁(黒い四角)は、首都パリに極端に集中しており、他の都市にはほとんど立地していません。この記述は図から読み取れる事実であり、正しいです。
②【正】
ドイツの地図を見ると、大企業の本社(星印)は首都ベルリンだけでなく、西部のルール地方や南部のミュンヘン、フランクフルト、シュツットガルトなど、国内の複数の都市に分散して立地しています。この記述は図から読み取れる事実であり、正しいです。
③【正】
ドイツのように政治や経済の中枢機能が国内の複数の都市に分散している都市システムは、一つの都市(特に首都)が災害などで機能不全に陥った場合でも、国全体への影響を小さくできるという利点(リスク分散効果)があります。この記述は正しいです。
④【誤】
フランスのような首都一極集中型の都市システムは、首都に人口や機能が過度に集中するため、地価の高騰、交通渋滞、住宅問題、環境悪化といった様々な都市問題が「発生・深刻化」しやすくなります。問題が「緩和されやすい」という記述は、一極集中のデメリットと完全に矛盾しており、誤りです。
第6問
問1:正解④
<問題要旨>
北アメリカ大陸の3つの断面(ア、イ、ウ)における年降水量の変化を、3つのグラフ(A、B、C)と正しく結びつける問題です。山脈と風の関係(地形性降雨、雨蔭効果)など、降水量分布のメカニズムを理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
Aをア、Bをイ、Cをウとする組み合わせですが、AとBの判断が誤りです。
②【誤】
Aをア、Bをウ、Cをイとする組み合わせですが、すべての判断が誤りです。
③【誤】
Aをイ、Bをア、Cをウとする組み合わせですが、AとBの判断が本問の正解とは異なります。
④【正】
Bは、西側(左端)で降水量が多く、東へ向かうにつれて減少するパターンです。これは、太平洋からの湿った空気が西海岸の山脈にぶつかって多量の雨を降らせ、内陸では雨蔭効果で乾燥する断面アの降水パターンに対応します。
Cは、西側(左端)の降水量が極めて多く、東へ急激に減少しています。これは、メキシコ湾からの暖かく湿った空気が流れ込む沿岸部で多雨となり、内陸へ向かうほど乾燥する断面ウのパターンです。
Aは、比較的降水量が少なく、なだらかな変化を示しています。これは、大陸東部を横切る断面イのパターンに対応します。
したがって、Aがウ、Bがア、Cがイの組み合わせであるこの選択肢が正解です。
問2:正解②
<問題要旨>
アメリカ合衆国とカナダまたはメキシコとの国境周辺の景観写真について、その説明文として適当でないものを選ぶ問題です。国境の種類(自然的国境・人為的国境)や、国境が持つ意味合い(交流の場、障壁)に関する知識が問われます。
<選択肢>
①【正】
写真カはナイアガラの滝で、アメリカとカナダの国境に位置します。世界的な観光地であり、国境を越えて多くの観光客が訪れます。この記述は正しいです。
②【誤】
写真キは、森林を直線的に伐採して国境線を示したものです。これは、緯度線(北緯49度線)に沿って定められた「人為的国境」の典型例です。山脈の尾根(分水嶺)など、自然の地形を利用した「自然的国境」ではないため、この記述は誤りです。
③【正】
写真クは、アメリカとメキシコの国境地帯で、メキシコ側に建物が密集している様子です。アメリカでの就労機会を求めたり、国境に立地するマキラドーラ(保税加工区)で働いたりするために多くの人々が集住しています。この記述は正しいです。
④【正】
写真ケは、アメリカとメキシコの国境に建設された壁(フェンス)です。不法入国や密輸を防ぐ目的で、アメリカ合衆国によって建設が進められました。この記述は正しいです。
問3:正解⑥
<問題要旨>
中央アメリカの国々における3つの指標(農地面積の割合、第三次産業の割合、アフリカ系の割合)の分布図から、指標名(サ、シ、ス)を特定する問題です。この地域の多様な自然環境、歴史(植民地時代)、経済構造を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
サを農地割合、シを三次産業割合、スをアフリカ系割合としていますが、サとスの判断が誤りです。
②【誤】
サを農地割合、スを三次産業割合としていますが、すべての判断が誤りです。
③【誤】
サを三次産業割合、シを農地割合、スをアフリカ系割合としていますが、サとシの判断が誤りです。
④【誤】
サを三次産業割合、スを農地割合としていますが、すべての判断が誤りです。
⑤【誤】
サをアフリカ系割合、シを農地割合、スを三次産業割合としていますが、シとスの判断が逆になっています。
⑥【正】
サは、ジャマイカ、ハイチ、バハマといったカリブ海の島嶼国で割合が極めて高くなっています。これらの地域は、植民地時代にアフリカから多くの労働力が奴隷として連れてこられた歴史があり、「人種・民族構成に占めるアフリカ系の割合」を示していると判断できます。
シは、パナマ(パナマ運河)、バハマ(観光・金融)、コスタリカ(エコツーリズム)で割合が高くなっています。これは、交通の要衝であったり、観光業や金融業が発達していたりすることを示しており、「GDPに占める第三次産業の割合」に対応します。
スは、国土面積に比して農業が盛んな国で割合が高くなります。エルサルバドルやキューバ、ドミニカ共和国などで高い値を示しており、「国土に占める農地面積の割合」と判断できます。
したがって、サがアフリカ系、シが三次産業、スが農地面積の組み合わせであるこの選択肢が正解です。
問4:正解④
<問題要旨>
長野県の人口動態(社会増減と自然増減)の推移を示したグラフと、その背景を述べた文章から、誤りを含むものを一つ選ぶ問題です。グラフから人口動態の長期的な変化を正確に読み取り、その時代の社会経済的な背景と結びつけて考察する力が求められます。
<選択肢>
①【正】
「1960年代後半は、社会増減の減少幅が大きい」との記述は、グラフで社会増減を示す白棒が大きなマイナス値を示していることから正しいです 。その背景として、高度経済成長期に若年層が大都市圏へ流出したことは歴史的事実です 。
②【正】
「1970年代後半には、社会増減の減少幅が縮小に向かい」という記述は、白棒のマイナス幅が1970年代前半をピークに小さくなっていることから正しいです 。また、その結果、自然増(黒棒)と社会減(白棒)が相殺され、全体の人口増減がゼロに近づいたため、「総人口は横ばい傾向となった」という記述もグラフの示す状況と合致しています 。
③【正】
「1980年代から1990年代には、社会増減が減少から増加に転じる期間もみられた」との記述は、グラフで白棒がゼロのラインを越えてプラスになっている期間があることから確認でき、正しいです 。
④【誤】
この選択肢の後半「これによって、過疎化が著しく進行した場所もあると考えられる」という部分は、人口減少の結果として妥当です。しかし、前半の「2000年代以降は、社会減が続くとともに、
それを上回る数の自然減が生じた」という記述に誤りがあります 。グラフを詳しく見ると、2000年代の前半(およそ2000年~2005年)においては、自然減(黒棒のマイナス幅)よりも社会減(白棒のマイナス幅)の方が大きくなっています 。自然減が社会減を上回るようになるのは2010年頃からです。したがって、「2000年代以降」全般の傾向として「社会減を上回る自然減が生じた」と述べているこの部分は、グラフを正確に読み取っておらず、明確に誤りです。
問5:正解③
<問題要旨>
3か国(カナダ、キューバ、メキシコ)の国際観光に関する2つの指標の表から、国名(マ、ミ、ム)を特定する問題です。各国の経済水準、政治体制、地理的条件がインバウンド(外国人旅行者受入)およびアウトバウンド(自国民の海外旅行)にどう影響するかを考察する力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
マをカナダ、ミをキューバ、ムをメキシコとしており、マとミの判断が誤りです。
②【誤】
マをカナダ、ミをメキシコとしており、すべての判断が誤りです。
③【正】
ミは、「アウトバウンド旅行者数/インバウンド旅行者数」の比率が120.2%と3か国で唯一100%を超えており、海外へ出ていく国民が多い経済的に豊かな国であることを示しています。これはカナダに該当します。
マは、ヨーロッパからの旅行者の割合が29.5%と最も高く、一方でアウト/イン比率は15.2%と極端に低いです。これは、国民の海外旅行が容易ではない一方、ヨーロッパからの観光客に人気があるキューバの特徴と合致します。
ムは、ヨーロッパからの旅行者の割合が4.7%と極めて低いです。これは、インバウンド旅行者の大半を隣国のアメリカからの旅行者が占めるメキシコの特徴です。
したがって、マがキューバ、ミがカナダ、ムがメキシコの組み合わせであるこの選択肢が正解です。
④【誤】
マをメキシコ、ミをキューバとしており、マとミの判断が誤りです。
⑤【誤】
マをキューバ、ミをメキシコとしており、ミとムの判断が誤りです。
⑥【誤】
マをメキシコ、ミをカナダ、ムをキューバとしており、すべての判断が誤りです。