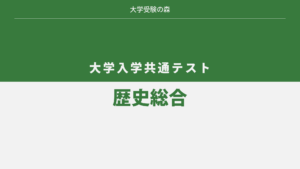解答
解説
第1問
問1:正解③
<問題要旨>
19世紀の産業革命期における工場労働者の時間意識や労働慣行、および産業革命が社会に与えた影響についての理解を問う問題です。資料(メモ1)から当時の労働者と資本家の関係性を読み解き、産業革命に関する基本的な歴史知識と照らし合わせる必要があります。
<選択肢>
①【誤】
文「あ」が誤りです。メモ1には、「聖月曜日」の習慣を持つ労働者は「月曜日の始業時間を守らず、欠勤する者もいた」とあります。これは、労働時間を厳守させようとする工場主(資本家)が求める姿勢とは正反対のものです。したがって、両者の姿勢が「合致する」という記述は誤りです。
②【誤】
文「あ」が誤りです。上記①の解説の通り、「聖月曜日」の習慣は資本家が求める労働規律とは相容れないものでした。
③【正】
文「い」と「う」がともに正しい記述です。
文「い」:メモ1には、「聖月曜日」の習慣は労働者側の「仕事の手順や労働時間は自分で決めるとい う自律心の表れ」とあります。これは、工場主(資本家)が一方的に定めた労働時間や規律とは異なる、労働者独自の価値観や慣行があったことを示しており、正しい記述です。
文「う」:産業革命期には、石炭を燃料とする蒸気機関が工場で広く使われました。その結果、工場から出るばい煙による大気汚染や、排水による河川の汚染などが深刻な社会問題となりました。これは産業革命に関する基本的な史実であり、正しい記述です。
④【誤】
文「え」が誤りです。イギリスの産業革命は、まず綿織物業などの軽工業で技術革新が進み、それが製鉄業や石炭業といった重化学工業へと波及していきました。「重化学工業から始まり、綿織物業に波及した」という記述は、展開の順序が逆であるため誤りです。
問2:正解②
<問題要旨>
第二次世界大戦後の日本における女性の働き方の変化を示すグラフを正確に読み解く問題です。高度経済成長期やバブル景気といった特定の時代と、グラフに示された長時間・短時間雇用者の割合の推移を正しく関連づける能力が問われます。
<選択肢>
①【誤】
文「い」が誤りです。バブル景気は一般に1986年頃から始まります。グラフで1986年時点の短時間雇用者((b)の破線)の割合を見ると25%程度です。「3人に1人」は約33.3%を指しますが、グラフがその水準に達するのは1990年以降です。したがって、バブル景気が始まった頃に「既に」3人に1人が短時間雇用者だったという記述は誤りです。
②【正】
文「あ」は正しく、文「い」は誤りです。
文「あ」:日本の高度経済成長期は一般に1950年代半ばから1970年代初頭までを指します。グラフを見ると、長時間雇用者((a)の実線)と短時間雇用者((b)の破線)の割合が交差して逆転するのは1965年から1970年の間です。これは高度経済成長期の期間内に収まるため、この記述はグラフから読み取れる事実として正しいです。
文「い」:上記①の解説の通り、バブル景気が始まった1986年頃には、短時間雇用者の割合はまだ3人に1人(約33.3%)には達していません。
③【誤】
文「あ」が誤りです。上記②の解説の通り、グラフの逆転は高度経済成長期に起こっており、「あ」の記述は正しいものです。したがって、これを誤りとするこの選択肢は不正解です。
④【誤】
文「あ」と「い」の両方が誤りであるとしていますが、上記②の解説の通り、「あ」は正しい記述です。したがって、この選択肢は不正解です。
問3:正解③
<問題要旨>
明治政府が太陽暦を導入した理由や歴史的背景について、与えられた資料と年表から読み解く問題です。資料中のキーワードを手がかりに、当時の日本の国際的立場や政策の方向性を理解することが求められます。
<選択肢>
①【誤】
尊王攘夷は、天皇を尊び外国勢力を打ち払おうとする幕末の思想です。明治政府は開国和親を国是とし、欧米諸国の制度・文物を積極的に取り入れました。資料にある「各国との交際」という言葉からも、攘夷思想とは正反対の方向性であることがわかり、この選択肢は誤りです。
②【誤】
自由民権運動は、国会開設などを求めた国民の政治運動で、1870年代後半から活発化しました。太陽暦導入は1873年であり、自由民権運動が高揚する前の出来事です。また、太陽暦導入は民権運動の要求項目ではなく、政府主導の欧化政策の一環であったため、この選択肢は誤りです。
③【正】
資料に「太陽暦を各国が普通に使用しているのに、日本のみが太陰暦を用いているのは不便ではないだろうか」とある通り、欧米諸国との外交や貿易を行う上での不便さを解消することが、太陽暦導入の大きな理由でした。これは、暦という基本的な制度を西洋諸国に合わせ、国際社会の一員となろうとする明治政府の方針を反映しており、正しい記述です。
④【誤】
年表を見ると、朝鮮が太陽暦に切り替えたのは1896年、中国は1912年です。日本が導入した1873年の時点では、両国ともまだ太陰暦を用いていました。したがって、中国・朝鮮に合わせたという記述は時系列が合わず、誤りです。
問4:正解①
<問題要旨>
年表にある「1895年に、日本で、新たに獲得した領域を通る標準時子午線が追加された」という記述について、その背景となる歴史的事実(領土の拡大)を特定し、地図上で追加された子午線の位置を答える問題です。1895年という年号が重要なヒントになります。
<選択肢>
①【正】
1895年は日清戦争が終結し、下関条約が結ばれた年です。この条約で日本は台湾などを清から獲得しました。日本の本土は東経135度の子午線(図のb)を標準時としていますが、新たに領土となった台湾はそれよりも西に位置します。そのため、台湾の時刻に合わせた新たな標準時(西部標準時)として、台湾を通る東経120度の子午線が設定されました。図のaは、この東経120度線に相当します。
②【誤】
図のbは、日本の本土の標準時である東経135度子午線です。問題は「追加された」子午線について問うているため、これは該当しません。
③【誤】
図のcは、小笠原諸島などを通る経線で、日本の本土より東に位置します。1895年時点の領土拡大とは関係がありません。
④【誤】
図のdは、日本の本土よりさらに東に位置する経線です。1895年時点の領土拡大とは関係がありません。
問5:正解④
<問題要旨>
1937年に日本の標準時が統一された背景にある対外的な危機意識について、1930年代の国際情勢を踏まえて空欄を補充する問題です。ワシントン海軍軍縮条約の失効と、ソ連の五か年計画に関する知識が問われています。
<選択肢>
①【誤】
空欄ア・イともに誤りです。ブレスト=リトフスク条約は第一次世界大戦中の1918年の出来事です。また、1930年代のソ連の指導者はスターリンであり、レーニン(1924年死去)ではありません。
②【誤】
空欄アが誤りです。ブレスト=リトフスク条約は1918年の出来事であり、1930年代の軍備拡張競争とは時代が異なります。
③【誤】
空欄イが誤りです。1930年代のソ連はスターリンの独裁体制下にあり、レーニンの独裁体制が確立した時期ではありません。
④【正】
空欄ア・イともに正しい記述が入ります。
空欄ア:ワシントン海軍軍縮条約は1936年末に失効し、列強間の軍艦建造競争(軍備拡張競争)が再燃する恐れが高まりました。これは1930年代の対外的危機意識の背景として適切です。
空欄イ:1928年から始まったソ連の五か年計画は、重工業化を強力に推し進めるものでした。これにより国力・軍事力を増強したソ連は、満洲国を建国した日本にとって大きな脅威と認識されました。これも当時の危機意識の背景として適切です。
問6:正解①
<問題要旨>
イギリス本国と、かつてその植民地であった香港における、第二次世界大戦の対日戦勝をめぐる記念日に関するパネルを読み解き、その内容や歴史的背景について正しく述べている文を選ぶ問題です。イギリス連邦の性質や戦後の賠償問題、香港史に関する知識が求められます。
<選択肢>
①【正】
パネルには、イギリス国王が「イギリス帝国及びイギリス連邦の全ての市民に対して」ラジオ演説を行ったとあります。カナダやオーストラリアは当時からイギリス連邦の主要な構成国であったため、これらの国でも国王の演説が放送されたと考えるのが最も自然であり、妥当な推論です。
②【誤】
サンフランシスコ平和条約により、日本は連合国への賠償原則を定められましたが、国家としてイギリスに巨額の賠償金を支払ったという事実はありません。パネルにある元捕虜への補償問題は、国家間の賠償とは別の問題として扱われました。
③【誤】
パネルによると、イギリス本国の対日戦勝記念日は「8月15日」ですが、香港の解放記念日は「8月30日(後に8月の最終月曜日)」と定められており、日付が異なります。
④【誤】
袁世凱は中華民国の初代大総統で、1916年に亡くなっています。イギリス軍が香港に再上陸した1945年とは時代が全く異なります。
問7:正解④
<問題要旨>
連合国間で対日戦勝記念日が異なることを示す表と、1947年の朝鮮語の新聞記事の内容を記したメモを結びつけ、記事が発行された地域を特定する問題です。第二次世界大戦直後の朝鮮半島が、アメリカとソ連によって分割占領されていたという歴史的背景の理解が鍵となります。
<選択肢>
①【誤】
メモ3で祝われているのは「9月3日」であり、これは表からソ連の対日戦勝記念日であることがわかります。アメリカの記念日(9月2日)ではないため、記述の前半が誤りです。
②【誤】
上記①の解説の通り、祝われているのはアメリカではなくソ連の記念日です。
③【誤】
祝われているのがソ連の記念日であることは正しいですが、ソ連の影響下にあったのは朝鮮半島北部です。南部はアメリカの影響下にあったため、発行地域が南部であるという記述が誤りです。
④【正】
メモ3から、この記事が「9月3日」の対日戦勝記念日を祝っていることがわかります。これは表にあるソ連の記念日と一致します。第二次世界大戦後、朝鮮半島は北緯38度線を境に、北半分をソ連、南半分をアメリカが占領しました。ソ連の記念日を祝う新聞が発行されたということは、その地域がソ連の占領下にあった朝鮮半島北部であると推測するのが最も合理的です。
問8:正解②
<問題要旨>
沖縄の「慰霊の日」と「屈辱の日」という二つの記念日に関するノートを読み解き、沖縄の戦後史について正しく説明している文の組み合わせを選ぶ問題です。サンフランシスコ平和条約、アメリカによる沖縄統治、日本復帰といった出来事を正確に理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
文「う」が誤りです。ノート1には「慰霊の日」は法令で定められたとありますが、ノート2では「屈辱の日」について「法令による定めはない」と明記されています。
②【正】
文「あ」と「え」がともに正しい記述です。
文「あ」:サンフランシスコ平和条約(1952年発効)によって、沖縄はアメリカの施政権下に置かれることが決まりました。これは、第二次世界大戦終結後から続いていたアメリカによる軍事占領が、条約によって継続される形になったことを意味します。したがって、条約発効以前から沖縄がアメリカに占領されていたという記述は正しいです。
文「え」:ノート1に、「慰霊の日」は「1961年に琉球政府によって」最初に定められたとあります。沖縄が日本に復帰したのは1972年なので、「慰霊の日」は日本復帰より前に制定されていたことになり、正しい記述です。
③【誤】
文「い」と「う」が誤りです。文「い」については、「屈辱の日」という呼び方が広まった1960年代には、朝鮮戦争(1950-53年)はすでに休戦していました。文「う」については、上記①の解説の通りです。
④【誤】
文「い」が誤りです。上記③の解説の通り、朝鮮戦争と「屈辱の日」の呼称が広まった時期は一致しません。
第2問
問1:正解①
<問題要旨>
19世紀から20世紀初頭の万国博覧会に関する会話文を読み、空欄ア(岩倉使節団の目的)とイ(万博の役割)を補充する問題です。明治初期の外交史と、当時の科学技術史の知識が求められます。
<選択肢>
①【正】
空欄ア・イともに正しい内容が入ります。
ア:岩倉使節団(1871-73年派遣)の主な目的の一つは、幕末に結んだ不平等条約の改正に向けた予備交渉でした。会話文にある1873年のウィーン万博は、使節団の派遣時期と一致します。
イ:会話文に「鉄製のエッフェル塔」「きらびやかな電気館」「地下鉄」「動く歩道」といった例が挙げられている通り、当時の万博は、各国の工業力や最先端の科学技術を披露し、国威を発揚する場としての役割を持っていました。
②【誤】
空欄イが誤りです。万博は技術や物産を展示するイベントであり、「平和と安全を保障する場」という役割は、国際連盟のような国際機関が担うものです。
③【誤】
空欄アが誤りです。パリ講和会議は第一次世界大戦後の1919年の出来事であり、岩倉使節団の時代とは全く異なります。
④【誤】
空欄ア・イともに誤りです。上記②、③の解説の通りです。
問2:正解④
<問題要旨>
19世紀末の西洋人の文明観・人種観を示す資料を読み解き、その内容を正しく要約した文と、同様の思想的背景を持つ歴史的事象を組み合わせる問題です。帝国主義時代の「文明の序列」という考え方と、委任統治制度の理念を結びつけられるかがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
文「あ」が誤りです。資料1は世界を四つの階層に分け、「文明諸民族」が「後進諸民族」に干渉する権利があるとしており、諸民族を「対等な関係」とは考えていません。
②【誤】
文「あ」が誤りです。上記①の解説の通りです。
③【誤】
歴史的事象Xが誤った組み合わせです。東南アジア諸国連合(ASEAN)は、主権を持つ国家が対等な立場で地域の協力と発展を目指す組織であり、資料1のような序列的・差別的な思想とは正反対の理念に基づいています。
④【正】
内容の要約「い」と歴史的事象「Y」がともに正しい組み合わせです。
い:資料1は、世界を「西洋文明」を頂点とする四つの地域に分け、文明の度合いに応じて序列化しているため、この要約は正しいです。
Y:第一次世界大戦後、国際連盟の下で始まった委任統治は、「文明が進んだ」とされる国が「未開な」地域の統治を代行し、将来の自立に向けて「後見」を行うという理念を持っていました。これは、資料1にある「後進諸民族の教育や保護は、…文明に富んだ諸民族のなすべきこと」という思想と通底しており、適切な組み合わせです。
問3:正解②
<問題要旨>
1922年に開催された「平和記念東京博覧会」の名称の背景にある、1920年代の国際情勢について問う問題です。第一次世界大戦の反省から生まれた、国際協調や軍縮、平和希求の動き(ヴェルサイユ・ワシントン体制)を象徴する出来事を選ぶ必要があります。
<選択肢>
①【誤】
フランスなどによるルール占領(1923年)は、ドイツの賠償金不払いを理由とする実力行使であり、国際協調ではなく対立を象徴する出来事です。
②【正】
不戦条約(1928年)は、戦争を国家の政策の手段として放棄することを宣言した条約で、1920年代の平和と国際協調を求める風潮の頂点を示すものです。「平和記念」という博覧会の名称の背景として最もふさわしい出来事です。
③【誤】
ウィーン会議は、ナポレオン戦争後の処理を目的として1814-15年に開かれたもので、時代が全く異なります。
④【誤】
独ソ不可侵条約は、第二次世界大戦直前の1939年に結ばれたものであり、1920年代の国際協調とは逆行する動きです。
問4:正解⑤
<問題要旨>
20世紀前半に満洲(現在の中国東北部)で起こった三つの出来事を、年代順に正しく並べる問題です。日露戦争後から満洲事変に至るまでの重要な事件の発生年次を正確に記憶しているかが問われます。
<選択肢>
Ⅱ:旅順・大連の租借権がロシアから日本へ移ったのは、日露戦争の講和条約であるポーツマス条約(1905年)によるものです。
Ⅰ:満洲の軍閥指導者・張作霖が奉天近郊で爆殺された事件(張作霖爆殺事件)は、1928年に発生しました。
Ⅲ:鉄道爆破事件(柳条湖事件)を調査するために国際連盟の調査団(リットン調査団)が派遣されたのは、満洲事変(1931年)が起こった後の1932年のことです。
したがって、起こった順はⅡ(1905年)→Ⅰ(1928年)→Ⅲ(1932年)となります。この順に並んでいるのは⑤です。
問5:正解②
<問題要旨>
1940年に計画されていた万博の延期をめぐる、1938年時点での海外の反応を報じた新聞記事を読み解く問題です。記事の内容を正確に理解するとともに、日中戦争や第二次世界大戦の開始時期といった歴史的知識と照らし合わせる必要があります。
<選択肢>
①【誤】
文「う」が誤りです。資料2には、延期に同意する国々の意見として「各種施設が出来上がらない今のうちに延期を決定するならば」とあり、準備が完了していなかったことが読み取れます。
②【正】
文「あ」と「え」がともに正しい記述です。
あ:資料2には、延期に反対する国々が「かえって中国側の逆宣伝に利用される」と懸念していると書かれています。この記事は日中戦争(1937年勃発)の最中である1938年に書かれたものであり、戦争下での万博延期が日本の国際的評価を下げる(=不利益になる)と彼らが考えていたことがわかります。
え:資料2の冒頭に「外務省でも諸外国に対する影響を重視し、かねてより注目していた」とあり、日本政府が万博の延期が外交問題に発展することを懸念していたことが直接読み取れます。
③【誤】
文「い」と「う」が誤りです。文「い」については、資料2が書かれた1938年7月時点では、第二次世界大戦(ヨーロッパでは1939年9月開戦)はまだ始まっていません。文「う」については、上記①の解説の通りです。
④【誤】
文「い」が誤りです。上記③の解説の通り、第二次世界大戦はこの時点ではまだ開戦していません。
問6:正解①
<問題要旨>
戦後の国連加盟国数、オリンピックとアジア競技大会の参加国・地域数の推移を示すグラフを読み解き、その変化と歴史的背景を正しく結びつける問題です。「アフリカの年」やソ連解体といった、戦後の世界史の大きな変動が国際スポーツ大会に与えた影響を考察する力が問われます。
<選択肢>
①【正】
変化「あ」と要因「X」の組み合わせが正しいです。
あ:グラフを見ると、1958年から1972年にかけて国連加盟国数(折れ線)と夏季オリンピック参加国・地域数(棒グラフ全体)はともに増加傾向にあります。これはグラフから読み取れる事実です。
X:この時期の参加国増加の大きな要因として、1960年の「アフリカの年」に象徴されるアフリカ諸国の相次ぐ独立があります。独立した新しい国家が国連に加盟し、オリンピックに参加したことで、加盟国・参加国数が大きく伸びました。
②【誤】
要因Y(ソ連の解体)は1991年の出来事であり、変化「あ」が示す1958年~1972年の時期とは合いません。
③【誤】
変化「い」の記述が誤りです。1986年以降、アジア競技大会の参加国・地域数(濃い色の棒グラフ)は、減少ではなく増加しています。
④【誤】
変化「い」の記述が誤りであるため、この選択肢も不正解です。
問7:正解④
<問題要旨>
アジア競技大会やオリンピックに関するパネルの空欄を補充する問題です。空欄エでは冷戦下の第三世界の動き、空欄オではソ連のアフガニスタン侵攻の目的が問われており、冷戦史の知識が不可欠です。
<選択肢>
①【誤】
空欄エ・オともに誤りです。エの「計画経済を採る国々による…国際機構」はソ連中心のCOMECONを指し、第三世界の動きではありません。オの「国際テロ組織…」は2001年のアメリカによるアフガニスタン攻撃の目的であり、1979年のソ連の侵攻とは異なります。
②【誤】
空欄エが誤りです。上記①の解説の通りです。
③【誤】
空欄オが誤りです。上記①の解説の通りです。
④【正】
空欄エ・オともに正しい内容が入ります。
エ:「東西冷戦から距離を置こうとする考え」を国際社会に示したのは、1955年のアジア・アフリカ会議(バンドン会議)で採択された「平和十原則」です。これは主権尊重や反植民地主義を掲げ、第三世界の連帯の基礎となりました。
オ:ソ連によるアフガニスタン侵攻(1979年)は、同国に成立していた親ソ的な社会主義政権が、イスラーム勢力の抵抗によって危機に陥ったため、これを軍事的に支援・維持する目的で行われました。
問8:正解③
<問題要旨>
グラフとパネルで示された情報に加え、さらに国際関係史に関する記述を追加する場合、内容として最も適当なものを選ぶ問題です。グラフの情報と、個別の歴史的出来事の年次を正確に照合する力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
グラフで1976年を見ると、夏季オリンピックの参加国・地域数は100に満たないのに対し、国連加盟国数は140を超えています。したがって、オリンピック参加国数が国連加盟国数を「超えていた」という記述は誤りです。
②【誤】
パレスチナ暫定自治協定(オスロ合意)が結ばれたのは1993年です。グラフを見ると、それ以前の1974年に中東の都市テヘランでアジア競技大会が開催されているため、「開催されたことはなかった」という記述は誤りです。
③【正】
日中国交正常化は1972年です。グラフを見ると、それ以前のアジア競技大会の開催地(東京、ジャカルタ、バンコク、テヘラン)は、いずれも当時の東側陣営(社会主義国)ではありません。東側陣営の中国で初めて開催されたのは1990年の北京大会です。したがって、この記述は正しいです。
④【誤】
アジア競技大会が広島で開催されたのは1994年です。一方、中距離核戦力(INF)全廃条約が締結されたのは1987年です。広島大会よりも前に締結されているため、「開催された後に…締結された」という記述は時系列が逆であり、誤りです。