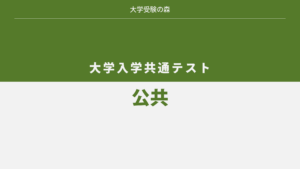解答
解説
第1問
問1:正解②
<問題要旨>
日本の男女平等に関する憲法上の規定と、その実現のために制定された法律についての知識を問う問題。
<選択肢>
①【誤】
空欄イの男女共同参画社会基本法は1999年に制定された法律です。日本が女性差別撤廃条約を批准したのは1985年であり、時期が一致しないため誤りです。
②【正】
空欄アの「法の下の平等」は、日本国憲法第14条第1項に明記されている基本的人権の原則です。空欄イの男女雇用機会均等法は、日本が女性差別撤廃条約を批准した1985年に制定されており、会話文の内容と合致します。したがって、この組合せが正解です。
③【誤】
空欄アの「両性の本質的平等」は、主に婚姻や家族に関する日本国憲法第24条で定められている内容です。第14条が保障する、より広い概念である「法の下の平等」を空欄アに入れるのが文脈上、より適切です。
④【誤】
空欄アの「両性の本質的平等」は憲法24条の規定です。問題文の会話では、性別を含むあらゆる差別を禁じる憲法14条について言及しているため、「法の下の平等」が適切です。また、空欄イの男女雇用機会均等法は1985年の制定ですが、アが不適切なため、この選択肢は誤りです。
問2:正解④
<問題要旨>
仕事に関する性別役割意識についての調査結果を示した表を正確に読み取り、内容と合致しない記述を選択する問題。
<選択肢>
①【正】
表1の左側「共働きでも男性は家庭よりも仕事を優先するべきだ」への肯定的な回答割合を見ると、女性は20代(14.5%)、30代(17.7%)、40代(23.3%)、50代(24.7%)、60代(28.0%)と、年代が上がるにつれて割合が高くなっています。したがって、この記述は表から読み取れる内容と合致します。
②【正】
表1の左側「共働きでも男性は家庭よりも仕事を優先するべきだ」について、20代の肯定的な回答割合は男性が26.2%、女性が14.5%です。その差は「26.2 – 14.5 = 11.7」ポイントとなり、10.0ポイント以上高いことがわかります。したがって、この記述は表から読み取れる内容と合致します。
③【正】
表1の右側「同程度の実力なら、まず男性から昇進させたり管理職に登用するものだ」への肯定的な回答割合を見ると、男性では20代(20.4%)と30代(20.7%)のみが20.0%を超えています。40代以降はいずれも20.0%を下回っています。したがって、この記述は表から読み取れる内容と合致します。
④【誤】
表1の右側「同程度の実力なら、まず男性から昇進させたり管理職に登用するものだ」への肯定的な回答割合について、各年代の男女差を計算します。
20代:20.4 – 11.0 = 9.4ポイント
30代:20.7 – 10.4 = 10.3ポイント
40代:17.6 – 10.4 = 7.2ポイント
50代:15.7 – 8.4 = 7.3ポイント
60代:15.8 – 9.4 = 6.4ポイント
男女の差が最も大きいのは30代の10.3ポイントです。したがって、「60代において男女の差が最も大きい」というこの記述は、表から読み取れる内容と合致しません。
問3:正解②
<問題要旨>
各国の女性議員比率の推移を示した表と、クオータ制などに関する会話文の内容を照らし合わせ、正しく読み取れる記述を選択する問題。
<選択肢>
①【誤】
会話文から、X国で各政党が男女比率均等化の努力を始めたのは「1990年頃」とわかります。しかし、表2を見ると、X国の女性議員比率は1970年の14.0%から1980年には27.8%へと大幅に上昇しており、1990年よりも前に上昇が始まっています。したがって、この記述は誤りです。
②【正】
会話文から、Y国で候補者を男女均等にすることを義務付ける法律が制定されたのは2000年であることがわかります。表2でY国の2000年の女性議員比率は10.9%です。その10年後である2010年の比率は18.9%です。その差は「18.9 – 10.9 = 8.0」ポイントであり、記述の内容と合致します。
③【誤】
表2を見ると、Z国の女性議員比率は、1960年(Z国3.9%、Y国1.5%)や1970年(Z国2.3%、Y国2.1%)において、Y国より高くなっています。「常にY国より低い」という記述は誤りです。
④【誤】
会話文から、日本で候補者の男女比率の均等化を促す法律(政治分野における男女共同参画推進法)が制定されたのは2018年です。表2の最新データである2020年を見ると、日本の女性議員比率は9.9%、Z国は27.3%であり、日本はZ国を上回っていません。したがって、この記述は誤りです。
問4:正解③
<問題要旨>
「形式的平等」と「実質的平等」という二つの平等の概念と、アイヌ民族に関する法制度の知識を問う問題。
<選択肢>
①【誤】
空欄アには「形式的平等」、空欄イには「実質的平等」が入るのが適切です。また、空欄ウのアイヌ文化振興法は1997年の法律で、「先住民族」と明記したものではありません。したがって誤りです。
②【誤】
空欄アとイに入る語句が逆です。「すべての人を同じように扱う」のは「形式的平等」、結果の平等を重視するのが「実質的平等」です。したがって誤りです。
③【正】
「個性や属性にかかわらず、すべての人を同じように扱う」平等は「ア:形式的平等」です。それに対し、結果として生じている格差を是正するためにクオータ制のような積極的改善措置をとることで目指す平等は「イ:実質的平等」です。また、2019年に制定され、アイヌ民族を初めて法律上「先住民族」と明記したのは「ウ:アイヌ施策推進法(アイヌ民族支援法)」です。すべての組合せが正しく、これが正解です。
④【誤】
空欄アとイに入る語句が逆です。「すべての人を同じように扱う」のは「形式的平等」であり、「実質的平等」ではありません。したがって誤りです。
第2問
問1:正解①
<問題要旨>
社会関係資本(ソーシャル・キャピタル)と社会的共通資本の概念を説明したメモを読み、その内容の解釈として適当でないものを選択する問題。
<選択肢>
①【誤】
メモ1の社会関係資本は、「直接の見返りを期待せず」に行動することが望ましいとされています。公園の清掃のような行動を、「直接的な報酬に動機づけられて行うことが望ましい」と解釈するのは、メモ1の説明と明らかに矛盾します。したがって、この記述は適当ではありません。
②【正】
メモ1は社会関係資本を「個人と共同体や個人間のつながり」と説明しています。毎日挨拶を交わすといった行為は、信頼関係を醸成し、社会的なつながりを形成・拡大することに寄与すると考えられます。これはメモ1の趣旨に沿った解釈であり、適当な記述です。
③【正】
メモ2の社会的共通資本は、自然や経済、社会の維持において「市場的な基準を無批判に取り入れてはならない」と説明しています。河川や森林といった自然資本は、たとえ私有物であっても社会全体の資産という側面があり、その管理には市場原理だけでなく社会的な基準(公共の福祉など)を考慮する必要がある、と読み取ることができます。これはメモ2の趣旨に沿った解釈であり、適当な記述です。
④【正】
メモ2は社会的共通資本を「すべての人々が豊かで文化的な生活を送ることを可能にするもの」と定義しています。その形成過程で「経済」の維持に言及していることから、調和的な経済的環境を整えることが求められている、と解釈できます。これはメモ2の趣旨に沿った解釈であり、適当な記述です。
問2:正解⑤
<問題要旨>
企業の3つの資金調達方法(株式発行、社債発行、クラウドファンディング)と、それぞれの特徴を正しく結びつける問題。
<選択肢>
・ア 株式の発行:企業が投資家に出資を募り、その見返りとして株式を交付する方法。調達した資金に返済義務はなく、企業の業績に応じて利益の一部を配当として株主に分配します。これは特徴Z「企業は調達した資金を返済する義務がない。事業の業績に応じるかたちで、資金の提供者に対して、各々の出資比率に基づき配当などを配分する」に合致します。
・イ 社債の発行:企業が投資家からお金を借り入れるために発行する有価証券。満期には元本を返済する義務があり、業績に関わらず定められた利子を支払う必要があります。これは特徴X「企業は調達した資金を期日までに返済する義務がある。事業の業績に関わりなく、資金の提供者に対して、確定した金額の利子を支払う」に合致します。
・ウ クラウドファンディング:インターネットを通じて不特定多数の人から資金を調達する方法。様々な形態がありますが、本文の選択肢から判断すると、資金提供の見返りとして商品やサービスなどの特典を提供する「購入型」を指していると考えられます。これは特徴Y「企業は調達した資金を返済する義務がない。事業の業績に必ずしも関わりなく、資金の提供者に対して、あらかじめ約束した特典などを提供する」に合致します。
以上のことから、「ア-Z」「イ-X」「ウ-Y」の組合せが正しいと判断できます。
①~④、⑥の組合せは上記と異なるため誤りです。
⑤の組合せが「ア-Z」「イ-X」「ウ-Y」となっているため、正解です。
問3:正解⑤
<問題要旨>
為替レートの変動(円高・円安)を正しく判断し、それによって生じる外貨建て価格の変化を計算する問題。
<選択肢>
・空欄ア:為替レートが「1ドル=150円」から「1ドル=100円」に変化しています。これは、以前より少ない円で1ドルと交換できるようになったことを意味し、円の価値がドルに対して上がった状態、すなわち「円高」です。
・空欄イ・ウ:商品の価格を各時点の為替レートでドルに換算します。
- 一年前:6,000,000円 ÷ 150円/ドル = 40,000ドル
- 現在:6,000,000円 ÷ 100円/ドル = 60,000ドル
現在の販売価格は一年前に比べて「60,000 – 40,000 = 20,000」ドル、すなわち「2」万ドル「高く」なっています。
以上のことから、空欄には「ア:円高」「イ:2」「ウ:高く」が入ります。この組合せと一致するのは選択肢⑤です。
問4:正解⑧
<問題要旨>
不況期における日本銀行の金融政策についての理解を問う問題。金融政策の種類、具体的な操作、金利への影響を正しく結びつける必要があります。
<選択肢>
・空欄ア:不況の際に景気を刺激するために行われるのは、世の中に出回るお金の量を増やす「金融緩和」政策です。逆に景気の過熱を抑えるのが「金融引締め」です。
・空欄イ:金融緩和のために日本銀行が公開市場操作で行うのは、市中銀行から国債などを買い入れて市場に資金を供給する「買いオペレーション(買いオペ)」です。資金を吸収する「売りオペレーション(売りオペ)」は金融引締め時に行われます。
・空欄ウ:買いオペによって短期金融市場の資金供給量が増えると、資金の調達コストである金利(政策金利)は「低下」します。この金利の動きに連動して、市中銀行の貸出金利も低下し、企業や家計が資金を借りやすくなることで経済活動の活性化が期待されます。
以上のことから、空欄には「ア:金融緩和」「イ:買いオペレーション」「ウ:低下」が入ります。この組合せと一致するのは選択肢⑧です。
第3問
問1:正解①
<問題要旨>
過去の衆議院議員選挙における一票の格差の計算と、選挙制度の変遷に関する知識を組み合わせる問題。
<選択肢>
・空欄ア:表1は定数が複数名(神奈川県第4区が4名)であることから、一つの選挙区から複数人の議員を選出する「中選挙区制」が採用されていた時期のデータだとわかります。会話文で「表1は、アの導入よりも前のもの」とあるため、中選挙区制の後(1994年の政治改革以降)に導入された「小選挙区制」がアに入ります。
・空欄イ:表1(1990年)の一票の格差を計算します。議員一人当たりの有権者数は、神奈川県第4区が「134万人÷4人=33.5万人」、宮崎県第2区が「32万人÷3人≒10.7万人」です。格差は「33.5÷10.7≒3.14」倍となり、「3」倍程度と判断できます。
・空欄ウ:表2(2000年)の一票の格差を計算します。議員一人当たりの有権者数は、神奈川県第14区が47万人、島根県第3区が19万人です。格差は「47÷19≒2.47」倍です。会話文で、この2.47倍の格差を最高裁は合憲(許容した)とあるため、「『2』倍を超える一票の格差を…許容した」という記述が成り立ちます。
以上のことから、「ア:小選挙区制」「イ:3」「ウ:2」の組合せである選択肢①が正解です。
問2:正解④
<問題要旨>
最高裁判所が出した違憲判決の内容について、正しい記述をすべて選択する問題。
<選択肢>
ア【正】
尊属殺人罪の法定刑を普通殺人罪より著しく重く定めた旧刑法の規定について、最高裁判所は1973年に、法の下の平等を定めた憲法第14条に違反するとして違憲判決を下しました。したがって、この記述は正しいです。
イ【正】
女性にのみ6か月の再婚禁止期間を定めた民法の規定について、最高裁判所は2015年に、100日を超える部分は合理性を欠き、憲法第14条や第24条に違反するとして違憲判決を下しました。したがって、この記述は正しいです。
ウ【誤】
最高裁は、一票の格差が著しい選挙を「違憲状態」や「違憲」と判断したことはありますが、選挙そのものを無効にしたことはありません。これは、選挙を無効にすると社会に大きな混乱が生じるため、「事情判決の法理」に基づき、違憲であることの宣言にとどめているためです。「選挙を常にやり直さなければならない」という記述は誤りです。
以上より、正しい記述はアとイの組合せである選択肢④が正解です。
問3:正解③
<問題要旨>
日本の裁判所の役割や権能に関する文章の空欄を、適切な語句や記述で埋める問題。
<選択肢>
・空欄ア:国や地方公共団体の行政処分の取消などを求める裁判は「行政裁判」(行政事件訴訟)と呼ばれます。「裁判員裁判」は、国民が重大な刑事裁判の審理に参加する制度です。したがって、アには「a 行政裁判」が入ります。
・空欄イ:憲法第81条は、最高裁判所を「一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審の裁判所」と定めています。したがって、イには「d 終審裁判所」が入ります。「特別裁判所」の設置は憲法で禁止されています。
・空欄ウ:個人が自らの権利を守るために裁判所に訴えることができるのは、憲法第32条で「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と定められているためです。したがって、ウには「e 何人も裁判を受ける権利を奪われない」が入ります。
以上のことから、「ア:a」「イ:d」「ウ:e」の組合せである選択肢③が正解です。
問4:正解②
<問題要旨>
刑事司法制度に関する会話文の空欄を、適切な記述で埋める問題。冤罪からの救済制度と、犯罪予防に関する制度の理解が問われています。
<選択肢>
・空欄ア:会話では、えん罪が生まれた場合に備えた仕組みについて言及しています。記述aの「判決の判断材料となった事実認定に合理的な疑いがもたれるような証拠が見つかったときに裁判をやり直す仕組み」は、再審制度のことであり、えん罪被害者を救済するための制度です。したがって、アには「a」が入ります。
・空欄イ:会話では、犯罪の予防に関わる仕組みについて言及しています。記述cの「罪を犯した20歳未満の少年について、保護や教育を通じた矯正を目指す仕組み」は、少年法に基づく少年司法手続のことであり、少年の再犯を防ぎ、健全な育成を図ることを目的としています。これは犯罪予防の一環です。したがって、イには「c」が入ります。
以上のことから、「ア:a」「イ:c」の組合せである選択肢②が正解です。
第4問
問1:正解⑤
<問題要旨>
公共空間に関する思想家の理論について、思想家名とその内容を正しく結びつける問題。ハーバーマスとアーレントの思想の理解が問われています。
<選択肢>
・空欄ア・イ:『コミュニケーション的行為の理論』を著し、公共空間での合意形成において、権力によらない自由で対等な対話(コミュニケーション的行為)の重要性を説いた思想家は「ハーバーマス」です。その合意形成に必要とされる理性を「対話的理性」と呼びます。したがって、アには「ハーバーマス」、イには「対話的理性」が入ります。
・空欄ウ:『人間の条件』を著し、人間の営みを「労働」「仕事」「活動」の三つに分類したのは「アーレント」です。彼女は、このうち「活動」、すなわち他者と「言葉を通して関わり合う」ことこそが、人間を人間たらしめる営みであり、公共空間を形成するものだと論じました。したがって、ウには「言葉を通して関わり合う」が入ります。
以上のことから、「ア:ハーバーマス」「イ:対話的理性」「ウ:言葉を通して関わり合う」の組合せである選択肢⑤が正解です。
問2:正解⑥
<問題要旨>
時間のゆとりや自由時間の過ごし方に関する二つの年の調査結果を比較し、表から読み取れる内容として正しい意見をすべて選択する問題。
<選択肢>
ア【誤】
意見の前半「『ゆとりがある』と回答した割合が半数を下回るようになったのは『30~39歳』と『40~49歳』」は、表1から正しいと読み取れます。しかし、後半の「この二つの年齢層は、『インターネット…利用』をあげた割合が半数を超えるようになった」について、表2を見ると「40~49歳」は45.6%であり半数を超えていません。したがって、この意見は全体として誤りです。
イ【正】
意見の前半「『ゆとりがない』割合は、すべての年齢層で上がっているが、上がった割合が1ポイント未満だったのは『18~29歳』だけ」は、表1の数値を比較すると正しいです(18~29歳は+0.7ポイント、他はすべて1ポイント以上上昇)。後半の「『友人や恋人との交際』…9ポイント以上増えたのは『18~29歳』だけで、50歳以上については、どの年齢層も減っている」も、表2から正しいと読み取れます(18~29歳は+9.1ポイント、50代以上はすべて減少)。したがって、この意見は正しいです。
ウ【正】
意見の前半「『社会参加』をあげた割合は、どの年齢層でも減っている」は、表2から正しいと読み取れます。後半の「『70歳以上』は、『社会参加』の割合が他のどの年齢層より高いままであり、『ゆとりがある』と答えた割合も、他のどの年齢層より高いまま」も、2022年のデータを見ると「社会参加」8.6%、「ゆとりがある」75.4%で、いずれも全年齢層で最も高く、正しいです。したがって、この意見は正しいです。
以上より、正しい意見はイとウの組合せである選択肢⑥が正解です。
問3:正解⑤
<問題要旨>
哲学対話における三つの発言を読み、そのうち帰納的な推論に該当するものをすべて選択する問題。
<選択肢>
I【帰納的】
「穏やかな態度で…対話が活発になった」という個別の事実が何度もあった、という複数の具体的な経験から、「活発な哲学対話は、安心して話せる取り決めがあれば可能になるという経験則」という一般的な法則を導き出しています。これは「具体例→一般法則」の流れであり、帰納的推論です。
II【演繹的】
「人間には、自分の考えや意見を自由に述べる権利があり…尊重し合う義務がある」という一般的な原理・前提から出発し、「哲学カフェに限らず、職場でも学校でも…対話のルールにしなければならない」という個別の場面における結論を導いています。これは「一般法則→具体例」の流れであり、演繹的推論です。
III【帰納的】
「初めて参加した人が素朴な質問をすると…問いが深まった」「同じ実感を他の参加者たちももっていた」といった複数の具体的な経験を基にして、「率直に質問や疑問を出し、問いを深めていくことが哲学対話の方針になった」という一般的な方針を導き出しています。これは「具体例→一般法則」の流れであり、帰納的推論です。
以上より、帰納的推論に該当するのはIとIIIの組合せである選択肢⑤が正解です。
問4:正解②
<問題要旨>
対面と非対面という二つの関わり方の類型について、その記述と具体例を正しく結びつける問題。
<選択肢>
・記述①は「対面の場に非対面で参加」する、いわゆるハイブリッド型を指しています。これは、事例ウの「公民館に集まった人々が行っている対話集会に、インターネットで参加した」という状況に合致します。したがって「①-ウ」の組合せが正しいです。
・記述②は「その場にいる人たちが互いに」やりとりする「対面的関わりのみのタイプ」を指しています。これは、事例イの「料理教室に講師と生徒が集まり…その場で…講評を受けた」という全員が同じ場所にいる状況に合致します。したがって「②-イ」の組合せが正しいです。
・(参考)事例アの「すべての参加者はインターネットで会議に出席した」は、構想メモ冒頭の「非対面的関わりのみのタイプ」に該当します。
以上のことから、「①-ウ」「②-イ」の組合せである選択肢②が正解です。