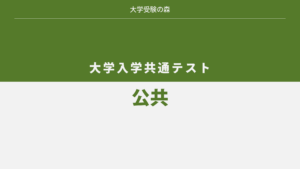解答
解説
第1問
問1:正解②
<問題要旨>
生命倫理の分野で対立しうる「功利主義」と「義務論」という二つの倫理的な考え方について、その基本的な内容を理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
イの「欲求」が不適切です。義務論は、個人の欲求ではなく、普遍的な道徳法則に従うことや、人間の尊厳を尊重することを重視します。
②【正】
功利主義は、社会全体の利益や幸福を最大化することを重視するため、「最大多数」の救命を目指すという考え方(ア)につながります。一方、義務論は、カントに代表されるように、人間一人ひとりを目的として扱い、その「尊厳」(イ)を無条件に尊重することを求めます。そのため、人の命に功利計算的な優先順位をつけることに慎重な立場をとります。よって、この組み合わせは適切です。
③【誤】
アの「無差別」とイの「欲求」が不適切です。功利主義は「最大多数の最大幸福」を原理とするため、結果を計算し、優先順位をつける考え方であり、「無差別」とは異なります。また、イの「欲求」も義務論の考え方とは異なります。
④【誤】
アの「無差別」が不適切です。功利主義は、より多くの幸福を生む選択を優先するため、「無差別」の立場とは相容れません。
問2:正解④
<問題要旨>
日本国憲法の基本的人権の保障に影響を与えた西洋の思想(法の支配、権力分立、天賦人権)と、それらを示す歴史的文書(権利の章典、フランス人権宣言、アメリカ独立宣言)を正しく結びつけることができるかを問う問題です。
<選択肢>
考え方アは「法の支配」、イは「権力分立」、ウは「天賦人権思想」です。
・カードX「すべて人は生来ひとしく自由かつ独立しており、一定の生来の権利を有する」 という記述は、権利が「生来」(生まれつき)のものであると述べており、まさしく考え方「ウ」(天賦人権)の内容と一致します。
・カードY「〔国王が、〕議会の同意なくして王の権威により法や法の執行を停止する…ことは違法である」 という記述は、国王という権力者も法(議会の同意)に従わなければならないということを示しており、考え方「ア」(法の支配)の内容と一致します。
・カードZ「同一の人間あるいは同一の役職者団体において立法権力と執行権力とが結合されるとき、自由は全く存在しない」 という記述は、権力が一つに集中することの危険性を述べ、権力を分ける必要性を説いており、考え方「イ」(権力分立)の内容と一致します。
以上の分析から、正しい組合せは「ア-Y」、「イ-Z」、「ウ-X」となります。
したがって、アとY、イとZ、ウとXの組み合わせが正しく、選択肢④が正解となります。
①【誤】アとX、イとY、ウとZの組み合わせが誤りです。
②【誤】イとZ、ウとYの組み合わせが誤りです。
③【誤】アとYは正しいですが、イとX、ウとZの組み合わせが誤りです。
④【正】アとY(法の支配)、イとZ(権力分立)、ウとX(天賦人権)の組み合わせがすべて正しく、適切です。
⑤【誤】アとZ、イとX、ウとYの組み合わせが誤りです。
⑥【誤】アとZ、イとY、ウとXの組み合わせが誤りです。
問3:正解③
<問題要旨>
地方自治における住民参加の手続きや、憲法上の人権(営業の自由、幸福追求権など)が具体的な社会生活の場面でどのように関わるかを理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
イの「労働基本権」、ウの「請願権」が不適切です。レストランの広告は経済活動であり「営業の自由」に関わります。また、環境権の根拠として挙げられるのは主に「幸福追求権」や「生存権」です。
②【誤】
イの「労働基本権」が不適切です。
③【正】
行政が条例案などを示す際に、広く市民から意見を公募する手続きを「パブリック・コメント」(ア)といいます。レストランの広告出稿は「営業の自由」(イ)の一環であり、景観を守るための条例はこれを制約する可能性があります。また、良好な景観の中で生活する利益(景観利益)を含む環境権は、憲法13条の「幸福追求権」(ウ)などを根拠に主張される新しい人権の一つです。よって、この組み合わせは適切です。
④【誤】
ウの「請願権」が不適切です。
⑤【誤】
アの「マニフェスト」が不適切です。マニフェストは選挙における政権公約です。
⑥【誤】
アの「マニフェスト」、イの「労働基本権」が不適切です。
⑦【誤】
アの「マニフェスト」、ウの「請願権」が不適切です。
⑧【誤】
アの「マニフェスト」が不適切です。
問4:正解②
<問題要旨>
契約に関する基本的な民法の原則(契約遵守の原則)と、消費者保護のルールである特定商取引法のクーリング・オフ制度について、正確に理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
発言bが誤りです。クーリング・オフ制度は、消費者が一方的に、事業者の同意なく契約を解除できる点に特徴があります。「事業者の同意を条件に」という部分が明確な誤りです。
②【正】
発言aは、一度有効に成立した契約は、原則として一方の都合で解消できないという「契約遵守の原則」を正しく説明しています(正)。発言bは、クーリング・オフが「事業者の同意を条件に」成立するとしている点が誤りです(誤)。したがって、「a-正、b-誤」の組み合わせが適切です。
③【誤】
発言aは正しい記述です。
④【誤】
発言aは正しい記述であり、発言bは誤った記述です。
第2問
問1:正解⑧
<問題要旨>
地方自治の二大原則である「住民自治」と「団体自治」、住民の直接請求権の種類、地方公共団体の統治の仕組みである「二元代表制」について、基本的な用語の知識を問う問題です。
<選択肢>
空欄アは、住民が地域の政治に意思を反映させ、参加することを指すので「住民自治」(b)が入ります。
空欄イは、住民が条例の制定・改廃を直接請求する権利であり、これは「イニシアティブ(住民発案)」(d)と呼ばれます。レファレンダム(c)は住民投票を指します。
空欄ウは、住民が首長と議会議員をそれぞれ別の選挙で選び、両者が抑制と均衡の関係に立つ仕組みであり、「二元代表制」(f)と呼ばれます。議院内閣制(e)は国政の仕組みです。
したがって、アにb、イにd、ウにfが入る⑧が正解です。
問2:正解⑦
<問題要旨>
与えられた二つの統計資料(地方議会の無投票当選の状況)を正確に読み解く力と、地方自治の事務・財政・組織に関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
まず、下線部aに関する記述ア~ウの正誤を判断します。
ア【誤】市区の無投票割合(例:2019年 11/314≒3.5%)は、町村の無投票割合(例:2019年 93/375≒24.8%)よりも全ての年で低くなっています。
イ【誤】無投票市区のうち、「5万人未満」が「5万人~20万人未満」より多いとは限りません。2011年は3市区に対し6市区と、後者の方が多くなっています。
ウ【正】無投票町村のうち、「5千人未満」の数は、全ての年で「5千人~2万人未満」の数を上回っています。
次に、下線部bに関する記述エ~カの正誤を判断します。
エ【正】地方公共団体の事務は、自らの判断と責任で行う「自治事務」と、本来は国などの事務で法律に基づき委託された「法定受託事務」に大別されます。記述は正しいです。
オ【誤】財源の分類が逆です。地方税は自ら確保できる「自主財源」、国庫支出金は国から交付される「依存財源」です。
カ【誤】首長は副知事・副市町村長や監査委員を任命しますが、議会の議長・副議長は議会内で互選されるため、首長は任命しません。
以上より、正しい記述はウとエです。その組み合わせである⑦が正解です。
問3:正解③
<問題要旨>
政治制度における「直接民主制」と「間接民主制」の概念を理解し、会話の文脈に即して適切に判断できるかを問う問題です。
<選択肢>
ア:住民自身が直接集まって物事を決める「町村総会」は、「直接民主制」の典型例です。
イ:人口増により直接民主制が困難になるため、代表者(議員)を選ぶ「間接民主制」が採られます。
ウ:現代の多くの国や地方公共団体で基本となっているのは「間接民主制」です。
エ:間接民主制を基本としつつ、住民投票のように部分的に取り入れられるのは「直接民主制」の要素です。
したがって、「直接民主制」という語が入るのはアとエになります。よって③が正解です。
問4:正解⑤
<問題要旨>
ホッブズとロックという近代の代表的な社会契約説思想家の主張内容と、経済学の基本的な用語である「インセンティブ」の意味を理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
ア:ホッブズは、国家なき自然状態を、各人が自己保存のために争う「万人の万人に対する闘争」(b)状態であると捉えました。
イ:ロックは、政府が人民の信託に背き、生命・自由・財産などの自然権を侵害した場合には、人民は政府に抵抗する権利(抵抗権)を持つと主張しました(c)。「哲人政治」はプラトンの思想です。
ウ:「地方議員になろうとする」動機づけ、誘因が足りないという文脈であり、経済学用語の「インセンティブ」(e)が当てはまります。「アウトソーシング」は外部委託の意味です。
以上から、アにb、イにc、ウにeが入る⑤が正解です。
第3問
問1:正解①
<問題要旨>
AI・データ解析の専門家の不足状況に関する二つの資料(グラフ・表)を正確に読み取り、記述内容の正誤を判断する問題です。計算や割合の比較を丁寧に行う必要があります。
<選択肢>
①【正】
資料1より、日本の「大いに不足している」は約35%であり、30%を上回っています。資料2より、日本の不足理由で「育成体制が整っていない」は38.5%、「育成方法がわからない」は26.3%です。回答数(n=853に各割合を掛けた値)は率の大小と同じになるため、「育成方法がわからない」の回答数の方が少なくなります。両方の記述が正しいです。
②【誤】
資料1より、アメリカの「不足していない」は約40%です。資料2より、アメリカの不足理由で「採用方法がわからない」は15.9%、「採用体制が整っていない」は32.2%であり、後者の方が率が高いです。「採用体制の方が少ない」という記述は誤りです。
③【誤】
資料2より、不足理由の「魅力的な処遇が設定できていない」の割合は、日本が25.3%、ドイツが16.5%であり、日本の方が高くなっています。「日本の方が少ない」という記述は誤りです。
④【誤】
資料2より、中国の不足理由で「市場にAI・データ解析の専門家が出回っていない」の回答数は、336人 × 35.4% ≒ 119人となり、100人より多くなります。「100より少ない」という記述は誤りです。
問2:正解③
<問題要旨>
ゲーム理論における「囚人のジレンマ」に似た状況設定を読み解き、各企業の合理的な選択(ナッシュ均衡)を予測し、さらに状況を改善するための方策を考察する問題です。
<選択肢>
ア:各企業が自社の利潤を最大化する行動を考えます。
・S社:T社が「投資する」なら、S社は3億円より8億円が良いので「投資しない」を選びます。T社が「投資しない」なら、-2億円より0円が良いので「投資しない」を選びます。S社は常に「投資しない」のが合理的です。
・T社もS社と全く同じ状況なので、常に「投資しない」のが合理的です。
結果として、両社とも「投資しない」を選択します(b)。これは、両社が協調して「投資する」(互いに3億円の利潤)方が良い結果になるにもかかわらず、非協力的な状況では互いに悪い結果(互いに0円の利潤)に陥る「囚人のジレンマ」的な状況です。
イ:両社が「投資する」という協調的な行動を促す方法を考えます。
・c「相談をする」ことで、互いに投資することを約束できれば、両社とも3億円の利潤を得られるため、投資が促進されます。
・d「赤字の半分を補填する」場合、一方が投資して-2億円の赤字になったとき、もう一方が1億円を補填します。しかし、投資した側の利潤は-1億円となり、依然として「投資しない」(利潤0円)よりも不利なため、投資する動機にはなりません。
よって、アにb、イにcが入る③が正解です。
問3:正解④
<問題要旨>
日本の租税制度、特に消費税と所得税の仕組みについて、その特徴を正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
消費税の軽減税率は、高所得者にも適用されるため、高所得者の負担額も軽減されます。「高所得者の消費税負担額を変えずに」という部分が誤りです。
②【誤】
企業は、仕入れの際に支払った消費税を、売上時に預かった消費税から差し引いて(仕入税額控除)、その差額を国に納付する義務があります。「納付しない」わけではありません。
③【誤】
日本の所得税は、個人の所得の大きさに応じて負担する「応能負担」の原則に基づいており、公共サービスの利用量に応じて負担額が変わる「応益負担」ではありません。
④【正】
会社員などの給与所得者の所得税は、給与の支払者(企業など)があらかじめ給与から天引きして(源泉徴収)、本人に代わって国に納付する「源泉徴収制度」が採られています。記述は正しいです。
問4:正解⑤
<問題要旨>
AI(人工知能)がもたらす倫理的・社会的な課題(責任の所在、偽情報)や、現代的な幸福の概念である「ウェルビーイング」について、関連する用語や考え方を理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
ア:自動運転車が事故を起こした場合、誰が法的な責任を負うのか、という問題は「責任主体」(b)の所在の問題です。「主権者」は国家の統治権の保持者を指し、文脈に合いません。
イ:AIによって生成された偽の情報やニュースは「フェイクニュース」(c)と呼ばれ、社会問題となっています。「デジタルデバイド」は情報格差を指す言葉です。
ウ:AIによるバーチャル空間での快適なコミュニケーションは、本人の主観的な満足感を高め、「ウェルビーイング」の上昇と捉えられますが、それが真の幸福と言えるか、という問いにつなげる文脈として、「AIによるバーチャルな空間で、他者との快適なコミュニケーションをするとき」(e)という記述は適切です。fはAIが人間に害を及ぼす話であり、「ウェルビーイング」が上昇する文脈には合いません。
以上から、アにb、イにc、ウにeが入る⑤が正解です。
第4問
問1:正解⑥
<問題要旨>
青年期における心理的・社会的な成熟の過程と、人生の節目で行われる「通過儀礼」の概念を区別し、それぞれの特徴を正しく分類できるかを問う問題です。
<選択肢>
Xは「七五三や成人式」といった、社会的な役割の移行を儀式によって示す「通過儀礼」についての記述です。
Yは、青年が自己を確立し、精神的に自立していく内面的な発達の時期(心理・社会的モラトリアム)についての記述です。
・ア「大人としての責任や社会的義務が、部分的に猶予される」のは、青年期(モラトリアム)の特徴であり、Yに該当します。
・イ「親や年長者の考え方や、社会的権威に反抗する」のは、自我を確立する過程で見られる第二反抗期など、青年期の特徴であり、Yに該当します。
・ウ「一定の儀式を経ることで、社会的な地位や社会的役割が与えられる」のは、通過儀礼(X)の機能そのものの説明です。
したがって、Xにウ、Yにアとイが該当する⑥が正解となります。
問2:正解⑨
<問題要旨>
スウェーデン、日本、アメリカの3か国について、「国民負担率」と「老後の備え」に関する二つの表を関連付け、各国の社会保障の特色(高福祉高負担、中福祉中負担、低福祉低負担)と国民の意識・行動を結びつけて考察する問題です。
<選択肢>
まず、一般知識と表1から国を特定します。国民負担率が最も高いY(54.5%)がスウェーデン、最も低いX(32.3%)がアメリカ、中間のZ(47.9%)が日本と考えられます。
次に、会話文を手がかりに表2と結びつけます。
・Bの発言「国民負担率が最も高い国(Y:スウェーデン)では、『老後も働いて…』の比率が顕著に低い」→ 表2でこの比率が最も低いのはイ(1.3%)。よってY=イ=スウェーデン。
・Aの発言「国民負担率が最も低かった国(X:アメリカ)では、『預貯金』『債券・株式…』『老後も働いて…』の比率が、最も高くなっている」→ 表2で「債券・株式…」(62.7%)と「老後も働いて…」(27.1%)が最も高いのはウ。自助努力の意識が高いアメリカの特徴と合致します。よってX=ウ=アメリカ。
・残ったアがZ=日本となります。Bの後半の発言(中間の国で個人年金や株式投資の比率が低い)も、アのデータと一致します。
問題では「Xに対応する国」とその「表2が示す国の記号」を問われているので、「アメリカ」と「ウ」の組み合わせである⑨が正解です。
問3:正解②
<問題要旨>
公的年金の財政方式である「積立方式」と「賦課方式」について、それぞれの仕組みの特徴と、社会情勢の変化(インフレ、少子高齢化)から受ける影響を正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
左側の年金制度(ア)は、自分が払った保険料を将来自分が受け取る方式なので「積立方式」です。この方式は、インフレ(持続的な物価上昇)が起こると、積み立てた資産や将来の給付額の実質的な価値が「減少」(ウ)するという弱点があります。
右側の年金制度(イ)は、現役世代の保険料で高齢者世代の年金を支える「賦課方式」です。この方式は、少子高齢化が進むと、支え手(現役世代)が減り、受け手(高齢者世代)が増えるため、給付水準を維持するには現役世代一人あたりの保険料負担を「増やす」(エ)必要が出てくるという課題があります。
したがって、空欄イには「賦課」、ウには「減少」、エには「増やす」が入ります。この組み合わせとなっている②が正解です。
問4:正解⑧
<問題要旨>
社会保障に関連する重要なキーワード(セーフティネット、労災保険)と、市民社会における社会参画の形態(ボランティア)についての知識を問う問題です。
<選択肢>
ア:「貧困などに陥った際に生じる問題を防ぐ仕組みや制度」とは、社会的な安全網である「セーフティネット」を指します。「ディーセント・ワーク」は働きがいのある人間らしい仕事を意味します。
イ:「事業主のみが負担する」社会保険は、労働者が業務上または通勤途中に負傷・疾病した場合に給付を行う「労災保険(労働者災害補償保険)」です。雇用保険は労使双方が負担します(事業主の負担割合は大きいですが)。
ウ:「阪神・淡路大震災」を契機に市民の自発的な社会貢献活動が大きく広まったことから、1995年は日本の「ボランティア元年」と呼ばれています。
したがって、アに「セーフティネット」、イに「労災保険」、ウに「ボランティア」が入る⑧が正解です。