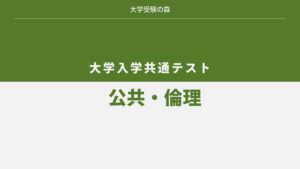解答
解説
第1問
問1:正解②
<問題要旨>
日本国憲法における平等原則と、男女平等の実現に向けた日本の法整備の歴史的経緯についての知識を問う問題。
<選択肢>
①【誤】
イの「男女共同参画社会基本法」は1999年に制定された法律であり、日本が1985年に女性差別撤廃条約を批准したのと同じ年ではないため、誤りです。
②【正】
アの空欄には、日本国憲法第14条第1項が定める「法の下の平等」が入ります。イの空欄には、日本が女性差別撤廃条約を批准した1985年に、同条約の実効性を確保する国内法として制定された「男女雇用機会均等法」が入ります。したがって、この組合せは正しいです。
③【誤】
アの「両性の本質的平等」は、日本国憲法第24条で家族生活に関して定められた原則であり、第14条が定める普遍的な平等原則とは異なります。また、イの「男女共同参画社会基本法」の制定年も誤りです。
④【誤】
アの「両性の本質的平等」が、第14条の内容ではないため誤りです。イの「男女雇用機会均等法」は正しいですが、組合せとして適切ではありません。
問2:正解④
<問題要旨>
二つの調査項目に関する統計データ(表1)を正確に読み取り、その内容と合致しない記述を選択する問題。データの読解力と丁寧な比較検討が求められます。
<選択肢>
①【正】
表1左側の「共働きでも男性は家庭よりも仕事を優先するべきだ」への肯定的な回答割合を見ると、女性は20代(14.5%)、30代(17.7%)、40代(23.3%)、50代(24.7%)、60代(28.0%)と、年代が上がるにつれて割合が一貫して高くなっています。したがって、この記述は表1から読み取れる内容として正しいです。
②【正】
表1左側の「共働きでも男性は家庭よりも仕事を優先するべきだ」への肯定的な回答割合について、男性20代は26.2%、女性20代は14.5%です。その差は「26.2 – 14.5 = 11.7」ポイントとなり、10.0ポイント以上高いという記述は正しいです。
③【正】
表1右側の「同程度の実力なら、まず男性から昇進させたり管理職に登用するものだ」への肯定的な回答割合を見ると、男性では20代が20.4%、30代が20.7%で20.0%を超えていますが、40代(17.6%)、50代(15.7%)、60代(15.8%)はいずれも20.0%を下回っています。したがって、この記述は正しいです。
④【誤】
表1右側の「同程度の実力なら、まず男性から昇進させたり管理職に登用するものだ」への肯定的な回答割合について、各年代の男女差を計算すると、20代は約9.4ポイント、30代は約10.3ポイント、40代は約7.2ポイント、50代は約7.3ポイント、60代は約6.4ポイントとなります。最も差が大きいのは30代であり、「60代において男女の差が最も大きい」という記述は表の内容と合致しないため、誤りです。
問3:正解②
<問題要旨>
4か国の女性議員比率の推移を示した表と、クオータ制に関する会話文を照合し、両方から読み取れる内容として最も適当なものを判断する問題。表と文章の情報を丁寧につなぎ合わせる読解力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
X国では、1960年(13.8%)から1970年(14.0%)にかけても比率はわずかに上昇しており、各政党が努力を始めた1990年頃より前から比率の上昇は見られます。したがって「初めて上昇し始めたのは」という記述は表の内容と一致しません。
②【正】
会話文から、Y国が候補者の男女比率を均等にする法を制定したのは2000年とわかります。表を見ると、Y国の女性議員比率は2000年に10.9%、その10年後の2010年には18.9%となっています。その差は「18.9 – 10.9 = 8.0」ポイントであり、記述の内容と完全に一致します。
③【誤】
Z国の女性議員比率は、1960年以降常に日本の比率より高いことは表からわかります。しかし、Y国と比較すると、1960年から1990年まではZ国の方がY国よりも比率が高いため、「常にY国より低い」という記述は誤りです。
④【誤】
会話文から、日本で候補者の男女比率の均等を促す法律が制定されたのは2018年とわかります。表を見ると、その後の2020年における日本の女性議員比率は9.9%であり、同年のZ国の比率27.3%を上回っていません。したがって、この記述は誤りです。
問4:正解③
<問題要旨>
平等の概念(形式的平等と実質的平等)の区別と、アイヌ民族に関する法制度についての正確な知識を問う問題。
<選択肢>
①【誤】
アは「形式的平等」、イは「実質的平等」で正しいですが、ウの「アイヌ文化振興法」(1997年制定)は、アイヌの文化振興を目的とするもので、アイヌ民族を「先住民族」と明記した法律ではありません。
②【誤】
アの「すべての人を同じように扱うこと」は、機会の平等を保障する「形式的平等」を指します。一方、「実質的平等」は結果の平等を重視する考え方です。アとイの説明が逆になっているため、誤りです。
③【正】
アの「形式的平等」とイの「実質的平等」の使い分けは適切です。ウについては、2019年に制定・施行された「アイヌ施策推進法(アイヌ民族支援法)」において、アイヌ民族が初めて法律上「先住民族」であると明記されました。したがって、この組合せは正しいです。
④【誤】
アとイの平等の説明が逆になっています。ウの「アイヌ施策推進法」は正しいですが、組合せとして誤りです。
第2問
問1:正解⑤
<問題要旨>
公共空間に関する現代思想家、ハーバーマスとアーレントの思想内容を正しく理解しているかを問う問題。
<選択肢>
①【誤】
アのアーレントは『人間の条件』の著者であり、『コミュニケーション的行為の理論』の著者ではありません。
②【誤】
アのアーレントが誤りです。また、ウの「契約を結んでこれを守る」は、社会契約説などに見られる考え方であり、アーレントが「活動」として論じた内容とは異なります。
③【誤】
アのアーレント、イの「他者危害原理」(J.S.ミル)がいずれも誤りです。
④【誤】
アのアーレント、イの「他者危害原理」、ウの「契約を結んでこれを守る」がいずれも誤りです。
⑤【正】
アの『コミュニケーション的行為の理論』の著者はハーバーマスです。彼が公共空間における合意形成に不可欠としたのがイの「対話的理性」です。また、『人間の条件』を著したアーレントは、人間の営みの一つである「活動」を、ウの「言葉を通して関わり合う」ことと説明しました。全ての組合せが正しく思想家の考え方と結びついています。
⑥【誤】
ウの「契約を結んでこれを守る」がアーレントの思想ではないため誤りです。
⑦【誤】
イの「他者危害原理」(J.S.ミル)がハーバーマスの思想ではないため誤りです。
⑧【誤】
イの「他者危害原理」とウの「契約を結んでこれを守る」がいずれも誤りです。
問2:正解⑥
<問題要旨>
二つの年の国民生活に関する世論調査の結果(表1・表2)を比較し、そこから読み取れる変化について正しく記述している意見を判断する問題。複数の表の数値を正確に比較・計算する能力が求められます。
<選択肢>
ア【誤】
前半の「『ゆとりがある』と回答した割合が半数を下回るようになったのは『30~39歳』と『40~49歳』だ」という部分は、2022年調査でそれぞれ48.6%、48.1%となっており正しいです。しかし、後半の「この二つの年齢層は、『自由時間の過ごし方』として『インターネットやソーシャルメディアの利用』をあげた割合が半数を超えるようになった」という部分について、40~49歳は45.6%で半数を超えていないため、意見全体としては誤りです。
イ【正】
「『ゆとりがない』と回答した割合は、すべての年齢層で上がっている」こと、「上がった割合が1ポイント未満だったのは『18~29歳』だけ」であること、「『友人や恋人との交際』をあげた割合に関して、9ポイント以上増えたのは『18~29歳』だけ」であること、「50歳以上については、どの年齢層も減っている」こと、これらは全て表1・表2の数値を比較することで確認でき、いずれも正しい記述です。
ウ【正】
「『社会参加』をあげた割合は、どの年齢層でも減っている」こと、2022年調査において「『70歳以上』は、『社会参加』の割合が他のどの年齢層より高いまま」であること、「『ゆとりがある』と答えた割合も、他のどの年齢層より高いままだ」ということ、これらは全て表1・表2の数値を比較することで確認でき、いずれも正しい記述です。
(①,②,③,④,⑤,⑦はイとウの組合せではないため誤り)
⑥【正】
意見イと意見ウがともに表を正しく読み取ったものであるため、この組合せが正解です。
問3:正解⑤
<問題要旨>
哲学対話における三つの発言を読み、それぞれが「帰納的推論」か「演繹的推論」かを判断する問題。推論方法の定義を理解し、具体的な文章に適用する論理的思考力が試されます。
<選択肢>
I【帰納】
「穏やかな態度で(中略)対話が活発にできるようになった」「これらの事実が何度もあった」という複数の具体的な経験(個別の事実)から、「活発な哲学対話は、安心して話せる取り決めがあれば可能になるという経験則が導き出せる」という一般的な法則を導いています。これは帰納的推論です。
II【演繹】
「人間には、自分の考えや意見を自由に述べる権利があり、お互いに認め合い尊重し合う義務がある」という一般的な原理・法則を大前提として、「そうであるならば、哲学カフェに限らず、職場でも学校でも(中略)対話のルールにしなければならない」という個別の場面における結論を導き出しています。これは演繹的推論です。
III【帰納】
「素朴な質問をしてくれると(中略)問いが深まった」「同じ実感を他の参加者たちももっていた」といった複数の具体的な経験(個別の事実)を基にして、「率直に質問や疑問を出し、問いを深めていくことが哲学対話の方針になった」という一般的な方針を導いています。これは帰納的推論です。
帰納的に推論されているのはIとIIIであるため、⑤が正解となります。
問4:正解②
<問題要旨>
対話や議論の場の類型を定義した文章を読み、それぞれの類型に合致する具体的事例を正しく結びつける問題。抽象的な定義を具体的な状況に当てはめる読解力・判断力が問われます。
<選択肢>
①【誤】
記述①は対面と非対面が混在するタイプ(ウ)ですが、ア(全員非対面)と結びつけているため誤りです。
②【正】
記述①「対面的関わりに非対面的関わりが加わっているタイプ」は、公民館という対面の場にいる人々と、ネットで参加する人がいる事例ウに該当します。記述②「非対面的関わりのみのタイプ」は、全員がオンラインで参加する事例アに該当します。記述③「対面的関わりのみのタイプ」は、講師と生徒が同じ場所に集まっている事例イに該当します。①-ウ、②-ア、③-イの組合せは正しいです。
③【誤】
記述①がイ(全員対面)、記述②がア(全員非対面)、記述③がウ(混在)と結びつけられていますが、①と③の組合せが逆です。
④【誤】
記述①がウ(混在)で正しいですが、記述②がイ(全員対面)、記述③がア(全員非対面)となっており、②と③の組合せが逆です。
⑤【誤】
記述①がイ(全員対面)、記述②がウ(混在)と結びつけられており、誤っています。
⑥【誤】
記述①がウ(混在)で正しいですが、記述②がア(全員非対面)であるべきところをイ(全員対面)としているため誤っています。
第3問
問1:正解④
<問題要旨>
古代ギリシアの主要な思想家(ヘシオドス、デモクリトス、ソクラテス、プラトン)における「美」の捉え方について、正しい記述を選ぶ問題。ギリシア哲学の基本的な知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
ヘシオドスの『神統記』は神々の系譜を体系的に叙述したものですが、神々に翻弄される人間の姿を美しく描いたのは、主に叙事詩人のホメロスとされます。
②【誤】
万物の根源を原子(アトム)と考えたのはデモクリトスで正しいですが、万物の秩序の根底に「数的比例の美」を見出したのはピタゴラスおよびピタゴラス学派の思想です。
③【誤】
ソクラテスは「無知の知」を自覚し、対話を通じて普遍的な真理を探究しました。彼はソフィストたちの相対主義的な考え方を批判する立場であり、彼らを説得しようとしましたが、人々に相対主義を浸透させようとしたわけではありません。
④【正】
プラトンは、この世の個々の美しいものへの愛(エロース)をきっかけとして、魂はイデア界に存在する永遠不変の「美そのもの」(美のイデア)を想起し、魂の上昇が始まると考えました。この記述はプラトンのエロース論、イデア論として正しいです。
問2:正解②
<問題要旨>
ユダヤ教、イスラーム、仏教、キリスト教といった各宗教と芸術(宗教美術)との関係について、正しい知識を問う問題。
<選択肢>
①【誤】
ユダヤ教は偶像崇拝を厳しく禁止しており、神殿やシナゴーグ(会堂)で「救世主(メシア)の像」を礼拝することはありません。
②【正】
イスラームも偶像崇拝を禁止しているため、モスクの内部に神や預言者の像が置かれることはありません。しかし、礼拝の方向(キブラ)を示す壁のくぼみであるミフラーブには、植物の蔓などを図案化したアラベスク模様や、幾何学模様の美しい装飾が施されることが多く、この記述は正しいです。
③【誤】
釈迦涅槃図は、ブッダ(釈迦)が亡くなり、すべての煩悩が消え、二度と生まれ変わることのない完全な安らぎの境地(涅槃)に入った様子を描いたものです。「よりよい世界に輪廻する様」という記述は、輪廻からの解脱を目指す仏教の教えに反します。
④【誤】
キリスト教において、イエスは神の子であり救い主であって、単なる「預言者」ではありません(イスラームではイエスを偉大な預言者の一人と位置づけます)。磔刑図がイエスの贖罪を表す点は正しいですが、イエスの位置づけに関する記述が不正確です。
問3:正解③
<問題要旨>
教父アウグスティヌスの思想について、授業資料の内容を正しく読み解き、彼の思想的背景と結びつけて説明している選択肢を選ぶ問題。資料読解力と思想史の知識が求められます。
<選択肢>
①【誤】
アウグスティヌスは、ギリシア哲学の四元徳(知恵・勇気・節制・正義)を否定したのではなく、キリスト教の立場からこれらを受け入れ、さらに信仰・希望・愛という三元徳を加えて重視しました。「四元徳を否定して」という部分が誤りです。
②【誤】
「四元徳を否定して」という部分が誤りです。また、「芸術家は美しいものを作ることを通じて、神に対する愛を自然に獲得する」という記述は、作られた美への愛を「罠」とし、神から遠ざけるものと述べた資料の内容と矛盾します。
③【正】
アウグスティヌスの思想は、キリスト教の使徒パウロの思想と、新プラトン主義を大成したプロティノスの思想から大きな影響を受けています。この思想的背景は正しいです。また、「芸術作品の美しさが神に由来すると考えているが、作られた美への愛にとどまり続けてはならないと主張している」という説明は、資料で示された「美の源泉は神」「作られた美への愛は罠」という内容と合致しています。
④【誤】
思想的背景は正しいですが、「芸術家は美しいものを作ることを通じて、神に対する愛を自然に獲得する」という記述が、資料の内容と矛盾するため誤りです。
問4:正解①
<問題要旨>
場面2の会話文の下線部ⓓ「中国思想は礼楽を重んじる」に関連して、諸子百家の思想家(孔子、孟子、荀子、老子、荘子、墨子)と礼楽に関する考え方の組み合わせを問う問題です。各思想家の中心的な思想を正確に理解している必要があります。
<選択肢>
①【正】
ア:人の本性を善とする性善説を唱え、道徳性の充実(浩然の気)に美を見出したのは孟子。
イ:価値の相対性を説き、人為的なものから自由になる境地を理想としたのは荘子。
ウ:内面的な徳である「仁」が外面に形式として現れたものが「礼」であるとし、克己復礼を説いたのは孔子。
エ:孔子の仁を差別的な愛(別愛)と批判し、無差別の愛(兼愛)を説いたのは墨子。
以上の組み合わせは全て正しいです。
②【誤】
イは墨子ではなく荘子、ウは老子ではなく孔子であり、誤りです。
③【誤】
アは孔子ではなく孟子、ウは老子ではなく孔子であり、誤りです。
④【誤】
イは老子ではなく荘子、ウは荀子ではなく孔子であり、誤りです。
⑤【誤】
アは荀子ではなく孟子、イは墨子ではなく荘子、エは荘子ではなく墨子であり、誤りです。
⑥【誤】
アは孔子ではなく孟子、イは老子ではなく荘子、ウは荀子ではなく孔子、エは荘子ではなく墨子であり、誤りです。
問5:正解②
<問題要旨>
場面2の会話文の下線部ⓔ「仏教では、人生は苦であるということを強調する」に関連し、大乗仏教の思想について正しく説明している記述を全て選ぶ問題です。大乗仏教の主要な概念(空、菩薩、唯識、仏性など)と、関連する経典や人物についての正確な知識が問われます。
<選択肢>
ア【正】
全ての物事は相互依存の関係(縁起)によって成り立っており、それ自体で存在する実体(自性)を持たない(無自性)、すなわち「空」であるとする思想は、大乗仏教の中心的な教義です。その源流がゴータマ・ブッダの説いた諸法無我などの教えにあるという点も正しいです。
イ【誤】
悟りを求めて修行する衆生(菩生)を「菩薩」と呼ぶのは大乗仏教の特徴です。しかし、『維摩経』は、在家のままで高い境地に達した維摩居士を主人公としており、「出家した菩薩が送る生活を理想化して」描いたものではありません。
ウ【正】
無著(アサンガ)や世親(ヴァスバンドゥ)は、全ての存在は心(識)の働きによって生み出されたものに過ぎないとする唯識思想を大成しました。この思想が、後に玄奘によって中国へ伝えられたことも正しいです。
エ【誤】
記述に複数の誤りがあります。『般若経』が主に説くのは「空」の思想です。「全ての衆生がブッダになる可能性(仏性)を有している」という考えは如来蔵思想であり、竜樹(ナーガールジュナ)は「空」の思想を大成した人物です。また、鑑真は日本に戒律を伝えた僧です。
したがって、正しい記述はアとウです。
問6:正解④
<問題要旨>
場面3の会話文の下線部ⓕに関連して、生徒Bが作成したレポートの空欄a、b、cを補充する問題です。近代における自然科学や芸術が、宗教から独立していく過程を、歴史的な人物や思想的背景と結びつけて理解しているかを問います。
<選択肢>
a:『天文対話』を著したのはガリレイ(ガリレオ・ガリレイ)です。コペルニクスは地動説を提唱しましたが、この著作の著者ではありません。
b:近代科学は、アリストテレス的な目的論的自然観(四原因)を排し、自然現象を原因と結果の連鎖(因果法則)として捉え、数学的に記述しようとしました。
c:ルネサンス期に、神中心の世界観から人間理性を中心に据え、個人の尊厳や能力を肯定するヒューマニズム(人文主義)が起こりました。芸術においても、人間の視点(遠近法)や人間そのものへの関心が高まりました。
以上のことから、aにはガリレイ、bには因果法則、cにはヒューマニズムが入ります。この組み合わせに合致するのは④です。
問7:正解③
<問題要旨>
場面3の会話文の下線部ⓖに関連して、ベンヤミンの資料を読み、複製技術と芸術作品の関係についての彼の考えを正しく説明している選択肢を選ぶ問題です。資料のキーワード(アウラ、伝統、複製、大衆)の意味を正確に読み取ることが求められます。
<選択肢>
①【誤】
資料では、複製技術によって芸術作品の「アウラ」は「失われていくもの」と述べられているため、「同等のアウラを作品に与える」という記述は明確に誤りです。
②【誤】
資料では、複製技術は作品を「伝統の領域から引き離してしまう」と述べられており、「歴史的、社会的文脈から切り離すことなく」という記述は誤りです。
③【正】
資料には、複製技術によって「一回限りの作品」に代わり「同一の作品を大量に出現させる」とあり、これは作品の「唯一無二性という価値を無力化する」ことを意味します。また、「その都度の状況の中で受け手に作品を近づける」「現代の大衆運動とも密接に結びついている」という記述は、「アクセスを容易なものとすることで、作品を広く大衆に開く」という説明と合致しています。
④【誤】
「唯一無二性という価値を無力化せず」という部分が、資料の内容と矛盾しています。
問8:正解②
<問題要旨>
場面3の会話文の下線部ⓗに関連して、ミシェル・アンリの二つの資料を読み、そこから導かれる「鑑賞者の美的体験」の説明として最も適当なものを選ぶ問題です。資料から筆者の主張の核心を捉え、それを的確に言い換えた選択肢を見つける読解力が試されます。
<選択肢>
①【誤】
資料では、芸術が伝える「情動」を鑑賞者が感受することが述べられていますが、「政治的態度や価値観を作者と共有すること」が必要であるとは述べられていません。
②【正】
資料1には「美的体験は倫理と断ちがたい絆を結び」「個人の生き方の変容にほかならない」とあります。これは、美的体験が単なる快楽にとどまらず、倫理的な側面を持ち、鑑賞者の生き方を変容させる力を持つことを示しており、この選択肢の内容と一致します。
③【誤】
「あらゆる社会的影響から離れた」「本来的実存に目覚めさせる」といった表現は、ハイデガーなどの実存主義哲学を思わせますが、提示された資料から直接導き出すことはできません。
④【誤】
資料1では、美的体験は「それ自身一つの倫理」となると述べられており、美的側面と倫理的側面が結びついていることを示しています。「美的というより倫理的なものである」というように、一方を他方より優位に置いたり、美的側面を軽視したりするような記述は資料にはありません。
問9:正解⑥
<問題要旨>
場面1~3を振り返った生徒Aの日記の空欄a、bを補充し、さらに下線部ⓘ「近代の思想家の芸術についての考え」として正しい記述を選ぶ、複合的な問題です。会話文の内容の理解と、近代思想に関する知識の両方が必要となります。
<選択肢>
a:場面2でCさんは、老子の「天下の人々が皆、これこそ美だと心得ているものは、実は醜悪なのだ」という言葉を引用し、「美醜を反転させている」と説明しています。これは常識的な価値観を覆す「逆説」という言葉が当てはまります。
b:場面3の会話でAさんは、現代アートを「必ずしも普通の意味で『美しい』とは言えない」と感じましたが、Cさんの言葉や実際の体験を通して、それでも「心が動かされた」と述べています。この文脈から、現代アートが「美しさがなくとも」心を動かす可能性を学んだと読み取れます。
下線部ⓘ:
オ(ウェーバー):ウェーバーは、西洋近代の合理化が宗教・経済・政治などあらゆる領域に及んだと考えました。芸術もまた、宗教的な呪術性から解放され、自律的な領域として成立したと捉えました。「合理化が芸術には及ばなかった」という記述は誤りです。
カ(ニーチェ):ニーチェは芸術の中に、理性的で秩序的な「アポロン的」衝動と、陶酔的で破壊的な「ディオニュソス的」衝動の対立と融合を見ました。しかし、それが「弱者の連帯を生み出した」という記述は、弱者の道徳(ルサンチマン)を批判した彼の思想とは相容れません。
キ(マルクス):マルクスは、社会の経済的構造(生産関係など)を土台(下部構造)とし、その上に法律・政治・文化・芸術といったイデオロギー(上部構造)が成り立つと考えました。この記述は、彼の唯物史観を正しく説明しています。
以上のことから、aはイ(逆説)、bはエ(美しさがなくとも)、下線部ⓘの正しい記述はキ(マルクス)となります。この組み合わせは⑥です。
第4問
問1:正解①
<問題要旨>
古代から近世にかけての日本における、在来の神々への信仰(神道)と、外来思想である仏教や儒教との関わり(神仏習合など)についての歴史的知識を問う問題。
<選択肢>
①【正】
仏教が伝来した6世紀頃、日本の人々にとって仏は未知の存在であり、外国の強力な神という意味で「蕃神(あだしくにのかみ)」などと呼ばれました。これは、在来の神(カミ)と同じような存在として仏教を受け入れようとした初期の段階を示すものであり、正しい記述です。
②【誤】
本地垂迹説は、仏を本体(本地)、日本の神をその仮の姿(垂迹)とする神仏習合の思想ですが、鎌倉時代以降には逆に神を本体とする反本地垂迹説も現れました。そのため、「仏と神の関係は固定された」という記述は誤りです。
③【誤】
山崎闇斎が提唱した垂加神道は、神道と儒教を結びつけたものですが、彼が重視したのは朱子学であり、陽明学ではありません。
④【誤】
平田篤胤は復古神道を大成しましたが、彼の思想は外来思想の影響を完全に排除したものではなく、また、死後の世界の行方(幽冥界)を詳しく論じており、「死後の霊魂の存在を否定する」という記述は明確に誤りです。
問2:正解②
<問題要旨>
浄土真宗の宗祖・親鸞の思想、特に他力本願や悪人正機の教えを、弟子との逸話を通じて正しく理解できているかを問う問題。
<選択肢>
①【誤】
親鸞は、阿弥陀仏の力(他力)によってのみ救われると説きました。念仏を自力で往生するための修行(自力の行)と捉えるのは、親鸞の教えとは異なります。
②【正】
親鸞は、煩悩から逃れられない人間(煩悩具足の凡夫)こそが、阿弥陀仏の救いの主たる対象(正機)であると説きました(悪人正機)。したがって、「喜ぶべきことを喜べないほどの煩悩を持つ私だからこそ、阿弥陀仏の救いの目当てなのだ」と確信できる、という文脈になり、親鸞の思想と合致します。
③【誤】
「他者に救いの手を差し伸べること」も善い行いですが、それを自分の往生の条件とするのは自力的な考え方であり、すべてを阿弥陀仏にまかせる親鸞の他力の教えとは異なります。
④【誤】
親鸞の言う「悪人」とは、自らが煩悩深い存在であると自覚した人のことであり、その自覚がない人を指すものではありません。また、阿弥陀仏の救いはあらゆる衆生に向けられており、救う対象を限定するような記述は不適切です。
問3:正解③
<問題要旨>
江戸時代の主要な思想家(伊藤仁斎、本居宣長、富永仲基、佐久間象山など)の思想内容を正確に識別する問題。
<選択肢>
①【誤】
後世の注釈に頼らず、『論語』『孟子』といった古典そのものに立ち返ろうとしたのは伊藤仁斎で、その学問は「古義学」と呼ばれます。「古文辞学」を提唱したのは荻生徂徠です。
②【誤】
儒教や仏教の考え方を「漢意(からごころ)」として批判し、日本古来の「真心(まごころ)」を尊んだのは本居宣長で正しいですが、「万人直耕」や「自然世」を理想としたのは、封建的な身分制度を批判した安藤昌益です。
③【正】
富永仲基は、様々な宗教や思想は、時代が下るにつれて後から解釈が付け加えられて(加上されて)成立したと考える「加上(かじょう)の説」を唱えました。これを用いて、仏教の経典も釈迦の死後に次々と作られたものであると論じました。この記述は正しいです。
④【誤】
「東洋道徳、西洋芸術(技術)」という和魂洋才論の考え方を示したのは佐久間象山で正しいですが、彼は西洋の進んだ技術を導入するために開国を主張しました。「鎖国攘夷の立場をとった」という記述は逆であり、誤りです。
問4:正解④
<問題要旨>
明治時代の思想家、西村茂樹の著書『日本道徳論』の一節を読み、彼が主張する日本の道徳の確立方法を正確に読み取る問題。読解力が問われます。
<選択肢>
①【誤】
資料によれば、「儒教と西洋哲学の精髄が一致するところ」が「天地の真理」であり、基礎そのものです。「真理を明らかにした後に、一致するところを基礎とする」という手順は、資料の記述と異なります。
②【誤】
西村は「二教が一致するところを採って」と述べており、儒教と西洋哲学の間に優劣や主従の関係を設定していません。「西洋哲学の精髄を主とし」という記述は、資料からは読み取れません。
③【誤】
②と同様に、「儒教の精髄を主とし」という記述は、両者の一致点を重視する西村の考えとは異なり、資料からは読み取れません。
④【正】
「儒教と西洋哲学の精髄が一致するところの天地の真理を基礎とし、その上で、諸々の教えを取捨選択する」という記述は、資料で述べられている「一定の主義(=天地の真理)を確立した上で、諸教を道徳として採用すれば…」という主張と完全に合致しています。
問5:正解⑤
<問題要旨>
近代日本の思想家(丸山真男、夏目漱石、内村鑑三など)の特徴的な言葉や思想を、空欄に正しく当てはめる問題。日本近代思想史の知識が問われます。
<選択肢>
a【丸山真男】
日本の文化や思想が、様々な外来思想を脈絡なく取り入れ併存させている構造を「雑居」と表現したのは、政治思想史家の丸山真男です。
b【夏目漱石】
「現代日本の開化は皮相上滑りの開化である」とは、作家・夏目漱石が講演「現代日本の開化」の中で述べた言葉で、西洋文明の表面的な模倣に終始する日本の近代化を批判したものです。
c【内村鑑三】
「武士道の台木に基督教を接いだもの」こそが最善であるという「接ぎ木」の思想を述べたのは、キリスト教思想家の内村鑑三です。
以上のことから、a-丸山真男、b-夏目漱石、c-内村鑑三の組合せである⑤が正解です。
第5問
問1:正解③
<問題要旨>
記憶に関する心理学の基本的な概念(記憶の種類と過程)を、具体的な実験内容と結びつけて理解する問題。
<選択肢>
①【誤】
イの「符号化(記銘)」は正しいですが、アの「言葉の意味についての情報」は、一時的な短期記憶ではなく、知識として蓄えられている長期記憶に属します。
②【誤】
アの「短期記憶」、イの「検索(想起)」が共に誤りです。
③【正】
アの「砂時計」や「テーブル」といった言葉の意味に関する情報は、個人の知識体系として長期間保持されている「長期記憶」にあります。 イの実験では、曖昧な図形を覚える(符号化する)段階で、「○○に似ています」という言語情報が与えられています。この言語情報が意味づけとして働き、記憶の形成(符号化)そのものに影響を与えたと解釈できます。したがって、この組合せは正しいです。
④【誤】
イの「検索(想起)」は、記憶を思い出す段階です。この実験では、思い出す段階ではなく、覚える(符号化)段階で言語情報が与えられているため、誤りです。
問2:正解②
<問題要旨>
日常的な思考の偏りである「認知バイアス」について、二つの具体例がそれぞれどのバイアスに該当するかを正しく結びつける問題。
<選択肢>
③の事例:「少年による刑法犯」が実際には減少しているにもかかわらず、テレビ報道で頻繁に目にするため「増えている」と思い込むのは、思い出しやすい情報を過大評価する「利用可能性ヒューリスティック」(ア)に該当します。
④の事例:クラスメイトの遅刻の原因を、本人のやる気がない(内的要因)せいだと考え、バスの遅延(外的要因)を考慮しないのは、他者の行動の原因をその人の内的属性に求めすぎる「根本的な帰属の誤り」(エ)に該当します。
したがって、③-ア、④-エの組合せである②が正解です。
問3:正解④
<問題要旨>
「クリティカル・シンキング(批判的思考)」の考え方と、西洋の哲学者たちの思想を結びつけた説明として、「適当でない」ものを選択する問題。
<選択肢>
①【適当】
ソクラテスが探究した「汝自身を知れ」は、自らの思考や知識を客観視することにつながり、自分の認知を対象とする「メタ認知」を重視する批判的思考と親和性が高いです。
②【適当】
J.S.ミルが『自由論』で擁護した自由な討論は、多様な視点を取り入れて自らの考えを検証する機会となり、多角的に物事を検討する批判的思考の精神と合致します。
③【適当】
デカルトが『方法序説』で説いた演繹法は、確実な前提から厳密に結論を導き出す論理的な推論であり、批判的思考を支える重要な要素です。
④【不適当】
デューイは知性を問題解決の「道具」と捉え、試行錯誤の過程を重視しました。一方、ヒューリスティックは迅速な判断を可能にする直感的な思考の「道具」ですが、時にバイアスを生みます。批判的思考は、このヒューリスティックに無批判に頼るのではなく、その働きを吟味し、より論理的な思考を心がける態度です。したがって、「ヒューリスティックに頼らない態度が重要である」ということ自体は批判的思考の説明として正しいですが、会話文ではヒューリスティックの有効性も示唆されており 、デューイの道具主義の柔軟な考え方と「頼らない」という断定的な表現が最も馴染まないため、不適当と考えられます。
問4:正解③
<問題要旨>
医学研究で用いられる「二重盲検法」の目的を、認知バイアスの観点から正しく説明しているものを選ぶ問題。
<選択肢>
①【誤】
これは患者側が抱く「プラセボ効果」であり、二重盲検法が対処するバイアスの一つですが、医師側も情報を知らない「二重」である理由を説明していません。
②【誤】
これは患者側が抱く「ノセボ効果」であり、①と同様の理由で最も適当とは言えません。
③【正】
二重盲検法では、患者だけでなく、治療や評価を行う医師も、誰が新薬を投与されているかを知りません 。これは、医師が「この患者は新薬を投与されているから、きっと効果が出ているはずだ」といった期待から、無意識のうちに評価を甘くしてしまう「観察者バイアス(期待バイアス)」を防ぐためです。この記述は、二重盲検法の核心的な目的を正しく説明しています。
④【誤】
これも医師側のバイアスですが、新薬の効果への期待がバイアスとして問題にされることがより一般的です。③の方がより中心的な目的を説明しています。
問5:正解①または②
<問題要旨>
災害時などに働く「正常性バイアス」(異常事態を正常の範囲内だと考えてしまうバイアス)への対処法を、二つの異なる方向性から考える問題。
<選択肢>
(1)まず、対処法の方針として二つの方向性から一つを選びます。
①「個々人に(客観的な)判断を促す環境を整える」という、個人の情報リテラシーや判断力を重視する方向性。
②「バイアスが働いても問題が生じない環境を整える」という、個人の判断に頼らず、行動を直接促す(ナッジする)ような仕組みを重視する方向性。
(2)次に、(1)で選んだ方針に合致する具体的な対処法を選びます。
【方針①を選んだ場合】
②の「自分の判断が間違っていないかを検討できるように、国や地方自治体が発信する公的な情報の利用を容易にする」は、個人が客観的な情報に基づいて冷静に判断することを支援するものであり、方針①に合致します。
【方針②を選んだ場合】
⑤の「人が危険と感じる警戒色や警告音を提示する」は、正常性バイアスが働いていても、直感的に危険を察知させ、理屈抜きで避難行動を促す仕組みであり、方針②に合致します。
問6:正解②または⑤
問5に記載
第6問
問1:正解①
<問題要旨>
非暴力による社会変革を訴えた人物とその思想内容について、正しい説明を選択する問題。
<選択肢>
①【正】
ロシアの文豪トルストイは、キリストの教えに基づく人道主義・非暴力主義を唱え、自らの貴族的な特権を省み、貧しい農民の生き方に共感しました。『戦争と平和』も彼の代表作であり、記述は正しいです。
②【誤】
『永遠平和のために』を著し、永遠平和の理念を構想したのはドイツの哲学者カントです。ロマン・ロランは第一次世界大戦期に反戦を訴えたフランスの作家ですが、この著作の作者ではありません。
③【誤】
ガンディーはインド独立の父であり、非暴力・不服従を貫きました。しかし、「アタラクシア」(心の平静)は古代ギリシアのヘレニズム哲学(エピクロス派など)で説かれた理想の境地であり、ガンディーが掲げた理念ではありません。
④【誤】
キング牧師はアメリカの公民権運動指導者ですが、「生命への畏敬」という思想を提唱したのは、アフリカで医療活動に従事した医師・思想家のシュヴァイツァーです。
問2:正解③
<問題要D旨>
会話文の流れを読み、フランスの思想家ミシェル・フーコーの権力論の考え方を的確に説明している記述を選ぶ問題。
<選択肢>
①【誤】
フーコーが分析した近代の権力は、物理的な暴力による強制だけでなく、より巧妙で非暴力的な形で人々を従わせる点を特徴としています。
②【誤】
フーコーが人間中心主義を批判したことは事実ですが、会話文の「人々は疑問を抱かずに戦争に加担してしまうかもしれない」という文脈に最も合致する説明ではありません。
③【正】
「日常生活の中に権力構造が潜んでいて、人々はそれに順応し、規格化されている」という記述は、権力が社会の隅々にまで浸透し、人々が自らを規律に従わせることで権力が機能するというフーコーの権力論(規律訓練型権力)の核心を的確に捉えています。
④【誤】
「権力の視線を内在化させること」は、権力に抵抗する手段ではなく、むしろ人々が権力に順応するメカニズムそのものです。
問3:正解⑦
<問題要旨>
安全保障に関する資料と会話文を読み、現代的な安全保障の概念や国際政治思想の用語を正しく理解し、結びつける問題。
<選択肢>
a【人間】
資料は、従来の国家中心の安全保障を批判し、「普通の人びとに対する正当な配慮」の重要性を説いています。これは、国家ではなく一人ひとりの生存、生活、尊厳を重視する「人間の安全保障」の考え方です。
b【コスモポリタニズム】
Jさんの「他国で起きている戦争や紛争」「そうした人たちだって同じ人間だよ」という発言は、国境や民族の違いを越えて、全ての人を同じ世界の市民(コスモポリス)の一員と見なす「コスモポリタニズム(世界市民主義)」の立場を示しています。
c【ストア派】
コスモポリタニズムの思想的源流は、古代ギリシアのストア派に求められます。ストア派は、理性を共有する点において全ての人間は同胞であると考えました。
したがって、a-人間、b-コスモポリタニズム、c-ストア派の組合せである⑦が正解です。
問4:正解③
<問題要旨>
フランクルが『夜と霧』で描いた強制収容所での人間の扱われ方の三つの特徴を読み取り、その全てが当てはまる身近な事例を判断する問題。
<選択肢>
フランクルの示す特徴は、①人間が単なる「数量」として扱われる、②組織の目標のもとで「管理」される、③「個人の存在が蔑ろにされている」の三点です。
①【誤】
「生徒の希望に応じて」という部分で、特徴③(個人の存在を蔑ろ)の度合いが低いです。
②【誤】
特徴①(数量化)の要素が明確ではありません。
③【正】
「必要な人員数を算出」(①数量化)し、「営業体制を維持するため」(②組織目標のもとでの管理)に、「本人の希望や健康を無視して」(③個人の存在を蔑ろ)業務を割り当てており、三つの特徴が全て明確に当てはまります。
④【誤】
組織的な管理というよりは、一対一の個人的な関係性の問題であり、特徴②の要素が弱いです。
問5:正解①
<問題要旨>
非暴力的闘争を論じたジーン・シャープの思想を資料から読み解き、彼の提唱する「非暴力的闘争」の考え方を具体化した事例として最も適当なものを選ぶ問題。
<選択-肢>
①【正】
シャープは、独裁体制下で人々が孤立化(原子化)させられていることを問題視しています 。したがって、「非政府系の団体を組織」し、「人々が自由に交流」し、「互いの境遇に関心」をもてるようにすることは、孤立を克服し、非暴力闘争の基盤となる社会的な連帯を築くための、戦略的で本質的な行動と言えます。
②【誤】
シャープは、交渉の結末は公正さではなく力関係で決まると指摘しており 、抵抗運動を停止して安易に交渉に入ることを推奨していません。
③【誤】
「政府から(中略)通達や通告が送られてきたので、これに従う」という行動は、シャープが断ち切るべきだと主張する「服従」そのものであり、非暴力的闘争とは正反対です。
④【誤】
シャープは「注意深く構成され、選択されてこそ、非暴力的闘争のための戦略計画の立案が信頼に足り、効果的なものとなる」と述べ、計画性の重要性を強調しています 。個別の判断による無計画な抵抗は、彼の思想とは異なります。