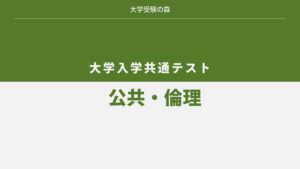解答
解説
第1問
問1:正解②
<問題要旨>
医療現場におけるトリアージ(治療優先順位の決定)を題材として、倫理学における「功利主義」と「義務論」の基本的な考え方を理解しているかを問う問題です。それぞれの思想が何を重視するのかを的確に把握する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
功利主義の基本的な考え方は「最大多数の最大幸福」であり、アに「最大多数」が入るのは正しいです。しかし、義務論は個人の「欲求」ではなく、人間が普遍的に持つべき「尊厳」を重視するため、イが誤りです。
②【正】
功利主義は、社会全体の利益や幸福が最大になることを目指す思想であり、その原理は「最大多数の最大幸福」と表現されます。したがって、アには「最大多数」が入ります。一方、義務論(特にカントの思想)は、行為の結果ではなく動機を重視し、人間一人ひとりが持つ目的としての価値、すなわち「尊厳」を無条件に尊重することを求めます。したがって、イには「尊厳」が入ります。両方の組み合わせが正しいです。
③【誤】
功利主義は、より多くの命を救うという結果を重視するため、優先順位をつけます。したがって、「無差別」の救命を目指すわけではありません。アが誤りです。
④【誤】
アの「無差別」が功利主義の考え方と合いません。功利主義は幸福の総量を計算し、最大化することを目指すため、救命においても差別(優先順位付け)を肯定する場合があります。
問2:正解④
<問題要旨>
日本国憲法の基本的人権の保障に影響を与えた西洋の思想(法の支配、権力分立、天賦人権)と、それらを示す歴史的文書(権利の章典、フランス人権宣言、アメリカ独立宣言)を正しく結びつけることができるかを問う問題です。
<選択肢>
考え方アは「法の支配」、イは「権力分立」、ウは「天賦人権思想」です。
・カードX「すべて人は生来ひとしく自由かつ独立しており、一定の生来の権利を有する」 という記述は、権利が「生来」(生まれつき)のものであると述べており、まさしく考え方「ウ」(天賦人権)の内容と一致します。
・カードY「〔国王が、〕議会の同意なくして王の権威により法や法の執行を停止する…ことは違法である」 という記述は、国王という権力者も法(議会の同意)に従わなければならないということを示しており、考え方「ア」(法の支配)の内容と一致します。
・カードZ「同一の人間あるいは同一の役職者団体において立法権力と執行権力とが結合されるとき、自由は全く存在しない」 という記述は、権力が一つに集中することの危険性を述べ、権力を分ける必要性を説いており、考え方「イ」(権力分立)の内容と一致します。
以上の分析から、正しい組合せは「ア-Y」、「イ-Z」、「ウ-X」となります。
したがって、アとY、イとZ、ウとXの組み合わせが正しく、選択肢④が正解となります。
①【誤】アとX、イとY、ウとZの組み合わせが誤りです。
②【誤】イとZ、ウとYの組み合わせが誤りです。
③【誤】アとYは正しいですが、イとX、ウとZの組み合わせが誤りです。
④【正】アとY(法の支配)、イとZ(権力分立)、ウとX(天賦人権)の組み合わせがすべて正しく、適切です。
⑤【誤】アとZ、イとX、ウとYの組み合わせが誤りです。
⑥【誤】アとZ、イとY、ウとXの組み合わせが誤りです。
問3:正解③
<問題要旨>
地方自治における条例制定プロセスと、それが市民の権利とどのように関わるかを問う問題です。パブリックコメント、営業の自由、幸福追求権といった憲法・行政法上の基本的な用語の知識が求められます。
<選択肢>
①【誤】
レストランの看板や広告の規制は、職業活動の自由の一部である「営業の自由」に関わります。「労働基本権」(団結権、団体交渉権、団体行動権)は労働者の権利であり、この文脈には当てはまりません。イが誤りです。
②【誤】
イの「労働基本権」、ウの「請願権」(国民が国や地方公共団体に要望を述べる権利)の両方が文脈に合いません。
③【正】
行政が規則などを制定する際に、事前に案を公表して広く国民や住民から意見を募る手続きを「パブリックコメント」と言います。レストランの広告規制は、憲法22条で保障される「営業の自由」を制約する可能性があります。また、良好な景観の享受といった新しい人権(環境権)は、憲法13条の「幸福追求権」を根拠に主張されることがあります。したがって、ア、イ、ウの全ての組み合わせが適切です。
④【誤】
環境権の根拠として主張されるのは「幸福追求権」や生存権であり、「請願権」ではありません。ウが誤りです。
⑤【誤】
「マニフェスト」は選挙時に政党や候補者が有権者に対して示す公約のことです。条例案への意見公募手続きではないため、アが誤りです。
⑥【誤】
アの「マニフェスト」、イの「労働基本権」、ウの「請願権」の全てが文脈に合いません。
⑦【誤】
アの「マニフェスト」が誤りです。
⑧【誤】
アの「マニフェスト」、ウの「請願権」が誤りです。
問4:正解②
<問題要旨>
民法における契約の基本原則(契約自由の原則)と、特定商取引法に定められたクーリング・オフ制度についての正確な理解を問う問題です。特にクーリング・オフの要件がポイントとなります。
<選択肢>
①【誤】
発言aは「正」ですが、発言bが「誤」であるため、この組み合わせは誤りです。
②【正】
発言aは、一度有効に成立した契約は、当事者の一方的な都合だけでは原則として解除できないという「契約の拘束力」について正しく説明しているため「正」です。一方、発言bは、クーリング・オフ制度について「事業者の同意を条件に」契約を解除できるとしていますが、クーリング・オフは、消費者が一定期間内であれば、理由を問わず、事業者の同意なしに一方的に契約の申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。したがって、発言bは「誤」となります。「正」と「誤」の正しい組み合わせです。
③【誤】
発言aは、契約の原則を正しく述べているため「正」です。したがって、発言aを「誤」としているこの選択肢は誤りです。
④【誤】
発言aは「正」であるため、この選択肢は誤りです。
第2問
問1:正解⑥
<問題要旨>
青年期の発達課題と、伝統社会における通過儀ale(イニシエーション)の特徴を区別し、正しく理解しているかを問う問題です。エリクソンやレビンソンなどの心理学者が論じた青年期の特徴と、通過儀礼の社会的な機能を的確に結びつける必要があります。
<選択肢>
①【誤】
記述Xは通過儀礼を指しており、その特徴はウです。青年期の特徴であるアとイを結びつけているため誤りです。
②【誤】
記述X(通過儀礼)に、青年期の特徴であるア(モラトリアム)を結びつけているため誤りです。
③【誤】
記述Yは青年期を指しており、その特徴はアとイです。通過儀礼の機能であるウを結びつけているため誤りです。
④【誤】
記述X(通過儀礼)に、青年期の特徴であるイ(第二反抗期)を結びつけているため誤りです。
⑤【誤】
記述Y(青年期)に、通過儀礼の機能であるウを結びつけているため誤りです。
⑥【正】
記述Xの「七五三や成人式のように、人生の節目に行われる行事」は、通過儀礼(イニシエーション)を指します。記述ウの「一定の儀式を経ることで、社会的な地位や社会的役割が与えられる」は、まさに通過儀礼の社会的な機能の説明です。したがって、「X-ウ」の組み合わせは正しいです。
記述Yの「自分自身をよく知り、独自の価値観や人生観を体得し、精神的な自立を実現する時期」は、青年期を指します。記述アの「大人としての責任や社会的義務が、部分的に猶予される」状態は青年期特有のモラトリアムであり、記述イの「親や年長者の考え方や、社会的権威に反抗する」のは自我を確立しようとする第二反抗期の特徴です。両方とも青年期に見られる心理・社会的特徴であるため、「Y-アとイ」の組み合わせは正しいです。
問2:正解⑨
<問題要旨>
スウェーデン、日本、アメリカの3か国について、「国民負担率」と「老後の生活への備え」に関する二つのデータ(表1、表2)を読み解き、国名とデータを正しく結びつける問題です。会話文のヒントを元に論理的に分析する力が求められます。
<選択肢>
①~⑨【正解⑨】
まず、各国の社会保障モデルを考えます。スウェーデンは高福祉・高負担、アメリカは自己責任を重んじる低福祉・低負担、日本はその中間的なモデルです。
表1の国民負担率を見ると、Y(54.5%)が最も高く、X(32.3%)が最も低く、Z(47.9%)が中間です。したがって、Yがスウェーデン、Xがアメリカ、Zが日本と推測できます。
会話文Aの発言「国民負担率が3か国のなかで最も低かった国(X=アメリカ)では、『預貯金』『債券・株式の保有、投資信託』と『老後も働いて…職業能力を高める』という回答の比率が、最も高くなっている」を確認します。
表2を見ると、国ウは「預貯金」(45.7%)はア(54.6%)に次いで2番目ですが、「債券・株式の保有、投資信託」(62.7%)と「老後も働いて…」(27.1%)の項目で3か国中最も高い数値を示しています。全体として自助努力の意識が最も高いことが読み取れ、低福祉・低負担のアメリカの特徴と合致します。
したがって、表1のXはアメリカであり、表2のウがアメリカに対応します。この組み合わせは⑨です。
(参考:国アは「預貯金」が突出して高く、日本の特徴と合致します。国イは「個人年金への加入」が高く、職業能力を高める意識が極端に低いため、社会保障が手厚いスウェーデンの特徴と合致します。)
問3:正解②
<問題要旨>
公的年金制度の二つの主要な財政方式、「積立方式」と「賦課方式」の仕組み、長所・短所を正確に理解しているかを問う問題です。特に、インフレや少子高齢化といった社会経済状況の変化が各方式に与える影響がポイントです。
<選択肢>
①【誤】
イの賦課方式は、少子高齢化が進むと支え手である現役世代の負担が増えるため、給付水準を維持するには保険料を「増やす」必要があります。エが誤りです。
②【正】
アは「現役時に年金受給者が支払った年金保険料を財源として」いるので、将来の自分のために保険料を積み立てていく「積立方式」です。イは「その時々の現役世代が負担する年金保険料を財源として」年金を支給するので、世代間で支え合う「賦課方式」です。アの積立方式は、インフレ(持続的な物価の上昇)が起こると、過去に積み立てた掛金の価値が目減りし、将来受け取る年金額の実質的価値が「減少」します。したがってウには「減少」が入ります。イの賦課方式は、少子高齢化で受給者に対する現役世代の比率が下がると、給付水準を維持するためには現役世代一人あたりの保険料負担を「増やす」必要があります。したがってエには「増やす」が入ります。全ての組み合わせが正しいです。
③【誤】
ウは「減少」です。また、エも「増やす」が正しく、誤りです。
④【誤】
ウは「減少」です。物価上昇で年金の実質価値が増加することはありません。
⑤【誤】
イは「賦課」方式です。
⑥【誤】
イは「賦課」方式です。
⑦【誤】
イは「賦課」方式です。また、ウも「減少」が正しいです。
⑧【誤】
イは「賦課」方式です。また、ウも「減少」が正しいです。
問4:正解⑧
<問題要旨>
社会保障制度に関連する現代的な課題とキーワードについての理解を問う問題です。セーフティネット、労災保険、ボランティアといった用語の意味を、会話の流れの中で正しく判断する必要があります。
<選択-肢>
①~⑦【誤】
文脈に合わない組み合わせを含んでいます。
⑧【正】
ア:貧困などに陥った際に人々を支える社会的仕組みを「セーフティネット(安全網)」と呼びます。
イ:社会保険のうち、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・死亡などに対して保険給付を行う「労災保険(労働者災害補償保険)」の保険料は、全額を事業主が負担します。
ウ:社会参加の方法として、阪神・淡路大震災をきっかけに活動が大きく広まり、1995年が「元年」と言われるのは「ボランティア」です。
したがって、ア「セーフティネット」、イ「労災保険」、ウ「ボランティア」の組み合わせが正しく、文脈に合致します。
第3問
問1:正解②
<問題要旨>
古代ギリシア哲学における幸福(エウダイモニア)についての考え方を問う問題です。ヘレニズム時代のストア派、エピクロス派、懐疑派、そして古典期のアリストテレスの思想を正確に区別できるかがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
「判断を停止せよ(エポケー)」と説いたのは懐疑派です。アリストテレスは、観想(テオーリア)的生活を最高の幸福としましたが、そのために判断停止を説いたわけではありません。
②【正】
懐疑派は、物事の真偽について断定的な判断を下すことを避ける「判断停止(エポケー)」によって、何ものにも乱されない「心の平静(アタラクシア)」が得られると考えました。記述は懐疑派の思想を正しく説明しています。
③【誤】
ストア派は、情念(パトス)に動かされない「無情念(アパテイア)」の状態を理想としました。そのためには理性に背くのではなく、「自然に従って生きる」こと、つまり理性に完全に従うことが求められます。
④【誤】
「自然の摂理である神を信頼し、思い煩うべきではない」というのはストア派の考え方です。エピクロス派は、原子(アトム)の偶然の運動から世界が生成されると考え、神々は人間の運命に関与しないとしました。そのため、神々や死への恐怖から解放され、「心の平静(アタラクシア)」を得ることを目指しました。
問2:正解③
<問題要旨>
世界の諸宗教(ユダヤ教、ジャイナ教、バラモン教・ウパニシャッド哲学、イスラーム)における戒律や宗教的実践に関する知識を問う問題です。各宗教の基本的な教義を正確に理解しているかが試されます。
<選択肢>
①【誤】
ユダヤ教では、神との契約の証である律法を守ることが救いの条件とされます。預言者たちは、形式化した律法主義を批判することはあっても、律法そのものを否定したわけではなく、神への愛と正義の実践を伴う内面的な服従を求めました。
②【誤】
不殺生(アヒンサー)や禁欲を厳格に説いたのはヴァルダマーナが開いたジャイナ教ですが、彼の教えがバラモン教として広まったわけではありません。ジャイナ教は、当時有力であったバラモン教の権威や祭式主義を批判する形で登場しました。
③【正】
ウパニシャッド哲学では、業(カルマ)の思想に基づき、魂が迷いの生存を繰り返す「輪廻」からの「解脱」が究極の目標とされました。そのためには、宇宙の根本原理であるブラフマン(梵)と個人の本質であるアートマン(我)が一体であると悟ること(梵我一如)が必要とされ、世俗を離れた瞑想などの修行が重視されました。
④【誤】
イスラーム法(シャリーア)において、許されているものを「ハラール」、禁止されているものを「ハラーム」と呼びます。記述は逆になっています。
問3:正解④
<問題要旨>
宗教改革者ルターの「信仰義認説」についての資料を読み解く問題です。ルターが「律法の行い」と「律法の成就」をどのように区別し、信仰との関係をどう捉えたかを正確に理解する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
資料から、ルターは律法そのものを否定しているのではなく、神の心にかなう善い生き方を示すものとして肯定的に捉えていることがわかります。aが誤りです。
②【誤】
aの「否定的」が資料の趣旨と合いません。
③【誤】
ルターは、人間の意志による「律法の行い」は救いにつながらないと批判しています。信仰によって聖霊が与えられ、自発的に律法を「成就」するようになると考えています。したがって、bが誤りです。
④【正】
資料においてルターは、強制されて外面的な行為として「律法の行い」をすることと、聖霊によって内面から喜んで神の心にかなう生き方をする「律法を成就する」こととを区別しています。彼は律法そのものを否定しているわけではなく、むしろそれが「成就」されるべきだと考えているため、律法に対してはa「肯定的」です。そして、その「成就」は人間の力ではなく、信仰によって与えられる聖霊の働きによってのみ可能になると説いています。したがって、信仰によってb「律法が成就される」と考えていることが読み取れます。両方の組み合わせが正しいです。
問4:正解⑥
<問題要旨>
中国の諸子百家における「幸福」や「あるべき社会」についての考え方を問う問題です。荀子、老子、朱熹、韓非子の思想の核心部分を、それぞれ正しく特定できるかが試されます。
<選択肢>
①~⑤【誤】
思想家と説明の組み合わせが誤っています。
⑥【正】
ア:人間の本性を欲望に流されやすい「性悪」と捉え、それを矯正するために聖人が定めた「礼」による社会秩序の実現を説いたのは、荀子の思想です。
イ:「仁義」といった人為的な道徳を否定し、無為自然の「道」に従って生きることを理想としたのは、道家の祖である老子の思想です。
ウ:事物の「理」を窮める「格物致知」を通じて、本来の善性を取り戻し、聖人になることを目指す「理気二元論」を大成したのは、宋学の朱熹です。
エ:儒家の徳治主義を批判し、信賞必罰の厳格な「法」によって国家を統治すべきだと説いたのは、法家の韓非子の思想です。
すべての組み合わせが正しく対応しています。
問5:正解⑤
<問題要旨>
カントの倫理思想に関する資料読解問題です。カントが、幸福を追求する原理(格率)と、普遍的な道徳法則をどのように区別したかを理解することが求められます。「格率」「普遍的規則」といったカント哲学の専門用語の知識も必要です。
<選択肢>
①~④【誤】
空欄に当てはまる語句の組み合わせが誤っています。
⑤【正】
資料でカントは、幸福の追求は個人の経験や見方に依存するため、普遍的な法則にはなりえないと論じています。
a:「幸福を追い求めるという原理」は、あくまで個人が立てる主観的な行動原理であるため、「格率(行動方針)」が入ります。これは普遍的な「道徳法則」とは区別されます。
b, c:幸福についての規則は、経験に基づき「概括的な規則」を与えることはできるが、全ての場合に例外なく妥当する「普遍的規則」を与えることはできない、と述べています。したがってbには「普遍的規則」が入ります。そして、「言いかえれば」の後で、この「概括的な規則」が「しばしば的中する規則」であると言い換えられています。したがってcには「しばしば的中する規則」が入ります。a, b, c全ての組み合わせが適切です。
⑥【誤】
cの「科学的規則」は文脈に合いません。カントは幸福の原理が経験的なものであると述べており、科学的規則とは異なります。
問6:正解④
<問題要旨>
西洋思想における理想社会論(ユートピア思想)についての問題です。複数の思想家(プラトン、トマス・モア、フーリエ、オーウェン)とその思想・活動内容を正しく結びつけられるかを問うています。語群から適切な人名・語句を選んで正しい文章を完成させる形式です。
<選択肢>
①【誤】
理想国家を統治者・防衛者・生産者の三階級から構想し、哲学者が統治すべき(哲人政治)と説いたのはa「プラトン」です。彼が国家のうちに実現すべきとしたのは「正義」であり、語群の「あ」に当てはまります。しかし、人名の語群にプラトンは含まれていません。
②【誤】
著書『ユートピア』で「私有財産」制のない社会を描いたのはb「トマス・モア」です。したがって、「い」には私有財産が入ります。この選択肢は内容的に正しいですが、人名bの語群にトマス・モアが含まれているかを確認する必要があります。
③【誤】
「ファランジュ」という名の協同体を構想したのはc「フーリエ」です。彼は農業を基盤とした共同体を考えました。しかし、人名の語群にフーリエは含まれていません。
④【正】
d「オーウェン」は、イギリスの社会改良家・空想的社会主義者です。彼は、人間は環境によって性格が形成される(環境決定論)と考え、教育を重視しました。アメリカで「ニューハーモニー村」という共産主義的な共同体を建設する試みは失敗しましたが、その思想は後の「協同組合運動」に大きな影響を与えました。したがって「え」には協同組合運動が入ります。人名、語句ともに語群に含まれており、説明としても正しいです。
問7:正解①
<問題要旨>
スピノザの倫理思想(『エチカ』)に関する資料読解問題です。自己の存在を維持しようとする努力(コナトゥス)を徳の基礎としつつ、理性が導く他者との協調関係をどのように論じたか、その論理を正確に読み取ることが求められます。
<選択肢>
①【正】
a:資料前半で「まったく同じ本性の二つの個体が互いに結合するなら、…二倍強力な」個体になると述べていることから、人間にとって最も有益なものは同じ本性を持つ「人間」であると分かります。
b:理性に導かれる人々は、孤立して自己の利益のみを追求するのではなく、他者と協力し、「皆に共通の利益を求める」ことが、結果的に自己の存在維持に最もつながるとスピノザは考えます。
c:最後の文は、「理性に支配される人間は、他の人々のために(も)欲しないようなこと(=共通の利益に反する、誰のためにもならないこと)は、自分の(利益の)ためにも求めない」という意味になります。これは理性が共通善を志向するという文脈に合致します。したがって「欲しない」が入ります。すべての組み合わせが適切です。
②【誤】
cに「欲する」を入れると、「理性に支配される人間は、他の人々のために(も)欲するようなこと(=共通の利益)を、自分のためには求めない」という意味になり、自己の存在維持を徳の基礎とするスピノザの思想と矛盾してしまいます。
③【誤】
bの「各自の利益を全て放棄する」は、自己保存を重視するスピノザの思想とは異なります。また、cも誤りです。
④【誤】
aには、文脈から「人間」が入ります。
⑤【誤】
a, b, c、いずれも文脈に合いません。
⑥【誤】
a, bが文脈に合いません。
問8:正解④
<問題要旨>
現代思想家(ハイデガー、アドルノ、クワイン、ドゥルーズなど)の思想を正確に理解し、その説明と結びつける問題です。それぞれの思想家のキーワードや中心的な主張を把握しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
「人間を含めた全てを役立つものに仕立てあげる」技術のあり方を問うたのはハイデガーですが、「二項対立の解体」を提唱したのは、デリダなどのポスト構造主義の思想家です。
②【誤】
「人間を画一的に管理する社会(管理社会)」を批判したのはアドルノですが、「生の根源に立ち戻って、より深い自己を取り戻し」といった表現は、むしろ実存主義などに近い発想です。
③【誤】
「知のホーリズム」を唱えたのはクラインですが、「他者の呼びかけに応えること」を倫理の基礎に据えたのはレヴィナスです。
④【正】
ドゥルーズは、人や物事を固定的な「同一性」に押し込める西洋哲学の伝統を批判し、常に変化し続ける多様な「差異」や「生成変化」そのものを肯定する哲学を展開しました。記述はドゥルーズの思想を正しく説明しています。
問9:正解⑤
<問題要旨>
場面1~3の会話を通じて変化した生徒Aの考えをまとめる問題です。会話の内容を振り返り、カントの倫理学やサルトルの実存主義に関する用語を正しく当てはめる必要があります。
<選択肢>
①【誤】
生徒Aは当初、「よいことをすると幸せになれる」「善人が報われるべきだ」と考えていました。aの「善行は見返りを求めるべきではない」は、むしろ場面2以降に傾いた考え方であり、当初の考えとは異なります。
②【誤】
aが当初の考えと異なります。
③【誤】
aが当初の考えと異なります。また、cの「被投性」(ハイデガーの用語で、人間が自分の意志とは無関係に特定の状況に投げ込まれて存在していること)は、社会への積極的関与を意味する文脈とは合いません。
④【誤】
bの「高邁の精神」はデカルトの用語で、自由意志を正しく用いることから生じる自己への尊厳の感情を指し、カントが無条件に善いとした「善意志」とは異なります。
⑤【正】
a:生徒Aは場面1や2で「よいことをすれば報われる」「幸せになれる」と考えていました。したがって、当初は「善行が幸福をもたらす」と考えていたと言えます。
b:カントは、いかなる状況でもそれ自体で無条件に善いと言えるのは、道徳法則に従おうとする意志、すなわち「善意志」のみであると説きました。
c:自己を社会や歴史的状況の中に投企し、主体的に関わっていくことを、サルトルは「アンガジュマン(社会参加)」と呼びました。
すべての組み合わせがメモの内容と合致します。
第4問
問1:正解①
<問題要旨>
古代日本の神道における「清き明き心」や「禊・祓い」といった精神文化に関する基本的な知識を問う問題です。記紀神話や『万葉集』の内容と関連付けた理解が求められます。
<選択肢>
①【誤】
「清き明き心」の「明き」は、私心がなく、公明正大で明るい心の状態を指します。一方、スサノヲは、乱暴狼藉を働き、姉であるアマテラスを天の岩戸に隠れさせてしまうなど、むしろ世の中を暗くする存在として描かれる場面があります。したがって、この記述は適当ではありません。
②【正】
『万葉集』には、自然の清らかさや雄大さを詠んだ歌が多く、そうした自然のあり方が、人間の理想的な心の状態である「清き明き心」のモデルと見なされていました。適当な記述です。
③【正】
記紀神話によれば、イザナキは亡き妻イザナミを追って黄泉国へ行きますが、その穢れを身に受けたため、地上に戻った際に川で身を清める「禊」を行いました。その際、アマテラス、ツクヨミ、スサノヲの三貴子が生まれたとされています。適当な記述です。
④【正】
古代日本では、罪や過ち(天津罪・国津罪)、そして病気や災害といった災厄は、すべて「ケガレ(穢れ)」と見なされ、これらを清めるための儀式として「祓い」が行われました。適当な記述です。
問2:正解④
<問題要旨>
江戸時代の儒学者・国学者が説いた「望ましい心のあり方」に関する問題です。中江藤樹、熊沢蕃山、契沖、賀茂真淵の思想を正確に区別できるかがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
親子の間の自然な愛情(愛敬)を人間関係の基本と捉え、それを社会全体に広げる「致良知」の思想を説いたのは中江藤樹ですが、彼は陽明学者であり、「上下定分の理」を強調する朱子学の考え方とは一線を画します。
②【誤】
「忠信と恕を実践することで、誠に近づく」ことを求めたのは、伊藤仁斎の思想です。熊沢蕃山も陽明学者ですが、この説明は伊藤仁斎のものです。
③【誤】
『古事記』の実証的研究を行ったのは本居宣長です。「もののあはれ」を日本人の本質的な感受性として見出したのも宣長です。契沖は『万葉集』の実証的研究を行い、国学の基礎を築きましたが、この記述は宣長のものです。
④【正】
賀茂真淵は、師である荷田春満の学問を受け継ぎ、『万葉集』の研究を通じて、奈良時代の日本人が持っていた素朴で力強い精神性を「ますらをぶり(丈夫(ますらお)ぶり)」と呼び、理想としました。記述は賀茂真淵の思想を正しく説明しています。
問3:正解④
<問題要旨>
江戸時代における武士の道徳(士道・武士道)の変遷と、その代表的な思想家についての知識を問う問題です。山鹿素行、山本常朝、吉田松陰の思想を、歴史的文脈の中で正しく位置づける必要があります。
<選択肢>
①【誤】
a「士道」を提唱したのは山鹿素行です。藤原惺窩は江戸時代初期の朱子学者で、武士の道徳について論じましたが、「士道」という言葉で体系化したのは素行です。
②【誤】
aが誤りです。また、bの西川如見は町人出身の学者であり、『葉隠』の著者ではありません。
③【誤】
a、bともに誤りです。
④【正】
a:戦乱のなくなった泰平の世において、武士が庶民の模範となるべき為政者としての道徳「士道」を説いたのは、古学者の山鹿素行です。
b:死を覚悟し、主君への滅私奉公を説く『葉隠』を口述したのは、佐賀藩士の山本常朝です。
c:幕末の思想家である吉田松陰は、藩という枠を超えて、すべての人民が直接天皇に忠誠を尽くすべきだとする「一君万民論」を唱えました。これは、それまでの封建的な主従関係(藩の分立する割拠体制)を乗り越え、近代的な国民国家の道徳へとつながる思想でした。
すべての組み合わせが正しいです。
⑤【誤】
cの記述が誤りです。吉田松陰の一君万民論は、藩体制を乗り越える点に画期性があり、単なる国粋主義的な主張ではありません。
⑥【誤】
bが誤りです。
問4:正解②
<問題要旨>
鎌倉新仏教の中から、特定の修行(専修念仏、只管打坐など)を説いた思想家の教えを特定する問題です。資料の「修行と悟りは等しい(修証一等)」、「初心者の修行も、本来的な悟りそのもの」というキーワードから、どの宗派の教えかを判断します。
<選択肢>
①【誤】
「他力を頼めば、悪人でも往生できる(悪人正機説)」と説いたのは、浄土真宗の開祖である親鸞です。資料の思想とは異なります。
②【正】
資料の「修行と悟りは等しい(修証一等)」「修行のほかに悟りを期待してはいけない」という考え方は、ただひたすらに坐禅すること(只管打坐)自体がすでに悟りの姿であると説いた、曹洞宗の開祖・道元の教えです。坐禅の実践によって、身も心も仏法の世界からとらわれなくなり、自由になることができるとしました。
③【誤】
「ひたすらに念仏すれば、誰でも往生できる(専修念仏)」と説いたのは、浄土宗の開祖である法然です。道元の思想とは異なります。
④【誤】
「ひたすらに題目を唱えれば、誰でも仏になることができる(唱題)」と説いたのは、日蓮宗の開祖である日蓮です。道元の思想とは異なります。
問5:正解②
<問題要旨>
日本の近代文学における自然主義(島崎藤村、田山花袋など)の人間観と、それを批判した哲学者・和辻哲郎の倫理学の思想内容を、レポート形式の文章から正しく読み解く問題です。
<選択肢>
①【誤】
記述bは和辻哲郎の思想を説明していますが、この問題の正解の組み合わせではありません。
②【正】
a:島崎藤村は、初期には『若菜集』などでロマン主義的な感情を新体詩の形式で生き生きと表現しましたが、その創作態度はやがて自己の内面を赤裸々に告白する自然主義へと移っていきました。レポートでは、この藤村の文学的変遷を、自然主義批判の導入として取り上げていると考えられます。
b:和辻哲郎は、人間を社会的な「間柄的存在」として捉えましたが、それは単に社会に埋没する存在という意味ではありません。彼は、人間が社会や歴史との関係性の中で、絶えず自己を問い直し、主体的に生きようとする動的な存在であるとも考えていました。この記述は、そうした和辻の思想における個人の主体性と社会性の複雑な関係を表現したものと解釈できます。したがって、この組み合わせが正解となります。
③【誤】
記述aは夏目漱石の文学観、記述bは和辻哲郎の思想をそれぞれ説明していますが、この問題で問われている組み合わせとは異なります。
④【誤】
記述bは、和辻哲郎の思想を正しく説明していません。
第5問
問1:正解①
<問題要旨>
生命倫理の分野における最新の医療技術(ゲノム編集、テーラーメイド医療、クローン技術、ヒトゲノム)に関する基本的な知識を問う問題です。それぞれの技術の概要と倫理的課題を正確に理解しているかが試されます。
<選択肢>
①【正】
ゲノム編集技術は、生物の遺伝情報をねらって改変する技術で、農作物の品種改良などに応用されています。しかし、これを人間の受精卵に応用すれば、親が望む能力や容姿を持つ子どもを意図的に作り出す「デザイナー・ベビー」につながる可能性があり、深刻な倫理的問題が指摘されています。記述は正しいです。
②【誤】
テーラーメイド医療とは、個人の遺伝情報(ゲノム)の違いに基づいて、各個人に最適化された治療や予防を行う医療のことです。「患者の自己決定に基づいて行われる医療」はインフォームド・コンセントの説明であり、テーラーメイド医療そのものの定義ではありません。
③【誤】
ヒトiPS細胞(人工多能性幹細胞)は、人間の皮膚などの体細胞に特定の遺伝子を導入して作製されます。これは再生医療への応用が期待されていますが、「羊の体細胞」から作られるわけではなく、また「ヒトクローン細胞」とは区別されます。
④【誤】
「ヒトゲノム」とは、一人の人間が持つすべての遺伝情報のことです。特定の家族に共通する遺伝情報を指す言葉ではありません。
問2:正解③
<問題要旨>
ビッグデータの活用が社会や個人に与える影響について、多角的な視点からその内容を問う問題です。個人情報保護法、環境問題、消費行動など、様々な分野との関連知識が求められます。
<選択肢>
①【誤】
個人情報保護法では、個人情報を本人の同意なく第三者に提供することは原則として禁止されています。また、特定の個人を識別できないように加工した「匿名加工情報」であっても、その利活用には一定のルールが定められており、「特に制限されておらず」という記述は誤りです。
②【誤】
「地球の有限性」という言葉は、1972年にローマクラブが発表した報告書『成長の限界』で有名になりました。この報告書は、有限な地球環境の中で無限の経済成長を続けることの危険性を警告したものであり、「技術革新によって長期的に利用するという」楽観的な考え方とは異なります。
③【正】
オンラインショッピングサイトなどでは、ユーザーの閲覧履歴や購買履歴といったビッグデータを分析し、個人の興味や関心に合わせた商品や情報を推薦(リコメンド)する仕組みが広く使われています。これにより、利用者の選択が知らず知らずのうちに特定の方向に誘導され、視野が狭まる「フィルターバブル」といった問題が指摘されています。
④【誤】
レイチェル・カーソンが1962年に著した『沈黙の春』は、農薬などの化学物質による環境汚染の危険性を告発し、後の環境保護運動に大きな影響を与えましたが、主なテーマは「地球温暖化」ではありません。地球温暖化が大きな国際問題となるのは、それより後の時代です。
問3:正解④
<問題要旨>
心理学における「心の理論」に関する実験(サリーとアン課題)を題材に、人間の認知能力の発達についての理解を問う問題です。他者の視点に立ってその意図や信念を推測する能力を指す用語を正しく選ぶ必要があります。
<選択肢>
①【誤】
口調や表情を手がかりにすることは推論の一部ですが、この実験で問われているのは、他者が自分とは異なる誤った信念を持っていることを理解できるか、というより高度な能力です。
②【誤】
物語の時系列を記憶する能力とは異なります。サリーが「知らない」という情報が重要になります。
③【誤】
個別事例からの一般化は、帰納的推論のことであり、この実験の趣旨とは異なります。
④【正】
この実験は「心の理論(Theory of Mind)」の能力を調べるための古典的な課題(誤信念課題)です。心の理論とは、自分や他者には「心」があり、その心(信念、意図、願望など)に基づいて行動していることを理解し、他者の心の状態を推論する能力のことです。サリーはボールが箱に移されたことを知らないため、「ボールはかごの中にある」と信じているはずだ、と推論できるかが問われています。
⑤【誤】
物語の矛盾を見つけ出す能力ではなく、登場人物の視点に立つ能力が問われています。
⑥【誤】
自分自身の思考を客観的に認識する能力は「メタ認知」と呼ばれますが、この実験では特に「他者」の心の状態を推論する能力が問われています。
問4:正解⑥
<問題要旨>
場面2の会話文の空欄補充問題です。ピアジェの発達段階説や、青年期の心理的特徴に関する用語の知識が問われています。
<選択肢>
①~⑤【誤】
語句の組み合わせが誤っています。
⑥【正】
b:ピアジェは、人間の認知発達の最終段階を「形式的操作期」と名付けました。この段階では、具体的な事物から離れて、仮説に基づいた論理的思考や抽象的な思考が可能になるとされます。「心の理論」が発達し、他者の視点に立てるようになることは、この形式的操作期に至るための重要なステップです。
c:「心の理論」は、他者の感情や意図を推し量る能力であり、他者の感情を自分のことのように感じる「共感」の基盤となります。道徳性の基盤となるという文脈にも合致します。
したがって、bに「形式的操作期」、cに「共感」が入るのが最も適切です。
(参考:「第二の誕生」はルソーが青年期を指して用いた言葉。「心理的離乳」はホリングワースが述べた、青年が親から精神的に自立すること。「愛着(アタッチメント)」はボウルビィが提唱した、乳幼児が特定の養育者との間に形成する情緒的な結びつきのことです。)
問5:(1)正解①又は②又は③ (2)正解⑤又は③又は④
<問題要旨>
AI(人工知能)との共生について、自らの立場(d)を選び、その立場に対する的確な懸念・反論(e)を組み合わせる問題です。論理的な思考力と、AIをめぐる現代的な論点についての知識が求められます。(1)で選んだ選択肢によって(2)の正解が変わる特殊な形式です。
(1) 解答番号27:正解 ①又は②又は③
この問いは、解答者がAIに対してどのようなスタンスを取るかを選択するもので、①~③のいずれを選んでも正解となります。
(2) 解答番号28:(1)の選択により、正解は⑤、③、④のいずれか
<問題要旨>
(1)で選んだ「AIとの共生に関する自分の立場」に対して、それとは異なる視点からの懸念や反論を的確に選ぶ問題です。選んだ立場の弱点や、考慮すべき別の側面を指摘できているかが問われます。
<選択肢>
(1)で①「AIを積極的に利用すべき」を選んだ場合 → 正解⑤
【理由】AIを積極的に利用する社会(例:犯罪予測)は、効率や安全性を高める一方で、⑤のように「罪を犯す可能性が高い」と予測された個人の人権を侵害する危険性をはらんでいます。これは、AIの功利的な利用に対する深刻な懸念・反論として適切です。
(1)で②「AIに頼らないようにすべき」を選んだ場合 → 正解③
【理由】AIに頼らない社会を目指すべきだ、という立場に対して、③のように、日本政府がAIなどを活用して社会課題の解決を目指す「Society 5.0」を推進しているという現実は、その立場とは逆の方向性を示す重要な論点となります。AIの活用が国の政策として進められている事実を考慮すべきだ、という反論として適切です。
(1)で③「AIを人間と対等に尊重すべき」を選んだ場合 → 正解④
【理由】AIを人間と対等に扱うべきだ、という主張に対して、④のように、現在のAIはあくまでプログラム(アルゴリズム)に従って動いているだけであり、人間のような意識や「心」を持つ存在ではない、という指摘は、その主張の根幹を問う的確な反論となります。対等な存在と見なすことの是非を問う懸念として適切です。
(その他の選択肢について)
①はAIと人間の類似性を述べており、特定の立場への強い反論にはなりにくいです。
②の「感情の中枢起源説」は、AIと感情を結びつける特定の学説であり、一般的な反論としてはやや限定的です。
第6問
問1:正解①
<問題要旨>
文化人類学者レヴィ=ストロースが提唱した「文化相対主義」の考え方を正確に理解しているかを問う問題です。文化の多様性をどのように捉えるかがポイントです。
<選択肢>
①【正】
文化相対主義は、それぞれの文化が、その社会が置かれた独自の環境や歴史的背景の中で形成されたものであり、固有の価値体系を持っていると考えます。そのため、異なる文化間に優劣の差はなく、自文化の価値基準で他文化を判断すべきではない、と主張します。この記述は文化相対主義の核心を正しく説明しています。
②【誤】
文化は「人々が生活する環境」と密接に関わって形成されると考えるため、「かかわりなく形成されている」という部分が誤りです。
③【誤】
文化相対主義の重要な点は、文化間に「優劣がない」と考えることです。「優劣がある」としている部分が根本的に誤りです。
④【誤】
各文化は、その社会にとって意味のある「固有の価値をもつ」と考えます。「価値をもたず」という部分が誤りです。
問2:正解③
<問題要旨>
コミュニタリアニズム(共同体主義)の代表的論者であるマイケル・サンデルの思想について、その内容を正確に把握しているかを問う問題です。「負荷なき自己」と「位置づけられた自己」、そして「共通善」というキーワードが理解の鍵となります。
<選択肢>
①【誤】
サンデルは、ロールズなどが想定する、共同体の価値観から切り離された自由な個人像(負荷なき自己)を批判しました。したがって、この前提が誤りです。
②【誤】
「負荷なき自己」という前提がサンデルの思想とは異なります。
③【正】
サンデルは、個人は特定の家族、共同体、国家、歴史といった文脈の中に「位置づけられた自己」であると主張します。私たちは、そうした共同体が持つ歴史や価値観を負っており、それらを参照しながら自己の善(生き方)を構想する存在であるとしました。そのため、共同体が目指すべき「共通善」を尊重し、それをめぐる議論に参加することが重要だと考えます。Kさんの「親の生まれ育った国の伝統をしっかりそのまま受け継ぎたい」という発言は、こうしたサンデルの思想と合致しています。
④【誤】
サンデルは、個人が共同体の「共通善」を尊重し、それに関わることを重視します。「共通善の価値に拘束しないようにすべき」という部分は、彼の思想とは逆の方向性です。
問3:正解④
<問題要旨>
会話文の論理的なつながりを読み解き、不適切な発言を指摘する問題です。会話の流れや発言者の意図を正確に把握し、論理的な矛盾や飛躍を見抜く力が求められます。
<選択肢>
①【正】
Jの発言を受けて、KはLさんに言った人物の意図を推測しています。「Lさん個人の経験が問題ならば、『外国人には』という一般化はしないはずだ」という指摘は、論理的に妥当です。
②【正】
Jは、「外国人」という理由だけで文化の理解を否定することの問題点を、仏教が外来文化であるという歴史的事実や、「外国人」という言葉に含まれる差別的なニュアンスを指摘することで論じており、論理的に妥当です。
③【正】
Kは、相手の主張の根拠を問うために「どういう状態になると、『わかった』と言えるのか」と問い返すことを提案しています。これは、相手の無根拠な断定を明らかにするための有効な反論であり、論理的に妥当です。
④【誤】
Kは、直前のJの「その人は、そもそも文化に関する知識の量や習得の度合いを問題にしているのではなさそうですね」という発言に「はい、多分、そうだと思います」と同意しています。それにもかかわらず、結論として「だからその発言には、『あなたはまだまだ勉強が足りてない』といったメッセージが込められている」と述べています。これは、「知識の量を問題にしていない」という直前の合意と、「勉強が足りない(=知識の量が足りない)」という結論が矛盾しています。したがって、この発言は論理的につながりません。
問4:正解⑥
<問題要旨>
教育における親の権利と子の権利、そして多文化共生社会のあり方をめぐる二つの対立する立場(A:文化的マイノリティの集団的権利を尊重する立場、B:個人の自律性を尊重するリベラルな立場)と、それらに対する反論を正しく結びつける問題です。現代政治哲学の論点を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①~⑤【誤】
立場と反論の組み合わせが誤っています。
⑥【正】
立場Aは、マイノリティ集団の文化や価値観の維持を尊重する、いわゆる多文化主義的な立場です。この立場に対しては、ウ「マイノリティ集団が相互に無関心ないし排他的になり、社会全体のまとまりが失われる(社会の断片化)」という反論がなされます。
立場Bは、子どもが将来、自分で生き方を選択できるような「自律的な個人」に育つことを重視する、リベラルな立場です。この立場に対しては、ア「『個人の自律』を絶対視すること自体が、西洋近代的な価値観(リベラリズム)の押し付けであり、文化的に中立ではない」という反論や、イ「マジョリティの価値観が押し付けられ、結果的にマイノリティの文化が衰退し、社会の多様性が損なわれる」という反論がなされます。
したがって、「立場A―ウ」「立場B―アとイ」という組み合わせが正しいです。
問5:正解③
<問題要旨>
多様な文化的・宗教的背景を持つ人々が共存するためのルール作り(合意形成)の難しさについて問う問題です。提示された解決策(聞き取りと多数決を組み合わせた方法)が持つ、前提段階での破綻の可能性と、手続きの過程で生じる問題点を、それぞれ論理的に指摘できるかが試されます。
<選択肢>
①【誤】
アが不適切です。解決策には、もし最多得票が複数ある場合は「抽選で決定する」とあるため、「生徒の票がばらばらに分かれてしまった」としても、メニューが決まらなくなることはありません。
②【誤】
アが不適切です。また、イの「食べられないもの」は、解決策の最初の段階で聞き取りを行い、候補から外すことになっているため、原則として無視されることはありません。
③【正】
ア:この解決策は「全ての生徒が食べられるものを洗い出して、そこから複数のメニューの選択肢を作る」ことを前提としています。しかし、生徒たちの食の制約(アレルギー、宗教上の禁忌など)が多岐にわたり、もし「生徒の食べられるものが重なり合わなかった」場合、つまり全員が共通して食べられるメニュー候補を一つも作れなかった場合、この解決策は投票に進むことすらできず、破綻してしまいます。「メニューを決めること自体ができなくなる」という指摘として正しいです。
イ:この解決策は、食べられないものを除いた後、最終的には多数決で決定します。多数決は、多数派の意見を優先する一方で、少数派の意見を切り捨てるという性質を持っています。そのため、ある生徒にとっては食べられるメニューではあっても、最も「食べたいもの」ではなかった、という不満が生じる可能性があります。手続き上、少数派の「食べたいもの」という選好は無視されることになるため、この指摘は正しいです。
④【誤】
イが不適切です。この解決策の手続きは、まさに「食べられないもの」を持つ生徒に配慮し、それを無視しないように設計されています。手続きの結果、無視される可能性があるのは、あくまで個人の「食べたい」という好みや希望(選好)です。