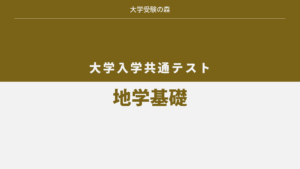解答
解説
第1問
問1:正解①
<問題要旨>
天体が大気を持つ条件と、惑星の分類に関する問題です。天体が大気を保持できるかどうかは、主に天体の質量(重力)と温度(太陽からの距離)によって決まります。質量が大きいほど重力が強く、大気を引きつけておく力が強くなります。また、太陽からの距離が遠いほど温度が低くなり、大気分子の熱運動が穏やかになるため、宇宙空間へ逃げ出しにくくなります。
<選択肢>
①【正】
文章a、bともに正しい記述です。
a:図1から、グループX(月、水星)は地球に比べて質量が著しく小さいことがわかります。質量が小さいと天体の重力も小さくなるため、気体分子を地表に引きつけておく力が弱く、大気は宇宙空間に逃げてしまいます。したがって、月や水星には大気がほとんど存在しません。
b:図1から、グループY(木星、土星)は太陽からの距離が地球よりもはるかに遠いことがわかります。太陽から遠いため、表面温度が非常に低くなります。水素やヘリウムのような軽い気体分子も、熱運動が穏やかになり、天体の重力に捉えられます。また、木星や土星は質量も非常に大きいため、これらの軽い気体からなる厚い大気を保持することができます。
②【誤】
文章aは正しいですが、文章bが誤りであるという選択肢です。上記のとおり、文章bも正しい記述です。
③【誤】
文章aが誤りであるという選択肢です。上記のとおり、文章aは正しい記述です。
④【誤】
文章a、bともに誤りであるという選択肢です。上記のとおり、両方とも正しい記述です。
問2:正解③
<問題要旨>
プレートテクトニクスにおける、プレートの衝突と沈み込みに関する問題です。特に、大陸プレートどうしが衝突する「衝突帯」が形成されるメカニズムを理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
海洋プレートは大陸プレートに比べて密度が大きいため、大陸プレートと衝突するとその下に沈み込みます。したがって、アは「大陸」が適切です。
②【誤】
海洋プレートが沈み込むのは密度が大きいためであり、温度が低いことは直接的な理由ではありません。また、アも不適切です。
③【正】
ヒマラヤ山脈のような大山脈(衝突帯)は、大陸プレートと大陸プレートが衝突することによって形成されます。大陸プレートを構成する大陸地殻は、マントルや海洋地殻に比べて密度が小さいため、マントルの中に沈み込みにくい性質があります。そのため、大陸プレートどうしがぶつかると、一方が他方の下に大きく沈み込むことはなく、圧縮されて隆起し、巨大な山脈を形成します。したがって、アには「大陸」、イには「密度が小さい」が入ります。
④【誤】
大陸プレートが沈み込みにくいのは、密度が小さいためであり、温度が低いためではありません。
問3:正解②
<問題要旨>
火成岩の分類についての問題です。火成岩は、組織(マグマの冷え方)と化学組成(特にSiO2の割合)によって分類されます。
・組織:斑状組織は火山岩(地表付近で急冷)、等粒状組織は深成岩(地下深部で徐冷)を示します。
・化学組成:SiO2の割合によって、少ない方から塩基性岩(~52%)、中性岩(52~66%)、酸性岩(66%~)に分類されます。
<選択肢>
①【誤】
Bは深成岩で塩基性岩なので斑れい岩、Cは深成岩で酸性岩なので花こう岩です。組合せが一致しません。
②【正】
A:斑状組織なので火山岩です。SiO2が59.59%なので中性岩に分類されます。火山岩の中性岩は安山岩です。
B:等粒状組織なので深成岩です。SiO2が48.24%なので塩基性岩に分類されます。深成岩の塩基性岩は斑れい岩です。
C:等粒状組織なので深成岩です。SiO2が70.18%なので酸性岩に分類されます。深成岩の酸性岩は花こう岩です。以上のことから、この組合せは正しいです。
③【誤】
Aは火山岩の中性岩なので安山岩です。斑れい岩ではありません。
④【誤】
Aは火山岩なので深成岩である斑れい岩や閃緑岩ではありません。
⑤【誤】
AのSiO2は59.59%(中性岩)なので、塩基性岩である玄武岩ではありません。
⑥【誤】
AのSiO2は59.59%(中性岩)なので、塩基性岩である玄武岩ではありません。
問4:正解②
<問題要旨>
火山の噴火によってもたらされる現象に関する知識を問う問題です。噴煙の到達高度と大気圏の構造、および火砕流の構成物を理解している必要があります。
<選択肢>
①【誤】
火砕流は火山砕屑物と「火山ガス」の混合物です。エが誤りです。
②【正】
ウ:地球の大気は、地表から対流圏(高度約10kmまで)、成層圏(高度約10~50km)、中間圏、熱圏と続きます。噴煙が高度20kmに達したということは、対流圏を突き抜けて成層圏に達したことを意味します。
エ:火砕流は、高温の火山砕屑物(火山灰、軽石、火山岩塊など)と火山ガスが一体となって、高速で火山の斜面を流れ下る現象です。したがって、火山砕屑物とともに流れるのは火山ガスです。
③【誤】
ウは成層圏が適切です。また、エも雨水ではなく火山ガスです。
④【誤】
ウは成層圏が適切です。
問5:正解②
<問題要旨>
代表的な堆積構造の写真を正しく同定する問題です。それぞれの堆積構造がどのような見た目であるかを理解しておく必要があります。
<選択肢>
①【誤】
Bは斜交葉理、Dは級化構造です。組合せが誤っています。
②【正】
A:地層の表面(層理面)に見られる、水流や波によって形成された波状の模様は、漣痕(リプルマーク)です。
B:地層の断面に見られる、内部の細かい縞模様(葉理)が地層全体の傾斜とは斜めに交わっている構造は、斜交葉理(クロスラミナ)です。
D:地層の断面で、下から上に向かって堆積物の粒の大きさが連続的に小さくなっている構造は、級化構造(級化層理)です。
Cは生物が這った跡などを示す生痕化石であり、設問の選択肢には含まれません。
したがって、この組合せは正しいです。
③【誤】
Bは斜交葉理、Cは生痕化石です。組合せが誤っています。
④【誤】
Aは漣痕、Cは生痕化石です。組合せが誤っています。
⑤【誤】
Cは生痕化石です。また、BとDの組合せも逆です。
⑥【誤】
Cは生痕化石です。組合せが誤っています。
問6:正解①
<問題要旨>
堆積構造から、それが形成された当時の水流の方向を推定できるかどうかを判断する問題です。
<選択肢>
①【正】
Aの漣痕(リプルマーク)は、特に流れの方向が一定の場合、非対称な形になります。風上側(流れのやってくる側)は緩やかに、風下側(流れの去っていく側)は急に傾斜するため、水流の方向を推定できます。
Bの斜交葉理(クロスラミナ)は、砂などが水流の風下側に運ばれて堆積することで形成されます。斜交している葉理の傾斜方向が、おおよその水流の方向を示します。
したがって、AとBはどちらも水流の方向の復元に利用できます。
②【誤】
Cの生痕化石は、生物の活動の痕跡であり、特定の水流の方向を示すとは限りません。
③【誤】
Dの級化構造は、粒の大きさの違いから地層の上下判定には利用できますが、水平方向の水流の向きを特定することはできません。
④【誤】
Cの生痕化石は水流の方向の推定には使えません。
⑤【誤】
Dの級化構造は水流の方向の推定には使えません。
⑥【誤】
Cの生痕化石、Dの級化構造ともに水流の方向の推定には使えません。
第2問
問1:正解④
<問題要旨>
放射冷却が起こる気象条件に関する問題です。放射冷却のメカニズムと、天気図から気象条件を読み取る能力が問われます。
<選択肢>
①【誤】
アには赤外線が入ります。地表は太陽から受けたエネルギーを赤外線の形で宇宙空間に放出しています。
②【誤】
アには赤外線が入ります。また、イもbが適切です。
③【誤】
イにはbが入ります。天気図aでは、日本の南岸に前線が停滞しており、地点Aの周辺も雲が多く湿っている可能性が高いです。雲は地表からの赤外線放射を吸収・再放射するため、気温の低下を妨げます。
④【正】
ア:夜間に地表から熱が奪われる現象は、地表が熱を電磁波(主に赤外線)の形で放出することによります。これを地球放射(赤外放射)といいます。
イ:放射冷却は、空が晴れていて風が弱い夜によく起こります。天気図を見ると、aでは日本の南に前線があり雲が多いと予想されるのに対し、bでは地点Aがすっぽりと高気圧に覆われています。一般に高気圧に覆われると下降気流が発生し、雲ができにくく晴天になります。また、等圧線の間隔も広く、風が弱い状態です。したがって、放射冷却がより強く起こるのはbの日です。
問2:正解①
<問題要旨>
地球全体の水収支と、それに伴う大気中の水蒸気輸送についての問題です。緯度別の降水量(P)と蒸発量(E)の差のグラフから、水蒸気がどの緯度帯からどの緯度帯へ輸送されているかを考察します。
<選択肢>
①【正】
グラフから、P-Eが正の領域(降水量>蒸発量)は、水蒸気が他の地域から供給されていることを意味します。一方、P-Eが負の領域(降水量<蒸発量)は、水蒸気が他の地域へ供給されていることを意味します。
・赤道付近:P-Eが正であり、水蒸気の流入超過地域です。
・中緯度帯(南北30°~40°付近):P-Eが負であり、水蒸気の流出超過地域です(亜熱帯高圧帯)。
・高緯度帯(南北60°付近):P-Eが正であり、水蒸気の流入超過地域です。
したがって、水蒸気は中緯度帯(P-Eが負)から、赤道(P-Eが正)と高緯度帯(P-Eが正)に向かって輸送されているはずです。この模式図は、北半球では中緯度から赤道へ南向き、高緯度へ北向きの輸送を、南半球では中緯度から赤道へ北向き、高緯度へ南向きの輸送を示しており、正しく表現しています。
②【誤】
北半球で常に北向き、南半球で常に南向きの輸送にはなりません。
③【誤】
輸送の向きが逆になっています。
④【誤】
①と全く逆の輸送を示しており、誤りです。
問3:正解①
<問題要旨>
海水の塩分に関する基本的な知識を問う問題です。塩分の定義(単位)と、塩分を変化させる要因について理解している必要があります。
<選択肢>
①【正】
ウ:塩分は、海水1kgに含まれる塩類の総量をグラムで表したもので、単位には‰(パーミル、千分率)が用いられます。外洋の平均塩分は、およそ35‰です。
エ:海水の塩分濃度は、淡水の出入りによって変化します。海水が凍結する際には、水分子が先に凍って氷(淡水に近い)になり、塩類は凍らずに周囲の海水中に残されます。その結果、残された海水の塩分は高くなります。逆に、海氷が融解したり、河川水が流入したりすると、淡水が加わるため塩分は低くなります。したがって、この組合せは正しいです。
②【誤】
海氷が融解すると、淡水が供給されるため塩分は低くなります。
③【誤】
塩分の単位は‰(パーミル)なので、3.5ではなく35が正しい数値です。3.5は%(パーセント、百分率)で表記する場合の数値です。
④【誤】
数値と現象の両方が誤っています。
第3問
問1:正解④
<問題要旨>
宇宙の誕生から現在までの歴史(宇宙史)の概要を理解しているかを問う問題です。宇宙の膨張と温度変化、そして「宇宙の晴れ上がり」と「太陽系の誕生」という二つの重要な出来事の前後関係を正しく把握している必要があります。
<選択肢>
①【誤】
宇宙は膨張によって温度が低くなりました。また、出来事の順序も逆です。
②【誤】
宇宙は膨張によって温度が低くなりました。
③【誤】
出来事の順序が逆です。太陽系の誕生(約46億年前)より、宇宙の晴れ上がりの方がはるかに昔の出来事です。
④【正】
ア・イ:宇宙は約138億年前にビッグバンで始まり、それ以来、膨張を続けています。断熱膨張により、宇宙全体の温度は低下してきました。したがって、アは「膨張」、イは「低く」です。
ウ・エ:ビッグバンから約38万年後、宇宙の温度が約3000Kまで下がると、電子が原子核に捕らえられて中性の原子が作られました。これにより、光が電子に散乱されずに直進できるようになりました。この出来事を「宇宙の晴れ上がり」といいます。一方、太陽系が誕生したのは、宇宙誕生から約92億年後(今から約46億年前)です。したがって、時系列は「宇宙の晴れ上がり」(ウ)が先で、「太陽系の誕生」(エ)が後になります。よってこの組合せが正しいです。
⑤【誤】
宇宙は膨張しています。
⑥【誤】
宇宙は膨張しており、温度は低くなりました。
⑦【誤】
宇宙は膨張しています。また、出来事の順序も逆です。
⑧【誤】
宇宙は膨張しています。
問2:正解③
<問題要旨>
「宇宙の晴れ上がり」がなぜ起こったのか、その物理的な原因を問う問題です。光が直進できるようになった理由を、宇宙の構成粒子の状態変化と関連付けて理解することが重要です。
<選択肢>
①【誤】
ヘリウム原子核の合成(ビッグバン元素合成)は、宇宙誕生後数分で起こった出来事であり、約38万年後の晴れ上がりよりもずっと前のことです。
②【誤】
陽子(水素の原子核)は、ビッグバン直後にはすでに存在していました。晴れ上がりの時期に陽子が増えたわけではありません。
③【正】
晴れ上がり以前の宇宙は、陽子やヘリウム原子核と、自由に飛び回る電子がプラズマ状態で混在していました。この自由電子が光(光子)を頻繁に散乱させるため、光はまっすぐ進むことができず、宇宙は「霧がかった」状態でした。宇宙の温度が約3000Kまで下がると、電子が原子核に捕らえられて中性の水素原子やヘリウム原子が形成されました。これにより、光を散乱させる自由電子の数が激減し、光が直進できるようになったのです。これが「宇宙の晴れ上がり」です。
④【誤】
これは「電離(イオン化)」と呼ばれる、晴れ上がりとは逆のプロセスです。晴れ上がり以前の宇宙がこの状態でした。
問3:正解①
<問題要旨>
私たちが住む銀河系(天の川銀河)の構造と、地球からの見え方についての問題です。太陽系が銀河系のどの部分に位置しているかを知っていることが前提となります。
<選択肢>
①【正】
オ:私たちの太陽系は、銀河系の中心(バルジ)から外れた、円盤部(ディスク)の中に位置しています。図ではAがその位置を示しています。
カ:私たちは銀河系の円盤の内部にいるため、円盤を内側から見渡すことになります。そのため、夜空には円盤に沿って星が密集して見える部分が、川のような「帯状」に広がって見えます。これが天の川です。渦巻き状の構造は、銀河系を真上や真下から見ないとわかりません。
②【誤】
地球から見た銀河系は「帯状」に見えます。
③【誤】
太陽系は円盤部(A)に位置しています。
④【誤】
太陽系は円盤部(A)に位置しており、見え方は「帯状」です。
第4問
問1:正解③
<問題要旨>
様々な自然現象や人為的現象がもつ、時間的・空間的なスケールを正しく対応させる問題です。それぞれの現象が、どのくらいの期間続き、どのくらいの範囲に影響を及ぼすかを大まかに把握している必要があります。
<選択肢>
①【誤】
Aは津波、Bは台風のスケールです。
②【誤】
Aは津波のスケールです。
③【正】
グラフの各領域に現象を当てはめていきます。
A:時間スケールが数時間(10⁻⁴年)、空間スケールが数百~数千km。これは、地震発生から数時間で沿岸に到達し、広い範囲に影響を及ぼす「津波」のスケールに合致します。
B:時間スケールが数日(10⁻²年)、空間スケールが数百~数千km。これは、発生から消滅まで数日間続き、大きな影響範囲をもつ「台風」のスケールに合致します。
C:時間スケールが1年程度、空間スケールが地球規模(1万km~)。これは、数か月から1年以上続き、太平洋全体から世界中に影響を及ぼす「エルニーニョ現象」のスケールに合致します。
D:時間スケールが数十年~100年以上、空間スケールが地球全体。これは、長期にわたって全球的に影響が及ぶ「人為起源の地球温暖化」のスケールに合致します。
したがって、この組合せは正しいです。
④【誤】
B、C、Dの当てはめが誤っています。
問2:正解②
<問題要旨>
地層の柱状図から過去の出来事(この場合は津波)を読み取り、地質学的な法則に基づいて考察する問題です。地層累重の法則や、堆積物とそれをもたらしたイベントの関係性を正しく理解できているかが問われます。誤った記述を選ぶ問題であることに注意が必要です。
<選択肢>
①【正】
「地層累重の法則」により、地層は(逆転していなければ)下に位置するものほど古く、上に位置するものほど新しく堆積します。これは正しい記述です。
②【誤】
この記述は誤りです。砂層は津波という非常に短い時間のできごと(イベント)によって堆積したものです。その厚さは津波の規模(運搬した砂の量)に依存します。一方、その直下の泥層は、前の津波から次の津波までの長い期間(この場合約100~150年)にわたって、平常時にゆっくりと堆積したものです。その厚さは、堆積期間の長さに比例します。津波の規模とその発生間隔に直接的な比例関係はないため、この記述は誤りです。
③【正】
泥層の厚さ(=津波の発生間隔)と、その直上の砂層の厚さ(=次の津波の規模)の間には、直接的な比例関係はありません。これは正しい記述です。
④【正】
柱状図の年代を見ると、砂層が堆積した年代の間隔は、1950-1850=100年、1850-1700=150年、1700-1600=100年、1600-1500=100年、1500-1400=100年となっており、約100年~150年の間隔であることがわかります。これは正しい記述です。
問3:正解②
<問題要旨>
地震活動とその被害に関する総合的な問題です。本震・前震・余震の関係、初期微動継続時間、液状化、土砂災害といったキーワードの正しい理解が求められます。誤った記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
初期微動継続時間(P波が到着してからS波が到着するまでの時間)は、震源からの距離にほぼ比例します。図を見ると、地点Xは地震bの震央よりも地震aの震央に近いです。震源の深さは同じなので、地点Xは震源距離も地震aのほうが短くなります。したがって、初期微動継続時間も地震aのほうが短くなります。これは正しい記述です。
②【誤】
この記述は誤りです。一連の地震活動において、最も規模(マグニチュード)の大きい地震を「本震」と呼びます。本震の前に起こる、それより小さい地震を「前震」、本震の後に起こる、それより小さい地震を「余震」と呼びます。この問題では、地震a(M6.5)の後に、より規模の大きい地震b(M7.0)が発生しているため、地震aは本震である地震bの「前震」と位置づけられます。「余震」ではありません。
③【正】
液状化現象は、水分を多く含んだ緩い砂地盤が、地震の強い揺れによって液体のようにふるまう現象です。地点Yは「旧河川」に位置しており、このような場所は埋め立てられた砂や泥でできていることが多く、地下水位も高いため、液状化が発生しやすい典型的な地形です。これは正しい記述です。
④【正】
地点Zは「急斜面の多い山地」に位置しています。地震の強い揺れは、山地の斜面を不安定にし、がけ崩れや地すべりなどの土砂災害を引き起こす大きな要因となります。これは正しい記述です。