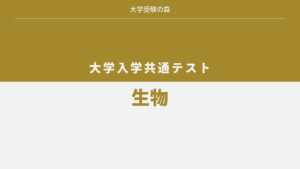解答
解説
第1問
問1:正解①
<問題要旨>
神経における刺激の強弱がどのように情報として伝達されるかを問う問題です。神経インパルスの発生と伝達に関する基本的な知識が求められます。
<選択肢>
①【正】
刺激が強いほど、より多くのニューロンが興奮の閾値に達して活動電位を発生させます(数の法則)。また、個々のニューロンにおいても、刺激が強いほど活動電位の発生頻度(単位時間あたりの回数)が高くなります(頻度の法則)。この二つの仕組みによって、刺激の強さの情報が伝えられます。したがって、アとイは両方とも関与しています。
②【誤】
イは関与しますが、アも関与するため、この組み合わせは不十分です。
③【誤】
イは関与しますが、ウとエは関与しません。個々のニューロンにおける興奮の伝導速度(ウ)や活動電位の大きさ(エ)は、刺激の強さによらず一定であり、「全か無かの法則」に従います。
④【誤】
アは関与しますが、ウは関与しません。
⑤【誤】
アは関与しますが、エは関与しません。
⑥【誤】
アとイの両方が関与するため、この組み合わせは不十分です。また、ウとエは関与しません。
問2:正解②
<問題要旨>
生物の進化の過程で生じた遺伝子の多型について、祖先型と比較して突然変異が起こった順序を推定する問題です。分子系統樹の考え方を用いて、最も節約的な(少ない変異回数で説明できる)経路を導き出す必要があります。
<選択肢>
①【誤】
この順序(SNP1→SNP2→SNP3)では、PAV→AAV→AVI→…となり、AAIがどのように生じたかを説明できません。
②【正】
ヒトとチンパンジーの共通祖先が持つ対立遺伝子がPAV(プロリン、アラニン、バリン)であったと考えられます。ここからヒトの多様性が生じたと仮定します。
最初の変異としてSNP1(プロリン[P]→アラニン[A])が起こると、PAVからAAVが生じます。現存する4種類の遺伝子のうち、PAV以外の3つはすべて49番目がアラニン[A]であることから、この変異が早期に起こったと考えるのが最も合理的です。
次に、AAV(アラニン、アラニン、バリン)からSNP3(バリン[V]→イソロイシン[I])が起こると、AAIが生じます。
さらに、AAI(アラニン、アラニン、イソロイシン)からSNP2(アラニン[A]→バリン[V])が起こると、AVIが生じます。
このPAV → AAV → AAI → AVIという一連の変異で、現存する4種類の対立遺伝子すべてを説明できます。したがって、突然変異はSNP1、SNP3、SNP2の順で起こったと考えるのが最も適当です。
③【誤】
SNP2が最初に起こるとPAVからPVVという遺伝子型が生じますが、これは表に存在しません。
④【誤】
SNP2が最初に起こるとPAVからPVVという遺伝子型が生じますが、これは表に存在しません。
⑤【誤】
SNP3が最初に起こるとPAVからPAIという遺伝子型が生じますが、これは表に存在しません。
⑥【誤】
SNP3が最初に起こるとPAVからPAIという遺伝子型が生じますが、これは表に存在しません。
問3:(1)正解⑤ (2)正解②
<問題要旨>
(1)アミノ酸配列の違い(一塩基多型)が、DNAのどの塩基の多型に由来するかを、遺伝暗号表を用いて特定する問題です。mRNAのコドンとDNAの塩基配列の関係を理解しているかが問われます。
(2)タンパク質のアミノ酸の位置から、mRNA上の塩基の位置を計算する問題です。コドンが3つの塩基で1つのアミノ酸を指定することを理解しているかが問われます。
<選択肢>
(1)
①【誤】
②【誤】
③【誤】
④【誤】
⑤【正】
SNP2は、262番目のアミノ酸がアラニン(A)かバリン(V)かの違いです。遺伝暗号表(表2)を見ると、アラニンのコドンはGCU, GCC, GCA, GCG、バリンのコドンはGUU, GUC, GUA, GUGです。1塩基の置換でアラニンとバリンが変化する組み合わせは、2番目の塩基がC⇔Uのいずれかの場合です(例:GCU ⇔ GUU)。
これはmRNA上の塩基配列です。問題ではDNAのセンス鎖の塩基を問われています。mRNAの塩基とDNAのセンス鎖の塩基の関係は、A→A, U→T, G→G, C→Cです。したがって、mRNAでのC⇔Uの置換は、DNAセンス鎖でのC⇔Tの置換に対応します。
⑥【誤】
(2)
①【誤】
②【正】
翻訳は開始コドンから始まり、3つの塩基で1つのアミノ酸を指定します。したがって、n番目のアミノ酸を指定するコドンは、mRNAの開始コドンから数えて(3n-2)番目、(3n-1)番目、3n番目の塩基で構成されます。
SNP2は262番目のアミノ酸に関する多型なので、これを指定するコドンは、(3×262-2) = 784番目の塩基から始まります。
(1)の考察から、この多型はコドンの2番目の塩基の置換によるものであることがわかっています。したがって、SNP2の位置は、コドンの2番目にあたる785番目の塩基となります。
③【誤】
④【誤】
⑤【誤】
⑥【誤】
問4:正解⑥
<問題要旨>
遺伝子型と表現型(PTC感受性)の関係を示したグラフを読み取り、SNP(一塩基多型)がタンパク質の機能に与える影響の大きさと、対立遺伝子の優劣関係を考察する問題です。
<選択肢>
①【誤】
②【誤】
③【誤】
④【誤】
⑤【誤】
⑥【正】
ア:SNPが機能へ与える影響の大きさを考えます。図1のグラフから、各遺伝子型におけるPTC感受性の値を比較します。
・SNP1(PとAの違い):PAV/PAV(約1.0)とAAV/AAV(約0.8)を比較すると、差が大きい。
・SNP2(AとVの違い):AAV/AAV(約0.8)とAVI/AVI(約0.3)を比較すると、差が大きい。
・SNP3(IとVの違い):AAI/AAI(約0.7)とAAV/AAV(約0.8)を比較すると、差が最も小さい。
したがって、受容体タンパク質の機能への影響が最も小さいのは、PTC感受性の差が最も小さいSNP3に対応するアミノ酸の変化と考えられます。
イ:対立遺伝子AVIの優劣関係を考えます。「低感受性」を感受性0.5以下と定義します。
・AVI/AVIの個体は感受性が約0.3であり、低感受性です。
・PAV/PAVの個体は感受性が1.0であり、高感受性です。
・両方の対立遺伝子を持つヘテロ接合体AVI/PAVは、感受性が約0.9であり、高感受性の表現型を示しています。
ヘテロ接合体において高感受性という形質が現れているため、低感受性という形質は現れていない(隠れている)ことになります。したがって、対立遺伝子AVIによる低感受性は潜性(劣性)形質であるといえます。
よって、アにSNP3、イに潜性(劣性)が入る⑥が正解です。
第2問
問1:正解①、⑥
<問題要旨>
タンパク質の構造や機能、アミノ酸の性質に関する基本的な知識を問う正誤問題です。複数の正しい記述を選ぶ必要があります。
<選択肢>
①【正】
タンパク質の一次構造とはアミノ酸の配列順序のことです。これは、mRNAの塩基配列(コドン)によって指定されるため、この記述は正しいです。
②【誤】
アミノ酸は、tRNAの3’末端にあるアミノ酸結合部位に結合してリボソームへ運ばれます。アンチコドンは、mRNAのコドンと相補的に結合する部分です。
③【誤】
ペプチド結合は、一方のアミノ酸のカルボキシ基(-COOH)と、もう一方のアミノ酸のアミノ基(-NH2)の間で水が1分子とれて形成されます。側鎖は関与しません。
④【誤】
βシート構造は、1本または複数本のポリペプチド鎖が平行または逆平行に並び、鎖の間で水素結合が形成されることによってできるシート状の構造です。αヘリックス構造が並んでできるわけではありません。
⑤【誤】
四次構造は、複数のポリペプチド鎖(サブユニット)が集合して形成される高次の立体構造です。一つのポリペプチド鎖内で完結する構造ではありません。
⑥【正】
生体膜には、チャネルや輸送体、受容体など、脂質二重層を貫通して存在する膜貫通タンパク質が多数存在します。
⑦【誤】
アミノ酸は、脱アミノ反応によってアミノ基が除去されると有機酸となり、クエン酸回路などに取り込まれて呼吸基質として利用されることがあります。
問2:正解③
<問題要旨>
遺伝子組換え技術におけるマーカー遺伝子を利用した選抜方法の原理を理解しているかを問う問題です。栄養要求性変異株の性質を利用した実験系の読解力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
②【誤】
③【正】
この実験では、ロイシンを合成できない変異体L(ロイシン要求性株)を用いています。ここに、外来遺伝子と共に「正常なロイシン合成酵素遺伝子」を組み込んだプラスミドを導入します。
・プラスミドが導入された細胞:ロイシン合成酵素遺伝子を持つため、自らロイシンを合成できます。
・プラスミドが導入されなかった細胞:ロイシンを合成できません。
したがって、培養する培地としてロイシンを【ア:含まない】培地(最小培地)を用いれば、プラスミドが【イ:入った】細胞だけがロイシンを合成して増殖することができます。これにより、目的の遺伝子が導入された細胞だけを選抜できます。
④【誤】
問3:(1)正解④ (2)正解④
<問題要旨>
(1)生物間の相互作用に関する仮説を検証するための実験計画と、その結果予測を論理的に考える問題です。対照実験の考え方が重要になります。
(2)酵素の活性調節(アロステリック阻害)と、タンパク質が部分的に分解された場合の影響について考察する問題です。酵素の構造と機能の関係を理解しているかが問われます。
<選択肢>
(1)
①【誤】
②【誤】
③【誤】
④【正】
仮説:「植物AのTD酵素は、幼虫Sのトレオニン吸収を減らし、成長を抑制する」
・ウ:変異体MはTD酵素を合成できません。そのため、変異体Mの葉を食べた幼虫Sの消化管内ではトレオニンが分解されず、野生株の葉を食べた場合よりも多く吸収できます。したがって、体重の増加は【速くなる】と予想されます。
・エ:変異体Mの葉(TD酵素なし)にTD酵素を添加して与えると、野生株を食べた場合と同様にトレオニンが分解されます。したがって、変異体Mの葉のみを与えた場合(速く成長する)と比べて、体重の増加は【遅くなる】と予想されます。
・オ:野生株の葉を食べるとTD酵素によってトレオニンが分解され、成長が抑制されます。この抑制効果を相殺し、体重増加を速くするためには、分解される分を補うために【トレオニン】を追加で与えるのが有効だと考えられます。
以上の考察から、ウ「速くなる」、エ「遅くなる」、オ「トレオニン」の組み合わせが最も適当です。
⑤【誤】
⑥【誤】
⑦【誤】
⑧【誤】
(2)
①【誤】
イソロイシンによる阻害は非競争的阻害(アロステリック阻害)であり、阻害物質であるイソロイシンは活性部位ではなくアロステリック部位に結合します。
②【誤】
アロステリック阻害は、最終産物(イソロイシン)の濃度に依存して起こります。基質(トレオニン)の濃度が高くても、イソロイシンの濃度が高ければ阻害は起こります。
③【誤】
幼虫Sの消化管内では、TD酵素はアロステリック部位を失っているため、イソロイシンによる調節を受けません。反応速度は基質であるトレオニンの濃度に依存しますが、一般的に基質濃度が低くなれば反応速度は低下します。上昇することはありません。
④【正】
幼虫Sの消化管内では、TD酵素はアロステリック部位を失い、イソロイシンによるフィードバック阻害を受けなくなります。そのため、触媒作用は保たれたまま、イソロイシンの濃度に関係なくトレオニンの分解反応を触媒し続けると考えられます。
第3問
問1:正解③
<問題要旨>
生態系における生物種の共存の仕組みに関する基本的な知識を問う問題です。競争、捕食、ニッチ、すみ分け、食い分けといった概念の理解が求められます。
<選択肢>
①【正】
捕食者と被食者の関係では、両者の個体数が周期的に変動しながら共存する例が知られています。これは適当な記述です。
②【正】
同じ場所に生息していても、利用する食物資源が異なる「食い分け」を行うことで、種間の競争が緩和され、共存が可能になります。これは適当な記述です。
③【誤】
ニッチ(生態的地位)とは、生物種が利用する食物、生息場所、活動時間などの様々な環境要因を総合したものです。ニッチの重なりが大きいほど、資源をめぐる種間競争が激しくなるため、競争的排除が起こりやすくなり、共存はむしろ難しくなります。したがって、この記述は適当ではありません。
④【正】
競争の結果、利用する生息場所をずらす「すみ分け」が起こり、競争が緩和されて共存することがあります。これは適当な記述です。
問2:正解②
<問題要旨>
森林の光環境の季節変化と、そこに生育する草本植物の光合成や呼吸の特性との関係を、図と表から読み取り、考察する問題です。複数の資料から情報を統合して判断する能力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
アは正しい記述ですが、イは誤った記述です。
②【正】
・ア:図1から、種Aは林床が明るい春(4〜5月)に緑葉をつけていることがわかります。表1から、この時期の種Aの最大光合成速度は0.68と非常に高い値を示します。これは、高木層の葉が展開する前の強い光を有効に利用している戦略と考えられ、正しい記述です。
・ウ:表1から、種Bの最大光合成速度は、林冠の樹木が葉をつけている夏(0.17)では、葉をつけていない春(0.30)や秋(0.24)に比べて小さいことがわかります。これも正しい記述です。
したがって、アとウの組み合わせであるこの選択肢が正解です。
③【誤】
アは正しい記述ですが、エは誤った記述です。
④【誤】
イは誤った記述です。
⑤【誤】
イは誤った記述です。
⑥【誤】
エは誤った記述です。
(個々の記述の正誤)
・ア【正】上記参照。
・イ【誤】表1を見ると、種Bの最大光合成速度は夏に0.17であり、種Aの春の0.68よりもはるかに低い。強い光を当てても種Aと同程度の光合成はできません。
・ウ【正】上記参照。
・エ【誤】種Bの(最大光合成速度/呼吸速度)の比を計算すると、春:0.30/0.015=20、夏:0.17/0.009≒18.9、秋:0.24/0.023≒10.4となり、季節によって大きく変化しています。
問3:正解①
<問題要旨>
植物の葉に含まれるクロロフィルやルビスコの量が、季節的な光環境の変化にどのように適応しているかを、複数の表と図から考察する問題です。光合成における光化学系(光捕集)とカルビン・ベンソン回路(CO2固定)の役割分担の理解が鍵となります。
<選択肢>
①【正】
・ア、イ:図1から、林床が【ア:薄暗い】のは夏、林床が【イ:明るい】のは春や秋です。表2を見ると、種Bは薄暗い夏にクロロフィルの量が多く(0.44)、明るい春にはクロロフィルの量が少ない(0.28)ことがわかります。一方、ルビスコの量は薄暗い夏に少なく(0.50)、明るい春には多い(1.5)です。
・ウ:クロロフィルは光エネルギーを吸収する役割、ルビスコはCO2を固定し、最大光合成速度を決定する主要因の一つです。薄暗い環境では、少ない光を効率よく集めるために光捕集系(クロロフィル)を増やし、光が強い環境では、豊富な光エネルギーを利用してCO2を効率よく固定するためにカルビン・ベンソン回路の酵素(ルビスコ)を増やすという適応戦略が考えられます。これらの量は、【最大光合成速度】の変化に影響します。
以上のことから、この選択肢が最も適当です。
②【誤】
ウが「呼吸速度」となっている点が誤りです。
③【誤】
アとイが逆になっています。
④【誤】
アとイが逆であり、ウも誤りです。
問4:正解②、⑥
<問題要旨>
植物個体全体の乾燥重量(バイオマス)の季節変化を示したグラフを読み取り、光合成による生産と呼吸による消費のバランス(物質収支)を考察する問題です。葉だけでなく、根や茎などの非光合成器官の呼吸も考慮する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
7月以降に乾燥重量が減少するのは、光合成量が個体全体の呼吸量を下回ったためであり、「光合成ができない」わけではありません。光補償点を下回る光環境になったと考えられます。
②【正】
6月以降、林冠が閉じて林床が暗くなると、葉の光合成による有機物生産量が減少します。一方で、葉、茎、根といった個体全体(非光合成器官を含む)は呼吸によって有機物を消費し続けます。個体全体の総光合成量が総呼吸量を下回ると、貯蔵していた有機物が消費され、個体の乾燥重量は減少します。これは妥当な説明です。
③【誤】
図2を見ると、翌年4月の乾燥重量(y軸の値)は、種Aも種Bも前年の緑葉出現時の値(相対値1)より大きくなっています。
④【誤】
種Aと種Bでは、緑葉が出現する時期や春先の成長速度が異なります。この違いが、その後の成長に影響し、6月時点での乾燥重量の差として現れています。緑葉が出現する時期とは無関係ではありません。
⑤【誤】
図2のグラフの傾きは成長速度を表します。種Bは、林冠の樹木が葉を広げている時期(6月〜11月)よりも、葉を落としている時期(11月〜翌4月)の方が傾きが急であり、成長速度が速いことがわかります。
⑥【正】
図2で、種Bは林冠の樹木が葉を広げている時期(6月〜11月)においても、乾燥重量が増加し続けています。これは、弱い光環境下でも、呼吸による消費量を上回る物質生産(純生産)ができていることを示しています。
第4問
問1:正解⑤
<問題要旨>
動物の配偶子形成、特に卵形成における減数分裂の過程でのDNA量と核相の変化についての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
アは正しい記述ですが、イは誤った記述です。
②【誤】
アは正しい記述ですが、ウは誤った記述です。
③【誤】
イ、ウともに誤った記述です。
④【誤】
ウは誤った記述です。
⑤【正】
・イ:G1期の卵原細胞のDNA量を2とします。DNA複製後の一次卵母細胞のDNA量は4になります。減数第一分裂が完了すると、一つの二次卵母細胞と一つの第一極体が生じ、それぞれのDNA量は2となります。したがって、第一極体に含まれるDNA量は、G1期の卵原細胞のDNA量と同量であり、この記述は正しいです。
・エ:二次卵母細胞は減数第二分裂の過程にある細胞で、核相はn、DNA量は2です。G1期の卵原細胞は核相2n、DNA量2です。したがって、二次卵母細胞にはG1期の卵原細胞と同量のDNAが含まれるという記述は正しいです。
⑥【誤】
イは正しい記述ですが、ウは誤った記述です。
(個々の記述の正誤)
・ア【誤】一つの卵原細胞から、減数分裂を経て1個の卵と、通常2個または3個の極体が形成されます。4個ではありません。
・イ【正】上記参照。
・ウ【誤】一次卵母細胞のDNA量は卵の4倍ですが、DNA複製後の状態なので核相は2n(複相)です。4nではありません。
・エ【正】上記参照。
問2:正解③
<問題要旨>
胚発生における誘導の仕組みについて、シグナル伝達物質(タンパク質A、B)の働きを元に、人為的な操作によって生じる結果を論理的に推測する問題です。原因と結果の因果関係を正確にたどる能力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
操作1では全てが腹側中胚葉になります。これは、背側を誘導するタンパク質Bの濃度が胚全体で低くなったことを意味します。タンパク質Aの濃度が高くなると、むしろタンパク質Bの濃度も高くなり、背側中胚葉が誘導されるはずなので、記述は逆です。
②【誤】
操作1の結果から、タンパク質Bの濃度は胚全体で低くなったと考えられます。背側で高くなるという記述は矛盾します。
③【正】
操作2では全てが背側中胚葉になります。これは、背側を誘導するタンパク質Bが胚全体で高濃度になったことを意味します。タンパク質Bの発現はタンパク質Aによって活性化されるため、この現象は、もともと背側に局在していたタンパク質Aが胚全体に分布するように操作された結果であると推測するのが最も合理的です。
④【誤】
操作2の結果から、タンパク質Bの濃度は胚全体で高くなったと考えられます。減少するという記述は矛盾します。
問3:正解①、④
<問題要旨>
神経誘導のメカニズムに関する実験結果を解釈し、関与するタンパク質(C、D)の働きを推論する問題です。複数の実験結果を比較し、対照実験の意味を理解して「抑制の抑制」という複雑な制御関係を読み解く必要があります。
<選択肢>
①【正】
実験1(操作なし→表皮)と実験2(遺伝子Cの発現阻害→神経)を比較します。タンパク質Cを作れなくすると、本来なら表皮になるはずの外胚葉が神経に分化しました。このことから、タンパク質Cには、外胚葉が神経へ分化するのを抑制し、表皮へと分化させる働きがあると考えられます。したがって、この記述は正しいです。
②【誤】
実験1(操作なし→表皮)と実験3(タンパク質Dを添加→神経)を比較します。タンパク質Dを加えることで、分化する組織が表皮から神経に変わっています。したがって、タンパク質Dは外胚葉の表皮への分化に影響を与えています。
③【誤】
実験結果から、タンパク質Cは神経への分化を「抑制」する働きがあります。「促進」ではありません。
④【正】
問題文に「タンパク質Dはタンパク質Cに結合」するとあります。実験結果から、Cは神経分化を抑制し、Dは神経分化を誘導(Cの抑制を解除)すると考えられます。つまり、DはCに結合することでCの働き(神経分化抑制作用)を阻害していると推論できます。したがって、この記述は正しいです。
⑤【誤】
タンパク質CとDは協働して働くのではなく、DがCの働きを抑制するという拮抗的な関係にあります。
⑥【誤】
タンパク質Dの働きは、タンパク質Cによって促進されるのではなく、むしろタンパク質Cの働きを抑制することです。
第5問
問1:正解②
<問題要旨>
イネの種子の発芽における、胚、胚乳、糊粉層の役割と、植物ホルモンであるジベレリンの働きに関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
イの「デンプンの合成」が誤りです。発芽時にはデンプンを分解します。
②【正】
種子が吸水すると、【ア:胚】でジベレリンが合成されます。ジベレリンは【イ:糊粉層】に働きかけ、デンプン分解酵素であるアミラーゼの合成を誘導します。アミラーゼは【ウ:胚乳】に分泌され、胚乳に蓄えられたデンプンをグルコースに分解します。このグルコースが胚に供給され、発芽のエネルギー源として利用されます。
③【誤】
イの「DNAの複製」が誤りです。ジベレリンが直接誘導するのはアミラーゼの合成です。
④【誤】
ア、イ、ウの全てが誤りです。ジベレリンは胚で合成されます。
⑤【誤】
アとウが誤りです。
⑥【誤】
ア、イ、ウの全てが誤りです。
問2:正解②
<問題要旨>
イネの開花を制御する光周性とフロリゲンの関係について、品種による違いを示すグラフを読み解き、北海道という環境への適応を考察する問題です。
<選択肢>
①【誤】
カが「長日」である点が不適当です。
②【正】
・エ:図2のグラフを見ると、本州型のイネは明期が13時間を超えるとフロリゲン遺伝子のmRNA量が急激に減少するのに対し、北海道型のイネは明期が【長い】(例:14時間)条件でも、本州型よりはるかに多いmRNA量を維持しています。
・オ:フロリゲンは花芽形成を促進するホルモン(花成ホルモン)です。そのmRNA量が多いということは、フロリゲンが多く作られ、【花芽の形成が早く】なることを意味します。これにより、夏の短い北海道でも、寒くなる前に種子を実らせることができます。
・カ:本州型のイネは、日長が短くならないと開花しない典型的な短日植物です。一方、北海道型は、比較的日長が長くても開花できる性質を獲得しています。これは、日長に対する応答性が鈍くなった、つまり【中性】植物の性質に近づいたと考えるのが最も適当です。
③【誤】
オ、カが不適当です。フロリゲンは植物体全体の成長ではなく花芽形成を直接促進します。
④【誤】
オが不適当です。
⑤【誤】
エ、カが不適当です。
⑥【誤】
エが不適当です。
⑦【誤】
エ、オ、カの全てが不適当です。
⑧【誤】
エ、オが不適当です。
問3:正解③
<問題要旨>
交配による品種改良の過程と、その結果得られる「純系」の遺伝的な特徴について問う問題です。
<選択肢>
①【正】
「ゆめぴりか」は純系なので、体細胞である胚の遺伝子構成はホモ接合です。そこから作られる配偶子(花粉)も、減数分裂を経ても遺伝情報は同一になります。これは適当な記述です。
②【正】
純系では相同染色体上の対立遺伝子が同一(例:AA)なので、減数分裂の際に乗換えが起きても、交換される遺伝子は同じです。そのため、結果として生じる配偶子の遺伝情報はすべて同一になります。これは適当な記述です。
③【誤】
「ゆめぴりか」は、二つの親品種「ほしたろう」と「北海287号」を交配し、その後代から選抜を繰り返して育成された品種です。この過程で、両親の遺伝子は染色体の乗換えや分離によって組み換えられます。したがって、「ゆめぴりか」は両親の遺伝子の一部を受け継いでいますが、「全ての遺伝情報」を両方持っているわけではありません。これは適当でない記述です。
④【正】
「純系」とは、ほとんどの遺伝子座がホモ接合になっている系統を指します。そのホモ接合になっている対立遺伝子は、元をたどれば「ほしたろう」または「北海287号」に由来するものです。これは適当な記述です。
問4:正解④
<問題要旨>
植物の重力屈性におけるオーキシンの役割について、一連の実験結果から論理的に推論を導き出す問題です。実験の目的と結果から、どの器官が重力を感知し、どの器官がオーキシンを供給しているのかを特定する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
②【誤】
③【誤】
④【正】
・ア:実験3では、子房を切除し、オーキシンを子房柄の切断面に「一様に」与えています。それでも正の重力屈性が起きたということは、子房柄自身が重力の方向を感知し、オーキシンの濃度勾配を自ら作り出したことを意味します。よって、この推論は正しいです。
・イ:実験1(子房あり→屈性あり)と実験2(子房なし→屈性なし)を比較すると、子房の有無が屈性の有無を決定しています。また、実験3でオーキシンを外部から補うと屈性が回復することから、子房が屈性に必要な量のオーキシンを合成し、子房柄に供給していると考えられます。よって、この推論は正しいです。
・ウ:実験3でオーキシンを「一様に」与えても屈性が起きることから、オーキシンの分布の変化(偏り)は子房での輸送の変化ではなく、子房柄自身で起きると考えられます。よって、この推論は誤りです。
正しい推論はアとイであり、これらを過不足なく含む④が正解です。
⑤【誤】
⑥【誤】
⑦【誤】
問5:正解①、⑤
<問題要旨>
通常の茎の「負の重力屈性」と、ラッカセイの子房柄の「正の重力屈性」のメカニズムの違いを、オーキシンの濃度分布や組織の感受性といった複数の観点から考察する問題です。
<選択肢>
キ・ク
①【正】
一般に、植物の茎を水平に置くと、オーキシンは重力の影響で下側に多く移動します。その結果、下側のオーキシン濃度が【キ:高く】なります。茎の細胞は、オーキシン濃度が高いほど伸長が促進されるため、下側の細胞の伸長速度が上側よりも【ク:大きく】なり、結果として茎は上向きに曲がります(負の重力屈性)。
②【誤】
③【誤】
④【誤】
ケ・コ
⑤【正】
子房柄が茎とは逆の「正の重力屈性(下向きに曲がる)」を示す理由を考えます。
・可能性1:オーキシンの分布が茎と同じ(下側が高い)と仮定した場合。下側の細胞伸長が上側よりも抑制されれば、下向きに曲がります。オーキシンには最適濃度があり、濃度が高すぎると伸長を阻害する作用があります。もし子房柄全体のオーキシン濃度が茎よりも【ケ:高い】とすると、上側は伸長に適した濃度でも、より濃度の高い下側は最適濃度を超えて伸長が抑制される、という説明が可能です。
・可能性2:同様に、もし子房柄の細胞がオーキシンに対して茎よりも【コ:高い】感受性を持つとすると、茎では伸長を促進する程度の濃度でも、子房柄にとっては高すぎて伸長が抑制される濃度域に入ってしまう、という説明が可能です。
どちらの可能性も、正の重力屈性を説明できます。
⑥【誤】
⑦【誤】
⑧【誤】