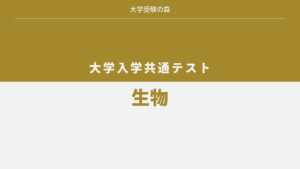解答
解説
第1問
問1:正解①
<問題要旨>
DNAの塩基配列に起こる突然変異のうち、タンパク質のアミノ酸配列に変化を及ぼさない可能性があるものを選択する問題です。コドンとアミノ酸の関係(特に、複数のコドンが同じアミノ酸を指定する「縮重」)についての理解が問われます。
<選択肢>
①【正】
ⓐのみ。1塩基が他の塩基に置き換わる「置換」が起きても、翻訳されるアミノ酸が変化しない場合があります。これは、多くの種類のアミノ酸が複数のコドンによって指定されているためです(コドンの縮重)。例えば、フェニルアラニンを指定するコドンはUUUとUUCの2種類があり、DNAレベルでAAAがAAGに置換されても、翻訳されるアミノ酸は同じフェニルアラニンです。したがって、ⓐはアミノ酸配列が変化しない場合があるものに該当します。ⓑの「挿入」とⓒの「欠失」は、1塩基であってもコドンの読み枠をずらしてしまう(フレームシフト突然変異)ため、それ以降のアミノ酸配列が大きく変化します。よって、ⓐのみが適切です。
②【誤】
ⓑのみ。上記①の解説の通り、1塩基の挿入はフレームシフトを引き起こすため、アミノ酸配列は必ず変化します。
③【誤】
ⓒのみ。上記①の解説の通り、1塩基の欠失はフレームシフトを引き起こすため、アミノ酸配列は必ず変化します。
④【誤】
ⓐとⓑ。ⓑは不適切です。
⑤【誤】
ⓐとⓒ。ⓒは不適切です。
⑥【誤】
ⓑとⓒ。両方とも不適切です。
⑦【誤】
ⓐ、ⓑ、ⓒ。ⓑとⓒは不適切です。
問2:正解③
<問題要旨>
異常な立体構造をもつタンパク質を修復する「シャペロン」の働きについて問う問題です。タンパク質の一次構造から高次構造までの各構造と、それらが変化する要因を正しく理解しているかがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
タンパク質の一次構造とはアミノ酸の配列のことです。これはDNAの塩基配列によって決まっており、シャペロンがアミノ酸の配列自体を修復することはできません。
②【誤】
ペプチド結合はアミノ酸同士をつなぐ共有結合で、一次構造を形成します。シャペロンは切断されたペプチド結合を再結合させる機能はありません。
③【正】
pHの変化は、タンパク質を構成するアミノ酸側鎖のイオン状態を変化させ、分子内の静電的な引力や反発力のバランスを崩します。これにより、タンパク質の立体構造(高次構造)が変化(変性)することがあります。酵素の活性部位も特定の立体構造によって機能するため、pH変化で構造が変わり活性を失うことがあります。シャペロンは、このようにして崩れた立体構造を、正しい形に折りたたむ(フォールディング)のを助ける働きがあるため、修復できる可能性があります。
④【誤】
補酵素は、タンパク質である酵素の働きを助ける低分子の有機物で、タンパク質そのものではありません。代謝の過程で化学的に変化(酸化や還元など)しますが、これを修復するのはシャペロンの役割ではありません。
問3:(1)正解ア・イ③ ウ・エ⑨
<問題要旨>
遺伝子からmRNAが作られ、タンパク質に翻訳される一連の流れについて、実験結果から考察する問題です。選択的スプライシング、フレームシフト突然変異、コドンの読み枠といった複数の概念を統合して考える必要があります。
<選択肢>
ア・イ
①【誤】
ア:除去されたmRNA領域の塩基数は、通常時(1160塩基)と高温時(1134塩基)の差である26塩基です。図1からエキソン3が26塩基対であるため、除去されたのはエキソン3と判断できます。イ:選択的スプライシングは特定のエキソンを除く処理であり、残りのエキソンの塩基配列を変えるものではないため、「同じ」配列です。したがって、アが「エキソン2」である点が誤りです。
②【誤】
上記①の解説の通り、アが「エキソン2」、イが「異なる」である点が誤りです。
③【正】
ア:上記①の解説の通り、除去されたのは「エキソン3」です。イ:残りの領域の塩基配列は「同じ」です。両方とも正しいため、この選択肢が正解です。
④【誤】
上記①の解説の通り、イが「異なる」である点が誤りです。
⑤【誤】
上記①の解説の通り、アが「エキソン4」である点が誤りです。
⑥【誤】
上記①の解説の通り、アが「エキソン4」、イが「異なる」である点が誤りです。
ウ・エ
⑦【誤】
ウ:エキソン3(26塩基)が除去されると、それ以降(3’末端側)のコドンの読み枠がずれます(26は3の倍数でないため)。したがって、ウは「3’」です。エ:翻訳されるアミノ酸は172個なので、翻訳される塩基数は172×3=516塩基です。開始コドンはエキソン1のATGです。エキソン1の翻訳領域(143塩基)、エキソン2(240塩基)、エキソン4(80塩基)を足し合わせると、143+240+80=463塩基となります。516塩基目はその次のエキソン5(71塩基)の領域内にあるため、新たな終止コドンはエキソン5に生じたと考えられます。したがって、ウが「5’」である点が誤りです。
⑧【誤】
上記⑦の解説の通り、ウが「5’」、エが「エキソン6」である点が誤りです。
⑨【正】
上記⑦の解説の通り、ウは「3’」、エは「エキソン5」であり、両方とも正しいです。
⑩【誤】
上記⑦の解説の通り、エが「エキソン6」である点が誤りです。
問3:(2)正解⑧
<問題要旨>
実験結果を解釈し、支持される仮説と、その仮説をさらに検証するための適切な実験計画を選択する問題です。実験系の目的(プロモーター活性=転写の促進をGFPの蛍光で検出していること)を正確に理解することが重要です。
<選択肢>
①【誤】
仮説ⓐ:実験結果は転写レベルの変化を示唆しており、タンパク質の分解については何も分かりません。実験ⓔ:タンパク質間結合を調べる実験であり、転写促進の検証には不適切です。
②【誤】
仮説ⓐは不適切です。
③【誤】
仮説ⓑ:実験結果は転写レベルの変化を示唆しており、タンパク質の分解については何も分かりません。実験ⓔも不適切です。
④【誤】
仮説ⓑは不適切です。
⑤【誤】
仮説ⓒ:タンパク質Xuを導入しても蛍光は見られなかったため、XuがmRNA合成を促進するという仮説は実験結果に反します。
⑥【誤】
仮説ⓒは不適切です。
⑦【誤】
実験ⓔは不適切です。支持される仮説はⓓ「タンパク質Xsは、シャペロンAのmRNAの合成を促進する」です。これを検証するには、転写因子であるタンパク質Xsが、標的遺伝子(シャペロンA)の転写を調節するDNA領域(プロモーターや転写調節領域)に結合するかを直接調べる実験ⓕが適切です。実験ⓔはタンパク質分解に関する仮説の検証にはなり得ますが、転写促進の検証にはなりません。
⑧【正】
実験結果は、タンパク質Xsが存在するときにシャペロンA遺伝子のプロモーターが活性化し、転写が促進されることを示しています。これは仮説ⓓ「タンパク質Xsは、シャペロンAのmRNAの合成を促進する」を支持します。この仮説をさらに検証するには、タンパク質Xsが転写因子としてシャペロンA遺伝子のプロモーターや転写調節領域に直接結合するかを調べる実験ⓕが最も適しています。したがって、仮説ⓓと実験ⓕの組み合わせが正解です。
第2問
問1:正解⑥
<問題要旨>
光合成と呼吸における電子伝達系の類似点と相違点に関する問題です。それぞれの反応が細胞のどこで起こり、何が電子を供給し、結果としてどこにプロトン(H+)が蓄積するのかを正確に覚えているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
ア:葉緑体では、チラコイド膜での電子伝達系の働きにより、ストロマからチラコイドの内側にH+が輸送されるため、H+濃度は「チラコイドの内側」で高くなります。ウ:光合成の電子伝達系への最初の電子の供給源は「水(H2O)」です。
②【誤】
アが「ストロマ」、ウが「O2」である点が誤りです。
③【誤】
アが「ストロマ」、イが「マトリックス」(正しくは内膜と外膜の間)、ウが「O2」である点が誤りです。
④【誤】
アが「ストロマ」、イが「マトリックス」である点が誤りです。
⑤【誤】
ウが「O2」である点が誤りです。
⑥【正】
ア:葉緑体ではH+は「チラコイドの内側」に蓄積します。イ:ミトコンドリアではH+は内膜を越えて「内膜と外膜の間(膜間腔)」に蓄積します。ウ:光合成では、光化学系Ⅱにおいて「H2O」が分解されて電子を供給します。全ての組み合わせが正しいです。
⑦【誤】
イが「マトリックス」、ウが「O2」である点が誤りです。
⑧【誤】
イが「マトリックス」である点が誤りです。
問2:(1)正解②
<問題要旨>
植物の窒素栄養と光合成の関係についての考察問題です。窒素が植物体内でどのような物質の構成成分となるかを理解していることが鍵となります。
<選択肢>
①【誤】
フィトクロムやフォトトロピンは光受容体であり、光合成の反応速度を直接的に決める主要な因子ではありません。
②【正】
窒素は、アミノ酸、タンパク質、核酸、クロロフィルなどの有機窒素化合物の構成元素です。光合成の炭酸固定を担う酵素であるルビスコはタンパク質であり、光エネルギーを吸収するクロロフィルも窒素を含みます。したがって、培地中の窒素濃度が高いと、これらの物質の合成が盛んになり、光合成能力が高まると考えられます。これは実験結果を説明する最も妥当な理由です。
③【誤】
ATPとNADPHは光合成の光化学系で合成され、窒素同化などの反応で消費されます。窒素同化によってこれらが産生されるわけではありません。
④【誤】
有機酸は窒素同化の過程でアミノ基と結合してアミノ酸になりますが、有機酸の量が増えることが直接的に光合成を促進するわけではありません。
⑤【誤】
図1を見ると、窒素濃度の上昇に伴い呼吸速度も上昇していますが、光合成速度の上昇に比べるとわずかです。呼吸で放出されるCO2が光合成を促進する効果は限定的であり、光合成速度が大きく増加した主因とは考えにくいです。
問2:(2)正解⑤⑥
<問題要旨>
実験結果のグラフを読み解き、窒素濃度が高い条件で葉のデンプン蓄積量が少なくなる理由を考察する問題です。光合成産物の分配(ソースからシンクへの転流)の概念が問われています。
<選択肢>
①【誤】
デンプンは光合成の産物であり、光化学系の反応の材料として使われることはありません。
②【誤】
デンプンは光合成の産物であり、電子伝達系の反応の材料として使われることはありません。
③【誤】
デンプンを分解して得られる糖は、呼吸などを経てカルビン・ベンソン回路のRuBP再生にも利用されますが、窒素が豊富な状況でデンプンが減る主な理由としては、他の要因の方がより直接的です。
④【誤】
根粒菌はマメ科植物に共生するものであり、イネには共生しません。
⑤【正】
窒素濃度が高いと、吸収した無機窒素化合物をアミノ酸やタンパク質に変換する「窒素同化」が活発になります。この窒素同化には、炭素骨格(有機酸)とエネルギー(ATPなど)が必要であり、それらは光合成産物から供給されます。そのため、多くの光合成産物が窒素同化に使われ、デンプンとして葉に蓄積される量が減ったと考えられます。
⑥【正】
図1から、窒素濃度が高いと地上部の乾燥重量が増加していることがわかります。これは、植物体の成長が盛んであることを示しています。成長のためには、細胞壁の材料となるセルロースや、細胞の構成成分であるタンパク質など、多くの有機物が必要です。これらの材料も光合成産物から作られるため、多くの光合成産物が成長に使われ、デンプンとしての蓄積が抑えられたと考えられます。
問3:正解③
<問題要旨>
農業における窒素肥料の大量使用が、自然の生態系にどのような影響を及ぼすかについての問題です。富栄養化という環境問題に関する基本的な知識が問われています。
<選択肢>
①【誤】
硝化菌はアンモニウムイオンを硝酸イオンに酸化する細菌であり、有機窒素化合物を蓄積させる働きはありません。
②【誤】
窒素肥料の投入は、生態系内の窒素量を「増加」させます。「低下して」という部分が誤りです。
③【正】
農地で使われた窒素肥料のうち、作物体に吸収されなかった過剰な無機窒素化合物(硝酸イオンなど)は、雨水などによって土壌から流出し、河川や湖沼、沿岸の海域に流れ込みます。これにより、水中の窒素濃度が異常に高くなる「富栄養化」が起こり、それを栄養源とする植物プランクトンが大量発生(アオコや赤潮)する原因となります。
④【誤】
植物が吸収した窒素を窒素ガス(N2)として直接放出するわけではありません。また、大気中に放出される窒素化合物で問題となるのは、主に土壌中の微生物の働き(脱窒)によって生じる亜酸化窒素(N2O)で、これは強力な温室効果ガスです。選択肢の記述は複数の点で不正確です。
第3問
問1:正解①⑥
<問題要旨>
ヒトの視覚に関する様々な知識を問う問題です。眼の構造、遠近調節の仕組み、視覚の神経生理、自律神経による調節など、幅広い範囲から出題されています。
<選択肢>
①【正】
視神経の軸索が束になって眼球から出ていく部分は、光を受容する視細胞(桿体細胞・錐体細胞)が存在しないため、像を結んでも視覚が生じません。この場所は盲斑(盲点)と呼ばれます。
②【誤】
ヒトのように眼が顔の前面についていると、左右の眼で見える視野が大きく重なります。この両眼視野が広いことで、物体までの距離感を正確に捉える立体視の能力が高くなります。眼が側方についている草食動物などと比較して、立体視できる範囲は「広い」です。
③【誤】
網膜の層構造は、光が入る側から順に、神経節細胞層、双極細胞層、視細胞層、色素細胞層となっています。視神経(神経節細胞の軸索が束になったもの)は最も手前(水晶体側)にあり、最も奥にある色素細胞層とは隣接していません。
④【誤】
近くのものを見るときは、水晶体を厚くして屈折力を強める必要があります。そのためには、毛様筋が「収縮」し、水晶体を引っ張っているチン小帯がゆるみます。
⑤【誤】
瞳孔の大きさは自律神経によって調節されます。興奮したり緊張したりしたときに働く交感神経の作用によって、より多くの光を取り込むために瞳孔は「散大」します。リラックスしているときに働く副交感神経の作用で瞳孔は収縮します。
⑥【正】
桿体細胞は暗い場所での視覚を担う視細胞で、その中にあるロドプシンという視物質が光を吸収します。ロドプシンの量が多ければ、弱い光でも吸収できる確率が高まり、感度が高くなります。逆にロドプシンの量が減少すれば、光に対する感度は下がります。
問2:正解⑥
<問題要旨>
発生における「誘導」の仕組みを、組織培養実験の結果から考察する問題です。実験結果を正しく解釈し、どの組織がどの組織に働きかけているか、あるいは組織がどのような能力を既に持っているかを推論する力が求められます。
<選択肢>
ⓐ【誤】
組織Bが水晶体になるには眼胞からの作用が必要ですが、組織Cは眼胞がなくても単独で水晶体になっています。したがって、「頭部外胚葉が水晶体を形成するには眼胞からの作用が必要である」と一括りにはできず、この記述は適当ではありません。
ⓑ【誤】
組織Cは単独でも、間充織と一緒でも水晶体を形成しています。このことから、間充織が水晶体形成を阻害するとは考えられません。組織Bで形成が見られなかったのは、間充織の阻害作用ではなく、眼胞からの誘導作用がなかったためと考えられます。
ⓒ【正】
実験結果から、組織Cは眼胞からの誘導がなくても、自律的に水晶体になる能力(形成能)を既に持っていると考えられます。したがって、組織Cを本来の場所から切り出して、眼胞と接するBの位置に移植したとしても、Cは自身の持つ能力によって水晶体を形成すると予測できます。この記述は実験結果から導かれる妥当な推論です。
問3:(1)正解①
<問題要旨>
マウスの視神経が、左右の網膜から左右の脳へどのように接続されているか、その経路を理解し、特定の経路を遮断した場合の影響を考える問題です。複雑な問題文を正確に読み解き、情報の伝達経路を図に当てはめて考える必要があります。
<選択肢>
問題文から、情報の伝達経路は以下のようになります。
・左網膜の黒い領域 → 交差 → 右脳 (経路g)
・左網膜の白い領域(耳腹側) → 交差せず → 左脳 (経路f)
・右網膜の黒い領域(耳腹側) → 交差せず → 右脳 (経路h)
・右網膜の白い領域 → 交差 → 左脳 (経路d)
右脳に情報が伝わるのは、経路gと経路hです。
実験結果では「右脳に細胞体の興奮が伝わった網膜の領域は右の耳腹側のみになった」とあります。これは、経路hからの情報は届いているが、経路gからの情報が遮断されたことを意味します。
経路gを遮断するには、gそのものを切断するか、gの通り道である左の視神経(経路e)を切断すればよいことになります。
したがって、切断したのはeまたはgであると考えられます。
①【正】
アにe、イにgが入るため、この組み合わせが正しいです。
②【誤】
fを切断しても右脳への情報伝達には影響しません。
③【誤】
dを切断しても右脳への情報伝達には影響しません。
④【誤】
hを切断すると、右の耳腹側からの情報が右脳に伝わらなくなってしまいます。
⑤【誤】
eとfを切断した場合を想定しています。
⑥【誤】
eとhを切断した場合を想定しています。
⑦【誤】
fとhを切断した場合を想定しています。
⑧【誤】
fとgを切断した場合を想定しています。
⑨【誤】
fとhを切断した場合を想定しています。
⑩【誤】
gとhを切断した場合を想定しています。
問3:(2)正解①
<問題要旨>
軸索誘導に関わるタンパク質Pの機能を、正常な個体とPの機能を失った個体の神経回路を比較することで推測する問題です。Pがない場合に何が起こるか(表現型)から、Pが本来持っている役割(機能)を逆算して考えます。
<選択肢>
①【正】
正常なマウスでは、耳腹側の網膜から伸びる軸索は視交叉で交差しませんが、タンパク質Pを失ったマウスでは交差するようになります。これは、視交叉の中心に存在するタンパク質Pが、耳腹側からの軸索が中心部へ侵入するのを防ぎ、反対側へ渡らないようにしていることを示唆します。軸索の伸長を妨げる働きを持つ因子は「反発因子」と呼ばれます。一方、耳腹側以外の網膜からの軸索はPの有無にかかわらず交差しているため、Pはこれらの軸索には影響しないか、異なる作用をしていると考えられます。したがって、この記述が最も適当です。
②【誤】
タンパク質Pは耳腹側の軸索に明らかに影響を与えています。「影響しない」という部分が誤りです。
③【誤】
もしPが網膜全体の軸索に反発因子として働くなら、正常なマウスでは全ての軸索が交差しないはずですが、実際には耳腹側以外は交差しています。したがって誤りです。
④【誤】
もしPが網膜全体の軸索に誘引因子として働くなら、Pを失ったマウスでは軸索が視交叉に集まれなくなるはずですが、実際には全ての軸索が交差しています。したがって誤りです。
第4問
問1:正解⑤
<問題要旨>
神経の興奮伝導やシナプス伝達、筋肉の収縮の仕組みに関する基本的な知識を問う問題です。それぞれの過程で関わるイオン、物質、構造変化を正確に理解しているかが試されます。
<選択肢>
①【誤】
活動電位から静止電位に戻る過程(再分極)では、電位依存性のカリウムチャネルが開き、細胞内のカリウムイオン(K+)が細胞外へ流出します。ナトリウムイオン(Na+)が細胞外に出ていくのではありません。
②【誤】
運動神経の末端と筋繊維との接合部(神経筋接合部)で放出される神経伝達物質はアセチルコリンです。
③【誤】
個々の筋繊維の収縮は「全か無かの法則」に従いますが、筋肉全体としては、興奮する運動神経の数(運動単位の数)を増減させることで、収縮の強さをなめらかに調節しています。
④【誤】
筋肉が収縮する際には、アクチンフィラメントとミオシンフィラメントが互いに滑り込むことで、筋収縮の単位であるサルコメアの長さが「短く」なります。フィラメント自体の長さは変化しません。
⑤【正】
筋肉収縮のエネルギー源はATPです。ミオシンの頭部がアクチンフィラメント上を滑る際に、ミオシン頭部に結合したATPがADPとリン酸に分解され、その際に放出されるエネルギーが利用されます。
問2:正解④
<問題要旨>
提示された仮説(感覚刺激→感覚神経→運動神経→筋収縮)を検証するための一連の実験計画の中で、その検証に「適当でない」ものを選択する問題です。仮説における情報の流れ(因果関係の方向性)と、実験における操作と測定の方向性が一致しているかを見極めることが重要です。
<選択肢>
①【適当】
匂い刺激(原因)を与え、感覚神経の活動(最初の結果)を調べる実験です。仮説の最初のステップ「ニンニクの匂いを受容すると、感覚神経に信号が伝わり」を検証できます。
②【適当】
匂い刺激(原因)を与え、運動神経の活動(最終的な指令)を調べる実験です。仮説全体「匂いを受容すると、感覚神経と運動神経を介して外套に信号が伝わり」を検証できます。
③【適当】
感覚神経への電気刺激(原因)を与え、筋肉の収縮(最終的な結果)を調べる実験です。「感覚神経からの信号が(中枢を介して)運動神経に伝わり、筋肉を収縮させる」という部分を検証できます。
④【不適当】
外套の筋肉(結果側)に刺激を与え、運動神経(原因側)の活動を調べる実験です。これは仮説における情報の流れ(神経→筋肉)とは逆方向の操作と測定を行っており、仮説の検証にはなりません。
問3:正解⑦
<問題要旨>
ナメクジの連合学習(古典的条件づけ)に関する実験結果を解釈し、文章の空欄を埋める問題です。グラフから行動の変化を読み取り、その変化を生み出す神経系の変化を推測し、学習行動と生得的行動を区別する知識が求められます。
<選択肢>
①【誤】
ア:処理に使った匂いに対して、外套はより短縮している(忌避行動が強くなっている)ので、「弱い」は誤りです。
②【誤】
アが「弱い」である点が誤りです。
③【誤】
アが「弱い」である点が誤りです。
④【誤】
アが「弱い」である点が誤りです。
⑤【誤】
ウ:光に対する走性は、学習によらず生まれつき備わっている「生得的行動」の例です。一方、「接触刺激に対する慣れ」は学習の一種(非連合学習)であり、後天的な行動の変容です。文脈上、学習によって後天的に獲得される行動と対比する概念として「生得的行動」の例を挙げるのが適切です。イ:匂いという感覚情報と電気刺激という不快な刺激が連合された結果、その匂い情報を受け取った中枢神経系が、最終的な出力である「外套の運動神経」をより強く興奮させるようになったと考えられます。感覚神経の応答自体が変化した可能性も否定はできませんが、学習による行動の変化は、感覚入力から運動出力に至る神経回路の変化として捉えるのが一般的です。
⑥【誤】
ウが「接触刺激に対する慣れ」である点が不適切です。
⑦【正】
ア:処理に使った匂いに対して忌避行動は「強い」です。イ:神経系の変化としては「外套の運動神経」の応答が増加したと考えるのが妥当です。ウ:この行動は学習による後天的なものであり、生得的行動の例である「光に対する負の走性」とは区別されます。全ての組み合わせが適切です。
⑧【誤】
ウが「接触刺激に対する慣れ」である点が不適切です。
問4:正解⑤
<問題要旨>
動物が群れを形成することの利点(対捕食者効果)について、群れの大きさが個体の行動や能力にどう影響するかを予測する問題です。「多くの目効果」や情報伝達の効率化といった群れの利益を理解していれば、論理的に推測できます。
<選択肢>
①【誤】
ⓐ:群れの個体数が増えると、多くの個体で警戒を分担できるため、1個体あたりの警戒の負担(見回し回数)は「減少する」と考えられます。
②【誤】
ⓐが「増加する」、ⓒが「短くなる」である点が誤りです。
③【誤】
ⓐとⓑが「増加する」である点が誤りです。
④【誤】
ⓐが「増加する」、ⓑが「減少する」、ⓒが「短くなる」である点が誤りです。
⑤【正】
ⓐ:1個体あたりの警戒負担は「減少する」。ⓑ:誰かが天敵に気づき、それが群れ全体に伝わることで、危険を回避できる個体の割合は「増加する」。ⓒ:個体数が多いほど遠くの天敵を誰かが見つける確率が高まるため、発見距離は「長くなる」。すべての予測が適切です。
⑥【誤】
ⓒが「短くなる」である点が誤りです。
⑦【誤】
ⓑが「減少する」である点が誤りです。
⑧【誤】
ⓑが「減少する」、ⓒが「短くなる」である点が誤りです。
問5:正解⑦
<問題要旨>
群れの利益(警戒)と不利益(争い)のバランスから最適な群れのサイズが決まるというモデルについて、条件が変化した場合のグラフの変化(エ)と、食物の分布様式が順位と獲得資源量の関係にどう影響するか(オ)を考察する問題です。
<選択肢>
エの考察:
「群れ全体で得られる食物量が増える」と、個体あたりの食物をめぐる争いは緩和されます。そのため、群れが大きくなったときの「争いにかける時間」の増加が緩やかになり、グラフの右半分が下方にシフトします。また、最適な群れサイズ(グラフの谷底)はより大きい方へ移動します。この変化を示しているのはグラフgです。
オの考察:
図5の実線は、順位が高い個体ほど多くの食物を得られる、つまり食物を独占しやすい状況を示しています。これは、食物が特定の場所に「集中して」分布している場合に起こりやすいです。一方、破線は順位と獲得食物量に相関がない状況を示しており、これは食物を独占できない状況を意味します。このような状況は、食物が広範囲に「ランダムに」分散している場合に起こります。
①【誤】
エがd、オがランダムに。エが誤り。
②【誤】
エがd、オが集中して。両方誤り。
③【誤】
エがe、オがランダムに。エが誤り。
④【誤】
エがe、オが集中して。両方誤り。
⑤【誤】
エがf、オがランダムに。エが誤り。
⑥【誤】
エがf、オが集中して。両方誤り。
⑦【正】
エはg、オはランダムに。両方とも正しく、この組み合わせが正解です。
⑧【誤】
エはg、オは集中して。オが誤り。
第5問
問1:正解④⑦
<問題要旨>
集団遺伝学や分子進化の基本的な考え方について、正しい記述を選択する問題です。自然選択、遺伝的浮動、突然変異の性質、ハーディ・ワインベルグの法則など、進化のメカニズムに関する正確な知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
生存に重要な機能を持つ遺伝子やその領域では、アミノ酸配列を変えてしまうような変異は生存に不利になることが多く、自然選択によって集団から除去されやすくなります(負の選択)。そのため、変異が蓄積する速度は、機能的に重要でない領域に比べて「遅く」なります。
②【誤】
有性生殖を行う集団では、遺伝子の組換えや突然変異によって、常に新しい遺伝子の組み合わせが生まれます。そのため、一卵性双生児を除き、個体間でDNAの塩基配列は異なります。
③【誤】
進化は、生存に有利な変異が自然選択によって広まるだけでなく、生存に有利でも不利でもない「中立な」突然変異が、偶然(遺伝的浮動)によって集団内に広まったり固定されたりすることでも起こります(分子進化の中立説)。
④【正】
多細胞生物の進化において、その個体の体細胞で起こった突然変異は子孫に受け継がれません。生殖細胞(精子や卵)の系列で起こった突然変異のみが遺伝し、進化の材料となります。
⑤【誤】
ハーディ・ワインベルグの法則が成立するための条件の一つに、「突然変異が起こらない」ことがあります。この法則は、進化の要因がない場合に遺伝子頻度がどうなるかを示すモデルです。
⑥【誤】
生じた突然変異のうち、生存に不利なものは自然選択によって除去され、有利なものであっても偶然失われることがあります。したがって、過去に生じた全ての変異が遺伝子プールに保存されているわけではありません。
⑦【正】
遺伝的浮動とは、偶然によって集団の遺伝子頻度が変動する現象です。その影響は、サンプリング誤差が大きくなる小集団においてより顕著に現れます。
問2:正解②
<問題要旨>
DNAの塩基配列の相違度を示した表と、それに基づいて作成された系統樹を照らし合わせ、未知の動物種を特定する問題です。系統樹から読み取れる種間の近縁関係と、表の数値(相違度が小さいほど近縁)を対応させて考えます。
<選択肢>
系統樹から、5種の中で「マメジカ」が他の4種と最も遠縁であることがわかります。したがって、マメジカと他の種との相違度が最も大きくなるはずです。表1を見ると、「ウ」と他の種との相違度(17.7, 18.2, 17.6, 17.4)が全体的に最も大きい値を示しています。よって、「ウ」はマメジカです。
次に、系統樹から「キリン」と「オカピ」が非常に近縁であり、「アカシカ」と「ジャコウジカ」も近縁なグループであることがわかります。
表1で「ア」と「オカピ」の相違度は12.0であり、「ア」と「ジャコウジカ」の相違度は13.2です。「ア」はジャコウジカよりもオカピに近縁ということになります。系統樹上でオカピと最も近縁なのはキリンなので、「ア」はキリンです。
同様に、「イ」と「ジャコウジカ」の相違度は12.7、「イ」と「オカピ」の相違度は14.2です。「イ」はオカピよりもジャコウジカに近縁ということになります。系統樹上でジャコウジカと近縁なのはアカシкаなので、「イ」はアカシカです。
以上のことから、ア=キリン、イ=アカシカ、ウ=マメジカという組み合わせになり、選択肢②が正解となります。
問3:正解③
<問題要旨>
生物の系統樹と形質の有無から、その形質がどのように進化してきたかを推定する問題です。「進化の回数が最小になる」という最節約(さいせつやく)の考え方を用いて、最も単純で合理的な進化シナリオを選択します。
<選択肢>
角の有無を整理すると、あり:キリン、オカピ、アカシカ。なし:ジャコウジカ、マメジカ、化石種Z。
各選択肢のシナリオにおける進化の回数を数えます。
①【3回以上】祖先Cで角を獲得(1回)、化石種Zで喪失(1回)、祖先Eで獲得(1回)。合計3回。
②【3回】祖先F、祖先G、祖先Hで、それぞれ独立に角を獲得。合計3回。
③【2回】祖先Eで角を獲得し(1回)、キリン、オカピ、アカシカ、ジャコウジカの共通祖先が角を持つようになる。その後、ジャコウジカの系統で角を失う(1回)。あるいは、祖先Eで角を獲得し(キリン、オカピが角を持つ)、祖先Hで別に角を獲得する(アカシカが角を持つ)と考えることもできます。この場合も獲得は2回です。他のシナリオと比較して、このシナリオが最も進化の回数が少なくなります。
④【4回】祖先Aで角を獲得(1回)。その後、化石種Zの系統、マメジカの系統、ジャコウジカの系統(祖先I)でそれぞれ角を喪失(3回)。合計4回。
比較すると、③のシナリオが最も少ない進化回数(2回)で現状を説明できるため、最も節約的な仮説として適当です。
問4:正解④
<問題要旨>
アカシカの年齢ごとの繁殖成功度(子の数)と生存曲線を示した2つのグラフを読み解き、そこから導かれる記述として正しいものを選択する問題です。グラフの軸の意味を正確に理解し、複数の情報を組み合わせて考察する能力が求められます。
<選択肢>
ⓐ【誤】
左のグラフは「一頭が一年当たりにつくる子の数(平均)」です。10歳以上の雄でこの平均値が減少するのは、闘争に勝てなくなる個体が増えたり、繁殖能力が衰えたりするためと考えられます。生存個体数が減少したこと自体が、一頭あたりの平均値を下げる直接の原因ではありません。
ⓑ【正】
雄の一頭当たりが作る子の数は10歳でピークを迎えています。右の生存曲線を見ると、雄は10歳以降に個体数が急減しており、死亡率が雌よりも顕著に高まっていることが読み取れます。
ⓒ【正】
左のグラフで、グラフの線が0から立ち上がる年齢を見ると、雌は4歳ごろ、雄は5歳ごろから子を作り始めていることがわかります。したがって、子を残し始める年齢は、雌のほうが雄よりも低いです。
ⓓ【誤】
子の総数は「生存個体数 × 一頭当たりの子の数」で大まかに見積もれます。8歳の雌は、生存個体数が約750頭、一頭当たりの子の数が約0.8です。一方、13歳の雌は、生存個体数が約300頭、一頭当たりの子の数が約0.8です。生存個体数が大きく異なるため、産まれる子の総数はほぼ同じにはなりません。
以上より、正しい記述はⓑとⓒであるため、その組み合わせである④が正解です。