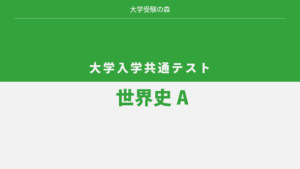解答
解説
第1問
問1:正解④
<問題要旨>
ルネサンス期のヨーロッパにおける文化・学術に関する知識を問う問題です。各選択肢の人物や作品が、ルネサンス期のものか、またその内容が正しいかを判断する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
『神曲』を著したのは、14世紀イタリアの詩人ダンテです。シェークスピアは、16世紀後半から17世紀初頭にかけて活躍したイギリス・ルネサンスを代表する劇作家ですが、『神曲』の作者ではありません。
②【誤】
ミレーが「落ち穂拾い」を描いたのは19世紀半ばのフランスです。彼は農民の生活を描いた写実主義の画家として知られており、ルネサンス期の芸術家ではありません。
③【誤】
コペルニクスは、地球が太陽の周りを公転しているという「地動説」を唱えました。古代ギリシアのプトレマイオス以来、キリスト教世界で公認されてきた「天動説」を覆すものでした。選択肢は「天動説を唱えた」となっているため誤りです。
④【正】
エラスムスは、16世紀に活躍したオランダの人文主義者で、北方ルネサンスの代表的人物です。彼は主著『愚神礼賛』の中で、聖職者の堕落や教会の形式主義を痛烈に風刺・批判しました。これは正しい記述です。
問2:正解③
<問題要旨>
問題文の空欄に入る歴史上の人物と、デューラー作「カール大帝」の制作意図を正しく組み合わせる問題です。文章の読解力と、神聖ローマ帝国の成立に関する知識が求められます。
<選択肢>
①【誤】
人物アは、東フランク王で、教皇から帝冠を受けて神聖ローマ帝国の起源となった人物です。これは962年に戴冠したオットー1世を指します。ユスティニアヌスは6世紀の東ローマ皇帝であり、該当しません。
②【誤】
人物アがユスティニアヌスではないため、この選択肢は誤りです。
③【正】
人物アはオットー1世です。制作の意図について、問題文には都市イ(ニュルンベルク)が帝冠を保管しており、その都市からの依頼でデューラーがこの絵を制作したとあります。また、銘文には「帝冠と衣装は尊崇され、イにて毎年他の宝物とともに展示される」と書かれています。これらの記述から、都市イが、自らが保管する帝冠(当時はカール大帝のものと信じられていた)の権威を借りて、神聖ローマ帝国の長い伝統と結びつく由緒ある都市としての地位を内外に示そうとした意図(X)が読み取れます。よって、「い-X」の組み合わせは正しいです。
④【誤】
制作の意図Yでは「古代ローマで制作された帝冠」とありますが、問題文にはそのような記述はなく、事実に反します。帝冠は、本文の記述によればオットー1世の時代に作られたと推測されています。
問3:正解④
<問題要旨>
問題文の空欄イ(都市名)とウ(政党名)を特定する問題です。文章中に散りばめられたヒントから、20世紀のドイツ史に関する知識を用いて解答を導き出します。
<選択肢>
①【誤】
都市イは、神聖ローマ帝国の宝物を保管し、戦後には国際軍事裁判が開かれた場所です。これはニュルンベルクを指します。ベルリンではありません。また、政党ウは1932年の選挙で第一党になったドイツの政党で、これはナチス党です。ファシスト党はイタリアの政党です。
②【誤】
都市イがベルリンであるという点が誤りです。政党ウが国民社会主義ドイツ労働者党(ナチス党)であるという点は正しいです。
③【誤】
都市イがニュルンベルクであるという点は正しいですが、政党ウがイタリアのファシスト党となっている点が誤りです。
④【正】
都市イは、神聖ローマ帝国の帝国都市であり、ナチスが党大会を開き、その威光を利用しようとした都市、そして第二次世界大戦後にナチス戦犯を裁く国際軍事裁判が開かれた都市であることから、ニュルンベルクと特定できます。政党ウは、1932年の総選挙で第一党となり、ニュルンベルクで党大会を開催したことから、ヒトラー率いる国民社会主義ドイツ労働者党(ナチス党)であることがわかります。両方の組み合わせが正しいです。
問4:正解①
<問題要旨>
問題文の会話から人物エを特定し、その人物の事績として正しいものを選択する問題です。ロシア革命史の基本的な知識が問われています。
<選択肢>
①【正】
会話文にある「四月テーゼを発表した」というキーワードから、人物エはレーニンであることがわかります。レーニンはボリシェヴィキ(後の共産党)を指導し、1917年11月(ロシア暦10月)に武装蜂起(十一月革命/十月革命)を成功させ、ケレンスキーの臨時政府を打倒しました。これは正しい記述です。
②【誤】
世界革命論を唱えたトロツキーを追放し、一国社会主義論を確立したのはスターリンです。
③【誤】
1917年の三月革命(ロシア暦2月)でロマノフ朝が倒れた後に成立した臨時政府で、後に首相に就任したのはケレンスキーです。
④【誤】
第一次世界大戦末期の1918年に、戦後国際秩序の構想として「十四か条の平和原則」を発表したのは、アメリカ大統領ウィルソンです。
問5:正解③
<問題要旨>
写真1の銅像建設、写真2の銅像建設、下線部(東欧革命)の3つの出来事を、問題文の記述を基に年代の古い順に並べる問題です。歴史的な出来事の時期を正確に把握する能力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
年代順が異なります。
②【誤】
年代順が異なります。
③【正】
各出来事の年代は以下の通りです。
・写真2(カロル1世像建設):問題文に「第二次世界大戦勃発の年(1939年)に…建設されました」とあります。
・写真1(レーニン像建設):問題文に「エ(レーニン)の生誕90年を記念して建設されました」とあります。レーニンは1870年生まれなので、生誕90年は1960年です。
・下線部(東欧革命):本文に「東欧諸国で民主化を求めた一連の革命」とあり、これはベルリンの壁崩壊などに象徴される1989年の出来事です。
したがって、古い順に並べると「写真2(1939年)→ 写真1(1960年)→ 下線部(1989年)」となり、この選択肢が正しいです。
④【誤】
年代順が異なります。
⑤【誤】
年代順が異なります。
⑥【誤】
年代順が異なります。
問6:正解③
<問題要旨>
問題文の内容を踏まえて書かれた二人の学生のメモの正誤を判断する問題です。文章の読解力と、冷戦やフランス革命に関する基本的な歴史知識を応用する力が試されます。
<選択肢>
①【誤】
羽生さんのメモも正しいです。
②【誤】
矢木さんのメモも正しいです。
③【正】
・矢木さんのメモ:ベルリンの壁が冷戦(東西対立)の象徴であったことは歴史上の常識です。また、問題文には、写真1のレーニン像が「当時のルーマニアの政権が…自らの権力を正統化するために…建設した」とあり、社会主義政権の象徴であったことがわかります。したがって、矢木さんのメモは正しいです。
・羽生さんのメモ:フランス革命において、ルイ16世の処刑や、王政時代の名称の変更など、旧体制(アンシャン・レジーム)を否定する動きがあったことは事実です。問題文には、写真2のカロル1世像が「社会主義政権が…王政を否定するため」に破壊されたとあります。両者は、旧来の権威や体制を否定するという点で動機が類似しており、羽生さんのメモは正しいと言えます。
以上より、二人とも正しいです。
第2問
問1:正解③
<問題要旨>
下線部の国(ソ連)の歴史に関連する出来事を年代順に正しく配列する問題です。ロシア革命から冷戦期に至るまでの大まかな流れを理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
年代順が異なります。
②【誤】
年代順が異なります。
③【正】
各出来事の年代は以下の通りです。
・い(血の日曜日事件):1905年。ペテルブルクで発生した、皇帝への平和的な請願デモに軍隊が発砲した事件で、第一次ロシア革命の端緒となりました。
・あ(干渉戦争):1918年~1922年。ロシア革命で成立したソヴィエト政権を打倒するため、日本、イギリス、フランス、アメリカなどが軍隊を派遣した戦争です。
・う(コミンフォルム結成):1947年。第二次世界大戦後、冷戦が激化する中で、ソ連が東ヨーロッパ諸国の共産党・労働者党を統制するために結成した組織です。
したがって、古い順に並べると「い → あ → う」となり、この選択肢が正しいです。
④【誤】
年代順が異なります。
⑤【誤】
年代順が異なります。
⑥【誤】
年代順が異なります。
問2:正解④
<問題要旨>
世界史における民族自決や民族運動に関する事例について、正しい記述を選ぶ問題です。20世紀のアジアやヨーロッパの歴史に関する幅広い知識が求められます。
<選択肢>
①【誤】
第一次世界大戦後にウィルソンが提唱した民族自決の原則は、主に東ヨーロッパ諸国の独立に適用されましたが、アジアやアフリカの植民地には適用されず、独立は認められませんでした。
②【誤】
フィンランドは、ロシア革命によるロシア帝国の混乱に乗じて1917年に独立を宣言しました。第二次世界大戦後ではありません。
③【誤】
三民主義(民族の独立、民権の伸長、民生の安定)を提唱したのは、中国の革命家である孫文です。林則徐は、アヘン戦争前の清の官僚で、アヘンの密輸を取り締まった人物です。
④【正】
スカルノは、オランダの植民地支配下にあったインドネシアで、独立運動の指導者として1927年にインドネシア国民党を結成しました。これは正しい記述です。
問3:正解④
<問題要旨>
ソ連のペレストロイカ期からソ連解体後にかけての民族問題に関する文章を読み、その内容と合致する記述を選ぶ問題です。文章の正確な読解力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
文章の最後に「ソ連の解体後、全ての共和国の独立が国際的に承認された。一方、自治共和国の様々な要求は認められず、両者の対立は継続した」とあり、対立は解消されていません。
②【誤】
文章中に「連邦の共産党の指導力が低下し」「調整能力を失っていった」とあり、指導力を維持し続けたという記述は誤りです。
③【誤】
文章中に「共和国や自治共和国では、学校教育を通じて、それぞれの中心となる民族の母語や歴史が教えられ」とあり、ロシア語以外の言語教育が禁止されていたわけではありません。
④【正】
文章中に「1980年代後半以降に改革が進み…連邦の共産党の指導力が低下し、共和国や自治共和国の発言力が強まる」とあります。1980年代後半の改革とはゴルバチョフによるペレストロイカを指すため、この選択肢は本文の内容と合致します。
問4:正解①
<問題要旨>
19世紀末から20世紀半ばにかけてのイギリスにおける主要3政党の得票率の推移を示したグラフから、a・b・cがそれぞれどの政党を指すかを特定する問題です。イギリス近代政治史の知識が不可欠です。
<選択肢>
①【正】
イギリスでは、19世紀から保守党と自由党による二大政党制が続いていました。20世紀に入ると、労働者階級の支持を基盤とする労働党が台頭し、自由党に取って代わって保守党と二大政党を形成するようになります。グラフを見ると、aは安定した得票率を維持しており、伝統的な保守党と考えられます。bは20世紀初頭から急激に支持を失っており、衰退した自由党と判断できます。cは20世紀初頭から得票率を伸ばしており、台頭した労働党と判断できます。よって、この組み合わせが正しいです。
②【誤】
bが労働党、cが自由党となっており、史実とグラフの推移が一致しません。
③【誤】
aが自由党、bが保守党となっており、史実とグラフの推移が一致しません。
④【誤】
aが自由党、cが保守党となっており、史実とグラフの推移が一致しません。
⑤【誤】
aが労働党、bが保守党となっており、史実とグラフの推移が一致しません。
⑥【誤】
aが労働党、cが保守党となっており、史実とグラフの推移が一致しません。
問5:正解①
<問題要旨>
前の問題のグラフで、c(労働党)の得票率が上昇した背景について問う問題です。労働党の支持基盤拡大につながった歴史的出来事を選択します。
<選択肢>
①【正】
グラフでc(労働党)の得票率が顕著に上昇するのは、1918年以降です。イギリスでは第一次世界大戦後の1918年に行われた第4回選挙法改正で、21歳以上の全男性と30歳以上の女性に選挙権が与えられ、有権者数が大幅に増加しました。これにより、労働者階級の票が労働党に集まり、同党の躍進につながりました。したがって、この記述は労働党台頭の背景として適切です。
②【誤】
農業労働者に選挙権が拡大されたのは1884年の第3回選挙法改正であり、グラフでcが台頭する時期とは合いません。
③【誤】
社会主義者鎮圧法は、1878年にドイツ帝国のビスマルクによって制定された法律であり、イギリスの出来事ではありません。
④【誤】
第1インターナショナル(国際労働者協会)が結成されたのは1864年であり、労働党が議会で勢力を伸ばすよりも前の出来事です。
問6:正解②
<問題要旨>
グラフの期間(1885年~1966年)にイギリスが関わった3つの出来事を、年代の古いものから順に正しく配列する問題です。帝国主義時代から第一次世界大戦、戦間期にかけてのイギリス史の知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
年代順が異なります。
②【正】
各出来事の年代は以下の通りです。
・あ(ファショダ事件):1898年。アフリカ大陸の植民地化をめぐり、イギリスとフランスがスーダンのファショダで衝突した事件です。
・う(バルフォア宣言):1917年。第一次世界大戦中に、イギリスがユダヤ人のパレスチナにおける「民族的郷土」の建設を支持した宣言です。
・い(イギリス連邦成立):1931年。ウェストミンスター憲章によって、イギリス本国とカナダ、オーストラリアなどの自治領が対等な主権国家として連合するイギリス連邦が法的に成立しました。
したがって、古い順に並べると「あ → う → い」となり、この選択肢が正しいです。
③【誤】
年代順が異なります。
④【誤】
年代順が異なります。
⑤【誤】
年代順が異なります。
⑥【誤】
年代順が異なります。
問7:正解⑤
<問題要旨>
19世紀後半のエジプトをめぐる国際関係について、空欄イ・ウに入る国の名を正しく組み合わせる問題です。エジプトの財政破綻とそれに続くイギリスの保護国化の流れを理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
国の組み合わせが異なります。
②【誤】
国の組み合わせが異なります。
③【誤】
国の組み合わせが異なります。
④【誤】
国の組み合わせが異なります。
⑤【正】
スエズ運河会社の株買収や近代化政策による負債でエジプトが財政破綻すると、債権国であったイギリスとフランス(イ・ウ)がエジプトの財政を管理下に置きました。これに対し「エジプト人のためのエジプト」を掲げたウラービーの反乱が起こると、スエズ運河の支配権を確保したいイギリス(イ)が単独で軍事介入し、反乱を鎮圧。1882年にエジプトを実質的な保護国としました。問題文の「イ はこの反乱を武力鎮圧し」という記述から、イがイギリス、ウがフランスと特定できます。よってこの組み合わせが正しいです。
⑥【誤】
国の組み合わせが異なります。
問8:正解①
<問題要旨>
エジプトの対外借入を示すグラフと、その背景を説明した本文の内容を正しく結びつけている選択肢を選ぶ問題です。資料読解力と歴史的背景の理解力が試されます。
<選択肢>
①【正】
グラフから、1868年以降の対外借入額がそれ以前に比べて大幅に増加していることが読み取れます。本文には、その背景として「アメリカ合衆国で1860年代初頭に生じた戦争(南北戦争)」によってエジプト産綿花の需要が高まったが、戦争終結後(1865年以降)にアメリカ産綿花の供給が再開されると「エジプト産綿花の需要は低下し、綿花の輸出収入は減少した」「不足した財源を対外借入に頼るようになった」と説明されています。1868年以降の借入急増は、この綿花収入の減少による財政悪化が背景にあると考えられるため、この選択肢はグラフの示す事柄と背景を正しく結びつけています。
②【誤】
スエズ運河の国有化は1956年のナセル大統領によるものであり、グラフの時代(19世紀後半)とは全く異なります。
③【誤】
「1868年以後の対外借入は…少ない」というグラフの読み取りが誤っています。
④【誤】
「1868年以後の対外借入は…少ない」というグラフの読み取りが誤っている上、スエズ運河国有化の時期も誤っています。
問9:正解②
<問題要旨>
ムハンマド=アリーの近代化政策の性格を本文から読み解き、それと類似した性格を持つ清朝の近代化運動を選ぶ問題です。非西洋世界における近代化のパターンの違いを理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
変法運動は、政治制度の変革を目指した運動であり、ムハンマド=アリーの近代化とは性格が異なります。
②【正】
・ムハンマド=アリーの近代化の性格:本文に「西欧から実用的な技術や制度を導入して近代化を図ったものの、従来の支配理念を維持し、西欧の政治思想に基づく制度の導入には消極的であった」とあります。これは選択肢「あ」の内容と一致します。
・清朝の近代化運動:洋務運動は、アロー戦争の敗北を機に、「中体西用(中国の伝統的な精神・体制を本体とし、西洋の技術を実用的に用いる)」をスローガンに、主に軍事技術の導入を進めた運動です。政治体制の変革には踏み込まなかった点で、ムハンマド=アリーの近代化と性格が類似しています。よって、Yが該当します。
以上より、「あ-Y」の組み合わせが正しいです。
③【誤】
ムハンマド=アリーの近代化の性格を「い」と捉えている点が誤りです。
④【誤】
ムハンマド=アリーの近代化の性格を「い」と捉えている点が誤りです。
承知いたしました。解説の続き(第3問、第4問)をお送りします。
第3問
問1:正解④
<問題要旨>
フランスの三部会の歴史に関する正しい知識を選ぶ問題です。フランス革命前後の各議会の役割を正確に区別できるかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
アメリカの独立宣言を採択したのは、1776年にフィラデルフィアで開かれた大陸会議です。フランスの三部会ではありません。
②【誤】
フランス革命中の1792年にオーストリアに対して宣戦布告したのは、立法議会です。
③【誤】
王政の廃止と共和政の樹立を宣言したのは、1792年に成立した国民公会です。
④【正】
1789年、国王ルイ16世は、破綻した国家財政を再建するため、聖職者・貴族の特権身分にも課税しようとしました。この課税承認を得るために約170年ぶりに召集されたのが三部会です。しかし、議決方法をめぐって身分間の対立が激化し、フランス革命の直接的なきっかけとなりました。これは正しい記述です。
問2:正解①
<問題要旨>
空欄アに入るゲルマン系の部族国家の歴史と、王位継承に関する格言の意味を正しく理解し、組み合わせる問題です。フランク王国の歴史と、比喩表現の読解力が求められます。
<選択肢>
①【正】
・アの歴史:本文で言及されている『サリカ法典』は、ゲルマン系のフランク人が用いた部族法典です。フランク王国は、732年のトゥール・ポワティエ間の戦いでイスラーム勢力の西ヨーロッパへの進出を阻止しました(文あ)。これは正しい記述です。
・格言の意味:「槍」は伝統的に武器として男性(戦士)を象徴し、「紡ぎ棒」は家事の道具として女性を象徴します。したがって、「王位は男性(槍)から女性(紡ぎ棒)の系統へは移らない」という意味になり、女性や女系子孫による王位継承を認めない原則(文X)を示しています。
以上より、「あ-X」の組み合わせは正しいです。
②【誤】
格言の意味Yが誤っています。「槍」が女性、「紡ぎ棒」が男性という解釈は逆です。
③【誤】
アの歴史について、ポーランド分割(18世紀後半)に参加したのはロシア、プロイセン、オーストリアであり、フランク王国とは時代も場所も異なります。
④【誤】
アの歴史(い)と格言の意味(Y)の両方が誤っています。
問3:正解②
<問題要旨>
フランスの王位継承問題に関する本文の内容を正確に読み取り、それに基づいて作成された二人の学生のメモの正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
星野さんのメモは誤っています。
②【正】
・星野さんのメモ:本文には「イギリス王は、14世紀からアイルランド併合の時期まで、しばしばフランス王位を主張していました」とあります。アイルランド併合が成立したのは1801年です。両大戦間期(20世紀)まで主張が続いたわけではないため、このメモは誤りです。
・滝沢さんのメモ:本文には「女系男子の王位継承も否定され」た理由として、「フランス王家出身の女性を母に持つ外国の君主を王位継承から排除し、外国人によるフランス支配を防ぐため」と明確に書かれています。したがって、このメモは本文の内容と合致しており、正しいです。
以上より、滝沢さんのみ正しいです。
③【誤】
星野さんのメモが誤っているため、この選択肢は誤りです。
④【誤】
滝沢さんのメモが正しいので、この選択肢は誤りです。
問4:正解④
<問題要旨>
下線部(1959年)の時期、すなわち冷戦期に起こった出来事として最も適当なものを選ぶ問題です。各選択肢の出来事の年代を特定する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
ロカルノ条約が結ばれたのは1925年で、戦間期の出来事です。
②【誤】
スターリング=ブロック(ポンド=ブロック)が形成されたのは、世界恐慌後の1930年代です。
③【誤】
ロンドン海軍軍縮会議が開催されたのは1930年で、戦間期の出来事です。
④【正】
中ソ友好同盟相互援助条約が結ばれたのは1950年です。他の選択肢がすべて第二次世界大戦前の戦間期の出来事であるのに対し、この条約は第二次世界大戦後から冷戦期(1950年代)にかけての米ソ対立の文脈の中にあります。下線部の1959年という年に最も時代背景が近い出来事であり、適切です。
問5:正解③
<問題要旨>
アメリカの公民権運動に関する記述の正誤を判断する問題です。運動の目的と具体的な出来事についての知識が問われています。
<選択肢>
①【誤】
文あが誤っています。
②【誤】
文あが誤っています。
③【正】
・文あ:公民権運動は、南部などで根強く残っていた人種「隔離」政策(ジム=クロウ法など)の「撤廃」を求めて展開された運動です。「隔離政策の実現」を求めたわけではないため、誤りです。
・文い:1963年、人種差別撤廃を求めるワシントン大行進が行われ、その際に指導者であるキング牧師が「I have a dream(私には夢がある)」という有名な演説を行いました。これは正しい記述です。
以上より、「あ-誤、い-正」の組み合わせが正しいです。
④【誤】
文いが正しいので、この選択肢は誤りです。
問6:正解①
<問題要旨>
授業の内容をまとめた二人の学生のメモの正誤を、本文の記述に基づいて判断する問題です。資料の読解力と、公民権運動に関する正確な知識が求められます。
<選択肢>
①【正】
・山田さんのメモ:資料1でアメリカの指導者は、最新式の台所を「女性たちの負担を軽減」するものとして誇っています。これは、女性の役割を家庭内に限定する「性別役割分業」を前提とした発言です。ソ連側の指導者はこれを「資本主義的な姿勢」と批判しており、山田さんのメモは資料1の内容を正しく読み取っています。
・小川さんのメモ:公民権運動の大きな成果である公民権法が成立したのは1964年です。ケネディ大統領が法案を議会に提出し、成立を強く訴えましたが、彼が暗殺された(1963年)のはその成立前でした。法案を成立させたのは、彼の跡を継いだジョンソン大統領です。したがって、「ケネディ大統領在任中に公民権法成立という成果を生み」という記述は誤りです。
以上より、山田さんのみ正しいです。
②【誤】
小川さんのメモは誤っています。
③【誤】
小川さんのメモが誤っているため、この選択肢は誤りです。
④【誤】
山田さんのメモが正しいので、この選択肢は誤りです。
第4問
問1:正解③
<問題要旨>
空欄アに入る国(16世紀のイランの王朝)を特定し、その国の歴史に関する正しい記述を選ぶ問題です。西アジア史の知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
アンカラの戦い(1402年)でオスマン帝国を破ったのは、中央アジアから興ったティムール朝のティムールです。
②【誤】
インドのムガル帝国の第3代皇帝アクバルが、非イスラーム教徒に課されていた人頭税(ジズヤ)を廃止しました。
③【正】
本文の「16世紀、イランに成立した ア」で、オスマン帝国と対立した国はサファヴィー朝です。その第5代君主アッバース1世は、サファヴィー朝の最盛期を現出し、首都をイスファハーンに移して整備しました。これは正しい記述です。
④【誤】
サファヴィー朝は、イスラーム教シーア派の十二イマーム派を国教としました。スンナ派を国教としたのはライバルのオスマン帝国です。
問2:正解⑥
<問題要旨>
下線部(ロシアのカフカス領有)に関連する3つの出来事を、年代の古いものから順に正しく配列する問題です。19世紀から20世紀末までのロシア・ソ連史の流れを把握している必要があります。
<選択肢>
①【誤】
年代順が異なります。
②【誤】
年代順が異なります。
③【誤】
年代順が異なります。
④【誤】
年代順が異なります。
⑤【誤】
年代順が異なります。
⑥【正】
各出来事の年代は以下の通りです。
・う(トルコマンチャーイ条約):1828年。ロシアがカージャール朝イランとの戦争に勝利し、東アルメニアなどを獲得した条約です。
・い(ソ連成立):1922年。ロシア革命後、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ザカフカースの4共和国が連合してソヴィエト社会主義共和国連邦が成立しました。
・あ(独立国家共同体(CIS)成立):1991年。ソ連が解体され、ロシアやアルメニア、アゼルバイジャンなど旧ソ連構成共和国の多くが結成したゆるやかな国家連合体です。
したがって、古い順に並べると「う → い → あ」となり、この選択肢が正しいです。
問3:正解①
<問題要旨>
カフカス地域の紛争に関する本文の内容を正確に読み取り、それに関する二つの文の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【正】
・文え:本文には「三国(アゼルバイジャン、アルメニア、ジョージア)とも国内に少数民族を抱えて」おり、「ナゴルノ=カラバフ紛争は、アゼルバイジャン領内に少数民族として居住するアルメニア人をめぐり、アゼルバイジャン・アルメニア間で生じた」とあります。文えは、この本文の内容を正しく要約しています。
・文お:本文に、ロシアの進出に対して「現地の諸民族による抵抗運動も見られた」とあります。また、チェチェン紛争がロシアからの独立を目指す運動であることは、現代史の基本的な知識です。カフカスの民族がロシアの支配に抵抗してきたという文脈とも合致しており、正しい記述と考えられます。
以上より、二人とも正しいです。
②【誤】
文おも正しいです。
③【誤】
文えも正しいです。
④【誤】
両方とも正しい記述です。
問4:正解②
<問題要旨>
空欄イに入る文(第一次大戦後のイタリアの領土問題)と、空欄ウに入る語(戦後の国際体制)の正しい組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
ウに入る語がウィーン体制となっている点が誤りです。ウィーン体制はナポレオン戦争後の国際秩序です。
②【正】
・イに入れる文:第一次世界大戦後、イタリアはサン=ジェルマン条約でオーストリアから南ティロルとトリエステを獲得しました。しかし、同じく要求していた港湾都市フィウメの割譲は認められませんでした。したがって、「トリエステとともに割譲されたが、フィウメは割譲されなかった」という記述が正しいです。
・ウに入れる語:第一次世界大戦後に成立した国際秩序は、ヴェルサイユ条約を基本とするためヴェルサイユ体制と呼ばれます。
両方の組み合わせが正しいです。
③【誤】
イに入れる文の内容と、ウに入れる語の両方が誤っています。
④【誤】
イに入れる文の内容が誤っています。
問5:正解③
<問題要旨>
下線部「19世紀から20世紀にかけて高揚する、ネーション(民族,国民)の統一や自治・独立を目指す国民主義的な運動」の具体例として、最も適当なものを選ぶ問題です。19世紀ヨーロッパ史の知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
1848年のフランクフルト国民議会では、オーストリアのドイツ系地域を含まない形でドイツを統一する小ドイツ主義が採択されました。オーストリアを含める大ドイツ主義は採用されませんでした。
②【誤】
オーストリアが、マジャール人(ハンガリー)の独立運動と妥協し、オーストリア=ハンガリー(二重)帝国を成立させました。ロシアは関係ありません。
③【正】
1821年に始まったギリシア独立戦争は、オスマン帝国からの独立を目指すナショナリズムの運動でした。この運動はヨーロッパ各地の世論の支持を集め、最終的にイギリス・フランス・ロシアの軍事支援を受けて独立を達成しました。国民主義的な運動の典型例です。
④【誤】
サルデーニャ王国がイタリア統一戦争で戦った相手はオーストリア帝国です。フランスは、サヴォイア・ニースの割譲を条件にサルデーニャを支援しました。
問6:正解②
<問題要旨>
本文の記述を参考に、ナチス=ドイツのマイノリティ政策についての二つの文の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
文いが誤っています。
②【正】
・文あ:ナチス=ドイツが、人種主義に基づいてユダヤ人やロマ(ジプシー)などを組織的に迫害・虐殺したことは歴史的事実です。本文で述べられているマイノリティの「排除」や「同化」の具体例として正しいです。
・文い:本文には、南ティロール問題について、ドイツは「対立していたイタリアとの関係改善に向けて」この「選択」政策に合意したとあります。これは、南ティロールの領有を目的とするものではなく、むしろイタリアとの友好関係を優先して領有を断念した政策です。したがって、この記述は誤りです。
以上より、「あ-正、い-誤」の組み合わせが正しいです。
③【誤】
文あが正しいので、この選択肢は誤りです。
④【誤】
文あが正しいので、この選択肢は誤りです。
問7:正解④
<問題要旨>
清朝の周辺地域(藩部)に対する統治政策と、地図に示された地域の知識を正しく組み合わせる問題です。文章の空欄に入る歴史的な事実と、地図上の位置を正確に理解する力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
文「あ」は満漢併用制を説明しています。これは清が中国本土を統治するために導入した官僚任用制度であり、藩部の統治方法ではありません。また、文章Cのテーマは新疆(地図上のb)であり、満州(地図上のa)ではないため、組み合わせとして不適切です。
②【誤】
文「あ」が藩部の統治方法として不適切です。文章のテーマである新疆(地図上のb)との組み合わせとしても誤りです。
③【誤】
文「い」の「現地の自治が認められた」という記述は、藩部の統治方法として正しいですが、組み合わせられている地域が「a」(満州)であるため誤りです。文章Cは一貫して新疆について述べているため、文脈に合いません。
④【正】
・エに入れる文:文章Cは、清代の新疆が「藩部」の一部であったと述べています。藩部とは、モンゴル、チベット、新疆など、主に非漢人居住地域を指します。清朝はこれらの地域に対し、現地の社会や文化を尊重し、現地の首長などを通じて統治する間接統治(羈縻政策)を行いました。これは大幅な自治を認めるものであったため、「い 現地の自治が認められた」が空欄エに当てはまる最も適切な説明です。
・下線部に該当する地域:問題文Cは、テーマとして一貫して「新疆」について記述しています。設問が問う「下線部」も、この文章の主題である新疆を指していると考えるのが自然です。地図上で現代の中華人民共和国新疆ウイグル自治区の位置を示しているのは「b」です。
したがって、「い-b」の組み合わせが正しいです。
問8:正解②
<問題要旨>
新疆の人口動態に関する表の読み取り(オ)と、現代中国史の出来事(カ・キ)を正しく組み合わせる問題です。
<選択肢>
①【誤】
カとキが逆です。
②【正】
・オに入れる文:表を見ると、1953年から1982年にかけて、漢族の人口は約33万人から約528万人へと約495万人増加し、少数民族の人口は約445万人から約780万人へと約335万人増加しています。「う 漢族人口の増加数が少数民族のそれを上回り」は正しいです。また、1982年の漢族の比率は40.4%であり、「その比率も約4割に達した」も正しいです。
・カ・キに入れる語:農業の集団化を進める「人民公社」は「カ 大躍進」政策(1958年~)の中心でした。「紅衛兵」が動員され、権力闘争が展開されたのは「キ 文化大革命」(1966年~)です。
以上から、「う」「カ-大躍進」「キ-文化大革命」の組み合わせが正しいです。
③【誤】
オに入れる文が「え」となっており、表の読み取りが誤っています。また、カとキも逆です。
④【誤】
オに入れる文が「え」となっており、表の読み取りが誤っています。
問9:正解②
<問題要旨>
1980年代以降の新疆における少数民族の状況について、本文を参考にした二つの文の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
文かが誤っています。
②【正】
・文お:本文に「1980年代末から1990年代にかけてウイグル族による政府への抵抗運動や暴動が頻発しており」とあります。天安門事件(1989年)から西部大開発開始(2000年)までの期間はこの時期と重なります。したがって、この記述は正しいです。
・文か:本文では、西部大開発の目的の一つが経済発展によってウイグル族の反発を抑えることであったと述べられていますが、その結果として「民族問題が見られなくなった」とまでは書かれていません。現代の状況を鑑みても、民族問題が解消されたとは言えず、この記述は誤りです。
以上より、「お-正、か-誤」の組み合わせが正しいです。
③【誤】
文おが正しいので、この選択肢は誤りです。
④【誤】
文おが正しいので、この選択肢は誤りです。