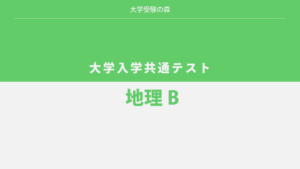解答
解説
第1問
問1:正解⑤
<問題要旨>
世界地図上に示された3つの海域(A、B、C)の海底地形の特徴を、水深別の面積割合を示した表(ア、イ、ウ)と正しく結びつける問題です。プレートテクトニクスに関連する海溝や海嶺、そして大陸棚といった大きな地形の知識が問われています。
<選択肢>
①【誤】
Aは太平洋プレートのほぼ中央に位置するハワイ諸島周辺です。ここはホットスポットによって形成された火山島で、周囲は広大な深海平原(水深3000~6000m)が広がっています。したがって、この水深帯の割合が93.3%と圧倒的に高い「ウ」がAに対応します。この選択肢ではAとアが組み合わされており、誤りです。
②【誤】
Aに対応するのはウ、Bに対応するのはアです。この選択肢ではAとア、Bとウが組み合わされており、誤りです。Bはグリーンランド北東沖に位置し、広大な大陸棚が広がっています。大陸棚は水深が非常に浅い(一般に200m未満)ため、水深500m未満の割合が98.6%を占める「ア」がBに対応します。
③【誤】
Aに対応するのはウ、Cに対応するのはイです。この選択肢ではAとイ、Cとアが組み合わされており、誤りです。Cはフィリピンやインドネシア東部にあたり、プレートが沈み込む複雑な地形をしています。そのため、浅い海(縁海)から非常に深い海(海溝)まで、様々な水深が混在します。水深500m未満から6000mまで比較的まんべんなく分布する「イ」がCに対応します。
④【誤】
Bに対応するのはア、Cに対応するのはイです。この選択肢ではBとウ、Cとイが組み合わされており、誤りです。
⑤【正】
Aは広大な深海平原に囲まれているため「ウ」、Bは広大な大陸棚であるため「ア」、Cは海溝や島弧など複雑な海底地形を持つため「イ」と判断できます。A-ウ、B-ア、C-イの組合せは⑤であり、これが正解です。
⑥【誤】
Aに対応するのはウ、Bに対応するのはア、Cに対応するのはイです。この選択肢はBとイ、Cとアが組み合わされており、誤りです。
問2:正解⑧
<問題要旨>
南半球にあるマダガスカル島の降水量分布図(カ、キ)がそれぞれ1月と7月のどちらに該当するかを判断し、会話文中の空欄F(降水分布に影響を与える風)とG(熱帯低気圧の風の渦の向き)を正しく埋める問題です。気候を形成する要因(熱帯収束帯、貿易風、地形)と、南半球における熱帯低気圧の性質に関する知識が問われます。
<選択肢>
①~④【誤】
まず、図カと図キの時期を特定します。マダガスカル島は南半球にあるため、夏は1月頃、冬は7月頃です。図キは島全体で降水量が多くなっています。これは、夏(1月)に太陽高度が高くなり、赤道低圧帯(熱帯収束帯)が南下してくる影響で、島全体が雨季に入るためです。一方、図カは、島の東側で降水量が多く、西側で少なくなっています。これは、島の中心を南北に走る山脈に対して、南東から貿易風が吹き付け、風上にあたる東岸に多くの地形性降雨をもたらすためです。この影響は一年中ありますが、特に熱帯収束帯が遠ざかる冬(7月)において、この降水パターンの特徴が明瞭になります。したがって、カは7月、キは1月です。この時点でカを1月とする①~④は誤りとなります。
⑤~⑦【誤】
次に会話文の空欄を考えます。空欄Fは、図カ(7月)の降水分布(東岸で多雨、西岸で少雨)をもたらす風なので「貿易風」が適当です。偏西風はこれより高緯度帯を吹く風です。空欄Gは、南半球における熱帯低気圧の渦の向きです。コリオリの力の影響で、南半球の低気圧性の渦は「反時計」回りとなります(北半球では時計回り)。したがって、Fは貿易風、Gは反時計回りが正しい組み合わせです。このことから、⑤、⑥、⑦は誤りです。
⑧【正】
カは7月、Fは貿易風、Gは反時計回りという、ここまでの分析と一致します。したがって、⑧が正解です。
問3:正解②
<問題要旨>
アイスランドの地形図と4つの景観写真(J~M)を結びつけ、それぞれの景観の成因に関する説明文のうち、下線部が不適当なものを特定する問題です。アイスランドに見られる火山地形と氷河地形の基本的な知識が問われます。
<選択肢>
①【正】
Jは海岸段丘の景観です。アイスランドはかつて厚い氷河に覆われていました。最終氷期が終わり氷河が融解すると、地殻が押さえつけられていた重みから解放されて隆起します(アイソスタティック・アイソスタシー)。この隆起によって形成されたのが海岸段丘です。記述は適当です。
②【誤】
Kは火山活動によって形成された火口(またはカルデラ)の景観です。このような窪地は、火山噴火やそれに伴う地下のマグマだまりの空洞化による陥没で形成されます。「溶食」とは、石灰岩などが水に溶けることによって地形が作られる作用(カルスト地形)を指します。アイスランドは火山島であり、石灰岩地形ではないため、この記述は不適当です。
③【正】
Lはフィヨルドの景観です。フィヨルドは、氷河が谷を深く侵食してできたU字谷に、後氷期の海面上昇によって海水が浸入して形成された、水深の深い細長い湾です。記述は適当です。
④【正】
Mは「ギャオ」と呼ばれる大地の裂け目の景観です。アイスランドは、大西洋中央海嶺というプレートが左右に広がる境界の真上に位置しています。そのため、地殻が引き裂かれる力が働き、このような谷が形成されます。記述は適当です。
問4:正解①
<問題要旨>
カナリア諸島の植生分布図、特定地点の雨温図、そしてそれらに関する会話文を読み、下線部a~cの正誤を判断する問題です。気候区分の判定、地形や海流が植生に与える影響を総合的に読み取る力が求められます。
<選択肢>
①【正】
a:地点Pの雨温図(図5)を見ると、年間を通じて温暖ですが、年降水量は合計で200mmに満たない程度で非常に少ないです。特に夏(7~8月)の降水量はほぼ0です。これは地中海性気候(Cs)に似ていますが、降水量が極端に少ないため、乾燥気候のステップ気候(BS)と判断するのが妥当です。したがって「正」です。
b:図4を見ると、常緑広葉樹林が分布している島々(西側のテネリフェ島など)は最高地点の標高が1400m以上と高く、分布していない島々(東側のランサローテ島など)は標高が低いことがわかります。この記述は図から読み取れる事実であり、「正」です。
c:カナリア諸島の沖合には、アフリカ大陸の西岸を南下する寒流のカナリア海流が流れています。寒流の上には冷たく安定した大気が形成されやすく、水蒸気が上昇しにくくなるため、霧が発生しやすくなります。この霧が、降水量が少なくても樹木が育つための水分を供給しています。したがって、寒流が島の大気の状態に影響を与えているという記述は「正」です。a,b,cすべてが正しいため、この選択肢が正解です。
②~⑧【誤】
a, b, cのいずれかが誤りであるとする組み合わせは、すべて誤りとなります。
問5:正解④
<問題要旨>
サンゴ礁の島であるツバルのフォンガファレ島について、1941年と2004年の土地利用の変化図と、2004年の地形断面図を基に、この島に関する記述の正誤を判断する問題です。環礁の地形的特徴と、近年の人間活動や環境問題との関わりを読み取ることが求められます。
<選択肢>
①【誤】
図7の地形断面図を見ると、滑走路が建設されたのは標高1m程度の「埋立部分」であり、島の他の部分と比較しても特に標高が高いわけではありません。むしろ、島の縁にある砂の高まり(R側やS側の一部)の方が標高は高くなっています。したがって、この記述は誤りです。
②【誤】
図6を比較すると、1941年に存在した湿地が2004年には縮小し、その場所に滑走路や建物が建設されています。これは、人間による土地利用の変化(埋め立て)が原因であり、温暖化による乾燥化が原因であるとは図から読み取れません。したがって、この記述は誤りです。
③【誤】
この島は環礁の一部であり、一般に外洋に面する側(この図では東岸のS側)の方が波浪の影響が強く、砂礫が堆積して「砂や礫の高まり」が形成され、標高が高くなる傾向があります。西岸のR側は、穏やかな礁湖に面しているため、堆積作用が弱く標高が低くなります。西岸部が低いのは侵食が進んだためではなく、堆積作用が相対的に弱いからです。したがって、この記述は誤りです。
④【正】
図6から、1941年から2004年にかけて、建物(住宅など)が大幅に増加し、その分布域も島全体に拡大していることがわかります。図7が示すように、この島の土地の大部分は標高が2~3m以下と非常に低いです。このような標高の低い場所に人口や資産が集中したことが、近年の海面上昇や大潮の際に浸水被害が深刻化する一因となっていると考えられます。したがって、この記述は最も適当です。
問6:正解④
<問題要旨>
島の自然と人間生活の関わりについて、4人の生徒が述べた内容から、誤りを含むものを一つ選ぶ問題です。火山、地震・津波、島の水資源、サンゴ礁の成因という、地理の様々な分野の知識が問われています。
<選択肢>
①【正】
大規模な火山噴火によって大量の火山灰やエアロゾルが成層圏まで達すると、太陽からの日射を遮る「日傘効果」により、地球全体の平均気温が低下することがあります。これは「火山の冬」とも呼ばれ、歴史上にも記録があります。したがって、この記述は正しいです。
②【正】
プレート境界で発生する巨大地震は、大規模な津波を引き起こすことがあります。津波は非常に波長が長いため、大洋を越えて伝播し、発生源から何千キロも離れた遠隔地の島や大陸の沿岸にも大きな被害をもたらすことがあります。したがって、この記述は正しいです。
③【正】
島は面積が小さく、大きな河川がないことが多いため、水を貯めておく能力が低い場合があります。特に、地質がサンゴ礁の石灰岩や火山島の溶岩のように水を通しやすい(透水性が高い)場合、降った雨はすぐに地下に浸透したり海に流れ出たりしてしまい、水資源として利用しにくくなります。そのため、降水量が多くても水不足に悩まされることがあります。したがって、この記述は正しいです。
④【誤】
サンゴ礁の形態が、島の周りに発達する「裾礁」から、沖合に離れて発達する「堡礁」、そして島が完全に水没して輪の形になった「環礁」へと変化する主な要因は、ダーウィンの沈降説で説明されているように、火山島が地盤沈降する速さと、サンゴが上方に成長する速さのバランスによるものです。海岸侵食が主な要因ではありません。したがって、この記述は誤りです。
第2問
問1:正解③
<問題要旨>
世界の地域別の木材伐採量とその用途(薪炭材、製材・丸太、パルプ材)を示したグラフから、AとBが「アジア」と「北・中央アメリカ」のいずれか、アとイが「薪炭材」と「製材・丸太」のいずれかを特定する問題です。各地域の経済発展段階と、それに伴う林産資源の利用方法の違いを理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
まず凡例のアとイを判別します。「薪炭材」は調理や暖房などの生活燃料として使われ、発展途上国での利用割合が高いです。一方、「製材・丸太」は工業原料として利用されます。グラフを見ると、「アフリカ」ではアが伐採量の大半を占めています。アフリカは発展途上国が多い地域であることから、アが「薪炭材」、イが「製材・丸太」と判断できます。この時点で、薪炭材をイとする①は誤りです。
②【誤】
アが薪炭材、イが製材・丸太です。次に地域AとBを判別します。Aは総伐採量が世界で最も多く、薪炭材(ア)の割合も高いです。これは人口が多く、発展途上国も多く含む「アジア」の特徴と一致します。Bは総伐採量がAより少なく、薪炭材(ア)の割合が低く、製材・丸太(イ)やパルプ材の割合が高いです。これは、工業化が進み、エネルギー源として薪炭材への依存度が低い先進国(アメリカ、カナダ)を含む「北・中央アメリカ」の特徴と一致します。したがって、北・中央アメリカはBです。この選択肢では北・中央アメリカをAとしており、誤りです。
③【正】
北・中央アメリカはB、薪炭材はアという、ここまでの分析と一致します。これが正解です。
④【誤】
薪炭材はアであるため、イとするこの選択肢は誤りです。
問2:正解①
<問題要旨>
菜種油とパーム油、それぞれの生産国の分布図(カ、キ)と、その特徴を述べた文(e、f)の正しい組み合わせを選ぶ問題です。主要な植物油の原料となる農産物の栽培条件(気候)と、その用途に関する知識が問われます。
<選択肢>
①【正】
まず、図カとキを判別します。パーム油の原料となるアブラヤシは、高温多湿の熱帯雨林気候で栽培されるため、生産はインドネシアやマレーシアなど東南アジアに集中します。図キは東南アジアに生産が極端に集中しているため、これがパーム油です。一方、菜種の原料となるセイヨウアブラナは、比較的冷涼な温帯気候に適しています。図カは、カナダ、ヨーロッパ、中国、インドといった中緯度帯の国々に生産が広がっており、これが菜種油です。
次に、文eとfを判別します。文fの「近年は生産量が急増している」は、プランテーション開発が世界的に問題となっているパーム油の状況と一致します。文eの「かつては灯火にも用いられた」は、菜種油の伝統的な利用法です。
したがって、「菜種油」に該当するのは図カと文eの組み合わせであり、①が正解です。
②~④【誤】
菜種油は図カと文eの組み合わせです。他の組み合わせはすべて誤りです。
問3:正解③
<問題要旨>
1次エネルギーの自給率と供給量によって分類された表(P,Q,R)と、それぞれの国のエネルギー事情を説明した文(サ,シ,ス)を、オーストラリア、ブラジル、ベトナムの3カ国に正しく対応させる問題です。各国の資源産出状況、経済レベル、エネルギー政策の特徴を総合的に判断する必要があります。
<選択肢>
①・②・④~⑥【誤】
まず、国P,Q,Rを特定します。
R:1人当たりエネルギー供給量が2トン以上と多く、自給率も100%以上と高い。これは石炭や天然ガスなどの資源が豊富で、先進国である「オーストラリア」に該当します。
Q:自給率が100%以上だが、1人当たり供給量は2トン未満。水力発電やバイオ燃料の生産が盛んでエネルギー自給率が高い一方、経済レベルから1人当たりの消費量はそれほど多くない「ブラジル」に該当します。
P:1人当たり供給量が2トン未満で、自給率も100%未満。これは、近年経済成長が著しいものの、1人当たりのエネルギー消費量はまだ少なく、国内資源だけでは需要を賄えない「ベトナム」に該当します。
次に、文サ,シ,スを特定します。
サ:「水力が約60%」は水力大国「ブラジル」の特徴です。
シ:「石炭が約50%、水力が約30%」「1人当たり1次エネルギー供給量が約2倍」は、急激な工業化に伴い石炭火力と水力でエネルギー需要の増大を賄っている「ベトナム」の状況を反映しています。
ス:「石炭が約50%、天然ガスが約20%」と化石燃料の割合が高いのは、資源大国「オーストラリア」の特徴です。
以上のことから、P(ベトナム)-シ、Q(ブラジル)-サ、R(オーストラリア)-ス、という組み合わせになります。
③【正】
P-シ、Q-サ、R-スという組み合わせであり、分析と一致します。これが正解です。
問4:正解②
<問題要旨>
インドネシア、シンガポール、ペルーの3カ国のGDP産業別割合を示したグラフ(タ、チ、ツ)を正しく特定する問題です。それぞれの国の経済発展レベルや自然環境を背景とした産業構造の特徴が問われます。
<選択肢>
①・③~⑥【誤】
まず、最も特徴的な国から考えます。「シンガポール」は国土が非常に狭い都市国家であり、農業はほとんど行われていません。金融、貿易、観光などのサービス業が経済の中心です。グラフ「ツ」は、「農林水産業」の割合がほぼ0で、「サービス業など」の割合が極めて高いことから、シンガポールと判断できます。
次に「ペルー」は、アンデス山脈を有し、銅などの鉱産資源が豊富です。したがって、「鉱業・エネルギー業」の割合が他の2国より高くなるはずです。グラフ「チ」は「鉱業・エネルギー業」の比率が他に比べて高いことから、ペルーと判断できます。
残ったグラフ「タ」が「インドネシア」となります。インドネシアは農林水産業が今も重要な産業であり、3カ国の中では「農林水産業」の割合が最も高くなっています。
したがって、タ-インドネシア、チ-ペルー、ツ-シンガポールという組み合わせになります。
②【正】
タ-インドネシア、チ-ペルー、ツ-シンガポールという組み合わせは選択肢②と一致するため、これが正解です。
問5:正解④
<問題要旨>
綿織物の輸出に関する文章を読み、下線部①~④の中から適当でない記述を選ぶ問題です。繊維産業の立地移動の歴史や、各国の工業の特色についての知識が問われます。
<選択肢>
①【正】
織物業は、多くの労働力を必要とする労働集約型の工業です。そのため、生産拠点はより安価な労働力を求めて、先進国から発展途上国へと移転してきました。2022年時点で中国が世界の輸出額の約半分を占めているのは、この国際的な分業の結果です。記述は適当です。
②【正】
インドは世界有数の綿花生産国であり、特に西部のデカン高原は綿花の栽培に適した土壌(レグール)が広がっています。国内で産出される豊富な綿花を原料として、古くから綿工業が発達してきました。記述は適当です。
③【正】
イタリアやドイツといった先進工業国では、発展途上国の安価な製品と価格で競争することは困難です。そのため、優れたデザイン、高い品質、有名なブランドといった付加価値を高めることで製品を差別化し、国際競争力を維持しています。記述は適当です。
④【誤】
イタリアにおいて、付加価値の高い繊維・アパレル産業が集積しているのは、「第三のイタリア」と呼ばれる北東部や中部地方です。そこでは、熟練した技術を持つ中小企業が地域内で分業ネットワークを形成し、高い競争力を生み出しています。イタリア南部は、歴史的に経済開発が遅れている地域であり、織物業の主要な集積地ではありません。したがって、この記述は誤りです。
問6:正解③
<問題要旨>
1965年と2014年の日本の工業生産額の業種別割合を示したレーダーチャート(X、Y)と、凡例のマとミ(化学、機械)を正しく特定する問題です。日本の高度経済成長期から現代に至るまでの産業構造の変化を理解しているかが鍵となります。
<選択肢>
①・②・④【誤】
まず、年代(XとY)を特定します。1965年は高度経済成長の真っ只中で、繊維工業の割合がまだ比較的高く、重化学工業(金属・化学・機械)がバランスよく成長していました。2014年になると、産業構造がさらに高度化し、繊維工業の割合は大幅に低下し、特定の産業への集中が進みます。グラフを見ると、Xに比べてYは「繊維」の割合が著しく低く、マの割合が突出して高くなっています。このことから、Xが1965年、Yが2014年と判断できます。
次に、業種(マとミ)を特定します。現代の日本の工業生産額の中で、自動車工業や電気機器工業を含む「機械」工業が圧倒的な割合を占めています。Y(2014年)のグラフで突出して高い割合を示している「マ」が「機械」に該当します。残った「ミ」が「化学」となります。
したがって、「2014年」はY、「機械」はマの組み合わせが正しいです。
③【正】
2014年はY、機械はマという組み合わせは、分析と一致します。これが正解です。
第3問
問1:正解④
<問題要旨>
発展途上国であるタンザニアの人口関連指標(出生率、乳幼児死亡率、平均寿命)の推移を示したグラフ(A,B,C)を正しく特定する問題です。人口転換モデルにおける各指標の変化の順序と特徴を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①~③・⑤・⑥【誤】
人口転換のプロセスでは、一般に、まず公衆衛生の改善や医療の普及によって「死亡率」(特に乳幼児死亡率)が急激に低下します。死亡率の低下に伴い、「平均寿命」は延びます。そして、価値観の変化や教育水準の向上などにより、遅れて「出生率」が低下し始めます。
グラフを見ると、Cは2000年から2020年にかけて指数が100から40程度まで最も大きく低下しており、これは「乳幼児死亡率」の急激な改善を示していると判断できます。Aは唯一上昇しており、これは乳幼児死亡率の低下などに伴う「平均寿命」の延伸を示しています。Bは緩やかに低下しており、これは「出生率」の低下を示していると考えられます。
したがって、Aは平均寿命、Bは出生率、Cは乳幼児死亡率です。
④【正】
出生率-B、乳幼児死亡率-C、平均寿命-A という組み合わせは、分析と一致します。これが正解です。
問2:正解①
<問題要旨>
東京大都市圏の3つの地域(都心、郊外、圏外)における、年少人口割合(14歳以下)と老年人口割合(65歳以上)の推移を示したグラフから、指標(E,F)と地域(ア,イ)を特定する問題です。都心回帰、郊外の高齢化、地方の過疎化といった、現代日本の人口動態の地域的特徴を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【正】
まず指標EとFを判別します。日本全体で少子高齢化が進んでいるため、老年人口割合は上昇傾向、年少人口割合は低下傾向にあります。グラフFは全体として上昇傾向、グラフEは全体として低下傾向にあるため、Fが「65歳以上人口割合」、Eが「14歳以下人口割合」と判断できます。
次に地域アとイを判別します。「大子町」(ア or イ)は東京圏外の地方であり、高齢化と過疎化が最も進んでいると考えられます。したがって、65歳以上割合(F)が最も高く、14歳以下割合(E)が最も低いグラフが該当します。「実線(ア)」は、Fのグラフで最も高い値を示し、Eのグラフで最も低い値を示しているため、アが大子町です。
「港区」(ア or イ)は都心にあり、2000年代以降の都心回帰で若い世代や子育て世帯が流入し、14歳以下人口割合が上昇に転じるという特徴があります。「点線(イ)」は、グラフEにおいて2000年頃を底に上昇に転じており、港区の動向と一致します。
したがって、「14歳以下人口割合」はE、「港区」はイの組み合わせが正しく、①が正解です。
②~④【誤】
他の組み合わせはすべて誤りです。
問3:正解②
<問題要旨>
4カ国(イギリス、オランダ、韓国、中国)における巨大企業の本社数とその首都への集中度を示した表から、「韓国」に該当するものを選ぶ問題です。各国の経済規模の推移と、国内における経済活動の地理的集中度(プライメイトシティ化)に関する知識が問われます。
<選択し>
①【誤】
2000年時点で37社と多くの巨大企業があったものの、2020年には21社に減少しています。これは伝統的な経済大国である「イギリス」と考えられます。首都ロンドンへの集中度が高いのも特徴です。
②【正】
2000年から2020年にかけて企業数は11社から14社へと微増していますが、特筆すべきは首都への集中度です。国全体14社のうち12社が首都にあり、集中率は約86%と極めて高いです。これは、ソウル首都圏への一極集中が著しい「韓国」の経済構造の特徴と一致します。
③【誤】
企業数は11社から13社へと微増していますが、首都への本社数は4社であり、集中度は約31%と比較的低いです。これは、首都アムステルダム以外にも経済的な中心地を持つ「オランダ」と考えられます。
④【誤】
2000年の9社から2020年には124社へと、巨大企業数が爆発的に増加しています。これは、この期間に驚異的な経済成長を遂げた「中国」に該当します。
問4:正解③
<問題要旨>
ナイロビ、パリ、メルボルンの3都市の景観写真を見て、「都心周辺部から都心を撮影したもの」を全て選ぶ問題です。各都市の都市構造、特に都心と副都心の位置関係や、歴史的景観の有無に関する知識が問われます。
<選択肢>
①・②・④~⑧【誤】
各写真を分析します。
a(ナイロビ):手前に比較的低層の建物群が広がり、奥に高層ビルが林立する中心業務地区(CBD)が見えます。これは都心周辺部や郊外から都心を望んだ景観と判断できます。
b(パリ):奥に見えるのは、新凱旋門を中心とする高層ビル群「ラ・デファンス地区」です。ここはパリの歴史的な都心から西に離れて建設された副都心です。写真の手前にはシャンゼリゼ通りのような歴史的市街地が広がっており、これは「都心から都心周辺部(副都心)を撮影した」構図です。設問の条件とは逆です。
c(メルボルン):手前に低層の建物群があり、川を隔てた奥に高層ビルが立ち並ぶ都心部が見えます。これも都心周辺部から都心を撮影した景観と判断できます。
したがって、設問の条件に合うのは「aとc」です。
③【正】
条件に合うのはaとcの両方であり、この選択肢が正解です。
問5:正解③
<問題要旨>
カナダのトロント市とその周辺自治体について、「トロント市への通勤率」と「トロント市への通勤者増加率」を示した2枚の地図を読み解き、最も適当な記述を選ぶ問題です。大都市圏における居住地の拡大(郊外化)と都心との結びつきの変化を、地図から読み取る力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
地域カは、トロント市への通勤率が10~20%未満と比較的低いですが、通勤者の増加率は20%以上と非常に高い地域です。ベッドタウン化が進んでいる可能性はありますが、「企業の社員向け住宅が多く建設された」とまでは断定できません。
②【誤】
地域キは、トロント市に隣接し、通勤率が30%以上と非常に高い、結びつきの強い地域です。しかし、通勤者の増加率の地図を見ると、キは「減少」に分類されています。つまり、トロント市との結びつきは、この10年間で相対的に「弱まった」と考えられます。「強まった」という記述は誤りです。
③【正】
地域クは、トロント市からやや離れていますが、通勤率は10~30%台であり、通勤者の増加率は20%以上と非常に高いです。これは、この地域で新たに住宅開発が進み、トロント市へ通勤する人々が急増した、つまり「トロント市のベッドタウンとして成長した」ことを強く示唆しています。この記述は最も適当と考えられます。
④【誤】
「トロント市への通勤率」の地図を見ると、市役所のある都心部からの距離が近いほど通勤率が高く、遠くなるほど低くなるという、同心円状の傾向が概ね見て取れます。したがって、「距離の長短は影響を与えていない」という記述は明らかに誤りです。
問6:正解①
<問題要旨>
日本の伝統的な集落を示した3つの地形図(サ、シ、ス)と、それぞれの集落の特徴を説明した文(J、K、L)の正しい組み合わせを選ぶ問題です。地形図から輪中集落、街村、谷口集落といった集落形態を読み取り、その立地理由と結びつける知識が問われます。
<選択肢>
①【正】
まず、各地形図の特徴を読み取ります。
サ:大きな川沿いの低平地にあり、集落が堤防のようなものに囲まれているように見えます。これは水害を防ぐための「輪中集落」です。したがって、文J「水害を避けるため、周囲よりわずかに高い場所に集落が立地している」という説明(自然堤防や人工的な堤防)が当てはまります。
シ:台地上にあり、道路(街道)沿いに家屋が並び、その背後に短冊状の耕地が広がっています。これは近世以降に開発された「(道路)街村」の特徴です。したがって、文K「台地上の集落で、道路沿いの住居の背後に耕地が短冊状に配列している」という説明が完全に一致します。
ス:山麓の谷の出口に位置しています。これは「谷口集落」で、山からの湧水が得やすい場所に立地することが多いです。したがって、文L「湧き水を得やすい場所に集落が立地している」が当てはまります。
以上のことから、サ-J、シ-K、ス-Lという組み合わせが正しく、①が正解です。
②~⑥【誤】
他の組み合わせはすべて誤りです。
第4問
問1:正解②
<問題要旨>
世界地図上の4地点(A~D)について、「冬日」(最低気温が0℃未満)と「真冬日」(最高気温が0℃未満)の月別日数を示したグラフ(①~④)の中から、地点Dに該当するものを特定する問題です。各地点の大まかな気候特性、特に冬の厳しさを推測し、グラフを正しく読み解く力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
このグラフは、冬に真冬日が多く、夏には冬日・真冬日がないという寒冷な気候を示していますが、後述する②ほど極端ではありません。北極圏にある地点B(スヴァールバル諸島)などが候補と考えられます。
②【正】
このグラフは、10月から4月にかけて長期間にわたり、ほぼ毎日が真冬日であることを示しています。特に12月から2月は月の全ての日が真冬日となっており、冬の寒さが極めて厳しいことを表しています。地点Dはシベリア東部の内陸に位置し、「北半預の寒極」とも呼ばれる世界で最も冬の寒さが厳しい地域の一つです。したがって、このグラフが地点Dに該当します。
③【誤】
このグラフも冬の寒さを示していますが、真冬日の日数は②に比べて少なく、最も寒い月でも月の半分程度です。中国内陸の高地に位置する地点Cなどが候補と考えられます。
④【誤】
このグラフは、冬に冬日は多いものの、真冬日は比較的少なくなっています。これは、高緯度にありながら暖流(北大西洋海流)の影響で冬の冷え込みが比較的緩やかな、地点A(アイスランド)の気候特性と一致します。
問2:正解②
<問題要旨>
世界地図上の同緯度帯にある4つの範囲(ア~エ)について、それぞれの土地被覆(地表面の状態)の面積割合を示した表(①~④)から、範囲イに該当するものを特定する問題です。気候帯と植生の関係(バイオーム)についての知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
この選択肢は「森林」の割合が98.0%と、ほぼ全域が森林であることを示しています。範囲イ(スカンディナビア半島)もタイガ(針葉樹林)が広がりますが、湖沼も多いため、後述の②の方がより適当と考えられます。
②【正】
この選択肢は「森林」の割合が88.8%と非常に高く、かつ「水域」の割合も8.8%と一定の割合を占めています。範囲イのスカンディナビア半島は、タイガ(針葉樹林)に覆われ、氷河期に形成された多数の湖沼が点在することで知られています。この特徴とよく一致するため、これが正解です。
③【誤】
この選択肢は「低木・草地」の割合が78.1%と大半を占めています。これは、樹木が育たないほど寒冷または乾燥したツンドラ気候やステップ気候の地域の特徴です。範囲ウ(シベリア内陸部)がこれに該当します。
④【誤】
この選択肢は「氷河・氷床」の割合が62.7%と半分以上を占めています。これは、国土の大半が厚い氷に覆われている範囲ア(グリーンランド)に該当します。
問3:正解③
<問題要旨>
アンデス山脈周辺の3カ国(エクアドル、ペルー、ボリビア)について、各国の人口上位10都市の人口と標高を示した散布図(カ~ク)を正しく特定する問題です。各国の主要都市の立地(高地か低地か)や、人口規模の偏り(プライメイトシティの有無)に関する知識が決め手となります。
<選択肢>
①・②・④~⑥【誤】
まず、最も特徴的な都市を持つ国から考えます。「ペルー」は首都リマが沿岸の低地にあり、人口1000万人を超える突出したプライメイトシティです。散布図を見ると、「カ」にのみ人口1000万人を超え、標高が0m付近にある都市が存在します。これがリマであり、「カ」がペルーです。
次に、「ボリビア」は内陸国で、主要都市の多くが標高3000m以上の高地にあります。散布図の「ク」は、多くの都市が標高3000~4000mの間に集中しており、ボリビアの特徴と一致します。
残った「キ」が「エクアドル」となります。エクアドルは、首都キトが高地(約2800m)に、経済の中心都市グアヤキルが低地にあるなど、高地と低地の両方に都市が分布しており、「キ」の散布図の様子と一致します。
したがって、カ-ペルー、キ-エクアドル、ク-ボリビアという組み合わせになります。
③【正】
エクアドル-キ、ペルー-カ、ボリビア-クという組み合わせは、分析と一致します。これが正解です。
問4:正解①
<問題要旨>
ネパールにおける主要農産物(米、ジャガイモ、トウモロコシ)の最多生産量を示した地図の凡例(サ~ス)を特定する問題です。山岳地域における農作物の「垂直分布」の知識、つまり標高によって栽培される作物が異なることを理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【正】
ネパールは、南部のタライ平原(低地)、中央部の丘陵地帯、北部のヒマラヤ山脈(高地)という地形区分が重要です。
「米」は温暖で水を豊富に必要とするため、主に南部の低地で栽培されます。地図上で南部に広く分布する「サ」が米です。
「ジャガイモ」は冷涼な気候に強く、高地での栽培に適しています。地図上で北部の山岳地帯に多く分布する「ス」がジャガイモです。
「トウモロコシ」は米よりは冷涼な気候でも栽培でき、丘陵地の斜面などで作られます。地図上で中央の丘陵地帯に広く分布する「シ」がトウモロコシです。
したがって、米-サ、ジャガイモ-ス、トウモロコシ-シという組み合わせが正しく、①が正解です。
②~⑥【誤】
他の組み合わせはすべて誤りです。
問5:正解③
<問題要旨>
カナダの4つの主要な輸出品目(鉱産資源、水産物、農畜産物、林産物)について、カナダ全体に占める各州の輸出額の割合を示した地図(①~④)から、「鉱産資源」に該当するものを探す問題です。カナダの農林水産業や鉱業の地域的な偏り(どこで何が盛んか)を知っているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
この地図は、大西洋岸と太平洋岸の州に輸出が集中しています。これは、それぞれの海洋に面した地域で盛んな「水産物」の輸出分布を示しています。
②【誤】
この地図は、広大な針葉樹林帯(タイガ)が広がるケベック州やブリティッシュコロンビア州からの輸出が多いことを示しています。これは「林産物」の分布です。
③【正】
この地図は、アルバータ州やサスカチュワン州といった内陸のプレーリー諸州、そしてオンタリオ州、ケベック州など、広い範囲の州から輸出されています。アルバータ州は石油・天然ガス、サスカチュワン州はウランやカリ鉱石、オンタリオ州・ケベック州は金属資源と、カナダの多様な地下資源の産出地域と一致します。これが「鉱産資源」です。
④【誤】
この地図は、プレーリー3州と呼ばれる内陸の平原(アルバータ、サスカチュワン、マニトバ)に輸出が極端に集中しています。この地域は世界的な小麦地帯であり、肉牛の放牧なども盛んです。これは「農畜産物」の分布です。
問6:正解④
<問題要旨>
北欧3国の人口分布図と、国内交通(航空・鉄道)の旅客数データを見て、「ノルウェー」と「航空」の正しい組み合わせを選ぶ問題です。国の地形的特徴が国内の交通網の発達にどのように影響するかを考察する力が求められます。
<選択肢>
①~③【誤】
まず、国(マ、ミ)と交通手段(X、Y)を特定します。
旅客輸送量は、日常的に利用される鉄道の方が、長距離移動が中心の航空よりも多くなるのが一般的です。表2の数値を見ると、Xの値(数千万人~数億人規模)がYの値(数百万人規模)より圧倒的に大きいため、Xが「鉄道」、Yが「航空」と推測できます。
次に国を特定します。図6の人口分布図と地形の知識から、ノルウェーはスカンディナビア山脈が国土を縦断し、フィヨルドが複雑に入り組むため、長距離鉄道網の建設が困難です。そのため、国内の都市間移動において航空交通への依存度が高くなるという特徴があります。表を見ると、航空(Y)の旅客数は「ミ」が14,757千人と、「マ」の1,760千人に比べて突出して多くなっています。このことから、航空交通が発達している「ミ」がノルウェー、「マ」がフィンランドと判断できます。
④【正】
以上の分析から、ノルウェーは「ミ」、航空は「Y」となります。この組み合わせと一致するため、④が正解です。
第5問
問1:正解①
<問題要旨>
北海道の3つの市町(倶知安町、旭川市、釧路市)の雨温図(ア~ウ)を正しく特定する問題です。日本海側、内陸部、太平洋側という、北海道内の気候の地域差を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【正】
「倶知安町」は日本海側に位置し、冬の季節風の影響を受ける世界有数の豪雪地帯です。雨温図「ア」は冬(12月~2月)の降水量が突出して多く、この特徴と一致します。
「旭川市」は内陸盆地にあり、夏は暑く冬は非常に寒いという気温の年較差が大きい大陸性の気候です。雨温図「イ」は、夏の気温が20℃を超え、冬は-8℃前後まで下がり、年較差が最も大きいため、旭川市と判断できます。
「釧路市」は太平洋側に位置し、夏に寒流の親潮の影響で気温が上がらず冷涼です。雨温図「ウ」は、夏でも平均気温が20℃に届かず、年較差が小さいという特徴があり、釧路市と判断できます。
したがって、倶知安町-ア、旭川市-イ、釧路市-ウ の組み合わせが正しく、①が正解です。
②~⑥【誤】
他の組み合わせはすべて誤りです。
問2:正解②
<問題要旨>
ニセコ地区3町の土地利用図と、農畜産物別産出額のグラフ(カ~ク)を照合し、正しい組み合わせを選ぶ問題です。地図情報(土地利用)と統計情報(農業産出額)を関連付けて分析する力が求められます。
<選択肢>
①・③~⑥【誤】
まず、図1の土地利用図を確認します。「倶知安町」は羊蹄山麓に「畑・草地など」が多く分布します。「蘭越町」は尻別川の下流域に「水田」が広く分布します。「ニセコ町」はその中間に位置します。
次に、図3のグラフを確認します。「カ」は「野菜」「イモ類」が多く、畑作中心です。「キ」は「生乳・乳製品」が多く、酪農中心です。「ク」は「米」が圧倒的に多く、稲作中心です。
両者を結びつけます。畑作が盛んな「倶知安町」はグラフ「カ」に、稲作が盛んな「蘭越町」はグラフ「ク」に該当します。残ったグラフ「キ」が「ニセコ町」となります。
②【正】
倶知安町-カ、ニセコ町-キ、蘭越町-クという組み合わせは、分析と一致します。これが正解です。
問3:正解④
<問題要旨>
ニセコ地区の地形図や写真に関する会話文を読み、下線部①~④の中から誤りを含む記述を選ぶ問題です。地形図の読図能力に加え、火山地形、北海道の歴史(開拓)、河川地形(河畔林)など、多角的な知識が問われます。
<選択肢>
①【正】
地点aから見える地形は、頂上が広く緩やかな斜面を持つ形状から、火山活動によって形成された地形(溶岩台地など)の一部と推測できます。記述は妥当です。
②【正】
図4-Bの等高線を見ると、地点bは周囲より標高の高い尾根筋に位置しています。また、写真bの奥には富士山に似た形の羊蹄山が見えており、スキーをしながら羊蹄山を眺めることができるという記述は妥当です。
③【正】
地点cから見える倶知安町の市街地は、道路が碁盤目状に整備されています。これは明治以降の北海道開拓において、計画的に区画整理されたこと(条里制に倣った区画)を示す景観です。記述は妥当です。
④【誤】
地点dから見える蛇行した木々の列は、川の流れに沿って形成された自然堤防上に生育する「河畔林」です。住居を風雪から守るために人工的に植えられる「防風林(屋敷林)」は、通常、家屋を囲むように、あるいは直線的に造成されます。したがって、この木々を防風林と説明するのは誤りです。
問4:正解②
<問題要旨>
ニセコ地区における訪日外国人の動向に関する地図、写真、会話文を読み解き、空欄X(場所)とy(文)の正しい組み合わせを選ぶ問題です。インバウンド観光が地域に与える経済的・社会的影響について、資料から論理的に考察する力が求められます。
<選択肢>
①・③~⑥【誤】
まず、空欄Xを特定します。会話文では、写真tのような「外国人が多く利用する宿泊施設」が範囲Xにあると述べられています。写真tは近代的なリゾートマンション(コンドミニアム)です。図6の地図を見ると、範囲Fはスキー場の麓にあり、訪日外国人の利用人数を示す黒いメッシュが集中しています。ここに外国人向けの宿泊施設が集まっていると考えられます。したがって、XはFです。
次に、空欄yを特定します。会話は、宿泊料金が1泊10万円を超えるほど高騰しているという流れです。この状況を受けての結論として最も自然なのは、文シ「宿泊施設の周辺では、観光による利益を見込んで、土地の価格が上昇するだろうね」です。高い需要と収益性は、地価の高騰を招くのが経済の原則です。文サ(波及効果はない)や文ス(新たな建設はない)は、この状況とは逆の結論であり不自然です。
②【正】
XにF、yにシが入る組み合わせは、分析と一致します。これが正解です。
問5:正解③
<問題要旨>
ニセコ地区の「外国人」と「日本人」の延べ宿泊者数について、年次推移のグラフ(タ、チ)と、月別割合のグラフ(P、Q)を正しく特定する問題です。ニセコが国際的なウィンターリゾートであるという知識を基に、コロナ禍の影響や観光シーズンの違いをグラフから読み解きます。
<選択肢>
①・②・④【誤】
まず、年次推移(タ、チ)を特定します。ニセコは外国人観光客に非常に人気があるため、2020年以降の新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる国際的な移動制限の影響を大きく受けたはずです。グラフ「タ」は、2019年まで高い水準だったものが2020年以降に激減しており、外国人宿泊者数の推移と判断できます。一方、「チ」は元々の数が少なく、変動も比較的小さいため、日本人宿泊者数と判断できます。
次に、月別割合(P、Q)を特定します。外国人観光客の主な目的は冬のスキーであるため、宿泊は冬シーズン(12月~2月)に極端に集中するはずです。グラフ「P」はまさにその特徴を示しており、これが外国人の月別割合です。一方、日本人は夏のアクティビティなども楽しむため、夏(7、8月)にもピークがあり、年間を通じて観光客が訪れます。グラフ「Q」がその特徴を示しており、これが日本人です。
したがって、「外国人延べ宿泊者数の推移」はタ、「外国人延べ宿泊者数の月別割合」はPとなります。
③【正】
推移がタ、月別割合がPという組み合わせは、分析と一致します。これが正解です。
問6:正解②
<問題要旨>
ニセコの観光に関する4つの「住民意見」と、それに対応する「施策案」、「指標案」の組み合わせの中から、論理的なつながりとして適当でないものを一つ選ぶ問題です。地域課題の発見から解決策の立案、そして効果測定という一連の流れ(PDCAサイクルなど)を正しく理解できているかが問われます。
<選択肢>
①【適当】
「景観が壊れる」という意見に対し、「住民説明会の開催」を施策とし、その「開催回数・参加者数」を指標とするのは、住民合意の形成プロセスとして妥当な組み合わせです。
②【不適当】
「交通に支障が出る(渋滞)」という意見に対し、「需要の季節的な偏りに対応した事業者の誘致」という施策は、直接的な渋滞対策とは言えません。むしろ事業者が増えれば交通量が増える可能性もあります。また、指標の「キャッシュレス化率」も、渋滞緩和の効果を直接測るものではありません。意見、施策、指標の間に論理的なつながりが弱く、これが不適当な選択肢です。
③【適当】
「農産物を売りたい」という意見に対し、「加工・販売への補助」を施策とし、その結果を「売上額」で測るのは、6次産業化の推進策として非常に分かりやすく、妥当な組み合わせです。
④【適当】
「外国人を受け入れたい」という意見に対し、「文化や言語を学ぶ場の創出」を施策とし、その成果を「住民の親しみ度」で測るのは、多文化共生に向けたソフト面の施策として妥当な組み合わせです。