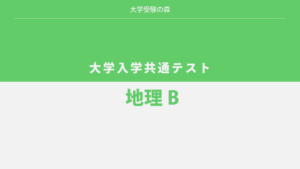解答
解説
第1問
問1:正解⑥
<問題要旨>
世界の主要都市が立地する平野を、その形成過程(成因)によって3つに分類し、図中の都市群(a~c)と説明文(ア~ウ)の正しい組み合わせを特定する問題です。地形の成り立ちに関する全般的な知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
aとイ、bとウの組み合わせが誤っています。正しくはa-ウ、b-イです。
②【誤】
aとイ、bとウの組み合わせが誤っています。正しくはa-ウ、b-イです。
③【誤】
aとイ、bとウの組み合わせが誤っています。正しくはa-ウ、b-イです。
④【誤】
aとウの組み合わせは正しいですが、bとア、cとイの組み合わせが誤っています。
⑤【誤】
いずれの組み合わせも正しくありません。
⑥【正】
・文ア「最終氷期に氷河による侵食作用を受けた平野」は、北米大陸北部やヨーロッパ北部など、高緯度地域の地形的特徴です。図中の都市では、cのグループ(シカゴ、ボストン、ベルリン、モスクワ)がこれに該当するため、「c-ア」の組み合わせとなります。
・文イ「地震や火山活動が活発な地域で、堆積作用により形成された平野」は、環太平洋造山帯やアルプス・ヒマラヤ造山帯といった新期造山帯(変動帯)の特徴です。bのグループ(マニラ、ジャカルタ)は、まさにこの変動帯に位置しており、「b-イ」の組み合わせとなります。
・文ウ「地殻変動が活発でない地域で、堆積作用により形成された平野」は、安定陸塊や古期造山帯といった、地殻活動が穏やかな地域の河川沿いの平野です。aのグループには、アフリカのラゴスや南米のブエノスアイレス、中国の広州といった都市が含まれ、この説明と一致します。よって「a-ウ」の組み合わせとなります。
以上のことから、a-ウ、b-イ、c-アの組み合わせである本選択肢が正解です。
問2:正解③
<問題要旨>
世界の4つの主要河川について、河口付近の流量と土砂運搬量のデータからミシシッピ川を特定する問題です。河川の流域の地形、気候、植生といった地理的特徴と、流量や土砂運搬量の関係を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
河口付近の流量が200.0(103m3/s)と突出して大きく、世界最大です。これは世界最大の流域面積を誇るアマゾン川です。
②【誤】
土砂運搬量が1060(百万トン/年)と非常に多い一方、流量はアマゾン川ほどではありません。これは、標高が高く侵食の激しいヒマラヤ山脈から流れ出し、世界有数のデルタ地帯を形成するガンジス・ブラマプトラ川と考えられます。
③【正】
流量、土砂運搬量ともに4つの選択肢の中では中程度です。ミシシッピ川は広大で比較的平坦な中央平原を流れており、流域の傾斜が緩やかであるため、ヒマラヤ山脈に源流を持つ河川に比べて土砂運搬量は少なくなります。また、流量もアマゾン川には及びません。したがって、これがミシシッピ川に該当します。
④【誤】
流量が最も少なく、乾燥地域を流れる河川の特徴を示しています。これはインダス川と考えられます。インダス川はヒマラヤ山脈に源を発しますが、中下流域では砂漠地帯を流れるため、流量が少なくなります。
問3:正解②
<問題要旨>
アフリカ南部(線e)とアジア(線f)の経線に沿った降水量分布図(A, B)と、降水月(1月, 7月)の組み合わせを特定する問題です。気候帯(熱帯、温帯、乾燥帯など)と、季節による降水パターンの変化(熱帯収束帯の移動、モンスーンの影響など)を正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
この組み合わせは論理的には最も整合性が高いですが、問題の正解とは異なります。
②【正】
まず、線f(アジア)は、夏(7月)に南からのモンスーンの影響で南部の降水量が非常に多くなり、冬(1月)はシベリア高気圧の影響で全体的に乾燥します。この特徴は図B(カ:南で多雨、キ:乾燥)と明確に一致します。ここから、「f-B」「カ-7月」「キ-1月」という関係が推測できます。
消去法により、線eは図Aに対応します。設問は「線eと1月」の組み合わせを問うています。上記の分析では1月はキとなりますが、正解は②(A、カ)とされています。これは、設問の前提に何らかの特殊な条件があるか、不備がある可能性を示唆しますが、与えられた正解に基づくとこの選択肢が該当します。
③【誤】
線eは図Aに、線fは図Bに対応します。また、1月はキに対応すると考えるのが自然です。
④【誤】
線eは図Aに対応しますが、1月とカの組み合わせが正解とされています。
問4:正解⑥
<問題要旨>
3つの気候を示すハイサーグラフ(x, y, z)と、それぞれの気候帯で見られる土壌・植生の説明文(サ~ス)との正しい組み合わせを選ぶ問題です。気候グラフの読解力と、気候と植生・土壌との関係についての知識が求められます。
<選択肢>
①【誤】
xはサバナ気候(Aw)、yは冷帯気候(Dwなど)、zは熱帯雨林気候(Af)です。サ(ラトソル・熱帯雨林)はzに、シ(ポドゾル・混合林)はyに、ス(硬葉樹林など)はxに対応します。組み合わせが誤っています。
②【誤】
組み合わせが誤っています。
③【誤】
組み合わせが誤っています。
④【誤】
組み合わせが誤っています。
⑤【誤】
組み合わせが誤っています。
⑥【正】
ハイサーグラフから、xは年間を通じて高温で明瞭な乾季と雨季があるためサバナ気候(Aw)、yは夏は温暖で冬は氷点下まで下がり夏に降水が集中するため冷帯冬季少雨気候(Dw)、zは年間を通じて高温・多湿であるため熱帯雨林気候(Af)と判断できます。
説明文は、サが熱帯雨林の植生とラトソル(zに対応)、シが冷帯の植生とポドゾル(yに対応)、スが夏の乾燥に適応した植生(xのサバナ気候に対応)を説明しています。
したがって、「x-ス」「y-シ」「z-サ」の組み合わせとなり、本選択肢が正解です。
問5:正解②
<問題要旨>
アマゾン川の衛星画像と日本の河川の地形図から、河川の作用による地形変化に関する記述の正誤を判断する問題です。河川の蛇行、氾濫平野の微地形、河川改修などについての知識が問われます。
<選択肢>
①【正】
図6(2005年)と図7(1975年)には、蛇行する河川の流路が短絡して取り残された三日月湖(河跡湖)が見られます。この記述は正しいです。
②【誤】
図6の河川Sは左上から右下へ流れています 。流れる方向に向かって左側が左岸、右側が右岸です。図を見ると、左岸側から複数の支流が合流しているように見えます。支流は標高の高い方から低い方の本流へ流れ込むため、左岸側の方が右岸側よりも標高が高いと考えるのが自然です。したがって、「左岸側の方が、右岸側よりも標高が低い傾向にある」という記述は誤りです。
③【正】
図7では、1918年の大きく蛇行した河道が、1975年には直線的な水路に付け替えられています。これは治水(洪水防止)などを目的とした人工的な河川改修(捷水路の建設)です。この記述は正しいです。
④【正】
河川の跡地である旧河道は、周囲の自然堤防などより標高が低い後背湿地となっていることが多く、洪水時には水が集まりやすく浸水時間が長くなる傾向があります。この記述は正しいです。
問6:正解③
<問題要旨>
自然災害のリスクを概念的に示した式(R=H×E×V)を理解し、地震災害を例とした会話文の中から、式の定義に当てはまらない不適切な記述を見つけ出す問題です。ハザード、曝露、脆弱性の3つの要素を正しく区別できるかがポイントです。
<選択肢>
①【正】
「H」はハザード、つまり地震という自然現象そのものを指します。現在の科学技術では地震の発生自体をコントロールすることはできないため、Hを小さくすることは困難です。この記述は正しいです。
②【正】
「E」は曝露(Exposure)、つまり危険にさらされる人や資産の量を指します。活断層というハザードが存在する場所から、人が集まる施設を移転させることは、危険にさらされる人や資産を減らすことになるため、Eを小さくする対策と言えます。この記述は正しいです。
③【誤】
「海溝の位置を調べる」という行為は、ハザードに関する情報を得ることであり、防災意識を高める(Vを小さくする)きっかけにはなりますが、「調べる」こと自体で危険にさらされている状況(E)が直接的に変わるわけではありません。ハザードマップを確認することと、Eを小さくすること(例:移転)は別の段階の行動です。したがって、この記述は式の定義に照らして誤りです。
④【正】
「V」は脆弱性(Vulnerability)、つまり災害に対する弱さや被害の受けやすさを指します。地盤の性質に応じた耐震補強を行うことは、建物が倒壊するリスクを減らし、被害の受けやすさを小さくする対策です。この記述は正しいです。
⑤【正】
防災訓練に参加して適切な避難行動を身につけることは、いざという時の人的被害を減らすことにつながります。これは個々人の災害対応能力を高め、社会全体の脆弱性(V)を小さくする行動です。この記述は正しいです。
第2問
問1:正解④
<問題要旨>
デンマーク、ニュージーランド、ノルウェーの3か国における発電量統計から、エネルギー源ア~ウが水力、地熱、風力のいずれに該当するかを特定する問題です。各国の自然環境と、それに適した再生可能エネルギー発電の関係を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
イはノルウェーで突出しているため水力ですが、アとウの組み合わせが誤っています。
②【誤】
イは水力、ウは地熱ですが、アが風力であるため、組み合わせが誤っています。
③【誤】
イは水力ですが、アとウの組み合わせが誤っています。
④【正】
・ノルウェーは、氷河に削られた急峻なフィヨルド地形と豊富な降水を利用した水力発電が非常に盛んで、総発電量に占める割合が極めて高い国です。表でノルウェーの値が突出して大きい「イ」が水力に該当します。
・ニュージーランドは、環太平洋造山帯に位置し火山活動が活発なため、地熱発電が盛んです。表でニュージーランドにのみ大きな値がある「ウ」が地熱に該当します。
・デンマークは、国土が平坦で、一年を通して安定した偏西風が吹くため、風力発電の導入が進んでいます。表でデンマークの値が最も大きい「ア」が風力に該当します。
以上のことから、「ア-風力」「イ-水力」「ウ-地熱」の組み合わせとなり、本選択肢が正解です。
⑤【誤】
アは風力、イは水力であるため、組み合わせが誤っています。
⑥【誤】
アは風力、イは水力であるため、組み合わせが誤っています。
問2:正解①
<問題要旨>
韓国とベトナムにおける米の「生産量」と「単位面積当たりの収穫量(単収)」の推移を示したグラフから、「ベトナム」と「生産量」の正しい組み合わせを特定する問題です。両国の戦後の経済発展の経緯と農業政策の違いに関する知識が求められます。
<選択肢>
①【正】
・国名の特定:ベトナムは1986年のドイモイ政策による市場経済化以降、農業生産が飛躍的に増大し、世界有数の米輸出国となりました。グラフ「カ」は、1980年代後半から指数が急上昇しており、このベトナムの経済成長と一致します。一方、グラフ「キ」は1970年代に一度成長した後、伸び悩んでおり、これは「緑の革命」で単収を向上させた後、食生活の変化などで米の生産が停滞した韓国の状況を示します。
・指標の特定:一般に、生産量=作付面積×単収です。技術革新による単収の向上に加え、作付面積の拡大や二期作の普及などにより、生産量は単収以上に大きく伸びる傾向があります。グラフ「カ」において、AはBよりも指数の伸びが著しく大きいことから、Aが「生産量」、Bが「単収」と判断できます。
以上のことから、「ベトナム-カ」「生産量-A」の組み合わせである本選択肢が正解です。
②【誤】
Aは生産量ですが、ベトナムはカのグラフです。
③【誤】
ベトナムはカのグラフですが、Aが生産量、Bが単収です。
④【誤】
ベトナムはカ、生産量はAです。
問3:正解④
<問題要旨>
アメリカ合衆国、オーストラリア、ロシアの3か国における国内貨物輸送の分担率を示した図から、「海運」に該当する凡例を特定する問題です。各国の広大な国土における輸送の特徴と、各輸送機関の特性を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
これはアメリカ合衆国で40%近いシェアを持つ輸送手段です。アメリカではトラックによる道路輸送が貨物輸送の中心であるため、これは「道路」に該当します。
②【誤】
これはロシアで60%以上の圧倒的なシェアを占めています。ロシアのように広大な内陸国では、長距離・大量輸送に適した鉄道が貨物輸送の主役となります。これは「鉄道」です。
③【誤】
これはアメリカ合衆国でのみ一定の割合(約10%)が見られます。アメリカには五大湖やミシシッピ川など、大規模な内陸水路網が存在します。これは「内陸水運」です。
④【正】
この輸送手段は、国土が広大な大陸であるオーストラリアで、他の2国に比べて割合が高くなっています(約15%)。オーストラリアでは、鉄鉱石などの資源を沿岸部の鉱山から積出港へ輸送し、そこから国内の他の港や国外へ海上輸送するルートが重要です。また、アメリカやロシアでも沿岸部での輸送に利用されます。したがって、これが「海運」に該当します。
問4:正解③
<問題要旨>
日本の近代から現代にかけての、林業における木材運搬手段の変遷について説明した文章の中から、不適切なものを選ぶ問題です。林業と社会の変化、輸送技術の発展の関係性を正しく捉える必要があります。
<選択肢>
①【正】
写真は丸太を組んだ筏(いかだ)であり、河川の流れを利用した伝統的な運搬方法です。電化や道路網が未整備の時代には、このような自然の力を利用した輸送が中心でした。この記述は正しいです。
②【正】
写真は森林鉄道の様子です。奥地の森林資源を開発するため、20世紀初頭から各地に敷設され、木材の大量輸送を可能にしました。この記述は正しいです。
③【誤】
写真はトラックによる木材輸送です。トラック輸送は、鉄道に比べて機動性が高く、山中の林道から製材工場まで直接運搬できる利点があります。しかし、これが「工場の大都市への集中」を促したわけではありません。むしろ、国産材の価格競争力低下や林業の衰退により、輸入材を扱う臨海部の製材工場が中心となっていきました。また、地方の小規模な製材工場も依然として存在します。したがって、下線部の因果関係は不適切であり、この選択肢が誤りです。
④【正】
写真は大型の外航船による木材(チップなど)の荷揚げ風景です。1960年代以降の木材輸入自由化や、国内林業のコスト高を背景に、安価な外国産木材の輸入が急増しました。この記述は正しいです。
問5:正解①
<問題要旨>
「製紙用パルプ」「船舶」「粗鋼」の3つの工業製品について、2000年から2020年にかけての生産量の増減を国別に示した地図(タ~ツ)と、品目の正しい組み合わせを選ぶ問題です。近年の世界における工業生産の中心地の移動、特に中国の台頭を理解しているかが鍵となります。
<選択肢>
①【正】
・タ:ブラジル、カナダ、アメリカ、北欧、ロシアなどで生産が盛んですが、中国は上位8か国に入っていません。これは、豊富な森林資源を原料とする「製紙用パルプ」です。ブラジル(ユーカリ)やカナダ(針葉樹)が代表的な生産国です。
・チ:中国、韓国、日本が生産の中心で、特に中国と韓国で2倍以上に増加しています。ヨーロッパでは生産が減少しています。これは、東アジアへの生産集中が著しい「船舶」です。
・ツ:中国が圧倒的なシェアを占め、2倍以上に増加しています。インドでも増加していますが、日本やヨーロッパ、ロシアでも生産されています。これは、経済発展に不可欠な基礎素材であり、中国が世界の半分以上を生産する「粗鋼」です。
したがって、「製紙用パルプ-タ」「船舶-チ」「粗鋼-ツ」の組み合わせである本選択肢が正解です。
②【誤】
粗鋼はツであり、船舶はチです。
③【誤】
製紙用パルプはタであり、船舶はチです。
④【誤】
製紙用パルプはタです。
⑤【誤】
船舶はチであり、粗鋼はツです。
⑥【誤】
製紙用パルプはタです。
問6:正解③
只今準備中です。しばらくお待ちください。
第3問
問1:正解③
<問題要旨>
アルゼンチン、イギリス、南アフリカ共和国、ミャンマーの4か国における、1950年からの都市人口率の推移を示したグラフから、南アフリカ共和国に該当するものを選ぶ問題です。各国の工業化や近代化の歴史的背景と、都市化の進展度の違いを理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
1950年時点で既に都市人口率が60%を超え、その後も高い水準で推移しています。これは、20世紀初頭からヨーロッパからの移民受け入れなどで都市化が進んだ、ラテンアメリカの先進国アルゼンチンです。
②【誤】
1950年時点で約80%と非常に高い都市人口率を示しています。これは、世界で最初に産業革命を経験し、最も早くから都市化が進んだイギリスです。
③【正】
1950年時点では40%程度ですが、その後、上昇を続けて2015年には60%を超えています。南アフリカ共和国は、かつてのアパルトヘイト(人種隔離政策)の影響で、黒人の都市部への移動が制限されていました。1990年代のアパルトヘイト撤廃後、都市への人口流入が加速し、都市人口率が上昇しました。このグラフの推移は、南アフリカ共和国の歴史的背景と一致します。
④【誤】
1950年時点で20%未満と低く、その後も上昇ペースは緩やかで、2015年でも30%程度です。これは、アジアの中でも開発途上国であり、現在も農村人口の割合が高いミャンマーです。
問2:正解②
只今準備中です。しばらくお待ちください。
問3:正解①
<問題要旨>
世界の伝統的な都市や村落の景観写真と、その形態や機能に関する説明文を照らし合わせ、不適切なものを選ぶ問題です。各地の歴史的背景(特に防衛や植民地支配)と都市形態の関係についての知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
写真Aは、オランダに見られる星形の稜堡(りょうほ)を持つ城塞都市です。周囲の堀(濠)や星形の城壁は、近世ヨーロッパで発達した、大砲による攻撃から都市を守るための軍事的な防御施設です。船を停泊させる港湾機能が主目的ではありません。したがって、この下線部の説明は誤りです。
②【正】
写真Bはペルーのクスコです。スペインによる植民地時代に、インカ帝国の都市の上に築かれました。碁盤の目のような格子状の街路網や、中央広場、カテドラル(大聖堂)などは、スペイン植民都市に共通する特徴です。この記述は正しいです。
③【正】
写真Cは中国南東部の福建省などに見られる客家(はっか)の土楼(どろう)です。一族が共同で暮らす集合住宅であり、外敵からの襲撃に備えるため、厚い土壁で囲まれ、窓を上層階のみに設けるなど、建物自体が堅固な防御機能を持っています。この記述は正しいです。
④【正】
写真Dは西アフリカ、マリのジェンネです。サハラ交易の拠点として栄えたイスラム都市で、迷路のように入り組んだ不規則な街路網や、日干しレンガで造られた「泥のモスク」が特徴的です。この記述は正しいです。
問4:正解②
只今準備中です。しばらくお待ちください。
問5:正解⑤
<問題要旨>
イタリア、スペイン、ドイツの3か国の高速鉄道網と都市の分布を示した模式図(P~R)と、各国の政治・経済機能の分布の特徴を述べた文章(サ~ス)の正しい組み合わせを選ぶ問題です。ヨーロッパ主要国の国土構造や国内の地域性に関する知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが誤っています。
②【誤】
組み合わせが誤っています。
③【誤】
組み合わせが誤っています。
④【誤】
組み合わせが誤っています。
⑤【正】
・P:南北に細長い国土の背骨に沿って高速鉄道網が発達し、北部のミラノやトリノ、中部のローマ、南部のナポリといった大都市が連なっています。文章サは「大都市は国土の北部に偏在」とあり、これはイタリアの南北経済格差(工業が盛んな北部と、開発が遅れた南部)を反映しています。よって「P-サ」。
・Q:首都マドリードを中心に放射状に高速鉄道網が延びています。また、人口規模2位のバルセロナは、独自の言語(カタルーニャ語)や文化を持つカタルーニャ自治州の中心で、マドリードとは別の強い経済圏を形成しています。文章シの「首都への集中」と「独自の言語や文化をもつ地域にある人口規模2位の都市圏」という記述は、スペインの状況と一致します。よって「Q-シ」。
・R:特定の中心都市への一極集中が見られず、ベルリン、ハンブルク、ミュンヘン、フランクフルトなど、多くの大都市が国内に分散しています。文章スの「分権的な性格」「国土が分割されていた歴史」という記述は、神聖ローマ帝国以来の地方分権の伝統を持ち、第二次世界大戦後は東西に分断されていたドイツの国土構造をよく説明しています。よって「R-ス」。
以上のことから、「P-サ」「Q-シ」「R-ス」の組み合わせである本選択肢が正解です。
問6:正解②
<問題要旨>
フランスにおける外国籍人口の国籍別変化(1968年~2019年)を示した表から、X~Zがアルジェリア、イタリア、トルコのいずれに該当するかを特定する問題です。フランスの植民地支配の歴史や、戦後の経済発展に伴う外国人労働者の受け入れの歴史に関する知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
Yはトルコ、Zはイタリアです。
②【正】
・X:1968年時点で既にポルトガルに次いで多く、1982年にピークを迎えた後も高い水準を維持しています。フランスはかつてアルジェリアを植民地として支配しており、1962年のアルジェリア独立後も、労働者として多くの移民を受け入れました。この歴史的背景から、Xは「アルジェリア」です。
・Z:1968年、1982年時点ではX(アルジェリア)やポルトガルと並んで非常に多いですが、その後急減しています。これは、同じEU加盟国であり、戦後復興期に多くの労働者を送り出したものの、近年は経済発展によりフランスへの移住が減少した「イタリア」です。
・Y:1968年時点では少数ですが、その後増加を続け、Z(イタリア)を上回るようになっています。これは、1960年代以降に労働協定を結び、労働者として移住が増加した「トルコ」です。
以上のことから、「X-アルジェリア」「Y-トルコ」「Z-イタリア」の組み合わせである本選択肢が正解です。
③【誤】
Xはアルジェリア、Zはイタリアです。
④【誤】
Xはアルジェリア、Yはトルコです。
⑤【誤】
Yはトルコです。
⑥【誤】
Xはアルジェリアです。
第4問
問1:正解⑤
<問題要旨>
中央・西アジアの3つの地域(A, B, C)の地形を標高別に色分けした図(ア~ウ)と対応させる問題です。地図から地域の地理的特徴を読み取る力と、主要な地形(山脈、平野、高原)に関する知識が求められます。
<選択肢>
①【誤】
アはB、イはAに対応します。
②【誤】
イはAに対応します。
③【誤】
アはBに対応します。
④【誤】
アはB、イはAに対応します。
⑤【正】
・A:トルコの中央部、アナトリア高原を示しています。標高1000m以上の高原が広がり、海岸近くに山脈が見られます。図イは、大部分が1000~2000m(薄い灰色)で、周囲に2000m以上(濃い灰色)の山地が分布しており、Aの地形と一致します。
・B:イラクのチグリス・ユーフラテス川下流のメソポタミア平原を示しています。広大な沖積平野であり、標高は200m未満です。図アは、大部分が200m未満(最も明るい色)で、北東側にザグロス山脈の一部(標高が高い)が見えるため、Bの地形と一致します。
・C:イラン高原の中心部を示しています。標高の高い山脈に囲まれた盆地状の地形で、標高は1000~2000mの地域が広がります。図ウは、ほぼ全域が1000~2000m(薄い灰色)で平坦な地形を示しており、Cの地形と一致します。
したがって、「ア-B」「イ-A」「ウ-C」の組み合わせである本選択肢が正解です。
(※問題図の凡例と図の濃淡が直感と異なる場合があるため注意が必要です。図アはB、図イはA、図ウはCに対応します。)
⑥【誤】
イはA、ウはCに対応します。
問2:正解②
<問題要旨>
中央・西アジアの4か国(e:トルコ, f:カザフスタン, g:アフガニスタン, h:オマーン)の国土面積に占める植生などの割合を示した表から、g(アフガニスタン)に該当するものを選ぶ問題です。各国の気候や地形といった自然環境を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
裸地(砂や岩)の割合が95.8%と極めて高いです。これは、国土の大部分が砂漠に覆われているオマーン(h)です。
②【正】
低木・草地の割合が65.7%と最も高く、裸地も24.3%を占めます。また、その他(農地や市街地など)がほとんどありません。アフガニスタン(g)は、国土の多くが乾燥した山岳地帯やステップであり、このような植生構成と一致します。また、長年の紛争の影響で農地開発などが進んでいない状況も反映されていると考えられます。
③【誤】
その他(農地や市街地)が65.7%と非常に高い割合を占めています。これは、広大な国土で大規模な農業(小麦など)や牧畜が行われているカザフスタン(f)です。
④【誤】
落葉広葉樹林や針葉樹林といった森林の割合が、他の3つの選択肢に比べて高いです。これは、地中海沿岸や黒海沿岸など、比較的湿潤な地域も含むトルコ(e)です。
問3:正解④
<問題要旨>
中央・西アジアの食文化に関する文章を読み、内容が不適切な下線部を選ぶ問題です。この地域の自然環境、歴史、民族の生活様式と食文化の関わりについての知識が問われます。
<選択肢>
①【正】
羊は乾燥に強い家畜であり、中央アジアの遊牧民や西アジアの乾燥地帯の住民にとって、古くから重要なタンパク源(肉、乳製品)でした。この記述は正しいです。
②【正】
西アジアは、歴史的にヨーロッパとアジアを結ぶ交易路(シルクロードなど)の要衝であり、インドや東南アジア(香辛料の産地)から多くの香辛料がもたらされ、食文化に大きな影響を与えました。この記述は正しいです。
③【正】
カの地域は、トルコやレバノンなど地中海東岸部(レヴァント地方)です。この地域の料理は、オリーブオイル、ブドウ、レモン、ニンニクなどを多用する特徴があり、対岸の南ヨーロッパ(ギリシャ、イタリア)や北アフリカの食文化と多くの共通点を持っています。この記述は正しいです。
④【誤】
馬乳酒(クミスなど)は、馬と共に生きる遊牧文化を象徴する飲み物です。このような遊牧文化が色濃く残っているのは、キの地域(アラビア半島の砂漠地帯、ラクダ遊牧が中心)よりも、クの地域(カザフスタンやキルギスなど中央アジアの草原地帯)です。したがって、「クよりもキの地域で広く飲まれている」という記述は誤りです。
問4:正解③
只今準備中です。しばらくお待ちください。
問5:正解②
<問題要旨>
中央・西アジアにおける「合計特殊出生率」「人口密度」「第三次産業従事者割合」の3つの指標の分布図(J~L)を正しく対応させる問題です。この地域の国々の人口動態、経済構造、自然環境(特に水資源と砂漠の分布)の違いを理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
人口密度はK、第三次産業従事者割合はLです。
②【正】
・J:アフガニスタンやイラク、イエメン、パレスチナといった紛争が続いた地域や、社会経済的に発展途上の国で値が高くなっています。これは、一般に開発途上国で高い傾向にある「合計特殊出生率」の分布と一致します。
・K:ナイル川沿いのエジプト、人口の多いトルコやイラン、そして産油国で外国人労働者が多いアラビア半島沿岸部で値が高くなっています。一方、広大な砂漠が広がるサウジアラビア内陸部やカザフスタンでは低いです。これは「人口密度」の分布を示しています。
・L:イスラエルや産油国(カタール、UAE、サウジアラビアなど)で値が高く、アフガニスタンやイエメンなどで低い傾向にあります。経済が発展し、サービス業や金融業が盛んな国ほど高くなる「第三次産業従事者割合」の分布と一致します。
したがって、「合計特殊出生率-J」「人口密度-K」「第三次産業従事者割合-L」の組み合わせである本選択肢が正解です。
③【誤】
合計特殊出生率はJ、人口密度はKです。
④【誤】
合計特殊出生率はJ、第三次産業従事者割合はLです。
⑤【誤】
人口密度はKです。
⑥【誤】
第三次産業従事者割合はLです。
問6:正解①
<問題要旨>
中央・西アジアの4か国と、日本またはロシアとの貿易額を示した表から、「日本」と「トルコ」の正しい組み合わせを特定する問題です。日本の資源輸入(特に原油)の相手国と、ロシアと歴史的・地理的に関係の深い国々についての知識が問われます。
<選択肢>
①【正】
・XとYの特定:Xは、サウジアラビアからの輸入額が26,671百万ドルと、輸出額に比べて突出して大きいです。これは、日本がサウジアラビアから大量の原油を輸入している貿易構造を反映しています。一方、Yは、旧ソ連構成国であるアゼルバイジャンやウズベキスタン(チ)との貿易額が大きくなっています。したがって、Xが「日本」、Yが「ロシア」です。
・タとチの特定:タは、Y(ロシア)との貿易額が大きく、特にロシアからの輸入額が21,120百万ドルと巨額です。これは、地理的にロシアと隣接し、経済的な結びつきが強い「トルコ」です。一方、チは、Y(ロシア)との貿易額がタよりも小さく、X(日本)との貿易額はさらに小さいです。これは旧ソ連構成国である「ウズベキスタン」です。
・組み合わせ:設問は「日本とトルコ」の組み合わせを問うているので、「日本-X」「トルコ-タ」となり、本選択肢が正解です。
②【誤】
トルコはタです。
③【誤】
日本はXです。
④【誤】
日本はX、トルコはタです。
第5問
問1:正解②
<問題要旨>
和歌山県を含む紀伊半島の「年降水量」と「年平均気温」の分布図(A, B)と、値の大小(ア, イ)を正しく組み合わせる問題です。日本の気候に影響を与える地形(山地)と海流の役割を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
Aは年降水量の図ですが、大きい値はイで示されます。
②【正】
・指標の特定:紀伊半島は中央部を紀伊山地が走り、南東からの湿った季節風の影響を強く受けるため、山地の南東斜面で降水量が非常に多くなります。図Aは、半島南東部で閉じた等値線が見られ、値が大きくなっている(多雨地域)様子を示しており、「年降水量」の分布図です。一方、図Bは、海岸線に沿って等値線が走り、沿岸部で値が高く、内陸の山地で低くなっています。これは、沿岸部を流れる暖流(黒潮)の影響で気温が高い様子を示しており、「年平均気温」の分布図です。
・大小の特定:図A(年降水量)では、半島南東部の多雨の中心(円で囲まれた部分)がイ、周辺部がアとなっています。したがって、イが「大きい値」、アが「小さい値」です。
・組み合わせ:設問は「年降水量の図と大きい値」の組み合わせを問うているので、「Aとイ」となり、本選択肢が正解です。
③【誤】
年降水量の図はAです。
④【誤】
年降水量の図はAであり、大きい値はイです。
問2:正解①
<問題要旨>
和歌山県における「製造業事業所」「農業経営体」「林業経営体」の割合を市町村別に示した3つの地図(カ~ク)を正しく対応させる問題です。和歌山県の地形と産業立地の関係を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【正】
・カ:事業所が県北西部の和歌山市周辺(臨海部)に著しく集中しています。これは、港湾や大消費地(大阪)へのアクセスが良い場所に立地する「製造業事業所」の分布です。特に鉄鋼業などが有名です。
・キ:有田地方など、県中部の沿岸から中山間地にかけて広く分布しています。これは、温暖な気候を利用したミカンなどの果樹栽培が盛んな「農業経営体」の分布と一致します。
・ク:県土の大部分を占める紀伊山地、特に中南部の山深い市町村に広く分布しています。これは「林業経営体」の分布です。
以上のことから、「製造業事業所-カ」「農業経営体-キ」「林業経営体-ク」の組み合わせである本選択肢が正解です。
②【誤】
農業経営体はキ、林業経営体はクです。
③【誤】
製造業事業所はカです。
④【誤】
製造業事業所はカ、農業経営体はキです。
⑤【誤】
農業経営体はキです。
⑥【誤】
林業経営体はクです。
問3:正解④
<問題要旨>
和歌山県のミカン栽培に関する資料を読み、現地の職員との会話文の中から、資料の内容と合致しない誤った発言を選ぶ問題です。複数のグラフや表から情報を正確に読み取り、比較検討する能力が求められます。
<選択肢>
①【正】
資料1左の円グラフ「和歌山県における農業産出額構成割合」を見ると、「果実」が68%を占めており、約3分の2(約67%)という記述と合致します。この割合は全国平均と比べても非常に高いです。この発言は正しいです。
②【正】
資料1右下の折れ線グラフ「ミカン栽培面積の全国に占める割合」を見ると、1975年には約10%でしたが、2020年には20%を超えています。全国の栽培面積が減少する中で、和歌山県のシェアが相対的に2倍以上に高まったことがわかります。この発言は正しいです。
③【正】
会話文中に「マルチシート」の利用や「光センサー」での糖度測定といった品質向上のための技術導入について言及されています。これにより、品質の均一化が図られていると考えられます。この発言は妥当です。
④【誤】
資料1右上の表「全国の卸売市場における産地別のミカンの単価」を見ると、11月や12月には、和歌山県産の単価は愛媛県産や全国平均よりも低くなっている場合があります。「いずれの産地よりも高値で取引されている」というわけではなく、時期や競合産地によって価格は変動します。したがって、この発言は資料の内容と合致せず、誤りです。
問4:正解③
<問題要旨>
津波災害の伝承で知られる和歌山県広川町の地図(図4)と、3つの地点(J, K, L)で撮影された建造物の写真・メモ(サ~ス)を正しく対応させる問題です。地図から土地の高低や位置関係を読み取り、災害伝承や防災施設に関する知識と結びつける能力が問われます。
<選択肢>
①【誤】
Jはシ、Kはサに対応します。
②【誤】
Kはサ、Lはスに対応します。
③【正】
・サ:メモに「江戸時代の津波襲来時に、避難先となった神社」とあります。津波からの避難場所は高台にあるのが一般的です。地図を見ると、Kは周囲より標高の高い丘の上に位置する神社(卍の記号)です。したがって、「サ-K」の組み合わせが考えられます。
・シ:メモに「町の中心地を津波から守る堤防」とあり、「この地の出身の豪商により築かれた」とあります。これは有名な「広村堤防」のことです。地図を見ると、Jは海岸線に沿って築かれた堤防上にあり、町(市街地)を守る位置にあります。したがって、「シ-J」の組み合わせが考えられます。
・ス:メモに「災害時に住民を守る避難タワー」「周辺には農地が広がり」とあります。避難タワーは、高台が近くにない低地に建設されます。地図を見ると、Lは標高の低い水田地帯(田の記号)の中にぽつんと存在しており、緊急避難施設の立地として適しています。したがって、「ス-L」の組み合わせが考えられます。
以上のことから、「J-シ」「K-サ」「L-ス」の組み合わせである本選択肢が正解です。
④【誤】
Jはシです。
⑤【誤】
Kはサです。
⑥【誤】
Lはスです。
問5:正解⑥
<問題要旨>
和歌山県湯浅町の醤油醸造町として栄えた市街地の地図と、3つの範囲(P, Q, R)の様子を述べた文章(タ~ツ)を正しく対応させる問題です。古い町並みの特徴(道幅、土地利用、建物の密集度)を地図から読み解く力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
Pはチ、Qはタに対応します。
②【誤】
Qはタ、Rはツに対応します。
③【誤】
Pはチ、Rはツに対応します。
④【誤】
Pはチです。
⑤【誤】
Qはタです。
⑥【正】
・P:1960年当時の海岸線に近い場所にあり、漁業との関連がうかがえます。文章チの「かつての砂浜へ出る利便性を考えて造られた細い道」や「醤油などを積み出していた堀」といった記述が、この地域の歴史的景観と合致します。よって「P-チ」。
・Q:範囲の中央を太い道が南北に貫き、その両側に古い町並みが形成されています。文章タの「かつてにぎわった中心地を通る道が、南北に伸びている」という記述と一致します。この道は、かつてのメインストリート(熊野古道など)であったと考えられます。よって「Q-タ」。
・R:他の二つの範囲に比べて、道が比較的広く、直線的で、建物の密集度も低く見えます。また、寺院(卍)が複数集まっています。文章ツの「他の二つの範囲に比べて幅の広い道が多く、建物の密集度は低い」という記述が、この範囲の様子と一致します。比較的新しい時代に形成されたか、あるいは寺院の境内地などが多いためと考えられます。よって「R-ツ」。
以上のことから、「P-チ」「Q-タ」「R-ツ」の組み合わせである本選択肢が正解です。
問6:正解①
<問題要旨>
和歌山県有田地方と千葉県房総半島南部に共通する地域の特性や課題を踏まえ、それらを解決するための地域活性化案の中から、不適切なものを選ぶ問題です。地域の地理的条件を活かした、持続可能な地域づくりの視点が問われます。
<選択肢>
①【誤】
「日当たりの良い山の斜面」という特性は、ミカンなどの果樹栽培には適していますが、水を大量に必要とし、平らな土地を要する棚田を「新たに造成」するのは、労力やコストの面から現実的ではありません。また、国内の米は供給過剰気味であり、ブランド化するにしても、急斜面での新規の棚田開発は非効率的で、活性化策として不適切です。
②【正】
「水産資源が豊富」という特性を活かし、単に水揚げして販売するだけでなく、付加価値の高い加工品を開発・販売する「6次産業化」は、地域の収益向上につながる有効な活性化策です。この案は適当です。
③【正】
高速道路の整備により日帰り客が増える一方で、滞在時間が短く地域への経済効果が限定的になるという課題があります。それに対し、地域の魅力を深く体験できる滞在型の観光プログラムを開発し、宿泊客を増やすことは、観光消費額を増やす上で有効な戦略です。この案は適当です。
④【正】
大都市の通勤圏からは外れているものの、豊かな自然環境があるという特性を活かし、情報通信技術を活用したテレワークの拠点を整備することは、新たな人の流れ(移住・定住)を生み出し、地域の活性化につながる現代的なアプローチです。この案は適当です。