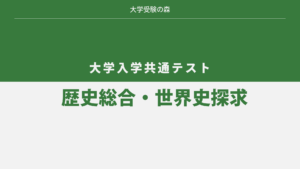解答
解説
第1問
問1:正解①
<問題要旨>
19世紀の万国博覧会に関して、岩倉使節団の目的と万博の性格について正しく理解できているかを問う問題です。
<選択肢>
①【正】
空欄ア:岩倉使節団(1871~73年)の主な目的の一つは、幕末に欧米諸国と結んだ不平等条約の改正に向けた予備交渉でした。空欄イ:会話文にあるエッフェル塔、電気館、地下鉄、動く歩道などは、いずれも当時の最先端の科学技術の産物です。これらの記述から、万博が最新技術を披露する場であったことがわかります。したがって、この組合せは正しいです。
②【誤】
空欄イの「参加国間の平和と安全を保障する場」という記述は、万博の機能ではなく、国際連盟などの国際機関が目指した役割です。したがって、この組合せは誤りです。
③【誤】
空欄アのパリ講和会議は、第一次世界大戦後(1919年)に開催されたもので、岩倉使節団の派遣時期(1871年)とは異なります。したがって、この組合せは誤りです。
④【誤】
空欄アのパリ講和会議の時期が異なる点、空欄イの記述が万博の機能として不適切な点、両方が誤りです。したがって、この組合せは誤りです。
問2:正解④
<問題要旨>
資料1に示された19世紀末の欧米における序列的な世界観を読み解き、同様の思想的背景を持つ歴史的事象を特定する問題です。
<選択肢>
①【誤】
内容「あ」は、資料1が世界を「西洋文明」を頂点とする序列で捉えている点と矛盾するため誤りです。事象「X」の東南アジア諸国連合(ASEAN)は、各国の主権平等を原則とする組織であり、資料1の思想とは異なります。
②【誤】
内容「あ」が資料1の趣旨と異なるため、この組合せは誤りです。
③【誤】
事象「X」のASEANは、主権平等を原則としており、資料1の序列的な世界観とは異なるため、この組合せは誤りです。
④【正】
内容「い」は、資料1が世界を「西洋文明」からの度合いで四つの地域に序列化していることを正しく読み取っています。事象「Y」の日本の南洋諸島委任統治は、第一次世界大戦後、国際連盟の下で「文明が進んだ」とされる日本が「文明が未熟だ」とされた旧ドイツ領の島々を統治した後見制度であり、資料1と同様の優越思想に基づいています。したがって、この組合せは正しいです。
問3:正解②
<問題要旨>
1922年に開催された「平和記念東京博覧会」の背景となった、1920年代の国際情勢について問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
ルール占領(1923年)は、ドイツの賠償金支払い不履行に対するフランスとベルギーによる実力行使であり、国際協調ではなく対立の激化を示す出来事です。
②【正】
不戦条約(ケロッグ=ブリアン協定、1928年)は、第一次世界大戦の反省から、国際紛争の解決手段として戦争を放棄することを多国間で定めたものであり、1920年代の国際協調の気運を象徴する出来事です。第一次大戦の教訓から「平和記念」と名付けられた博覧会の背景として最も適当です。
③【誤】
ウィーン会議(1814~15年)はナポレオン戦争後の国際秩序を定めたものであり、時代が全く異なります。
④【誤】
独ソ不可侵条約(1939年)は、第二次世界大戦直前に結ばれたものであり、1920年代の国際情勢ではありません。
問4:正解⑤
<問題要旨>
下線部「満洲」で20世紀前半に起きた出来事を、年代の古い順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
出来事を年代順に整理すると以下のようになります。
III:旅順・大連の租借権がロシアから日本へ移ったのは、日露戦争後のポーツマス条約(1905年)によります。
I:満洲の軍閥指導者、張作霖が奉天近郊で爆殺されたのは1928年です(張作霖爆殺事件)。
II:鉄道爆破事件(柳条湖事件)に端を発する満洲事変(1931年)の後、国際連盟の調査団(リットン調査団)が派遣されたのは1932年です。
したがって、古い順に並べると「III → I → II」となります。この順で配列されている選択肢は⑤です。
問5:正解②
<問題要旨>
1940年に計画された日本の万国博覧会の延期をめぐる、1938年時点の新聞記事(資料2)と会話文の内容を正確に読み取る問題です。
<選択肢>
①【誤】
文「う」について、資料2には延期に賛成する国々が「各種施設が出来上がらない今のうちに延期を決定するならば」と述べており、準備が終わっていないことが示唆されています。したがって、「開催準備は終わっていたが」という記述は誤りです。
②【正】
文「あ」は、資料2で延期反対国が「中国側の逆宣伝に利用される」と懸念していることから、延期が日本の不利益になると考えていたことがわかります。文「え」は、資料2冒頭の「外務省でも諸外国に対する影響を重視し、かねてより注目していた」という記述から、外交問題化を懸念していたことがわかります。両方とも正しいため、この組合せは正しいです。
③【誤】
文「い」について、資料2の記事は1938年のものであり、第二次世界大戦の開戦(1939年)より前です。したがって、「この時点で第二次世界大戦が開戦していたため」という理由が誤りです。また、文「う」も誤りです。
④【誤】
文「い」の「第二次世界大戦が開戦していたため」という理由が誤りです。
問6:正解①
<問題要旨>
国際スポーツ大会の参加国・地域数と国連加盟国数の推移を示したグラフを読み解き、その変動の要因を正しく結びつける問題です。
<選択肢>
①【正】
変化「あ」について、グラフを見ると1958年から1972年にかけて国連加盟国数(実線)と夏季オリンピック参加国・地域数(棒グラフ)は共に増加傾向にあります。これは正しい読み取りです。事柄「X」の「アフリカの年」(1960年)にはアフリカの多くの国が独立し国連に加盟しており、この時期の加盟国数増加の主要因です。したがって、この組合せは正しいです。
②【誤】
事柄「Y」のソ連解体は1991年の出来事であり、変化「あ」の時期(1958~72年)の要因ではありません。
③【誤】
変化「い」について、グラフでは1986年以降、アジア競技大会の参加国・地域数は減少しておらず、むしろ増加しています。したがって、グラフの読み取りが誤りです。
④【誤】
変化「い」のグラフの読み取りが誤りです。
問7:正解④
<問題要旨>
パネルの空欄に入る語句の組合せを問う問題です。アジア・アフリカ会議と、ソ連のアフガニスタン侵攻に関する知識が問われています。
<選択肢>
①【誤】
空欄エ:「計画経済を採る国々による…国際機構」はソ連中心のコメコン(経済相互援助会議)を指しますが、文脈の「東西冷戦から距離を置こうとする考え」とは合いません。空欄オ:「国際テロ組織…」は2001年のアメリカによるアフガニスタン攻撃の理由であり、1980年のモスクワ五輪ボイコットの理由ではありません。
②【誤】
空欄エが文脈に合いません。
③【誤】
空欄オが時代・内容ともに異なります。
④【正】
空欄エ:パネルの「欧米主導ではない形でのアジア諸地域の連帯」「東西冷戦から距離を置こうとする考え」は、1955年のアジア・アフリカ会議(バンドン会議)で採択された平和十原則(主権の尊重、反植民地主義など)によって示されました。したがって正しいです。空欄オ:1980年のモスクワ五輪ボイココットは、前年(1979年)にソ連がアフガニスタンの社会主義政権を支援するために軍事介入したことへの抗議が直接の原因でした。したがって正しいです。
問8:正解③
<問題要旨>
グラフやパネルの内容を踏まえ、国際関係史に関する記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
グラフで1976年を見ると、夏季オリンピックの参加国・地域数(棒グラフ)は、国連加盟国数(実線)よりも少ないです。「超えていた」という記述は誤りです。
②【誤】
パレスチナ暫定自治協定(オスロ合意)は1993年です。グラフを見ると、それ以前の1974年にイランのテヘランでアジア競技大会が開催されています。テヘランは中東の都市なので、この記述は誤りです。
③【正】
日中国交正常化は1972年です。それ以前のアジア競技大会の開催地(東京、ジャカルタ、バンコク)は、いずれも西側陣営または非同盟諸国であり、東側陣営の国ではありません。1990年の北京大会が、東側陣営(当時は社会主義国)で開催された最初の大会となります。したがって、この記述は正しいです。
④【誤】
アジア競技大会の広島開催は1994年です。中距離核戦力(INF)全廃条約の締結は1987年であり、広島大会よりも前です。したがって、「後に」という記述は誤りです。
第2問
問1:正解③
<問題要旨>
資料1~3と会話文の記述を手がかりに、古代ローマ共和政末期の人物「ア」を特定し、その人物の事績を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
『ローマ法大全』の編纂を命じたのは、6世紀の東ローマ(ビザンツ)皇帝ユスティニアヌス1世です。
②【誤】
帝国内の全自由民にローマ市民権を与えた(アントニヌス勅令)のは、3世紀初頭の皇帝カラカラです。
③【正】
資料1の「ルビコン川」、会話文の「ガリア遠征」「終身の独裁官」といったキーワードから、人物「ア」はカエサル(ユリウス・カエサル)と特定できます。カエサルは、紀元前60年に有力者のポンペイウス、富豪のクラッススと手を結び、元老院に対抗するための私的な盟約である第1回三頭政治を結成しました。これはカエサルの正しい事績です。
④【誤】
ミラノ勅令によってキリスト教を公認したのは、4世紀初頭の皇帝コンスタンティヌス1世です。
問2:正解⑥
<問題要旨>
資料1~3に記された古代ローマ共和政期の出来事を、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
各資料が示す出来事を特定し、年代順に並べます。
資料3:
護民官による農地改革の試みと、その指導者の殺害は、グラックス兄弟の改革(兄ティベリウス:紀元前133年、弟ガイウス:紀元前121年)を指します。これが「内乱の一世紀」の始まりとされます。
資料2:
財産を持たない無産市民を志願兵として軍団に組み入れたのは、マリウスによる軍制改革(紀元前107年頃)です。
資料1:
「賽は投げられた」の言葉とともにルビコン川を渡り、ローマに進軍したのは、カエサルによる内乱の開始(紀元前49年)です。
したがって、古い順に並べると「資料3 → 資料2 → 資料1」となります。この配列になっているのは⑥です。
問3:正解⑤
<問題要旨>
百年戦争の過程における、イングランド王の大陸領土(フランスにおける領地)の変遷を示した地図を、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
各図が示す時期を特定します。
図I:イングランド領は南西部のギュイエンヌ(アキテーヌ)地方に限られています。これは百年戦争開始(1337年)前後の、プランタジネット家の伝統的な所領を示しています。
図II:イングランドの勢力がフランス北部からパリ周辺、南西部にまで及んでいます。これは、アザンクールの戦い(1415年)での大勝後、イングランドが最も広大な領域を支配した時期(1420年代)を示します。
図III:イングランド領は、カレー(地図の北端にある港町)を除いて、大陸からほぼ一掃されています。これは、フランスの反撃により、ボルドーが陥落した1453年以降の状況を示します。
したがって、時代の流れは「I → II → III」となります。この配列になっているのは⑤です。
問4:正解①
<問題要旨>
会話文の内容に基づき、百年戦争の終結年とされる「1453年」と「1558年」の根拠となる出来事を正しく組み合わせる問題です。
<選択肢>
①【正】
年「あ」(1453年)について、会話文では「この1453年にボルドーが陥落して百年戦争は終結した」とあり、ボルドーはフランス南西部の都市です。したがって、根拠「X」(フランスの南西部から、イングランド勢力が追い出された)は正しいです。年「い」(1558年)について、会話文では「フランス北部の所領は、1558年にフランスが取り戻している」「大陸からイングランドの勢力が完全に排除された」とあります。この最後の拠点がカレーであったため、根拠「Y」(フランスがカレーを奪い、大陸からイングランド勢力を完全に排除した)は正しいです。したがって、この組合せは正しいです。
②【誤】
根拠「Z」の「イングランド王が、フランス王を自称しなくなった」のは、会話文によれば1801年のことであり、1558年の根拠ではありません。
③【誤】
1453年の根拠はXであり、Yではありません。
④【誤】
1453年の根拠がY、1558年の根拠がZとなっており、両方誤りです。
⑤【誤】
1453年の根拠はXであり、Zではありません。
⑥【誤】
1453年の根拠がZとなっており、誤りです。
問5:正解②
<問題要旨>
会話文で示された百年戦争の終結の捉え方と、キムさんと浜野さんのメモに書かれた他の戦争の終結理由との類似性を比較し、メモの正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
キムさんのメモは誤っているため、この選択肢は誤りです。
②【正】
キムさんのメモ:第3回ポエニ戦争は、ローマが敵国カルタゴを完全に滅亡させたことで終結しました。一方、百年戦争の1475年終結説は「戦争停止の条約」締結を根拠としており、敵国の滅亡とは終結の様相が異なります。よってキムさんのメモは誤りです。
浜野さんのメモ:スペイン継承戦争は、ユトレヒト条約などでブルボン家の王位継承が承認され、王位継承問題に決着がついたことで終結しました。一方、百年戦争の1492年終結説は「条約が結ばれ、…ヴァロワ家の君主がフランス王として記され」たことを根拠としており、こちらも王位継承問題に一つの区切りをつけたという点で類似しています。よって浜野さんのメモは正しいです。
したがって、浜野さんのみ正しいとするこの選択肢が正解です。
③【誤】
キムさんのメモが誤っているため、この選択肢は誤りです。
④【誤】
浜野さんのメモは正しいため、この選択肢は誤りです。
問6:正解②
<問題要旨>
イギリス領インドの独立をめぐるイギリスの提案と、実際の分離独立の経緯について、会話文とスライドから空欄を補充する問題です。
<選択肢>
①【誤】
空欄ウについて、イギリスの統一連邦案は最終的に受け入れられませんでした。分離独立は宗教に基づく地区分け、つまり「中段」の枠組みを基に行われたため、「上段」は誤りです。
②【正】
空欄イ:会話文に「B地区とC地区の主なムスリム多数派地域」が独立したとあり、これはパキスタンを指します。空欄ウ:会話文ではA地区がインド、B・C地区がパキスタンになったと説明されており、スライドの「中段」にある地区の枠組みが分離独立の原型となったことがわかります。したがって、この組合せは正しいです。
③【誤】
空欄ウについて、分離独立は州(下段)を単位としましたが、そのグループ分けの考え方は「中段」の地区案に基づいているため、「中段」がより適切です。
④【誤】
空欄イに入るのはパキスタンであり、バングラデシュではありません。バングラデシュは、東パキスタンとして独立した後、1971年にパキスタンからさらに独立した国です。
⑤【誤】
空欄イがバングラデシュであるため誤りです。
⑥【誤】
空欄イがバングラデシュであるため誤りです。
問7:正解④
<問題要旨>
神田さんと川原さんが行った国家の分類基準を推測し、その基準に従ってインドがどのグループに入るかを判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
インドはイギリスから独立したので、神田さんの分類ではWに入ります。したがって「あ」は誤りです。また、インドは第二次大戦後に独立したので、川原さんの分類ではYに入ります。したがって「う」は誤りです。
②【誤】
「あ」の記述(インドはVに入る)が誤りです。
③【誤】
「う」の記述(インドはXに入る)が誤りです。
④【正】
神田さんの分類:Wのガーナはイギリスから独立、Vのブラジルはポルトガル、カンボジアはフランスから独立しています。よって「イギリスから独立したかどうか」が基準と推測されます。インドはイギリスから独立したので、Wに入ります。したがって、文「い」は正しいです。
川原さんの分類:Yのカンボジア(1953年独立)、ガーナ(1957年独立)は第二次大戦後、Xのブラジル(1822年独立)は第二次大戦よりずっと前に独立しています。よって「第二次世界大戦終結後に独立したかどうか」が基準と推測されます。インドは1947年に独立しており第二次大戦後なので、Yに入ります。したがって、文「え」は正しいです。
「い」と「え」が共に正しいので、この組合せが正解です。
第3問
問1:正解①
<問題要旨>
16世紀以降に魔女裁判が流行した背景について、レポートの空欄を埋める問題です。書物による特定のイメージの流布を可能にした技術的背景を問うています。
<選択肢>
①【正】
15世紀半ばのグーテンベルクによる活版印刷術の改良は、書籍の大量生産を可能にしました。これにより、『魔女への鉄槌』のような書物がヨーロッパ社会に広く普及し、レポートにある「魔女に関する情報が広く流布した」状況を生み出しました。時期、内容ともに文脈に合致するため、これが正解です。
②【誤】
クレルモン教会会議は1095年の出来事であり、十字軍の派遣を提唱したものです。16世紀の魔女裁判の流行とは時代が大きく異なります。
③【誤】
トマス・アクィナスが『神学大全』を著したのは13世紀のことであり、16世紀の情報の流布と直接結びつくものではありません。
④【誤】
科学革命は17世紀以降に本格化する動きであり、合理的な思考によって魔女への迷信を打ち破っていく流れを生み出しました。したがって、魔女裁判流行の背景としては逆の動きとなります。
問2:正解③
<問題要旨>
資料1・2およびレポートの内容を踏まえ、ルターの魔女観と、魔女告発の要因に関する記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
記述「あ」が誤りです。資料1でルターは、魔女を「悪魔の淫婦」と呼び、様々な災いをもたらす有害な存在として明確に記述しています。
②【誤】
記述「あ」が誤りです。
③【正】
記述「あ」は、資料1の内容から「無害なものと捉えていた」という部分が明らかに誤りです。記述「い」は、資料2で産婆ヴァルプルガが「乳幼児殺害」の嫌疑で告発されていること、またレポートで当時の乳幼児死亡率が非常に高かったことと女性の役割(出産・子守り)が関連付けられていることから、不幸な出来事が女性のせいにされ、魔女告発につながったと読み取れます。したがって「あ」が誤り、「い」が正しいとするこの選択肢が正解です。
④【誤】
記述「い」は正しいため、この選択肢は誤りです。
問3:正解①
<問題要旨>
メモ1に記された情報(マラッカ陥落後の主要寄港地、イスラーム王国)を手がかりに、17世紀に存在したアチェ王国の位置を地図上から特定する問題です。
<選択肢>
①【正】
アチェ王国は、現在のインドネシア、スマトラ島の北端に位置していました。この場所は、マラッカ海峡の入り口にあたり、メモにある「マラッカの陥落後、アチェはムスリム商人の主要寄港地となった」という記述とも合致します。地図上の「a」がこの位置を正しく示しています。
②【誤】
「b」はスマトラ島の中部から南部にかけての地域を指しており、アチェの位置ではありません。
③【誤】
「c」はジャワ島を指しており、誤りです。
④【誤】
「d」はフィリピン諸島のルソン島を指しており、誤りです。
問4:正解④
<問題要旨>
「貴族たちが君主権力を弱めるために、あえて女性を君主にした」という仮説について、その根拠となりうる事象をメモ1から選び出す問題です。
<選択肢>
①【誤】
仮説の前提である「女性が男性より劣位とされていた」状況を説明するには、イスラーム教の影響(男性優位規範の強化)が必要です。よって「あ」(イスラーム教の影響が弱かった)は誤りです。また、「う」(君主が交易の利益を掌握)だと、貴族が権力を維持する動機と矛盾します。
②【誤】
「あ」が誤りです。
③【誤】
「う」が仮説の根拠として不適切です。貴族が権力を維持したいのであれば、君主が利益を掌握している状況は望ましくありません。
④【正】
仮説が成り立つには、「①女性が男性より劣位とみなされる社会規範」と「②貴族が自分たちの権力を維持したい動機」が必要です。①はメモ1の「イスラーム教の浸透が、男性優位の規範を強化する傾向」から「い」が根拠となります。②は「え貴族層が、交易の利益を掌握していた」ことで、その利益を守るために君主の権力を抑えようとした、と考えることができます。したがって、この組合せは仮説の根拠として適切です。
問5:正解④
<問題要旨>
図のプレートとメモ2の内容を読み解き、そこからわかる事柄と、プレートが設置された時期(20世紀初頭)のアメリカの状況について、正しい組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
事柄「あ」:プレートには、奴隷制廃止運動家のフレデリック・ダグラスが女性参政権の決議案に「賛成した」と明記されているため、「反対した」は誤りです。時期「X」:大陸横断鉄道の完成は1869年であり、プレート設置年(1908年)とは時期が異なります。
②【誤】
事柄「あ」が誤りです。
③【誤】
時期「X」がプレート設置時期と異なります。
④【正】
事柄「い」:メモ2に、スタントンが「女性であることを理由に」世界奴隷制反対大会への参加を拒否されたとあり、正しい記述です。時期「Y」:プレートが設置された1908年は、アメリカが世界最大の工業国となり、セオドア・ルーズベルト大統領などの下で独占規制などの「革新主義」と呼ばれる改革が進められていた時代です。正しい記述です。したがって、この組合せは正しいです。
問6:正解②
<問題要旨>
19世紀のアメリカ合衆国で活躍した女性とその活動内容として、最も適当なものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
オランプ・ド・グージュは、フランス革命期のフランスで活動した人物です。
②【正】
ストウ(ハリエット・ビーチャー・ストウ)は、19世紀アメリカの作家で、奴隷制の非人道性を描いた小説『アンクル=トムの小屋』(1852年)を著し、国内外の世論に大きな影響を与えました。これは19世紀アメリカの女性による活動として正しいです。
③【誤】
ローザ・ルクセンブルクは、20世紀初頭のドイツで活動した革命家です。
④【誤】
ナイティンゲールは、クリミア戦争(1853~56年)で活躍したイギリスの看護師です。
第4問
問1:正解①
<問題要旨>
張騫を西域に派遣した前漢の皇帝の治世に起きた出来事を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
張騫を派遣したのは前漢の武帝です。武帝は積極的な対外政策を推し進め、紀元前111年には南越(現在のベトナム北部から広東・広西地方)を滅ぼして領土を拡大しました。これは武帝の治世の出来事として正しいです。
②【誤】
『漢書』を編纂したのは、後漢の時代の歴史家である班固です。
③【誤】
商鞅による変法は、前漢より前の戦国時代に、秦で行われた改革です。
④【誤】
呉楚七国の乱は、武帝の父である景帝の時代(紀元前154年)に起きた諸侯王の反乱です。
問2:正解③
<問題要旨>
資料1と会話文を参考に、張騫が皇帝に提案した新たな西域へのルートとその理由を正しく組み合わせる問題です。
<選択肢>
①【誤】
張騫が勧めたのは蜀を経由する南のルート(b)であり、自身が苦難を겪った北のルート(a)ではありません。
②【誤】
ルート(a)も理由(い)も誤りです。当時の漢はまだタリム盆地を支配していませんでした。
③【正】
張騫は、自分が通ってきた北のルート(a)が漢の宿敵である匈奴の勢力圏内にあるため、危険だと考えました(理由あ)。そこで、資料1にあるように、蜀からインドを経由して大夏国へ至る南のルート(b)であれば「害をなす者もいない」と考え、こちらを進言しました。したがって、この組合せは正しいです。
④【誤】
理由「い」が誤りです。当時の漢はまだ西域(タリム盆地)を支配しておらず、だからこそ匈奴を避けようとしたのです。
問3:正解④
<問題要旨>
表に示されたアフリカからの奴隷貿易の統計データを正しく読み取り、そこから導き出せる結論として最も適当なものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
表を見ると、東アフリカからの奴隷の数は17世紀から18世紀にかけて100千人から400千人に増加していますが、その割合は3.6%から5.1%への微増にとどまっています。「規模は拡大した」とは言えますが、他のルート、特に大西洋ルートの急拡大に比べると限定的です。
②【誤】
紅海を通じた奴隷の数は、18世紀に200千人となっていますが、17世紀の100千人からの増加であり、「急増した」とは言えません。また、割合はむしろ減少しています(3.6%→2.6%)。
③【誤】
16世紀においては、サハラ砂漠経由の奴隷数(550千人)が、大西洋経由(338千人)よりも多くなっています。したがって、「いずれの世紀においても…大西洋を通じて連れ出された奴隷の数が…多かった」という記述は誤りです。
④【正】
16世紀のサハラ砂漠を通じた奴隷貿易の規模は550千人で、全体の50.6%を占めています。他の全ルートの合計(紅海100 + 東アフリカ100 + 大西洋338 = 538千人)よりも大きいことがわかります。したがって、この記述は正しいです。
問4:正解①
<問題要旨>
資料2のイギリス探検家の発言と会話文の内容から、19世紀前半のイギリスにおける奴隷貿易と奴隷制に対する政策の空欄を埋める問題です。
<選択肢>
①【正】
空欄イ:資料2で探検家は、イギリス王が「この貿易に従事する全ての船を拿捕し…奴隷を解放し」ていると述べています。これは「大西洋を航行する奴隷貿易船の取締りを行っていた」ことを示します。空欄ウ:会話文で菅井が「イギリスは、奴隷貿易と奴隷制を明確に区別していた」と結論づけていることから、この時点(1824年)のイギリスでは、奴隷の売買(奴隷貿易)は禁止されていた(1807年)ものの、植民地での奴隷所有(奴隷制)はまだ廃止されていなかった(1833年に廃止法成立)状況が読み取れます。したがって、この組合せは正しいです。
②【誤】
空欄ウの記述が逆です。奴隷制より奴隷貿易が先に禁止されました。
③【誤】
空欄イ:資料2では解放奴隷を「アフリカにある我々の植民地の一つで土地と家を与える」とあり、イギリスの植民地(シエラレオネなど)を指しています。「リベリア」はアメリカで解放された奴隷たちが建国した国であり、異なります。
④【誤】
空欄イもウも誤っています。
問5:正解②
<問題要旨>
メモにあるロシアと清朝の間の条約(エ)が締結された時期を、他の二つの出来事(I、II)との前後関係で正しく配列する問題です。
<選択肢>
まず、各出来事の年代を特定します。
I 清朝は、ジュンガルを滅ぼして、イリ地方に支配の拠点を築いた。
これは、清の乾隆帝が中央アジアのジュンガル部を平定した出来事で、**18世紀半ば(1750年代)**のことです。
エ メモの条約
メモには「ロシア帝国は、清朝との間で清朝北西側の境界を定めたエを締結している」とあり、グラフの時期(1850年以降)と関連しています。これは新疆(イリ地方)の国境を定めた**イリ条約(1881年)**を指していると考えられます。
II ロシア帝国は、遼東半島の鉄道利権の一部を他国に譲渡した。
これは、日露戦争(1904-05年)に敗北したロシアが、ポーツマス条約で南満洲の鉄道利権を日本に譲渡したことを指します。**20世紀初頭(1905年)**の出来事です。
以上の年代を古い順に並べると、
I (18世紀半ば) → エ (1881年) → II (1905年)
となります。この順序になっている選択肢は②です。
問6:正解②
<問題要旨>
19世紀後半のロシア・清朝間の貿易を示すグラフの読み取りと、両国の勢力範囲に関する歴史的事象を正しく組み合わせる問題です。
<選択肢>
①【誤】
事象「X」:英露協商(1907年)で定められたのは、ペルシア(イラン)、アフガニスタン、チベットにおける勢力範囲であり、朝鮮ではありません。朝鮮をめぐる日本の優越権は日露戦争後のポーツマス条約でロシアが認めています。
②【正】
グラフの読み取り「あ」:グラフを見ると、全ての年代で「清朝からの輸入総額」(白棒)が「清朝への輸出総額」(黒棒)を大幅に上回っており、ロシア帝国側の大幅な貿易赤字であったことがわかります。1890年代には輸入が約4200、輸出が約600で、差額は約3600となり、「3000万紙幣ルーブルを超えた」という記述と合致します。正しい読み取りです。事象「Y」:清朝は、モンゴルやチベット、新疆といった藩部を、専門機関である理藩院を通じて間接的に統治していました。これは清朝の統治に関する正しい記述です。したがって、この組合せは正しいです。
③【誤】
事象「X」が誤りです。
④【誤】
グラフの読み取り「い」:グラフの「清朝への毛皮・皮革輸出額」(網掛棒)は、どの年代も100万紙幣ルーブルに達しておらず、「500万紙幣ルーブルを超えることもあった」という記述は明らかな誤りです。
第5問
問1:正解②
<問題要旨>
16~17世紀の寒冷化(小氷期)の影響について、図と資料1を基にパネルの空欄を補充する問題です。
<選択肢>
①【誤】
空欄イについて、資料1には反乱や軍隊に関する記述はなく、食糧輸送の問題が述べられています。
②【正】
空欄ア:図に描かれているのは、凍った川でスケートや遊びに興じる人々の様子で、特定の身分を示すものはありません。「農民や民衆」の日常風景と捉えるのが妥当です。空欄イ:資料1では、ボスフォラス海峡の凍結により「イスタンブルに船が近づけず、食糧を搬入できなくなった」とあり、飢饉と物価高騰につながったと述べられています。これは、寒冷化によって「交通網が麻痺し、物流が滞る」という困難が生じたことを示しています。したがって、この組合せは正しいです。
③【誤】
空欄ア:図は宮廷生活を描いたものではありません。空欄イも資料の内容と異なります。
④【誤】
空欄アが不適切です。
問2:正解①
<問題要旨>
17世紀の清朝における貿易制限と経済状況について、資料2とメモの内容から空欄を埋める問題です。
<選択肢>
①【正】
空欄ウ:メモによると、この時期、康熙帝が戦争をしていた相手です。17世紀後半、清朝は台湾に拠点を置いて抵抗を続ける鄭氏政権と対峙し、その経済基盤を断つために厳しい貿易制限(遷界令)を行いました。鄭氏政権は日本や東南アジアとの中継貿易で利益を上げていたため、文「あ」の記述は鄭氏政権を正しく説明しています。空欄エ:メモによると、清朝は銀を貨幣としており、その供給を輸入に依存していました。貿易が停止すれば、国外からの銀の流入が止まり、国内で流通する貨幣の量が減少します(X)。資料2にあるように、貨幣(現金)が不足すると、人々は物を買えなくなり、物価が下落するデフレーションが発生します。したがって、この組合せは正しいです。
②【誤】
空欄エについて、商品の供給が増加(Y)すれば物価は下落しますが、資料2とメモの文脈は、貨幣供給の減少によるデフレを問題にしているため不適切です。
③【誤】
空欄ウについて、文「い」の「マドラスやカルカッタを拠点とし、中国にアヘンを輸出した」のは、主に18世紀以降のイギリス東インド会社であり、康熙帝が戦った相手ではありません。
④【誤】
空欄ウ、エともに不適切です。
問3:正解④
<問題要旨>
19世紀のロシア帝国支配下のポーランドで起きた蜂起(1863年の正月蜂起)をめぐるパネルの空欄を補充する問題です。
<選択肢>
①【誤】
空欄オ:1861年に農奴解放令を発布したのは、ロシア皇帝アレクサンドル2世です。ヨーゼフ2世は18世紀のオーストリアの君主です。
②【誤】
空欄オが誤りです。
③【誤】
空欄カについて、蜂起側がより有利な農奴解放を宣言したのに対抗するため、ロシア皇帝が発布した1864年のポーランド向け農奴解放令は、蜂起側の宣言に近い内容(補償負担なし)となり、1861年のロシア本国のものとは異なる内容でした。
④【正】
空欄オ:1861年の農奴解放令を発布したのはロシア皇帝アレクサンドル2世です。空欄カ:1864年に皇帝がポーランドで発布した農奴解放令は、蜂起した勢力が農民の支持を得るのを妨げるため、蜂起側の宣言に同調する形で、より農民に有利な条件を提示するものでした。つまり、ロシア皇帝が「蜂起に対抗する過程」で出された政治的な措置であったと言えます。したがって、この組合せは正しいです。
問4:正解③
<問題要旨>
第二次世界大戦後のフランスにおけるアルザス地方出身者「マルグレ=ヌ」をめぐる問題について、会話文の内容を正しく理解する問題です。
<選択肢>
①【誤】
空欄キについて、アルザス・ロレーヌ地方がフランスに復帰したのは、第一次世界大戦の結果、ヴェルサイユ条約によってです。プロイセン=フランス戦争(普仏戦争)では、フランスはこの地方をドイツに割譲しました。
②【誤】
空欄キが誤りです。また、事柄Yについて、恩赦は「アルザスの住民の心情に沿った判断」であり、「オラドゥール村の人々は納得しませんでした」とあるため、彼らに配慮したものではありません。
③【正】
空欄キ:アルザス地方がフランス領となったのは第一次世界大戦後のことです。事柄X:会話文に「ナチス=ドイツに強制的に徴発されたこの地方の人々は、『マルグレ=ヌ(意に反して)』と呼ばれます」とあり、正しい説明です。したがって、この組合せは正しいです。
④【誤】
事柄Yが誤りです。
問5:正解③
<問題要旨>
資料3(アメリカ独立宣言の一部)の内容を読み解き、それが第1~4班の発表事例のうち、どの事例と最も類似しているかを判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
資料3は、政治的な抑圧からの独立と革命の権利を主張するものであり、気候変動や食糧危機について述べた1班の事例とは類似していません。
②【誤】
資料3は、貨幣供給の減少による経済危機(デフレーション)を述べた2班の事例とは関係ありません。
③【正】
資料3は、「現在のイギリス国王」による「絶対的な専制」と「権利侵害」を非難し、人々が政府を改変・廃止する権利を主張しています。これは、大国(イギリス)の支配に対して、政治的な権利を求めて立ち上がった事例です。3班が取り上げた、ロシア帝国の支配下にあったポーランドの貴族や知識人が、独自の政府を名乗り蜂起した事例と、「大国の支配によって政治危機が起こった」という点で強く類似しています。
④【誤】
資料3は、戦争責任や歴史認識をめぐる和解の困難さを述べたものではないため、4班の事例とは異なります。