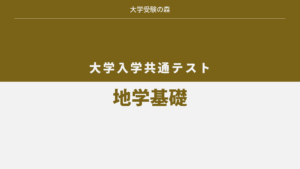解答
解説
第1問
問1:正解④
<問題要旨>
ホットスポットとプレートの移動によって形成される火山島の地形的特徴に関する問題です。ホットスポットの位置と、火山の形成順序や浸食の関係を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
ホットスポットはプレートに対してほぼ固定されているため、プレートの移動に伴い、形成された火山列の中で最も活動的な火山の位置にあります。この図では、ホットスポットが最も古い(最も浸食された)火山の下にあり、プレートの移動方向と火山列の形成順序が矛盾するため、誤りです。
②【誤】
ホットスポットは、新しい火山を形成する場所です。この図では、ホットスポットが活動を終えた古い火山の下に位置しているため、誤りです。
③【誤】
プレートが左に移動しているため、ホットスポットで形成された火山は次々と左に移動していきます。したがって、最も右側にある火山が最も新しく、活動的で標高が高いはずです。この図では、最も新しいはずの火山が最も低く描かれており、不適切です。
④【正】
ホットスポットはマントル内の特定の位置にほぼ固定されています。海洋プレートがその上を移動することにより、次々と火山が形成されます。形成された火山はプレートとともに移動していくため、ホットスポットから離れるほど古い火山となります。古い火山ほど活動を終えてからの時間が長く、波などによる浸食が進むため、標高は低くなります。この図は、プレートが左へ移動する中で、最も右側にある火山が最も新しく(標高が高く)、その下にホットスポットが存在するという関係を正しく示しています。
問2:正解①
<問題要旨>
本震と余震の関係、特に震源域と余震の発生頻度の時間的変化について問う問題です。基本的な地震学の知識と、累積数グラフの読み取り能力が求められます。
<選択肢>
①【正】
ア:余震は、本震を引き起こした断層運動によって不安定になった周辺の岩盤で発生する地震です。そのため、余震の震源分布域は、本震の震源域(本震時に破壊された領域)とほぼ「重なる」ことが一般的です。
イ:図は地震の「累積数」を示しており、グラフの傾きが単位時間あたりの地震発生回数を表します。本震が発生した5月1日直後はグラフの傾きが急ですが、時間が経つにつれて傾きは緩やかになっています。これは、1日あたりの余震の発生回数が時間とともに「減っていく」ことを示しており、この経験則は大森公式として知られています。
したがって、アに「重なる」、イに「減っていく」が入るこの選択肢が正解です。
②【誤】
イの「増えていく」が誤りです。グラフの傾きは時間とともに緩やかになっており、単位時間あたりの地震発生数は減少しています。
③【誤】
アの「重ならない」が誤りです。余震は本震の震源域およびその周辺で発生します。
④【誤】
アの「重ならない」、イの「増えていく」の両方が誤りです。
問3:正解③
<問題要旨>
地殻を構成する主要な岩石である玄武岩、花こう岩、斑れい岩の密度に関する知識を問う問題です。大陸地殻と海洋地殻の構成岩石とその性質を理解しているかがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
ウ(玄武岩)とエ(花こう岩)の密度が逆です。
②【誤】
ウ(玄武岩)とエ(花こう岩)の密度が逆であり、エの数値(3.3 g/cm³)もかんらん岩の密度に近く、花こう岩としては不適切です。
③【正】
大陸地殻を主に構成する花こう岩の密度は約2.7 g/cm³、海洋地殻を主に構成する玄武岩の密度は約3.0 g/cm³です。斑れい岩は玄武岩と同じような化学組成を持つ深成岩で、密度も約3.0 g/cm³です。したがって、ウ(玄武岩の密度)が3.0 g/cm³、エ(花こう岩の密度)が2.7 g/cm³という組合せは妥当です。
④【誤】
エ(花こう岩)の密度として3.3 g/cm³は不適切です。これはマントルを構成するかんらん岩の密度に近いです。
⑤【誤】
ウ(玄武岩)の密度として3.3 g/cm³は不適切です。
⑥【誤】
ウ(玄武岩)とエ(花こう岩)の両方の密度が不適切です。
問4:正解②
<問題要旨>
上部マントルの主要な構成岩石である「かんらん岩」を構成する鉱物についての知識を問う問題です。火成岩の分類と主要な造岩鉱物の関係を整理できているかが重要です。
<選択肢>
①【誤】
石英は、SiO₂からなる無色鉱物で、花こう岩などの酸性岩に多く含まれます。マントルを構成する超苦鉄質岩であるかんらん岩にはほとんど含まれません。
②【正】
かんらん岩は、その名の通り「かんらん石」と、「輝石」を主成分とする超苦鉄質岩です。したがって、鉱物Aは輝石が最も適当です。
③【誤】
角閃石は、輝石よりもややシリカに富む岩石(安山岩や閃緑岩など)に多く含まれる有色鉱物です。かんらん岩の主成分ではありません。
④【誤】
黒雲母は、花こう岩や閃緑岩などに含まれる有色鉱物です。かんらん岩の主成分ではありません。
問5:正解⑤
<問題要E旨>
地球の原始大気の主成分と、その後の大気組成の変化、特に二酸化炭素の減少要因について問う問題です。地球史における大気と海洋の相互作用を理解しているかがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
オ(原始大気の主成分)がメタンではありません。主成分は水蒸気と二酸化炭素です。
②【誤】
オ(原始大気の主成分)がメタンではありません。
③【誤】
オ(原始大気の主成分)がメタンではありません。また、カ(氷床の発達)は、先カンブリア時代よりも後の時代の現象です。
④【誤】
カの理由が不適切です。植物の光合成による二酸化炭素の固定が活発になるのは、シアノバクテリアの繁栄以降であり、原始海洋への溶解の方がより初期の大きな減少要因です。
⑤【正】
オ:原始地球の微惑星衝突や火山活動によって放出されたガスの主成分は、水蒸気(H₂O)と「二酸化炭素(CO₂)」であったと考えられています。
カ:大気中の二酸化炭素が先カンブリア時代前半に大きく減少した最も大きな原因は、地球の温度が下がり、大気中の水蒸気が凝結して「原始海洋が形成され」、二酸化炭素がその海水に大量に「溶け込んだ」ことです。
したがって、この組合せが最も適当です。
⑥【誤】
カの理由が不適切です。先カンブリア時代前半には大規模な氷床は存在していませんでした。
問6:正解④
<問題要旨>
海底堆積物の崩壊によって生じ、タービダイトを堆積させる流れの名称を問う問題です。海底で起こる堆積作用に関する基本的な用語の知識が求められます。
<選択肢>
①【誤】
津波は、地震などによって引き起こされる海水の長周期の波であり、海底の地形変化そのものです。問題文の流れとは異なります。
②【誤】
海流は、風や海水の密度差によって生じる、比較的定常的な海水の流れです。問題文にあるような、突発的で高速な堆積物の流れではありません。
③【誤】
土石流は、山地などで大雨が原因となり、土砂が水と混じって高速で流れ下る現象であり、陸上で発生する災害です。
④【正】
混濁流(乱泥流)は、地震などをきっかけに海底の堆積物が海水と混ざり合って高密度の流れとなり、海底斜面を高速で流れ下る現象です。この流れによって運ばれた堆積物が、級化構造を持つ「タービダイト」と呼ばれる堆積物を形成します。問題文の状況と完全に一致します。
問7:正解③
<問題要旨>
図に示されたデータから、海底ケーブルを切断した流れ(混濁流)の速さの変化を計算し、読み取る問題です。速さ・距離・時間の関係を正しく計算できるかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
各区間の速さを計算すると、速さが一定でないことがわかります。
②【誤】
計算結果は、速さが増加ではなく減少していることを示します。
③【正】
各区間の速さを計算します。
・ケーブルA→B間:距離140km、時間(05:30 – 02:30) = 3時間。速さ = 140km / 3h ≒ 46.7 km/h。
・ケーブルB→C間:距離70km、時間(07:30 – 05:30) = 2時間。速さ = 70km / 2h = 35.0 km/h。
・ケーブルC→D間:距離140km、時間(12:00 – 07:30) = 4.5時間。速さ = 140km / 4.5h ≒ 31.1 km/h。
AからDへ向かうにつれて、流れの速さは約47km/h → 35km/h → 31km/hと、次第に「減少した」ことがわかります。これは、海底の勾配が沖合に向かって緩やかになるためと考えられます。
④【誤】
計算結果は、速さが増加した区間はなく、一貫して減少していることを示します。
第2問
問1:正解④
<問題要旨>
大陸と海洋の熱的な性質の違い(比熱の差)が、季節による気圧配置や風の強さにどう影響するかを問う問題です。季節風のメカニズムの根本的な理解が求められます。
<選択肢>
①【誤】
イ、ウが誤りです。
②【誤】
ウが誤りです。
③【誤】
イが誤りです。
④【正】
ア:海洋(水)は大陸(陸地)に比べて比熱が大きいため、「暖まりにくく、冷めにくい」性質を持ちます。
イ:このため、夏は大陸が海洋より暖められて低圧部に、冬は大陸が海洋より冷やされて高圧部になります。図を見ると、夏は大陸(A)が低圧、海洋(B)が高圧です。冬は大陸(A)が高圧、海洋(B)が低圧(アリューシャン低気圧)になっています。しかし、問題文では「地点Bは地点Aにくらべて」と、それぞれの季節内での比較を求めているように読めますが、気圧の値そのものを比較すると、夏はB>A、冬はA>Bとなり一定ではありません。ここで問われているのは、熱的な性質の違いによる気圧変化の大きさのようです。海洋は温度変化が小さいため、気圧変化も小さいです。一方、大陸は温度変化が大きいため、夏は著しい低圧、冬は著しい高圧となります。この結果、夏は海洋側が相対的に高圧(B>A)、冬は大陸側が高圧(A>B)となります。ここで文章の流れを見ると「冬の日本付近では北西の季節風が吹く」とあります。冬に北西風が吹くのは、大陸(A付近)に高気圧、海洋(B付近)に低気圧が位置する「西高東低」の気圧配置になるためです。つまり冬においてAはBより気圧が高い、すなわちBはAより気圧が低いとなります。夏の図を見るとAは低圧部の中心、Bは高圧部の中心なのでBはAより気圧が高いです。選択肢では夏冬で共通の説明を求めているため、文章の解釈が難しいですが、冬の状況から考えると、アが「暖まりにくく、冷めにくい」であることは確定です。これを前提にイを考えます。冬の図を見ると、ユーラシア大陸上(A)に高気圧、太平洋上(B)に低気圧があり、Aの気圧>Bの気圧です。つまりBはAに比べて気圧が低いです。夏の図を見ると、大陸上(A)に低気圧、太平洋上(B)に高気圧があり、Bの気圧>Aの気圧です。つまりBはAに比べて気圧が高いです。選択肢は夏冬共通の傾向を求めているため、問題文の「夏、冬それぞれにおいて、地点Bは地点Aにくらべて気圧が イ」という表現は適切でない可能性があります。しかし、続く「このため、冬の日本付近では北西の季節風が吹く」という記述から、冬の状況を正しく説明できる選択肢を選ぶべきと判断します。冬はA(高圧)からB(低圧)へ風が吹くため、BはAより気圧が「低い」が適切。ウ:冬の気圧配置図は、夏の図に比べて等圧線の間隔が非常に狭くなっています。等圧線の間隔が狭いほど気圧傾度力が大きく、風は「強い」ことを意味します。
この消去法的な吟味の結果、ア「暖まりにくく、冷めにくい」とウ「強い」が確定的に正しく、これを含むのは④のみです。イの「高い」は夏の状況を表していると解釈するのが最も自然です。
問2:正解①
<問題要旨>
北半球の海洋の表層循環(還流)の回転方向と、その主な駆動力について問う問題です。風成循環の基本的な知識が求められます。
<選択肢>
①【正】
エ:北半球の中緯度帯では、低緯度側の貿易風(東風)と高緯度側の偏西風(西風)が吹いています。この風系と、地球自転の影響(コリオリの力)によって、北太平洋や北大西洋の亜熱帯域には大規模な「時計回り」の還流(亜熱帯循環)が形成されます。
オ:このような海洋の表層で起こる大規模な循環は、主に「海上の風」によって引き起こされるため、風成循環と呼ばれます。
したがって、この組合せが正解です。
②【誤】
オが誤りです。「海水の密度差」によって駆動されるのは、世界の海洋を数千年かけて循環する深層循環(熱塩循環)です。
③【誤】
エが誤りです。北半球の亜熱帯循環は時計回りです(反時計回りは亜寒帯循環)。
④【誤】
エ、オともに誤りです。
第3問
問1:正解⑤
<問題要旨>
太陽の形成、内部構造、化学組成、進化段階についての基本的な知識を問う問題です。恒星として太陽を正しく理解しているかが試されます。
<選択肢>
①【誤】
aが誤りです。原始太陽は、星間雲が自己重力によって「収縮」して誕生しました。
②【誤】
aとcが誤りです。
③【誤】
aが誤りです。
④【誤】
cが誤りです。太陽を構成する元素で最も多いのは水素(質量比で約74%)です。
⑤【正】
b:太陽のエネルギーは、高温・高圧の「中心部」で起こる水素核融合反応によって生み出されています。これは正しい記述です。
d:太陽は、約46億年前に誕生してから現在まで、安定して輝き続ける「主系列星」という進化段階にあります。これも正しい記述です。
したがって、正しい文の組合せであるこの選択肢が正解です。
⑥【誤】
cが誤りです。
問2:正解⑥
<問題要旨>
太陽系形成論における、惑星の形成過程の違いを問う問題です。太陽からの距離による温度勾配(特にスノーラインの存在)が、地球型惑星と木星型惑星の形成を分けたことを理解しているかがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
ア、イが誤りです。
②【誤】
ア、ウが誤りです。
③【誤】
ア、イ、ウすべてが誤りです。
④【誤】
イ、ウが誤りです。
⑤【誤】
イが誤りです。
⑥【正】
ア:原始太陽系円盤では、太陽からある程度離れた低温領域(スノーラインの外側)になると、「水」が氷として固体で存在できました。太陽に近い高温領域では水は水蒸気となり、固体は岩石や金属のみでした。
イ:スノーラインの外側では、岩石や金属に加えて豊富な氷も材料となったため、巨大な原始惑星(コア)が形成されました。このコアの強い重力は、円盤に大量に存在した水素やヘリウムなどの「ガス」を引きつけました。
ウ:こうして、巨大なガスの大気をまとった「木星型惑星」が誕生しました。
したがって、この組合せが正解です。
問3:正解⑤
<問題要旨>
地球、木星、天王星の物理的特徴(半径、平均密度、公転周期)と太陽からの距離の関係を、グラフから読み解く問題です。惑星の分類(地球型・木星型)とケプラーの法則の知識を応用する力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
a, b, cの組合せが異なります。
②【誤】
a, b, cの組合せが異なります。
③【誤】
a, b, cの組合せが異なります。
④【誤】
a, b, cの組合せが異なります。
⑤【正】
まず、横軸の「太陽からの距離」で3つの点を特定します。太陽に近い方から順に、地球(約1AU)、木星(約5.2AU)、天王星(約19.2AU)です。
・aのグラフ:太陽から離れるほど値が急激に大きくなり、天王星では80を超えています。これはケプラーの第3法則(公転周期の2乗は軌道長半径の3乗に比例する)で説明される「公転周期」の特徴と一致します(地球1年、木星約12年、天王星約84年)。
・bのグラフ:木星の値が最も大きく(地球の約11倍)、天王星がそれに次ぎ(地球の約4倍)、地球が1となっています。これは惑星の「半径」の特徴と一致します。
・cのグラフ:地球が1で最も大きく、木星と天王星は0.3以下の小さな値になっています。これは、岩石質の地球型惑星(地球)は密度が大きく、ガスや氷が主体の木星型惑星(木星、天王星)は密度が小さいという「平均密度」の特徴と一致します。
したがって、aが公転周期、bが半径、cが平均密度の組合せが正解です。
⑥【誤】
a, b, cの組合せが異なります。
第4問
問1:正解①
<問題要旨>
日本に飛来する黄砂が、どの風によって運ばれ、どのくらいの時間を要するかを問う問題です。中緯度帯の気象と、大まかなスケールでの計算能力が求められます。
<選択肢>
①【正】
ア:黄砂の発生源である中国大陸内陸部やモンゴルの砂漠地帯は、日本と同じ中緯度帯に位置します。この緯度帯の上空には、一年を通して西から東へ向かう恒常風である「偏西風」が吹いており、黄砂はこの風に乗って日本へ運ばれます。
イ:発生源から日本までの距離(3000~5000km)を、偏西風の速度(時速100km程度)で割ると、到達時間は 3000/100 = 30時間 ~ 5000/100 = 50時間 となります。これは「数日」に相当します。
したがって、この組合せが正解です。
②【誤】
イの「数週間」は長すぎます。
③【誤】
アの「貿易風」は、低緯度帯で東から西へ吹く風であり、誤りです。
④【誤】
ア、イともに誤りです。
問2:正解①
<問題要旨>
火山がもたらす様々な災害のメカニズムと、火山ガスの主成分についての知識を問う問題です。複数の火山現象を正確に区別して理解しているかが重要です。
<選択肢>
①【正】
ウ:マグマが地下水や地表水に接触すると、水が急激に加熱されて体積が爆発的に増大する「水蒸気爆発」が発生します。
エ:水蒸気爆発や地震などによって山体の一部が大規模に崩壊し、大量の岩屑が高速で斜面を流れ下る現象を「岩なだれ(岩屑なだれ)」と呼びます。
オ:火山ガスを構成する成分のうち、最も割合が大きいのは「水蒸気」で、通常70~90%以上を占めます。
したがって、この組合せが正解です。
②【誤】
オが誤りです。二酸化炭素も含まれますが、主成分は水蒸気です。
③【誤】
エが誤りです。「溶岩流」は噴出したマグマ自体が流れる現象であり、山体崩壊による土石の流れとは区別されます。
④【誤】
エ、オが誤りです。
⑤【誤】
ウが誤りです。「液状化現象」は地震の揺れによって砂地盤が液体のようになる現象です。
⑥【誤】
ウ、オが誤りです。
⑦【誤】
ウ、エが誤りです。
⑧【誤】
ウ、エ、オすべてが誤りです。
問3:正解④
<問題要旨>
太陽活動の指標である黒点の性質と、太陽フレアによって放出されるものが地球に到達するまでの時間差に関する問題です。
<選択肢>
①【誤】
カ、キともに誤りです。
②【誤】
カが誤りです。
③【誤】
キが誤りです。
④【正】
カ:黒点は、強い磁場の影響で太陽内部からの熱エネルギーの輸送が妨げられるため、周囲の光球(約6000℃)よりも温度が「低い」(約4000℃)領域です。温度が低いために黒く見えます。
キ:太陽フレアで放出されるもののうち、電磁波(X線や光)は光速で進むため約8分で地球に到達します。一方、荷電粒子(陽子や電子など)は光速よりはるかに遅く、地球に到達するまでには「数日」かかります。この時間差を利用して、フレア発生の観測から荷電粒子の到来を予測(宇宙天気予報)します。
したがって、この組合せが正解です。