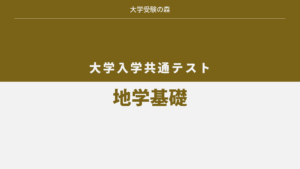解答
解説
第1問
問1:正解①
<問題要旨>
地球の表層を覆うプレートと、プレートを区分する基準についての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
地球の表面は、固い岩盤であるプレートで覆われています。プレートとその下のマントルの一部(アセノスフェア)は、岩石の構成物質は似ていますが、物理的な性質、特に「かたさ(流動しにくさ)」によって区分されます。プレート(リソスフェア)は固く、アセノスフェアは流動性を持っています。したがって、アに「プレート」、イに「かたさ(流動しにくさ)」が入るこの選択肢が正解です。
②【誤】
プレートとその下の部分を分ける基準は、構成物質の違いではなく、かたさ(流動性)の違いです。
③【誤】
地殻はプレートの一部を構成しますが、地球の表面を覆う動いている岩盤全体を指す言葉はプレートです。
④【誤】
アが「地殻」である点、イが「岩石(構成物質)」である点の両方が誤りです。地殻とマントルは構成物質の違いで区分されますが、プレート(リソスフェア)とアセノスフェアはかたさの違いで区分されます。
問2:正解②
<問題要旨>
地震波の速度と距離から到達時間を計算し、緊急地震速報が発令されてから主要動(S波)が到達するまでの時間を求める計算問題です。
<選択肢>
①【誤】
S波が震源から大阪市(距離200km)に到達するまでにかかる時間は、距離 ÷ 速度 で求められます。
時間 = 200 km ÷ 4 km/秒 = 50 秒
地震発生から50秒後にS波が到着します。緊急地震速報は地震発生の15秒後に出されているので、速報を受信してからS波が到着するまでの時間は、
50 秒 – 15 秒 = 35 秒
となります。15秒ではありません。
②【正】
上記計算の通り、S波の到達時間(50秒)から緊急地震速報が発令された時間(15秒)を引くと35秒となります。
③【誤】
50秒は、地震発生からS波が到達するまでにかかる時間です。問題では「緊急地震速報を受信してから」と問われているため、発令までの15秒を引く必要があります。
④【誤】
この数値は、S波の到達時間(50秒)と緊急地震速報の発令時間(15秒)を足したものです。計算方法が誤っています。
問3:正解④
<問題要旨>
火成岩や造岩鉱物の特徴に関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
造岩鉱物は結晶であり、原子が規則正しく配列した構造を持っています。原子が不規則に配列しているのは、ガラス(非晶質)の特徴です。
②【誤】
深成岩はマグマが地下深くでゆっくり冷えて固まった岩石であり、大きな結晶(等粒状組織)からなります。ガラスはマグマが急冷した場合にできるため、通常、深成岩には含まれません。
③【誤】
安山岩(火山岩)と閃緑岩(深成岩)は、どちらも中間の化学組成を持つマグマからできます。両者の違いは、マグマの冷却速度の違いによる組織(結晶の大きさ)の違いであり、化学組成の違いを反映したものではありません。
④【正】
苦鉄質岩(塩基性岩)は、Fe(鉄)やMg(マグネシウム)に富む有色鉱物を多く含む岩石です。代表的な造岩鉱物として、斜長石、輝石、かんらん石の組み合わせが一般的です。
問4:正解④
<問題要旨>
マグマが地層に貫入して固まった火成岩体の形態(岩脈、岩床、底盤)を模式図から判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
Aは周囲の地層を切るように貫入しており「岩脈」、Bは地層に平行に貫入しており「岩床」です。Cは地下深部にある大規模な岩体で「底盤(バソリス)」です。AとBの名称が逆です。
②【誤】
BとCの名称が逆です。
③【誤】
A、B、Cすべての名称が誤っています。
④【正】
Aは地層を垂直または斜めに切るように貫入する「岩脈」、Bは地層面に沿って水平に貫入する「岩床」、Cは地下深部に存在する広大な面積を持つ深成岩体「底盤(バソリス)」であり、正しく対応しています。
⑤【誤】
AとCの名称が逆です。
⑥【誤】
BとCの名称が逆です。
問5:正解④
<問題要旨>
先カンブリア時代から古生代にかけての生物の進化と、大気中の酸素濃度の変化に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
エの被子植物が繁栄したのは中生代以降です。
②【誤】
ウのグリパニアは真核生物ですが、大規模に酸素を放出し始めたのは原核生物であるシアノバクテリアです。
③【誤】
ウは正しいですが、エの被子植物が栄えたのは中生代以降です。古生代後半に大森林を形成したのはシダ植物です。
④【正】
ウには、約27億年前に出現し、光合成によって地球に大量の酸素を供給した原核生物である「シアノバクテリア」が入ります。エには、古生代後半(特に石炭紀)に大森林を形成し、現在の石炭のもととなった「シダ植物」が入ります。
問6:正解①
<問題要旨>
原生代初期の地球環境に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
原生代初期(約24億年前~22億年前)には、地球全体が氷で覆われる「全球凍結(スノーボールアース)」という極めて寒冷な出来事が起こったと考えられています。
②【誤】
地球表層がマグマの海(マグマオーシャン)で覆われていたのは、地球形成初期の冥王代の出来事です。
③【誤】
多細胞生物が爆発的に多様化した「カンブリア爆発」が起こったのは、古生代カンブリア紀の始まり(約5.4億年前)です。
④【誤】
原始的な魚類が登場したのは、古生代カンブリア紀からオルドビス紀にかけてです。
第2問
問1:正解④
<問題要旨>
台風の一般的な移動経路と勢力の変化を理解し、複数の天気図を時系列に並び替える問題です。
<選択肢>
①【誤】
台風は、日本の南海上では北西に進み、その後、偏西風の影響を受けて北東に進路を変えるのが一般的です。また、発達するにつれて中心気圧が下がり、衰弱するにつれて中心気圧が上がります。d(915hPa)→c(935hPa)→b(950hPa)→a(975hPa)の順に、台風が北上しながら中心気圧が上昇(勢力が衰弱)しており、時間の経過と一致します。
②【誤】
時系列が正しくありません。
③【誤】
時系列が正しくありません。
④【正】
天気図中の台風の位置と中心気圧に着目します。
d:最も南に位置し、中心気圧が915hPaと最も低い(最盛期)。
c:dよりやや北上し、中心気圧は935hPa。
b:さらに北上し、日本に接近。中心気圧は950hPa。
a:日本列島に沿って北東に進み、中心気圧は975hPaと最も高い(衰弱期)。
このd→c→b→aの順が、台風の移動と変化として最も自然です。
問2:正解②
<問題要旨>
台風がもたらす災害や現象に関する説明文の中から、誤りを含むものを見つけ出す問題です。
<選択肢>
①【正】
台風が南から暖かく湿った空気を大量に送り込むことで、停滞している前線の活動が活発化し、広範囲で大雨となることがあります。正しい記述です。
②【誤】
北半球において、台風内部の風は中心に向かって反時計回りに吹き込みます。風の強さは、台風自体の風と、台風の移動速度が合わさったものになります。進行方向の右側では両者が足し合わされるため風が強くなり、左側では打ち消し合うため風が弱くなる傾向があります。記述は「左側では、風がより強く吹くことが多い」となっており、誤りです。
③【正】
等圧線の間隔が狭いほど気圧傾度力が大きく、風は強く吹きます。台風の中心近くは等圧線が密集しているため、風が非常に強いです。正しい記述です。
④【正】
台風の中心付近は気圧が極端に低いため、海面が吸い上げられる効果(吸い上げ効果)と、強い風が海水を岸に吹き寄せる効果(吹き寄せ効果)によって海面が異常に上昇する「高潮」が発生します。正しい記述です。
問3:正解②
<問題要旨>
海洋の熱収支、特に蒸発による潜熱の移動と、電磁波の放射による熱の放出に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
イの「可視光線」が誤りです。地球の温度で放射される電磁波の主成分は赤外線です。
②【正】
ア:海水の蒸発にはエネルギー(気化熱)が必要で、この熱は海水から奪われます。そのため、蒸発は海面水温を「下げる」働きをします。これを潜熱の放出と呼びます。
イ:地球の海面のような温度の物体が放射する電磁波は、主に「赤外線」です。夜間は太陽からのエネルギー供給がないため、この赤外線の放射によって熱が宇宙空間に逃げ、海面水温が下がります。
③【誤】
アの「上げる」とイの「可視光線」の両方が誤りです。
④【誤】
アの「上げる」が誤りです。
第3問
問1:正解④
<問題要旨>
太陽系の形成過程における、原始太陽系星雲の形状と、惑星の材料となった天体の成長過程についての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
原始太陽系星雲は回転しながら収縮するため、遠心力によって「円盤状」になります。また、天体は衝突・合体を繰り返して大きく成長します。
②【誤】
原始太陽系星雲の形状が「球状」であるという点が誤りです。
③【誤】
天体は分裂ではなく、合体して成長します。
④【正】
ア:ガスや塵でできた原始太陽系星雲は、回転しながら中心に物質を集め、その周囲には「円盤状」の構造を形成します。
イ:円盤の中で微惑星が形成され、それらが互いに衝突・「合体することで、より大きな天体」(原始惑星)へと成長していきました。
問2:正解①
<問題要旨>
太陽のような恒星の進化段階(主系列星、赤色巨星、白色矮星)と、それぞれの段階での核融合反応についての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
主系列星は、中心部で水素をヘリウムに変える核融合反応(水素核融合)によって輝いています。赤色巨星の段階では、中心部での水素核融合は終了していますが、その外側にある殻(シェル)で水素核融合が起こっています。したがって、主系列星と赤色巨星の両方で水素の核融合が起こっています。
②【誤】
白色矮星は、恒星が核融合を終えた後の核が冷えていく天体であり、内部で核融合は起こっていません。
③【誤】
白色矮星では核融合は起こっていません。
④【誤】
白色矮星では核融合は起こっていません。
問3:正解④
<問題要旨>
天体の分布図を見て、それがどの種類の天体群を示しているかを、天の川や黄道との位置関係から推測する問題です。
<選択肢>
①【誤】
小惑星は、太陽系の惑星と同様に黄道面に集中して分布するため、図の破線で示された黄道付近に多く見られるはずです。図の分布は黄道とは無関係です。
②【誤】
太陽近傍の恒星は、我々が属する銀河系(天の川銀河)の天体です。そのため、銀河系の円盤部分である天の川の方向に多く分布するはずです。図の分布は天の川とは一致しません。
③【誤】
星間雲も銀河系の構成要素であり、恒星と同様に天の川の方向に濃く分布するはずです。
④【正】
図の天体は、天の川や黄道といった太陽系や銀河系内の構造とは無関係に、空全体に広がって分布しています。また、領域Aのように集団(銀河団)を形成しています。これは、我々の銀河系の外にある、さらに遠方の「銀河」の分布の特徴を示しています。
第4問
問1:正解②
<問題要旨>
活火山の定義と、爆発的な噴火を引き起こすマグマの性質、およびその際に発生する現象(火砕流)に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
アは「1万年」、ウは「火砕流」が正しいです。
②【正】
ア:気象庁による「活火山」の定義は、おおむね過去「1万」年以内に噴火した火山、および現在活発な噴気活動のある火山です。
イ:爆発的な噴火は、マグマの粘性が高いことに加え、マグマに溶け込んでいる水蒸気などの「揮発性(ガス)成分」が多い場合に起こりやすくなります。
ウ:高温の火山ガスと火山砕屑物が一体となって高速で山腹を流れ下る現象を「火砕流」といいます。
③【誤】
アは「1万年」が正しいです。また、イは「揮発性(ガス)成分」が正しいです。
④【誤】
アは「1万年」、ウは「火砕流」が正しいです。
問2:正解③
<問題要旨>
柱状図に示された火山灰層の構成鉱物や層厚から、供給源や堆積量を読み取り、地質学的な解釈の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
aが誤りです。
②【誤】
a、bともに記述が逆です。
③【正】
a:火山灰層X、Y、Zに含まれる鉱物の組み合わせ(XとZは石英、Yは角閃石・輝石)が異なっています。これは、元のマグマの性質が異なることを示しており、すべてが同一の火山からもたらされたと考えるのは困難です。したがって、この文は「誤」です。
b:問題文に「堆積後に侵食を受けていなかった」とあるため、湖に堆積した火山灰層の厚さは、その場に降った火山灰の量をおおむね反映していると考えられます。したがって、この文は「正」です。
④【誤】
bが誤りです。
問3:正解③
<問題要旨>
北太平洋の海流の流れる向きを理解し、軽石の移動距離と日数から海流の平均的な速さを計算・比較する問題です。
<選択肢>
①【誤】
エの向きが誤りです。
②【誤】
エの向きとオの数値の両方が誤りです。
③【正】
エ:黒潮などを含む北太平洋の亜熱帯環流は、北半球の貿易風や偏西風、コリオリの力の影響で「時計回り」に流れています。
オ:各区間の海流の速さを計算します。
・対馬海流(N1→N2):
距離300km、日数(5/25~6/24)=30日間。速さ = 300km ÷ 30日 = 10km/日。
・黒潮(S1→S2):
距離1200km、日数(4/1~5/30)=30日(4月)+ 30日 = 60日間。速さ = 1200km ÷ 60日 = 20km/日。
黒潮の速さ(20km/日)は対馬海流の速さ(10km/日)の「2」倍です。
④【誤】
オの数値が誤りです。