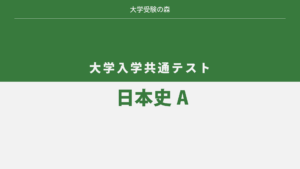解答
解説
第1問
問1:正解②
<問題要旨>
1858年に江戸幕府がアメリカと結んだ日米修好通商条約の内容について、正確に理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
日米修好通商条約では、江戸と大坂の開市、神奈川(のちに横浜)・長崎・新潟・兵庫(のちに神戸)の開港が定められました。京都は開市の対象ではありませんでした。
②【正】
この条約により、外国人は開港場に設けられた居留地に居住し、貿易活動を行うことが定められました。居留地外への自由な移動や商業活動は認められていませんでした。
③【誤】
アメリカ船への石炭や水、食料の提供(薪水給与)を定めたのは、1854年に結ばれた日米和親条約です。
④【誤】
この条約では、日本在住のアメリカ人が罪を犯した場合、日本の法律ではなくアメリカの領事が本国の法律に基づいて裁判を行う「領事裁判権(治外法権)」を認めました。日本人がアメリカの領事裁判にかけられるわけではありません。
問2:正解④
<問題要旨>
資料として示された「金銀比価の推移」のグラフと「欧米諸国の金本位制採用年」の表を正確に読み取り、19世紀後半の日本の金融制度と国際経済の関係を考察する問題です。
<選択肢>
X【誤】
問題文Aより、日本が銀本位制を採用したのは1885年、金本位制を採用したのは日清戦争後(1897年)です。グラフを見ると、1885年の金銀比価(金1に対する銀の量)は約19、1897年は約33です。金に対する銀の価値は、1885年を1とすると1897年には約19/33≒0.57となり、半分以下には下落していません。
Y【誤】
安政の五か国条約の相手国は、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、オランダの5か国です。日本が銀本位制を採用した1885年の時点で、資料の表から金本位制を採用していたのはイギリス、オランダ、フランス、アメリカです。ロシアは1897年に採用しており、1885年時点では採用していません。したがって、「すべて」の国が金本位制を採用していたわけではありません。
問3:正解③
<問題要旨>
1890年代から1930年代にかけての日本の貿易、産業、経済政策の動向について、誤っている記述を選択する問題です。
<選択肢>
①【正】
日清戦争後、紡績業は中国市場などへの綿糸輸出を伸ばし、日本の基幹産業となりました。その原料となる綿花は主にインドやアメリカから輸入されたため、国内の伝統的な綿花栽培は衰退しました。
②【正】
第一次世界大戦中、ヨーロッパ諸国が戦争で生産力を落としたため、日本はアジア市場への輸出を拡大し、また連合国への軍需品輸出も増え、一時的に輸出超過(大戦景気)となりました。しかし、大戦が終わりヨーロッパの生産力が回復すると、日本の輸出は減少し、再び輸入超過の状態に戻りました(戦後恐慌)。
③【誤】
浜口雄幸内閣(蔵相・井上準之助)は、世界恐慌が始まる直前に、円の価値を安定させる目的で金輸出を解禁(金解禁)しました。その準備として、デフレを進行させる緊縮財政や産業合理化を「推進」しました。これは「緊縮財政からの転換」ではなく、むしろ緊縮財政を強化する政策でした。
④【正】
浜口内閣の政策で深刻化した昭和恐慌に対し、犬養毅内閣(蔵相・高橋是清)は金輸出を再び禁止(再禁止)しました。これにより円の為替相場は下落(円安)し、日本の製品の輸出価格が下がったため、輸出が増大して景気回復につながりました。
問4:正解④
<問題要旨>
1930年代の日本の貿易に関する2つの統計資料(表1、表2)を読み解き、当時の日本の植民地との経済的な関係(いわゆるブロック経済)について正しく考察する問題です。
<選択肢>
a【誤】
表1から、植民地への輸出額(1,077百万円)が輸出総額(3,276百万円)に占める割合は、1077 ÷ 3276 ≒ 32.9%となり、30%を超えています。しかし、問題文Bにあるように、植民地との貿易は円で決済されたため、外貨の獲得には直接寄与しませんでした。
b【正】
表1から、植民地からの輸入品目で最も金額が大きいのは食料品(572百万円)です。本来、外国から外貨を使って輸入する必要がある食料品を、円で決済できる植民地から輸入することで、外貨の流出を抑える(節約する)効果がありました。
c【誤】
表2を見ると、日本の植民地である朝鮮の対本国貿易比率(輸出78%, 輸入85%)は、イギリスのインド(34%, 31%)やフランスのフランス領インドシナ(47%, 52%)と比べて著しく高く、本国経済への依存度が非常に強かったことがわかります。
d【正】
歴史的背景から、フィリピンはアメリカの植民地、東インド(現在のインドネシア)はオランダの植民地でした。したがって、空欄アにはアメリカ、空欄イにはオランダが入ります。
問5:正解①
<問題要旨>
日中戦争からアジア・太平洋戦争の時期にかけて、日本が戦争を遂行するために行った物資や資源の確保に関する政策や軍事行動について、正しい記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
1938年に制定された国家総動員法は、戦争遂行のために、政府が議会の承認を経ずに勅令によって、物資や労働力、資金などを統制・動員できる広範な権限を認めた法律です。
②【誤】
アメリカやイギリスが中国の蔣介石政権を支援した輸送ルート(援蔣ルート)の遮断は、日本軍の重要な戦略目標でした。しかし、その拠点であった重慶を占領することは最後までできませんでした。
③【誤】
アメリカが対日石油輸出を全面禁止したのは、1941年7月の日本軍による南部フランス領インドシナへの進駐が直接のきっかけです。マレー半島への進駐は、同年12月の真珠湾攻撃と同時に行われました。出来事の順序が誤っています。
④【誤】
日本軍は占領地で、現地で流通していた通貨とは別に、独自の軍票(軍用手票)を発行し、物資調達の代価としました。これは乱発されたため、占領地の経済に深刻なインフレーションと混乱をもたらしました。
問6:正解①
<問題要旨>
1952年に行われた吉田茂首相と中華民国(台湾)の特使・張群との会談に関する新聞記事(史料)を読解し、その内容から当時の日本の外交・経済状況を正しく理解する問題です。
<選択-肢>
X【正】
史料には「中共貿易が困難な限り当然日本として開発せざるを得ないものであるが」「東南アジア貿易によって局面打開を考慮している」とあります。1949年に成立した中華人民共和国との貿易が、朝鮮戦争(1950-53年)などの冷戦の影響で困難であったため、日本が東南アジアとの貿易に活路を見出そうとしていたことがわかります。
Y【正】
史料には、張群氏が「国民政府が仲介として華僑との貿易促進に便宜を供与する旨を約束した」とあります。また、会談の背景として共産主義(中共)に対抗する「防共問題」があったことも記されています。中華民国は、西側陣営の一員として日本との連携を強め、東南アジア貿易の促進に協力しようとしていました。
問7:正解⑤
<問題要旨>
第二次世界大戦後の日本の貿易環境を大きく変えた3つの出来事について、発生した年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
Ⅰ.変動為替相場制への移行は、1971年のニクソン・ショック(アメリカがドルと金の交換を停止)をきっかけに、ドルを基軸通貨とする固定為替相場制(ブレトン・ウッズ体制)が崩壊し、1973年から主要国で導入されました。
Ⅱ.G5(先進5か国蔵相・中央銀行総裁会議)でドル高是正が合意されたのは、1985年のプラザ合意です。これにより急激な円高が進行し、日本経済は大きな影響を受けました。
Ⅲ.日本がIMF(国際通貨基金)8条国へ移行したのは1964年です。これは、経常的な支払いに対する為替制限を原則として撤廃することを意味し、日本の貿易や資本の自由化が進んだことを象徴する出来事です。
以上のことから、年代順は Ⅲ(1964年)→ Ⅰ(1973年)→ Ⅱ(1985年)となります。
第2問
問1:正解⑤
<問題要旨>
ペリー来航(1853年)から明治維新までの幕末期における重要な出来事を、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
Ⅰ.薩摩藩の島津久光らが主導した公武合体運動の一環として、幕府が政治改革(文久の改革)を行い、参勤交代制を緩和したのは1862年です。
Ⅱ.長州藩が、前年の政変(八月十八日の政変)で失った京都での勢力を回復しようと出兵し、会津・薩摩藩兵と衝突した事件は、1864年の禁門の変(蛤御門の変)です。
Ⅲ.開国(1859年)後、生糸などの重要輸出品が横浜の開港場に直送され、江戸で物価が高騰したため、幕府がこれらの品物を一度江戸の問屋を通すように命じた五品江戸廻送令を出したのは1860年です。
以上のことから、年代順は Ⅲ(1860年)→ Ⅰ(1862年)→ Ⅱ(1864年)となります。
問2:正解②
<問題要旨>
徳川慶喜が大政奉還を明治天皇に上奏した際の文書(史料1)を読解し、その内容と、その後の政治の動きに関する知識を問う問題です。
<選択肢>
X【正】
史料1には、「外国の交際、日に盛んなるにより、愈朝権一途に出申さず候ては綱紀立ち難く候間、…政権を朝廷に帰し奉り」とあります。これは、外国との交渉が盛んになる中で、朝廷のもとに政権を統一しなければ国家の規律が保てない、という大政奉還の理由を述べており、文Xの内容と一致します。
Y【誤】
歴史の順序が逆です。まず徳川慶喜による大政奉還(1867年10月)が行われ、それを受けて薩長両藩が主導して同年12月に王政復古の大号令を発し、新政府の樹立を宣言しました。その後に新政府軍と旧幕府軍が衝突したのが鳥羽・伏見の戦い(1868年1月)です。
問3:正解①
<問題要旨>
明治時代の条約改正交渉と、初期の対外条約に関する具体的な知識を問う問題です。
<選択肢>
Xは、外国人判事を日本の大審院(最高裁判所)に任用するという条約改正案を提示し、国内から「国辱的」と激しい批判を浴びて爆弾を投げられ負傷した外務大臣についての記述です。これは、大隈重信です。
Yは、明治政府が初めて(欧米諸国以外と)対等な立場で結んだ条約についての記述です。これは、1871年に清との間で結ばれた日清修好条規を指します。この条約では、領事裁判権を相互に認め、関税も両国の協定によって定めることなどが規定されていました。
したがって、正しい組み合わせはX-a、Y-cとなります。
問4:正解②
<問題要旨>
明治天皇の最初の東京行幸(1868年)に関する史料と錦絵を読み解き、当時の社会状況やメディアの役割について考察する問題です。
<選択肢>
a【正】
明治天皇が初めて東京に入ったのは1868年10月ですが、この時点ではまだ戊辰戦争は終結していませんでした。東北地方では会津藩などが抵抗を続けており、箱館(函館)では榎本武揚ら旧幕府軍が五稜郭に立てこもっていました。旧幕府勢力の抗戦は翌年まで続きました。
b【誤】
多色刷りの浮世絵である錦絵は、江戸時代中期の18世紀後半に鈴木春信らによって完成された技法です。開国後に外国文化の影響で誕生したものではありません。
c【誤】
史料2には「貴賤老稚道路に輻輳して」(身分の高い者も低い者も、老人も子供も、道に集まってごった返して)とあり、人々が入り乱れて行列を見物していた様子がわかります。「整然と区分けされ」という記述は、史料の内容と合いません。
d【正】
図の錦絵は、10月の行幸の翌月である11月に制作・発行されています。このことから、錦絵がニュース速報のように時事的な出来事を人々に伝えるメディアとしての役割を果たしていたことがうかがえます。
第3問
問1:正解①
<問題要旨>
明治政府が出した法令に関連する出来事(X)と、地方制度の整備に関わった人物(Y)についての知識を問う問題です。
<選択肢>
Xは、廃刀令などに不満を持つ士族が熊本県で起こした反乱についての記述です。これは、1876年に熊本の敬神党(しんぷうれん)が起こした神風連の乱を指します。
Yは、内務大臣として地方制度の整備を進め、ドイツの制度を参考に市制・町村制を公布した中心人物についての記述です。これは、山県有朋です。
したがって、正しい組み合わせはX-a、Y-cとなります。
問2:正解④
<問題要旨>
明治初期の啓蒙思想家である森有礼の論考(史料1)を読解し、彼が所属した明六社やその機関誌『明六雑誌』の性格について正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
a【誤】
史料1で森有礼は、民撰議院設立の建白書について「民間の人物を政府の撰にて設くる議員の意なるべし」と評しています。これは、「政府の役人を議員にする」という意味ではなく、「民間人の中から政府が議員を選ぶ」という意味だと解釈できる、と指摘しているものです。
b【正】
上記aの解説の通り、森有礼は建白書の文言が「政府によって議員が選ばれる」と読めると評しています。
c【誤】
『明六雑誌』は、福沢諭吉や西周など当時の代表的な知識人が参加し、欧米の近代的な思想や学問、政治制度などを紹介した啓蒙雑誌です。政府の欧化政策を批判し平民主義を主張したのは、徳富蘇峰が主宰した民友社やその機関誌『国民之友』などです。
d【正】
『明六雑誌』は、欧米の進んだ思想や文化、政治・経済の仕組みなどを広く日本に紹介し、社会の近代化を促すことを目的としていました。
問3:正解②
<問題要旨>
初期議会における政府と民党の対立を背景とした、第2回衆議院議員総選挙(1892年)での政府による選挙干渉に関する議事速記録(史料2)を読み解く問題です。
<選択肢>
ア:史料2で登壇者は、政府が選挙において「法律を無視して集会を……、言論を束縛し、集会を妨害し」たと非難しています。これは、集会や結社の自由を制限する法律を濫用したことを指していると考えられます。選択肢のうち、集会や言論を取り締まるための法律は保安条例(1887年制定)です。統帥権は天皇が軍隊を直接指揮する権限であり、選挙干渉とは関係ありません。
イ:この選挙は、第2次松方正義内閣(内相・品川弥二郎)が警察などを動員して行った大規模な選挙干渉で知られています。しかし、こうした厳しい干渉にもかかわらず、政府を支持する吏党は過半数を獲得することができず、反政府的な民党が多数の議席を維持しました。
したがって、正しい組み合わせはア-保安条例、イ-獲得しませんでした、となります。
問4:正解③
<問題要旨>
明治期から大正期にかけての日本画・洋画の動向について、画家、団体、作品に関する知識を問い、誤っている記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
岡倉天心は、東京美術学校を追われた後、横山大観や菱田春草らとともに日本美術院を創設し、伝統にとらわれない新しい日本画の創造を目指しました。
②【正】
黒田清輝は、フランスで外光派の明るい画風を学び、日本洋画界に大きな影響を与えました。代表作に「湖畔」や「読書」などがあります。
③【誤】
「麗子像」は、洋画家である岸田劉生の代表作の一つです。横山大観は、岡倉天心のもとで活躍した日本画家であり、代表作に「生々流転」などがあります。画家と作品の組み合わせが誤っています。
④【正】
官設の文部省美術展覧会(文展)の審査方針に不満を持つ進歩的な洋画家たちが、自由な創作活動の場を求めて結成した在野の美術団体が二科会です。
問5:正解④
<問題要旨>
問題文の杉浦非水が活動した期間(1908年~1934年)に起きた社会的な出来事について、発生した年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
Ⅰ.血盟団事件は、国家主義者の井上日召が率いるグループが、政財界の要人である井上準之助や団琢磨らを暗殺した事件で、1932年に起きました。
Ⅱ.平塚らいてう(雷鳥)らが、女性の自覚と解放を訴える文芸雑誌『青鞜』を創刊したのは1911年です。
Ⅲ.コミンテルン(国際共産党)の指導のもと、堺利彦や山川均らが中心となって、非合法の政党として日本共産党が結成されたのは1922年です。
以上のことから、年代順は Ⅱ(1911年)→ Ⅲ(1922年)→ Ⅰ(1932年)となります。
問6:正解②
<問題要旨>
日露戦争後の日本の政治状況に関する犬養毅の議会演説(史料3)を読解し、その内容と関連する歴史的事実の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
X【正】
史料3で犬養毅は、「世界が、日本の軍事計画について一種の猜疑心をもっている」「戦争が終わったというのに、予算案の軍備費はますます増額されている」と述べ、日露戦争後も軍備拡張を続ける日本の姿勢が、国際社会の不信や警戒を招いていると批判しています。
Y【誤】
韓国が日本の保護国となったこと(第二次日韓協約)に反発して、韓国各地で起こったのは義兵闘争です。東学を信仰する農民が中心となった大規模な蜂起は、日清戦争のきっかけとなった甲午農民戦争(1894年)であり、時期と内容が異なります。
問7:正解③
<問題要旨>
大正時代から昭和戦前期にかけて制作された3つのポスター(資料1~3)について、高校生3人の会話の内容の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
ノゾミ【正】
資料1は、「帝都復興と地下鉄道」という文字から、1923年の関東大震災後の東京の復興事業と関連していることがわかります。日本初の地下鉄(現・東京メトロ銀座線の一部)は、復興が進む1927年に開通しました。ノゾミさんの発言は正しいです。
ユウト【誤】
資料2は、「民政党」「政友会」という二大政党の名前が描かれ、民政党側が「国民の総意を反映す」と主張し、政友会側を「私利党略」と批判しているポスターです。会話では「原敬が率いている立憲政友会」とありますが、原敬は1921年に暗殺されており、このポスターが描かれたと考えられる普通選挙後の政党政治期(1920年代後半以降)にはすでに亡くなっています。したがって、ユウトさんの発言は誤っています。
リコ【正】
資料3には「贅沢は敵だ!」「決戦へ! 頑張れニッポン」といった戦時標語が見られます。これは、国民精神総動員運動などが展開されたアジア・太平洋戦争期に、国民に銃後の協力を呼びかけたポスターであると考えられます。リコさんの発言は正しいです。
以上より、ユウトさんのみが間違っていることになります。
第4問
問1:正解③
<問題要旨>
明治時代の政治史と美術史に関する知識を組み合わせ、会話文中の空欄を補充する問題です。
<選択肢>
ア:西南戦争で政府に反逆したとされた西郷隆盛の名誉が回復され、正三位が贈られたのは、1889年の大日本帝国憲法発布に伴う大赦がきっかけでした。これを機に、彼の功績を称える銅像の建設運動が起こりました。
イ:高村光雲の息子で、自身も彫刻家であった高村光太郎と親しく、フランスの彫刻家ロダンの影響を強く受けた人物は、荻原守衛(碌山)です。荻原は「女」などの作品で知られています。島村抱月は演劇運動の指導者です。
したがって、正しい組み合わせはア-大日本帝国憲法の発布、イ-荻原守衛となります。
問2:正解⑥
<問題要旨>
明治末期から大正期にかけての政治・社会の出来事を報じた新聞記事の一部を読み、それらが報じられた時期を古いものから順に配列する問題です。
<選択肢>
Ⅰ.「米価暴騰」「漁師町一帯の女房連」といった記述から、1918年(大正7年)に富山県の漁村から全国に広がった米騒動に関する記事であることがわかります。
Ⅱ.「十年前の二月十日は、…強露討伐の詔勅を下し給える日」(日露開戦の日)、「山本内閣に対する宣戦の烽火」という記述から、日露開戦10周年にあたる1914年(大正3年)に、シーメンス事件で批判を浴びていた第1次山本権兵衛内閣への退陣要求運動が起きた際の報道だと判断できます。
Ⅲ.「新帝御践祚の初に当り」「桂公の内閣を組織せん」という記述から、明治天皇が崩御し大正天皇が即位した直後の1912年(大正元年)に、第3次桂太郎内閣が成立しようとしたことに対し、閥族政治打破を掲げる第一次護憲運動が起こったことを報じた記事だとわかります。
以上のことから、年代順は Ⅲ(1912年)→ Ⅱ(1914年)→ Ⅰ(1918年)となります。
問3:正解④
<問題要旨>
幕末の大老・井伊直弼の銅像建設に関する史料を読み解き、その背景にある歴史的な出来事と正しく結びつける問題です。
<選択肢>
X「意外の障害」:史料1によると、1884年(明治17年)に記念碑の建設が障害に遭い中止されています。井伊直弼は安政の大獄で吉田松陰をはじめとする多くの尊王攘夷派を弾圧しました。明治政府の中心には、弾圧された長州藩の出身者が多かったため、彼らからの強い反発が「意外の障害」であったと考えられます。→b
Y「直弼公の遭難地」:井伊直弼が暗殺されたのは、1860年、江戸城の桜田門外で水戸・薩摩の浪士に襲撃された桜田門外の変です。この事件で幕府の権威は大きく失墜し、幕府は朝廷との融和を図る公武合体政策に転換し、孝明天皇の妹・和宮を将軍徳川家茂の妻に迎えました。→d
(a:井伊直弼は将軍継嗣問題で一橋派と対立し、これを弾圧した南紀派の中心人物です。c:井伊直弼は桜田門外で暗殺されており、失脚ではありません。また、襲撃したのは水戸・薩摩の浪士です。)
したがって、正しい組み合わせはX-b、Y-dとなります。
問4:正解①
<問題要旨>
明治天皇の死去(1912年)に際して、その銅像建設について述べた板垣退助の意見(史料2)を読解し、史料が書かれた時期の板垣の状況と合わせて正誤を判断する問題です。
<選択肢>
a【正】
史料2で板垣は、「神宮のみにては如何にも物足らぬ」「必ず銅像を建立し御英姿を拝し得るようしたきもの也」と述べており、神宮だけでは不十分で、天皇の姿をかたどった銅像こそが人々が天皇を慕う気持ちを高めるために必要だと主張しています。
b【誤】
aが正しいため、この選択肢は誤りです。板垣は神宮だけでは物足りないと考えています。
c【正】
板垣退助が率いた自由党は、政府の弾圧や内部対立により1884年に解党しています。1912年の時点では、かつて党首を務めた「自由党」は存在していませんでした。
d【誤】
板垣退助は内務大臣などを歴任しましたが、総理大臣になったことはなく、また首相の推薦など国政の重要事項に関与する元老にも任じられていません。
問5:正解①
<問題要旨>
日中戦争の勃発(1937年)から日本の敗戦(1945年)までの、戦時下の国民の政治・社会生活について、正しい記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
戦争が末期になるにつれて、食糧事情は極度に悪化しました。米の供給量は減少し、配給も滞りがちになったため、国民はサツマイモやカボチャ、大豆かすなどを主食の代わり(代用食)とすることを強いられました。
②【誤】
独占禁止法は、戦後の経済民主化の一環として、財閥解体を進めるために1947年に制定された法律です。戦時中の法律ではありません。
③【誤】
段祺瑞政権は、第一次世界大戦期に日本からの多額の借款(西原借款)によって支えられていた中国の政権です。イギリスによる援助に反発したという事実はありません。
④【誤】
「東亜新秩序」の建設を声明したのは、1938年の第1次近衛文麿内閣です。米内光政内閣(1940年)ではありません。
問6:正解③
<問題要旨>
戦後、軍人・寺内正毅の銅像跡に建てられた裸婦の群像に関する新聞記事(史料3)を読解し、その内容と関連する歴史的事実の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
X【誤】
史料3の銅像のモデルであった寺内正毅が首相を務めた内閣(1916~18年)は、中国の段祺瑞政権に西原借款と呼ばれる多額の借款を行いました。中国に対し二十一か条の要求を突きつけたのは、その前の第2次大隈重信内閣(1915年)です。
Y【正】
史料3には、この裸婦像を「まさに軍国日本から文化日本への脱皮を象徴する女神の像」「平和日本のシンボル」と記されています。この記事が、裸婦像を軍国主義からの脱却の象徴とみなしていることは明らかです。
問7:正解②
<問題要旨>
日本の敗戦から1970年代までの科学技術の発展と、それに伴う社会の変化について述べた文の中から、誤っているものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
物理学者の湯川秀樹は、中間子の存在を理論的に予言した業績により、1949年に日本人として初めてノーベル物理学賞を受賞しました。
②【誤】
1950年代後半から始まった電化ブームの中で、人々のあこがれの的となった「三種の神器」は、白黒テレビ・電気洗濯機・電気冷蔵庫です。自動車、カラーテレビ、クーラー(3C)が新たな「三種の神器」として普及したのは、1960年代後半の高度経済成長期です。
③【正】
高度経済成長期には、エネルギー源が石炭から石油へと転換するエネルギー革命が進みました。これを背景に、石油を原料とする化学製品を生産する大規模な石油化学コンビナートが、太平洋沿岸地域に次々と建設されました。
④【正】
1970年に大阪で開催された日本万国博覧会(大阪万博)では、アメリカ館に展示された「月の石」や、動く歩道、ワイヤレス電話など、未来を感じさせる新しい技術が数多く紹介され、大きな話題となりました。
第5問
問1:正解②
<問題要旨>
キョウさんが生まれた1930年に始まった経済恐慌(昭和恐慌)の影響について、正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
X【正】
1929年の世界恐慌と、それに続く日本の金解禁が引き金となり、昭和恐慌が発生しました。企業の倒産が相次ぎ、失業者が急増した都市部では、労働者の生活は困窮し、労働争議が激化しました。
Y【誤】
生活必需品の切符制や配給制が導入されたのは、日中戦争が長期化し、物資不足が深刻化した戦時体制下(1940年代初頭から)のことです。昭和恐慌の時期ではありません。
問2:正解①
<問題要旨>
第二次世界大戦敗戦後の労働運動に関する主要な出来事を、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
Ⅰ.GHQによる戦後改革の一環として、労働者の団結権、団体交渉権、争議権を保障する労働組合法が制定されたのは、1945年12月です。
Ⅱ.官公庁労働者を中心に、賃上げや政府打倒を掲げて計画された全国的なゼネラル・ストライキ(二・一ゼネスト)は、GHQの指令によって実行直前(1947年2月1日)に中止させられました。
Ⅲ.それまでの労働組合の全国組織であった総同盟と産別会議が解散した後、新たな全国組織として日本労働組合総評議会(総評)が結成されたのは、1950年です。
以上のことから、年代順は Ⅰ(1945年)→ Ⅱ(1947年)→ Ⅲ(1950年)となります。
問3:正解①
<問題要旨>
敗戦から3年後の1948年における東京の都心の状況を描写した文章(史料1)を読み解き、その内容を最も的確に説明している選択肢を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
史料1には、「焼跡の新世界」「戦災者の渦のように息苦しくなる」「戦災と飢えと宿なしがいたるところに流れている」といった記述があります。これらは、空襲によって家を失い、住む場所がない人々が街にあふれていた当時の状況を明確に示しています。
②【誤】
「焼跡の新世界」という言葉が示すように、空襲の爪痕は依然として生々しく残っていました。「空襲の影響を見出すことが難しくなっている」という記述は、史料の内容と正反対です。
③【誤】
敗戦に伴い、旧植民地やアジア各地の占領地から多くの軍人や民間人が日本に引き揚げてきました。彼らの多くもまた、住む家や職を失っており、史料1に描かれている「人々」の中に多数含まれていたと考えるのが自然です。
④【誤】
敗戦直後の日本経済は、生産設備の破壊や物資の極端な不足により、激しいインフレーション(物価の高騰)に見舞われていました。物価が下落するデフレーションではありません。
問4:正解③
<問題要旨>
アジア・太平洋戦争中の国民生活について述べた文の中から、誤っているものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
戦争の長期化で労働力不足が深刻になると、政府は学生・生徒を軍需工場などに動員する勤労動員を実施したり、未婚女性を工場などで働かせる女子挺身隊を組織したりしました。
②【正】
1944年後半から、アメリカ軍のB29爆撃機による本土への空襲が本格化し、特に主要都市は焼夷弾による無差別爆撃を受け、多くの民間人が犠牲となりました。
③【誤】
都市部への空襲が激しくなると、政府は学童(小学生)を、親元から離して地方の農村などに集団で避難させる学童疎開を実施しました。「都市を離れることは許されず」という記述は事実に反します。
④【正】
戦争が長引き、食糧不足や空襲の被害など国民生活の困窮が深まるにつれて、人々の間には戦争への疲れや嫌気(厭戦気分)が広がっていきました。
問5:正解③
<問題要旨>
1960年代の日本の政治・社会の動向について、正しい記述の組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
a【誤】
アメリカの水爆実験で日本の漁船「第五福竜丸」が被ばくした事件は1954年の出来事です。これをきっかけに原水爆禁止を求める国民運動が広まりましたが、1960年代の出来事ではありません。
b【正】
1960年に日本社会党から右派が分裂して民主社会党(民社党)が結成され、1964年には創価学会を支持母体とする公明党が結成されるなど、野党の多党化が進んだのが1960年代の特徴です。
c【正】
高度経済成長のひずみとして、四日市ぜんそくや水俣病などの公害問題が深刻化しました。これを受けて、国として公害対策に取り組むための基本法である公害対策基本法が1967年に制定されました。
d【誤】
第4次中東戦争をきっかけにアラブ産油国が石油輸出を制限したことで起こった第1次石油危機(オイルショック)は、1973年の出来事です。
問6:正解④
<問題要旨>
1960年から1975年にかけての日本の人口に関するデータをまとめたグラフを読み取り、その内容や背景について正しく解釈している文を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
センさんが公団住宅に転居したのは「沖縄が返還される2年前」とあるので、沖縄返還の1972年から2年前の1970年です。グラフを見ると、1970年の全人口は1億人をわずかに超えています(約104,000千人)。したがって、「1億人に達していなかった」は誤りです。
②【誤】
都市部を除く地域の人口は、「全人口」から「都市部人口」を引くことで算出できます。1960年は約9,300万人-約4,100万人=約5,200万人。1975年は約1億1,100万人-約6,400万人=約4,700万人。減少はしていますが、半減はしていません。
③【誤】
グラフから農業従事者数の割合が減少していることは読み取れますが、それが直ちに「都市部の食料難が常態化」を意味するわけではありません。この時期は農業の機械化・近代化で生産性が向上し、食料輸入も増えたため、都市部で食料難が常態化していたわけではありません。
④【正】
グラフから、都市部人口は1960年の約4,100万人から1975年の約6,400万人へと、約2,300万人増加しています。「2000万人以上増加」しており、これは地方から都市部への大規模な人口流入(集団就職など)があったことを示唆しており、都市部の過密化が進んだと考えられます。
問7:正解③
<問題要旨>
戦時中の職工住宅と1960年代の公団住宅の間取り図や関連史料から、戦後日本の住宅事情と生活様式の変化について総合的に考察する問題です。
<選択肢>
a【誤】
史料2には「家族全員がひとつの卓袱台を囲んで食事をする習慣が定着」とあり、個別のちゃぶ台で食事をするのが一般的だったわけではありません。
b【正】
センさんのメモには、1960年代に「家電普及率も伸び」「様々な家電を置くことができた」とあります。2DKという間取りは、台所、食事をする部屋、寝室といったように部屋の機能が分化しているため、それぞれの部屋の用途に応じて冷蔵庫やテレビなどの家電を設置する生活様式が生まれたと考えられます。
c【正】
史料2には、「就寝の場所と食事の場所を分けたいという『食寝分離』の欲求が国民の間に高まり」、それがダイニング・キッチン(DK)形式の住宅が生まれる背景の一つになったと記されています。この記述は、職工住宅のような食事と就寝が同じ部屋で行われる生活からの変化を示唆しています。
d【誤】
史料3(1965年の記事)で、3DKの公団住宅に入居した人が「ここを子ども部屋にして」と喜んでいる様子が描かれています。これは3DKによって子ども部屋の確保がより容易になったことを示しますが、「初めて…できるようになった」と断定することはできません。2DKでも一部屋を子ども部屋として使うことは可能であり、史料からそこまで限定的な解釈はできません。