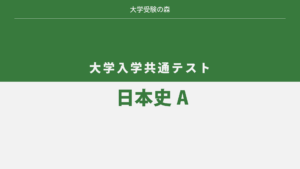解答
解説
第1問
問1:正解②
<問題要旨>
明治初期の士族の状況や、政府が彼らに対してとった「士族授産」と呼ばれる一連の政策についての理解を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
1873年(明治6年)に公布された徴兵令は、身分にかかわらず満20歳に達した男子に兵役の義務を課すものでした。これにより、従来の士族中心の軍隊から、広く国民を対象とする近代的な軍隊(国民皆兵)の創設が目指されました。
②【誤】
士族反乱は、廃刀令や秩禄処分など、士族の特権を奪う政策に対して不満を抱いた士族によって起こされました。一方、地租を地価の3%から2.5%に引き下げることを求めたのは、地租改正に反対する農民たちであり、各地で「地租改正反対一揆」を起こしました。したがって、この選択肢は士族反乱の理由を取り違えています。
③【正】
政府は、秩禄を失い困窮する士族を救済するため、新しい仕事に就くことを奨励する「士族授産」政策を行いました。その一環として、事業を始めるための資金を貸し付ける制度(帰商法など)がありました。
④【正】
「士族授産」政策の一環として、政府は士族に北海道への移住を奨励し、開拓に従事させました。これが屯田兵制度で、北海道の開拓とロシアに対する防衛を兼ねる目的がありました。
問2:正解①
<問題要旨>
史料として提示された伊藤博文の談話を正確に読解し、明治期のキリスト教に関する基本的な知識と結びつけて、正しい記述の組み合わせを判断する問題です。
<選択肢>
a【正】
史料1で伊藤博文は、「欧州においては」「宗教なるものありてこれが機軸をなし、深く人心に浸潤して人心此に帰一せり」と述べています。これは、ヨーロッパでは宗教が人々の心をまとめ、国家の軸として機能していると伊藤が理解していたことを示しています。
b【誤】
史料1で伊藤博文は、「然るに我が国にありては宗教なるものその力微弱にして、一も国家の機軸たるべきものなし」「我が国にありて機軸とすべきは独り皇室あるのみ」と述べています。これは、日本では宗教の力が弱いので、宗教「に加えて」皇室を機軸とするのではなく、宗教の代わりに「ただ皇室だけ」を機軸にすべきだと考えていたことを示しています。
c【正】
明治期に来日したキリスト教の宣教師や、新島襄・植村正久といった日本人キリスト教徒たちは、布教活動だけでなく、大学(同志社など)や女学校(フェリス女学院など)、病院といった教育・社会事業にも積極的に取り組みました。
d【誤】
内村鑑三は、第一高等中学校の教員だった1891年(明治24年)、教育勅語の拝礼式でキリスト教の信仰を理由に最敬礼をしなかったため、社会から激しい非難を浴びて職を追われました(不敬事件)。彼は教育勅語を礼賛したのではなく、むしろ自身の信仰と相容れないものとして対峙しました。
問3:正解④
<問題要旨>
明治期に開催された万国博覧会と、そこに出品された日本の製品や作品、関連する人物についての知識を問う問題です。
<選択肢>
Xに当てはまるのはb「生糸・絹織物」です。1873年(明治6年)のウィーン万博当時、生糸や絹織物は日本の最も重要な輸出品でした。官営の富岡製糸場が設立されたのもこの時期であり、国策として品質向上と増産が図られていました。
Yに当てはまるのはd「高村光雲」です。写真の木彫は、彫刻家である高村光雲の代表作「老猿」です。この作品は1893年(明治26年)のシカゴ万博に出品され、高い評価を受けました。狩野芳崖は日本画家であり、木彫家ではありません。
したがって、X-b、Y-dの組み合わせが正しくなります。
問4:正解⑥
<問題要旨>
幕末から明治にかけての、日本とロシア(ソ連)との間の国境画定に関する三つの条約の締結順序を問う問題です。
<選択肢>
Iの内容は、日露戦争(1904~1905年)の講和条約であるポーツマス条約(1905年)に関するものです。この条約で日本は、ロシアから南樺太(サハリン島南部)を譲渡されました。
IIの内容は、樺太・千島交換条約(1875年)に関するものです。この条約で、日露雑居地とされていた樺太全島をロシア領とする代わりに、千島列島全島を日本領とすることが定められました。
IIIの内容は、日露和親条約(1854年)に関するものです。この条約で、択捉島とウルップ島の間に国境が引かれましたが、樺太については国境を定めず、これまで通り日露両国民の雑居地とされました。
したがって、締結された年代の古い順に並べると、III(1854年)→ II(1875年)→ I(1905年)となります。
問5:正解③
<問題要旨>
年表から、著者が「小学校教員講習所を卒業してから、陸軍を除隊するまで」の期間(1940年3月~1944年8月)を特定し、その間に起こった出来事として合致する記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
共産党員が公然と講義を行うような状況は、治安維持法下の戦時中には考えられず、戦後の記述である可能性が高いです。
②【誤】
国民精神総動員運動が始まったのは1937年(昭和12年)であり、設問で指定された1940年3月よりも前の出来事です。
③【正】
それまでの尋常小学校などが「国民学校」と改称されたのは、1941年(昭和16年)の国民学校令によるものです。この年は1940年3月から1944年8月までの期間に含まれます。
④【誤】
天皇による終戦の詔書(玉音放送)がラジオで放送されたのは、日本のポツダム宣言受諾後の1945年(昭和20年)8月15日であり、設問で指定された期間よりも後です。
問6:正解①
<問題要旨>
第二次世界大戦敗戦後の南樺太(サハリン)における、ソ連軍政下の日本人学校の状況について、史料から読み取れる内容を正しく判断する問題です。
<選択肢>
X【正】
ソ連は、当時まだ有効であった日ソ中立条約を一方的に破棄して1945年8月に対日参戦し、満州や南樺太に侵攻しました。史料には「ソ連当局の指示」「ソ連の女性視学官」といった記述があり、日本の敗戦後、樺太の日本人学校がソ連の監督下に置かれていたことがわかります。
Y【正】
史料には、著者が教員免許状を実家に置いていると説明したところ、「翌月から少し給料を減額されてしまう羽目になった」とあります。この記述から、日本の教員免許状を所持しているか(または、その場で提示できるか)どうかが、給料の額に影響を与えていたことが読み取れます。
問7:正解③
<問題要旨>
第二次世界大戦敗戦後の、兵士の抑留や引揚げ、国内の社会状況についての知識を問う問題です。
<選択肢>
ア:旧満州(中国東北部)などでソ連軍の捕虜となった多くの日本軍兵士は、極寒の地である「シベリア」の収容所に送られ、長期間にわたる厳しい強制労働を強いられました(シベリア抑留)。
イ:戦争による生産基盤の破壊で仕事が激減したところに、海外の旧植民地や占領地からの引揚者、そして復員した兵士が大量に加わったため、都市部を中心に労働力が供給過剰となり、深刻な「失業問題」が発生しました。
したがって、アに「シベリア」、イに「失業問題」が入る組合せが正しくなります。
第2問
問1:正解②
<問題要旨>
明治初期の鉄道建設を主導した中央官庁と、日本で最初に鉄道が開業した区間についての基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
ア:鉄道建設、鉱山開発、電信、製糸場の運営といった、明治政府の殖産興業政策の中心的な役割を担った官庁は「工部省」です。内務省は、地方行政・警察・土木などを所管する官庁として、工部省が廃止された後にその一部業務を引き継ぎましたが、鉄道建設を最初に主導したのは工部省です。
イ:日本で最初の鉄道は、1872年(明治5年)に「新橋」(現在の汐留付近)と横浜(現在の桜木町駅付近)の間で正式開業しました。
したがって、アに「工部省」、イに「新橋」が入る組合せが正しくなります。
問2:正解④
<問題要旨>
ペリー来航直後の1853年に出された幕府の法令に関する史料を読み、その内容を正確に解釈する問題です。
<選択肢>
X【誤】
史料には「作用方ならびに船数共委細相伺い、差図を受くべき旨」とあります。これは、大型船を建造する際には、その仕様や数などを詳しく幕府に報告し、指示を受けなさいという意味です。したがって、大名が幕府に断りなく自由に西洋式艦船を製造できるようになったわけではありません。
Y【誤】
史料の最後には「邪宗門御制禁等の儀は、弥以て先規のごとく相守り」とあります。これは、キリスト教の禁止(邪宗門の禁制)については、これまで通り厳重に守るように、ということを意味しています。時勢に応じてキリスト教を解禁したわけではなく、むしろ祖法である禁教令は維持することを強調しています。
問3:正解⑥
<問題要旨>
幕末の開国から攘夷の実行に至る時期の、主要な対外関係の出来事を年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
I:薩英戦争は、1862年(文久2年)に発生した生麦事件をきっかけに、翌1863年(文久3年)に薩摩藩とイギリスとの間で起こった武力衝突です。
II:日米修好通商条約が締結されたのは1858年(安政5年)です。この条約では、アメリカに領事裁判権を認め、日本に関税自主権がない協定関税制が定められました。その後、幕府はイギリスなど4か国とも同様の条約(安政の五か国条約)を結びました。
III:日米和親条約は、ペリーの来航(1853年)を受けて、翌1854年(嘉永7年)に締結された条約です。この条約で日本は、アメリカ船に薪水や食料を供給することなどを約束し、下田・箱館の2港を開きました。
したがって、締結・発生した年代の古い順に並べると、III(1854年)→ II(1858年)→ I(1863年)となります。
問4:正解②
<問題要旨>
提示されたメモ(文章)と表(統計)の両方の情報を踏まえて、明治期の近代化(技術導入と国産化)の状況について正しく述べた文を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
東京美術学校は、フェノロサや岡倉天心らの尽力により、当初は日本画や木彫などの日本の伝統美術の振興を目的として設立されました。お雇い外国人(フォンタネージら)が主導して西洋美術を教えたのは工部美術学校であり、記述が異なります。
②【正】
メモには、高輪築堤の建設において「石垣の基礎として、胴木と呼ばれる丸太や松の杭が使用されるなど、江戸時代の埋立て・石垣造りの技術が用いられた」と明確に記されています。これは、西洋の技術を導入しつつも、日本の在来技術が活用されたことを示しています。
③【誤】
表を見ると、お雇い外国人の総数が最も多かったのは1875年(527人)です。この年の内訳は、学術教師が144人、技術者が205人であり、「技術者」の数が「学術教師」の数を上回っています。他の年も同様の傾向が見られます。
④【誤】
メモによれば、日本人初の機関士が誕生したのは1879年です。表を見ると、1879年と1880年にはお雇い外国人に占める技術者の割合が43%と高くなっていますが、その後1880年代前半には低下しています。したがって、この頃から技術者の割合が「上昇する傾向にあった」とは言えません。むしろ、日本人への技術移転が進んだ結果、外国人技術者への依存度が徐々に低下していったと解釈できます。
第3問
問1:正解④
<問題要旨>
1880年代の朝鮮半島情勢、特に朝鮮内部の対立(事大党と独立党)と、それをめぐる日清両国の関係についての正確な理解を問う問題です。
<選択肢>
X【誤】
壬午軍乱(1882年)の後、日本は朝鮮と済物浦条約を、清は朝鮮と中朝商民水陸貿易章程を結び、朝鮮に対する宗主権を強めました。その後、金玉均らがクーデタを起こした甲申政変(1884年)の事後処理として、日清両国は天津条約(1885年)を結び、朝鮮から両国軍を撤兵させ、将来出兵する際には互いに事前通告することを定めました。したがって、「壬午軍乱を受けて、日清両国は天津条約を結び」という部分が誤りです。
Y【誤】
閔氏の政権(事大党)は、清との伝統的な関係を重視する保守派でした。これに対し、金玉均らのグループ(独立党・開化派)は、日本の明治維新をモデルとして急進的な近代化を目指し、清からの自立を図ろうとしました。選択肢の記述は、閔氏政権と金玉均らの政治的立場が逆になっています。
問2:正解①
<問題要旨>
明治中期の思想やジャーナリズム、および日露戦争後の民衆の動きに関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
Xに当てはまるのはa「徳富蘇峰」です。徳富蘇峰は、出版社である民友社を設立し、雑誌『国民之友』や新聞『国民新聞』を通じて、西欧的な自由・平等を理想とする平民主義を主張しました。
Yに当てはまるのはc「日比谷焼打ち事件」です。日露戦争の講和条約であるポーツマス条約では、ロシアからの賠償金が得られなかったことなどから、国民の不満が高まりました。1905年、講和条約に反対する国民大会がきっかけとなり、民衆が内務大臣官邸や交番、親政府系の新聞社などを襲撃・放火する暴動(日比谷焼打ち事件)が発生しました。
問3:正解④
<問題要旨>
20世紀初頭の、日本における中国人留学生数の推移を示すグラフと、その背景を説明したメモを関連づけて、各期間の増減を正しく判断する問題です。
<選択肢>
X(1903~1905年頃):メモには、清政府が日本への留学生を優遇する政策をとったことや、日本で短期養成の学校が設立されたことが記されています 。これらは留学生の増加要因であり、グラフの傾向とも一致します。よってXは「増加」です。
Y(1905~1907年頃):メモには、1905年末に日本政府が留学生の受け入れ制限を強化し、清政府も留学に条件を設けた結果、留学熱が「沈静化」したとあります 。これは留学生の減少要因です。よってYは「減少」です。
Z(1911~1912年頃):メモには、1911年に辛亥革命が起こると、留学生が続々と帰国したとあります 。グラフでもこの時期に急激な減少が見られます。よってZは「減少」です。
以上のことから、X増加・Y減少・Z減少の組合せが正しいと判断できます。
問4:正解①
<問題要旨>
第一次世界大戦に日本が参戦した際の、その口実(理由)と具体的な軍事行動についての知識を問う問題です。
<選択肢>
ア:日本が第一次世界大戦に参戦する名目としたのは「日英同盟」です 。同盟国であるイギリスからの要請を口実に、日本は連合国側としてドイツに宣戦布告しました。
イ:参戦後、日本軍は、中国におけるドイツの租借地であった山東半島の「青島(チンタオ)」と、その背後にある膠州湾鉄道を占領しました 。また、太平洋のドイツ領南洋諸島も占領しました。
したがって、アに「日英同盟」、イに「青島」が入る組合せが正しくなります。
問5:正解②
<問題要旨>
第一次世界大戦後から1920年代にかけての、日本の主要な外交上の出来事を、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
I:国際連盟は、第一次世界大戦後の1920年に正式に発足し、日本はイギリス、フランス、イタリアと共に常任理事国となりました。
III:シベリア出兵などで断絶していたソ連との国交は、1925年の日ソ基本条約の調印によって樹立されました。
II:対中国強硬外交(東方会議の開催、山東出兵など)で知られる田中義一内閣が成立したのは、1927年です。
したがって、発生した年代の古い順に並べると、I(1920年)→ III(1925年)→ II(1927年)となります。
問6:正解②
<問題要旨>
日本統治下の台湾と朝鮮の状況について、史料(台湾議会設置請願理由書)と表(朝鮮総督一覧)から読み取れる内容を正しく判断する問題です。
<選択肢>
a【正】
史料1に「大正十(1921)年春帝国議会に第一回台湾民選議会設置請願をして以来」とある通り 、台湾での議会設置運動は1920年代に行われました。これは、日本国内で普通選挙を求める運動(普選運動)が高揚した時期と重なります。
b【誤】
史料1は「台湾民選議会設置請願」の理由書です。「請願」しているということは、その時点ではまだ台湾に民選議会は存在せず、その設置を求めている段階であることを示しています。
c【誤】
ワシントン海軍軍縮条約の首席全権は、海軍大臣であった加藤友三郎です。表に名前のある斎藤実は、このとき朝鮮総督を務めていました。
d【正】
表に記載されている人物のうち、寺内正毅、斎藤実、宇垣一成、小磯国昭、阿部信行の5名は、朝鮮総督と内閣総リ大臣の両方を経験しています。よって、「複数いる」という記述は正しいです。
問7:正解④
<問題要旨>
明治末期から昭和初期にかけての、日本における中国料理の受容のされ方について、複数の史料を読み解き、その内容と合致しない、誤った記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
史料2(1907年)には、日清戦争以降に生まれた中国への軽侮の念が、本来日本人の口に合うはずの中国料理の普及を妨げている、という趣旨の記述があります 。
②【正】
史料2(1907年)は、西洋文化を無条件に良いものとする風潮の中で、洋食が普及し始めているのに対し、中国料理はそうなっていない、と述べています 。
③【正】
史料3(1922年)には、油の強さを控えめにするなど、「調理を日本人向きに加減しました」と書かれており 、日本人の味覚に合わせる工夫がなされていたことがわかります。
④【誤】
史料4(1932年)は、満州事変後の日中関係が悪化する中でも、「美味いものは美味いと見えて、東京市内に九百余軒の支那料理店がある」と記しています 。これは、中国料理が禁じられるどころか、庶民に広く受け入れられていたことを示しており、選択肢の記述は史料の内容と明らかに矛盾します。
第4問
問1:正解④
<問題要旨>
明治期の基幹産業であった製糸業と紡績業の発展を支えた、重要な技術と中心人物に関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
ア:官営の富岡製糸場に導入されたのは、フランスから輸入した蒸気機関を動力とする「器械製糸」の技術であり、日本の製糸業の近代化と大量生産を可能にしました 。
イ:第一国立銀行を設立し、蒸気機関を用いた大規模工場である大阪紡績会社を創設して、日本の紡績業の発展の基礎を築いた人物は、「近代日本資本主義の父」とも称される「渋沢栄一」です 。
したがって、アに「器械製糸」、イに「渋沢栄一」が入る組合せが正しくなります。
問2:正解⑤
<問題要旨>
明治期の日本の鉄道網の発達過程における、官設鉄道と私設鉄道に関する主要な出来事を、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
III:日本初の本格的な私鉄である日本鉄道会社(上野~青森間などを建設)は、華族などの出資により1881年に設立されました 。
I:日本の大動脈である官営の東海道線(新橋~神戸間)が全通したのは、1889年です 。
II:日露戦争で獲得した利権を基に、南満州(中国東北部)の鉄道経営などを行う半官半民の国策会社、南満州鉄道株式会社(満鉄)が設立されたのは、1906年です 。
したがって、設立・全通した年代の古い順に並べると、III(1881年)→ I(1889年)→ II(1906年)となります。
問3:正解②
<問題要旨>
1920年代末から30年代初頭にかけての、工場の動力源の変化(電化)がもたらした効果と、当時の耐久消費財の普及状況について、史料の読解と歴史知識を基に判断する問題です。
<選択-肢>
X【正】
史料1には、工場の電化によって「事業者は自らの生産能率を高め」、市民は石炭を燃やすことで生じる「煤煙から逃れて非常な便宜を得ている」と明記されています 。
Y【誤】
史料1が書かれた1931年(昭和6年)当時、ラジオや電灯は都市部で普及し始めていましたが、「三種の神器」と呼ばれたテレビ、電気洗濯機、電気冷蔵庫が一般家庭に広く普及するのは、戦後の高度経済成長期である1950年代後半以降のことです。したがって、この時期にこれらの家電が普及したという記述は誤りです。
問4:正解③
<問題要旨>
1900年代から1930年代にかけての日本の鋼材の生産・輸出入量を示すグラフを読み取り、その変動の背景に関する記述の中から、誤っているものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
グラフ全体を通じて、生産量(黒い棒)は輸出量(白い棒)をはるかに上回っており、生産された鋼材の多くは国内で消費されたと考えられます 。
②【正】
1900年代から1910年代にかけて生産量は著しく増加しています 。この背景には、日露戦争後の軍備拡張に加え、造船奨励法などによる海運・造船業の発展があり、鋼材の需要が大きく伸びたことがあります。
③【誤】
1910年代から1920年代にかけて輸入量が増加しています 。これは第一次世界大戦後の反動不況による生産の停滞などが原因です。日本が金本位制に復帰(金解禁)したのは1930年で、この政策はデフレを深刻化させ、むしろ輸入を抑制する方向に働きました。したがって、輸入増加の理由として金本位制への復帰を挙げるのは、時期も経済効果も誤りです。
④【正】
1920年代から1930年代にかけて生産量は爆発的に増加しています 。これは、満州事変(1931年)以降の軍国主義化の中で、軍需生産が拡大し、鉄鋼需要が急増したためです。
問5:正解②
<問題要旨>
史料として提示された田中正造の天皇への直訴状の内容と、それをまとめたメモを比較し、メモの記述のどこが史料を正しく、あるいは誤って解釈しているかを判断する問題です。正確な史料読解力が求められます。
<選択肢>
史料とメモを比較検討します。
・<鉱毒の原因>のメモ:史料にある「毒水」と「山林を乱伐し(中略)洪水」という二つの原因を正しくまとめています。
・<鉱毒の被害>のメモ:史料では「魚族は死に、田園は荒廃し、数十万の人民は財産や職を失い(中略)流離せり」と、既に甚大かつ深刻な被害が発生していると述べられています。しかし、メモでは「このままでは近隣住民の生活への影響が生じるであろうと予想している」と、まだ被害が発生しておらず、将来を予測しているかのような記述になっています。これは、史料が示す被害の深刻さと現状を正しく反映しておらず、明確な誤りです。
・<責任の所在>のメモ:史料にある「政府当局が(中略)悲境に陥らしめて省みるなき」という、政府の無策を批判し責任を追及する内容を正しくまとめています。
以上のことから、
① メモの<鉱毒の原因>は史料を正しくまとめているため、この選択肢は誤りです。
② メモの<鉱毒の被害>は史料を誤ってまとめているため、この選択肢が正しい記述です。
③ メモの<責任の所在>は史料を正しくまとめているため、この選択肢は誤りです。
④ メモ全体としては<鉱毒の被害>の箇所が誤っているため、「正しくまとめている」とは言えず、この選択肢は誤りです。
問6:正解②
<問題要旨>
日本の高度経済成長期に深刻化した公害問題と、それに対応する形で誕生した「革新自治体」に関する具体的な知識を、新聞記事風の文章から判断する問題です。
<選択肢>
X:文章中の「四大公害訴訟」「石油(石油化学)コンビナートの排煙による大気汚染」「複数企業を相手にしている」という特徴は、三重県四日市市で発生した「四日市ぜんそく」に関する訴訟のものです。したがって、該当する語句はa「三重県」です。
Y:文章は、革新知事として有名な美濃部亮吉氏が、沖縄の本土復帰(1972年)を前に、琉球政府主席(本土の知事に相当)の屋良朝苗氏と会談している場面です。美濃部亮吉は「東京都」の知事を務め、福祉政策や公害対策を進めた革新都政の象徴的な人物です。したがって、該当する語句はd「東京都」です。
以上のことから、X-a、Y-dの組合せが正しくなります。
問7:正解①
<問題要旨>
第4問全体のテーマである「近現代の工業化と環境問題」について、プリントA・Bの内容を総合的に理解し、その内容と合致しない、誤った記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
プリントAには、明治初期の製糸業について「熱源として多くの薪や木炭が必要とされたため、木が乱伐されることもあった」と明記されています。薪や木炭を得るための森林伐採(乱伐)は、自然環境の破壊にあたります。したがって、製糸業が「自然環境と調和しながら発展した」という記述は、プリントの内容と矛盾しており、明確に誤りです。
②【正】
プリントAでは紡績工場から、プリントBでは鉄鋼業などの重工業の工場から煙が排出され、煙害が発生したことが述べられており、正しい記述です。
③【正】
プリントBには「高度経済成長期には、水や大気の汚染が社会問題化し」とあり、これを受けて公害対策を求める住民運動が各地で広がり、公害対策基本法(1967年)の制定などにつながりました。正しい記述です。
④【正】
プリントBや問6の内容の通り、1960年代後半から70年代前半にかけて、公害対策や福祉の充実を公約に掲げる革新系の知事や市長が、東京、大阪、横浜などで次々と誕生しました。正しい記述です。
第5問
問1:正解①
<問題要旨>
アジア・太平洋戦争下の総力戦体制において、それまで学業に専念していた学生・生徒・児童が、どのように戦争へ動員されていったかについての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
学生・生徒を軍需工場などへ動員すること(勤労動員)は、1944年の学徒勤労令などによって本格化しました。国民徴用令は、一般国民を対象として1939年(昭和14年)に制定されたものであり、学生動員のために「新たに制定された」わけではありません。したがって、この記述は誤りです。
②【正】
戦局が悪化し兵力不足が深刻になると、政府は1943年(昭和18年)、それまで徴兵を猶予されていた大学などの文科系学生も徴兵の対象としました。これを学徒出陣(学徒動員)といいます。
③【正】
1944年(昭和19年)にサイパン島が陥落し、アメリカ軍による本土空襲が本格化すると、政府は都市部の国民学校初等科の児童を、空襲の危険が少ない地方へ集団で移住させる「学童疎開」を実施しました。
④【正】
戦争の長期化は深刻な労働力不足をもたらし、男性に代わって女性も軍需工場などでの労働力として期待されるようになりました。未婚の女性が工場などに動員された女子勤労挺身隊などがその例で、メモにある通り、女学生であった田辺聖子も動員の対象となりました。
問2:正解⑤
<問題要旨>
アジア・太平洋戦争の開戦前から末期にかけての、日本の戦局に大きな影響を与えた出来事を、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
III:ノモンハン事件は、満州国とモンゴルの国境線をめぐり、日本の関東軍とソ連・モンゴル軍が衝突した大規模な武力紛争で、第二次世界大戦前の1939年(昭和14年)に発生しました。
I:マリアナ諸島のサイパン島が陥落したのは1944年(昭和19年)7月です。これにより、アメリカの戦略爆撃機B-29の基地が日本本土に近づき、本土への大規模な空襲が本格化する転換点となりました。
II:ヤルタ会談は、1945年(昭和20年)2月にアメリカ・イギリス・ソ連の首脳(ルーズベルト・チャーチル・スターリン)によって行われ、ドイツ降伏後のソ連の対日参戦が秘密裏に決定されました。
したがって、発生した年代の古い順に並べると、III(1939年)→ I(1944年)→ II(1945年)となります。この順序に合致する選択肢は5です。
問3:正解③
<問題要旨>
1995年(平成7年)1月17日に発生した阪神・淡路大震災と、その当時の日本の政治状況に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
X【誤】
阪神・淡路大震災では、原子力発電所の大きな被害は報告されていません。原子力発電所の事故とその安全性、耐震性などが社会的に極めて大きな問題となったのは、2011年(平成23年)の東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故が直接のきっかけです。
Y【正】
阪神・淡路大震災が発生した1995年当時の内閣は、日本社会党の村山富市を首相とし、自由民主党、新党さきがけの3党が連立を組んだ「村山富市内閣」でした。
問4:正解④
<問題要旨>
日本の近代文学史、映画史を代表する人物とその作風や作品に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
Xに当てはまるのはb「谷崎潤一郎」です。谷崎潤一郎は、美のためには道徳をも無視するような、感覚的な美の世界を追求する「耽美派」を代表する作家として知られています。
Yに当てはまるのはd「黒澤(黒沢)明」です。黒澤明が監督した映画『羅生門』(1950年)は、1951年のヴェネツィア国際映画祭で最高賞である金獅子賞を受賞し、日本映画のレベルの高さを世界に知らしめる画期的な出来事となりました。
したがって、X-b、Y-dの組合せが正しくなります。
問5:正解①
<問題要旨>
史料として提示された田辺聖子の日記の内容から、敗戦直後の占領期の重要人物と、当時の文学の潮流(無頼派)に関する知識を判断する問題です。
<選択肢>
ア:1945年9月9日の日記 にある、日本に進駐してきた連合国軍を率いる元帥とは、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)の最高司令官であった「マッカーサー」です。
イ:1946年12月23日の日記 にある、織田作之助や坂口安吾と並び、戦後の虚無的・退廃的な風潮の中で活躍したデカダン(無頼派)文学の代表的作家は「太宰治」です。小林多喜二は戦前のプロレタリア文学の作家で、1933年に亡くなっています。
したがって、アに「マッカーサー」、イに「太宰治」が入る組合せが正しくなります。
問6:正解③
<問題要旨>
敗戦直後に組閣された幣原喜重郎内閣(1945年10月~1946年5月)の時期に行われた、占領下の民主化改革についての正確な知識を問う問題です。
<選択肢>
a【誤】
GHQの人権指令(治安維持法の廃止、特別高等警察の廃止など)の実行に消極的な姿勢を示して総辞職したのは、幣原内閣の一つ前に組閣された東久邇宮稔彦王内閣です。幣原内閣は、この指令を実行しました。
b【正】
GHQは幣原首相に対し、婦人解放、労働組合の結成奨励、教育の民主化などを含む「五大改革指令」を発しました。幣原内閣は、この指令に基づいて戦後改革を進めました。
c【正】
深刻なインフレーションを抑制するため、預金の引き出しを制限し(預金封鎖)、旧紙幣を無効にして新円に切り替える金融緊急措置令が発せられたのは1946年2月であり、幣原内閣の時期の出来事です。
d【誤】
幣原内閣のもとで松本烝治を委員長とする憲法問題調査委員会が憲法改正案を作成しましたが、GHQはこれを拒否しました。現在につながる憲法改正案の作成と国会提出・可決は、次の第一次吉田茂内閣の時期に進められました。
問7:正解③
<問題要旨>
作家個人の日記という史料から、戦時中から敗戦直後にかけての、個人の思想や感情、生活の実態を読み取り、歴史的な社会状況と照らし合わせて内容を解釈する問題です。
<選択肢>
①【誤】
1945年5月23日の日記では、ドイツが無条件降伏した後も、「日本はあくまで一億が玉砕するまで戦うであろう」「私も(中略)人には遅れを取らぬつもりだ」と記しており 、戦争の継続と徹底抗戦の意思がうかがえます。
②【誤】
戦後の1945年11月や1946年4月の日記には、「家の経済状態は暗黒だ」 、「収入のない私の家では、苦しいことこの上なし」とあり 、敗戦後も経済的な苦境が続いていたことがわかります。
③【正】
1946年4月10日の日記に出てくる投票は 、日本国憲法の公布に先立って行われた衆議院議員総選挙です。この選挙では選挙法が改正され、初めて満20歳以上の男女に選挙権が与えられました。したがって、作者の母にとって、この選挙が「生まれて初めて投票権を得た総選挙」であったというのは正しい記述です。
④【誤】
1946年12月23日の日記で、織田作之助や坂口安吾らのデカダン(無頼派)文学の流行を「悲しむべきことだ」と記しており 、好意的・共感的に捉えているわけではなく、むしろ批判的に見ています。