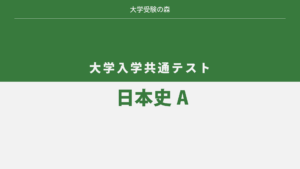解答
解説
第1問
問1:正解③
<問題要旨>
明治十四年の政変と、それに伴う自由民権運動の動向についての理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
X:明治十四年の政変で参議を罷免されたのは、急進的な憲法制定を主張し、政府内で伊藤博文らと対立した大隈重信です。板垣退助は、征韓論をめぐる対立(明治六年の政変)で下野しています。
Y:1881年(明治14年)、国会開設の勅諭が出されると、国会期成同盟のメンバーを中心に自由党が結成されました。これは明治十四年の政変と同じ年の出来事です。
したがって、Xが誤りでYが正しい記述です。
②【誤】
Xが誤りであるため、この選択肢は誤りです。
③【正】
Xが誤り、Yが正しい記述であるため、この組合せが正解です。
④【誤】
Yが正しい記述であるため、この選択肢は誤りです。
問2:正解③
<問題要旨>
史料から金子堅太郎の議事堂建築に関する考えを読み取り、金子に関する知識と結びつけて正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
aは誤りです。史料1で金子は「如何なる国の議院を模範として取るが宜しいというものは無い」と述べ、建築法は「日本で一種特別の建築法」を主張しています。装飾については「英国の精神を模倣して」「日本の歴史をば装飾に適用したい」と述べており、イギリスの建築方法をそのまま用いるとは考えていません。
②【誤】
aとdがともに誤りです。dの「コンドルに師事し、東京駅などの建築物を設計した」人物は辰野金吾です。金子堅太郎は政治家・官僚であり、建築家ではありません。
③【正】
b:史料2で金子は、英国議院の装飾が議員に「国家に忠愛ならしむるの精神に出でざるはなし」と、国家への忠誠心を起こさせると述べており、正しい記述です。
c:金子堅太郎は、伊藤博文や井上毅らとともに、ドイツ人顧問ロエスレルの助言を受けながら大日本帝国憲法の草案作成に深く関わりました。正しい記述です。
したがって、bとcの組合せが正解です。
④【誤】
dが誤りであるため、この選択肢は誤りです。
問3:正解②
<問題要旨>
初期の衆議院議員の職業構成を示した表を読み取り、当時の政治状況と関連付けて解釈する問題です。
<選択肢>
①【誤】
Yが誤りです。政府による激しい選挙干渉が行われたのは第2回総選挙(1892年)ですが、その対象は政府に批判的な民党(自由党・改進党など)でした。吏党は政府寄りの立場をとったため、選挙干渉の直接の対象ではありません。表で「官吏」が激減しているのは、民党の勢力が強く、有権者の支持を得られなかった結果と考えられます。
②【正】
X:表を見ると、第1回から第3回の総選挙まで一貫して「地主及び農業」を職業とする議員が最多であることがわかります。当時の選挙権は高額の直接国税納税者に限られており、地主が多くを占めていました。地主は地租を主な収入源としていたため、彼らを支持基盤とする民党は、地租の軽減(民力休養)をスローガンに掲げて政府と対立しました。したがって、この記述は正しいと考えられます。
Y:上記の通り、吏党が政府の選挙干渉を受けたという記述は誤りです。
したがって、Xが正しくYが誤りであるこの組合せが正解です。
③【誤】
Xが正しい記述であるため、この選択肢は誤りです。
④【誤】
Xが正しく、Yが誤りであるため、この選択肢は誤りです。
問4:正解④
<問題要旨>
日清戦争とその後の国際関係についての理解を問う問題です。誤った記述を選びます。
<選択肢>
①【正】
日清戦争が始まると、それまで政府と対立していた自由党や改進党などの民党も、挙国一致の立場から政府に協力する姿勢に転じました。
②【正】
日清戦争の戦場は朝鮮半島や中国東北部に及びました。特に朝鮮半島は主要な戦場の一つとなり、朝鮮民衆の生活に甚大な被害と影響を与えました。
③【正】
下関条約で日本が獲得した遼東半島について、ロシア・ドイツ・フランスが清への返還を勧告したのが三国干渉です。これにより、日本国内ではロシアに対する敵愾心(「臥薪嘗胆」)が高まりました。
④【誤】
日清戦争後、列強による中国分割が進みますが、アメリカは特定の勢力範囲(租借地や鉄道敷設権など)を設定するのではなく、中国市場への機会均等と領土保全を求める門戸開放宣言(1899年)を発表しました。中国で勢力範囲を設定したのは、ロシア、ドイツ、イギリス、フランスなどです。したがって、この記述は誤りです。
問5:正解②
<問題要旨>
第一次・第二次護憲運動のスローガンと、運動の対象となった内閣についての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
イが誤りです。第二次護憲運動(1924年)が批判の対象としたのは、貴族院を基盤として成立した超然内閣である清浦奎吾内閣です。桂太郎内閣は第一次護憲運動(1912-13年)で退陣しました。
②【正】
ア:第一次護憲運動は、長州閥の桂太郎が三たび首相の座についたことに対し、「閥族打破・憲政擁護」をスローガンに掲げて展開されました。
イ:第二次護憲運動は、政党内閣の慣例を無視して成立した清浦奎吾内閣に対し、護憲三派(憲政会・政友会・革新倶楽部)が中心となって倒閣運動を展開したものです。
したがって、この組合せが正解です。
③【誤】
アが誤りです。「民力休養」は初期議会で民党が掲げたスローガンであり、第一次護憲運動の主要スローガンではありません。
④【誤】
アが誤りです。
問6:正解④
<問題要旨>
昭和戦前期における軍部の台頭を示す出来事を、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
I:軍部大臣現役武官制は、二・二六事件後の1936年、広田弘毅内閣のときに復活しました。これにより、軍部の同意がなければ組閣できないようになり、軍部の政治的発言力が一層強まりました。
II:ロンドン海軍軍縮条約(1930年)の調印をめぐり、野党や軍令部(海軍)が、補助艦の保有量を決定したのは内閣であり、天皇の統帥権を干犯するものであると政府(浜口雄幸内閣)を激しく攻撃しました(統帥権干犯問題)。
III:1931年、関東軍が奉天(現在の瀋陽)郊外の柳条湖で南満州鉄道の線路を爆破し、これを中国軍の仕業として軍事行動を開始しました。これが満州事変の始まりです。
年代順に並べると、II (1930年) → III (1931年) → I (1936年)となります。したがって、④が正解です。
問7:正解①
<問題要旨>
1960年の安保闘争における、条約改定に対する様々な立場を史料から読み解く問題です。
<選択肢>
①【正】
a:史料3で著者は、「『日本の自主性向上の面もあるのだから、安保改定に全面的に反対するのは子供じみている。』という『大人』の条件闘争への進言」があったと述べています。これは、著者が「全面的に反対」する立場であるのに対し、「進歩的知識人」が条約の一部の側面を評価しつつ条件付きで交渉すべきだという立場(部分的に賛成し、交渉でより良い条件を引き出すべきだという立場)であったことを示しています。したがって、この記述は正しいと解釈できます。
c:史料4は省略されていますが、新安保条約に反対する一般的な論理として、条約によって日本がアメリカの世界戦略に組み込まれ、中国やソ連との対立に巻き込まれ、攻撃の基地となることへの強い懸念がありました。したがって、この記述は安保反対運動の主張として妥当であり、正しいと考えられます。
よって、aとcの組合せが正解です。
②【誤】
dが誤りです。新安保条約は、日本の防衛における自衛隊と米軍の役割を定め、日米共同防衛を明確にするものでした。反対派は、これによって日本の軍備が強化され、戦争に巻き込まれる危険が高まると主張しました。「自衛隊の強化が阻害される」という危機感は、むしろ改憲・再軍備を主張する立場の論理であり、安保反対の論理とは逆です。
③【誤】
bが誤りです。史料3から、「進歩的知識人」は「全面的に賛成」ではなく、「条件闘争」の立場、つまり部分的な評価と修正を求める立場であったことがわかります。
④【誤】
bとdがともに誤りです。
第2問
問1:正解③
<問題要旨>
明治初期の政治において重要な役割を果たした藩と人物についての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
Yに該当する人物は後藤象二郎(c)であり、副島種臣(d)ではありません。副島種臣は佐賀藩出身で、征韓論を主張した人物の一人です。
②【誤】
Xに該当する藩は長州藩(b)であり、薩摩藩(a)ではありません。薩摩藩は薩英戦争でイギリスと交戦しましたが、文中の「幕府の命令に応じて」という点では、下関で外国船を砲撃した長州藩がより適切です。
③【正】
X:幕末期、朝廷を動かして幕府に攘夷実行を迫り、実際に下関海峡を通過する外国船を砲撃したのは長州藩(b)です。
Y:土佐藩出身の後藤象二郎(c)は、前藩主の山内豊信を通して、将軍徳川慶喜に大政奉還を建白しました。その後、明治政府に参加し、民選議院設立建白書にも名を連ねるなど、自由民権運動にも関わりました。
したがって、この組合せが正解です。
④【誤】
Xに該当するのは長州藩(b)です。
問2:正解②
<問題要旨>
廃藩置県(1871年)から沖縄県設置(1879年)までの間に起こった出来事を、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
I:朝鮮への使節派遣をめぐる征韓論政変が起こり、西郷隆盛や板垣退助らが下野したのは1873年です。
II:旧士族の不満が爆発し、熊本の神風連の乱、福岡の秋月の乱、山口の萩の乱といった不平士族の反乱が相次いで起こったのは1876年です。
III:台湾に漂着した琉球の島民が殺害された事件を口実に、政府が台湾に出兵したのは1874年です。
これらの出来事を年代順に並べると、I (1873年) → III (1874年) → II (1876年)となります。したがって、②が正解です。
問3:正解①
<問題要旨>
木戸孝允の手紙とイラストから、版籍奉還前後の彼の国家構想を読み取り、木戸に関する知識とあわせて正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【正】
X:史料1で木戸は、現状を「各々自分の山を高くいたし」ている状態(図1)と批判し、これでは外国に対抗できないと述べています。そして、目指すべき姿として、朝廷を中心に各藩が一体となる(図2)ことで、「五州強大(世界の強国)何ぞ終に恐るるに足らん」と、強い国家を築けると主張しています。これは、中央集権国家の必要性を説いたものと解釈でき、記述は正しいです。
Y:木戸孝允は、板垣退助や大久保利通らとの大阪会議(1875年)に参加しました。この会議の結果、立憲政体を段階的に進める「漸次立憲政体樹立の詔」が出され、立法諮問機関としての元老院、最高裁判所としての大審院などが設置されました。記述は正しいです。
したがって、XとYがともに正しく、この組合せが正解です。
②【誤】
Yが正しい記述であるため、この選択肢は誤りです。
③【誤】
Xが正しい記述であるため、この選択肢は誤りです。
④【誤】
X、Yともに正しい記述であるため、この選択肢は誤りです。
問4:正解④
<問題要旨>
明治政府による琉球処分をめぐる、政府の通達(史料2)と琉球藩の願い(史料3)の内容を正確に読み解く問題です。
<選択肢>
①【誤】
aが誤りです。史料2は「今より差し止められ候事」と、明治新政府が清への朝貢などを禁止する通達であり、江戸幕府の方針ではありません。
②【誤】
aとcが誤りです。cでは、琉球藩は「天皇陛下御大徳ますます相顕れ」るために朝貢継続を願ったのではなく、「支那との続も信義取り失わざる様」にと、清との信義関係を失わないために継続を願っています。
③【誤】
cが誤りであるため、この選択肢は誤りです。
④【正】
b:史料2には「藩王代替わりの節、従前清国より冊封受け来り候趣に候えども、今より差し止められ候事」とあり、明治新政府が清からの冊封を止めるよう命じていることがわかります。正しい記述です。
d:史料3で琉球藩は、「往古より両属の儀は各国明知するところにて」と、琉球が日本と清の両方に所属してきた歴史は諸外国も知っていることであり、「弊藩支那との続も信義取り失わざる様」に、つまり清との朝貢関係を続けさせてほしいと訴えています。正しい記述です。
したがって、bとdの組合せが正解です。
第3問
問1:正解④
<問題要旨>
明治初期の税制改革と教育制度に関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
アが誤りです。税を米で納める物納から、お金で納める金納へと変更したのは「地租改正条例」です。「新貨条例」は、「円・銭・厘」を単位とする新しい貨幣制度を定めたものです。
②【誤】
アが誤りです。
③【誤】
イが誤りです。「6歳以上の男女すべてに小学校教育を受けさせることを義務づけた」のは、1872年に制定された「学制」です。「教育令」は、学制が画一的で実情に合わないという批判を受けて、1879年に制定されたもので、就学義務を緩和しました。
④【正】
ア:「地租改正条例」(1873年)により、土地の所有者に地券を発行し、地価の3%を地租として現金で納めさせることが定められました。
イ:「学制」(1872年)は、フランスの学区制にならい、全国を学区に分けて小学校・中学校・大学校を設置し、身分にかかわらず6歳以上のすべての男女が小学校教育を受けることを目指した、日本初の近代的な学校制度です。
したがって、この組合せが正解です。
問2:正解③
<問題要旨>
明治時代の産業発展や都市化に関する記述の中から、誤っているものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
福岡県の三池炭鉱は、官営事業として開発が進められ、後に三井に払い下げられました。三池は八幡製鉄所とともに、日本の近代化を支える筑豊工業地帯の中核をなしました。
②【正】
東京の銀座通りには、1872年の大火の後、ジョサイア・コンドルの弟子であるトーマス・ウォートルスの設計により、西洋風のレンガ造りの街並みが建設されました。ガス灯も設置され、文明開化の象徴となりました。
③【誤】
北海道の開拓を管轄する官庁として「開拓使」が置かれたのは、1869年(明治2年)です。幕末ではありません。
④【正】
官営八幡製鉄所は、日清戦争で得た賠償金の一部を充てて、1901年に福岡県八幡村で操業を開始しました。日本の重工業の基礎を築きました。
問3:正解⑤
<問題要旨>
大蔵卿松方正義によるデフレ政策(松方財政)の時期に起こった出来事を、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
I:秩父事件は、松方デフレによる農産物価格の下落や重税に苦しんだ埼玉県秩父地方の農民たちが、高利貸しや役所を襲撃した事件で、1884年に起こりました。
II:三大事件建白運動は、地租軽減、言論の自由、条約改正の三つを求めて、片岡健吉らが政府に建白書を提出しようとした運動で、1887年に高まりを見せました。
III:日本銀行は、西南戦争によるインフレーションを収束させ、近代的な通貨・金融制度を確立するため、松方正義の主導で1882年に設立された中央銀行です。
これらの出来事を年代順に並べると、III (1882年) → I (1884年) → II (1887年)となります。したがって、⑤が正解です。
問4:正解①
<問題要旨>
明治時代の貧困問題や労働事情について調査・告発した刊行物と、その内容についての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
X:『職工事情』(a)は、1903年に農商務省が刊行した、工場や鉱山における労働者の過酷な労働実態に関する詳細な公式調査報告書です。
Y:『日本之下層社会』(c)は、ジャーナリストの横山源之助が、1899年に刊行したルポルタージュです。彼は自ら都市や農村を歩き、貧民の生活実態を克明に記録しました。
したがって、この組合せが正解です。
②【誤】
Yに該当するのは『日本之下層社会』(c)であり、『太陽のない街』(d)ではありません。『太陽のない街』は、プロレタリア作家の徳永直が1929年に発表した小説です。
③【誤】
Xに該当するのは『職工事情』(a)であり、『国民之友』(b)ではありません。『国民之友』は、徳富蘇峰が創刊した総合雑誌です。
④【誤】
X、Yともに該当する語句が誤っています。
問5:正解③
<問題要旨>
庶民の金融機関としての質屋の役割について述べた史料を読み解き、その内容を正しく理解できているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
Xが誤りです。史料には「貯蓄銀行はもっぱら資本家の資金調達機関」「庶民にとって頼りになる金融機関ということは出来ない」と明記されており、庶民にとっては質屋の方が身近で利用しやすい金融機関であったことがわかります。
②【誤】
Xが誤りであるため、この選択肢は誤りです。
③【正】
X:上記の通り、庶民にとって貯蓄銀行は利用しにくかったとされており、記述は誤りです。
Y:史料の後半に「近来不況の永続深刻化とともに」「質屋を甚だしき苦境に陥れた」とあります。この史料の背景には昭和恐慌があり、不況によって庶民の生活が苦しくなり、質草となるような物さえもなくなり、質屋の経営も厳しくなったと推測できます。記述は正しいです。
したがって、Xが誤りでYが正しいこの組合せが正解です。
④【誤】
Yが正しい記述であるため、この選択肢は誤りです。
問6:正解②
<問題要旨>
質屋の仕組みを示した図と、実際の取引記録である表を照らし合わせ、会話文の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
オミさんの発言が誤りです。
②【正】
ヤス:表の質物には「着物(普段着)」や「大豆」など、庶民の生活に密着した品物が含まれており、質屋が身近な存在であったことがうかがえます。正しい発言です。
コウ:表を見ると、利子を払っていないAさんとCさんは質物が「流質」となっていますが、利子を払っているBさんは質物を「受戻」できています。正しい発言です。
オミ:オミさんは「貸金額は売払額より大きくなっている」と発言していますが、これは誤りです。質屋が利益を出すには、売払額が貸金額(+利子・経費)より大きくなる必要があります。実際に表のAさんの例では、貸金額1円50銭に対し、売払額は1円80銭となっており、「売払額」の方が大きくなっています。オミさんの発言は事実とも、商売の論理とも反しています。
したがって、ヤスさんとコウさんのみ正しいので、この選択肢が正解です。
③【誤】
ヤスさんの発言は正しいです。
④【誤】
コウさんの発言は正しいですが、オミさんの発言は誤りです。
問7:正解②
<問題要旨>
近代日本の民衆生活や社会政策に関する出来事について、正しい記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
大衆娯楽雑誌『キング』が創刊されたのは1925年(大正14年)であり、1890年代ではありません。
②【正】
労働者の保護を目的とした工場法は、1911年(明治44年)に制定され、1916年(大正5年)に施行されました。1910年代の出来事として正しい記述です。
③【誤】
農民を満州へ移民させる国策(満蒙開拓移民)が本格的に推進されたのは、満州事変(1931年)以降の1930年代です。
④【誤】
関東大震災が発生したのは1923年(大正12年)であり、1930年代ではありません。
第4問
問1:正解④
<問題要旨>
大正デモクラシー期の政治・社会運動に関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
aが誤りです。第二次護憲運動後の総選挙で護憲三派が勝利し、首相となったのは憲政会総裁の加藤高明です。
②【誤】
aとcが誤りです。cの植木枝盛らによる私擬憲法の起草は、自由民権運動が盛んだった1880年代の出来事です。
③【誤】
cが誤りです。
④【正】
b:吉野作造は、総合雑誌『中央公論』などで民本主義を提唱しました。これは、主権の所在は問わないものの、政治の運用は民衆の意向に基づいて、民衆の幸福のために行われるべきだとする思想で、大正デモクラシーの理論的支柱となりました。正しい記述です。
d:平塚らいてう、市川房枝らは、1920年に新婦人協会を設立し、女性の政治活動の自由を求める運動(治安警察法第5条改正運動)や、婦人参政権の実現を目指しました。大正期の女性解放運動の代表的な例です。正しい記述です。
したがって、bとdの組合せが正解です。
問2:正解⑤
<問題要旨>
近現代における社会主義運動の弾圧や組織化に関する出来事を、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
I:満州事変後、1930年代に入ると、治安維持法による社会主義者への弾圧が強化され、獄中で思想を放棄する「転向」者が相次ぎました。
II:日本共産党の幹部が公職から追放され、民間企業でも共産主義者が解雇された「レッド=パージ」は、戦後、占領下の1949年から1950年にかけて、GHQの指令のもとで行われました。
III:片山潜や幸徳秋水らは、日本で最初の社会主義政党である社会民主党を1901年に結成しましたが、治安警察法により即日解散を命じられました。
これらの出来事を年代順に並べると、III (1901年) → I (1930年代) → II (1949-50年)となります。したがって、⑤が正解です。
問3:正解①
<問題要旨>
ジャーナリスト石橋湛山の社説を読み、彼の思想(小日本主義)と、史料が書かれた時期の国際情勢を理解する問題です。
<選択肢>
①【正】
X:史料1で石橋湛山は、軍縮会議を成功させるためには「朝鮮・台湾・満州を棄てる、支那から手を引く」といった、すべての植民地や勢力圏を放棄する覚悟が必要だと主張しています。これは彼の持論である小日本主義の考え方であり、記述は正しいです。
Y:史料1が発表されたのは1921年7月です。日本がロシア革命への干渉を目的としてシベリアに出兵したのは1918年から1922年までなので、この時点ではまだ日本はシベリアに出兵中でした。記述は正しいです。
したがって、XとYがともに正しく、この組合せが正解です。
②【誤】
Yが正しい記述であるため、この選択肢は誤りです。
③【誤】
Xが正しい記述であるため、この選択肢は誤りです。
④【誤】
X、Yともに正しい記述であるため、この選択肢は誤りです。
問4:正解①
<問題要旨>
日中戦争から太平洋戦争の終結に至るまでの時期の、重要な出来事に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
ア:1940年、日本は日中戦争の早期解決を図るため、元国民党の有力者であった汪兆銘を首班とする親日政権(南京国民政府)を樹立しました。
イ:1945年8月14日にポツダム宣言の受諾を決定し、翌15日に天皇がラジオ放送で国民に終戦を告げた後、9月2日に東京湾上の米戦艦ミズーリ号で、日本政府の全権が降伏文書に調印しました。
したがって、この組合せが正解です。
②【誤】
イが誤りです。
③【誤】
アが誤りです。蔣介石は、汪兆銘政権とは対立し、重慶を拠点に抗日戦争を継続しました。
④【誤】
ア、イともに誤りです。
問5:正解②
<問題要旨>
アジア・太平洋戦争期の日本の政治・戦争指導について、誤っている記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
政府は、この戦争を「欧米の植民地支配からアジアを解放し、日本を盟主とする共存共栄の新たな国際秩序を建設する」ための「大東亜戦争」であるとし、「大東亜共栄圏」の建設をスローガンとして掲げました。
②【誤】
戦争中も帝国議会は、大政翼賛会の推薦候補者がほとんどを占める「翼賛議会」として存続しました。政府の提出する法案や予算を承認する役割を担い、停止されたわけではありません。したがって、この記述は誤りです。
③【正】
1942年6月のミッドウェー海戦で、日本海軍は主力空母4隻を失うという大敗を喫し、これ以降、太平洋における戦いの主導権を失い、戦局は悪化の一途をたどりました。
④【正】
1943年11月、東条英機内閣は、日本の占領下・影響下にあるアジア各国の代表者を東京に集め、大東亜会議を開催し、「大東亜共栄圏」の結束を内外にアピールしました。
問6:正解①
<問題要旨>
戦時中の作家の日記と、彼が読んだ新聞記事を比較し、当時の報道(大本営発表)の実態と、それに対する知識人の認識を読み解く問題です。
<選択肢>
①【正】
a:史料2で高見順は、新聞記事を「気休めの、ごまかしの記事」と断じ、「敵に明らかに押されているのだ。敗けているのだ。なぜそれが率直に書けないのだ」と、戦局が悪化しているにもかかわらず、それを正確に伝えない報道のあり方を厳しく批判しています。正しい記述です。
c:史料3の記事は、ボルネオ島の「タラカン」における戦闘を報じており、「油田地帯にかけて拡大せんとしつつあり」と、油田地帯が戦場になっていることを伝えています。正しい記述です。
したがって、aとcの組合せが正解です。
②【誤】
dが誤りです。史料3は「わが方は」「既に敵兵力の二割弱に当る千五百名を殺傷している」と報じています。これは「日本軍が敵軍の約2割にあたる1500人を殺傷した」という意味であり、「日本軍の兵力量が敵軍より2割少ない」という意味ではありません。
③【誤】
bが誤りです。史料2から、高見順は記事の内容を信じておらず、実際の戦局は「敗けている」と認識していることがわかります。
④【誤】
bとdがともに誤りです。
問7:正解③
<問題要旨>
第二次世界大戦後の出版文化と社会状況に関する記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
Xが誤りです。プロレタリア文学運動と、その機関誌『種蒔く人』の創刊は、1920年代(1921年創刊)の出来事です。
②【誤】
Xが誤りであるため、この選択肢は誤りです。
③【正】
X:上記の通り、プロレタリア文学運動の『種蒔く人』創刊は戦前の出来事であり、誤りです。
Y:1950年代後半からの高度経済成長期には、国民の所得が増え、生活に余裕が生まれる中で、テレビや週刊誌などのマスメディアが急速に発達し、大衆文化が花開きました。週刊誌の発行部数が増加したのもこの時期の特徴です。記述は正しいです。
したがって、Xが誤りでYが正しいこの組合せが正解です。
第5問
問1:正解⑥
<問題要旨>
戦前の二大政党時代から、戦時体制下の政党解散に至るまでの政治の出来事を、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
I:近衛文麿を中心に、挙国一致の新体制を樹立しようとする新体制運動が起こり、1940年に既成の政党(立憲政友会、立憲民政党、社会大衆党など)が次々と解散して大政翼賛会に合流しました。
II:1932年、海軍青年将校らが犬養毅首相を暗殺した五・一五事件により、1924年から続いてきた政党内閣の時代は終わりを告げました。
III:1927年の金融恐慌の際、震災手形の処理をめぐり、台湾銀行への緊急融資案が枢密院に否決されたため、若槻礼次郎内閣(憲政会)は総辞職に追い込まれました。
これらの出来事を年代順に並べると、III (1927年) → II (1932年) → I (1940年)となります。したがって、⑥が正解です。
問2:正解①
<問題要旨>
GHQによる占領政策の内容について、正しい記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
占領当初、GHQは日本に対して厳しい賠償を科す方針でした。しかし、中国での国共内戦の激化や朝鮮半島情勢の緊迫化など冷戦が深刻になると、アメリカは日本を「反共の防波堤」と位置づけ、経済復興を優先する方針に転換しました(占領政策の転換)。その一環として、賠償は大幅に軽減されました。
②【誤】
3%の消費税が導入されたのは、1989年の竹下登内閣のときです。
③【誤】
サンフランシスコ平和条約第11条で、日本は極東国際軍事裁判(東京裁判)などの戦争犯罪に関する裁判を受諾しており、その結果を無効とはしていません。
④【誤】
1949年、GHQの要請で来日した経済顧問ドッジは、深刻なインフレを収束させるため、財政支出を歳入の範囲内に収める「超均衡予算」の編成を日本政府に強く求めました(ドッジ=ライン)。税収を超える財政支出(赤字財政)を勧告したわけではありません。
問3:正解④
<問題要旨>
GHQによる財閥解体と、その後の企業集団の再編成について、史料から読み取れる内容と歴史的知識を組み合わせて判断する問題です。(※説明文が省略されているため、史料1と一般的な歴史知識から判断します)
<選択肢>
①【誤】
cが誤りです。史料1には「戦前の財閥本社に代わって、金融機関と直系主要会社を中心に再編成」とあり、旧財閥本社が復活したわけではないことがわかります。
②【誤】
aとcが誤りです。aは省略された説明文の内容に関するもので判断できませんが、cは史料1から明確に誤りと判断できます。
③【誤】
cが誤りです。
④【正】
b:省略された説明文の内容は不明ですが、GHQによる財閥解体などの経済民主化政策が、世界恐慌期のアメリカで行われたニューディール政策(独占を規制し公正な競争を促す政策)の影響を受けていたことは、歴史的事実として知られています。
d:史料1には、「金融機関と直系主要会社を中心に再編成が進められ」「同系会社内の相互持株比率は戦前の水準に近づいてきた」とあります。これは、銀行などを中心とした新たな企業グループが形成され、そのグループ内で株式を持ち合うことで結束を強めていったことを示しており、記述は正しいです。
したがって、bとdの組合せが正解と考えられます。
問4:正解②
<問題要旨>
1955年の保守合同(55年体制の成立)前後の政治状況に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
イが誤りです。自由民主党の初代総裁に就任したのは鳩山一郎です。岸信介は鳩山の後の首相です。
②【正】
ア:1954年に、吉田茂の対米協調・軽武装路線に反発する鳩山一郎らを中心に結成された日本民主党は、自主憲法の制定と再軍備を綱領に掲げました。
イ:1955年11月、自由党と日本民主党が合同して自由民主党が結成され、初代総裁には鳩山一郎が就任しました。
したがって、この組合せが正解です。
③【誤】
アが誤りです。警察予備隊が設置されたのは1950年で、朝鮮戦争の勃発が直接のきっかけです。日本民主党が結成された1954年には、警察予備隊は保安隊を経て、自衛隊へと改編されていました。
④【誤】
ア、イともに誤りです。
問5:正解④
<問題要旨>
サンフランシスコ平和条約をめぐり分裂し、その後再統一した日本社会党の安全保障政策の変遷について、史料から読み解く問題です。(※史料2が省略されているため、問題文の記述と史料3から推測して判断します)
<選択-肢>
①【誤】
X、Yともに誤りです。
②【誤】
Yが誤りです。
③【誤】
Xが誤りです。
④【正】
X:問題文に「分裂後、安全保障政策では、左派は非武装中立を主張し、右派は日米安保条約を支持した」とあります。史料3の統一社会党の政策は、日米安保条約を将来的に「解消する」ことを目指し、「いずれの陣営にも属しないアジア諸国との提携を強化」するとしており、左派の非武装中立に近い立場です。正解が「X誤」であることから、省略された史料2は、これとは異なる右派の主張(日米安保条約を支持する立場)であったと推測できます。したがって、史料2を「左派の主張」とするこの記述は誤りです。
Y:史料3は、「いずれの陣営にも属しないアジア諸国との提携を強化し、すべての国との友好関係を増進する」と述べています。これは、アメリカを中心とする資本主義陣営(西側陣営)との結束を強化するのではなく、非同盟・中立の立場を目指すものであり、記述は誤りです。
したがって、X、Yともに誤りであるこの組合せが正解です。
問6:正解①
<問題要旨>
1950年代に展開された日本の平和運動について、誤っている記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
ベ平連(ベトナムに平和を!市民連合)は、アメリカによる北ベトナム爆撃(北爆)が開始されたことをきっかけに、1965年に結成された反戦市民運動です。1950年代の運動ではありません。したがって、この記述は誤りです。
②【正】
1950年代、沖縄では米軍による土地の強制的な接収が相次ぎ、これに反対する住民が「島ぐるみ闘争」と呼ばれる全島的な抵抗運動を展開しました。
③【正】
1954年のビキニ環礁での水爆実験による第五福竜丸の被爆事件をきっかけに、原水爆禁止を求める署名運動が全国に広がり、1955年に広島で第1回原水爆禁止世界大会が開催されました。
④【正】
石川県の内灘村(内灘事件、1952年~)や東京都の砂川町(砂川事件、1955年~)では、在日米軍基地の設置や拡張に反対する激しい住民運動が起こりました。これらは1950年代の代表的な基地反対闘争です。
問7:正解②
<問題要旨>
敗戦後の日本の政治・経済・社会について、総括的に述べた文の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
bが誤りです。傾斜生産方式は、石炭・鉄鋼といった基幹産業(重化学工業)に、資金・資材・労働力を重点的に投入し、生産の回復を図る政策でした。繊維などの軽工業に集中したわけではありません。
②【正】
a:GHQによる経済の民主化政策として、財閥解体や独占禁止法による巨大企業の分割が行われました。しかし、冷戦の激化に伴う占領政策の転換(逆コース)の中で、日本の経済復興が優先されるようになり、これらの政策は緩和され、不徹底なまま終わった側面があります。正しい記述です。
d:独立回復後、鳩山一郎内閣などの保守陣営は憲法改正(特に第9条の改正による再軍備の明記)を目指しました。しかし、憲法改正の発議に必要な衆参両院での3分の2以上の議席を確保できませんでした。これは、日本社会党などの革新勢力が「護憲」を掲げ、改憲を阻止できる3分の1以上の議席を維持し続けたためです。正しい記述です。
したがって、aとdの組合せが正解です。
③【誤】
bとcが誤りです。cの「GHQは天皇制への批判を禁止した」は、正確ではありません。GHQは、天皇の神格化を否定する一方、占領を円滑に進めるために天皇制を存続させましたが、言論の自由は民主化の柱であり、天皇制そのものへの批判が全面的に禁止されたわけではありません。
④【誤】
bが誤りであるため、この選択肢は誤りです。