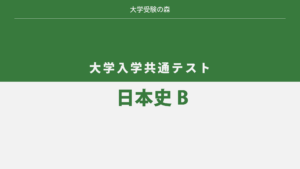解答
解説
第1問
問1:正解③
<問題要旨>
1930年代の文化の広まりの背景と、民衆の伝統的な行事についての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
アは正しいですが、イが誤りです。富突は、寺社が幕府の許可を得て発行した富くじのことで、共同飲食をしながら夜を明かす行事ではありません。
②【誤】
アは正しいですが、イが誤りです。理由は①と同じです。
③【正】
ア:1925年にラジオ放送が始まり、1930年代には全国的なラジオ網が拡大しました。また、レコードも普及し、流行歌が全国に広まるメディアとなりました。「東京音頭」が全国に広まった背景として適切です。
イ:庚申講は、人間の体内にいる三尸の虫が、庚申の日の夜に人々が眠っている間に天に昇って天帝にその人の罪を報告すると信じられていたため、それを防ぐために集まって徹夜する行事です。共同飲食を伴うことも多く、問題文の記述と一致します。
④【誤】
アは誤りで、イは正しいです。理由は①と同じです。
問2:正解①
<問題要旨>
1920年代から1930年代にかけての重要事件(治安維持法、日満議定書、国体明徴声明)の年代順を問う問題です。
<選択肢>
史料Ⅰは、「国体ヲ変革シ、又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織」という内容から、共産主義を取り締まる目的で1925年に制定された治安維持法です。
史料Ⅱは、「日本国及満州国ハ(中略)両国共同シテ国家ノ防衛二当ル」「日本国軍ハ満州国二駐屯スル」という内容から、1932年の満州国建国直後に、関東軍の満州駐屯を合法化するために結ばれた日満議定書です。
史料Ⅲは、「統治権ガ天皇二存セズシテ、天皇ハ之ヲ行使スル為ノ機関ナリト為スガ如キハ(中略)我ガ国体ノ本義ヲ愆ルモノナリ」という内容から、美濃部達吉の天皇機関説を否定し、国体の明確化を求めた1935年の国体明徴声明です。
したがって、年代順はⅠ(1925年)→Ⅱ(1932年)→Ⅲ(1935年)となります。この順に並んでいるのは①です。
問3:正解③
<問題要旨>
江戸時代の祭礼・行事に関する図と史料を読み解き、その内容と合致しない選択肢を特定する問題です。
<選択肢>
①【正】
図1『東都名所 高輪廿六夜待遊興之図』を見ると、中央で踊る人々の中には、タコや魚のような被り物をしている人物がおり、仮装して楽しんでいたことがわかります。
②【正】
図1の右奥には「うどん」と書かれたのれんを掲げた出店が見えることから、食べ物を売る出店があったことがわかります。
③【誤】
史料1で幕府は「盆にはいつも賑ひ踊り候まま踊り申すべく候」と盆踊りを認めていますが、史料2で加賀藩は「踊り・辻相撲堅く御停止に候条」と踊りを禁止しています。したがって、加賀藩は幕府の法令通りに民衆の祭礼を認めていたわけではありません。
④【正】
史料1で幕府は盆踊りを認めつつ、「但し、喧嘩・口論これ無き様申し付くべく候」と釘を刺しており、踊りに伴う揉め事を懸念していたことがわかります。
問4:正解②
<問題要旨>
中世の風流踊りや踊念仏に関する図と史料を読み解き、記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
a【正】
図2の風流踊りでは人々が扇子などを持ち、図3の踊念仏では鉦や太鼓のような楽器を持っています。一方で、図2は輪になって比較的静かに踊っているように見えるのに対し、図3はより躍動的に踊っており、両者の踊りの姿は異なっています。
b【誤】
図3の踊念仏を広めたのは時宗の開祖である一遍です。一遍は「南無阿弥陀仏」の念仏を唱えることで誰もが救われると説きました。坐禅によって救われると説いたのは、栄西(臨済宗)や道元(曹洞宗)などです。
c【誤】
史料3の筆者は、村人たちの風流踊りについて「都の能者に恥じず」と述べており、都の芸能に劣らないと高く評価しています。「つまらないものと評価している」という記述は史料の内容と一致しません。
d【正】
史料4には、風流のために「懸銭・用銭」が課され、その額が「法量なし(程度が甚だしい)」であったため、「地下人(百姓)等迷惑せしむる」と記されています。これから、多額の費用負担が百姓の不満を招いていたことがわかります。
以上より、正しいものの組合せはaとdです。
問5:正解④
<問題要旨>
日本の原始・古代における信仰や祭祀に関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
X【誤】
縄文時代の抜歯は、成人になるための通過儀礼として、生前に行われたと考えられています。死者の霊を恐れて死後に行われたものではありません。
Y【誤】
祈年の祭は、春にその年の豊作を祈るために行われた祭りです。秋に収穫を感謝する祭りは新嘗の祭といいます。
問6:正解⑦
<問題要旨>
日本の祭礼・行事の歴史的変遷をまとめた図の空欄を、関連する歴史的事実と正しく結びつける問題です。
<選択肢>
Xは、中世の祭礼に影響を与えた古代の「信仰や思想」という枠組みです。メモの図では、Xから仏教行事である「盂蘭盆」へと線が伸びています。
bの「百済の聖明王から仏像・経典が贈られたことで公式に伝えられた思想」は仏教のことで、「盂蘭盆」に直接つながる思想として適切です。
aのアニミズムも古代の信仰ですが、図の中で仏教系の行事である「盂蘭盆」とのつながりが示されていることから、ここではbがより適切と判断できます。
Yは、中世に祇園会(祇園祭)が一時断絶した原因です。
dの「都で大きな戦乱が起こり、その大部分が荒廃した」は応仁の乱(1467~77年)を指しており、この戦乱で京都が焼け野原となったために祇園祭が長期にわたり中断しました。したがって、Yの原因として適切です。
cは嘉吉の変(1441年)に関する記述であり、時代が異なります。
Zは、近現代に盆踊りが一時禁止された理由です。
eの「明治維新の風潮のなかで、西洋と異なる伝統的な風俗が排斥された」ことは、盆踊りが風紀を乱すものとして一部地域で禁止・制限された背景として適切です。
fのキリスト教禁止は盆踊りの禁止とは直接関係がありません。
以上のことから、最も適当な組合せはX-b、Y-d、Z-eとなります。
第2問
問1:正解④
<問題要旨>
6世紀の古墳の変化に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
a【誤】
6世紀の古墳の副葬品は、銅鏡などの呪術的なものから、馬具・武具や須恵器など、大陸文化の影響を受けた実用的なものへと変化しました。
b【正】
6世紀には、石室の入り口を開ければ何度も埋葬(追葬)ができる横穴式石室が大陸から伝わり、広く普及しました。これは、家族墓としての性格を持ちます。
c【誤】
甕棺墓は、弥生時代に九州北部で特徴的に見られた墓の形式です。
d【正】
5世紀までの巨大な前方後円墳の造営は衰え、6世紀になると、特定の地域に小規模な円墳などが多数集中して造られる群集墳が各地に出現しました。
以上より、正しいものの組合せはbとdです。
問2:正解①
<問題要旨>
古墳時代から飛鳥時代にかけてのヤマト政権に関わる出来事を、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
Ⅰは、527年に九州北部の豪族・筑紫国造磐井が新羅と結んでヤマト政権に反乱を起こした磐井の乱についての記述です。
Ⅱは、推古天皇の時代の大臣(蘇我馬子)の死後、蘇我氏内部で権力争いが起こった際の出来事です。境部摩理勢は蘇我馬の子で、次期氏上に蘇我蝦夷が就くことに反発し、討たれました。これは7世紀前半の出来事です。
Ⅲは、壬申の乱に勝利して即位した天武天皇(在位673~686年)が定めた八色の姓に言及しており、天武天皇の死後の儀礼の様子を述べています。天武天皇の没年は686年です。
したがって、年代順はⅠ(527年)→Ⅱ(7世紀前半)→Ⅲ(686年)となります。この順に並んでいるのは①です。
問3:正解④
<問題要旨>
古代日本の律令(葬喪令)に関する史料を読み解き、その内容や律令制度の性格について判断する問題です。
<選択肢>
a【誤】
史料群1の令の条文には「三位以上、及び別祖・氏宗は、ならびに墓を営むことを得」とあります。「及び」とあるため、三位以上であれば氏の長でなくても墓の築造は許されたと解釈できます。
b【正】
史料群1の注釈書には、令では四位以下の墓の造営を禁じているにもかかわらず、「今行事(現在の実態としては)、濫りに作るのみ」とあり、令の規定が遵守されていなかった実態が示されています。
c【正】
史料群2では、日本の令と唐の令に、高官の死に際して氷を与えるという類似した規定があることが示されています。日本の律令は、唐の律令を模範として作られたため、内容が似ているものが多いです。
以上より、正しいものの組合せはbとcのみです。
問4:正解②
<問題要旨>
摂関期の権力者である藤原道長に関する史料を読み解き、当時の政治・社会状況を考察する問題です。
<選択肢>
X【正】
史料には、道長の邸宅である土御門殿の造営を「諸の受領に配し、営ましむ」とあり、受領たちが費用を負担したことがわかります。受領は任国で徴税などを通じて富を蓄積しており、その富を中央の権力者に提供することで自己の地位を維持・向上させていました。
Y【誤】
藤原道長は摂政・関白として太政官組織の最高位にあり、その組織を通して政治を行いました。太政官を無視して政治を行ったわけではありません。「帝王のごとし」と評されたのは、天皇の外戚として絶大な権勢を誇ったことを示しています。
問5:正解④
<問題要旨>
日本古代の墓制と葬送儀礼の歴史的変遷について、総合的な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
方形周溝墓は弥生時代の代表的な墓制の一つです。ヤマト政権の支配領域拡大とともに全国に広まったのは前方後円墳です。また、古墳文化は北海道には及んでいません。
②【誤】
日本で初めて墓の規模を規制したのは、孝徳天皇の時代に出された薄葬令(646年)です。これは、唐・新羅との戦争である白村江の戦い(663年)よりも前のことです。
③【誤】
天皇として初めて火葬されたのは持統天皇(在位690~697年、703年に火葬)です。聖武天皇(在位724~749年)も火葬されましたが、最初ではありません。
④【正】
レポートBにあるように、藤原道長は一族の墓地のそばに寺院を建て、子孫の極楽往生を祈願しました。これは、阿弥陀仏にすがって死後に極楽浄土へ生まれ変わることを願う浄土教の信仰が、貴族層に広まっていたことを示しています。
第3問
問1:正解⑥
<問題要旨>
鎌倉幕府が支配権を確立・拡大していく過程における重要な出来事を、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
Ⅰは、「平泉館炎上」という記述から、源頼朝が奥州藤原氏を滅ぼした1189年の奥州合戦後の出来事です。
Ⅱは、「諸国平均に守護地頭を補任」「兵粮米(反別五升)」といった内容から、1185年に後白河法皇から認められた、頼朝が全国の荘園・公領に守護・地頭を設置する権利(文治の勅許)に関する記述です。
Ⅲは、源(木曽)義仲を追討するために西上した源頼朝に対し、朝廷が東海・東山道諸国の荘園・公領の実質的な支配権(年貢の徴収など)を認めた1183年の寿永二年十月宣旨に関する記述です。
したがって、年代順はⅢ(1183年)→Ⅱ(1185年)→Ⅰ(1189年)となります。この順に並んでいるのは⑥です。
問2:正解②
<問題要旨>
建武の新政と室町幕府の地方支配に関する基本的な知識について、誤っているものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
後醍醐天皇による建武の新政では、東北地方の統治機関として、北畠顕家を長とする陸奥将軍府が置かれました。
②【誤】
室町幕府は東国の支配のために鎌倉府を置きました。その長官は鎌倉公方と呼ばれ、足利尊氏の子・基氏の子孫が世襲しました。その補佐役は関東管領で、上杉氏が世襲しました。細川氏は、京都の室町幕府の管領を輩出した三管領家の一つであり、鎌倉府の管領ではありません。
③【正】
室町幕府は、九州統治のために九州探題、奥羽両国統治のために奥州探題・羽州探題を設置しました。
④【正】
室町時代の守護は、半済令の施行などを通じて軍事・警察権だけでなく経済的権限も強化し、国衙の機能をも吸収して、一国を独自に支配する守護大名へと成長していきました。
問3:正解①
<問題要旨>
中世の国人たちが結んだ一揆の契約状を読み解き、その内容を正しく理解できているかを問う問題です。
<選択肢>
a【正】
契約状を結んだ26名は「御一族」「御一家」といった血縁的な言葉を使いつつ、「宇久浦中」という地域的なまとまり(地縁)で結びついていることが読み取れます。
b【誤】
争いが起きた場合の対応として、「一同に相談し、正しい判断をする」と定められており、合議による解決を目指しています。特定の長の裁定に従うという規定はありません。
c【正】
所領の境界における「山野河海において狩りや漁、同じく木・松・竹切りなど」について、境を越えてはならないという取り決めがなされています。
d【誤】
百姓や下人が逃亡した場合は、相互に協力して元の主人のもとに返すことが定められていますが、その手続きに守護の許可が必要であるとは記されていません。これは一揆内部のルールです。
以上より、正しいものの組合せはaとcです。
問4:正解②
<問題要旨>
中世の蝦夷ヶ島(北海道)と和人の関係史に関する文章と、関連する語句を正しく結びつける問題です。
<選択肢>
Xは、安藤(安東)氏が蝦夷ヶ島との交易で得た産物を将軍に献上している様子を示しています。安藤氏は、津軽のaの十三湊を拠点に、アイヌとの交易で繁栄しました。bの坊津は薩摩半島の港で、琉球貿易の拠点です。
Yは、1457年にアイヌが蜂起し、和人の館を攻撃した事件について述べています。この戦いは、指導者の名をとってdのコシャマインの戦いと呼ばれます。cのシャクシャインは、17世紀後半に大規模な蜂起を起こしたアイヌの指導者であり、時代が異なります。
したがって、正しい組合せはX-a、Y-dです。
問5:正解③
<問題要旨>
15~16世紀の琉球王国の中継貿易に関する史料と表を読み解き、その内容について正しく判断する問題です。
<選択肢>
X【誤】
設問は「史料2と表から読み取れること」を問うています。史料2は省略されており、表には琉球から明への朝貢品として硫黄・蘇木・螺殼・刀剣などが挙げられていますが、綿布・麻・芭蕉布は記載されていません。したがって、表からこの内容を読み取ることはできません。
Y【正】
表を見ると、琉球と日本の双方が明への朝貢品として刀剣を挙げています。琉球王国は日本と東南アジアを結ぶ中継貿易で繁栄しました。日本の刀剣は高品質で重要な輸出品であったため、琉球が日本から刀剣を輸入し、それを明への朝貢品(輸出品)としていたと考えるのが自然です。
第4問
問1:正解③
<問題要旨>
江戸時代の開発について、17世紀から18世紀にかけての状況を正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【正】
17世紀は、幕藩体制が確立していく中で、全国各地で城下町の建設や五街道などの交通網の整備が進められました。
②【正】
17世紀は「大開発時代」とも呼ばれ、幕府や諸藩の主導で大規模な新田開発が行われ、耕地面積が大幅に増加しました。
③【誤】
江戸時代の鉱山業では、17世紀に佐渡金山や石見銀山などの金銀山の産出量がピークに達しましたが、その後は減少し、代わって足尾銅山や別子銅山などの銅の産出が増加しました。18世紀に新たな金銀山の開発が盛んになったわけではありません。
④【正】
18世紀末、ロシアの南下政策への警戒から、幕府は最上徳内らを蝦夷地に派遣して調査を行いました。これが幕府による本格的な蝦夷地調査の始まりです。
問2:正解④
<問題要旨>
江戸時代の学者とその業績を正しく結びつける問題です。本草学と経世思想がテーマとなっています。
<選択肢>
Xは、植物や鉱物の薬効を記した本草学に関する記述です。これは、福岡藩の儒学者・本草学者であるbの貝原益軒が著した『大和本草』で知られます。aの渋川春海は、貞享暦を作成した天文学者です。
Yは、藩の財政再建のために殖産興業や専売制を論じる経世思想に関する記述です。これは、dの海保青陵が『稽古談』で論じた内容と一致します。cの富永仲基は、大坂の懐徳堂で学んだ町人学者で、儒教・仏教・神道を批判的に研究しました。
したがって、正しい組合せはX-b、Y-dです。
問3:正解②
<問題要旨>
江戸時代の農村における資源利用の様子を描いた図を解釈し、関連する用語を正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
図には「山方刈草して田育に仕る」とあり、山の草を刈り取って田の肥料にしている様子が描かれています。したがって、アは「山野から、田の肥料として用いる草を刈り取る」が正しいです。
このような、村の百姓たちが共同で薪や肥料を採取するために利用した山野をイの「入会地」といいます。「助郷」は、宿場町の負担を軽減するために、周辺の村々に課された人馬を提供する義務のことです。
したがって、正しい組合せは②です。
問4:正解①
<問題要旨>
江戸幕府が整備した国役普請の制度に関する法令を読み解き、その内容を正しく理解する問題です。
<選択肢>
X【正】
史料1には、「一国全体を支配しているか二十万石以上の所領を持つ大名は、これまで通り自力で行うこととする」と明記されており、これらの大名領は国役による工事の対象外であったことがわかります。
Y【正】
国役は、一国単位で課される普請の義務です。そのため、ある領主の領地内での工事であっても、同じ国に所領を持つ他の領主や、その支配下にある百姓たちも、石高に応じて費用や労働力を負担する必要がありました。
問5:正解③
<問題要旨>
江戸後期の秋田藩が出した森林管理に関する指示書を読み解き、当時の藩政が抱えていた問題意識や政策の意図を把握する問題です。
<選択肢>
a【誤】
史料は、山林伐採が耕地の荒廃や災害、物価(材木薪炭価)の高騰を招くと指摘していますが、物価の引き下げを直接命じるものではなく、根本的な対策として植林を奨励しています。
b【正】
史料には「材木薪炭価の高低、御国中一統に相係り」とあり、森林資源の状況が藩領全体の経済に影響を及ぼすという認識を持っていたことがわかります。
c【正】
史料の末尾に「種実苗木取り立て等、御入方(費用)は指し出さるべく候」とあり、藩が費用を負担して植林や苗木の育成を奨励する意思を示していることがわかります。
d【誤】
史料は天然林の保護だけでなく、「諸樹植え継ぎ」とあるように、積極的に植林を行うことを奨励しています。
以上より、最も適当なものの組合せはbとcです。
第5問
問1:正解⑤
<問題要旨>
ペリー来航(1853年)から幕末の動乱期にかけての重要事件を、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
Ⅰは、薩摩藩の島津久光の要求により行われた1862年の文久の改革の内容です。参勤交代の緩和が特徴的です。
Ⅱは、前年の八月十八日の政変で京都から追放された長州藩が、勢力回復を目指して京都に出兵し、会津・薩摩藩兵と衝突した1864年の禁門の変(蛤御門の変)です。
Ⅲは、1859年の開港直後の混乱に対応するため、幕府が1860年に出した五品江戸廻送令に関する記述です。
したがって、年代順はⅢ(1860年)→Ⅰ(1862年)→Ⅱ(1864年)となります。この順に並んでいるのは⑤です。
問2:正解②
<問題要旨>
徳川慶喜による大政奉還の上表文を読み解き、その内容と前後の政治状況について正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
X【正】
史料1で徳川慶喜は、「外国の交際、日に盛んなるにより、愈朝権一途に出申さず候ては綱紀立ち難く候」と述べており、外交問題に対処するためには政権を朝廷に統一する必要があるという論理で大政奉還を申し出ています。
Y【誤】
政治の流れは、①大政奉還(1867年10月)→②王政復古の大号令(同年12月)→③鳥羽・伏見の戦い(1868年1月)の順です。この文では、鳥羽・伏見の戦いの後に王政復古の大号令が出されたことになっており、時系列が誤っています。
問3:正解①
<問題要旨>
明治時代の外交に関する人物と条約の組合せを問う問題です。
<選択肢>
Xは、外国人判事を大審院に任用するという条約改正案への反対運動の中で負傷した外務大臣です。これは、1889年に玄洋社の来島恒喜に爆弾を投げつけられ片脚を失ったaの大隈重信です。
Yは、明治政府が初めて対等な立場で結んだ条約です。これは、1871年に清との間で結ばれたcの日清修好条規であり、相互に領事裁判権を認め、関税も協定によって定める内容でした。dの日英通商航海条約(1894年)は領事裁判権を撤廃した画期的な条約ですが、「初めて対等な内容で結んだ」条約ではありません。
したがって、正しい組合せはX-a、Y-cです。
問4:正解②
<問題要旨>
明治天皇の東京行幸に関する史料と錦絵を読み解き、当時の社会状況やメディアの役割について考察する問題です。
<選択肢>
a【正】
明治天皇の最初の東京行幸は1868年10月に行われましたが、戊辰戦争はまだ終結しておらず、箱館の五稜郭では榎本武揚ら旧幕府軍が抵抗を続けており、降伏したのは翌1869年5月のことでした。
b【誤】
錦絵は、多色刷りの木版画である浮世絵の一種で、江戸時代中期の鈴木春信らによって完成されました。開国後に誕生したものではありません。
c【誤】
史料2には「貴賤老稚道路に輻輳して」とあり、身分や年齢、性別に関係なく、多くの人々が入り乱れて行列を見物していた様子がわかります。「整然と区分けされ」ていたわけではありません。
d【正】
図の錦絵は、10月の東京行幸の翌月である11月には制作・出版されています。このことから、錦絵が時事的な出来事を人々に素早く伝えるメディアとしての役割を果たしていたことがうかがえます。
以上より、最も適当なものの組合せはaとdです。
第6問
問1:正解③
<問題要旨>
明治時代の政治史と文化史(彫刻)に関する知識を組み合わせる問題です。
<選択肢>
ア:西南戦争で「賊軍」とされた西郷隆盛の名誉が回復され、正三位が贈られたのは、1889年の大日本帝国憲法発布に伴う大赦によるものです。
イ:高村光雲の子である高村光太郎と親しく、フランスでロダンの彫刻に影響を受けた彫刻家は荻原守衛(碌山)です。
したがって、正しい組合せはアに「大日本帝国憲法の発布」、イに「荻原守衛」が入る③です。
問2:正解⑥
<問題要旨>
明治末期から大正時代にかけての政治・社会の出来事を報じた新聞記事を、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
Ⅰは、「米価暴騰」「女房連(が)米屋及び米所有者を襲い」という記述から、1918年に富山県で始まり全国に広がった米騒動の記事です。
Ⅱは、「強露討伐の詔勅」(日露戦争開戦)の10年後、つまり1914年頃の出来事を示唆し、「山本内閣に対する宣戦の烽火」とあります。これは、シーメンス事件で批判を浴びていた第1次山本権兵衛内閣に対する民衆の抗議運動の様子です。第一次護憲運動の継続と見なせます。
Ⅲは、「新帝御践祚の初」(大正天皇の即位直後)、「桂公の内閣」(第3次桂太郎内閣)、「閥族政治の打破」という記述から、1912年末から1913年にかけて起こった第一次護憲運動(大正政変)の記事です。
したがって、出来事の発生順はⅢ(1912年)→Ⅱ(1914年頃)→Ⅰ(1918年)となります。この順に並んでいるのは⑥です。
問3:正解④
<問題要旨>
井伊直弼に関する史料から、彼の政治的立場と、彼が関わった歴史的事件についての知識を問う問題です。
<選択肢>
Xの「意外の障害」とは、井伊直弼の記念碑建設に対する反発を指します。井伊は安政の大獄で吉田松陰ら長州藩士を含む多くの尊王攘夷派を弾圧したため、長州閥が実権を握る明治政府内で強い反発があったと考えられます。したがって、bの「井伊直弼による弾圧で処罰者が出た長州藩出身者などの反発」が適切です。aは、井伊が一橋派を弾圧した側なので誤りです。
Yの「直弼公の遭難地」とは、井伊直弼が暗殺された桜田門外の変(1860年)の現場です。この事件の後、幕府の権威は大きく失墜し、老中安藤信正らは朝廷との融和(公武合体)を図ることで権威回復を目指し、孝明天皇の妹・和宮と将軍徳川家茂との結婚を進めました。したがって、dが適切です。cの「会津藩浪士」は誤りで、水戸・薩摩の浪士による犯行でした。
以上のことから、正しい組合せはX-b、Y-dです。
問4:正解①
<問題要旨>
明治天皇の死後、その銅像建設について述べた板垣退助の意見書を読み解き、板垣自身の経歴とあわせて内容の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
a【正】
史料2で板垣は、「陛下の御銅像を製し奉り、以て民衆をして陛下に接するの思いあらしむるの必要あり」と述べており、銅像が天皇を身近に感じさせ、敬愛の念を深めるために必要だと主張しています。
b【誤】
板垣は、「神宮のみにては如何にも物足らぬ心地せらるれば、必ず銅像を建立し」と述べており、神宮だけでは不十分で、銅像も必要だと主張しています。銅像は不要という記述とは逆です。
c【正】
この史料が書かれたのは明治天皇が死去した1912年です。板垣退助が率いた自由党は、1884年に解党しています。その後、彼は政界で活動を続けますが、この時点で自由党は存在しません。
d【誤】
板垣退助は、内務大臣などを歴任しましたが、首相(内閣総理大臣)にはなっていません。また、首相選任に関与する元老にも任じられていません。
以上より、正しいものの組合せはaとcです。
問5:正解①
<問題要旨>
日中戦争勃発(1937年)から敗戦(1945年)までの戦時期の日本の政治・社会に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
戦争が長期化・拡大するにつれて食糧不足が深刻化し、1941年からは米が切符による配給制となり、国民はさつまいもや雑穀などの代用食で飢えをしのぐ生活を強いられました。
②【誤】
独占禁止法は、戦後、GHQによる財閥解体政策の一環として1947年に制定された法律です。戦時期ではありません。
③【誤】
段祺瑞政権は、第一次世界大戦期の中国北京政府の指導者です。この時期の反英運動は、日中戦争期とは時代が異なります。
④【誤】
「東亜新秩序」建設の声明を発表したのは、1938年の第1次近衛文麿内閣です。米内光政内閣(1940年)ではありません。
問6:正解③
<問題要旨>
戦後の銅像に関する新聞記事を読み解き、銅像のモデルとなった人物(寺内正毅)の時代の政治史と、記事の内容を正しく理解する問題です。
<選択肢>
X【誤】
記事にある「寺内元帥」とは、寺内正毅のことです。寺内正毅内閣(1916~18年)は、第一次世界大戦中に成立しました。しかし、中国に対して二十一か条の要求を行ったのは、その前の第2次大隈重信内閣(1915年)です。
Y【正】
史料3には、裸婦像を「軍国日本から文化日本への脱皮を象徴する女神の像」「平和日本のシンボル」と記されており、軍国主義からの脱却の象徴とみなしていることが明確にわかります。
問7:正解②
<問題要旨>
戦後から1970年代までの日本の科学技術と、それに伴う生活の変化について、誤っている記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
物理学者の湯川秀樹は、中間子の存在を理論的に予言した業績により、1949年に日本人として初めてノーベル賞(物理学賞)を受賞しました。
②【誤】
1950年代後半、生活の電化が進む中で憧れの家電製品とされた「三種の神器」は、白黒テレビ・電気洗濯機・電気冷蔵庫でした。問題文にある自動車・カラーテレビ・クーラー(3C)は、1960年代後半のいざなぎ景気の頃に新たな「三種の神器」として普及したものです。
③【正】
高度経済成長期には、エネルギー源が石炭から石油へと転換し(エネルギー革命)、技術革新を背景に、太平洋沿岸地域に大規模な石油化学コンビナートが次々と建設されました。
④【正】
1970年に大阪で開催された日本万国博覧会では、「人類の進歩と調和」をテーマに、アメリカ館の「月の石」や、動く歩道、ワイヤレステレホンなど、当時の最新技術が多数展示され、未来の生活が示されました。