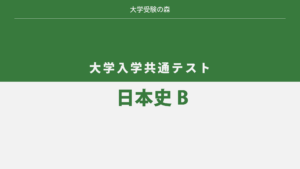解答
解説
第1問
問1:正解⑥
<問題要旨>
4世紀末から6世紀後半にかけての倭国と朝鮮半島との関係史について、出来事の発生順を問う問題です。それぞれの出来事がどの時期に起きたかを、具体的な史実と関連付けて特定する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
正しい年代順はⅢ→Ⅱ→Ⅰです。
②【誤】
正しい年代順はⅢ→Ⅱ→Ⅰです。
③【誤】
正しい年代順はⅢ→Ⅱ→Ⅰです。
④【誤】
正しい年代順はⅢ→Ⅱ→Ⅰです。
⑤【誤】
正しい年代順はⅢ→Ⅱ→Ⅰです。
⑥【正】
Ⅲの「倭国が、好太王(広開土王)の率いる高句麗軍と交戦した」という記述は、中国の好太王碑碑文に見られ、391年の倭の侵攻から始まる一連の交戦を指します。これは4世紀末から5世紀初頭の出来事です。次に、Ⅱの「倭王武が中国南朝に朝貢」したことは、『宋書』倭国伝に記されており、西暦478年のことです。これは5世紀後半にあたります。最後に、Ⅰの「加耶(伽耶・加羅)諸国が百済・新羅の支配下に入」り、倭国の影響力が後退したのは、6世紀の朝鮮半島の動乱によるものです。特に562年に大加耶が新羅に滅ぼされたことで、倭国の朝鮮半島南部における拠点は完全に失われました。これは6世紀後半の出来事です。したがって、Ⅲ→Ⅱ→Ⅰの順が正しいです。
問2:正解④
<問題要旨>
古代の国家による馬の飼育・利用に関して、9~11世紀(平安時代中期)の状況を示した史料を特定する問題です。表のYの時期の特徴である「御牧の重視」と、それに関連する史料の内容を正確に結びつける必要があります。
<選択肢>
①【誤】
史料a、cは8世紀の状況を示すため、Yの時期(9~11世紀)に合わず、不適切です。
②【誤】
史料a、cは8世紀の状況を示すため、Yの時期(9~11世紀)に合わず、不適切です。
③【誤】
史料cは8世紀の状況を示すため、Yの時期(9~11世紀)に合わず、不適切です。
④【正】
表のYの時期(9~11世紀)は、諸国牧が衰退し、朝廷が直轄する「御牧」が重視された時代です。史料bは「天皇が」「信濃国の御馬を覧じ」とあり、天皇が御牧の馬を観覧する儀式が行われていたことを示しています。これは表Yの記述と合致します。史料dは、甲斐・信濃・上野・武蔵といった特定の国(これらは御牧が置かれたことで知られます)の牧馬帳を、中央の馬寮(馬を管理する役所)へ直接提出させています。これは、特定の御牧を中央が直接管理する体制へ変化したことを示しており、表Yの「御牧が重視されていった」という状況と合致します。したがって、bとdがYの時期に対応する史料です。
問3:正解③
<問題要旨>
中世の絵巻物に描かれた馬の利用方法について、その内容を正しく理解できているかを問う問題です。武士の武芸と、中世の輸送業者の姿をそれぞれ正しく解釈する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
文Xが誤りです。
②【誤】
文Xが誤りです。
③【正】
文Xは、図1の笠懸について、「実践を想定しない遊興として行われていた」と説明していますが、笠懸は流鏑馬、犬追物と並ぶ「騎射三物」の一つで、武士にとって重要な実践的武芸訓練でした。したがって、この説明は誤りです。文Yは、図2の馬借について、「地方と都との間で物資が盛んに運送されていた状況を示している」と説明しています。馬借は鎌倉時代後期から室町時代にかけて活躍した輸送業者であり、図には逢坂の関も描かれていることから、交通の要衝で物資輸送が活発に行われていた様子を捉えたものと解釈できます。したがって、この説明は正しいです。よって、Xが誤り、Yが正しい本選択肢が正解となります。
④【誤】
文Yが正しいです。
問4:正解②
<問題要旨>
近世の民間輸送「中馬」に関するレポートを読み、それに基づいて交わされる会話文の正誤を判断する問題です。レポートの内容を正確に読解し、各人の発言がレポートの内容や歴史的事実と合致するかを慎重に吟味する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
リンさんの発言は、中馬が発展した背景としては不適切な点があり、正しいとは言えません。
②【正】
レイカさんの発言「中馬は安価で効率的な輸送方法で、需要を拡大したので、宿駅と争論になった」は、レポート1にある記述と完全に合致しており、正しいです。一方、リンさんの発言は、五街道の整備が宿駅制度の強化につながるものであり、宿駅を利用しない中馬の発展の直接的背景としては適切とは言えません。ミナミさんの発言は、レポート1の「信濃国とその周辺で展開した」という記述と異なり、「全国的な物資輸送を担えるようになった」としている点が誤りです。したがって、レイカさんのみの発言が正しいです。
③【誤】
ミナミさんの発言は「全国的な」という部分が誤りです。
④【誤】
リンさんの発言は、中馬が発展した背景としては不適切な点があり、正しいとは言えません。
⑤【誤】
リンさんの発言は正しいとは言えず、ミナミさんの発言も誤りです。
⑥【誤】
ミナミさんの発言は誤りです。
問5:正解③
<問題要旨>
年表とレポートを基に、近代日本における馬の改良(馬政)の歴史に関する空欄を補充する問題です。特定の出来事が起きた時期と、その背景にある国内外の情勢を結びつける知識が求められます。
<選択肢>
①【誤】
アは日露戦争、イは国際協調の流れを受けた軍縮の風潮です。
②【誤】
アは日露戦争です。
③【正】
レポート2には、アの「対外戦争」後に馬の改良計画が開始されたとあります。年表を見ると、馬政局が設置され改良計画が始まったのは1906年です。この直前に行われた大規模な対外戦争は、1904年~1905年の日露戦争であるため、アには「日露戦争」が入ります。次に、レポート2には、イをきっかけに馬政局が一時廃止されたとあります。年表から、馬政局が廃止されたのは1923年です。この時期は、第一次世界大戦後のワシントン会議などに見られる「国際協調の流れを受けた軍縮の風潮」が高まっていた時期であり、陸軍省の管轄であった馬政局の廃止もこの流れの一環と考えられます。イには「国際協調の流れを受けた軍縮の風潮」が入ります。
④【誤】
イは国際協調の流れを受けた軍縮の風潮です。昭和恐慌は1930年代の出来事であり時期が合いません。
問6:正解①
<問題要旨>
これまでの設問全体を踏まえ、日本の馬の歴史について総合的に理解しているかを問う正誤判定問題です。各時代の馬と社会の関わりについて、正確な知識が求められます。
<選択肢>
①【正】
8世紀に律令国家の地方軍事組織である軍団に馬を供給していた諸国牧は、9世紀以降の律令制の変質とともに衰退しました。代わりに、朝廷や権力者が直接管理する御牧が重視されるようになったため、この記述は正しいです。
②【誤】
騎馬武者が戦闘の主力であったのは鎌倉・室町時代を通じてであり、戦闘で用いられなくなったわけではありません。足軽が戦闘で重要な位置を占めるようになるのは、応仁の乱以降、特に戦国時代になってからです。
③【誤】
武家諸法度で「文武弓馬の道」に励むことが定められたのは、徳川綱吉の代ではなく、1635年の徳川家光の代に出された武家諸法度(寛永令)においてです。
④【誤】
レポート2と年表にあるように、満州事変以降、軍用馬の需要は高まり、日中戦争期には陸軍主導で馬の国家的統制はむしろ強化されました。統制が緩和されたという記述は誤りです。
第2問
問1:正解①
<問題要旨>
古代朝鮮三国のうち、新羅に関する記述として誤っているものを選ぶ問題です。百済や高句麗との関係、日本との関係史についての基本的な知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
朝鮮半島南西部に位置し、6世紀の欽明天皇の時代に日本へ仏教を公伝したのは百済です。新羅は朝鮮半島の南東部に位置していました。したがって、この記述は主語が誤っており、選択すべき誤文です。
②【正】
8世紀に入り、日本と新羅の関係が悪化すると、遣唐使船は危険な新羅沿岸を通過する北路を避け、東シナ海を横断する南路や南島路をとるようになりました。これは正しい記述です。
③【正】
新羅は7世紀後半、唐と連合して百済(660年)、高句麗(668年)を相次いで滅ぼし、その後、唐の勢力を半島から駆逐して676年に朝鮮半島を統一しました。これは正しい記述です。
④【正】
新羅は10世紀初頭に国力が衰え、935年に王建が建国した高麗によって滅ぼされました。これは正しい記述です。
問2:正解③
<問題要旨>
8世紀後半の新羅郡設置について、関連する年表を読み解き、その背景を正しく説明した文を選ぶ問題です。年表から、出来事の前後関係や同時代性を正確に把握する読解力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
年表の冒頭に「672~709年 日本と新羅との間で頻繁に外交使節が往来した」とあり、7世紀末の外交関係は途絶えておらず、むしろ良好でした。
②【誤】
年表の687年の記述に、新羅から渡来した「百姓」を武蔵国に移住させたとあり、僧尼・官人だけではなかったことがわかります。
③【正】
年表を見ると、新羅郡が設置された758年の前後には、753年の遣新羅使の追い返し、759年の新羅征討計画など、両国関係の悪化を示す出来事が集中しています。したがって、新羅郡の設置が両国関係の険悪化の中で行われたことは正しいです。
④【誤】
年表の760年の記述に、新羅郡設置の2年後にも渡来した新羅人を武蔵国に移住させたとあり、移住が途絶えたわけではないことがわかります。
問3:正解③
<問題要旨>
8世紀後半の日本と新羅、渤海との国際関係について、その内容を正しく理解しているかを問う問題です。対等な関係を求める新羅と、新羅に対抗するために日本と結んだ渤海という、当時の東アジアの構図を把握しているかがポイントとなります。
<選択肢>
①【誤】
文Xが誤りです。
②【誤】
文Xが誤りです。
③【正】
文Xは「新羅は、日本に従属するという立場を受け入れた」とありますが、実際には新羅は日本との対等外交を主張し、日本側が求めた朝貢(従属)を拒否したため、両国の関係は悪化しました。よってこの記述は誤りです。文Yは「渤海は、新羅と対抗関係にあり、たびたび使者を日本へ派遣した」とありますが、渤海は南の新羅や唐と対立していたため、日本とは友好関係を結び、頻繁に使者を派遣しました。よってこの記述は正しいです。したがって、Xが誤り、Yが正しい本選択肢が正解となります。
④【誤】
文Yが正しいです。
問4:正解①
<問題要旨>
奈良時代から平安時代初期にかけての新羅との交易に関する会話文の空欄を、史料に基づいて補充する問題です。史料から当時の交易の実態や、それに対する朝廷の政策を読み取り、適切な語句や年代を判断する必要があります。
<選択肢>
①【正】
アには、史料2の記述から、a「新羅からの物品を高い値段で買い、資産を減らした日本の人々がいた」ことが読み取れます。イには、史料2に「西海道を統括する官司に下知して」とあり、外交・交易の窓口であったc「大宰府」が交易を管理したことがわかります。ウには、唐の商人が盛んに来航するようになる時期として、遣唐使が停止される前後のe「9世紀後半」が最も適当です。
②【誤】
ウは9世紀後半が適切です。
③【誤】
イは太政官ではなく大宰府です。
④【誤】
イは太政官ではなく大宰府、ウは9世紀後半が適切です。
⑤【誤】
アはbではなくaです。
⑥【誤】
アはbではなくa、ウは9世紀後半が適切です。
⑦【誤】
アはbではなくa、イは太政官ではなく大宰府です。
⑧【誤】
アはbではなくa、イは太政官ではなく大宰府、ウは9世紀後半が適切です。
問5:正解⑤
<問題要旨>
7世紀から9世紀の新羅との贈答品・交易品に関する史料と表を分析し、そこから導き出される結論として正しいものを選ぶ問題です。複数の資料から情報を抽出し、それらを組み合わせて総合的に判断する能力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
文cも正しいです。
②【誤】
文bは誤りです。
③【誤】
文aも正しいです。
④【誤】
文bは誤りです。
⑤【正】
文aは、表で7世紀の贈答品に「金」があり、史料1で8世紀の交易品に「金」があることから、正しいことがわかります。文bは、「蘇芳」や「駱駝」が新羅の産物ではないことから、交易品などが新羅の産物だけで構成されていたわけではないと判断できるため、誤りです。文cは、史料2に「朝廷にとって必要な物品は都に進上させて」とあり、朝廷が交易品を優先的に確保しようとしていたことがわかるため、正しいです。したがって、aとcが正しいです。
⑥【誤】
文bは誤りです。
第3問
問1:正解④
<問題要旨>
中世の仏教文化に関する解説パネルの空欄を補充する問題です。鎌倉時代の浄土教美術と、室町時代の禅宗文化についての基本的な知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
アは極楽浄土、イは臨済宗です。
②【誤】
アは極楽浄土です。
③【誤】
イは臨済宗です。
④【正】
アには、源頼朝が模したとされる平泉の毛越寺庭園が、阿弥陀如来のいる「極楽浄土」を地上に表現しようとしたものであることから、「極楽浄土」が入ります。イには、室町幕府が五山・十刹の制を定めて手厚く保護し、政治や文化に大きな影響を与えた禅宗の一派である「臨済宗」が入ります。
問2:正解②
<問題要旨>
鎌倉時代に活躍した仏教僧の事績について、正しいものの組合せを選ぶ問題です。それぞれの僧侶がどの宗派に属し、どのような活動を行ったかを正確に記憶しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
cは義堂周信ではなく夢窓疎石の事績であり、誤りです。
②【正】
aの重源は、宋の工人・陳和卿の協力を得て東大寺を再建したことで知られます。dの忍性は、律宗の僧として貧民救済や橋の修造などの社会事業に尽力したことで知られます。この二つの記述は正しいです。一方、bの龍安寺石庭は室町時代の作であり栄西の活動とは関係がありません。cの天龍寺創建に関わったのは夢窓疎石です。したがって、aとdの組合せが正しいです。
③【誤】
b、cともに誤りです。
④【誤】
bは栄西の事績ではなく、誤りです。
問3:正解③
<問題要-旨>
正長の土一揆に際して柳生の地に刻まれた徳政碑文(史料1)と、当時の様子を記した年代記(史料2)を対照し、碑文の文言に相当する内容を史料2から見つけ出す問題です。古文書の読解力と、歴史的背景の理解が求められます。
<選択肢>
①【誤】
「徳政と号し」は一揆のスローガンであり、負債の破棄という具体的な内容を指すものではありません。
②【誤】
「破却せしめ」は土倉などの建物を破壊する行為を指します。
③【正】
史料1の「ヲキメアルヘカラス」は「負債はあるべきではない」という意味で、債務の免除を要求する内容です。これは、史料2の③「借銭等悉くこれを破る」、つまり借金の証文などをことごとく破棄するという行為と直接的に対応します。農民たちが求めた徳政の具体的な中身を示しています。
④【誤】
「管領これを成敗す」は、一揆に対する幕府の対応を述べた部分であり、一揆側の要求内容ではありません。
問4:正解④
<問題要旨>
室町幕府8代将軍・足利義政と、彼が生きた時代の政治・文化についての正誤を判定する問題です。将軍の権力基盤や、東山文化を支えた人々の構成に関する正確な知識が必要となります。
<選択肢>
①【誤】
文X、Yともに誤りです。
②【誤】
文X、Yともに誤りです。
③【誤】
文X、Yともに誤りです。
④【正】
文Xは、足利義政が応仁の乱を回避できなかった理由を「将軍に直属軍や直轄領がなかったため」としていますが、室町将軍には奉公衆という直属軍も、御料所という直轄領も存在しました。この説明は誤りです。文Yは、義政の文化活動を支えた人々を「会合衆」と説明していますが、会合衆とは堺の自治を担った有力商人たちのことです。義政を支え、東山文化の担い手となったのは同朋衆でした。したがって、この説明も用語が誤っています。よって、X、Yともに誤りの本選択肢が正解となります。
問5:正解①
<問題要旨>
中世における石臼の普及に関する図・表を読み解き、それに基づいて行われた高校生たちの発言の正誤を判断する問題です。資料から読み取れる事実と、歴史的な知識とを結びつけて推論する力が試されます。
<選択肢>
①【正】
発言Aは、表1と日本史における二毛作の普及時期から、両者の関係性を推論しており、妥当です。発言Bは、表2から16世紀になっても饅や抹茶などが特別な扱いであったことを指摘しており、資料の内容と合致します。発言Cは、表1と後北条氏の台頭による鎌倉の地位低下という歴史的事実を結びつけており、妥当な推論です。したがって、三つの発言はすべて正しいと考えられます。
②【誤】
発言B、Cも正しいです。
③【誤】
発言A、Cも正しいです。
④【誤】
発言A、Bも正しいです。
⑤【誤】
発言Cも正しいです。
⑥【誤】
発言Bも正しいです。
⑦【誤】
発言Aも正しいです。
⑧【誤】
三つとも正しいです。
第4問
問1:正解③
<問題要旨>
江戸時代初期、寛永の飢饉を契機として、幕府の統治方針が転換したことに関する空欄補充問題です。「武断政治」から「文治政治」へ移行し、農民の生活安定を図るようになった歴史の流れを理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
アは本百姓経営の維持・安定を目指す政策であり、イは文治政治です。
②【誤】
アは本百姓経営の維持・安定を目指す政策です。
③【正】
寛永の飢饉を教訓に、幕府は年貢の安定確保のため、農民の経営を安定させる方針に転換しました。具体的には、1643年に田畑永代売買の禁令を出すなど、ア「本百姓経営の維持・安定を目指す」ようになりました。また、4代将軍徳川家綱の頃からは、それまでの武断政治に代わり、儒学の理念に基づくイ「文治」政治が進展しました。
④【誤】
イは武断政治ではなく文治政治です。
問2:正解②
<問題要旨>
5代将軍徳川綱吉の政治に関して、生類憐みの令の趣旨と、服忌令の影響についての正誤を判断する問題です。史料から法令の意図を読み解く力と、歴史用語の正確な理解が求められます。
<選択肢>
①【誤】
文Yが誤りです。
②【正】
文Xは、史料1から、幕府が法令の形式的な遵守だけでなく、人々の内面的な道徳心を養うことを目的としていたことが読み取れるため、正しいです。一方、文Yの服忌令は、近親者の死に際して喪に服す期間を定めたものですが、これにより日本社会に古くから存在した死を「穢れ」とする意識が「消滅していった」というのは事実ではありません。したがって、Xが正、Yが誤りの本選択肢が正解となります。
③【誤】
文Xは正しいです。
④【誤】
文Xは正しいですが、文Yは誤りです。
問3:正解⑤
<問題要旨>
江戸時代に発生した主要な災害や飢饉を、年代順に正しく配列する問題です。それぞれの出来事がどの将軍の治世や、どの時期に起こったかを特定する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
正しい年代順はⅢ→Ⅰ→Ⅱです。
②【誤】
正しい年代順はⅢ→Ⅰ→Ⅱです。
③【誤】
正しい年代順はⅢ→Ⅰ→Ⅱです。
④【誤】
正しい年代順はⅢ→Ⅰ→Ⅱです。
⑤【正】
Ⅲの明暦の大火は1657年、4代将軍徳川家綱の時代に発生しました。Ⅰの享保の飢饉は、8代将軍吉宗の時代の1732年に発生しました。Ⅱの天明の飢饉は、1782年から1787年にかけて発生し、その最中の1783年に浅間山の大噴火が被害を拡大させました。したがって、発生順はⅢ→Ⅰ→Ⅱとなります。
⑥【誤】
正しい年代順はⅢ→Ⅰ→Ⅱです。
問4:正解①
<問題要旨>
享保の改革において、医療や医学に関連する政策に携わった人物を特定する問題です。改革の具体的な内容と、それに関わった人物についての知識が問われます。
<選択肢>
①【正】
文Xの「小石川養生所」の設置を将軍吉宗に進言したのは、江戸町奉行のa「大岡忠相」です。文Yの、将軍吉宗の命でオランダ語を学び、蘭学の発展の基礎を築いた人物としては、c「青木昆陽」が挙げられます。よって、X-a、Y-cの組合せが正しいです。
②【誤】
Yに該当する人物は青木昆陽です。
③【誤】
Xに該当する人物は大岡忠相です。
④【誤】
Xに該当する人物は大岡忠相、Yに該当する人物は青木昆陽です。
問5:正解④
<問題要旨>
幕末の思想家・横井小楠の著作(史料2)を読み解き、彼の欧米認識と、当時の日本の状況に関する記述の正誤を判断する問題です。史料の正確な読解と、幕末の対外関係・洋学受容史の知識を組み合わせる必要があります。
<選択肢>
①【誤】
cは誤りです。
②【誤】
a、cともに誤りです。
③【誤】
aは誤りです。
④【正】
文bは、史料2で横井小楠が欧米の政治や厚生施設を儒教の理想である「三代の治教」と重ね合わせて高く評価していることから、正しいと判断できます。文dは、幕末の対外関係の複雑化を背景に、幕府が洋学の研究・教育機関として蕃書調所を設置したという史実と合致しており、正しいです。したがって、bとdの組合せが正しいです。
第5問
問1:正解②
<問題要旨>
明治初期の鉄道創業に関する基本的な知識を問う空欄補充問題です。殖産興業政策を担った官庁と、日本で最初に開通した鉄道の区間を特定します。
<選択肢>
①【誤】
最初の鉄道の起点(東京側)は新橋です。
②【正】
明治政府の殖産興業政策の中心となった官庁で、鉄道などを管轄したのはア「工部省」です。日本で最初の鉄道は、1872年(明治5年)に、イ「新橋」と横浜の間で正式開業しました。
③【誤】
鉄道建設を管轄したのは工部省であり、起点は新橋です。
④【誤】
鉄道建設を管轄したのは工部省です。
問2:正解④
<問題要旨>
1853年(ペリー来航の年)に出された大船建造の解禁令に関する史料を読み解き、その内容についての説明の正誤を判断する問題です。史料中の条件や留保事項を正確に読み取ることが重要となります。
<選択肢>
①【誤】
文X、Yともに誤りです。
②【誤】
文X、Yともに誤りです。
③【誤】
文X、Yともに誤りです。
④【正】
文Xは、大名が「幕府に断ることなく」艦船を製造できるようになったとしていますが、史料には幕府の許可と指示が必要であったことがわかるため誤りです。文Yは、幕府がキリスト教を解禁したとしていますが、史料にはキリスト教の禁止は従来通り継続することが明記されているため誤りです。したがって、X、Yともに誤りの本選択肢が正解となります。
問3:正解⑥
<問題要旨>
幕末期の日本と欧米諸国との間で起こった重要な出来事を、年代順に正しく配列する問題です。ペリー来航から開国、攘夷運動の激化に至る流れを把握しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
正しい年代順はⅢ→Ⅱ→Ⅰです。
②【誤】
正しい年代順はⅢ→Ⅱ→Ⅰです。
③【誤】
正しい年代順はⅢ→Ⅱ→Ⅰです。
④【誤】
正しい年代順はⅢ→Ⅱ→Ⅰです。
⑤【誤】
正しい年代順はⅢ→Ⅱ→Ⅰです。
⑥【正】
Ⅲの日米和親条約の締結は1854年。Ⅱの日米修好通商条約の締結は1858年。Ⅰの薩英戦争は、1862年の生麦事件を原因として1863年に勃発しました。したがって、Ⅲ→Ⅱ→Ⅰの順が正しいです。
問4:正解②
<問題要旨>
明治初期の西洋技術導入に関して、メモと表の情報を統合して、当時の状況を正しく説明している文を選ぶ問題です。複数の資料から的確に情報を読み取り、それらを組み合わせて判断する力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
メモと表からは、東京美術学校に関する情報は一切読み取れません。
②【正】
メモには「高輪築堤の建設にあたっては、…江戸時代の埋立て・石垣造りの技術が用いられた」と明確に記されています。これは、日本の在来技術が生かされたことを示しており、この記述は正しいです。
③【誤】
表によると、お雇い外国人の人数が最多だった1875年は、技術者の数が学術教師の数を上回っています。したがって、この記述は表の内容と一致しません。
④【誤】
メモによれば日本人初の機関士が誕生したのは1879年です。表で1879年以降の技術者の割合を見ると、上昇ではなく横ばいから減少傾向に転じていることがわかります。したがって、この記述は誤りです。
第6問
問1:正解④
<問題要旨>
明治期の基幹産業である製糸業と紡績業の発展に関する空欄補充問題です。官営模範工場で導入された技術と、民間の紡績業を主導した企業家の名前を特定します。
<選択肢>
①【誤】
アは器械製糸、イは渋沢栄一です。
②【誤】
アは器械製糸です。
③【誤】
イは渋沢栄一です。
④【正】
アには、官営の富岡製糸場で導入された西洋式の生産技術である「器械製糸」が入ります。イには、大阪紡績会社を設立し、日本の紡績業の発展を主導した「渋沢栄一」が入ります。
問2:正解⑤
<問題要旨>
明治期の鉄道網の発展に関する出来事を、年代順に正しく配列する問題です。官営鉄道の延伸と、民間による鉄道会社の設立、そして大陸への進出という鉄道史の展開を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
正しい年代順はⅢ→Ⅰ→Ⅱです。
②【誤】
正しい年代順はⅢ→Ⅰ→Ⅱです。
③【誤】
正しい年代順はⅢ→Ⅰ→Ⅱです。
④【誤】
正しい年代順はⅢ→Ⅰ→Ⅱです。
⑤【正】
Ⅲの日本鉄道会社の設立は1881年です。Ⅰの官営東海道線の全通は1889年です。Ⅱの南満州鉄道株式会社(満鉄)の設立は、日露戦争後の1906年です。したがって、Ⅲ→Ⅰ→Ⅱの順が正しいです。
⑥【誤】
正しい年代順はⅢ→Ⅰ→Ⅱです。
問3:正解②
<問題要旨>
昭和初期の工場の動力の変化(電化)に関する史料を読み、その内容と当時の社会状況についての正誤を判断する問題です。史料の読解と、昭和初期の生活文化史の知識が必要となります。
<選択肢>
①【誤】
文Yが誤りです。
②【正】
文Xは、史料1から、電化によって生産能率が向上し、煤煙問題も緩和されたことがわかるため、正しいです。一方、文Yが述べるテレビや電気洗濯機が一般家庭に普及し始めるのは、1950年代後半の高度経済成長期であり、史料1が書かれた1931年頃の状況ではないため誤りです。したがって、Xが正、Yが誤りの本選択肢が正解となります。
③【誤】
文Xは正しいです。
④【誤】
文Xは正しいですが、文Yは誤りです。
問4:正解③
<問題要旨>
20世紀前半の日本の鋼材(鉄鋼)需給の推移を示すグラフを読み解き、その背景に関する説明として誤っているものを選ぶ問題です。グラフの変動と、各年代の経済・外交情勢とを正しく関連づける分析力が求められます。
<選択肢>
①【正】
グラフの全期間を通じて、国内で消費される割合が極めて高かったことがわかります。これは正しい解釈です。
②【正】
1910年代は、第一次世界大戦の好景気で造船業や海運業が大きく発展した時期であり、それに伴い鉄鋼の国内生産量が増加したと考えられます。これは正しいです。
③【誤】
1920年代に輸入量が増加していますが、日本が金本位制に復帰(金解禁)したのは1930年1月のことであり、時期が合いません。したがって、この記述が誤りです。
④【正】
1930年代は満州事変以降、軍備拡張が進んだ時期であり、軍需生産の拡大が鉄鋼生産量の急増につながったと考えられます。これは正しいです。
問5:正解②
<問題要旨>
足尾銅山鉱毒事件に関する田中正造の直訴状(史料2)と、その内容をまとめたメモを比較し、メモの記述の正誤を判断する問題です。史料の内容を正確に、かつニュアンスまで含めて理解できているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
メモの<鉱毒の原因>は、史料2の記述を正しくまとめているため、誤りではありません。
②【正】
メモの<鉱毒の被害>は、被害を「予想している」とまとめていますが、史料2ではすでに甚大な被害が発生していると断定的に述べています。被害の現状認識において、メモは史料の内容を誤ってまとめていると言えます。
③【誤】
メモの<責任の所在>は、史料2が「政府当局」の責任を追及している点を正しくまとめているため、誤りではありません。
④【誤】
上記の通り、<鉱毒の被害>に関する記述に誤りがあるため、メモ全体が正しくまとめているとは言えません。
問6:正解②
<問題要旨>
四大公害訴訟と革新自治体に関する新聞記事を読み、それぞれがどの地域・人物に関連するかを特定する問題です。現代史の重要事項に関する知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
Yの美濃部知事は東京都知事です。
②【正】
新聞記事Xは、「石油(石油化学)コンビナートの排煙による大気汚染」という特徴から、四日市ぜんそく訴訟を指していることがわかります。四日市市はa「三重県」にあります。新聞記事Yは、著名な革新知事である美濃部亮吉の名を挙げています。美濃部亮吉はd「東京都」の知事を務めました。したがって、X-a、Y-dの組合せが正しいです。
③【誤】
Xは三重県、Yは東京都です。
④【誤】
Xは三重県です。
問7:正解①
<問題要旨>
プリントA・Bの内容を総合し、日本の近現代における工業化と環境問題の関係について述べた文の中から、誤っているものを選ぶ問題です。各時代の産業のエネルギー源や、環境への影響を正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
この文が選択すべき誤文です。プリントAには、明治初期の製糸業の熱源として「多くの薪や木炭が必要とされたため、木が乱伐されることもあった」と記されています。これは、森林伐採という形で自然環境に負荷を与えていたことを意味するため、「自然環境と調和しながら発展した」という記述は明確に誤りです。
②【正】
プリントA・Bの記述から、重工業の発展が各地で大気汚染(煙害)を引き起こしたことは正しいです。
③【正】
プリントBにあるように、高度経済成長期には深刻な公害が社会問題化し、住民による反対運動や訴訟など、公害への対策を求める国民的な運動が広がりました。これは正しいです。
④【正】
プリントBや問6の内容からもわかるように、1960年代から70年代前半にかけて、公害問題などを背景に環境・福祉政策を重視する革新自治体が全国各地で誕生しました。これは正しいです。