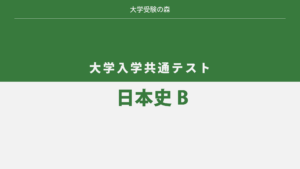解答
解説
第1問
問1:正解②
<問題要旨>
古代から室町時代にかけての文化史に関する基本的な知識を問う問題です。会話文中の空欄に入る語句として、柿本人麻呂と雪舟にそれぞれ関連する作品名の正しい組み合わせを選びます。
<選択肢>
①【誤】
柿本人麻呂は『万葉集』の歌人ですが、『瓢鮎図』は室町時代の画僧である如拙の作品です。雪舟の作品ではありません。
②【正】
柿本人麻呂は、飛鳥時代から奈良時代初期にかけて活躍した『万葉集』の代表的な歌人です。雪舟は室町時代に活躍した水墨画家で、『四季山水図』(山水長巻)はその代表作の一つです。したがって、この組み合わせは正しいです。
③【誤】
『懐風藻』は現存する日本最古の漢詩集であり、柿本人麻呂は和歌の歌人であるため、関連がありません。『瓢鮎図』は如拙の作品であり、雪舟の作品ではありません。
④【誤】
『懐風藻』は漢詩集であり、柿本人麻呂とは関連がありません。『四季山水図』は雪舟の代表作ですが、アの組み合わせが誤りです。
問2:正解④
<問題要旨>
戦国時代から江戸時代にかけての鉱業について、その特徴や関連する技術、政策に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
佐渡鉱山(佐渡金銀山)は、金銀の産出で知られた鉱山であり、銅が中心ではありません。銅山としては足尾銅山などが有名です。
②【誤】
灰吹法は、銀の精錬技術であり、16世紀前半に朝鮮半島経由で博多の商人によって日本にもたらされました。琉球から伝えられたものではありません。
③【誤】
たたら製鉄は、砂鉄を原料とする日本古来の製鉄法で、特に中国山地で盛んに行われました。鉄鉱石を主要な原料とし、中部地方が中心であったわけではありません。
④【正】
豊臣秀吉は、石見銀山や佐渡金山などの重要な鉱山を直轄地(蔵入地)とし、政権の財政基盤としました。江戸幕府もこの方針を継承し、全国の主要鉱山を幕府の直轄領(天領)として支配しました。
問3:正解③
<問題要旨>
江戸時代の藩政、特に専売制や社会経済の動向に関する正誤を判断する問題です。18世紀と19世紀の社会状況の違いを正確に理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
Xが正しく、Yが正しいとする選択肢です。Xは誤りです。
②【誤】
Xが正しく、Yが誤りとする選択肢です。Xは誤り、Yは正しいです。
③【正】
Xの「18世紀半ばから、世直しを求める百姓一揆が起きるようになり」という記述は誤りです。世直しをスローガンとする一揆が頻発するのは、社会不安が深刻化する19世紀、特に幕末期です。Yの「19世紀前半に、薩摩藩では、調所広郷によって奄美の黒砂糖の専売が強化された」という記述は正しいです。調所広郷は薩摩藩の財政改革を断行し、黒砂糖の専売制強化や琉球を通じた密貿易によって巨額の利益を上げました。したがって、Xは誤り、Yは正しいので、この選択肢が正解です。
④【誤】
Xが誤り、Yが誤りとする選択肢です。Yは正しいです。
問4:正解③
<問題要旨>
中世の遺跡から出土した輸入陶磁器量の推移を示すグラフを読み取り、その背景にある対外関係の歴史的展開について考察する問題です。グラフの各時期と対外関係の出来事を正しく結びつける必要があります。
<選択肢>
①【誤】
Ⅰ期(1100年代)からⅡ期(1200年代)は平安時代末期から鎌倉時代にあたり、この時期の中国大陸の王朝は南宋です。日宋貿易が盛んであったため輸入陶磁器が増加しました。明が建国されるのは14世紀後半(1368年)であり、時期が合いません。
②【誤】
渤海は10世紀初頭に滅亡しており、13世紀以降の貿易の衰退とは全く関係がありません。
③【正】
Ⅲ期(1300年代)からⅣ期(1400年代)にかけて、室町幕府による日明貿易(勘合貿易)が開始され、また朝鮮(李氏朝鮮)との貿易も活発になりました。特に応永の外寇(1419年)後、対馬の宗氏の仲介で日朝間の貿易は安定し、木綿などが輸入されました。グラフで輸入陶磁器量が再び増加している背景として、朝鮮半島との貿易活性化は妥当な説明です。
④【誤】
V期(1500年代)からVI期(1600年代)にかけて輸入量が減少している背景として、豊臣秀吉の朝鮮出兵(1592年~1598年)により日朝間の国交が断絶したことは事実です。しかし、国交は江戸時代初期の1607年には回復しており、「17世紀末まで日朝間の国交が途絶えた」という記述は誤りです。
問5:正解②
<問題要旨>
江戸時代の絵図と中世の史料という、異なる時代の資料を組み合わせて、高津港の歴史的変遷を考察する問題です。各資料から読み取れる情報を正確に解釈する能力が問われます。
<選択肢>
a【正】図には高津川河口に「係船杭」が描かれ、船が停泊している様子がうかがえます。史料1にも「西の方には入海ありて」と記されており、船が停泊しやすい入り江が港の立地条件であったことが分かります。
b【誤】史料2は1240年の文書であり、この時点で港が存在していたことが確認できます。一方、史料1は15世紀半ば成立の文書で、柿本人麻呂の堂について述べています。港の存在の方が古いため、「堂に人々が集うようになったから港が設けられた」という因果関係は成立しません。
c【誤】史料2では、荘園領主が地頭を港の支配から「いっさい関与させないようにしたい」と訴えています。これは、地頭が港の支配に関与しようとしていた、あるいは既に関与していたことを示唆しており、「地頭に排除されていて、関わっていなかった」という記述とは逆です。
d【正】図には津和野藩の施設である「御船蔵」「御武器蔵」「御米中場」「船見番所」が描かれています。これらの施設から、江戸時代の高津港が藩によって管理・運営されていたことが分かります。
正しい文はaとdなので、その組み合わせである②が正解です。
問6:正解④
<問題要旨>
大正期の政治・経済・外交と、それに伴う交通網(鉄道・海運)の関連について問う問題です。政党、内閣、条約、地理に関する知識が複合的に求められます。
<選択肢>
①【誤】
Xに該当するのは立憲政友会、Yに該当するのは関東州です。
②【誤】
Xに該当するのは立憲政友会、Yに該当するのは関東州です。
③【誤】
Xに該当するのは立憲政友会、Yに該当するのは関東州です。
④【正】
Xの「大戦景気を背景とした積極政策を掲げた内閣」とは、原敬内閣を指します。原内閣の与党は「b 立憲政友会」であり、鉄道敷設法の改正など鉄道網の拡充を進めました。Yの「ポーツマス条約を受けて日本が租借していた地域」とは、ロシアから租借権を引き継いだ遼東半島南部の「d 関東州」を指します。したがって、X-b, Y-dの組み合わせが正しいです。
第2問
問1:正解②
<問題要旨>
史料1(他田日奉部直神護解)から、奈良時代の地方行政、特に郡司の役割や任命の実態を読み解く問題です。史料の読解力と、律令制に関する基本的な知識が問われます。
<選択肢>
a【正】
史料1で神護は、「祖父は…父は…兄もまた大領となりました」と父祖代々の家柄を主張し、さらに有力者(藤原麻呂や中宮の藤原宮子)に長年仕えた実績を挙げて、郡司への任命を希望しています。
b【誤】
史料1は神護自身が任命を願い出た文書(解)であり、主君である藤原宮子からの指示があったという記述はありません。
c【誤】
郡司には、国造など古くからの地方豪族が任命されることが多かったのは事実ですが、その地位は終身官であり、国司のような任期はありませんでした。
d【正】
郡司は、中央から派遣された国司の指揮監督のもと、郡家(郡衙)と呼ばれる役所で、徴税などの地方行政の実務を担いました。
正しい文はaとdなので、その組み合わせである②が正解です。
問2:正解②
<問題要旨>
奈良時代の政争史、特に藤原氏が関わった重要な出来事を年代順に正しく配列する問題です。聖武天皇の治世における政治的事件の因果関係を理解しているかがポイントです。
<選択肢>
I:藤原光明子(藤原不比等の娘)が臣下として初めて皇后に立てられたのは、政敵であった長屋王が変(729年)で自殺に追い込まれた直後の729年です。
III:藤原四兄弟(武智麻呂・房前・宇合・麻呂)が、当時流行した天然痘によって相次いで病死したのは737年です。
II:藤原広嗣が、藤原四兄弟の死後に政権を握った橘諸兄や僧玄昉らを排除しようと九州で反乱を起こしたのは740年です。
したがって、起こった順は I → III → II となります。
問3:正解④
<問題要旨>
古代の文化(奈良時代と平安時代前期)の特徴と、それに該当する作品を正しく結びつける問題です。写真が省略されているため、文化の特徴から作品の時代を推測する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
Xは平安前期の弘仁・貞観文化、Yは奈良時代の天平文化の特徴です。組み合わせが誤っています。
②【誤】
Xは平安前期の弘仁・貞観文化、Yは奈良時代の天平文化の特徴です。組み合わせが誤っています。
③【誤】
Yは天平文化の特徴ですが、選択肢の写真「あ」は、Xの弘仁・貞観文化(密教美術など)に属する作品と推測されるため、組み合わせが誤っています。
④【正】
Yの「唐の文化の影響を強く受け、貴族を中心とした国際色豊かな文化」は、天平文化の正しい説明です。選択肢の写真「い」は、この天平文化を代表する作品(例えば、正倉院宝物や興福寺の阿修羅像など)と推測されます。したがって、この組み合わせが正しいです。
問4:正解③
<問題要旨>
平安時代初期の地方制度に関する正誤を判断する問題です。勘解由使や健児といった特定の制度について正確な知識が求められます。
<選択肢>
①【誤】
Xが正しく、Yが正しいとする選択肢です。Xは誤りです。
②【誤】
Xが正しく、Yが誤りとする選択肢です。Xは誤り、Yは正しいです。
③【正】
Xの「郡司の交替の事務引継ぎを監督させるために、勘解由使が設けられた」は誤りです。勘解由使は、国司の交替時の不正を防ぐため、事務引継ぎを厳しく監査する令外官でした。Yの「郡司の子弟のなかには、健児として採用され、国府の警備などにあたる者もいた」は正しいです。桓武天皇の軍制改革により、従来の軍団・兵士制が廃止され、地方の有力者である郡司の子弟などを健児として採用し、国府の警備などにあたらせました。したがって、Xは誤り、Yは正しいので、この選択肢が正解です。
④【誤】
Xが誤り、Yが誤りとする選択肢です。Yは正しいです。
問5:正解④
<問題要旨>
史料2「尾張国郡司百姓等解文」と10世紀頃の地方行政の変化について述べた文の中から、誤っているものを選ぶ問題です。受領の強欲な徴税と、それに対抗する郡司・百姓の動き、そして律令制の変質を理解しているかが問われます。
<問題要旨>
①【正】
史料2には、国司(受領)である藤原元命が、部下を使って先例を無視した過酷な徴税を行っている様子が描かれており、この記述は正しいです。
②【正】
「尾張国郡司百姓等解文」という史料名自体が示すように、この史料は郡司と百姓らが連名で、国司の暴政を朝廷に訴えた文書であり、この記述は正しいです。
③【正】
10世紀頃になると、政府は財政収入を確保するため、国司の最上席者である受領に、国内の租税徴収に関する大きな権限と責任を委ねるようになりました。この記述は正しいです。
④【誤】
10世紀頃には、律令制の基本であった班田収授法や戸籍・計帳に基づく人別支配は崩壊していました。政府は、人単位ではなく土地単位で課税する、新たな租税システム(負名体制)へと移行していきました。したがって、「戸籍・計帳の作成を厳密に行わせ、戸を単位とした租税徴収を強化した」という記述は、この時代の変化とは逆であり、誤りです。
第3問
問1:正解④
<問題要旨>
鎌倉新仏教の広がりの中で、幕府に保護された禅宗や、旧仏教の側で戒律復興に努めた律宗の僧侶に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
Xに該当するのは蘭渓道隆、Yに該当するのは叡尊です。
②【誤】
Xに該当するのは蘭渓道隆、Yに該当するのは叡尊です。
③【誤】
Xに該当するのは蘭渓道隆、Yに該当するのは叡尊です。
④【正】
Xの「北条時頼に招かれ来日し、鎌倉に建長寺を開いた」人物は、南宋の禅僧「b 蘭渓道隆」です。Yの「西大寺を拠点に戒律の復興に努め、非人救済事業などを行った」人物は、律宗の「d 叡尊」です。したがって、X-b, Y-dの組み合わせが正しいです。
問2:正解①
<問題要旨>
室町時代の史料を読み解き、幕府と座の関係や、座の特権について問う問題です。史料の正確な読解と、中世の商工業組合である「座」についての知識が求められます。
<選択肢>
①【正】
Xの「幕府は…大山崎油座の独占権を保護した」は、史料1で幕府(管領)が、座に属さない土民の油器を破却するよう命じていることから正しいと判断できます。Yの「座のなかには、関銭の免除などの特権を認められて…」も、座が本所(寺社や公家)の権威を背景に、営業の独占権や関銭免除などの特権を得ていたという歴史的事実から正しいです。したがって、X、Yともに正しいので、この選択肢が正解です。
②【誤】
Yは正しいです。
③【誤】
Xは正しいです。
④【誤】
X、Yともに正しいです。
問3:正解①
<問題要旨>
戦国時代の紛争に関する史料X・Yが、それぞれどの事件を指し、その場所が地図上のどこに当たるかを特定する問題です。史料の内容から事件を同定し、地理的な知識と結びつける必要があります。
<選択肢>
①【正】
史料Xは、一揆が守護の富樫氏を滅ぼし、国を支配したという記述から、1488年の「加賀の一向一揆」を指します。加賀国は現在の石川県にあたり、地図上の「a」です。史料Yは、「叡山を取り詰め、根本中堂,山王二十一社」などを焼き払ったという記述から、1571年の織田信長による「比叡山延暦寺の焼き討ち」を指します。比叡山は京都と滋賀の境にあり、地図上の「b」です。したがって、X-a, Y-bの組み合わせが正しいです。
②【誤】
Yの場所が誤っています。
③【誤】
XとYの場所が逆になっています。
④【誤】
Xの場所が誤っています。
⑤【誤】
X、Yともに場所が誤っています。
⑥【誤】
Yの場所が誤っています。
問4:正解②
<問題要旨>
史料2(1587年に出された伴天連追放令)を読み解き、豊臣秀吉のキリスト教政策の内容と意図を正確に理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
a【正】史料2には「神社仏閣を打ち破るの由、前代未聞に候」とあり、キリスト教徒による寺社破壊を追放令の理由の一つとして挙げています。
b【誤】史料2では「日域の仏法をあい破ること、曲事に候条」(日本の仏法を破壊するのはとんでもないことだ)と述べており、仏教の破壊を問題視しています。「問題ないと考えている」という記述は逆です。
c【誤】追放の対象として「伴天連(バテレン=宣教師)」を名指ししており、すべてのキリスト教徒を対象とはしていません。
d【正】史料2の最後の条文で「仏法の妨げをなさざる輩は、商人の儀は申すにおよばず…往還くるしからず」とあり、布教を伴わない商船の来航(南蛮貿易)は認める方針を示しています。
正しい文はaとdなので、その組み合わせである②が正解です。
問5:正解③
<問題要旨>
本願寺教団(浄土真宗)の成立から戦国時代までの歴史について、適当でない記述を選ぶ問題です。他の宗派(特に日蓮宗)の出来事と混同しないかがポイントです。
<選択肢>
①【正】
浄土真宗は親鸞の『教行信証』を根本聖典とし、悪人正機説などの分かりやすい教えで、鎌倉時代以降、農民や武士に広く浸透しました。
②【正】
本願寺の勢力が強い地域では、寺院を中心に信者が集住して自治的な都市「寺内町」を形成しました。大坂の石山本願寺や、富田林などがその例です。
③【誤】
京都の町衆(商工業者)が自治を行い、延暦寺と対立して焼き討ちされたのは、日蓮宗(法華宗)の信者たちです(天文法華の乱、1536年)。本願寺の出来事ではありません。
④【正】
本願寺は、蓮如の時代に勢力を拡大し、顕如の代には摂津国石山(大坂)に巨大な寺内町を築きました。天下布武を進める織田信長と10年間にわたり対立(石山戦争)しましたが、1580年に和睦し、石山から退去しました。
第4問
問1:正解⑤
<問題要旨>
江戸時代中期の幕府財政政策に関連する出来事を、年代順に正しく配列する問題です。徳川綱吉、家宣・家継(新井白石)、家治(田沼意次)の各時代の政策を区別できるかが問われます。
<選択肢>
I:新井白石が正徳の治の一環として、貿易額を制限する海舶互市新例を出したのは1715年です。
II:田沼意次が、計数貨幣である南鐐二朱銀を鋳造し、株仲間を公認して運上・冥加を徴収したのは1772年以降です。
III:荻原重秀が、貨幣の質を落として差益(出目)を得る貨幣改鋳(元禄金銀)を行ったのは、徳川綱吉の治世下である1695年以降です。
したがって、起こった順は III → I → II となります。
問2:正解④
<問題要旨>
儒学者・荻生徂徠の逸話が書かれた史料を読み解き、徳川吉宗が行った享保の改革の内容と結びつけて、誤っている記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
史料で徂徠が「海内の封国、皆国家の命なり」(全国の土地はすべて将軍のものである)と述べていることから、正しいと判断できます。
②【正】
徂徠は、幕府が米を「借り上げる」という形式をとったことに対し、「御借とは何ごとぞや」と批判しています。将軍が命じればよいものを、なぜ「借りる」などという回りくどい言い方をするのか、という趣旨です。
③【正】
上米の制は、大名に石高1万石あたり100石の米を上納させる見返りに、参勤交代における江戸在府期間を1年から半年に短縮する制度でした。
④【誤】
徳川吉宗は、年貢収入を安定させるため、豊凶にかかわらず過去の平均収穫高に基づいて一定の年貢率を課す「定免法」を奨励しました。収穫高を毎年調査して年貢率を決める「検見法」の採用を命じたわけではありません。
問3:正解③
<問題要旨>
江戸城への登城風景を描いた図を読み取り、大名行列の様子や、それを取り巻く社会の状況について正誤を判断する問題です。図から具体的な情景を読み取る観察力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
Xが正しく、Yが正しいとする選択肢です。Xは誤りです。
②【誤】
Xが正しく、Yが誤りとする選択肢です。Xは誤り、Yは正しいです。
③【正】
Xの「商いをしている人たちは営業を中断し…平伏している」という記述は、図を見ると誤りです。行列の脇では酒を売るなど商いが続けられており、人々は平伏するどころか、座って見物しています。Yの「大名行列が…行き来することなどによって…本陣のある宿場町が発展した」は、参勤交代が交通網の整備と宿場町の発展を促したという歴史的事実から正しいです。したがって、Xは誤り、Yは正しいので、この選択肢が正解です。
④【誤】
Xが誤り、Yが誤りとする選択肢です。Yは正しいです。
問4:正解②
<問題要旨>
幕末の文久の改革に伴う社会の変化を示す史料を読み解き、改革の内容と影響について考察する問題です。史料読解と、文久の改革に関する知識を組み合わせる必要があります。
<選択肢>
a【正】史料2には、参勤交代の緩和で大名の江戸滞在が減ったため、雇われていた足軽・中間などが解雇される場合があったことが記されています。
b【誤】史料2では、解雇されて帰郷を願う者には幕府が「御手当」(費用)を支給するとあり、「強制的に国元に帰された」わけではありません。
c【誤】徳川斉昭を幕政に参与させ、江戸湾に台場を築いたのは、ペリー来航(1853年)後の阿部正弘政権下でのことであり、文久の改革(1862年)ではありません。
d【正】文久の改革では、幕政改革を担う役職として、松平慶永が政事総裁職に、徳川慶喜が将軍後見職に任命され、軍制改革(西洋式軍制の採用)も行われました。
正しい文はaとdなので、その組み合わせである②が正解です。
問5:正解②
<問題要旨>
江戸時代の幕府と大名の関係(幕藩体制)について、総合的に理解しているかを問う問題です。大名統制策や身分制度に関する正確な知識が求められます。
<選択肢>
①【誤】
末期養子の禁止を緩和したのは4代将軍徳川家綱の時で、大名の改易(取り潰し)を減らし、牢人の発生を抑制する効果がありました。「牢人の大量発生を引き起こし」たというのは逆です。
②【正】
問題のリード文にもあるように、幕府は武家諸法度などで大名行列の供の人数に基準を設けたり、武具や道具を許可制にしたりすることで、行列の華美・大規模化を抑制し、大名の財力を削ぐ統制策をとりました。
③【誤】
参勤交代で人質として江戸に常住させられたのは大名の妻子(正室と世継ぎ)であり、彼女たちは行列を組んで国元と往復はしませんでした。大名自身が家臣を率いて江戸と国元を往復しました。
④【誤】
大名が家臣への俸禄を、土地を直接与える地方知行から、米で支給する蔵米知行へ変更する動きは、江戸時代初期から各藩で財政上の理由により進められていました。「18世紀後半から…始め」たわけではありません。
第5問
問1:正解③
<問題要旨>
幕末から明治維新にかけての重要な藩と人物の動向を結びつける問題です。版籍奉還を主導した薩長土肥の4藩のうち、長州藩と土佐藩の活動が問われています。
<選択肢>
①【誤】
Xに該当するのは長州藩、Yに該当するのは後藤象二郎です。
②【誤】
Xに該当するのは長州藩、Yに該当するのは後藤象二郎です。
③【正】
Xの「朝廷を動かして幕府に攘夷の決行を迫り、幕府の命令に応じて外国船を砲撃した」のは、1863年に下関で外国船を砲撃した「b 長州藩」の行動です。Yの「将軍徳川慶喜に前藩主を通して政権の返還を勧め、明治新政府の成立後は自由民権運動に深く関わった」のは、土佐藩の「c 後藤象二郎」です(坂本龍馬とともに大政奉還を建白)。したがって、X-b, Y-cの組み合わせが正しいです。
④【誤】
Xに該当するのは長州藩、Yに該当するのは後藤象二郎です。
問2:正解②
<問題要旨>
明治初期、廃藩置県(1871年)から沖縄県設置(1879年)までの間に起こった出来事を、年代順に正しく配列する問題です。征韓論政変、台湾出兵、士族反乱という、密接に関連した事件の順序を理解しているかが問われます。
<選択肢>
I:西郷隆盛らの征韓論が、大久保利通らの反対で退けられた征韓論政変が起きたのは1873年です。
III:琉球漂流民殺害事件を口実に、不平士族の不満を外に向ける目的もあって台湾に出兵したのは1874年です。
II:廃刀令や秩禄処分に不満を持つ士族の反乱が相次ぎ、熊本で神風連の乱、福岡で秋月の乱、山口で萩の乱が起きたのは1876年です。
したがって、起こった順は I → III → II となります。
問3:正解①
<問題要旨>
木戸孝允の手紙と彼が描いたイラストを読み解き、中央集権国家を目指した彼の思想と、彼の経歴に関する正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【正】
Xは、史料1と図1・2の内容を正しく要約しています。木戸は、各藩がバラバラ(図1)では外国に対抗できないため、朝廷(新政府)のもとに一体化(図2)すべきだと主張しています。Yの「木戸が参加した大阪会議の結果、漸次立憲政体樹立の詔が出されるとともに、元老院・大審院などが設置された」も、1875年の史実として正しいです。したがって、X、Yともに正しいので、この選択肢が正解です。
②【誤】
Yは正しいです。
③【誤】
Xは正しいです。
④【誤】
X、Yともに正しいです。
問4:正解④
<問題要旨>
明治政府と琉球藩(旧琉球王国)との間で交わされた文書を読み解き、琉球処分(沖縄県設置)に至る過程での両者の主張を理解する問題です。
<選択肢>
a【誤】史料2は明治新政府が琉球藩に出した通達であり、江戸幕府の政策ではありません。
b【正】史料2には、琉球藩王が代替わりする際に清から冊封(国王として承認される儀式)を受けることを禁じる内容が明記されています。
c【誤】史料3で琉球藩は、清への朝貢継続を「天皇陛下御大徳ますます相顕れ」るためだと述べており、「藩王の大徳を示すため」ではありません。日本に従属しつつも、清との伝統的関係を維持したいという苦しい立場がうかがえます。
d【正】史料3で琉球藩は、「往古より両属の儀は各国明知するところ」と述べ、日本と清の両方に服属してきた歴史を挙げ、清との信義を失わないように朝貢を継続させてほしいと訴えています。
正しい文はbとdなので、その組み合わせである④が正解です。
第6問
問1:正解④
<問題要旨>
大正デモクラシー期の政治・社会運動に関する基本的な知識を問う問題です。民本主義や婦人解放運動など、この時代を象徴する事柄の正しい理解が求められます。
<選択肢>
a【誤】第2次護憲運動後の総選挙で勝利し、護憲三派内閣の首相となったのは憲政会の加藤高明です。
b【正】吉野作造は、雑誌『中央公論』などで民本主義を提唱し、大正デモクラシーの理論的指導者となりました。
c【誤】植木枝盛が私擬憲法(私案の憲法草案)を作成したのは、自由民権運動が盛んだった明治時代(1880年代)のことです。
d【正】平塚らいてうや市川房枝らは、1920年に新婦人協会を設立し、女性の政治参加を禁じた治安警察法第5条の改正や婦人参政権を求める運動を展開しました。
正しい文はbとdなので、その組み合わせである④が正解です。
問2:正解⑤
<問題要旨>
20世紀前半から半ばにかけての日本の社会主義運動とその弾圧に関する出来事を、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
I:1925年に制定された治安維持法により、特に満州事変(1931年)後は社会主義運動への弾圧が強化され、獄中で思想を放棄する「転向」が相次ぎました。
II:日本共産党の幹部らが公職追放され、民間企業でも共産主義者が解雇された「レッド=パージ」は、第二次世界大戦後の1949年から1950年にかけて、GHQの指令のもとで行われました。
III:片山潜や幸徳秋水らが日本で最初の社会主義政党である社会民主党を結成したものの、治安警察法により即日解散させられたのは1901年のことです。
したがって、起こった順は III → I → II となります。
問3:正解①
<問題要旨>
ジャーナリスト石橋湛山の社説(史料1)を読み、第一次世界大戦後の日本の対外政策に関する彼の主張とその歴史的背景を考察する問題です。
<選択肢>
①【正】
Xの「石橋湛山は、ワシントン会議の開催に際して、日本の植民地を放棄するべきだと主張している」は、史料1で彼が「朝鮮・台湾・満州を棄てる」と具体的に述べていることから正しいです。Yの「史料1が発表された時には、日本はシベリアに出兵していた」も、史料1が書かれた1921年当時は、1918年から始まったシベリア出兵がまだ続いていたため、正しいです(撤兵は1922年)。したがって、X、Yともに正しいので、この選択肢が正解です。
②【誤】
Yは正しいです。
③【誤】
Xは正しいです。
④【誤】
X、Yともに正しいです。
問4:正解①
<問題要旨>
日中戦争から太平洋戦争の終結にかけての重要な出来事に関する空欄補充問題です。中国に樹立された傀儡政権の首班と、日本の降伏に関する手続きを正確に理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【正】
ア:1940年、日本は南京に親日的な国民政府(傀儡政権)を樹立させましたが、その主席は国民党から離反した「汪兆銘」でした。イ:1945年8月にポツダム宣言を受諾した日本は、9月2日に東京湾上のアメリカ戦艦ミズーリ号上で「降伏文書に調印」しました。したがって、この組み合わせが正しいです。
②【誤】
イが誤っています。ポツダム宣言の受諾は降伏文書調印の前です。
③【誤】
アが誤っています。蔣介石は日本の敵対勢力である重慶国民政府の主席でした。
④【誤】
ア、イともに誤っています。
問5:正解②
<問題要旨>
太平洋戦争(大東亜戦争)中の日本の政治・軍事について述べた文の中から、誤っているものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
日本政府は、欧米の植民地支配からアジアを解放し、日本を盟主とする「大東亜共栄圏」を建設することを、この戦争の目的として国内外に宣伝しました。
②【誤】
戦時下においても、帝国議会は形式的には存続していました。ただし、ほとんどの議員が大政翼賛会に所属し、政府の決定を追認するだけの「翼賛議会」と化しており、政府をチェックする機能は失われていました。議会が「停止」されたわけではありません。
③【正】
1942年6月のミッドウェー海戦で、日本海軍は主力空母4隻を失うという大敗を喫しました。これを境に、日本は太平洋における戦いの主導権を失い、戦局は悪化の一途をたどりました。
④【正】
東条英機内閣は、1943年に「大東亜共栄圏」の結束を内外に示すため、日本の勢力下にあったアジア各地域の代表者(フィリピン、ビルマ、満州国など)を東京に招き、大東亜会議を開催しました。
問6:正解①
<問題要旨>
作家・高見順の日記(史料2)と、彼が読んだ新聞記事(史料3)を比較し、戦時下の報道(大本営発表)に対する知識人の批判的な視点を読み解く問題です。
<選択肢>
a【正】高見順は日記に「敵に明らかに押されているのだ。敗けているのだ。なぜそれが率直に書けないのだ」と記しており、新聞記事が戦局の劣勢を正確に伝えていないと批判していることが分かります。
b【誤】高見順は日本の戦局が「敗けている」と認識しており、優勢であるとは考えていません。
c【正】史料3の記事には「現在戦線は…油田地帯にかけて拡大せんとしつつあり」とあり、タラカンの油田地帯付近で戦闘が行われていると報じています。
d【誤】史料3は、日本軍が「敵兵力の二割弱に当る千五百名を殺傷している」と報じています。これは日本軍の戦果を述べたものであり、日本軍の兵力が敵より少ないと述べているわけではありません。
正しい文はaとcなので、その組み合わせである①が正解です。
問7:正解③
<問題要旨>
第二次世界大戦後の出版文化と社会の動向に関する正誤を判断する問題です。戦前の文学運動や、戦後のメディアの発達について、時代を混同せずに理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
Xが正しく、Yが正しいとする選択肢です。Xは誤りです。
②【誤】
Xが正しく、Yが誤りとする選択肢です。Xは誤り、Yは正しいです。
③【正】
Xの「プロレタリア文学運動が始まり、『種蒔く人』が創刊された」のは、第一次世界大戦後の1920年代のことであり、敗戦後ではありません。Yの「高度経済成長のなかでマスメディアが発達し、週刊誌の発行部数が増加した」は正しい記述です。テレビの普及とともに、大衆の消費生活や娯楽への関心が高まり、『週刊新潮』などが創刊され人気を博しました。したがって、Xは誤り、Yは正しいので、この選択肢が正解です。
④【誤】
Xが誤り、Yが誤りとする選択肢です。Yは正しいです。