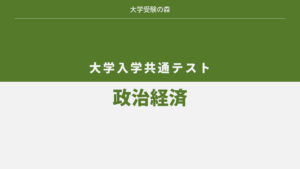解答
解説
第1問
問1:正解①
<問題要旨>
ケインズとフリードマンの経済思想について、政府の役割に関する考え方の違いを正しく理解できているかを問う問題です。それぞれの思想家が「自由放任」や「市場への介入」をどのように捉えていたかがポイントとなります。
<選択肢>
①【正】
まず、二人の思想家の立場を整理します。ケインズは、市場の自動調整機能に任せる「自由放任」では大規模な失業などが解決されないと考え、政府が公共事業などを行う「裁量的な政策介入」によって有効需要を創出し、経済を安定させるべきだと主張しました。これに対し、フリードマンは新自由主義の立場から、ケインズ的な政府の介入はかえって経済を不安定化させるとして批判し、市場原理を重視する「小さな政府」を主張しました。
この対比からメモの空欄を考えます。ケインズが主張したのは「イ:裁量的な政策介入」による補完です。そして、フリードマンが批判したのは、その「イ:裁量的な政策介入」が拡大した状況です。したがって、イには「裁量的な政策介入」が入ります。
次にアとウを考えます。アはケインズが自由放任を批判する記述、ウはフリードマンが政府介入を批判する記述です。この組合せに合うのは、記述aがケインズの主張、記述bがフリードマンの主張となる選択肢①です。
②【誤】
イが「市場での競争」である点が誤りです。ケインズは、政府の政策介入によって「市場での競争」がもたらす問題を補完する必要があると考えました。
③【誤】
アとウに当てはまる記述が逆です。この選択肢では、記述bがケインズの主張、記述aがフリードマンの主張となりますが、それではメモの文脈と一致しません。
④【誤】
イが「市場での競争」である点、およびアとウに当てはまる記述が逆である点、両方が誤りです。
問2:正解⑤
<問題要旨>
日本の国税収入の内訳を示すグラフから所得税、法人税、消費税を特定し、それぞれの税の特徴に関する記述と正しく結びつけることができるかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
組合せが誤っています。
②【誤】
組合せが誤っています。
③【誤】
組合せが誤っています。
④【誤】
組合せが誤っています。
⑤【正】
まず、グラフのウは1990年度の7.4%から2019年度には29.5%へと構成比が著しく増加しています。これは1989年に導入され、その後税率が引き上げられてきた消費税であると判断できます。消費税は付加価値税の一種であり、軽減税率も導入されているため、記述bと対応します。
次に、直接税であるアとイを判断します。記述cは、所得に応じて税率が高くなる「累進課税制度」に言及しており、これは所得税の特徴です。記述aは、企業の国際競争力強化を目的とした減税について述べており、これは法人税の特徴です。日本の税収の根幹をなすのは所得税であり、一般的に法人税よりも税収割合が高いため、割合の大きいアが所得税(記述c)、イが法人税(記述a)と判断できます。
したがって、「ア-c」「イ-a」「ウ-b」の組合せが正しいです。
⑥【誤】
組合せが誤っています。
問3:正解③
<問題要旨>
日本の財政制度(一般会計、特別会計、政府関係機関予算、財政投融資、暫定予算、補正予算など)に関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
国が特定の事業を行う場合などに設けられる会計は「特別会計」です。「一般会計」は、国の基本的な経費を計上する中心的な会計です。
②【誤】
政府関係機関予算は、政府が全額出資する特殊法人のうち、政策的に重要な機関の予算です。これは一般会計や特別会計と同様に、国会の議決を経る必要があります。
③【正】
財政投融資は、「第二の予算」とも呼ばれ、かつては郵便貯金や年金積立金を原資としていました。現在は、国債の一種である財投債の発行などによって調達した資金を財源とし、政策的な必要性のある事業(中小企業支援や社会資本整備など)に投融資を行っています。
④【誤】
年度の途中で当初予算に追加や変更を行う場合に組まれる予算は「補正予算」です。「暫定予算」は、年度開始までに本予算(当初予算)が成立しない場合に、数か月程度の期間を限って編成される暫定的な予算です。
問4:正解③
<問題要旨>
1980年代のアメリカで問題となった「双子の赤字(財政赤字と貿易赤字)」について、グラフから正しく読み取ることができるかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
図の組合せが誤っています。
②【誤】
図の組合せが誤っています。
③【正】
1980年代、レーガン政権下のアメリカは「強いアメリカ」を掲げ、大規模な減税と軍事費の拡大を行いました。これにより、歳入が伸び悩む一方で歳出が増大し、財政赤字が拡大しました。この状況を示すのは、歳出(濃い色の棒)が歳入(薄い色の棒)を一貫して上回っている「図イ」です。
また、財政赤字と並行して、高金利政策などによりドル高が進行し、輸出が伸び悩み輸入が増加したため、貿易赤字も拡大しました。経常収支は、貿易収支、サービス収支、第一次所得収支、第二次所得収支から構成されますが、その中でも貿易収支の赤字が大幅に拡大したことが経常収支赤字の主因でした。この状況を示すのは、貿易収支(最も下の濃い色の部分)が大幅なマイナス(赤字)となっている「図ウ」です。
④【誤】
図の組合せが誤っています。
問5:正解⑤
<問題要旨>
問題文のメモから、国際政治におけるNGO(非政府組織)の役割を正しく読み取る問題です。本文に書かれている具体例と選択肢の記述を照らし合わせて判断します。
<選択肢>
①【誤】
アとウが正しいため、アのみを選ぶこの選択肢は不十分です。
②【誤】
イは誤りです。NGOは条約を遵守しない国に対して、報告書を提出して問題点を指摘することはできますが、国家のような強制力を持つわけではなく、是正措置を「命令する」ことはできません。
③【誤】
アとウが正しいため、ウのみを選ぶこの選択肢は不十分です。
④【誤】
イが誤りであるため、この組合せは誤りです。
⑤【正】
ア:気候変動枠組み条約の例で「交渉の経緯や進捗状況を報告する」とあり、これは交渉過程の透明性を確保する役割を果たしているといえます。
ウ:対人地雷全面禁止条約の例で「人道上の見地から対人地雷の廃止を訴えた」とあり、これは国際社会が取り組むべき課題を示し、条約成立を後押ししたといえます。
したがって、アとウはメモの内容から読み取れる正しい記述です。
⑥【誤】
イが誤りであるため、この組合せは誤りです。
⑦【誤】
イが誤りであるため、この組合せは誤りです。
問6:正解④
<問題要旨>
都道府県と市町村の民生費の内訳を示した2つのグラフから、各費用の金額や構成比の変化・比較を正確に読み取り、誤った記述を選択する問題です。
<選択肢>
①【正】
図1(都道府県)を見ると、2000年度から2019年度にかけて、社会福祉費は1005億円→2538億円、老人福祉費は1597億円→3329億円と、いずれも2倍以上に増加しています。児童福祉費は1169億円→1899億円と金額は増加していますが、構成比は28.5%→23.2%と下がっています。記述は正しいです。
②【正】
図2(市町村)を見ると、2000年度から2019年度にかけて、児童福祉費は3217億円→8575億円と2倍以上に増加しています。社会福祉費(27.9%→25.0%)、老人福祉費(23.2%→18.2%)、生活保護費(17.9%→17.1%)はいずれも金額は増加していますが、構成比は下がっています。記述は正しいです。
③【正】
図1(2019年度都道府県)の構成比は、老人福祉費(40.7%)>社会福祉費(31.0%)>児童福祉費(23.2%)の順です。図2(2019年度市町村)の構成比は、児童福祉費(39.4%)>社会福祉費(25.0%)>老人福祉費(18.2%)の順です。記述は正しいです。
④【誤】
2019年度の民生費総額は、市町村(21兆7867億円)が都道府県(8兆1829億円)の2倍以上になっています。しかし、各費用の金額を見ると、老人福祉費は市町村(3962億円)が都道府県(3329億円)の2倍以上にはなっていません。したがって、この記述は誤りです。
問7:正解①
<問題要旨>
国連の安全保障機能について、安全保障理事会(安保理)だけでなく、総会が果たしてきた役割にも着目し、その具体的な内容を正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【正】
2022年4月、国連総会は、安保理の常任理事国が拒否権を行使した場合、総会でその理由を説明するよう求める決議を採択しました。これは、拒否権の行使を牽制し、安保理の機能不全を少しでも改善しようとする総会の役割を示す事例です。
②【誤】
新戦略兵器削減条約(新START)は、アメリカとロシアの二国間条約であり、国連総会が採択したものではありません。
③【誤】
安保理が機能しない場合に、総会が平和維持のための措置を勧告できる「平和のための結集」決議がありますが、その採択には加盟国の「3分の2以上」の賛成が必要です。「過半数」ではありません。
④【誤】
湾岸戦争(1991年)の際に多国籍軍の武力行使を容認する決議を採択したのは、国連総会ではなく「安全保障理事会」です。
問8:正解⑤
<問題要旨>
国家が自国の領域に対して持つ権利(領域主権)の具体的な内容を、国際法の観点から正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
アとウが正しいため、アのみを選ぶこの選択肢は不十分です。
②【誤】
イは、他国の領域主権を侵害する行為であり、国際法上認められません。犯罪人の引き渡しは、国家間の条約に基づいて行われるのが原則です。
③【誤】
アとウが正しいため、ウのみを選ぶこの選択肢は不十分です。
④【誤】
イが誤りであるため、この組合せは誤りです。
⑤【正】
ア:自国の領域(領海を含む)内にある人や物に対して排他的に支配権(警察権など)を行使する例であり、正しいです。
ウ:自国の領域を使用・処分する権利の一例として、国際機関にその一部を使用させる(事務局の設置を認める)ことは正しいです。
したがって、アとウは国家の領域主権の行使例として正しいです。
⑥【誤】
イが誤りであるため、この組合せは誤りです。
⑦【誤】
イが誤りであるため、この組合せは誤りです。
第2問
問1:正解⑥
<問題要旨>
経済指標における「ストック」と「フロー」の概念を理解し、「国富」がどのように定義されるかを問う問題です。
<問題要旨>
①【誤】
国富は「ストック」の指標です。フローは一定期間内の経済活動の流れ(例:GDP)を示す指標です。
②【誤】
国富は「ストック」の指標です。
③【誤】
国富は「ストック」の指標です。また、国富の計算には「対外純資産」を用います。
④【誤】
国富は「ストック」の指標です。また、国富の計算には「対外純資産」を用います。
⑤【誤】
国富は表中の「正味資産」にあたります。「総資産」には国内の金融資産と負債が含まれており、これらは国内で相殺されるため国富には含めません。
⑥【正】
国富は、ある一時点において国全体で蓄積された富の量を示す「ストック」指標です。国富の計算は、国内の資産から負債を差し引いて行います。具体的には、土地や建物、機械設備などの「非金融資産」と、海外に対する債権から債務を差し引いた「対外純資産(海外純資産)」の合計で表されます。表において、「正味資産」は総資産から負債を引いたものであり、これが国富に相当します。したがって、アはストック、イは対外純資産、ウは正味資産となります。
⑦【誤】
国富の計算には「対外純資産」を用います。「外貨準備」は、通貨当局が保有する外貨建て資産のことであり、対外純資産の一部ではありますが、イにはより包括的な対外純資産が入るのが適切です。
⑧【誤】
国富の計算には「対外純資産」を用います。また、国富は「正味資産」にあたります。
問2:正解②
<問題要旨>
循環型社会の形成に不可欠な「3R」(リデュース、リユース、リサイクル)の概念を、図と具体例から正しく理解し、結びつけることができるかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
組合せが誤っています。
②【正】
ア:生産段階での投入を減らす→リデュース(発生抑制)→ a
イ:処理された廃棄物が生産に戻る→リサイクル(再生利用)→ c
ウ:消費されたものが廃棄されずに再び消費に戻る→リユース(再使用)→ b
したがって、正しい組合せは「ア-a」「イ-c」「ウ-b」です。選択肢②が正解となります。
③【誤】
組合せが誤っています。
④【誤】
組合せが誤っています。
⑤【誤】
組合せが誤っています。
⑥【誤】
組合せが誤っています。
問3:正解③
<問題要旨>
財政赤字や国債の問題について、財政規律を重視する立場(緊縮財政派)と、積極的な財政出動を是とする立場(積極財政派)のそれぞれの主張を正しく理解する問題です。
<選択肢>
①【誤】
△△氏の主張は、財政赤字を問題視し、将来世代への負担を懸念する緊縮財政派の立場です。そのため、アには「歳出削減と増税により基礎的財政収支(プライマリー・バランス)を黒字化」すべき、という主張(b)が入るのが自然です。
②【誤】
△△氏の主張は緊縮財政派であるため、アにaが入るのは不適切です。また、○○氏の主張は、日本国債の保有者がほとんど国内であることから、財政破綻のリスクは低いというものであり、イには「国内」(c)が入ります。
③【正】
△△氏の主張は、財政赤字を問題視し、将来世代への負担を懸念する緊縮財政派の立場です。そのため、アには財政健全化を目指す「歳出削減と増税により基礎的財政収支(プライマリー・バランス)を黒字化」(b)が入ります。一方、○○氏の主張は、積極財政を肯定する立場で、日本国債はそのほとんどが「国内」の経済主体に保有されているため、債務不履行(デフォルト)のリスクは極めて低いと述べています。したがって、イには「国内」(c)が入ります。
④【誤】
○○氏の主張は、日本国債の保有者がほとんど国内であることを根拠の一つとしているため、イに「国外」(d)が入るのは誤りです。
問4:正解⑦
<問題要旨>
第二次世界大戦後の国際経済体制の変遷、特にWTO体制の停滞とFTA/EPAの増加という流れについて、歴史的背景や用語の知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
日本の最初のEPA相手国はアメリカではなく、シンガポールです。
②【誤】
日本の最初のEPA相手国はシンガポールです。また、イが「計画経済」である点も誤りです。
③【誤】
日本の最初のEPA相手国はシンガポールです。
④【誤】
日本の最初のEPA相手国はシンガポールです。また、イが「計画経済」である点、ウが「減少」である点も誤りです。
⑤【誤】
イが「計画経済」である点が誤りです。ブロック経済は、世界恐慌後、本国と植民地などで排他的な経済圏を形成する動きで、第二次世界大戦の一因とされます。
⑥【誤】
イが「計画経済」である点、ウが「減少」である点も誤りです。
⑦【正】
日本が初めてEPA(経済連携協定)を締結した相手国は、2002年の「シンガポール」です(ア)。FTA/EPAのような特定の国・地域間での自由貿易協定が、非締約国を排除する動きにつながると、第二次世界大戦の一因ともなった「ブロック経済」の再来が懸念されます(イ)。WTOの多角的貿易交渉(ドーハ・ラウンド)が停滞した背景には、発展途上国など交渉に参加する国や地域が「増加」(ウ)し、利害調整が困難になったことがあります。
⑧【誤】
ウが「減少」である点が誤りです。WTO(GATT時代から含む)の加盟国は一貫して増加傾向にあります。
問5:正解⑥
<問題要旨>
日本の経済協力や国際交流について、EPA(経済連携協定)やODA(政府開発援助)に関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
日本はASEAN全体とEPAを締結しています。また、国境なき医師団は民間のNGOであり、政府のODAとは異なります。
②【誤】
国境なき医師団は民間のNGOであり、政府のODAとは異なります。
③【誤】
日本はASEAN全体とEPAを締結しています。また、国境なき医師団は民間のNGOです。
④【誤】
日本はASEAN全体とEPAを締結しています。
⑤【誤】
国境なき医師団は民間のNGOです。
⑥【正】
日本は「ASEAN(東南アジア諸国連合)」全体とのEPAを締結しており、さらにフィリピンやインドネシアなど加盟国と個別の二国間EPAを結び、看護師や介護福祉士候補者を受け入れています(ア)。また、発展途上国への援助として、政府は「日本のODA(政府開発援助)を行う国際協力機構(JICA)を通じた技術協力や無償資金協力など」を実施しています(イ)。記述dの「国境なき医師団」は民間のNGOであり、政府のODA実施機関ではありません。
問6:正解③
<問題要旨>
外国人との共生社会をテーマに、「バリアフリー」の概念や、外国人労働者の労働法規上の扱いについての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
アが「デジタル・デバイド」である点が誤りです。「デジタル・デバイド」とは、インターネットなどの情報通信技術を利用できる人とできない人との間に生じる格差のことです。
②【誤】
アが「デジタル・デバイド」である点、イが「外国人労働者には、労働基準法が適用されない」である点が誤りです。
③【正】
国籍や言語の違いにかかわらず、誰もが情報を得やすくしたり、社会生活上の障壁を取り除いたりすることを、情報保障やユニバーサルデザインの観点を含めて広く「バリアフリー」と呼びます(ア)。また、日本国内で働く労働者には国籍を問わず日本の労働関係法規が適用されるため、「外国人労働者にも、労働者災害補償保険(労災保険)が適用される」(イ)というのは正しい記述です。労働基準法なども同様に適用されます。
④【誤】
イが「外国人労働者には、労働基準法が適用されない」である点が誤りです。日本の労働基準法は、国籍を問わず、日本国内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
問7:正解③
<問題要旨>
日本の「食の安心・安全」に関する制度や消費者の行動についての基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
アのみを選ぶこの選択肢は不十分です。
②【誤】
イは誤った記述です。
③【正】
ウの記述は正しいです。トレーサビリティとは、食品などの生産から加工、流通、販売に至るまでの履歴情報を追跡できる仕組みのことです。BSE(牛海綿状脳症)問題などを契機に導入が進みました。
④【誤】
アとイはいずれも誤った記述です。
⑤【誤】
アは誤った記述です。
⑥【誤】
イは誤った記述です。
⑦【誤】
アとイはいずれも誤った記述です。
【各記述の正誤】
ア【誤】食品安全基本法に基づき、食品の安全性について科学的・中立的な評価(リスク評価)を行うために設置された機関は「食品安全委員会」です。「消費生活センター」は、消費者からの相談受付や情報提供などを行う地方公共団体の機関です。
イ【誤】環境への負荷が少ない製品を優先的に購入する消費者を「グリーン・コンシューマー」と呼びます。自身の健康を最優先に栄養バランスを考慮する行動は、これとは異なります。
ウ【正】記述の通り、食品などの生産・加工・流通の履歴を明らかにする仕組みをトレーサビリティといいます。
問8:正解⑤
<問題要旨>
社会保障制度の歴史的発展について、イギリスのエリザベス救貧法、ベバリッジ報告、ILOのフィラデルフィア宣言の思想的な位置づけを正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
組合せが誤っています。
②【誤】
組合せが誤っています。
③【誤】
組合せが誤っています。
④【誤】
組合せが誤っています。
⑤【正】
ア:17世紀の「エリザベス救貧法」は、教会の慈善事業に代わり、国家が救貧の責任を負うとした画期的な法律ですが、労働能力のない貧民の救済をあくまで「国家の恩恵」として位置づけ、労働を強制する側面もありました。したがって、cが入ります。
イ:20世紀のイギリス「ベバリッジ報告」は、「ゆりかごから墓場まで」をスローガンに、国民が最低限度の生活(ナショナル・ミニマム)を送る権利を「国家の責任において」保障すべきと提言し、現代の社会保障制度の基礎を築きました。したがって、aが入ります。
ウ:1944年の「フィラデルフィア宣言」は、ILO(国際労働機関)が採択したもので、社会保障の充実を国際的な原則として位置づけ、基本的人権として保障する考え方を世界的に広めました。したがって、bが入ります。
よって、「ア-c」「イ-a」「ウ-b」の組合せが正しいです。
⑥【誤】
組合せが誤っています。
第3問
問1:正解③
<問題要旨>
日本国憲法における天皇の地位と権能(国事行為)に関する正確な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長官を任命します。「国会の指名」ではありません(憲法第6条2項)。
②【誤】
憲法改正の公布は天皇の国事行為ですが、改正の発議や国民投票の要件に関する記述が誤っています。憲法改正には、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票で有効投票の「過半数」の賛成が必要です(憲法第96条)。「4分の3以上」ではありません。
③【正】
日本国憲法第4条1項は「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と定めています。また、第3条では、天皇のすべての国事行為には「内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」と定められています。記述は正しいです。
④【誤】
アとイが誤りです。
⑤【誤】
アが誤りです。
⑥【誤】
イが誤りです。
⑦【誤】
アとイが誤りです。
問2:正解①
<問題要旨>
第二次世界大戦後の武力紛争の形態の変化をグラフから読み取り、その背景にある歴史的な出来事(冷戦の終結など)と関連づけて考察する問題です。
<選択肢>
①【正】
ア:グラフを見ると、冷戦期(1950年~1980年代末)から冷戦後(1990年以降)まで一貫して、「国内紛争」(斜線部分)の件数が「国家間紛争」(白抜きの部分)の件数を上回っています。したがって、「冷戦期以降一貫して…『国内紛争』の割合は、『国家間紛争』の割合よりも高い」という記述aは正しいです。
イ:1990年代前半に「国内紛争」が増加した背景には、冷戦の終結によって東西のイデオロギー対立の枠組みが崩壊し、それまで抑えられていた民族・宗教対立が表面化したことがあります。その代表例が、旧ユーゴスラビア連邦の崩壊に伴う「ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争」です。したがって、記述cは正しいです。
記述dの「シリア紛争」のような「アラブの春」に伴う紛争は2010年代以降の出来事であり、1990年代前半の紛争増加の要因としては時期が合いません。
②【誤】
イの記述が誤っています。シリア紛争は2010年代の出来事です。
③【誤】
アの記述が誤っています。グラフから、「冷戦期以降一貫して」国内紛争の割合が高いことが読み取れます。「冷戦終結後になって初めて」ではありません。
④【誤】
ア、イともに記述が誤っています。
問3:正解⑥
<問題要旨>
国連PKO(平和維持活動)への各国の部隊派遣人数の推移を3つの時点の表から読み取り、メモの記述と照らし合わせて国名(ア)と年(エ)を特定する問題です。
<選択肢>
①【誤】
組合せが誤っています。
②【誤】
組合せが誤っています。
③【誤】
組合せが誤っています。
④【誤】
組合せが誤っています。
⑤【誤】
組合せが誤っています。
⑥【正】
まず、空欄アを特定します。メモには「アは紛争中にはPKOを派遣される側の国であったが、紛争後は…PKOに部隊を多く派遣するようにもなった」とあります。1994年に大規模なジェノサイドが発生したルワンダでは、国連PKOが派遣されましたが(派遣される側)、その後、経済成長を遂げ、近年はアフリカ諸国の中でもPKOへの主要な部隊派遣国となっています。一方、ソマリアは依然として国内情勢が不安定です。したがって、アは「ルワンダ」と判断できます。
次に、イ、ウ、エの年を特定します。メモに「日本の部隊派遣人数は減少した」とあります。表を見ると、日本は表1で680人、表3で4人、表2で0人となっています。このことから、派遣人数が多かった表1が最も古く、減少した後の表3が最も新しい時点と考えられます。表1の日本の680人という派遣人数は、カンボジアPKO(1992-93年)などへの大規模派遣を反映していると考えられます。したがって、イが「1990年」(正しくは1992年頃の状況を反映しているが選択肢から判断)、ウが「2002年」、エが「2022年」と推測できます。
ルワンダ(ア)が派遣人数0人から5,929人(第2位)へと大きく増加していることから、表3が紛争後のルワンダの状況を示していることがわかります。この表3が最も新しい「2022年」(エ)であることも、この推論を裏付けます。
したがって、「ア-ルワンダ」「エ-2022年」の組合せが正しいです。
問4:正解④
<問題要旨>
日本の国会の制度と権能(委員会、憲法審査会、両議院の関係、国政調査権など)に関する正確な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
委員会は、重要な議案について公聴会を開くことができますが、すべての法律案について「必ず開催しなければならない」わけではありません。必要に応じて開催されます。
②【誤】
憲法審査会は、憲法および憲法に密接に関連する基本法制について調査を行い、憲法改正原案などを審査する機関です。法律や命令が憲法に違反するかどうかを最終的に判断する権限(違憲審査権)を持つのは、裁判所(特に最高裁判所)です。
③【誤】
予算の先議権と内閣不信任決議権が衆議院に認められているのは正しいですが、参議院に「法律案の先議権」は定められていません。法律案はどちらの議院から先に審議してもかまいません。
④【正】
憲法第62条は、両議院がそれぞれ「国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」と定め、国政調査権を保障しています。これは、議院が立法や行政監督の機能を果たすために重要な権能です。
問5:正解④
<問題要旨>
日本における差別解消に関連する法律(部落差別解消推進法、ヘイトスピーチ解消法、アイヌ施策推進法、障害者雇用促進法)の内容について、誤っている記述を選択する問題です。
<選択肢>
①【正】
同和対策事業特別措置法などが失効した後も部落差別が依然として存在することから、その解消を推進する目的で、2016年に部落差別解消推進法が制定されました。正しい記述です。
②【正】
特定の民族や国籍の人々に対する差別的言動(ヘイトスピーチ)が社会問題化したことを受け、その解消に向けた取り組みを推進する目的で、2016年にヘイトスピーチ解消法が制定されました。正しい記述です。
③【正】
1997年のアイヌ文化振興法に代わり、2019年に制定されたアイヌ施策推進法は、前文でアイヌの人々を「先住民族」と初めて法律に明記し、総合的な施策を推進することを目的としています。正しい記述です。
④【誤】
障害者雇用促進法は、障害者の雇用機会の確保を図るため、民間企業、国、地方公共団体のすべてに対して、従業員数に一定の割合(法定雇用率)を乗じた人数以上の障害者を雇用することを義務づけています。「企業には義務づけていない」という部分が誤りです。
問6:正解①
<問題要旨>
日本の最高裁判所が、法律の規定を憲法違反(違憲)と判断した判例に関する問題です。判決の対象となった法律、争点、および関連する憲法の条文を正しく組み合わせているものを選択します。
<選択肢>
①【正】
1987年の共有林分割制限規定違憲判決です。最高裁判所は、共有林の分割請求を制限する森林法の規定が、目的達成のために必要とはいえない過度の制約であるとして、財産権を保障する憲法第29条に違反すると判断しました。
②【誤】
2013年の婚外子相続分差別規定違憲決定です。最高裁判所は、婚外子(非嫡出子)の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定が、法の下の平等を保障する憲法第14条に違反すると判断しました。「生存権」(憲法第25条)ではありません。
③【誤】
1975年の薬局距離制限規定違憲判決です。最高裁判所は、薬局の開設に距離制限を設ける薬事法の規定が、不良医薬品の供給防止という目的達成のために合理的・必要とはいえず、職業選択の自由を保障する憲法第22条に違反すると判断しました。「法の下の平等」(憲法第14条)ではありません。
④【誤】
衆議院議員定数配分規定に関する判決(違憲状態判決など)で問題となるのは、一票の価値の格差であり、これは投票価値の平等を定めた憲法第14条(法の下の平等)に違反するかが争点となります。「職業選択の自由」(憲法第22条)ではありません。
問7:正解⑤
<問題要旨>
国際的な人権保障の枠組みである、世界人権宣言や国際人権規約に関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
アとウが正しいため、アのみを選ぶこの選択肢は不十分です。
②【誤】
イは誤りです。
③【誤】
アとウが正しいため、ウのみを選ぶこの選択肢は不十分です。
④【誤】
イが誤りです。
⑤【正】
ア:1948年に国連総会で採択された世界人権宣言は、人権保障の国際的な基準を示しましたが、法的拘束力はありませんでした。その内容を条約として具体化し、締約国に法的拘束力を持たせたものが、1966年に採択された国際人権規約(社会権規約と自由権規約)です。記述は正しいです。
ウ:日本は社会権規約を批准する際、財源の問題などから高等教育の漸進的無償化の条項などを留保していましたが、2012年にこの留保を撤回しました。記述は正しいです。
⑥【誤】
イが誤りです。
⑦【誤】
イが誤りです。
【イの正誤】
イ【誤】国連では、1965年に「人種差別撤廃条約」、1979年に「女子差別撤廃条約」が採択されており、どちらも日本は批准しています。「人種差別の撤廃についてはいまだ条約は採択されていない」という記述は誤りです。
問8:正解③
<問題要旨>
発展途上国が抱える経済問題である「南北問題」と「南南問題」について、その歴史的背景や関連する用語の知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
アは誤りです。
②【誤】
イは誤りです。
③【正】
ウの記述は正しいです。「南南問題」とは、発展途上国(南)の間で生じている経済格差の問題です。1970年代以降、NIES(新興工業経済地域)のように工業化に成功した国・地域が現れる一方で、依然として開発が遅れている後発発展途上国(LDC)も存在し、その格差が問題となっています。
④【誤】
アとイは誤りです。
⑤【誤】
アは誤りです。
⑥【誤】
イは誤りです。
⑦【誤】
アとイは誤りです。
【各記述の正誤】
ア【誤】モノカルチャー経済とは、特定の一次産品の生産や輸出に依存する経済のことです。「工業製品」ではありません。植民地時代に宗主国の都合で形成されたこの経済構造が、多くの途上国の経済的自立を妨げる一因となりました。
イ【誤】南北問題の協議を行うために1964年に創設された国連の常設機関は「国連貿易開発会議(UNCTAD)」です。プレビッシュはUNCTADの初代事務局長です。「国連開発計画(UNDP)」は、発展途上国への技術協力などを中心に行う機関です。
ウ【正】記述の通りです。
第4問
問1:正解②
<問題要旨>
知的財産権(特に著作権)を保護する目的や、その根拠となる財の性質(非競合性)についての理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
組合せが誤っています。
②【正】
ア:創作物などの知的財産は、ある人が利用(消費)しても、他の人が利用できる量が減るわけではありません。このような性質を「非競合性」といいます。これは公共財が持つ性質の一つです。したがって、記述aは正しいです。
イ:知的財産権(著作権)を保護する理由として、創作者個人の権利を守るだけでなく、創作活動を奨励することで新たな著作物が生まれ、社会全体の文化が豊かになるという考え方があります。これは「文化発展という公益を促進する手段として著作権を保護する」(記述d)という功利主義的な考え方であり、会話文の流れに合致しています。
③【誤】
組合せが誤っています。
④【誤】
組合せが誤っています。
問2:正解⑤
<問題要旨>
第二次世界大戦後の日本の産業構造の変化を、時期(高度経済成長期、安定成長期、1990年代以降)と内容(重化学工業化、知識集約化など)で正しく整理し、産業別就業者割合のグラフと結びつける問題です。
<選択肢>
①【誤】
組合せが誤っています。
②【誤】
組合せが誤っています。
③【誤】
組合せが誤っています。
④【誤】
組合せが誤っています。
⑤【正】
メモの内容を時系列で整理します。
・高度経済成長期:軽工業から鉄鋼や石油化学などの「重化学工業への転換」(b)が進みました。
・1970年代以降の安定成長期:自動車や電機などの「加工組立型産業や知識集約型産業への転換」(c)が進み、国際競争力を高めました。
・1990年代以降の課題:経済のサービス化・ソフト化が進む中で、従来型産業に代わる新産業の育成が課題とされています。「製造業において従来型の電機などに代わる新産業の発展、第三次産業において次代を担いうる新産業の発展」(a)が十分に進んでいないことが指摘されています。
したがって、メモの空欄は、時期の古い順にイがc、ウがaとなります。
次に、グラフを見ます。Aは2002年から2022年にかけて就業者割合が大きく減少しています。これは、海外への生産拠点移転や国際競争の激化が進んだ「製造業」(e)と考えられます。一方、Bは割合が大きく増加しており、高齢化の進展などを背景に需要が拡大している「医療,福祉」(d)と判断できます。
したがって、イにc、Bにdの組合せが正しいです。
⑥【誤】
組合せが誤っています。
問3:正解④
<問題要旨>
道路運送法改正を例に、政府による産業への規制緩和とその後の再規制の動きについて、長文の資料からその経緯や趣旨を正確に読み取る問題です。
<選択肢>
①【誤】
アとイが正しいため、アのみを選ぶこの選択肢は不十分です。
②【誤】
アとイが正しいため、イのみを選ぶこの選択肢は不十分です。
③【誤】
ウは誤りです。
④【正】
ア:改正前の法律には「需給調整要件」があり、供給が需要を上回らないように新規参入が制限されていました。そのため、個人に安全運行能力があっても、この要件によって参入できない可能性がありました。記述は正しいです。
イ:乗合バス事業について、規制緩和後も地方公共団体が補助金を出して路線を維持していることや、独占禁止法特例法が制定されたことから、収支が厳しくても国民生活の基盤として存続が求められていることが読み取れます。記述は正しいです。
⑤【誤】
ウは誤りです。
⑥【誤】
ウは誤りです。
⑦【誤】
ウは誤りです。
【ウの正誤】
ウ【誤】タクシー事業については、過当競争による安全性やサービスの質の低下が懸念されたため、2013年の法改正により、特定地域での新規参入や増車の禁止、運賃変更命令といった行政による介入(再規制)が行われるようになりました。「市場による解決に委ねられており、行政は介入しない」という記述は誤りです。
問4:正解⑧
<問題要旨>
企業の生産拠点の海外移転(産業の空洞化)が、自国の輸出入や貿易収支に与える影響(輸出代替効果、輸出誘発効果、逆輸入効果、輸入転換効果)を論理的に考察する問題です。
<選択肢>
①~⑦【誤】
組合せが誤っています。
⑧【正】
ア(輸出代替効果):A国内で生産して輸出していた製品をB国の拠点で生産するようになると、A国からの輸出は「減少」します。
イ(輸出誘発効果):B国の生産拠点に、A国から部品や資本財を送るため、A国からの輸出は「増加」します。
ウ(逆輸入効果):B国で生産した製品をA国に輸入するため、A国の輸入は「増加」します。
エ(輸入転換効果):A国で生産するために輸入していた原材料が不要になるため、A国の輸入は「減少」します。
オ:当初貿易収支が均衡(輸出額=輸入額)していたと仮定します。「輸出代替効果」(輸出の減少)が「輸入転換効果」(輸入の減少)より大きい場合、輸出の減少幅が輸入の減少幅を上回るため、貿易収支は「赤字化」します。
カ:「輸出誘発効果」(輸出の増加)が「逆輸入効果」(輸入の増加)より小さい場合、輸出の増加幅が輸入の増加幅を下回るため、貿易収支は「赤字化」します。
したがって、ア減少、オ赤字化、カ赤字化の組合せが正しいです。
問5:正解⑥
<問題要旨>
新しい技術やビジネスモデルで成長を目指すベンチャー企業について、その設立や資金調達に関連する日本の制度の知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
アは誤りです。
②【誤】
イとウが正しいため、イのみを選ぶこの選択肢は不十分です。
③【誤】
イとウが正しいため、ウのみを選ぶこの選択肢は不十分です。
④【誤】
アは誤りです。
⑤【誤】
アは誤りです。
⑥【正】
イ:大学の研究成果を事業化する「大学発ベンチャー」など、先端技術を基盤とするベンチャー企業は多く存在します。記述は正しいです。
ウ:ベンチャー企業にとって資金調達は重要な課題であり、その受け皿として、東京証券取引所のマザーズ(現・グロース)市場のような新興企業向けの株式市場が整備されてきました。記述は正しいです。
⑦【誤】
アは誤りです。
【アの正誤】
ア【誤】2006年に施行された会社法により、最低資本金制度が撤廃され、株式会社の設立が容易になりました。また、新たに合同会社(LLC)という会社形態も導入されました。しかし、この会社法の施行に伴い、「有限会社」は新たに設立できなくなりました(既存の有限会社は特例有限会社として存続)。「有限会社の新規設立条件が緩和された」という部分が誤りです。
問6:正解③
<問題要旨>
イノベーションを促進するための国の政策について、「特区(特別区域)」制度や、社会人の学び直しを指す「リスキリング」といった現代的な用語の知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
アが「広域連合」である点、イが「リスキリング」ではない点が誤りです。「広域連合」は、複数の地方公共団体が行政サービスを共同で行うための制度です。
②【誤】
アが「広域連合」である点が誤りです。
③【正】
ア:国が特定の地域を限り、規制緩和などの特例措置を認める制度を「特区(特別区域)」といいます。構造改革特区や国家戦略特区などがあります。
イ:技術革新やビジネスモデルの変化に対応するため、社会人が新しい知識やスキルを学ぶことを「リスキリング」と呼び、政府も支援策を打ち出しています。
④【誤】
イが「テクノクラート」である点が誤りです。「テクノクラート」とは、高度な科学技術の専門知識を持つ官僚や技術者のことを指します。