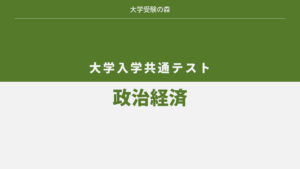解答
解説
第1問
問1:正解⑥
<問題要旨>
1980年代以降の先進国でみられた、政府の役割を小さくしようとする動き(新自由主義的な改革)と、その具体例としての日本の行政改革についての理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
アの「大きな政府」が誤りです。サッチャー政権やレーガン政権が目指したのは、市場原理を重視し、政府の介入を減らす「小さな政府」です。
②【誤】
アの「大きな政府」が誤りです。サッ…
③【誤】
アの「大きな政府」が誤りです。サッチャー政権やレーガン政権が目指したのは、市場原理を重視し、政府の介入を減らす「小さな政府」です。
④【誤】
イの記述が誤りです。日本郵政公社は2003年に発足し、2007年に日本郵政株式会社などに分割民営化されました。本文の「株式会社が…公社に改編される」という記述は、民営化の流れとは逆であり、事実とも異なります。
⑤【誤】
イの記述が誤りです。日本道路公団は2005年に民営化され、NEXCO各社となりました。本文の「独立行政法人から特殊法人に改組される」という記述は、民営化とは異なる上、事実関係も誤っています。
⑥【正】
ア・イともに正しい記述です。サッチャー政権やレーガン政権は、新自由主義の考え方に基づき、規制緩和や民営化を進める「小さな政府」を目指しました。日本でも同様の動きとして、中曽根康弘内閣の下で行政改革が進められ、その一環として1987年に日本国有鉄道(国鉄)がJR各社へ分割民営化されました。
問2:正解③
<問題要旨>
電力事業のように、生産のための初期投資が非常に大きい産業において、生産量の増加に伴ってコストが下がり、結果的に少数の企業による独占・寡占が起こりやすくなる現象を指す経済用語を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
外部不経済とは、ある経済活動が市場を通さずに第三者へ悪影響を及ぼすこと(例:工場の排煙による大気汚染)を指します。巨大設備投資とコストの関係を説明するものではありません。
②【誤】
非競合性と非排除性は、公共財(例:警察、消防)がもつ性質です。非競合性はある人が消費しても他の人が消費できる量は減らないこと、非排除性は対価を支払わない人を消費から排除できないことです。問題の趣旨とは異なります。
③【正】
規模の経済とは、生産規模を拡大すればするほど、製品1単位あたりの平均費用が低下していく現象のことです。巨大な生産設備が必要な産業ではこの傾向が強く、大規模な企業ほど有利になるため、新規参入が難しくなり自然独占が生じやすいとされます。本文の記述と合致します。
④【誤】
情報の非対称性とは、取引を行う当事者間で、持っている情報に量や質の差がある状態を指します(例:中古車の売り手と買い手)。巨大設備投資とコストの関係を説明するものではありません。
問3:正解③
<問題要旨>
日本の無担保コールレート(短期金利の指標)とマネタリーベース(日銀が供給する資金量)の推移を示したグラフから、日本銀行が行った金融政策との関係性を正しく読み取る力を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
1995年から1996年にかけて無担保コールレートは低下しています。金利を下げるためには、日本銀行が市場から国債などを買い入れて資金を供給する「買いオペレーション」を行う必要があります。「売りオペレーション」は金利を引き上げる操作であるため、誤りです。
②【誤】
2008年から2010年にかけて、無担保コールレートは0%に近い水準で推移しています。これはゼロ金利政策がとられている状態を示します。ゼロ金利政策が「解除」されたのではなく、リーマンショックを受けて再導入・維持されていた時期にあたるため、誤りです。
③【正】
2013年からマネタリーベースが急激に増加しています。これは、2013年4月に黒田東彦日銀総裁のもとで導入された「量的・質的金融緩和(異次元緩和)」によるものです。市場への資金供給量を大幅に増やすことでデフレ脱却を目指したこの政策により、マネタリーベースが拡大しました。
④【誤】
2020年から2021年にかけてマネタリーベースは増加し続けています。これは資金供給を継続していることを意味し、「買いオペレーション」に相当する金融緩和が行われていることを示します。「売りオペレーション」は市場から資金を吸収し、マネタリーベースを減少させる操作であるため、誤りです。
問4:正解⑦
<問題要旨>
現代の企業活動において重要となる「コーポレート・ガバナンス」「社会的責任投資(SRI)」「ISO(国際標準化機構)」に関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
イ、ウも正しい記述です。
②【誤】
ア、ウも正しい記述です。
③【誤】
ア、イも正しい記述です。
④【誤】
ウも正しい記述です。
⑤【誤】
イも正しい記述です。
⑥【誤】
アも正しい記述です。
⑦【正】
ア、イ、ウはいずれも正しい記述です。
ア:コーポレート・ガバナンス(企業統治)は、企業の不正行為を防ぎ、健全な経営を確保するために、株主などが経営者を監視・監督する仕組みのことです。
イ:社会的責任投資(SRI)は、投資家が企業の財務状況だけでなく、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)への配慮(ESG)を評価して投資先を選ぶ手法です。
ウ:国際標準化機構(ISO)は工業製品などの国際的な規格を定めており、その中でISO14001は、企業などの組織が環境に与える負荷を管理・低減するためのシステム(環境マネジメントシステム)に関する国際規格です。
問5:正解③
<問題要旨>
ジェンダー平等の実現に関する国際的な目標と、そのための具体的な制度についての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
アが誤りです。「ドーハ開発アジェンダ」は世界貿易機関(WTO)における多角的貿易交渉のことで、ジェンダー平等を直接の目標とするものではありません。
②【誤】
ア、イともに誤りです。イの「ショップ制」は、労働組合への加入を雇用条件とする制度のことであり、議席の割り当てとは関係ありません。
③【正】
ア、イともに正しい記述です。「持続可能な開発目標(SDGs)」は2015年に国連で採択された国際目標で、その目標5に「ジェンダー平等の実現」が掲げられています。また、政治分野における女性の参加を促進するため、議席や候補者の一部を女性に割り当てる制度を「クオータ制」と呼びます。
④【誤】
イが誤りです。「ショップ制」は労働組合に関する制度であり、文脈に合いません。
問6:正解⑤
<問題要旨>
日本の議院内閣制における衆議院の解散について、憲法の規定や関連する判例、解散後の手続きに関する正確な理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
イは誤った記述です。
②【誤】
イは誤った記述です。
③【誤】
アは正しい記述です。
④【誤】
イは誤った記述です。
⑤【正】
アとウが正しい記述です。
ア:衆議院の解散は、内閣不信任決議が可決された際の内閣の対抗措置として行われる場合(憲法69条)だけでなく、内閣の助言と承認により天皇の国事行為として行われる場合(憲法7条)があります。実際には、後者の「7条解散」が慣例として多く行われており、不信任決議を経ない解散が多数を占めます。
ウ:憲法54条には、衆議院解散後の手続きとして「解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない」と定められています。
(補足)イ:衆議院の解散のような高度に政治的な国家行為は、司法審査の対象になじまないとする考え方を「統治行為論」といいます。最高裁判所は苫米地事件においてこの理論を採用し、解散の合憲性について判断を避けました。「違憲と判断した」わけではないため、イは誤りです。
問7:正解①
<問題要旨>
租税法律主義や予算の国会議決など、国の財政を国民の代表である国会がコントロールするという「財政民主主義」の原則に関する理解を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
憲法84条は「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と定めています。これは租税法律主義と呼ばれ、財政民主主義の根幹をなす原則です。
②【誤】
予算案について衆議院と参議院が異なる議決をした場合、憲法60条に基づき両院協議会を開くことが定められています。必ず開く必要があるため、「開く必要はない」という記述は誤りです。
③【誤】
財政投融資は「第二の予算」とも呼ばれ、その計画は毎年、国の予算とともに国会に提出され、審議・議決を受ける必要があります。「国会への提出を必要としない」という記述は誤りです。
④【誤】
特別会計予算も国の予算の一部であり、一般会計予算と同様に、毎年度、国会の審議と議決を経る必要があります。「国会の審議と議決を必要としない」という記述は誤りです。
問8:正解④
<問題要旨>
現代社会におけるメディア・リテラシーの重要性と、国民の「知る権利」を保障する情報公開制度の基本的な仕組みについての理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
ア、イともに誤りです。
②【誤】
アが誤りです。
③【誤】
イが誤りです。
④【正】
ア、イともに正しい記述です。アの「メディア・リテラシー」は、様々な情報メディアを主体的に読み解き、批判的に吟味し、活用する能力を指します。SNSなどの情報があふれる現代において、その重要性は増しています。イの日本の情報公開法は、その第3条で「何人も、この法律の定めるところにより、…行政文書の開示を請求することができる」と定めており、国籍や年齢を問わず、だれでも請求権を持っています。
第2問
問1:正解④
<問題要旨>
需要と供給の法則について、特定の条件下での需要曲線・供給曲線の形状と、外的要因による曲線のシフトを正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
図aでは供給曲線(物件数を表す)が右上がりになっており、「物件数は増減しない」という条件に合いません。
②【誤】
図aは条件に合いません。また、家賃に応じて借り手の数が変わるため、需要曲線は右下がりの曲線fとなります。
③【誤】
図bは正しいですが、需要曲線は右下がりの曲線fです。
④【正】
「賃貸アパートの物件数は増減しない」ため、供給量は家賃に関わらず一定となり、供給曲線は垂直な直線(図bの曲線e)になります。一方、家賃が高ければ借りたい人は減り、安ければ増えるため、需要曲線は右下がりのグラフ(図bの曲線f)となります。この状況で「都心へのアクセスが便利になった」ことは、そのアパートに住みたい人が増える(需要が増加する)要因となるため、需要曲線fが右方へシフトすることで表現されます。
(※選択肢⑤~⑧も同様の理由で誤りです)
問2:正解④
<問題要旨>
一国の経済規模を示すGDP(国内総生産)という指標が持つ限界と、国民の真の豊かさを測るために考案された代替的な指標についての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
ウが誤りです。
②【誤】
イ、ウが誤りです。
③【誤】
イが誤りです。
④【正】
ア、イ、ウ全ての組み合わせが正しいです。
ア:一人当たりGDPは「GDP÷人口」で計算されるため、GDPが一定でも人口が減少すれば、一人当たりの数値は「増大」します。
イ:GDPは市場で取引された付加価値の合計であるため、市場を介さない環境破壊(森林の損失など)はGDPには算入されません(むしろ、災害復旧のための公共事業などはGDPを増やす要因になります)。
ウ:GNP(国民総生産)はGDPと類似の指標ですが、NNW(国民純福祉)は、GDPから公害などのマイナス要因を引き、家事労働などのプラス要因を加えることで、より生活の豊かさ(福祉)を測ろうとする代替指標の例です。
(※他の選択肢はア~ウのいずれかの組み合わせが誤っているため不正解)
問3:正解②
<問題要旨>
株式会社の基本的な仕組み(株主の権利)、所有と経営の分離、企業の社会的責任(CSR)といった、企業経営に関する重要概念の理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
ウが誤りです。「コンプライアンス」は法令遵守を意味します。慈善的な寄付行為は「フィランソロピー」にあたります。
②【正】
ア、イ、ウ全て正しい語句が入ります。株主は出資額に応じて「配当」を受け取る権利があります。大企業で所有(株主)と経営(経営者)が別人格となることを「所有と経営の分離」といいます。また、企業の慈善活動を「フィランソロピー」と呼び、これは企業の社会的責任(CSR)の一環とされます。
③【誤】
イ、ウが誤りです。「持株会社の解禁」は独占禁止法改正に関する事項であり、所有と経営の分離を指す言葉ではありません。
④【誤】
イが誤りです。
⑤【誤】
ア、ウが誤りです。株主が出資の見返りに受け取るのは「利子」ではなく「配当」です。
⑥【誤】
アが誤りです。
⑦【誤】
ア、イ、ウ全て誤りです。
⑧【誤】
ア、イが誤りです。
問4:解答④
<問題要旨>
財政が持つ機能(資源配分、所得再分配、景気安定化)について、具体例と機能の対応関係を正しく理解しているかを問う問題です。誤っている選択肢を選びます。
<選択肢>
①【正】
環境税は、環境に負荷を与える経済活動に課税することで、その活動を抑制し、より望ましい状態(再生可能エネルギーの普及など)へ資源配分を促す機能を持っています。これは「資源配分の調整機能」の例として正しい記述です。
②【正】
累進課税制度(所得が高いほど税率が高くなる)や公的扶助制度(生活困窮者に給付を行う)は、高所得者から低所得者へ富を移転させ、所得格差を是正する働きがあります。これは「所得の再分配機能」の例として正しい記述です。
③【正】
失業保険制度は、不況期に自動的に失業者への給付が増え、好況期には給付が減るため、社会全体の有効需要を下支えし、景気の変動を自動的に和らげる働きがあります。これは「ビルト・イン・スタビライザー(自動安定化装置)」の例として正しい記述です。
④【誤】
所得税の累進課税制度が景気を自動安定化させる仕組みは、③と同様に「ビルト・イン・スタビライザー」の一例です。不況期には所得が減り自動的に税率も下がる(または低い税率の適用範囲が広がる)ことで、可処分所得の減少を和らげます。一方、「フィスカル・ポリシー(裁量的財政政策)」とは、政府や議会がその都度の判断で公共事業を増やしたり減税したりする意図的な政策を指します。したがって、この記述は誤りです。
問5:正解③
<問題要旨>
金本位制からIMF体制、キングストン体制(変動相場制)へと至る国際通貨体制の変遷について、各体制における通貨と金との関係(兌換性)および為替相場の仕組みを正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
イ、ウ、エが誤りです。
②【誤】
イ、エが誤りです。
③【正】
ア~エの全ての組み合わせが正しいです。
金本位制:各国の通貨が金(ゴールド)との交換(兌換)を保証されており(ア:兌換)、通貨間の交換比率も金に基づいて決まるため(ウ:固定)相場制でした。
IMF体制:米ドルのみが金との兌換性を維持し、各国の通貨は米ドルを介して金と結びつく金ドル本位制でした。したがって、ドル以外の紙幣は金と直接交換できない(イ:不換)のが原則で、為替相場は固定相場制でした(ウ:固定)。
キングストン体制:ニクソン・ショックによるドルと金の兌換停止後、主要国は変動相場制に移行しました。通貨は金と交換できず(イ:不換)、為替相場は市場の需給で決まる(エ:変動)相場制です。
④【誤】
ウが誤りです。
(※他の選択肢はア~エのいずれかの組み合わせが誤っているため不正解)
問6:正解①
<問題要D旨>
日本の輸出相手国の割合の推移を示すグラフと、戦後の日米貿易摩擦や為替相場の歴史的出来事を結びつけて考える問題です。グラフの特定と出来事の時系列整理の両方が求められます。
<選択肢>
①【正】
まず、グラフのアは、2000年頃から急激に割合を伸ばし、近年ではアメリカに次ぐ主要な輸出相手国となっていることから「中国」であると判断できます。次に、メモの出来事を時系列に並べ替えます。
d:1980年代前半、円安・ドル高を背景に日本の対米輸出が急増し、貿易摩擦が激化しました。
b:行き過ぎたドル高を是正するため、1985年にプラザ合意が結ばれ、急激な円高ドル安が進行しました。その後、1987年にドル安の行き過ぎを抑えるための「ルーブル合意」がなされました。
a:1989年から「日米構造協議」、1993年から「日米包括経済協議」が開始され、非関税障壁などが議論されました。
c:日米間の貿易摩擦は1990年代半ばに一段落し、その後しばらくは大きな問題とはなりませんでした。
この順(d→b→a→c)で並べると、3番目にくるのは「メモa」です。したがって、アが中国、3番目がメモaの組み合わせが正しいです。
(※他の選択肢は、グラフの特定または時系列の整理が誤っているため不正解)
問7:正解②
<問題要旨>
4か国の所得格差(ジニ係数)と労働組合組織率のデータを比較した2つのグラフから、読み取れる内容を正しく判断する問題です。グラフの数値を丁寧に比較することが求められます。
<選択肢>
①【誤】
「所得格差は縮小し」という部分が誤りです。図1を見ると、4か国すべてにおいて、1980年(黒い棒)よりも2019年(灰色の棒)の方がジニ係数は大きく(高く)なっており、所得格差は拡大しています。
②【正】
図2を見ると、1980年、2019年いずれの年も、スウェーデンとデンマークが労働組合の組織率で上位2か国です。次に図1を見ると、この2か国は、日本やアメリカに比べてジニ係数が低く、所得格差が小さいことがわかります。したがって、この記述はグラフから読み取れる内容として正しいです。
③【誤】
「所得格差は小さい」という部分が誤りです。図1を見ると、日本のジニ係数は、スウェーデンやデンマークよりも高く、特に2019年ではアメリカに次ぐ高さとなっており、この4か国の中では所得格差が小さいとは言えません。
問8:正解②
<問題要旨>
アプリを介して単発の仕事を請け負う「ギグワーカー」を題材に、彼らが日本の労働法制上どのような立場に置かれているか、また、労働問題を扱う公的機関は何かを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
イが誤りです。「国民生活センター」は、消費者問題に関する相談や情報提供を行う機関であり、労働問題の救済申し立て先ではありません。
②【正】
ア、イともに正しい語句が入ります。ギグワーカーが企業に雇用された「労働者」にあたるかどうかは、最低賃金法や労働組合法などの保護を受けられるかを左右する重要な論点です。企業側は雇用関係を否定することが多いですが、実態によっては労働者性が認められる場合があります。そして、企業(使用者)からの不当労働行為(団結権の侵害など)があった場合に、労働者が救済を申し立てる機関が、労・使・公益の三者で構成される「労働委員会」です。
③【誤】
ア、イともに誤りです。ギグワーカーはサービスを提供する側であり、受け取る側の「消費者」ではありません。
④【誤】
アが誤りです。
⑤【誤】
ア、イともに誤りです。ギグワーカーは「自営業者」に近い働き方ですが、労働者性の有無が争点となっています。
⑥【誤】
アが誤りです。
第3問
問1:正解⑤
<問題要旨>
刑事裁判における「疑わしきは被告人の利益に」という基本原則(証拠に基づいて合理的な疑いが残る場合は有罪としてはならない)を正しく理解し、具体的な事例に適用できるかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
イは原則に反しません。
②【誤】
イは原則に反しません。
③【誤】
アは原則に反します。
④【誤】
イは原則に反しません。
⑤【正】
アとウが原則に反する行為です。
ア:「合理的な疑いは残るものの、…可能性が高い」という理由で有罪判決を下しており、疑いが残る状態で有罪としているため、原則に反します。
ウ:「合理的な疑いが生じるにもかかわらず、…判決を下す」とあり、再審で無罪の可能性が出てきた(合理的な疑いが生じた)にもかかわらず有罪を維持しているため、原則に反します。
(補足)イ:「合理的な疑いを差し挟む余地はない」と判断して有罪判決を下すことは、証拠に基づき有罪であると確信した場合の判断であり、原則に反しません。
問2:正解④
<問題要旨>
国際法における条約と国際慣習法の違い、および日本の安全保障に関する基本政策(非核三原則)についての理解を問う会話文問題です。
<選択肢>
①【誤】
ア、イともに誤りです。
②【誤】
アが誤りです。
③【誤】
イが誤りです。
④【正】
ア、イともに正しい記述の組み合わせです。
ア:条約は締約国のみを拘束しますが、多くの国々で長年行われている慣行が法的効力を持つに至ったものを「国際慣習法」といい、これは原則として全ての国を拘束します。「領海の無害通航権」は国際慣習法として確立しているため、アメリカが国連海洋法条約の締約国でなくても、この権利を尊重する義務があります。
イ:日本が核兵器を搭載した艦船の領海通航を認めないのは、「持たず、作らず、持ち込ませず」から成る「非核三原則」という国是に基づいています。
問3:正解②
<問題要旨>
近代私法の基本原則である「契約自由の原則」と、その原則が制限される場合(公序良俗違反)についての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
イが誤りです。「過失責任の原則」とは、他人に与えた損害について、故意または過失がある場合にのみ賠償責任を負うという原則であり、契約の効力とは直接関係ありません。
②【正】
ア、イともに正しい語句です。アの「契約自由の原則」とは、個人が自由な意思に基づいて契約を締結できるという、私的自治の原則の中核をなすものです。しかし、その契約内容がイの「公序良俗(公の秩序又は善良の風俗)」に反する場合、その契約は民法第90条により無効とされます。
③【誤】
ア、イともに誤りです。「消費者主権」は、消費者の選択が企業の生産活動を方向づけるという経済上の考え方です。
④【誤】
アが誤りです。
問4:正解②
<問題要旨>
国内法である法律と、国際法である条約の効力関係についての学説、および条約の国会承認手続きや、条約批准に伴う国内法整備の具体例に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
イが誤りです。
②【正】
ア、イともに正しい語句の組み合わせです。
ア:日本は1985年に「女性差別撤廃条約」を批准するにあたり、それまで父系の血統のみを認めていた「国籍法」を1984年に改正し、父母両系血統主義に改めました。
イ:憲法第73条で条約の締結は内閣の権限とされ、国会の承認が必要です。この承認手続きについては、憲法第61条で「予算の議決」に関する衆議院の優越規定が準用されると定められています。
③【誤】
ア、イともに誤りです。「育児休業法」の制定は1991年で、女性差別撤廃条約批准(1985年)後のことです。「憲法の改正」手続きは準用されません。
④【誤】
アが誤りです。
問5:正解③
<問題要旨>
日本の司法制度における違憲法令審査権(違憲審査権)の担い手と、その行使のあり方(付随的違憲審査制)についての正確な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
アが誤りです。
②【誤】
ア、イともに誤りです。
③【正】
ア、イともに正しい記述の組み合わせです。
ア:日本の違憲審査権は、最高裁判所だけでなく、全ての「下級裁判所」も持っています。これを裁判所全体の権限とする考え方がとられています。
イ:日本の違憲審査制は「付随的違憲審査制」と呼ばれ、具体的な訴訟事件を解決するために必要な限度においてのみ、法律などが憲法に違反していないかを判断します。具体的な事件とは無関係に法律の合憲性を判断する「抽象的違憲審査制」は採用されていません。
④【誤】
イが誤りです。
問6:正解②
<問題要旨>
国際刑事裁判所(ICC)が、その規程の締約国ではない国の国家元首に対しても手続を開始できた理由を、具体的な事例から推論する問題です。
<選択肢>
①【誤】
例2は国連安保理の付託ではありません。
②【正】
ICCが管轄権を行使できるのは、原則として締約国で起きた犯罪などですが、例外があります。例1のダルフール紛争(スーダン)については、国連安全保障理事会が事態をICCに「付託」したため、スーダンが非締約国でも手続が開始できました。例2のウクライナでの戦争犯罪については、ウクライナ自身が非締約国でありながらICCの権限を受諾したため、ロシアが非締約国であっても、ウクライナ領内での犯罪についてプーチン大統領に逮捕状が発付されました。
③【誤】
例1と例2の理由が逆になっています。
④【誤】
例1は犯罪行為地国による権限受諾ではありません。
問7:正解①
<問題要旨>
プライバシーの権利や知る権利といった「新しい人権」に関連する日本の法制度(個人情報保護法、特定秘密保護法など)の内容について、正しい記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
個人情報保護法は、本人に自己に関する情報の開示を請求する権利(開示請求権)だけでなく、その情報に誤りがあった場合に訂正を求める権利(訂正請求権)や、不適切な利用を停止させる権利(利用停止請求権)も保障しています。
②【誤】
プライバシーを侵害された場合、民法上の不法行為として損害賠償を請求できるだけでなく、人格権に基づき、将来の侵害行為の差止めを請求することも判例で認められています。
③【誤】
特定秘密保護法は、国の安全保障に関する特に重要な情報を「特定秘密」として指定し、その漏えいを罰する法律であり、国民の知る権利を「保障する」というよりは、むしろ「制限する」側面が強いと指摘されています。
④【誤】
通信傍受法は、一定の重大犯罪の捜査において、裁判所の令状など厳格な要件のもとで、捜査機関が通信を傍受(盗聴)することを認めています。「一律に禁じられている」わけではありません。
問8:正解⑥
<問題要旨>
難民条約の条文を読み解き、条約上の「難民」の定義、締約国が難民に対して負う義務(ノン・ルフールマン原則、教育を受ける権利)について正しく理解する問題です。
<選択肢>
①【誤】
アは誤った記述です。
②【誤】
ア、ウは正しい記述です。
③【誤】
アは誤った記述です。
④【誤】
アは誤った記述です。
⑤【誤】
アは誤った記述です。
⑥【正】
イとウが資料から読み取れる内容として正しいです。
イ:第33条は、難民をその生命や自由が脅かされるおそれのある国へ追放・送還してはならないと定めており(ノン・ルフールマン原則)、理由として「宗教」も挙げられています。
ウ:第22条1項で、初等教育については自国民と同一の待遇(内国民待遇)を与える義務が、同条2項で、初等教育以外については「できる限り有利な待遇」を与えることとされており、内国民待遇までは義務づけられていません。
(補足)ア:第1条の定義は、迫害を受けるおそれがあることを理由としており、貧困を理由とする「経済難民」は含まれません。また、「国籍国の外にいる者」とされているため、「国内避難民」も含まれません。したがってアは誤りです。
第4問
問1:正解④
<問題要旨>
民主主義国家の政治体制を「選挙制度の比例性」と「執政制度の権力集中度」という二つの軸で分類し、アメリカ、イギリス、ドイツを正しく位置づける問題です。
<選択肢>
①【誤】
ア、イ、ウの配置が誤っています。
②【誤】
ア、イ、ウの配置が誤っています。
③【誤】
ア、イ、ウの配置が誤っています。
④【正】
ア、イ、ウの配置が正しいです。
ア:イギリスは、小選挙区制(比例性が低い)と議院内閣制(権力が集中的)を組み合わせたウェストミンスター・モデルの典型です。
イ:ドイツは、比例代表制を重視した選挙制度(比例性が高い)と、議院内閣制(権力が集中的)を採用しています。
ウ:アメリカは、小選挙区制(比例性が低い)と、行政府と立法府が厳格に分離された大統領制(権力が分立的)を採用しています。
⑤【誤】
ア、イ、ウの配置が誤っています。
⑥【誤】
ア、イ、ウの配置が誤っています。
問2:正解③
<問題要旨>
社会主義経済体制の特徴である「生産手段の公有」と、中国が市場経済を導入する過程で採用した「経済特区」についての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
アが誤りです。社会主義経済では生産手段は「公有」されます。「私有」は資本主義経済の特徴です。
②【誤】
ア、イともに誤りです。「人民公社」は毛沢東時代に推進された農業集団化政策で、改革開放政策で解体されました。
③【正】
ア、イともに正しい語句です。社会主義経済では、土地や工場といった「生産手段」は、原則として国や共同体が所有する「公有」とされます。中国は1970年代末からの改革開放政策で、外国資本や技術を導入するために沿岸部に「経済特区」を設置し、市場経済化を進めました。
④【誤】
イが誤りです。
問3:正解④
<問題要旨>
「経済学の父」アダム・スミスの主著『国富論』における「見えざる手」の考え方と、彼が批判した「重商主義」についての基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
ア、イともに誤りです。
②【誤】
アが誤りです。
③【誤】
イが誤りです。
④【正】
ア、イともに正しい語句です。アダム・スミスは、各個人が自己の利益を追求する自由な経済活動を行えば、まるで「見えざる手」に導かれるかのように、結果として社会全体の利益(公共の利益)が達成されると主張しました。そして、国家が輸出の促進や輸入の抑制を通じて富(金銀)を蓄積しようとする「重商主義」政策を批判し、自由な競争こそが国を富ませると考えました。
問4:正解④
<問題要旨>
国連安全保障理事会(安保理)における決議採択数と拒否権行使回数の推移を示した表から、国際情勢の変化(特に冷戦の終結)が安保理の機能に与えた影響を読み解く問題です。
<選択肢>
①【誤】
ア、イともに誤りです。
②【誤】
アが誤りです。
③【誤】
イが誤りです。
④【正】
ア、イともに正しい語句の組み合わせです。
ア:表を見ると、1986~1990年の期間と1991~1995年の期間の間で、決議採択数が約3.5倍に急増し、拒否権行使回数が激減しています。これは米ソ対立の構図であった「冷戦」が1989年頃に終結し、常任理事国間の対立が緩和されたことで、安保理が機能しやすくなったことを示しています。
イ:2011年以降の拒否権行使の増加の一因として、中東の「シリア」内戦が挙げられます。アサド政権を支援するロシアと、反政府側を支援する欧米諸国との間で見解が対立し、ロシアなどが拒否権を頻繁に行使しました。
問5:正解③
<問題要旨>
核兵器禁止条約の策定をめぐる各国の立場の違いを、「核保有国」「核の傘下にある国」「非核兵器地帯の国」というそれぞれの役割に即して理解する問題です。
<選択肢>
①【誤】
イ、ウが誤りです。
②【誤】
イ、ウ、オが誤りです。
③【正】
イ、ウともに正しい組み合わせです。
準備資料1:アは「メキシコ」。トラテロルコ条約はラテンアメリカ非核兵器地帯条約であり、メキシコはこれを主導した国の一つです。核兵器の非人道性を訴え(イ-b)、条約を推進する立場です。
準備資料2:ウは「フランス」。フランスはNPTで認められた核兵器国であり、自国の核抑止力が平和を保つと主張し(エ-a)、核兵器禁止条約には反対の立場です。
準備資料3:オーストラリアはアメリカの「核の傘」の下にあり、核廃絶の理想は認めつつも、核保有国が参加しない条約の実効性に疑問を呈し(オ-c)、交渉開始は時期尚早という立場をとります。
④【誤】
イが誤りです。
⑤【誤】
ウが誤りです。
⑥【誤】
イ、ウが誤りです。
問6:正解②
<問題要E旨>
経済思想家であるトマ・ピケティとアマルティア・センの格差是正に関する主張を正しく理解し、会話文に当てはめる問題です。
<選択肢>
①【誤】
イが誤りです。
②【正】
ア、イともに正しい組み合わせです。
ア:メモにあるように、ピケティは資産から得られる収益率(r)が経済成長率(g)を上回ることで格差が拡大すると指摘し、その是正策として「資産」に対するグローバルな累進課税を提唱しました。
イ:センは、人々が「なろうとするものになれる」「したいことができる」可能性、すなわち「潜在能力(ケイパビリティ)」を発揮できる機会を平等にすることが重要だと考えました。そのためには、単にモノ(自転車など)を一律に配るだけでなく、それを使える環境(バリアフリーな道路など)を整えるといった、「個別の事情に目を配る」アプローチが必要だと主張しました。
③【誤】
ア、イともに誤りです。ピケティが課税対象として重視したのは「労働による所得」ではなく「資産」です。
④【誤】
アが誤りです。