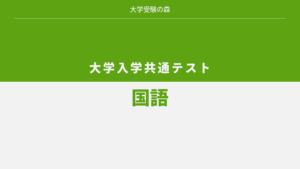解答
解説
第1問
問1:(ア)正解③ (イ)正解③ (ウ)正解① (エ)正解② (オ)正解④
<問題要旨>
傍線部のカタカナを漢字で正しく表記し、その漢字と同じ漢字が含まれている熟語を、選択肢の中から選ぶ問題です。漢字の知識が問われています。
<選択肢>
【ア:ジュンスイ】
①【誤】
「栄枯セイスイ」は「栄枯盛衰」です。「純粋」の漢字は含まれません。
②【誤】
「スイソクする」は「推測する」です。「純粋」の漢字は含まれません。
③【正】
傍線部の「ジュンスイ」は「純粋」と書きます。選択肢の「技術のスイを尽くす」の「スイ」は「粋」です。傍線部に含まれる「粋」という漢字が使われているため、これが正解です。
④【誤】
「スイチョク跳び」は「垂直跳び」です。「純粋」の漢字は含まれません。
【イ:コウソク】
①【誤】
「コウギする」は「抗議する」です。「拘束」の漢字は含まれません。
②【誤】
「コウショウをする」は「交渉をする」です。「拘束」の漢字は含まれません。
③【正】
傍線部の「コウソク」は「拘束」と書きます。選択肢の「ささいなことにコウデイする」の「コウデイ」は「拘泥」です。傍線部に含まれる「拘」という漢字が使われているため、これが正解です。
④【誤】
「コウミョウな駆け引き」は「巧妙な駆け引き」です。「拘束」の漢字は含まれません。
【ウ:ウリュウセイ】
①【正】
傍線部の「ウリュウセイ」は、文脈から「隆盛(勢いが盛んなこと)」と判断できます。選択肢の「地面がリュウキする」の「リュウキ」は「隆起」です。傍線部に含まれる「隆」という漢字が使われているため、これが正解です。
②【誤】
「ジリュウに乗る」は「時流に乗る」です。「隆盛」の漢字は含まれません。
③【誤】
「寺院をコンリュウする」は「寺院を建立する」です。「隆盛」の漢字は含まれません。
④【誤】
「健康にリュウイする」は「健康に留意する」です。「隆盛」の漢字は含まれません。
【エ:テイショウ】
①【誤】
「鉄道ハッショウの地」は「鉄道発祥の地」です。「提唱」の漢字は含まれません。
②【正】
傍線部の「テイショウ」は「提唱」と書きます。選択肢の「ガッショウ団に入る」の「ガッショウ」は「合唱」です。傍線部に含まれる「唱」という漢字が使われているため、これが正解です。
③【誤】
「ムショウで引き受ける」は「無償で引き受ける」です。「提唱」の漢字は含まれません。
④【誤】
「アンショウ番号」は「暗証番号」です。「提唱」の漢字は含まれません。
【オ:ハクメイ】
①【誤】
「ハクシキな人」は「博識な人」です。「薄明」の漢字は含まれません。
②【誤】
「勢いにハクシャをかける」は「勢いに拍車をかける」です。「薄明」の漢字は含まれません。
③【誤】
「ハクシンの演技」は「迫真の演技」です。「薄明」の漢字は含まれません。
④【正】
傍線部の「ハクメイ」は、文脈から「薄明(夜明け方のかすかな光)」と判断できます。選択肢の「根拠がハクジャクだ」の「ハクジャク」は「薄弱」です。傍線部に含まれる「薄」という漢字が使われているため、これが正解です。
問2:正解③
<問題要旨>
傍線部A「そこでは一人の人間の個別性はけっして存在しえない」と筆者が述べる理由を、本文の記述に基づいて理解する問題です。
<選択肢>
①【誤】
「任意の人間集団の特徴を体現したもの」という点が不正確です。本文では、キャラクターは「記号」の組み合わせであり、それによって個別性が失われると述べられていますが、特定の人間集団を代表するとは述べられていません。
②【誤】
「デッサンの技術に基づくことなく自己流で描かれており」という点は手塚自身の発言(本文12ページ)にありますが、それが直接「個別性が存在しえない」理由ではありません。理由は、表現がパターン化された「記号」の集積に還元されるからです。
③【正】
本文には「あらかじめこのような『記号』が存在し、そこにまた別の『記号』である男女や民族、年齢等を示すパターンが任意に組み合わされて、一人の人間が表現される」「表現された一人の人間はその感情も含めて記号の集積に還元されてしまう」とあり、キャラクターが類型化された要素(パターン、記号)の組み合わせであることが「個別性が存在しえない」理由だと説明されています。また、それらは「お話をつくる道具」として用いられると手塚が述べていることとも合致します。
④【誤】
「象形文字から発想を得た」というのは手塚のたとえ話であり、手法そのものではありません。「単純な線の集合で表現したもの」というだけでは、「個別性が存在しえない」理由の説明としては不十分です。
⑤【誤】
「細部の具体的な描写の集積によって作られており」という記述が本文の内容と逆です。手塚の絵は「非常に省略しきったひとつの記号」であると述べられています。
問3;正解③
<問題要旨>
傍線部B「〈記号〉として設計されたことと、汎世界化は不可分の関係として手塚は理解していた」と筆者が考える理由を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
「まんがから個性を除いて」という部分が不正確です。手塚は作者としての「個性」を「記号」という「無個性な言語」に還元したのであり、まんがのキャラクターから個性をなくしたわけではありません。
②【誤】
「作者としてのこだわりを持たず」「定型をふまえた」という表現は、本文で述べられている「作者の特権性の放棄」や「パターン」という言葉と関連しますが、傍線部の理由として最も重要な「歴史や文化との結びつきを絶った」という点が欠けています。
③【正】
本文で筆者は、手塚が自らのまんが表現を「いっさいそれを廃した人工言語として」「規定している」と述べ、それが「ことばの喚起する歴史的なイマジネーション」、すなわち「文化的な固有性」を拒絶した国際語であったと指摘しています。この固有性との結びつきがない「記号」だからこそ、文化や民族の壁を越えて「汎世界化」し得た、というのが筆者の論旨です。
④【誤】
「読者を意識した作品作り」については本文に明確な記述がありません。「作者の特権性を放棄」したことが、直接的に読者を意識したことには結びつきません。
⑤【誤】
「ジャパニメーションへと発展した」ことは結果であり、手塚が「記号」として設計した理由そのものではありません。また、「日本独自のものにとどまらない新たな表現」の具体的な内容、すなわち「歴史や文化と結びつかない」という点がこの選択肢では不明確です。
問4:正解④
<問題要旨>
【文章Ⅱ】の「記号のピラミッド」とメディアの発展に関する説明を正しく理解できているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
メディアの発展方向が逆です。本文には「個体や文化の場合とはちょうど逆の方向で進んできた」とあり、個体や文化はピラミッドの下層(指標)から上層(象徴)へ発展するのに対し、メディアは上層(象徴)から下層(指標)へと発展したと述べられています。
②【誤】
メディアの発展方向が逆であることと、「約束事を共有さえすれば」という部分が象徴記号の説明(上層)であり、メディアの発展のゴール(下層)とは異なるため、誤りです。
③【誤】
「イメージを複製する写真や映画」は類像(中間層)であり、メディアの発展の出発点ではありません。出発点は「文字の複製としての印刷術」、すなわち象徴(上層)です。
④【正】
本文には、メディアの発展が「文字の複製としての印刷術から、写真や映画といった…イメージの複製から、「いまここ」の出来事を構成するテレビを経て、一回的なものを複製する…デジタル技術へと変遷」したとあります。これはピラミッドの上層である「象徴(文字)」から、中間層の「類像(イメージ)」を経て、下層の「指標(接触、一回性)」へと向かう流れであり、選択肢の説明と合致します。
⑤【誤】
「具体的な場面の文脈に関わらず」という部分は、ピラミッドの上層である象徴記号の説明であり、メディアが向かっている下層(指標記号は文脈に埋め込まれている)の特徴とは異なります。
問5:正解②
<問題要旨>
傍線部C「〈キャラ〉は、そのような担保から切り離され、指標記号のレベルに接近したものである」の意味を説明する問題です。
<選択肢>
①【誤】
「消費者が既存の企業イメージを更新することができる」という点については、本文では述べられていません。〈キャラ〉は企業から「自立性」を獲得するとありますが、企業イメージを更新する役割を持つとは書かれていません。
②【正】
本文では、ロゴが「ブランド名を表す、アルファベットの文字要素を洗練化したVI」であり、象徴の次元に接している(担保がある)のに対し、〈キャラ〉は「ヒト化=人称化の力」を持ち、「それを作成した企業や、あるいは、それが登場する作品とは、無関係に独自の発展を遂げる」とあります。また、〈キャラ〉は「指標的」対象であり、指標記号は「接触(contact)」によって規定されるため、「それに接した人との間に直接的な関係を生み出し」という説明も妥当です。
③【誤】
ロゴが「特定の言語を共有する社会の内部で影響力を発揮する」とは限りません。アルファベットのロゴは国際的に通用します。また、〈キャラ〉が「情報を伝達するための道具」であるという側面よりも、本文では「コミュニケーションのvector」としての側面が強調されています。
④【誤】
ロゴが「企業や商品とは別にそれ自体が独立したシンボルとして流通する」という点が不正確です。ロゴは「企業や商品との関係を保持し続ける」ものです。〈キャラ〉はモノとの関係を断ち切るとされており、「企業や商品の価値を実感させつつ」という説明は本文の内容と合いません。
⑤【誤】
ロゴは「背景や状況を問わず消費者に同一の情報を伝達する」とは限りません。また、〈キャラ〉が「具体的な場面に即した交流の起点となり得る」という点は指標記号の特徴と合致しますが、ロゴとの対比において、選択肢②の説明の方がより本文の論旨を的確に捉えています。
問6:(1)正解① (2)正解④ (3)正解③
(1)空欄X:正解①
<問題要旨>
生徒Aの発言(空欄X)として、【文章Ⅰ】と【文章Ⅱ】のそれぞれの要旨を的確にまとめている選択肢を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
【文章Ⅰ】では、手塚のキャラクターが「文化的な固有性を拒絶した国際語」、すなわち「人工言語」的な性質を持ち、それによって「汎世界化」(普遍性)したと述べられています。【文章Ⅱ】では、〈キャラ〉が「指標的」対象であり、「それを作成した企業や…作品とは、無関係に独自の発展を遂げる」(自立性)と述べられています。この選択肢は両方の文章の要点を正しくまとめています。
②【誤】
【文章Ⅰ】で述べられているのはキャラクターの「普遍性」であり、「固有性」ではありません。また、【文章Ⅱ】では〈キャラ〉は類像に属しつつも「指標記号のレベルに接近したもの」とされており、「類像的性質」よりも「指標的性質」がその特徴として強調されています。
③【誤】
【文章Ⅰ】で述べられているのは「普遍性」であり、「固有性」ではありません。【文章Ⅱ】では、指標的性質から生まれるのは「自立性」であり、「親和性」は指標的である理由の一つとして述べられていますが、文章全体のテーマではありません。
④【誤】
【文章Ⅰ】でキャラクターの性質を「言語記号的」と表現するのは間違いではありませんが、「人工言語的」とする方がより筆者の主張に近いです。また、【文章Ⅱ】で〈キャラ〉の性質を「類像的性質」とするのは②と同様に不適切です。
(2)空欄Y:正解④
<問題要旨>
【文章Ⅱ】の内容を踏まえ、空欄Yに、読み手がキャラクターに思い入れを抱く理由となる〈キャラ〉の性質を説明する発言を入れる問題です。
<選択肢>
①【誤】
「自らの姿を投影することができる」という点については、本文に直接の記述がありません。
②【誤】
「〈顔〉にはモノとの関係を断ち切るはたらきがある」というのは、〈キャラ〉全体の特徴であり、〈顔〉単体の働きとして述べられているわけではありません。
③【誤】
〈キャラ〉との「対話」については、本文に記述がありません。「交話的(phatic)」とは、情報伝達よりも接触を確認する機能のことであり、必ずしも対話を意味しません。
④【正】
本文【文章Ⅱ】には、「われわれ人間は〈顔〉に対して、認知的親和性を持っている」「誕生直後の赤ん坊も〈顔〉的な対象に対して、特別な関心を示す」とあり、人間が〈顔〉を持つ存在に無条件に反応し、強く引きつけられる性質を持つことが述べられています。これが、インタビュアーがキャラクターに思い入れを抱いた理由を説明する根拠となります。
(3)空欄Z:正解③
<問題要旨>
【文章Ⅰ】と【文章Ⅱ】を総合的に理解し、手塚の意図(記号性)と読み手の反応(思い入れ)のずれを説明する発言を空欄Zに入れる問題です。
<選択肢>
①【誤】
「世界の人々に親しまれる個性的な特徴」と「日本固有の文化的な特徴」の二項対立は、本文の議論と異なります。手塚はむしろ「日本固有」の文化性を排したとされています。
②【誤】
「機械的な部分」と「人間的な部分」という対立は、本文で用いられていない独自の解釈です。本文のキーワード(記号、指標など)を使って説明する必要があります。
③【正】
手塚のキャラクターが持つ「特定の文脈を超えて広く流通し得る性質」は、【文章Ⅰ】で論じられた「記号」としての普遍性(汎世界化)に対応します。一方、「受容者がそれぞれの文脈で親しみを抱き得る性質」は、【文章Ⅱ】で論じられた〈キャラ〉の「指標的」性質(接触による直接的な関係、親和性)に対応します。この二つの性質を兼ね備えているからこそ、作者の意図を超えて、読み手が強い思い入れを抱くという現象が起こると説明できます。
④【誤】
「ストーリーを構成する要素」と「作品を代表するもの」という対立は、本文の議論の核心からずれています。特に【文章Ⅱ】で論じられた〈キャラ〉の指標性や親和性といった側面が考慮されていません。
第2問
問1:正解④
<問題要旨>
傍線部「男は鼻白んだ。」とあるが、その理由として男のどのような心情が考えられるかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
社長は「以前から会いたかった」と友好的に接しており、「なれなれしい態度」とは言えません。男が不快に感じたのは、話しかけられたこと自体ではなく、その内容です。
②【誤】
男が「鼻白んだ」のは、話しかけられて集中を邪魔されたからではありません。その後の社長のセリフの内容が直接の原因です。
③【誤】
社長は「職場の裏事情を知っているかのように」は振る舞っておらず、あくまで男が自ら会社を辞めて鳥の撮影に打ち込んでいる、と善意で解釈しているにすぎません。
④【正】
男が会社を辞めたのは「鳥のためではなかった」のに、社長は「会社をやめてまで鳥の撮影にうちこむのはちかごろ見上げた生き方だ」と、男の退職理由や生き方まで分かったかのように断定的に語っています。あまり親しくない相手に自分の内面を勝手に解釈されたことへの当惑や気まずさが「鼻白んだ」という反応につながっています。
⑤【誤】
社長は「放送局にまで押しかけて」はおらず、男の家を二、三度訪ねただけです。また、「生活を詮索しようとした」という悪意のある行動ではなく、写真集出版の話をするための訪問です。
問2:正解②
<問題要旨>
傍線部B「説明してもらいたい、と男はいった。」というセリフから、男の反応(心情や態度の変化)を的確に説明しているものを選択する問題です。
<選択肢>
①【誤】
社長の「強い意志を感じ取り」や、男が「企画に正面から向き合おうとしている」という段階にはまだ至っていません。この時点では、自分の写真集の話だと知って、まずは内容を聞いてみようという段階です。
②【正】
社長が写真集の話を切り出した当初、男は「それは結構だ」と「如才なく相槌をうった」だけで、真剣には聞いていませんでした。しかし、社長が「いや、あんたの写真集を出したいといってるんだよ」と言ったことで、自分に関わる話だと分かり、初めて関心を示して「説明してもらいたい」と応じています。この態度の変化を的確に説明しています。
③【誤】
「写真集を出す長年の願望」があったとは本文に書かれていません。また、この時点で「前向きになっている」とまでは言い切れません。
④【誤】
「積極的に説明を求めている」という表現は少し強すぎます。他人事だと思っていた話が自分事だと分かって、意外に感じながらもまずは話を聞こう、という冷静な反応と捉えるのが自然です。
⑤【誤】
「写真集が刊行される保証を得たと判断し」たわけではありません。まだ話の入り口に立ったばかりであり、興味を持ち始めた段階です。
問3:正解②
<問題要旨>
傍線部C「砂丘の上を歩きまわりながらしゃべりつづけた。」という社長の行動から、その時の社長の心情や様子を読み解く問題です。
<選択肢>
①【誤】
社長が「いら立った様子」を示しているというよりは、「昂奮した」様子です。また、訴えたいのは「自然界全体のバランス」というより、もっと身近な「鳥の世界でおこっている異変」です。
②【正】
社長は「鳥は狂ってるのだ」「そしてだれも鳥の世界でおこっている異見に気づかない」と昂奮しながら語っています。鳥たちの生態に起きている異変が世間に知られていないことへのもどかしさや危機感が、じっとしていられずに「歩きまわりながら」話すという行動に表れています。冷静ではいられないという様子を的確に捉えています。
③【誤】
「自然保護への使命感に燃える様子」とまでは言い切れません。社長の関心は、失われゆく「ここへやって来る鳥たちの記録写真」を残すことにあります。
④【誤】
社長の興奮は「写真集の企画に賛同してもらう機会を得たこと」から来ているのではありません。鳥の世界に起きている異変と、それを記録に残したいという思いから来ています。
⑤【誤】
社長は鳥の異変に「焦り、困惑した思い」を抱いているのではなく、その事実を指摘し、記録に残そうという強い意志を持っており、むしろ「昂奮」しています。
問4:正解⑤
<問題要旨>
傍線部D「なんという芝居気たっぷりのせりふだったろう、と男はにがにがしく回想した。」という記述から、写真集の一件をめぐる社長に対する男の受け止め方の変化を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
男が社長の主張に「同意してしまったこと」自体を不愉快に感じているわけではありません。不快感の対象は、社長の言動が結果的に中身のないものであったことです。
②【誤】
「他人の人生に関わる場面でも自分の善意に酔う自己顕示的なふるまい」という解釈は少し深読みしすぎています。男が感じているのは、もっと直接的に、社長の言葉が「わざとらしい」ものだったという点です。
③【誤】
社長の言葉を「思ってもいない出まかせ」とまでは断定できません。社長は本気だったかもしれませんが、会社の経営状況から結果的に実現できなかっただけ、という可能性も残ります。男の不快感は、社長の言葉と行動の「わざとらしさ」に向けられています。
④【誤】
男は社長の「焦りに気づけなかったこと」を不愉快に感じているわけではありません。不快感の矛先はあくまで社長の「芝居気たっぷり」な言動そのものです。
⑤【正】
当初、男は鳥のように両腕を広げる身ぶりまでして熱弁をふるう社長の姿に引き込まれていました。しかし、写真集の話が頓挫し、会社の倒産を知った後では、その言動が中身の伴わない「空疎でわざとらしい」ものであったと捉え直しています。その軽薄な言動に一時は同調してしまった自分を思い出し、「にがにがしく」感じているのです。
問5:正解③
<問題要旨>
傍線部E「自分は群から脱落した鳥の一羽かもしれぬ。しかしまだ飛ぶことはできる。」という男の独白から、その時の心情を読み取る問題です。
<選択肢>
①【誤】
「疎外感を覚えながらも」という部分は読み取れますが、「とどまることを知らない渡り鳥のように」という部分が不正確です。男は「翼を休める」鳥を肯定的に捉えており、休むことなく進むことを目指しているわけではありません。
②【誤】
「後ろめたさを感じながらも」という心情は本文からは読み取れません。男は休暇を「有効にすごした」と考えています。
③【正】
会社という「群から脱落した」自身の境遇に、社会からの逸脱や挫折感を感じつつも、「水辺に墜落した鳥」と自分を重ね、傷ついた鳥もやがて飛び立つように、自分にもまだ「飛ぶことはできる」力、すなわち再起する活力が残っていることを確認しています。「明日から新しい生活のために都会へ出発する」という状況とも合致しており、的確な説明です。
④【誤】
「社会で評価される機会を奪われたことに喪失感を覚えながらも」という点は、男の心情の核心ではありません。また、「未練がましく鳥を撮影すること」はしておらず、「シャッターをおさなかった」とあります。
⑤【誤】
「孤独に生きることにむなしさを覚えながらも」という心情は読み取れますが、「やはり一人で生きる道を求めなければならない」と決意しているわけではありません。「都会へ出発する」とあるように、再び社会の中に戻ろうとしています。
問6:(1)正解④ (2)正解⑤
(1)本文の時間の流れ:正解④
<問題要旨>
小説全体の時間の流れ(現在・過去の回想)を正しく説明している選択肢を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
「男はあの日」で移るのは、都会へ出発する現在の場面であり、過去の回想から現在に戻る場面です。
②【誤】
7行目を起点に過去に戻るのではなく、13〜14行目のノートをきっかけに過去の回想に入ります。
③【誤】
「男はあの日」で十一月一日に戻るのではなく、冒頭の現在(都会へ出発する日)に戻ります。
④【正】
冒頭は、男が河口で焚火をしている「現在」です。13〜14行目で「ノートに没頭した」ことをきっかけに、そのノートに記録された「十一月一日」の社長との出会いの場面の「過去の回想」に入ります。そして、68行目「男はあの日」という記述で、再び冒頭の「現在」の時間に戻り、回想を終えます。この時間の流れを正しく説明しています。
(2)男の描かれ方:正解⑤
<問題要旨>
この小説全体を通して、主人公の「男」がどのような人物として描かれているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
男は社長との関わりを通して、人間の本質を受け入れたというよりは、むしろ人間の言動の空疎さを再認識し、冷静に距離を置いています。
②【誤】
男は写真集の企画が頓挫しても絶望せず、「まだ飛ぶことはできる」と新たな生活へ出発しようとしており、「周囲の状況に埋もれていった」わけではありません。
③【誤】
「これまでの生き方を悔い」たり、「執着を断ち切った」りする様子は描かれていません。むしろ、自分の休暇期間を「有効にすごした」と肯定的に捉えています。
④【誤】
男は社長の言葉を最終的には「芝居気たっぷり」と否定的に捉えており、その言葉を真に「受けとめ」てはいません。
⑤【正】
男は、会社を辞めてから社長と出会い、写真集の話が立ち消えになるまでの一連の経験を、河口で静かに振り返っています。そして、社長の言動や自分自身の状況(群から脱落した鳥)を感情的にならずに冷静に分析し、捉え直した上で、未来へ向かおうとしています。
問7:(ⅰ)正解④ (ⅱ)正解③
(i)空欄:正解④
<問題要旨>
【Qさんの文章】の空欄に当てはまる、本文の表現技法の説明として最も適当なものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
括弧内の表現は、男の人生の「うつろいやすさ」だけでなく、「まだ飛ぶことはできる」という再起の意志も象徴しており、単にうつろいやすさだけを象徴しているのではありません。
②【誤】
括弧内の表現は、主に「男」自身の心情や状況を象徴しており、「男と社長の人生」全体を説明するものではありません。
③【誤】
括弧内の表現は、男が「自然に共感する姿勢」を示しているというより、自然の事象に自分自身の状況を重ね合わせて「象徴」的に捉えていることを示しています。
④【正】
「(潮流ってやつはいつかは変るのだ)」は、文字通り自然の潮流の変化を説明すると同時に、会社を辞めたり写真集の話がなくなったりといった男を取り巻く状況の変化を象徴しています。また、「(渡りの途中で、鳥も翼を休めるのだから)」は、鳥の生態を説明すると同時に、会社を辞めて休息期間を過ごす男自身の状況を象徴しています。このように、括弧内の表現が二重の意味を持っていることを的確に説明しています。
(ii)二つの文章の特徴:正解③
<問題要旨>
【Qさんの文章】と【Rさんの文章】のそれぞれの特徴を的確に述べ、両者の関係性を正しく説明している選択肢を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
Rさんの文章は、登場人物の会話から「自然環境の問題」という社会的な側面を読み取っており、「登場人物の心情を重視した読み方」とは言えません。
②【誤】
QさんとRさんは、着眼点(表現技法/会話内容)や読み取るテーマ(心情/社会問題)が異なっており、「類似した読み方」とは言えません。
③【正】
Qさんの文章は、「括弧を使って表されている箇所」という具体的な表現を根拠に、登場人物の心情を読み解いています。Rさんの文章は、「社長は…言及する」という具体的な会話を根拠に、本文に含まれる社会の問題(自然環境の問題)を浮かび上がらせています。両者ともに、本文の具体的な記述を「根拠」として自らの読解を述べており、その点を的確に説明しています。
④【誤】
Qさんの文章は、「多様な読み方の可能性」を示しているのではなく、括弧の表現が象徴として機能しているという明確な読み方を提示しています。Rさんの文章も、「社会的に結論づけている」わけではなく、作品から読み取れる一つのテーマとして自然環境の問題を提示しているにすぎません。
第3問
問1:(ア)正解④ (イ)正解⑤ (ウ)正解①
<問題要旨>
傍線部の古語の意味を文脈に即して正しく解釈する問題です。
<選択肢>
【ア:所知を賜べ】
①【誤】「金銀」ではありません。
②【誤】「計略」ではありません。
③【誤】「借金」の話は出てきません。
④【正】「所知(しょち)」は、中世において知行(支配)が認められた土地、つまり所領・領地のことです。「賜べ(たまべ)」は「賜ぶ」の命令形で「~ください」の意。夫を密告する見返りとして「領地をください」と要求している場面です。
⑤【誤】「知らせ」ではありません。
【イ:あらいたはしや】
①【誤】「無事」を喜んでいるのではありません。
②【誤】「信心深い」ことを言っているのではありません。
③【誤】「不快」に思っているのではありません。
④【誤】「役に立たない」と言っているのではありません。
⑤【正】「いたはし」は、相手を気の毒に思う、不憫に思うという意味の形容詞です。ここでは、落ちぶれた姿で帰ってきた夫の景清に対して(本心はともかく表面上は)「ああ、なんとお気の毒なことでしょう」と嘆いている場面です。
【ウ:けゆゆしくおはせしが】
①【正】「けゆゆし」は、見た目が立派だ、威厳がある、という意味の形容詞です。「おはせし」は、尊敬語「おはす(いらっしゃる)」の連用形+過去の助動詞「き」の連体形。平家の時代には「立派でいらっしゃったけれど」と、過去の栄華を偲ぶ言葉です。
②【誤】「不安そうに」という意味はありません。
③【誤】「みすぼらしい」は現在の景清の姿であり、過去の姿ではありません。
④【誤】「気味悪く」という意味はありません。
⑤【誤】「厳かに」という意味も含まれますが、ここでは見た目の立派さを指す意味合いが強いです。
問2:正解④
<問題要旨>
波線部の語句や表現に関する文法的な説明として正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
願望の終助詞「ばや」は、「(自分が)~したい」という自己の願望を表します。「誰かが~するのを願う」という他者への願望ではありません。
②【誤】
「参り」は謙譲語、「候ふ」は丁寧語です。このセリフは阿古王が頼朝に話している場面なので、話し手(阿古王)から聞き手(頼朝)への敬意(丁寧)を示しています。景清から観音菩薩への敬意を表すものではありません。
③【誤】
「聞こし召されて」の「聞こし召さ」は「聞く」の最高敬語であり、一つの単語です。「聞こす」と「召す」という二つの語から成るのではありません。頼朝の「お聞きになって」という動作を表す尊敬語です。
④【正】
「見慣れねば」の「ね」は、打消の助動詞「ず」の已然形です。下に接続助詞「ば」(~なので)が続いているため、活用形は已然形となります。「久しく会っていないので」という意味になり、説明は正しいです。
⑤【誤】
「さらば」は、接続詞で「それならば、それでは」という意味です。動詞「去る」の未然形ではありません。
問3:正解①
<問題要旨>
二重傍線部「思ひすました」とあるが、この時の阿古王がどのような考えに至ったのかを説明する問題です。
<選択肢>
①【正】
本文1段落に「包むとすると、このこと遂には洩れて討たれうず。(中略)このこと敵に知らせつつ、景清を討ち取らせ、二人の若を世に立てて、後の栄華に誇らむ」とあります。これは、夫をかくまってもどうせ見つかって討たれるだろう、それならばいっそ自ら密告して、子どもたちを出世させ、将来の栄華を手にしよう、と決心したことを示しており、選択肢の内容と一致します。
②【誤】
阿古王は「所知を賜べ」と要求しており、経済的に問題がないわけではありません。むしろ、報酬を得て「後の栄華」を誇ることを目的としています。
③【誤】
「自分も同罪とされる危険がある」とは本文に書かれていません。また、「子どもたちとを売り渡し」てもいません。
④【誤】
「子どもたちに景清を討たせて」という考えはありません。頼朝の軍勢に討たせようとしています。
問4:正解③
<問題要旨>
3段落における景清の行動や心情についての説明として、最も適当なものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
「四日路の道なるを、その日の暮れほどに」我が家に着いたとあるので、四日かかる道のりを一日で移動したことになりますが、到着したのは「十八日」当日ではなく、その前日の十七日の夕方と考えられます。「明日は十八日。清水へ参らばや」と思っているので、まだ十八日にはなっていません。
②【誤】
景清は子どもたちを見て「いとほしき子どもは並み居たり」と感じていますが、妻子を守ることと敵を討つことの間で葛藤している様子は描かれていません。
③【正】
「いとほしき子ども」「酌に立つたるは女房なり」という家族との再会の場面で、「いづくに心か置かるべき(どこに心配事などあろうか、いやない)」と思い、勧められるままに酒を飲み、「敵のことをばはつたと忘れ」て前後不覚になるほど酔ってしまいます。気を緩めてしまった様子を的確に説明しています。
④【誤】
景清は「清水へは明日参らうずるにて候ふ」と言っており、参詣を取りやめたわけではありません。また、運が尽きたのは、観音の怒りに触れたからではなく、妻の裏切りによって油断しきってしまったためです。
問5:(1)正解④ (2)正解①
(1)空欄X:正解④
<問題要旨>
『出世景清』における、十蔵と阿古屋の会話の内容を正しく要約している選択肢を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
阿古屋は「我が家が落ちぶれてしまったのも仕方がない」とは言っておらず、むしろ、落ちぶれたからこそ頼ってきている景清を裏切れない、と主張しています。
②【誤】
立て札に「親族も罰せられる」とは書かれていません。また、阿古屋は景清を「忠誠を誓った主君」とは言っていません。
③【誤】
十蔵は「北野天満宮に参詣していたおかげで」好機が来たと考えているのは事実ですが、阿古屋は「日本でも中国でも、夫を裏切るような非情な人はおらず」とは言っていません。
④【正】
十蔵は「我等が栄華の瑞相この時」「一かど御恩にあづからん」と言っており、景清を差し出して恩賞を得ようとしています。これに対し阿古屋は、平家の時代は勢いがあった景清が「今この御代にて候へばこそ、数ならぬ我々を頼みて御入り候ふものを」と言い、落ちぶれて自分たちを頼っている人を裏切ることはできない(「そもや訴人がなるべきか」)と反論しています。両者の主張を正しく要約しています。
(2)空欄Y:正解①
<問題要旨>
幸若舞『景清』と浄瑠璃『出世景清』を比較し、『出世景清』の作者が、新たに兄・十蔵という人物を登場させた意図を考察する問題です。
<選択肢>
①【正】
幸若舞『景清』では、妻の阿古王が自ら「二人の若を世に立てて、後の栄華に誇らむ」という現実的で打算的な考えに至り、夫を裏切ります。『出世景清』では、この打算的な役割を兄の十蔵に担わせ、妻の阿古屋は「人は一代名は末代」と述べ、夫への貞節を貫こうとする人物として描かれています。このように役割を分担することで、夫を裏切らない貞淑な妻・阿古屋の人物像をより鮮明に描き出す効果が生まれます。
②【誤】
「権力に追従する」や「地位や名誉を捨てても家族への愛を失わない」という表現は、本文の描写から読み取るにはやや行き過ぎた解釈です。
③【誤】
「北野詣で」は十蔵が行っており、信心深い性格が十蔵に移されたわけではありません。また、阿古屋が「神仏に逆らってでも」という行動をとっているわけでもありません。
④【誤】
立て札を最初に確認したのは十蔵ですが、それが作者の主要な意図とは考えにくいです。より重要なのは、その情報をめぐる登場人物の対立構造を作り出した点にあります。
第4問
問1:(ア)正解① (イ)正解④ (ウ)正解⑤
<問題要旨>
傍線部の漢文の基本的な句形や単語の意味を正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
【ア:不能去也】
①【正】「不能」は「あたはず」と読み、「~できない」という意味の不可能を表す句形です。「去」は「去る」。全体で「立ち去ることができなかった」となります。
②【誤】「~せざるをえない」という二重否定の意味はありません。
③【誤】「見捨てる」という意味はありません。
④【誤】「~はずがなかった」という推量の意味はありません。
⑤【誤】「追い払う」という意味はありません。
【イ:莫過此矣】
①【誤】「時を費やすことはない」という意味ではありません。
②【誤】「これ以前に現れたことはない」という意味ではありません。
③【誤】「この程度のものではない」という否定の意味ではありません。
④【正】「莫シ」+名詞+「ニ」+「過グルハ」+「此(これ)」で、「これにすぎるものはない」→「これ以上のものはない」という意味になります。大魚の大きさはこれが最大だ、という意味です。
⑤【誤】「ここを通ることはない」という意味ではありません。
【ウ:是以】
①【誤】「この状況において」という意味ではありません。
②【誤】「これに関して」という意味ではありません。
③【誤】「この手段によって」という手段・方法の意味ではありません。
④【誤】「これ以後は」という時間的な意味ではありません。
⑤【正】「是(こ)れを以(もっ)て」と読み、「これが原因で」「こういうわけで」と、前の事柄を受けて理由や原因を示す句です。
問2:正解⑤
<問題要旨>
傍線部A「豪傑之士亦若是魚而已矣。」(豪傑の士もまたこの魚のようなものである)という禿翁の言葉から、彼が考える「豪傑」の人物像を読み取る問題です。
<選択肢>
①【誤】
「自己の抱く理想を断固として貫く」という点までは、大魚のたとえからは読み取れません。
②【誤】
「不遇に奮起して研鑽を積む」という努力する側面は、大魚のたとえには含まれていません。
③【誤】
「堂々と反論できる」という側面は、大魚のたとえには含まれていません。大魚はただ時が来るのを待っているだけです。
④【誤】
「人々を徐々に心服させる」という側面は、大魚のたとえには含まれていません。
⑤【正】
大魚が、潮が引いて動けないという「思うに任せない状況」に陥り、「人々から攻撃される(肉を切り取られる)」ことがあっても、全く動じず、潮が満ちると悠々と去っていく姿は、「超然として意に介さずのびやかに生きる」豪傑の姿と重なります。
問3:正解④
<問題要旨>
傍線部B「不観之竜、乎。」の解釈として最も適当なものを選ぶ問題です。「不〜乎」が反語の句形であることを見抜けるかがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
反語を単純な否定として解釈しているため、誤りです。
②【誤】
「~だろうか」という疑問の句形として解釈しているため、誤りです。
③【誤】
「~に違いない」という断定・推量の意味はありません。
④【正】
「之を竜に観ずんばあらんや」と読み下します。「不〜乎(~ずんばあらんや)」は、「どうして~しないだろうか、いや~する」という強い肯定(反語)を表します。筆者は、変幻自在な聖賢のあり方を、同じく変幻自在な竜のあり方の中に見ることができるではないか、と主張しているのです。
⑤【誤】
「~なくてはならない」という義務の意味はありません。
問4:正解③
<問題要旨>
二重傍線部I「彼」とII「人」がそれぞれ何を指しているかを特定する問題です。
<選択肢>
【I「彼」】
「彼」は、直前の「竜」が「人」や「虫」や「葉」や「梭」に変化するという文脈で使われており、変化する主体である「竜」そのものを指しています。
【II「人」】
「世人安得而禍之也哉。」(世人安くんぞ得て之を禍せんや)という一節の中の「人」です。これは明らかに「世人」、つまり世間の人々を指します。
したがって、Iが「竜」、IIが「世間の人々(平凡な人々)」を指す③の組み合わせが正解です。
問5:正解③
<問題要旨>
傍線部C「是豈知竜之為竜哉。」について、正しい返り点の付け方と書き下し文の組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
返り点がなく、「之れ竜の為にする」という書き下しは意味が通りません。
②【誤】
「竜を知るは之れ竜たらんや」という書き下しは、「A之為B」の形を無視しており不自然です。
③【正】
「豈(あに)〜哉(や)」は反語の句形です。「竜之為竜」は「竜の竜たる」と読み、竜が竜であること(本質)を意味します。全体で「是れ豈に竜の竜たるを知らんや」と書き下し、「どうして(小さい形にばかりこだわる者は)竜が竜であること(の本質)を理解できようか、いやできない」という意味になります。返り点も書き下しも正しいです。
④【誤】
「竜の為すことを知るの竜ならんや」という書き下しは不自然です。
⑤【誤】
「竜を知るの竜の為ならんや」という書き下しは不自然です。
問6:正解②
<問題要旨>
傍線部D「使禿翁不為魚而為竜、世人安得而禍之也哉。」の解釈を問う問題です。「使〜」の仮定の句形と、「安〜哉」の反語の句形を正しく解釈できるかが鍵です。
<選択肢>
①【誤】
「~がゆえに」という原因・理由の文ではなく、「もし~であったならば」という仮定の文です。
②【正】
「使(もし)禿翁をして魚と為(な)らずして竜と為らしめば(もし禿翁が(ただ大きいだけの)大魚ではなく、(変幻自在な)竜であったならば)、世人安(いづくん)ぞ得て之を禍(わざはひ)せんや(世間の人々はどうして彼に災いをもたらすことができただろうか、いやできなかったはずだ)。」という仮定と反語の文です。選択肢の説明と完全に一致します。
③【誤】
「禿翁が大魚であって、竜ではなかったならば」という仮定が逆です。
④【誤】
「~がゆえに」という原因・理由の文ではなく、仮定の文です。
⑤【誤】
「~であったとしても」という逆接の仮定ではなく、順接の仮定です。
問7:正解①
<問題要旨>
この文章全体を通して、筆者が禿翁をどのように論評しているかを説明する問題です。
<選択肢>
①【正】
筆者は禿翁を「誠に豪傑なり」と評価する一方で、「徒だ豪傑の能く大を為すを知りて、聖賢の能く大を為さざるを知らず」(ただ豪傑が雄大であることを知っているだけで、聖賢が(あえて)雄大でないあり方ができることを知らない)と批判しています。つまり、禿翁は「雄大であること」は体現したが、大きさにこだわらず変幻自在である「竜(聖賢)」の境地は知らなかった、と論評しており、選択肢の内容と一致します。
②【誤】
禿翁は「自在な境地を目指した」わけではなく、「雄大であること」を好んでいました。
③【誤】
禿翁は雄大さを「体現して生きた」のであり、「体現して生きることはできず」という部分が誤りです。
④【誤】
禿翁は「自在な生き方は眼中になかった」のは事実ですが、「自在な境地を目指し」たわけではありません。
⑤【誤】
禿翁が「自在な生き方にもあこがれていた」という記述は本文になく、筆者の主張と異なります。