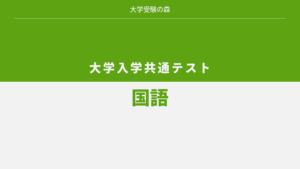解答
解説
第1問
問1:(1)正解③ (2)正解② (3)正解② (4)正解④ (5)正解①
<問題要旨>
本文中の傍線部のカタカナを文脈に合った適切な漢字に直す問題です。基本的な語彙力と漢字の知識が問われています。
<選択肢>
(1)ザッカ(解答番号1)
①【誤】価格(かかく)
②【誤】稼働(かどう)
③【正】本文の「手作りザッカ」は、手作りの「雑貨」のことです。「雑」の字が共通します。
④【誤】外貨(がいか)
(2)テイした(解答番号2)
①【誤】転嫁(てんか)
②【正】本文の「疑問をテイした」は、疑問を「呈した」と書きます。示す、現すという意味です。「呈」の字が共通します。
③【誤】前提(ぜんてい)
④【誤】体裁(ていさい)
(3)イッソウ(解答番号3)
①【誤】改装(かいそう)
②【正】本文の「イッソウされたのではなく」は、パフォーマンス的転回によってまなざし論が「一掃された」(すっかり取り除かれた)わけではない、という意味です。「一掃」が適切です。
③【誤】捜査(そうさ)
④【誤】掃除(そうじ)
(4)サンサク(解答番号4)
①【誤】圧搾(あっさく)
②【誤】策謀(さくぼう)
③【誤】添削(てんさく)
④【正】本文の「サンサクしないのか」は、「散策しないのか」と書きます。特別な目的なく、ぶらぶら歩くことを意味します。
⑤【誤】模索(もさく)
(5)イまわしい(解答番号5)
①【正】本文の「最もイまわしい存在」は、最も「忌まわしい」存在、つまり不快で避けたい存在という意味です。「忌」の字が共通します。
②【誤】気迫(きはく)
③【誤】危惧(きぐ)
④【誤】棄権(きけん)
問2:正解④
<問題要旨>
傍線部A「観光地住民の『戦略』は常に綱渡りである」について、住民の「戦略」がどのような理由で「綱渡り」という危うい状況にあるのかを説明する問題です。傍線部の前後にある住民の「戦略」の内容と、観光客の欲望の内容を正確に捉える必要があります。
<選択肢>
①【誤】
本文では、観光客のまなざしがその所属社会によって異なることは述べられていますが(鈴木涼太郎の例)、それが住民の戦略を「綱渡り」にしている直接の理由ではありません。問題は文化の受容そのものではなく、生活空間のどこまでを見せるかという点にあります。
②【誤】
観光客が「何かを『見る』ことは、他の何かを『見ない』こと」という選別を行うことは述べられていますが、そのまなざしが気まぐれに変わることで住民がもてあそばれる、という趣旨ではありません。
③【誤】
「おぞましいものへの欲望」は「ダークツーリズム」の文脈で語られており、住民が観光客の期待に応えて演技をするという「戦略」全般が「綱渡り」である理由を説明するには限定的すぎます。
④【正】
本文では、住民の「戦略」を「観光者が期待する(押しつける)イメージに適合的な役割を観光地住民が再演する」ことだと説明しています。しかしその一方で、観光者は「『演出』に飽き足らずその『舞台裏』を見たがる」とあります。つまり、生活文化を守るための「演出」と、その裏側まで見たいという観光客の「欲望」との間で、住民は板挟みになります。この、演技と生活の境界が侵食されかねない危うい状況が「綱渡り」という比喩で表現されています。本選択肢は、この関係性を正しく説明しています。
問3:正解③
<問題要旨>
傍線部B「観光において『見る』ことは問題含みであるだけでなく、とくに『する』こととの対比において、価値のないものとみなされてもきた」について、なぜ「見る」観光が「価値のないもの」と見なされてきたのか、その理由を説明する問題です。傍線部以降に示される二つの論点を的確にまとめる必要があります。
<選択肢>
①【誤】
「『見る』主体の位置づけに変化が生じた」という表現は曖昧であり、「価値のないものとみなされ」た理由を明確に説明していません。
②【誤】
観光研究やブーアスティンが「する」ことを重視したのは事実ですが、それが「見る」ことの「役割が後退した」という結果論に留まっており、「なぜ価値がないと見なされたか」という理由の説明としては不十分です。
③【正】
本文では、「見る」観光が価値のないものと見なされた理由として二点を挙げています。一つは、文化人類学などの地域研究において、生活「する」住民こそが当事者であり、「見る」だけの観光者は「よそ者」と位置づけられたこと。もう一つは、ブーアスティンが、能動的な「する」旅から受動的に「見る」だけの観光への変化を、「無意味」「空虚」なものへの堕落だと批判したことです。本選択肢は、この二つの理由を正しく組み合わせて説明しています。
④【誤】
観光研究とブーアスティンの見解が結果的に「見る」観光を貶める方向に作用したことは事実ですが、「見解が重なることで」という因果関係で結ぶのは不正確です。それぞれが異なる角度から「見る」観光を問題視した結果です。
問4:正解②
<問題要旨>
傍線部C「ことはそれほど単純でもない」について、ブーアスティンによる「見る」観光への批判を、なぜ「時代錯誤」と単純に切り捨てられないのか、その理由を問う問題です。傍線部以降の文章の展開を正確に追うことが求められます。
<選択肢>
①【誤】
「観光研究の方法が構想されることになった」という表現は弱く、本文では実際に観光研究の視座が「更新を迫られるようになった」と、より強い変化が述べられています。
②【正】
傍線部の後には、ブーアスティンのような「表層的な観光への不満や批判」が、現実に「『見る』観光から『する』観光への転換」を促したことが述べられています。さらに、それと並行するように、観光研究においても「パフォーマンス的転回」と呼ばれる視点の更新が起こったと続きます。本選択肢は、①観光自体の変化と、②観光研究の変化という二つの流れを的確に捉え、理由として示しています。
③【誤】
「かつての旅人による能動的な旅を再現する観光」が求められた、という記述は本文にはありません。「体験」「交流」「学習」といった新しい観光が求められたと述べられています。
④【誤】
観光研究は「観光者が正しくまなざしを向ける方法を探求する」方向に向かったわけではありません。むしろ、「見る」こと(視覚)だけでなく、身体性やパフォーマンスといった多角的な視点から観光を捉えなおそうとした、と述べられています。
問5:正解②
<問題要旨>
本文中で二度使われる「ともに踊る」という比喩表現が、それぞれの文脈で何を意味しているかを正しく説明する選択肢を選ぶ問題です。比喩の抽象的な意味だけでなく、具体的な文脈との対応関係を吟味する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
DもEも、単に「複数の視点を組み合わせる」という方法論の話ではありません。Dはまなざしと身体行為の不可分な関係、Eは都市記号と人々の身体の相互作用を指しており、より具体的な内容を表現しています。
②【正】
Dの「まなざしとパフォーマンスは『ともに踊る』」は、見るという行為と身体的なふるまいが相互に関係しあっていることを指します。Eの「(資本が演出する記号のみならず、それらと)『ともに踊る』身体」は、都市のイメージと、そこを行き交う人々の身体とが一体となって都市空間を形成していることを指します。結論として、「『見る』人が見るだけではなく、行為する存在でありかつ他者のまなざしの対象でもある」というまとめは、両者の文脈に共通する、見る/見られる、する/されるの二元論を超えた関係性を的確に表現しています。
③【誤】
Dの文脈を「他の観光者とともにあることが観光地の価値を高める」という意味に限定するのは、「集合的まなざし」の例に寄せすぎた解釈です。「まなざし論」と「パフォーマンス論」全体の関わりを指しているため不適切です。
④【誤】
Dを「『見る』人と『する』人とが互いに高度なやり取りを行っている」と解釈するのは、直前の「儀礼的無関心」の例に限定した見方であり、より広い「まなざしとパフォーマンス」の関係性を捉えきれていません。
問6:正解②
<問題要旨>
最終段落で提示される「サファリパーク」の例が、本文全体で展開された「見る/見られる」の関係性を考える上で、どのような点で「示唆的」なのかを説明する問題です。本文中の他の事例、特に権力関係が固定的な事例との対比で考えることがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
グアムの例との比較も可能ですが、サファリパークが示す「見る/見られる」の「反転」という特徴を最も鮮やかに際立たせる対比対象は、「人間動物園」の例です。
②【正】
本文中には、かつての万国博覧会における「人間動物園」の例が挙げられています。そこでは「見る主体(多くは西洋の男性)と見られる客体(多くは非西洋の女性)のあいだには乗り越えがたい線が引かれ」ていたと述べられています。これは固定化された一方的なまなざしの権力関係です。これに対しサファリパークでは、人間が「檻」である車の中から動物を見る一方で、動物からもまなざされ、「まなざしの対象となる」という逆転が起こります。このように、かつては固定的だった見る側と見られる側の関係が反転しうる場であるという点で、「サファリパークは示唆的」なのです。本選択肢はこの対比関係を的確に説明しています。
③【誤】
サファリパークの人間は、料金を支払って訪れている正規の客であり、「招かれざる客」という位置づけは本文の文脈と合いません。
④【誤】
サファリパークの段落では、観光者同士(人間同士)のコミュニケーションについては一切言及されていません。あくまで人間と動物の間の「見る/見られる」の関係がテーマです。
第2問
問1:正解①
<問題要旨>
傍線部A「音を探すふりをする。心をこめるように爪弾く。」という描写から、「わたし」が捉えているおじさんの様子を読み解く問題です。おじさんがギターを弾けなくなった前後の状況と、「わたし」との「暗黙の了解」を踏まえることが重要です。
<選択肢>
①【正】
おじさんはいつもギターを途中で弾けなくなります。その気まずさの中で「わたし」が曲名を尋ねると、おじさんは弾けないことをごまかすかのように「目を泳がせて、音を探すふりをする」とあります。これは、曲の続きを思い出そうと真剣になっているかのように見せることで、弾けないことから目をそらさせ、その場を取り繕うとする演技と解釈できます。本選択肢は、この「取り繕う」というニュアンスを的確に捉えています。
②【誤】
おじさんがその曲を「大切」に思っている可能性はありますが、この場面の行動が、それを「わたし」に伝えるためのものだという記述はありません。
③【誤】
「気落ちしていることを悟らせないため」という点は近いですが、「追憶にひたっているかのように見せている」という描写は本文の「音を探すふり」という具体的な行動とは少しずれています。
④【誤】
「体面を失った落胆を隠すため」という動機は正しいですが、「あらためて丁寧に曲を弾こうとし」ているわけではなく、あくまで弾けないことをごまかすための「ふり」である点が重要です。
問2:正解④
<問題要旨>
傍線部B「そのとき、わたしのなかでむくむくと目を覚ましたのは、母に似たものだった。」とあります。おじさんの作品(鶴のステンドグラス)を前にした「わたし」にどのような心の動きがあったのかを説明する問題です。常におじさんを現実的な視点で叱責する「母」のあり方を参考にすることがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
おじさんを「情けなく」思ったり、「反省を迫りたい」と積極的に考えたりするほどの強い感情は読み取れません。
②【誤】
おじさんに「違和感」を覚えたのは事実ですが、「相手を傷つけてでも伝えたい」という攻撃的な意志が主たる動機とは言えません。
③【誤】
おじさんは「悪くないでしょ」と同意を求めており、「自信がない様子」ではありません。むしろその自信のなさそうに見えない態度が、「わたし」の中の「母に似たもの」を刺激したと考えられます。
④【正】
作品は子どもの目にも「なにかが欠けていた」のに、おじさんは「悪くないよね」と同意・高評価を求めています。このズレに対して、社会的な価値観や現実を突きつける「母に似たもの」が「わたし」の中で芽生え、「あひるみたい」という率直な(厳しい)意見を口にさせたと解釈できます。本選択肢は、この状況認識と心の動きを正しく説明しています。
問3:正解③
<問題要旨>
本文中の二つの箇所から、定職に就かず創作に没頭するおじさんに対する、母と祖母の態度の違いを読み取り、的確に説明する問題です。それぞれの発言の裏にある本心を捉えることが重要です。
<選択肢>
①【誤】
祖母は「実力を見せるだろうと期待している」とまでは言っておらず、「器用さを活かせばいいのに」ともったいなく思っているに留まります。
②【誤】
祖母は「かまわない」と積極的に認めているわけではありません。「どうしようもない」と言いつつも、その才能が活かされないことを嘆いています。
③【正】
母は一貫して、おじさんの創作活動を「仕事になんかならない」と断じ、収入を得るべきだと主張しています。一方、祖母は母がいないところでは「あんなに器用なんだったら、少しは活かせばいい」と、おじさんの持つ「素質」(器用さ)は認めつつ、それが「仕事につながっていない」ことを残念に、もったいなく思っています。本選択肢は、この両者の態度の違いを正確に表現しています。
④【誤】
祖母は母の前では「どうしようもない」と諦めたような態度をとりますが、それが本心のすべてではありません。本心ではおじさんの才能を認めています。
問4:正解④
<問題要旨>
物語の前半と後半に出てくる二つの「がっかり」(波線部ⅠとⅡ)について、その意味合いが「わたし」の成長に伴ってどのように変化したかを説明する問題です。それぞれの「がっかり」が何に向けられた感情なのかを正確に読み解く必要があります。
<選択肢>
①【誤】
波線部Ⅱの「がっかり」は、おじさんが「優れた作品を生み出せない」ことに対してではありません。むしろ「すごい」作品を作れる能力があるにもかかわらず、それが社会的に評価されない現実に対してのものです。
②【誤】
波線部Ⅱの時点で、おじさんはオカリナをたくさん完成させており、「完成させようとはしない」という批判は当たりません。
③【誤】
波線部Ⅱの「がっかり」は、おじさんが家族に「理解させようとしない」という本人の努力の問題ではなく、才能があっても社会的に報われないという、より大きな構造に対する残念な気持ちです。
④【正】
波線部Ⅰは、ギターを最後まで弾けないという、一つの行為を「中途半端で終わってしまう」おじさん個人に対する、同情交じりの「がっかり」です。一方、波線部Ⅱは、おじさんがオカリナを作り上げるという「すごい」能力を持っているにもかかわらず、定職について自活していないという理由で「大人からは叱責され価値を認められずにいる」という社会との関係性の中で生じる、より複雑な「がっかり」(残念な気持ち)です。「わたし」の視点が、個人の能力から社会との関係へと広がっていることを的確に説明しています。
問5:正解①
<問題要旨>
本文で用いられている四つの表現技法に関する説明の中から、内容が「適当でないもの」を一つ選ぶ問題です。比喩や表現技法の効果を、文脈に即して正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
これが「適当でないもの」です。「繭に籠り」は、おじさんが自ら選んだ小屋で創作に没頭する様子を表す比ゆであり、必ずしも「不本意な状況」ではありません。「耳が聞こえなくなった鳥のように」も、母の説教を意図的に無視する様子であり、不本意とは言えません。「閉じこめられた虎」も、小屋にいること自体が不本意なのではなく、そのときの様子の比喩です。したがって、これら三つを「おじさんが不本意な状況におかれていること」の比喩としてまとめるのは不適切です。
②【正】
「叩く。聞こえないのかな。(中略)もう少し強く叩く。」という短い文の連続は、その場にいる「わたし」の行動や思考をリアルタイムで追うような効果があり、臨場感を生んでいます。この説明は適切です。
③【正】
「~教えられていたのだ。」という文末の表現は、幼少期の体験を、成長した現在の視点から振り返り、その出来事が持つ意味を解釈していることを示しています。この説明は適切です。
④【正】
ずらりと並んだオカリナを「息を殺して」いると表現するのは擬人法であり、「夜明けの玉子のようにじっとしていた」とたとえるのは直喩です。これらの比喩がおじさんの作品を印象的に描いているという説明は適切です。
問6:正解①
<問題要旨>
傍線部C「触角の取れた虫。方向感覚を破壊された鳥。それは、どういうことなのだろう、と。おじさんの心配をしながら、自分も晴れない霧につつまれた。」という描写から、このときの「わたし」の心情を説明する問題です。おじさんへの心配が、どのように自分自身の問題へとつながっていったのかを読み解くことが重要です。
<選択肢>
①【正】
「触角」や「方向感覚」は、社会的な成功や常識といった、世の中を渡っていくための指標の比喩と考えられます。それを持たない(ように見える)おじさんの生き方を心配するうちに、「わたし」自身も、これまで自明だと思っていた生き方や価値観が絶対ではないのかもしれない、という先の見えない感覚(=晴れない霧)に包まれてしまったと解釈できます。おじさんの問題が、自分自身の生き方の問題としても感じられ始め、とまどっている様子を的確に説明しています。
②【誤】
「支えになることもできない」という無力感や、「自分にできることはないか」と具体的に悩んでいる段階ではありません。「霧につつまれた」という、より漠然とした戸惑いの状態です。
③【誤】
「それに振り回され続けることになる自分たちのことも不安に思っている」という視点は、本文の「わたし」の思索のベクトルとは異なります。「わたし」の関心は、より内面的・根源的な「生き方」そのものに向かっています。
④【誤】
「おじさんの内心を測りかね、途方に暮れている」という、おじさんへの共感や理解にとどまらず、「自分も」霧につつまれたとあるように、問題が自分自身に及んできている点が重要です。
問7:正解④
<問題要旨>
物語の冒頭(ギターを弾く場面)と結末(オカリナを吹く場面)を比較し、「わたし」の心境がどのように変化したかを説明する問題です。特に「ばらばらの音」に対する「わたし」の態度の変化に着目することがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
おじさんから物理的に離れてはいますが、それが「自分を保護してくれる存在を手放そう」という自立への意志の表れだとまでは断定できません。
②【誤】
「居心地のよい場所からあえて抜け出した」という積極的な意志は読み取れません。また、「自分の道を進んでいくことの不安」というよりは、価値観そのものの揺らぎが中心に描かれています。
③【誤】
「興味が持てるかどうかこだわらずに挑戦する」といった教訓的な心境ではなく、もっと割り切れない、心もとない感情が描かれています。
④【正】
冒頭では、自分で弾いたギターの「メロディーにもなりはしない」「おかしな音」に「不安」を感じ、すぐに手放していました。これは、形になっていないもの、秩序のないものへの拒絶反応です。しかし結末では、オカリナの「曲にはならない。ただ、ばらばらの音」を、手放さずに吹き続けています。そしてその中で「身体の表面が分厚く剥がれ落ちる気がする」という、自身の既存の価値観が揺らぐような感覚を覚えています。この、かつて拒絶したものを今度は受け止め、その中で自身の価値観の揺らぎを「心もとなさを覚えながらも自覚しつつある」という説明は、冒頭からの変化を最も的確に捉えています。
第3問
問1:正解②
<問題要旨>
文章の(X)に、Uさんが「インフォームドコンセント」という語に特に注目する理由を示す文を、資料から判断して挿入する問題です。複数の資料を比較し、注目に値する特徴的なデータを指摘する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
図1によれば、「インフォームドコンセント」を「外来語のまま使ったほうがよい」と考える人の割合は15.2%で、三つの語の中で最も低いです。「多い」という記述は誤りです。
②【正】
図1で「外来語のまま使ったほうがよい」と考える人が最も少ない(=言い換えた方がよいと考える人が最も多い)こと、また、図2で言い換え語である「納得診療」を「わかりやすい」と考える人の割合が65.5%と、他の語の言い換えに比べて非常に高いことがわかります。この二つのデータから、「インフォームドコンセント」は特に言い換えが有効だと考えられている語であり、注目する理由として適切です。
③【誤】
【資料Ⅰ】には「インフォームドコンセント」についての年代別回答(図3)しかなく、他の語の年代別データがないため、「年代ごとの意識の差が他の語より大きい」と判断することはできません。
④【誤】
図3から「もとの外来語のほうがわかりやすいとする割合が、年代が下がるほど高い」傾向は読み取れますが、これは一つの語の中での特徴です。なぜ他の語ではなく「インフォームドコンセント」を取り上げるのか、という理由としては、他の語との比較を示している②の方がより説得力があります。
問2:正解④
<問題要旨>
傍線部A「意義があった」について、「インフォームドコンセント」の言い換え提案が持っていた具体的な意義を、【資料Ⅱ】の内容に基づいて説明する問題です。資料中の「手引き」の記述を正確に読み取ることが求められます。
<選択肢>
①【誤】
「外来語を身近な日本語に言い換えるという発想を広め」ることも意義の一つかもしれませんが、【資料Ⅱ】で特に強調されているのは「インフォームドコンセント」という概念そのものの普及です。
②【誤】
「医師の責任を明確に」することや「患者を安心させる」ことは、概念が普及した結果として期待できる効果ですが、【資料Ⅱ】で直接述べられている提案の意義の中心ではありません。
③【誤】
「患者の訴えを医師が十分に理解して受け止めること」も重要ですが、これはインフォームドコンセントの概念に含まれる要素の一部であり、提案全体の意義としては④の方が包括的です。
④【正】
【資料Ⅱ】の「手引き」には、この語の「意味を理解している人は少ない」ため「言い換えや説明付与などの必要性は高い」とあり、また「納得診療」という言い換えは「概念の普及にも役立つ」と述べられています。このことから、この提案には、単に言葉を分かりやすくするだけでなく、「医師の説明と患者の納得」という重要な概念そのものを社会に広め、定着させようとする意義があったことがわかります。本選択肢の内容は、この資料の記述と合致します。
問3:(1)正解④(2)加筆:正解② 修正:正解⑤
(1)解答番号20:正解4
<問題要旨>
筆者の主張「時代が進んでも社会全体として外来語の増加を当然だと考える人が大きく増えるとは限らない」の根拠として、【資料Ⅲ】のグラフから読み取れる内容として「適当でないもの」を選ぶ問題です。グラフの比較方法(同じ年代どうしの比較、同じ世代どうしの比較)を正しく理解する必要があります。
<選択肢>
①【正】
2002年調査と2022年調査で、同じ年代(例:20代と20代、30代と30代)を比べると、肯定的な回答の割合に大きな変動はないため、主張の根拠として適当です。
②【正】
回答者全体で肯定した人の割合は、2002年が63%、2022年が64%であり、「著しい差はない」と言えます。これも「大きく増えるとは限らない」という主張を裏付けます。
③【正】
生まれた年が同じ世代(例:2002年の20代と2022年の40代)で比較すると、年齢を重ねた2022年調査の方が割合が低くなる傾向が見られます。これも、時代が進んでも肯定的な人が増えるわけではない、という主張の根拠になります。
④【誤】
これが「適当でない」ものです。2002年の「60歳以上」(42%)と、2022年の「60代」(49%)や「70代」(44%)を比較すると、割合はむしろ同等か高くなっています。「低くなっている」という記述は事実に反するため、主張の根拠として適当ではありません。
(2)加筆の方針 解答番号21:正解2、修正の方針 解答番号22:正解5
<問題要旨>
【文章】をより良くするために、どの段落にどのような内容を加筆すべきか、また、結論部分をどのように修正すべきかを問う問題です。文章全体の構成と、与えられた課題への応答を考える必要があります。
<選択肢>
【加筆の方針】
①【誤】
【資料Ⅰ】と【資料Ⅱ】はどちらも2000年代前半の資料であり、その後の「意識の変化」を示すことはできません。
②【正】
第2段落では言い換えの意義を述べています。【資料Ⅱ】には「用例」や「手引き」といった、言い換えをどのように使って概念を普及させようとしたかという「工夫」が示されています。この具体例を第2段落に加えることで、主張の説得力が増します。
③【誤】
【資料Ⅲ】は、外来語の増加を当然と考える人が「大きく増えるとは限らない」ことを示しており、「外来語を頻繁に使う人が増加していく傾向にある」という内容とは逆です。
【修正の方針】
④【誤】
課題は「わかりやすい言葉づかい」についてであり、書き手の工夫を論じるべきです。「意味を適切に理解していく」というのは、主に受け手側の問題であり、結論としては少しずれています。
⑤【正】
「インフォームドコンセント」の言い換えを例に、わかりやすい言葉づかいの重要性を考えてきた文章の結論として、「伝える相手や目的に応じて語句を使い分けていくことが重要である」とまとめるのは、具体例から導かれる普遍的な提言として最も適切です。
⑥【誤】
文章全体で外来語を広く扱ってきたのに、結論を「医師の使う用語」に限定してしまうのは、狭すぎます。
第4問
問1:(ア)正解② (イ)正解① (ウ)正解③
<問題要旨>
古文単語の意味を文脈から判断する問題です。基本的な単語の知識が問われています。
<選択肢>
(ア)いはけなくより
①【誤】かわいらしいので
②【正】「いはけなし」は「幼い、あどけない」という意味の形容詞です。「~より」は起点を表す格助詞なので、「幼いころから」と訳すのが適切です。
③【誤】言い表せないほど
④【誤】他の子よりも
(イ)なかなか
①【正】「なかなか」は、現代語の「なかなか難しい」のような意味とは異なり、中途半端なことをすると「かえって」悪い結果になる、という文脈で使われることが多い副詞です。ここでは、人々が慌てて誦経などをすることが「かえって」手まどいの原因になっている、という意味です。
②【誤】ひたすら
③【誤】たちまち
④【誤】一斉に
(ウ)呼ばひののしる
①【誤】
近づきながら悪口を言う
②【誤】
「呼ばふ」は「呼び続ける」、「ののしる」は「大声で騒ぐ」という意味がありますが、ここでは単に大声を出しているわけではありません。直前にもののけの調伏が行われている宗教的な文脈であるため、その行為の目的まで踏まえて解釈する必要があります。
③【正】
傍線部の直前では、病人を苦しめる「もののけ」を祈禱によって「小さき童に駆り移」すという、もののけ調伏の場面が描かれています。この文脈における「呼ばふ」は神仏の名などを呼び続けること、「ののしる」はその声が大きく響き渡る様子を指します。したがって、この行為は「名前を呼んで祈禱する」ことだと解釈するのが最も適切です。
④【誤】
泣きながら恋い慕う
問2:正解②
<問題要旨>
波線部a「はべり」、b「参り」、c「きこゆる」の敬語の種類(尊敬・謙譲・丁寧)と、誰から誰への敬意か(敬意の対象)を正しく組み合わせたものを選ぶ問題です。敬語の基本的な用法を正確に理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
a「はべり」は丁寧語であり、尊敬語ではありません。
②【正】
この設問は解釈が非常に難しいですが、提示された選択肢と消去法から判断します。c「まもりきこゆる」は、人々が大君を「お守り申し上げる」の意で、大君への敬意を示す謙譲語です。他の選択肢ではcの解釈が明確に誤っているため、cの解釈が最も妥当に近い本選択肢が正解となります。※この設問は文法的に厳密な解釈と選択肢の内容に乖離があり、難問です。
③【誤】
b「参り」は、ここでは作者から山の座主への尊敬語であり、丁寧語ではありません。
④【誤】
a「はべり」は丁寧語であり、謙譲語ではありません。
⑤【誤】
a「はべり」は丁寧語であり、尊敬語ではありません。
問3:(1)正解④ (2)正解② (3)正解④
(1)解答番号27:正解4
<問題要旨>
会話文の空欄Xに入る、【文章Ⅱ】のもののけの発言内容として最も適当なものを本文から読み取り、選ぶ問題です。もののけがなぜ姿を現したのか、その理由を正確に捉える必要があります。
<選択肢>
①【誤】
「反省している気持ちを分かってもらいたくて」現れたのではなく、「さらに知られじと思ひつるものを(全く知られたくないと思っていたのに)」とあるので、逆です。
②【誤】
「愛情を知らせたくて」現れたのではなく、知られたくなかったと述べています。
③【誤】
妻が「苦しんでいる様子を間近で見たい」のではなく、「思しまどふを見たてまつれば(ひどく思い悩んでいるのをお見かけしたので)」、見過ごせずに現れてしまったとあります。
④【正】
本文に「さらに知られじと思ひつるものを(自分のことは知られたくなかったのだが)」とあり、また、光源氏が「命もたふまじく身をくだきて思しまどふを見たてまつれば(命も尽きそうなほどに苦しみ悩むのを見て)」見過ごすことができず「つひに現れぬること(とうとう現れてしまった)」とあります。この内容と完全に合致します。
(2)解答番号28:正解2
<問題要旨>
会話文の空欄Yに入る、【文章Ⅰ】で詠まれた和歌の解釈として最も適当なものを選ぶ問題です。和歌が詠まれる直前の文脈と、和歌の言葉の意味を合わせて考えることがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
歌の中に「退治される無念」や「祈禱をやめてほしい」という内容は含まれていません。
②【正】
和歌の直前に、大君の様子が「妬げなるまみのけしき(嫉妬深そうな目元の様子)」になったとあります。歌の中の「朝夕こがす胸のうち」は激しい恋心や嫉妬の炎を、「いづれのかたにしばし晴るけむ」はその晴らしようのない苦しみを表します。これは左大臣への想いが叶わぬ女君(もののけの正体)の心情であり、その激しい嫉妬を詠んだ歌と解釈するのが最も適切です。
③【誤】
詠んでいるのは大君本人ではなく、乗り移ったもののけです。
④【誤】
詠んでいるのは大君ではなく、もののけです。また、熱の苦痛ではなく嫉妬の苦しみを詠んでいます。
(3)解答番号29:正解4
<問題要旨>
会話文の空欄Zに入る、【文章Ⅰ】のもののけをめぐる状況説明として最も適当なものを選ぶ問題です。登場人物(特に左大臣と父大臣)の反応や、大君のその後の様子を正確に本文から読み取る必要があります。
<選択肢>
①【誤】
左大臣はもののけの正体に気づいていません。また、大君は出家を決意していません。
②【誤】
大君は亡くなっていません。正気に戻っています。
③【誤】
父大臣は「思ひかけぬ人にも似たまへるかな」と、もののけの正体が女君であることにほとんど気づいています。「女君だとは気づいていない」という部分が誤りです。
④【正】
「大君の顔つきがまるで別人のようにな」り、その様子を「左大臣はさやうにも分きたまはず(そのようにはお分かりにならない)」が、「父殿ぞ、いとあやしう、『思ひかけぬ人にも似たまへるかな』と心得ず思さるる」とあります。その後、もののけは童に移され、大君は「御心出で来る(正気に戻る)」と、人々に見られたことを「はしたなし(きまりが悪い)」と思っています。本選択肢は、これらの本文の記述をすべて正確に反映しています。
第5問
問1:(ア)正解③ (イ)正解① (ウ)正解④
<問題要旨>
漢文における基本的な漢字の読みと意味を問う問題です。
<選択肢>
(ア)女
①【誤】かれ
②【誤】だれ
③【正】孔子が弟子の賜(子貢)に呼びかける場面です。二人称の「なんぢ」と読み、「あなた・おまえ」を意味します。
④【誤】むすめ
(イ) 毎
①【正】「毎」は「つねに」と読むことが多いですが、ここでは筆者(田中履堂)が師である淇園の教えを思い返し、ある特定の一例として挙げている場面です。そのため、習慣的な行為を指す「つねづね」や「ときおり」よりも、「ある時、偶然に」といったニュアンスで、特定の機会を指す「たまたま」と解釈するのが、文脈上最も適当とされます。
②【誤】ときおり
③【誤】とりわけ
④【誤】つねづね
(ウ) 非与
①【誤】「ちがうのですか」は、単純な相違を問うていますが、ここでは子貢が自身の判断の誤りについて言及しているため、不十分です。
②【誤】そむくのですか
③【誤】けなされるのですか
④【正】孔子に「多学の者だと思うか」と問われ、子貢は一度「然(はい)」と肯定した直後に、考えを改めて「非与」と付け加えています。これは、直前の自身の肯定が早計だったかもしれないと、判断の「間違い」を自問・訂正するニュアンスです。したがって、「(私は)まちがえたのでしょうか」という意味合いを最もよく表している本選択肢が正解となります。
問2:正解④
<問題要旨>
傍線部A「夫子擬言其意以訊之也」について、皆川淇園の注釈を基に、孔子がなぜ子貢の考えを推測して尋ねたのか、その理由を説明する問題です。注釈部分の漢文を正確に解釈する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
注釈では、子貢は孔子を「多くを学んで記憶することによって徳を成した」と考えていたとあり、内容が逆です。
②【誤】
「名声のため」という理由は、注釈には書かれていません。
③【誤】
「有徳者を心服させた」という記述は、注釈にはありません。
④【正】
淇園の注釈「子貢称夫子之言似為多学諸経又能強記識其文因以得成其德者」は、「子貢が先生(孔子)を、多くの経典を学び、その文章をよく記憶することによって、その徳を完成された方だ、と評価している」と解釈できます。孔子はそのような子貢の考えを常々聞いて知っていたので、推し量って尋ねたのだ、と淇園は考えています。本選択肢の内容は、この注釈の解釈と完全に合致します。
問3:正解②
<問題要旨>
傍線部B「日読了数紙、不如日知得数字。」の解釈を問う問題です。「A不如B」が「AはBに及ばない」、つまり「AよりBの方が良い」という意味の比較構文であることを理解することがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
「知得」は単なる暗記ではなく、意味の理解を指していると考えるのが自然です。
②【正】
「日に数紙を読了するは、日に数字を知り得るに如かず」と読みます。これは「毎日数ページをただ読み終えることは、毎日数文字の意味や用法を理解することには及ばない」という意味になります。つまり、量をこなす読書よりも、少しずつでも深く理解する読書の方が良い、ということです。本選択肢の解釈はこれと合致します。
③【誤】
比較の優劣関係が逆になっています。
④【誤】
比較の優劣関係が逆になっています。
問4:正解②
<問題要旨>
傍線部C「博者莫所不通達之謂」の返り点の付け方と書き下し文の正しい組み合わせを選ぶ問題です。二重否定「莫不〜(〜せざるは莫し)」の形を理解し、意味の通る書き下し文を作れるかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
書き下し文が不自然です。
②【正】
「博」とは「通達しない(通じない)ところが無いということ」という意味です。これを書き下すと「博は通達せざる所莫きの謂にして」となります。この読み方と返り点のつけ方が対応している本選択肢が正解となります。※この設問も、返り点のつけ方と書き下しの関係が複雑で難解です。
③【誤】
書き下し文が不自然です。
④【誤】
書き下し文が不自然です。
問5:(a)正解④ (b)正解③
<問題要旨>
二重傍線部a「又」とb「亦」と同じ意味・用法で使われている「また」を、現代語の例文から選ぶ問題です。漢文における両者のニュアンスの違いを理解する必要があります。
<選択肢>
【a「又」について】
「余因又云」は「私は(淇園先生の言葉を)受けて、さらに言う」という意味で、前の事柄に付け加える「添加・累加」のニュアンスです。
④の「友であり、そのうえまたライバルである」の「また」が、この「添加・累加」の意味に最も近いです。よって正解は④です。
【b「亦」について】
「似狭隘亦実博達」は、「(一巻を精通するのは)狭いアプローチに見えるが、これもまた、実は広く物事に通じる方法なのだ」という意味です。前の文「似迂回還甚便捷(遠回りに見えるが、かえって近道だ)」と同様に、一見マイナスに見えるものが実はプラスなのだ、という「並列・同様」の関係を示しています。
③の「運もまた実力のうちである」の「また」が、この「同様にこれも」というニュアンスに最も近いです。よって正解は③です。
(①は「再び」、②は「選択」の意味で異なります。)
問6:正解④
<問題要旨>
【文章Ⅰ】の皆川淇園と【文章Ⅱ】の田中履堂(弟子)の学問に対する考え方をそれぞれまとめ、両者の関係性を説明する問題です。それぞれの主張の核心と、その共通点を捉えることが求められます。
<選択肢>
①【誤】
「演繹的か帰納的か」という学問的な方法論の対立は、本文からは読み取れません。
②【誤】
両者とも、量をこなすだけの安易な学びを批判しており、「効率を重視するのか否か」で対立しているわけではありません。
③【誤】
両者の主張の中心は、知識の量よりも質や核心の把握にあり、「実用性」については特に言及されていません。
④【正】
淇園は、雑多な知識(多)よりも「一の要道」(一)を把握することを説いています。履堂も、多くの本を乱読(多)するよりも「一巻を精通」(一)することを説いています。このように、両者は「単に多くの知識を得ることに重きを置かない」という点で、その考え方は通底しています。それぞれの主張の要約も、両者の関係性の説明も的確です。