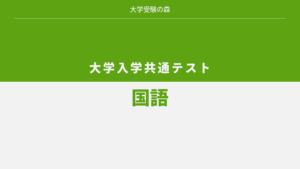解答
解説
第1問
この文章は「翻訳とは何か」という問題意識から始まり、翻訳が単なる言語変換ではなく、文化的背景や文体、読者の受容など多面的な要素を考慮しなければならないことを論じている。具体例として、フランス語から日本語への翻訳や英語表現の直訳の難しさなどを挙げ、「原文を厳密に移し替えるだけ」では読み手に不自然さや誤解を与えてしまう場面があることを指摘する。
さらに翻訳者自身の読み方・解釈によって作品は大きく変化し、翻訳における「正しさ」や「忠実さ」が一筋縄ではいかないことを示す。たとえば「I love you」のような英語表現を日本語に置き換える際も、文字通り「私はあなたを愛しています」とするとぎこちないため、場面や人物関係に応じた表現が必要となる。そうした「文化的・言語的背景を汲み取り、なおかつ作品の魅力を損なわない訳」を目指す難しさこそが、翻訳の核心的な問題であると論じられている。
最終的に文章は、「翻訳はただの機械的作業ではなく、人間の創造性と読解力を必要とする行為だ」と結論づける。原文にある複雑なニュアンスや作家の意図、文体の特質をどう再現するかという課題に取り組む姿勢こそが大切であり、翻訳者は「奇跡」を期待するほどの気持ちで、言葉の可能性を模索しながら“新たな表現”を創り出していく存在だ、という見方を提示している。
第2問
夫が入院し長期間不在となっている「私」の家では、母親が心の支えとして庭の世話を続ける一方、ある日、庭師が「月見草を雑草だ」と言ったことをきっかけに、家の庭にもう一度“新しい”月見草が現れる場面が描かれる。妹は畑を活用するために茄子やチンシャ菜などの苗を買い、日々の暮らしを支えようとする。そんな家庭の光景を背景に、「私」は六月の中頃、川原で友人と釣りをすることになり、自然の中でゆったりと過ごす。やがて月見草への思い、家族の失望や落胆を紛らわせようとする気持ち、そして妹・母とのかかわりが交錯し、改めて家の庭や花々が生む癒しの力を見いだしていく。
物語の終盤では、「私」が再び月見草を見出した時の驚きや安らぎが描かれる。川原での経験やガリン・カァ(汽車)での移動、橋番とのやり取りなどの小さな出来事を通じて、「私」は家族の不在や不安と向き合いつつも、月見草がかもし出す自然の美しさに慰められる。こうして繰り返し姿を見せる月見草は、家族の置かれた困難な状況の中でも絶えずめぐる季節や命の営みを象徴し、登場人物たちにささやかな希望ややすらぎをもたらしている。
第3問
本文は、十四、五歳のたいへん美しい姫君が登場し、その姿に魅せられた周囲の人々や“狐”の視点などを軸に物語が進む一場面である。姫君は父親のいる「世(社会)」とはやや隔絶したかたちで暮らしている様子がうかがえ、見る者を圧倒するかのような美しさをもつがゆえに、いつ消えてしまうのかと案じられたり、不思議な存在感を漂わせたりする。
物語の背景には、姫君をめぐる「嫁入り」や「御所(在家)への出仕」などの話題がほのめかされ、父や周囲が彼女をどう扱い、どのような未来を用意するのかが示唆されている。一方で、狐が姫君を見かけて魅了される描写や、姫君の美しさが“花園”にたとえられる様子などから、現実と幻想のあわいにあるかのような情景が浮かび上がる。全体としては、若くあでやかな姫君の姿が醸し出す神秘性や、ひそやかに進む縁談や日々の営みが、ゆるやかに重なり合いながら描かれている。
第4問
本文章は、中国・唐代の詩人である杜甫が、幼少期に自分を育ててくれた叔母(父方の伯母または叔母にあたる女性)の死を悼んで書いたもの。叔母は杜甫だけでなく、他の親族の子や自身の子どもも引き取り育てるなど、非常に面倒見がよく、孝行の篤い人物として知られていた。
作中では、叔母が病気を患いながらも愛情深く子どもたちの世話を続けたこと、杜甫がその恩に深く感謝していることなどが述べられている。また、杜甫のほうも叔母を実の親のように慕い、葬儀に際しては銘文(死者の功績を讃える文)を作って哀悼の意を表した。本来なら朝廷から官職に任ぜられるほどの功績者が受けるような礼を、杜甫は自分のできる限り尽くして叔母に捧げようとし、その徳を後世に伝えようとした。こうして文章全体を通じて、亡き叔母に対する杜甫の深い悲しみと感謝が真摯に綴られている。