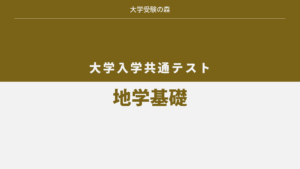解答
解説
第1問
問1:正解④
<問題要旨>
地球が完全な球体ではなく、赤道方向に膨らんだ回転楕円体であることを証明する測定結果を選ぶ問題です。地球が球であることの証明と、回転楕円体であることの証明を区別する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
北極星の高度が緯度とほぼ等しくなるのは、地球が球体である証拠です。北極へ行くほど北極星の高度が高くなる現象は、地球が丸いために起こります。しかし、これだけでは地球が偏平な回転楕エン体であることの証明にはなりません。
②【誤】
同じ経線上で、太陽の南中高度が緯度によって異なるため、同じ長さの棒の影の長さも変わります。これも地球が球体である証拠ですが、回転楕円体であることの直接的な証明ではありません。
③【誤】
春分の日に昼夜の長さがどこでもほぼ同じになるのは、地球が自転しながら太陽の周りを公転しているためです。地球の形状が球体であることを示唆しますが、偏平であることの証拠にはなりません。
④【正】
もし地球が完全な球体であれば、緯度差1度あたりの子午線弧長はどこでも同じになるはずです。しかし、実際には地球は赤道方向に膨らんだ回転楕円体であるため、極に近づくほど曲率が小さく(平たく)なります。そのため、同じ緯度差1度を進むのに必要な距離は、高緯度(極付近)ほど長くなります。この測定結果は、地球が偏平な回転楕円体であることの決定的な証拠です。
問2:正解①
<問題要旨>
地球の内部構造(地殻、マントル、核)と、それに関連するリソスフェアやアセノスフェアについての基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
地球の半径は約6400kmです。一方、地殻の厚さは、大陸地殻で平均30~40km、海洋地殻で5~10km程度です。最も厚い大陸地殻でも地球半径の1%に満たず、平均すればさらに小さくなります。したがって、「地球の半径の2%未満である」という記述は正しいです。
②【誤】
リソスフェアは地殻とマントル最上部の硬い岩盤を指し、プレートそのものです。地震は、この硬いリソスフェア(プレート)が割れたり、ずれたりすることによって発生します。したがって、リソスフェアの内部で地震は発生します。
③【誤】
アセノスフェアは、リソスフェアの下に位置する、マントルの一部で流動性を持つ部分です。リソスフェアが「地殻とマントルの上部」から構成されるため、この記述はリソスフェアの説明と混同させる誤りです。
④【誤】
地球の核の半径は約3500kmです。地球の半径は約6400kmなので、核の半径は地球半径の約55%(3500km / 6400km ≒ 0.55)です。したがって、「約80%である」という記述は誤りです。
問3:正解②
<問題要旨>
大陸地殻の構造モデルと、海洋地殻を構成する岩石の偏光顕微鏡写真の正しい組み合わせを問う問題です。それぞれの特徴を正しく理解しているかがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
大陸地殻の構造Aは正しいですが、写真Cは粗い粒の石英や黒雲母が見られることから、大陸地殻を構成する花こう岩です。海洋地殻の岩石としては不適当です。
②【正】
大陸地殻の構造は、上部の花こう岩質層と下部の玄武岩質・斑れい岩質層の二層構造で表されるのが一般的です(構造A)。また、海洋地殻の主な構成岩石は玄武岩や斑れい岩です。写真Dは、輝石やかんらん石の斑晶が、細かい結晶の集合である石基に囲まれた「斑状組織」を示しており、これは火山岩である玄武岩の特徴です。したがって、この組み合わせは正しいです。
③【誤】
大陸地殻の構造Bは、花こう岩質層のみで描かれており、二層構造を示すAに比べて不正確です。また、写真Cは花こう岩であり、海洋地殻の岩石ではありません。
④【誤】
大陸地殻の構造Bが不正確です。写真Dは玄武岩であり海洋地殻の岩石として正しいですが、組み合わせとして誤りです。
問4:正解①
<問題要旨>
岩石の風化作用(物理的風化、化学的風化)や、風化によって生じた粒子が運搬・堆積してできる地形に関する説明のうち、誤っているものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
化学的風化は、水や二酸化炭素などが関与する化学反応による風化であり、温暖で湿潤な(気温が高く、降水量が多い)地域で活発に進みます。一方、物理的風化は、温度変化による凍結・融解の繰り返しなどで岩石が機械的に破壊される作用で、気温が低く乾燥した(降水量が少ない)地域で優勢です。したがって、「気温が低く、降水量が少ない地域では、化学的風化が進みやすい」という記述は逆であり、誤りです。
②【正】
カルスト地形は、石灰岩が二酸化炭素を溶かした弱酸性の雨水によって溶食されることで形成されます。ドリーネはその代表的な地形です。この記述は正しいです。
③【正】
岩石が地表に露出すると、温度変化などの影響で表面から玉ねぎの皮をむくように薄くはがれていく風化作用があります。これを玉ねぎ状風化(または剥離作用)と呼びます。この記述は正しいです。
④【正】
扇状地は、河川が山地から平野に出る谷口などで、流れが緩やかになることによって、運搬してきた砂や礫などの粗い粒子を扇状に堆積させて形成される地形です。この記述は正しいです。
問5:正解③
<問題要旨>
堆積岩の分類(砕屑岩、生物岩、化学岩)に関する文章の空欄補充問題です。砕屑岩の粒径による分類と、生物岩の具体例についての知識が問われています。
<選択肢>
①【誤】
ア:風化・侵食でできた粒子が固結した岩石は「砕屑岩」です。「化学岩」は水に溶けていた成分が沈殿して固結した岩石です。
ウ:「放散虫」の遺骸は二酸化ケイ素(SiO2)でできており、これが固まると「チャート」になります。「石灰岩」は主に炭酸カルシウム(CaCO3)からなります。
②【誤】
ア:「化学岩」が誤りです。
イ:粒径1/16mm~2mmの粒子が固結したものは「砂岩」です。「泥岩」はもっと細かい粒子からなります。
③【正】
ア:岩石の破片などが集まってできた堆積岩は「砕屑岩(さいせつがん)」です。
イ:砕屑岩のうち、主要な構成粒子の粒径が1/16mm~2mmのものは「砂岩」です。
ウ:放散虫は二酸化ケイ素(SiO2)の殻を持つ生物で、その遺骸が堆積して固まると「チャート」になります。
すべての組み合わせが正しいため、これが正解です。
④【誤】
ウ:「石灰岩」が誤りです。放散虫からできるのはチャートです。
問6:正解②
<問題要旨>
地質断面図と示準化石の情報から、地層に起きたイベント(褶曲、不整合面の形成)がどの時代に起こったかを推定する問題です。地層累重の法則、不整合の法則、示準化石の知識を総合的に活用します。
<選択肢>
①【誤】
不整合面の形成時期が合いません。不整合面は、その上にある地層(D層:新生代古第三紀~新第三紀)より古く、下にある褶曲した地層(B層:中生代白亜紀)より新しい時代に形成されます。第四紀では新しすぎます。
②【正】
地層Bからトリゴニアの化石が見つかるため、B層は中生代(特に白亜紀が示唆される)に堆積しました。地層Dからはピカリア(ビカリア)の化石が見つかるため、D層は新生代新第三紀中新世に堆積しました。
褶曲はA~C層に及んでいますが、D層には及んでいません。したがって、褶曲はC層が堆積した後、D層が堆積する前に起こった地殻変動です。B層が白亜紀なので、褶曲は「白亜紀」以降に起こったと考えられます。
不整合面は、褶曲したA~C層を削り、その上にD層が堆積しています。したがって、不整合面の形成は褶曲の後、D層(新第三紀)の堆積前です。この期間に相当する時代として「古第三紀」は妥当です。
よって、褶曲が白亜紀(に始まった地殻変動)、不整合面の形成が古第三紀という組み合わせが最も適当です。
③【誤】
褶曲の時期が合いません。デボン紀は古生代であり、中生代のB層が堆積するよりもはるか昔です。
④【誤】
褶曲の時期がデボン紀であるため誤りです。
問7:正解③
<問題要旨>
地層の不整合に関する2つの文章の正誤を判断する問題です。基底礫岩と不整合面の関係、不整合が示す地質学的な意味を正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
文章aが誤りです。
②【誤】
文章aが誤り、文章bが正しいです。
③【正】
a【誤】基底礫岩は、不整合面が形成された後、新たに堆積が始まった際に、不整合面の「直上」に堆積する礫岩層です。侵食面の上に最初にたまった地層であるため、下の地層の礫などを含みます。したがって、「直下に堆積する」という記述は誤りです。
b【正】不整合は、①堆積→②隆起→③侵食→④沈降→⑤再堆積という一連の過程を経て形成されます。隆起や沈降は大規模な地殻変動を示すため、不整合面の存在は過去の地殻変動を知る重要な手がかりとなります。したがって、この記述は正しいです。
よって、aが誤、bが正の組み合わせが正解です。
④【誤】
文章bが正しいです。
第2問
問1:正解②
<問題要旨>
太平洋赤道域で見られるエルニーニョ現象、ラニーニャ現象、および平常時の海洋と大気の状態を示した模式図の正しい組み合わせを選ぶ問題です。貿易風の強さと、それに伴う暖水の分布がポイントです。
<選択-肢>
①【誤】
エルニーニョ時とラニーニャ時の組み合わせが逆です。
②【正】
平常時(A):東から西へ適度な強さの貿易風が吹き、西側のインドネシア付近に暖水が吹き寄せられ、東側の南米ペルー沖では冷たい水の湧昇が起きています。これが基準の状態です。
エルニーニョ時(C):貿易風が平常時より弱まり、西側に溜まっていた暖水が東側へ広がります。その結果、東側の湧昇が弱まり、海水温が高くなります。図Cは貿易風が最も弱い状態を示しています。
ラニーニャ時(B):貿易風が平常時より強まり、暖水がより一層西側へ吹き寄せられます。その結果、西側の海水温はさらに高く、東側の湧昇が強まって海水温はさらに低くなります。図Bは貿易風が最も強い状態を示しています。
したがって、平常時A、エルニーニョ時C、ラニーニャ時Bの組み合わせが正しいです。
③【誤】
平常時とエルニーニョ時の組み合わせが逆です。
④【誤】
3つの組み合わせがすべて異なります。
⑤【誤】
3つの組み合わせがすべて異なります。
⑥【誤】
平常時とラニーニャ時の組み合わせが逆です。
問2:正解⑥
<問題要旨>
日本の冬の気圧配置と天候に関する文章の空欄補充問題です。冬の典型的な気圧配置、卓越風、そして日本海側で大雪が降るメカニズムの理解が問われます。
<選択肢>
①【誤】
等圧線の方向と風向、海流名が誤りです。
②【誤】
風向と海流名が誤りです。
③【誤】
等圧線の方向と海流名が誤りです。
④【誤】
等圧線の方向と風向が誤りです。
⑤【誤】
海流名が誤りです。日本海に直接的に大きな影響を与えるのは対馬海流です。
⑥【正】
ア:冬の気圧配置は大陸に高気圧、東の海上に低気圧がある「西高東低」です。このとき、等圧線は縦縞模様、つまり「南北」方向に伸びます。
イ:風は気圧の高い西(大陸)から低い東(海上)へ向かって吹きます。北半球ではコリオリの力により、等圧線を横切って右向きにずれるため、日本付近では「北西」の季節風となります。
ウ:この冷たく乾燥した北西の季節風が日本海を渡る際、暖流である「対馬海流」の上を通過します。これにより、海面から大量の水蒸気と熱の供給を受け、雲が発達し、日本海側に雪を降らせます。
したがって、ア:南北、イ:北西、ウ:対馬海流の組み合わせが正しいです。
第3問
問1:正解③
<問題要旨>
太陽に関する基本的な事柄(太陽定数、表面温度と放射、スペクトル、核融合反応)についての記述の中から、正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
太陽定数は、地球の「大気圏外」で太陽光線に垂直な面が受け取るエネルギー量のことです。「地表」では大気による吸収や散乱があるため、受け取るエネルギーは太陽定数より小さくなります。
②【誤】
太陽の表面温度は約5800Kであり、ウィーンの変位則によれば、放射エネルギーが最も強くなる波長は可視光線の領域(約500nm)です。紫外線は可視光線より波長が短いため、この記述は誤りです。
③【正】
太陽スペクトルに見られる暗線はフラウンホーファー線と呼ばれます。これは、太陽の光球から放たれた連続スペクトルの光が、それより温度の低い太陽大気(彩層)を通過する際に、大気中の原子によって特定の波長の光が吸収されるために生じます。したがって、この記述は正しいです。
④【誤】
太陽内部で行われている核融合反応は、4個の水素原子核(陽子)が段階的に反応し、1個のヘリウム原子核に変わる反応(陽子-陽子連鎖反応)です。「2個の水素原子核が」という部分が誤りです。
問2:正解①
<問題要旨>
太陽の一生(誕生から終末まで)に関する記述の中から、下線部に誤りを含むものを選ぶ問題です。恒星の進化についての基本的な知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
恒星は、星間空間に浮かぶガスや塵の集まりである星間雲の中で、重力によって物質が集まることで誕生します。重力収縮が始まるのは、星間雲の中でも特に密度の「大きい」部分です。密度の小さい部分では重力が弱く、収縮は起こりにくいです。したがって、「密度の小さい部分が」という記述が誤りです。
②【正】
太陽は、中心核での水素核融合が終わると、外層が大きく膨張して「赤色巨星」になります。表面積が増大するため、表面温度は現在よりも低くなります。この記述は正しいです。
③【正】
赤色巨星になった後、太陽のような質量の比較的小さい恒星は、不安定になった外層ガスを宇宙空間に放出し、中心星の光に照らされて輝く「惑星状星雲」を形成します。この記述は正しいです。
④【正】
惑星状星雲の中心には、核融合を終えた中心核が「白色矮星」として残ります。白色矮星は新たなエネルギーを生まないため、時間をかけてゆっくりと冷えて暗くなっていきます。この記述は正しいです。
問3:正解③
<問題要旨>
対数スケールで示された宇宙の大きさや距離の図において、地球の直径と1天文単位がどの位置に相当するかを答える問題です。具体的な数値を桁数で捉える能力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
1天文単位の位置が違います。
②【誤】
地球の直径、1天文単位ともに位置が違います。
③【正】
地球の直径は約1万2700kmであり、これは1.27×104 kmです。対数スケール上では、104と105の間に位置し、b(104のすぐ右)が最も適当です。
地球と太陽の間の平均距離(1天文単位)は約1億5000万kmであり、これは1.5×108 kmです。対数スケール上では、108と109の間に位置し、c(108のすぐ右)が最も適当です。
したがって、地球の直径がb、1天文単位がcという組み合わせが正しいです。
④【誤】
地球の直径の位置が違います。
問4:正解④
<問題要旨>
恒星間の距離と恒星の大きさの比、銀河間の距離と銀河の大きさの比を比較し、宇宙の大規模構造について考察する問題です。対数スケールの読み取りと、宇宙構造の知識が必要です。
<選択肢>
①【誤】
アとイが誤りです。
②【誤】
アとイが誤りです。
③【誤】
アとイが誤りです。
④【正】
ア:図1から、太陽の直径は約106 m、太陽から最も近い恒星までの距離は約1013.5 kmと読み取れます。距離を直径で割ると、1013.5 / 106 = 107.5 となり、これは107 ×√10、つまり約3000万倍に相当します。「3000万」が適当です。
イ:恒星の大きさと恒星間距離の比(ア)が約3000万倍であるのに対し、銀河の大きさと銀河間距離の比は問題文に「およそ20倍」とあります。したがって、銀河間距離を銀河の大きさで割った値(比)は、恒星の場合に比べて圧倒的に「小さい」です。
ウ:非常に大きなスケールで宇宙を見ると、銀河は一様には分布しておらず、銀河団などが連なって壁のようになり、その間に銀河がほとんど存在しない巨大な空洞(ボイド)がある「泡状(網目状)」構造をなしています。
したがって、ア:3000万、イ:小さい、ウ:泡状(網目状)の組み合わせが正しいです。
⑤【誤】
イが誤りです。
⑥【誤】
アとイが誤りです。
第4問
問1:正解②
<問題要旨>
プレートの沈み込み帯で発生する地震の断層タイプを問う問題です。プレート境界で働く力の種類と、それによって生じる断層の種類を正しく結びつける必要があります。
<選択肢>
①【誤】
正断層は、地殻が左右に引っ張られる力(張力)が働く場所(発散型境界など)で形成されます。沈み込み帯は圧縮の場なので不適当です。
②【正】
プレートの沈み込み帯は、海洋プレートが大陸プレートの下に潜り込む場所であり、両プレートが互いに押し合う強い圧縮の力が働いています。このような圧縮力によって、上盤側が下盤側に対してせり上がる断層を「逆断層」と呼びます。プレート境界で発生する巨大地震は、この逆断層の運動によるものです。
③【誤】
左横ずれ断層は、断層を挟んで互いのブロックが水平に、相手側が左へずれるように動く断層です。トランスフォーム断層などで見られます。
④【誤】
右横ずれ断層は、断層を挟んで互いのブロックが水平に、相手側が右へずれるように動く断層です。トランスフォーム断層などで見られます。
問2:正解③
<問題要旨>
地震によって津波が発生するメカニズムについての文章の空欄補充問題です。津波の発生源と、その際の海水の動きを正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
津波の発生源はマントルではなく海底の変動です。
②【誤】
津波の発生源と海水の動きの両方が誤りです。津波は海水の温度上昇・膨張によって発生するものではありません。
③【正】
ア:地震津波は、震源域の「海底」が、断層運動によって急激に隆起または沈降することによって発生します。
イ:この海底の上下変動により、その上にある「海底から海面までの海水」全体が持ち上げられたり、引き下げられたりします。この大規模な海水の変動が波となって周囲に伝わっていくのが津波です。
したがって、ア:海底、イ:海底から海面までの海水が動く、の組み合わせが正しいです。
④【誤】
海水の動きに関する記述が誤りです。