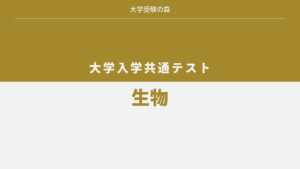解答
解説
第1問
問1:(1)正解⑤ (2)正解③
(1):正解⑤
<問題要旨>
タンパク質合成における翻訳のプロセスで必要とされる要素についての知識を問う問題です。翻訳は、mRNAの遺伝情報を読み取ってアミノ酸を連結させ、タンパク質を合成する過程です。
<選択肢>
①【誤】
DNAポリメラーゼは、DNA複製の際に、DNA鎖を合成する酵素です。翻訳には関与しません。
②【誤】
RNAポリメラーゼは、転写の際に、DNAを鋳型としてmRNAを合成する酵素です。翻訳には関与しません。
③【誤】
RNAのプライマーは、DNA複製の開始点として機能する短いRNA断片です。翻訳には関与しません。
④【誤】
二本鎖DNAは遺伝情報の本体ですが、翻訳の場であるリボソームに直接運ばれるわけではありません。転写によってmRNAに情報が写し取られた後、そのmRNAが翻訳の鋳型となります。
⑤【正】
tRNA(運搬RNA)は、mRNAのコドンに対応した特定のアミノ酸をリボソームまで運ぶ役割を担います。リボソーム上で、コドンとtRNAのアンチコドンが相補的に結合することで、アミノ酸が正しい順序で連結されます。したがって、tRNAは翻訳に必須の要素です。
(2):正解③
<問題要旨>
細胞内で合成された分泌タンパク質が、細胞外へ放出されるまでの輸送経路(小胞輸送)についての理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
矢印①は、細胞外から物質を取り込むエンドサイトーシス(食作用など)の経路を示しています。分泌の経路ではありません。
②【誤】
この矢印は粗面小胞体からゴルジ体を経て細胞外へ至る一連の流れを示してはいますが、一つの矢印で複数のステップ(小胞体→ゴルジ体、ゴルジ体→細胞膜)を含んでしまっています。設問は主要な「経路」を示す矢印を一つ選ぶことを求めており、より特定のステップを指す矢印が他にある場合、最も適当とは言えません。
③【正】
分泌タンパク質は、粗面小胞体で合成された後、まずゴルジ体へと輸送され、そこで糖鎖の付加などの修飾を受けます。この粗面小胞体からゴルジ体への輸送は、分泌タンパク質が細胞外へ運ばれるための中心的かつ必須のステップです。矢印③は、この最も重要な輸送経路を的確に示しているため、これが最も適当な選択肢となります。
④【誤】
矢印④は、ミトコンドリアからゴルジ体への経路を示していますが、分泌タンパク質の主要な合成・輸送経路ではありません。ミトコンドリアは主にエネルギー生産の場です。
⑤【誤】
矢印⑤は、ミトコンドリアから細胞外へ直接分泌される経路を示していますが、このような経路は一般的ではありません。
⑥【誤】
矢印⑥は、ミトコンドリアがリソソームに取り込まれるオートファジー(自食作用)の一部を示していると考えられ、分泌の経路ではありません。
問2:正解②
<問題要旨>
問題文で述べられている「卵形成過程でミトコンドリアの数が一時的に減少し、その結果、偶然によってミトコンドリアDNAの多様性が失われやすくなる」という現象が、集団遺伝学におけるどの進化の仕組みに相当するかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
自然選択は、環境への適応に有利な形質を持つ個体が生き残りやすく、子孫を多く残すことで集団全体の遺伝子構成が変化する現象です。問題文の現象は「偶然の作用」と明記されているため、自然選択とは異なります。
②【正】
遺伝的浮動は、ある生物集団において、偶然によって特定の遺伝子の頻度が変化する現象です。特に、個体数が少ない集団や、災害などで個体数が激減した場合(ボトルネック効果)にその影響が大きくなります。問題文の「ミトコンドリアの数が一時的に減少」し、「偶然の作用により」多様性が失われるという記述は、遺伝的浮動(特にボトルネック効果)の概念と一致します。
③【誤】
突然変異は、DNAの塩基配列が変化することであり、新たな遺伝子(対立遺伝子)を生み出す原因となります。多様性を生み出す要因であり、多様性が失われる直接的な仕組みではありません。
④【誤】
他の集団からの対立遺伝子の流入(遺伝子流動)は、集団間の個体の移動によって遺伝子構成が変化する現象です。これは集団の遺伝的多様性を増加させる方向に働くことが多く、問題文の現象とは逆です。
問3:正解①
<問題要旨>
卵形成過程におけるミトコンドリア数の一時的減少が、卵に含まれるミトコンドリアの種類(正常か、ATP合成機能が低下しているか)の割合にどのような影響を与えるかを考察する問題です。これは、遺伝的浮動(ボトルネック効果)がもたらす結果についての推論です。
<選択肢>
a【正】
細胞内に正常なミトコンドリアと機能低下したミトコンドリアが混在している場合、数が一時的に減少する過程で、偶然、正常なミトコンドリアだけが選ばれて残ることがあります。その後、それらが増殖することで、結果的に卵の中のミトコンドリアが全て正常になる確率が、数が減少しない場合よりも高くなります。
b【誤】
aとは逆に、偶然、機能低下したミトコンドリアのみが残る確率も高まります。しかし、そのような卵は正常な発生や個体の生存に不利益をもたらすため、多くは淘汰されると考えられます。問題文の「個体の生存に不利益をもたらすミトコンドリアが子孫に残りにくくなる」という趣旨を踏まえると、このメカニズムの適応的な意義は、有害なミトコンドリアを排除する方向に働く点にあると解釈できます。そのため、推論としてはaがより適当と考えられます。
c【誤】
ミトコンドリアの数が減少することと、ミトコンドリアDNAの突然変異が起こる頻度(突然変異率)は直接関係ありません。
d【誤】
cと同様に、ミトコンドリア数の減少が、機能低下を正常に戻すような特定の突然変異を誘発することはありません。
以上のことから、適当な記述はaであり、正解は①となります。
第2問
問1:正解④
<問題要旨>
昆虫の眼の色素合成経路に関わる遺伝子A、B、Cの働きを、移植実験の結果から特定する問題です。物質の移動に関する条件(物質2,3は移動可、物質4は移動不可)と、各変異体がどの反応を触媒できないかを組み合わせて考えます。
<選択肢>
まず、前提条件と実験結果を整理します。
・色素Pの合成経路:物質1 →(ア)→ 物質2 →(イ)→ 物質3 →(ウ)→ 物質4 → 色素P
・物質移動:物質2, 3は宿主→移植片へ移動可能。物質4は移動不可。
・変異体Aの移植片は、どの宿主でも色素を合成できない(×)。
・変異体Bの移植片は、変異体Cの宿主で色素を合成できる(○)。
・変異体Cの移植片は、変異体Bの宿主で色素を合成できない(×)。
考察:
タンパク質Aの特定:変異体Aの移植片は、どの宿主からも助けてもらえません。これは、変異体Aが担当する反応の産物が移動できないためと考えられます。物質4は移動できないため、反応ウの産物である物質4を他の宿主から供給してもらうことはできません。したがって、タンパク質Aは反応ウを触媒していると推測されます。
タンパク質BとCの順序の特定:
・「変異体B移植片を、変異体C宿主に移植すると○」:これは、宿主Cが蓄積している物質を、移植片Bが利用して色素Pを合成できたことを意味します。このことから、Cが担当する反応は、Bが担当する反応よりも上流にある(C→Bの順)と分かります。もし逆(B→C)だと、宿主Bが蓄積する物質を移植片Cは利用できないはずです。
・具体的に考えます。仮にア=B、イ=Cだとします。宿主C(イが×)は物質2を蓄積します。移植片B(アが×)は、宿主Cから物質2をもらえば、反応イとウを進めることができるため、結果は○となり、実験結果と一致します。
・「変異体C移植片を、変異体B宿主に移植すると×」:これは、宿主Bが蓄積している物質を、移植片Cが利用できなかったことを意味します。上記のア=B、イ=Cの仮説で検証します。宿主B(アが×)は物質1を蓄積します。移植片C(イが×)は、宿主Bから物質1をもらっても、自分の変異(イ)で反応が止まってしまうため、結果は×となり、実験結果と一致します。
以上の考察から、ア=タンパク質B、イ=タンパク質C、ウ=タンパク質Aという結論が得られます。これに合致する選択肢は④です。
問2:正解③
<問題要旨>
実験1の結果から、色素合成の出発物質である「物質1」が宿主から移植片へ移動できるかどうかを判断する問題です。実験結果から論理的に言えることと言えないことを見極める思考力が問われます。
<選択肢>
①【誤】
野生型の移植片は、宿主から物質1が供給されなくても、自分自身で物質1から色素Pを合成できます。そのため、この結果だけでは、物質1が宿主から移植片へ移動したかどうかを判断することはできません。
②【誤】
①と同様に、野生型の移植片は自律的に色素を合成できるため、どの変異体の宿主に移植された場合でも、宿主からの物質1の供給の有無は判断できません。
③【正】
物質1が宿主から移植片へ移動できるかどうかを調べるには、「物質1を合成できない変異体」の移植片を、物質1を供給できる宿主(例えば野生型)に移植し、色素が合成されるかどうかを見る必要があります。今回の実験では、そのような「物質1を欠く変異体」は使われていません。したがって、実験1の結果だけからは、物質1が移動できるかどうかを判断することはできません。
④【誤】
「物質1を欠く変異体の宿主」という条件は、物質1の移動の可否を判断するために適切ではありません。判断に必要なのは「物質1を欠く変異体の移植片」です。したがって、この記述は不適切です。
問3:正解⑤
<問題要旨>
遺伝子CがX染色体上に存在する場合の伴性遺伝に関する計算問題です。交配する雌雄の遺伝子型を正しく把握し、生まれてくる子の遺伝子型と表現型の分離比を考えます。
<選択肢>
・親の遺伝子型を考えます。
– 雌:野生型で、「正常な遺伝子Cが存在するX染色体を2本持つ」とあるので、遺伝子型はホモ接合の XCXCとなります。
– 雄:変異体Cなので、遺伝子型は XCY となります。
・この両親から生まれる子の遺伝子型を考えます。
– 雌(子)は、母親から XCを、父親から XCを受け継ぐので、全て XCXCとなります。
– 雄(子)は、母親から XCを、父親から Y を受け継ぐので、全て XCY となります。
・子の表現型を考えます。
– 設問では雄の眼の色を調べています。子の雄の遺伝子型は全て XCY であり、正常な遺伝子Cを持つため、眼で色素Pが合成されます。
– したがって、雄の個体においては100%の個体で色素Pが合成されることになります。
①【誤】0%ではありません。
②【誤】25%ではありません。
③【誤】50%ではありません。
④【誤】75%ではありません。
⑤【正】100%です。
第3問
問1:正解⑤⑥
<問題要旨>
植物ホルモンの機能に関する基本的な知識を問う問題です。代表的な植物ホルモンであるオーキシン、ジャスモン酸、ジベレリン、アブシシン酸、サイトカイニン、エチレンの働きについて、正しい記述を二つ選びます。
<選択肢>
①【誤】
オーキシンは、細胞壁を緩めることで細胞の伸長を「促進」する働きがあります。マカラスムギの幼葉鞘を用いた実験は、オーキシンの成長促進作用を示す代表的な例です。したがって、「抑制する」という記述は誤りです。
②【誤】
ジャスモン酸は、昆虫による食害などに応答して合成され、害虫に抵抗性を示すタンパク質の合成を誘導する働きがあります。したがって、「食害が拡大しやすくなる」という記述は誤りです。
③【誤】
ジベレリンは光によって分解される性質があります。暗所で発芽・成長した芽生え(黄化個体)は、茎の伸長が著しいですが、これはジベレリンが多く蓄積しているためです。明所に移すと、ジベレリンが分解され、茎の伸長が抑制されます。したがって、「増加する」という記述は誤りです。
④【誤】
アブシシン酸は、種子の休眠を維持し、発芽を「抑制」するホルモンです。また、レタス種子の発芽を促進するのは赤色光であり、遠赤色光は発芽を抑制します。したがって、この記述は二重に誤っています。
⑤【正】
頂芽で生産されるオーキシンは、側芽の成長を抑制します(頂芽優勢)。頂芽を取り除いたり、側芽にサイトカイニンを直接与えたりすると、この抑制が解除され、側芽が成長を始めます。したがって、この記述は正しいです。
⑥【正】
エチレンは、果実の成熟を促進するガス状のホルモンです。未熟な果実を密閉した容器に入れ、エチレンを注入すると、成熟が早まります。したがって、この記述は正しいです。
問2:正解①
<問題要旨>
実験結果を基に、未知のタンパク質の機能を推論する問題です。変異体Aの形質(矮性、ジベレリン量の低下、ジベレリン投与による回復)から、タンパク質Aの本来の働きを考えます。
<選択肢>
実験結果を整理します。
変異体Aは、通常条件で草丈が低い(矮性)。
変異体Aにジベレリンを与えると、野生型と同様に大きく伸長する。
変異体Aは、体内のジベレリン量が野生型より少ない。
この3つの事実から、変異体Aは「ジベレリンを外部から補えば正常になる」こと、そしてその原因が「体内でジベレリンを十分に作れていない」ことであると推測できます。タンパク質Aの機能が失われた結果、ジベレリンが合成できなくなったと考えられるため、野生型の個体において、タンパク質Aはジベレリンを合成する働きを担っていると結論付けられます。
①【正】
上記の推論に合致します。タンパク質Aがジベレリン合成酵素としてはたらいていると考えられます。
②【誤】
もしタンパク質Aがジベレリンを分解する働きを持つなら、その機能が失われた変異体Aでは、逆に体内のジベレリン量が増加し、過剰伸長するはずです。実験結果と逆です。
③【誤】
もしタンパク質Aがジベレリンを不活性化する働きを持つなら、②と同様に、変異体Aではジベレリン量が増加するはずです。
④【誤】
ジベレリンを輸送する働きが失われた場合、体内の総量が減少するとは考えにくいです。また、外部から与えたジベレリンに応答できることから、輸送よりも合成段階の問題である可能性が高いです。
⑤【誤】
実験結果から、タンパク質Aがジベレリンの合成に深く関わっていることは明らかです。
問3:正解①
<問題要旨>
ジベレリンの受容体が機能を失った変異体Rが、ジベレリンの有無によってどのような成長を示すかを予測する問題です。ホルモンが作用するためには、受容体との結合が不可欠であることを理解しているかがポイントです。
<選択肢>
変異体Rでは、ジベレリンの受容体であるタンパク質Rの機能が失われています。これは、細胞がジベレリンを認識できない状態であることを意味します。
・通常条件:体内でジベレリンが合成されていても、受容体がないため細胞は応答できません。その結果、ジベレリンが作用しない場合と同様に、茎の伸長が抑制され、矮性を示すと考えられます。
・ジベレリン条件:外部からジベレリンを大量に与えても、受容体がないため細胞は応答できません。したがって、通常条件と変わらず、矮性のままであると考えられます。
よって、変異体Rは通常条件でもジベレリン条件でも、ともに矮性を示すと予測されます。
①【正】
通常条件、ジベレリン条件ともに「矮性」であり、上記の予測と一致します。
②【誤】
ジベレリンに応答できないため、「通常」の成長はしません。
③【誤】
ジベレリンに応答できないため、「大きく伸長」はしません。
④【誤】
通常条件では「矮性」を示します。
⑤【誤】
通常条件では「矮性」を示します。
⑥【誤】
通常条件では「矮性」を示し、ジベレリンに応答できないため「大きく伸長」はしません。
⑦~⑨【誤】
ジベレリンに応答できないため、いずれの条件でも大きく伸長することはありません。
問4:正解②
<問題要旨>
「タンパク質Sは、タンパク質R(受容体)との相互作用を通して情報を受け取り、遺伝子の発現を調節する」という仮説を検証するために、適当「でない」実験を選ぶ問題です。仮説のどの部分を検証しようとしているのかを、各選択肢について吟味する必要があります。
<選択肢>
仮説のポイントは以下の3点です。
(1) Sが遺伝子の発現を調節する(転写調節領域に結合する)
(2) SはRと相互作用(結合)する
(3) (2)の相互作用はジベレリンによって変化する
①【適当】
これは、仮説の(1)「Sが遺伝子の発現を調節する」ことを検証する実験です。ジベレリンに応答してSが遺伝子に結合する量が増えるならば、仮説を支持します。
②【不適当】
この実験は、野生型と変異体でタンパク質Sの「量」を比較するものです。変異体Sは「機能」を失っているのであり、「量」が変化しているとは限りません。たとえ量が同じでも機能がなければ応答は低下します。したがって、タンパク質の量を調べることは、SとRの相互作用や遺伝子発現調節という仮説の核心部分を検証することにはならず、不適当です。
③【適当】
これは、仮説の(1)「Sが遺伝子の発現を調節する」ことを検証する実験です。Sを過剰に生産させることで、遺伝子発現がどう変化するかを見れば、Sの機能(発現を促進するのか抑制するのかなど)を検証できます。
④【適当】
これは、仮説の(2)「SはRと相互作用する」ことと(3)「ジベレリンによって変化する」ことを直接検証する実験です。ジベレリン存在下でSとRの結合が強まる(あるいは弱まる)ことが示されれば、仮説を強く支持します。
第4問
問1:正解⑤
<問題要旨>
社会性昆虫であるミツバチのワーカー(働きバチ)が行う利他行動が、なぜ自らの子孫を残さないにもかかわらず進化的に維持されるのか、そのメカニズムである血縁選択の成立条件を問う問題です。
<選択肢>
ワーカーの利他行動が、結果的に「自己と共通する遺伝子を広める効果」を持つためには、包括適応度(自身の子孫の数だけでなく、血縁者の子孫の数を加味した適応度)を高める必要があります。これを満たすための条件を考えます。
a. ワーカーの行動が、他のワーカーの生存を助けること
b. ワーカーの行動が、生殖個体の生存を助けること
c. ワーカーどうしが血縁関係にあること
d. ワーカーと生殖個体が血縁関係にあること
【考察】
ワーカー自身は原則として子を産みません。コロニーの中で次世代に遺伝子を伝えるのは、女王バチや雄バチなどの生殖個体です。
したがって、ワーカーの利他行動が遺伝的に意味を持つためには、その行動が生殖個体の生存や繁殖を手助けするものでなければなりません。これにより、生殖個体がより多くの子孫を残すことができます。これが条件 b です。
さらに、その生殖個体が残した子孫に、ワーカー自身と共通の遺伝子が含まれていなければ意味がありません。そのためには、行動の対象であるワーカーと生殖個体との間に血縁関係があることが必須となります。これが条件 d です。
条件bとdがそろうことで初めて、ワーカーは自ら子を産まなくても、自分と共通の遺伝子を血縁者(女王など)を通じて次世代に広めることができるのです。
選択肢 a と c について:ワーカーどうしが助け合い(a)、血縁関係にある(c)こともコロニーの維持に重要ですが、それだけでは遺伝子を次世代に広める直接的な説明にはなりません。ワーカーを助ける行動も、最終的に女王などの生殖個体の繁殖に貢献して初めて、遺伝子を広める効果につながります。したがって、最も根本的で必須の条件は b と d の組み合わせです。
以上のことから、⑤ (bとd) が正解となります。
問2:正解①
<問題要旨>
学習や経験によらず、生まれつき備わっている「生得的行動」の例を具体例から選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
カイコガの雄が、雌の分泌する性フェロモンという化学物質(鍵刺激)に特有のパターンで反応する行動は、学習によるものではなく、遺伝的にプログラムされた生得的行動(走性)の一例です。
②【誤】
ベルの音(本来は唾液分泌と無関係な刺激)と餌(唾液分泌を引き起こす刺激)が繰り返し対で提示されることで、ベルの音だけで唾液を出すようになるのは、古典的条件づけ(パブロフの犬の実験で有名)という学習行動です。
③【誤】
アメフラシの水管に繰り返し弱い刺激を与え続けると、次第に反応しなくなる現象は「慣れ」と呼ばれる、単純な学習行動の一種です。
④【誤】
尾部への強い刺激(有害刺激)を経験した後に、通常では反応しないような水管への弱い刺激にも強く反応するようになる現象は「感作」と呼ばれる、学習行動の一種です。
問3:正解③
<問題要旨>
ミツバチが巣から餌場までの距離をどのように知覚しているかを調べる実験の考察問題です。この解説は、正解が③であることを前提に、その結論に至る論理を説明します。
<選択肢の考察>
この問題を解く鍵は、**「ワーカーは飛行中に消費したエネルギー量を基に、飛行距離を判断している」**という仮説を立てて考察することです。
アとウの考察
ウ(距離を判断する手がかり):実験で唯一変更されたのは「視覚情報」ですが、それによってワーカーの「行動」が変化したと考えます。垂直縞という不自然で動きの速い視覚情報の中を飛ぶことは、ワーカーにとって飛行を安定させるのが難しく、通常よりも多くの**「エネルギー消費」(ウ)**を強いると推測されます。
ア(垂直縞での知覚距離):ワーカーが「エネルギー消費」を距離の基準としているならば、この過大なエネルギー消費を「長い距離を飛んだ」と誤って認識してしまいます。その結果、実際の距離は10mしかないにもかかわらず、長距離を意味する8の字ダンスを踊ったと考えられます。したがって、知覚した距離は実際に飛行した距離より**「より長い」(ア)**となります。
イの考察
イ(水平縞と垂直縞の比較):この項目は解釈が非常に難しいですが、**ウ(エネルギー消費)**を判断の基準とする考え方を一貫して用います。
水平縞のトンネルでは、景色が上下に流れないため、ワーカーは比較的少ないエネルギーで安定して飛行できたと推測されます。その結果、エネルギー消費量も実際の距離(10m)に相応するものとなり、正しい円形ダンスを踊りました。
ここで「と変わらない」(イ)が何を指すかですが、実験の結論として「距離の判断基準はエネルギー消費である」と考えるならば、垂直縞のときも水平縞のときも**「エネルギー消費を基準にして距離を判断する」という根本的な仕組み自体は変わらない**、と解釈することができます。
設問文の表現には難しい点がありますが、アとウが上記の推論で確定することから、選択肢として③が最も適当であると判断されます。
以上の考察から、ア=「より長い」、イ=「と変わらない」、ウ=「エネルギー消費」となる選択肢③が正解です。
問4:正解③
<問題要旨>
ミツバチのダンスが伝達する情報が、どのような性質のものであるかを問う問題です。ダンスは「巣を基点とした餌場の方向と距離」という相対的な位置情報なのか、それとも餌場の絶対的な座標情報なのかを考えます。
<選択肢>
実験では、巣(H)の中で、餌場(F)へのダンスを見て情報を得たワーカーを、別の場所(R)で放しています。
・ミツバチのダンスは、「巣(H)を基点として、太陽の方向から特定の角度に、特定の距離だけ飛べ」という情報(ベクトル情報)を伝達します。
・ワーカーはこの情報を受け取った後、自分がどこにいるか(現在地)を認識し、そこからその指示を実行するわけではありません。
・ワーカーは、自分が巣(H)から飛び立ったと仮定して、受け取った指示通りの方角と距離を飛行します。
・したがって、場所Rで放されたワーカーは、巣(H)から餌場(F)へ向かうのと同じ方向・同じ距離だけ、場所Rを基点として飛行すると考えられます。
・図を見ると、HからFへのベクトル(方向と距離)を、Rを始点として適用した軌跡は、矢印③に相当します。
①、②、④、⑤【誤】
他の軌跡は、餌場Fや巣Hの絶対位置を目指していたり、方向や距離が異なっていたりするため、ダンスが伝える情報の性質と合致しません。
第5問
問1:正解①
<問題要旨>
生態系における物質生産に関する基本的な知識を問う問題です。総生産量、純生産量、呼吸量、現存量、エネルギー効率などの用語の定義を正確に理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【正】
地球全体で見ると、面積は海洋の方が陸地より広いですが、単位面積当たりの純生産量は陸地の方が大きいです。その結果、生態系全体の純生産量は、陸地全体(約1150億トン/年)の方が海洋全体(約550億トン/年)よりも大きいとされています。
②【誤】
エネルギー効率は、同化量(総生産量)に対する次の栄養段階への移行エネルギー(成長量や被食量)の割合などで示されます。総生産量 = 純生産量 + 呼吸量 の関係があり、呼吸量が大きいほど、同化エネルギーのうち消費される分が大きくなり、成長などに使われる純生産量は小さくなります。その結果、次の栄養段階へ渡されるエネルギーは減るため、エネルギー効率は「低く」なります。
③【誤】
森林生態系は、巨大な樹木が生産者として存在するため、単位面積当たりの現存量(バイオマス)は、草原や海洋生態系などと比較して非常に大きくなります。
④【誤】
純生産量は、生産者が光合成によって生産した有機物の総量(総生産量)から、生産者自身の呼吸によって消費した有機物量(呼吸量)を差し引いたものです。純生産量 = 総生産量 – 呼吸量。一方、個体や個体群の「成長量」は、この純生産量から、他の生物に食べられた量(被食量)と、枯死した量(枯死量)を差し引いたものになります。成長量 = 純生産量 – (被食量 + 枯死量)。したがって、記述は誤りです。
問2:正解②⑤
<問題要旨>
海洋の異なる海域における純生産量(植物プランクトンの光合成量)の違いが、どのような環境要因によって生じているかを考察する問題です。特に、光、水温、栄養塩類(リン、窒素など)が主な制限要因となります。
<選択肢>
図2から、純生産量は 日本沿岸 > 太平洋北部 > 太平洋赤道付近 となっています。
①【誤】
日本沿岸は、河川から陸地の栄養分が流れ込むことや、海底から栄養塩類が湧き上がる(湧昇)ため、栄養塩類が「豊富」です。これが、植物プランクトンが活発に増殖し、純生産量が大きくなる主な理由です。したがって、「栄養塩類が少ないため」という記述は誤りです。
②【正】
上記①の解説の通り、日本沿岸域は河川からの栄養塩類の流入や湧昇によって栄養が豊かなため、純生産量が大きくなります。
③【誤】
物質生産(光合成)には光が必須です。したがって、光が届かない深い水深では、化学合成細菌による化学合成を除き、物質生産は行われません。太平洋北部の純生産量が赤道付近より大きいのは、水温が低いために海水が鉛直方向に混ざりやすく、深層の栄養塩類が表層に供給されやすいためです。
④【誤】
消費者が多いということは、それだけ生産者が豊富にいることを示唆します。純生産量が小さい原因を消費者の多さに求めるのは、因果関係が逆です。日本沿岸の方が生産者も消費者も多い(生物量が多い)と考えられます。
⑤【正】
太平洋赤道付近のような大陸から遠く離れた外洋域は、河川などからの栄養塩類の供給がほとんどなく、表層の海水も成層して安定しているため、深層からの供給も少ないです。その結果、栄養塩類が不足し、植物プランクトンの増殖が制限され、純生産量が小さくなります。
⑥【誤】
太平洋赤道付近は光が強いですが、⑤で述べたように栄養塩類が著しく不足していることが、純生産量が小さい主な制限要因となっています。光が強くても、他の要因が不足していれば生育は促進されません。
問3:正解③
<問題要旨>
鉄(Fe)の添加と水温の違いが、植物プランクトンの増殖(クロロフィル量)と栄養塩(窒素N)の消費にどう影響するかを、グラフから正確に読み取り、実験全体の考察として最も適当なものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
図3の5℃区を見ると、Feを添加しない場合(白丸)はクロロフィル量がほぼ横ばいですが、Feを添加した場合(黒丸)は8日目からわずかに増加しています。したがって、「影響しない」とは言えず、誤りです。
②【誤】
図3と図4の8℃区・Fe添加ありのデータを見ると、N量(図4)が7日目頃にほぼ0になっていますが、クロロフィル量(図3)は8日目まで増加を続けています。増殖が止まるのとNがなくなるのは「同時」ではないため、この記述は誤りです。
③【正】
図4は、海水中のN(窒素)量の変化を示しており、Nが減少した分だけ植物プランクトンに消費された(増殖に使われた)ことを意味します。各条件でのNの最終的な減少量を見ると、
・5℃区/Feなし:1.0 → 約0.8(消費量 約0.2)
・他の全ての条件では、これよりも大きくNが減少しています。
したがって、「Nの消費量が最も小さいのは、5℃区でFeを添加しないときである」という記述は、グラフから読み取れる客観的な事実であり、正しいです。これは、低温かつ鉄不足という、植物プランクトンの増殖にとって最も厳しい条件を反映した結果と言えます。
④【誤】
図3の8℃区と18℃区を見ると、Feを添加しない場合(白丸)でも、クロロフィル量はわずかながら増加しています。したがって、「増殖しない」という記述は誤りです。
⑤【誤】
この記述は、一見正しそうに見えます。Feを添加した場合(黒丸)だけを比べると、確かに18℃>8℃>5℃の順で増殖が速いです。しかし、Feを添加しない場合(白丸)では、水温が高くても増殖は非常に緩やかです。特に、18℃/Feなしの増殖は、8℃/Feありの増殖よりもはるかに遅いです。このことから、この実験条件下では鉄の有無が水温以上に増殖を左右する要因となっており、「水温が高いほど増殖は速い」という記述は、必ずしも常に成り立つわけではないため、実験全体の考察としては不適切です。
第6問
問1:(アイ)正解② (ウエ)正解⑨
<問題要旨>
地球の歴史における光合成と大気環境の変化、そしてそれに伴う生物の進化について、基本的な知識を問う問題です。前半は光合成の仕組みの進化、後半は酸素の増加がもたらした影響について問われています。
ア・イの解説 (正解 ②)
光合成は、光エネルギーを利用して、どこかから持ってきた**電子(ア)**を二酸化炭素(CO₂)に渡して有機物を合成する反応です。
初期の光合成細菌:初期の光合成細菌は、電子供与体として硫化水素(H₂S)を利用しました。硫化水素を分解して、電子(ア)と水素イオン(H⁺)を取り出していたのです。
シアノバクテリアの登場:その後登場したシアノバクテリアは、地球上に豊富に存在する水(H₂O)を電子供与体として利用する、画期的な能力を身につけました。水を分解して電子を取り出すためには非常に強い力が必要で、それを可能にしたのが**光化学系Ⅱ(イ)**という仕組みです。この光化学系Ⅱの働きによって、シアノバクテリアは水を分解して電子(ア)を取り出し、その副産物として酸素(O₂)を発生させる光合成を行うようになりました。
したがって、アには「電子」、**イには「光化学系Ⅱ」**が入ります。
ウ・エの解説 (正解 ⑨)
ウ(呼吸):シアノバクテリアが放出した酸素が海と大気に蓄積すると、今度はその酸素を利用して、有機物から効率よくエネルギーを取り出す呼吸(ウ)(好気呼吸)を行う生物が登場し、繁栄しました。ミトコンドリアによる呼吸は、酸素を使わない方法に比べて格段に多くのATPを生産できるため、その後の真核生物の大型化や複雑化につながりました。
エ(紫外線):大気中に増えた酸素(O₂)は、上空の成層圏で太陽からの強いエネルギーを受けるとオゾン(O₃)に変化し、オゾン層を形成しました。このオゾン層は、生物のDNAを傷つけるなど有害な太陽光の**紫外線(エ)**を吸収してくれます。このバリアができたおかげで、生物は水中にいなくても有害な光から守られるようになり、陸上へと進出することが可能になったのです。
したがって、ウには「呼吸」、**エには「紫外線」**が入ります。
問2:正解③
<問題要旨>
真核生物の細胞小器官(葉緑体やミトコンドリア)の起源に関する「細胞内共生説」についての理解を問う問題です。特に、藻類の葉緑体がどのようなプロセスで生じたかを問うています。
<選択肢>
①【誤】
細胞内共生説によれば、葉緑体の起源となったのは、酸素を発生する光合成を行う「シアノバクテリア」様の原核生物です。緑色硫黄細菌は酸素を発生しない光合成を行い、葉緑体の起源ではありません。
②【誤】
好気性細菌が細胞内に共生して生じたのは、葉緑体ではなくミトコンドリアです。
③【正】
細胞内共生説では、ある真核生物の祖先が、酸素発生型の光合成を行う原核生物(シアノバクテリア様の生物)を細胞内に取り込み、それが共生関係を経て葉緑体になったとされています。これが藻類の起源です。したがって、この記述は正しいです。
④【誤】
葉緑体は、ミトコンドリアと同様に、現在でも独自のDNAを持っています。共生の過程で多くの遺伝子は核へ移行しましたが、全てを失ったわけではありません。また、大気中のO₂濃度の上昇が葉緑体のDNAを失わせたという事実はありません。
⑤【誤】
問題文の図1を見ると、藻類の出現は約15億年前と示されています。約10億年前ではありません。
問3:正解③
<問題要旨>
植物が、水中から乾燥した陸上環境へ進出する際に獲得した、乾燥への適応に関する記述の中から、適当で「ない」ものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【適当】
気孔は、光合成に必要なCO₂を取り込むための入り口ですが、同時に水蒸気の出口でもあります(蒸散)。乾燥した環境では、体内の水分を保持するために気孔を閉じる仕組みが発達しました。
②【適当】
クチクラ層は、植物の体の表面(表皮細胞の外側)を覆う、クチンという脂質物質からなる層です。水を弾く性質があり、体表からの水分の蒸発を防ぐバリアとして機能します。
③【不適当】
陸上に最初に進出した植物は、コケ植物のようなものと考えられています。コケ植物は、シダ植物や種子植物が持つような、水を効率的に輸送するための維管束(道管や師管)が分化していません。維管束を持つ植物(シダ植物など)が登場するのは、コケ植物よりも後の時代です。したがって、「最初の植物は…維管束を持っていた」という記述は誤りです。
④【適当】
種子植物は、維管束や気孔、クチクラ層といった乾燥への適応に加え、受精に水を必要としない花粉や、乾燥に強い種子を形成することで、より多様で乾燥した陸上環境へと分布を広げることに成功しました。
問4:正解①
<問題要旨>
CO₂固定酵素ルビスコの性質が、異なる光合成生物のグループでどのように異なり、それが地球大気のCO₂濃度の変遷とどう関連していると考えられるかを、グラフから読み取り考察する問題です。
<選択肢>
図1は、地球史を通じて大気中のCO₂濃度が劇的に低下してきたことを示しています。図2は、後に出現した生物(シアノバクテリア→藻類→シダ植物→被子植物)ほど、より低いCO₂濃度で効率よく反応(CO₂固定)できるルビスコを持っていることを示しています。
これらの情報を組み合わせると、大気中のCO₂濃度が低下していく環境圧の中で、より低いCO₂を効率的に利用できるような性質を持つルビスコを獲得した生物が、その後の時代で繁栄していった、という進化の道筋が推測できます。
a【正】
上記の推論に合致します。グラフは、大気中のCO₂濃度が低下するという環境変化に対応して、光合成生物がより低CO₂濃度に適応したルビスコを進化させてきたことを示唆しています。
b【誤】
藻類が出現した約15億年前のCO₂濃度は、図1から1%以上と非常に高い値です。一方、図2の藻類のルビスコのグラフを見ると、CO₂濃度が0.4%程度で反応速度が最大値に近づいています(飽和しています)。したがって、出現当時の高いCO₂濃度では、すでに飽和状態にあり、「最大値に近い速度を示す」とは言えません。
c【誤】
被子植物のルビスコは、図2を見ると0.2%程度のCO₂濃度でほぼ最大速度に達しています。現在のCO₂濃度(約0.04%)は、このグラフではかなり低い領域にあり、反応速度は最大値には程遠い状態です。
d【誤】
cで述べたように、現在のCO₂濃度(0.04%)では、植物のルビスコの反応速度は飽和していません。したがって、CO₂濃度が0.08%まで上昇すれば、CO₂固定速度は明らかに上昇すると予測されます。「影響を与えない」という記述は誤りです。
以上より、正しい記述はaのみであり、正解は①です。