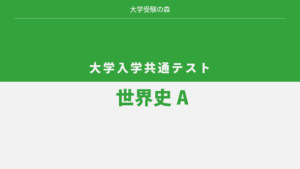解答
解説
第1問
問1:正解③
<問題要旨>
1830年にフランスで起こった七月革命について、タフターウィーの著作を史料として、革命によって変化した王の称号の意味と、この革命がヨーロッパの他国に与えた影響を正しく理解できているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
称号の組み合わせが逆です。「フランスの王」は神から授かった絶対的な王権を、「フランス人の王」は国民によって選ばれた王であることを示します。資料から、退位したシャルル10世が用いた称号がア、新たに即位したルイ=フィリップが用いた称号がイであるため、アが「フランスの王」、イが「フランス人の王」となります。
②【誤】
称号の組み合わせが逆である点、および出来事の影響に関する文が誤りです。七月王政では、選挙権は一部の富裕層に限られた制限選挙であり、普通選挙は導入されませんでした。
③【正】
称号と出来事の影響に関する文の組み合わせが正しいです。シャルル10世までのブルボン朝の君主は「フランスの王」を称し、七月革命で王位に就いたルイ=フィリップは国民の支持を背景とすることを示す「フランス人の王」を称しました。また、七月革命の影響を受けて、1830年にブリュッセルで暴動が起こり、ベルギーはオランダからの独立を宣言しました。
④【誤】
出来事の影響に関する文が誤りです。七月王政では普通選挙は導入されませんでした。普通選挙が導入されるのは、1848年の二月革命後のことです。
問2:正解④
<問題要旨>
19世紀から20世紀にかけてのエジプト近代史における主要な出来事を、年代順に正しく配列できるかを問う問題です。
<選択肢>
う ワフド党が独立運動を展開したのは、第一次世界大戦後の1918年以降です。
え ムハンマド=アリーがエジプト総督として富国強兵を進めたのは、19世紀前半(1805年~1848年)です。
お ウラービーが「エジプト人のためのエジプト」をスローガンに蜂起したのは、1881年~1882年のことです。
これらの出来事を年代の古い順に並べると、え(19世紀前半)→お(1881年)→う(1918年以降)となります。
したがって、④の「え→お→う」が正しい配列です。
①【誤】
配列が逆です。
②【誤】
配列が誤っています。
③【誤】
配列が誤っています。
④【正】
上記の通り、正しい年代順の配列です。
⑤【誤】
配列が誤っています。
⑥【誤】
配列が誤っています。
問3:正解①
<問題要旨>
19世紀後半から20世紀初頭にかけてのイスラーム世界における、ヨーロッパ列強の進出に対抗する様々な思想や運動に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
アフガーニーは、19世紀後半に活躍したイスラーム改革運動の思想家です。彼は、ヨーロッパ列強の侵略に直面するムスリム(イスラーム教徒)に対し、国や宗派を超えて団結する必要があるという「パン=イスラーム主義」を提唱しました。
②【誤】
ムスタファ=ケマル(アタテュルク)は、トルコ革命を指導し、トルコ共和国を建国した人物です。彼は近代化政策の一環として、1928年にトルコ語の表記をアラビア文字からラテン文字(ローマ字)に改める文字改革を行いました。したがって、アラビア文字を「導入した」という記述は誤りです。
③【誤】
ワッハーブ運動は、18世紀にアラビア半島で始まったイスラーム改革運動で、「クルアーン(コーラン)に戻れ」をスローガンに、イスラームの純化を目指しました。近代西欧をモデルとする改革運動ではないため、記述は誤りです。
④【誤】
イラン立憲革命(1905年~1911年)により、アジアで最初の憲法と議会が成立しましたが、この動きを警戒したロシアとイギリスの干渉によって革命は挫折しました。アメリカ合衆国の干渉によるものではないため、記述は誤りです。
問4:正解③
<問題要旨>
会話文中の空欄ウに入る「中国と日本との戦争」が日清戦争(1894年~1895年)であることを特定し、日清戦争に関する記述として正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
これは、1874年に起こった台湾出兵の理由です。日清戦争の原因ではありません。
②【誤】
日本がドイツの租借地がある青島(チンタオ)を占領したのは、第一次世界大戦(1914年~1918年)中の出来事です。
③【正】
日清戦争の講和条約である下関条約(1895年)によって、清から日本へ遼東半島、台湾、澎湖諸島が割譲されました。したがって、この記述は正しいです。
④【誤】
アメリカ合衆国大統領の調停によって講和条約が結ばれたのは、日露戦争(1904年~1905年)のポーツマス条約です。
問5:正解②
<問題要旨>
魯迅の小説『藤野先生』が発表された年(1926年)と、それに関連する20世紀初頭の中国と日本の関係史上の出来事を、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
あ 「扶清滅洋」をスローガンに義和団が蜂起し、それに清が乗じて列国に宣戦布告したことで起こったのが義和団事件(北清事変)です。日本を含む八か国連合軍が出兵したのは1900年です。
い 清朝の最後の皇帝であった溥儀が、日本の後押しで満洲国の執政(のちに皇帝)の地位に就いたのは、満洲事変後の1932年です。
『藤野先生』は、会話文中に「五・三〇事件が起こった年(1925年)の翌年に発表した」とあることから、1926年の出来事です。
これらの出来事を年代の古い順に並べると、あ(1900年)→『藤野先生』の発表(1926年)→い(1932年)となります。
したがって、②の「あ→『藤野先生』の発表→い」が正しい配列です。
①【誤】
配列が誤っています。
②【正】
上記の通り、正しい年代順の配列です。
③【誤】
配列が誤っています。
④【誤】
配列が誤っています。
⑤【誤】
配列が誤っています。
⑥【誤】
配列が誤っています。
問6:正解②
<問題要旨>
会話文中の空欄エに入る都市が南京であることを特定し、南京の歴史に関する記述の正誤を判断する問題です。汪兆銘が1940年に樹立した親日政府(南京国民政府)の首都は南京です。
<選択肢>
う 太平天国(1851年~1864年)は、南京を占領し、「天京」と改称して首都としました。したがって、この記述は正しいです。
え 李自成が率いる反乱軍によって占領され、明が滅亡するきっかけとなった都市は、首都の北京です。南京ではありません。したがって、この記述は誤りです。
以上から、「う」が正、「え」が誤の組み合わせである②が正解となります。
①【誤】
「え」が誤りです。
②【正】
上記の通り、「う」が正、「え」が誤です。
③【誤】
「う」が正、「え」が誤です。
④【誤】
「う」が正です。
第2問
問1:正解①
<問題要旨>
風刺画の読解を通じて、第一次バルカン戦争の敗戦国がオスマン帝国であることを特定し、オスマン帝国の歴史に関する記述として正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
カルロヴィッツ条約は、1699年に、大トルコ戦争でオスマン帝国がオーストリア、ポーランド、ヴェネツィアなどの神聖同盟に敗れた結果結ばれた条約です。この条約で、オスマン帝国は初めてヨーロッパ列強に領土を割譲(ハンガリーなど)しました。これはオスマン帝国の歴史に関する正しい記述です。
②【誤】
レザー=ハーンがクーデタを起こして実権を握ったのは、イラン(ペルシア)のカージャール朝で、1925年にパフレヴィー朝を創始しました。オスマン帝国の出来事ではありません。
③【誤】
コーカンド、ブハラ、ヒヴァの3ハン国は中央アジアに存在し、19世紀後半にロシア帝国によって支配下に置かれました。オスマン帝国とは関係ありません。
④【誤】
イギリス人へのタバコ利権売却に反対するボイコット運動(タバコ=ボイコット運動)が起こったのは、19世紀末のイラン(カージャール朝)です。
問2:正解①
<問題要旨>
第一次バルカン戦争(図1)と第二次バルカン戦争(図2)を描いた風刺画を比較し、描かれている国々の関係性を正しく読み取る問題です。
<選択肢>
①【正】
図1の4人の軍人は、オスマン帝国と戦ったバルカン同盟の国々(セルビア、ブルガリア、ギリシャ、モンテネグロ)です。図2では、第一次バルカン戦争の領土配分をめぐってブルガリア(中央の犬)と他の3国(セルビア、ギリシャ、モンテネグロなど)が対立した第二次バルカン戦争が描かれています。したがって、図1の軍人と図2の犬は、同じバルカン同盟の国々を描いています。
②【誤】
図1で描かれている国々は、図2でも描かれています。
③【誤】
図1で怪物として描かれている敗戦国はオスマン帝国です。図2で中央の犬として描かれている敗戦国はブルガリアです。両国は異なります。
④【誤】
図1の怪物(オスマン帝国)は、第二次バルカン戦争ではブルガリアを攻撃する側に回りましたが、中央の犬(ブルガリア)を襲っている3匹の犬(セルビア、ギリシャ、モンテネグロ)とは別の存在です。
問3:正解②
<問題要旨>
バルカン戦争と第一次世界大戦の関係について書かれた二人の生徒のメモの正誤を判断する問題です。
<選択肢>
川島さんのメモ:第一次世界大戦の勃発は、オーストリア=ハンガリー帝国の皇位継承者夫妻がサライェヴォでセルビア人の青年に暗殺されたサライェヴォ事件がきっかけです。この事件後、オーストリアがセルビアに宣戦布告したことで戦争が始まりました。図2で中央の犬として描かれた国(第二次バルカン戦争の敗戦国)はブルガリアであり、ブルガリアが宣戦布告したわけではありません。よって、川島さんのメモは誤りです。
中野さんのメモ:第二次バルカン戦争で敗北したブルガリアは、セルビアやギリシャなどへの報復感情から、第一次世界大戦ではセルビアと敵対する同盟国側(ドイツ、オーストリアなど)に立って参戦しました。よって、中野さんのメモは正しいです。
以上から、中野さんのみが正しい②が正解です。
①【誤】
川島さんは誤っています。
②【正】
上記の通り、中野さんのみ正しいです。
③【誤】
川島さんは誤っています。
④【誤】
中野さんは正しいです。
問4:正解④
<問題要旨>
文章中の空欄イに入るフランス第三共和政(1870年~1940年)の時代に起こった出来事として、正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
オスマン(ハウスマン)によるパリの都市改造が行われたのは、ナポレオン3世が皇帝であった第二帝政(1852年~1870年)の時代です。
②【誤】
国民公会が封建的特権の廃止を決議したのは、フランス革命中の1792年~1795年のことです。
③【誤】
フランスがベトナム民主共和国との間でインドシナ戦争を戦ったのは、第二次世界大戦後の第四共和政(1946年~1958年)の時代です。
④【正】
ドレフュス事件は、ユダヤ系軍人ドレフュスがドイツのスパイ容疑で冤罪に問われた事件で、1894年に発生し、フランス社会を二分する大論争となりました。これは第三共和政時代の出来事です。
問5:正解②
<問題要旨>
空欄ウに入る普仏戦争(1870年~1871年)に関連して、ドイツ皇帝の即位式が行われた宮殿と、フランスがドイツに割譲したアルザス・ロレーヌ地方の場所を正しく組み合わせる問題です。
<選択肢>
ドイツ皇帝の即位式:普仏戦争に勝利したプロイセン王ヴィルヘルム1世は、1871年にフランスのヴェルサイユ宮殿「鏡の間」でドイツ皇帝として即位しました。よって、「あ」が正しいです。サンスーシ宮殿はプロイセンのポツダムにあります。
割譲された地域:フランスがドイツに割譲したのは、ドイツとの国境に位置するアルザス・ロレーヌ地方です。地図中でこの地域を示しているのは「b」です。「a」はノルマンディー地方、「c」はプロヴァンス地方にあたります。
したがって、宮殿が「あ」、地域が「b」である②が正解です。
①【誤】
地域が誤っています。
②【正】
上記の通り、正しい組み合わせです。
③【誤】
地域が誤っています。
④【誤】
宮殿と地域が誤っています。
⑤【誤】
宮殿が誤っています。
⑥【誤】
宮殿と地域が誤っています。
問6:正解③
<問題要旨>
フランス第三共和政の時代に行われた国民統合政策についての生徒たちのメモの正誤を判断する問題です。
<選択肢>
岡村さんのメモ:フランスで国民皆兵を原則とする徴兵制が創始されたのは、フランス革命中の1798年です。第三共和政の時代ではありません。したがって、メモは誤りです。
渡瀬さんのメモ:第三共和政は、絶対王政ではなく共和政の体制です。「絶対王政を強化するために」という目的が誤っています。
小田さんのメモ:第三共和政は、普仏戦争の敗北からの再建とドイツへの復讐を目標に、国民意識を高める国民統合を重要な政策としました。その一環として、初等教育の無償化・義務化・非宗教化を進め、フランス語の標準語教育を通じて国民の一体感を醸成しようとしました。したがって、メモは正しいです。
以上から、小田さんのみが正しい③が正解です。
①【誤】
岡村さんは誤っています。
②【誤】
渡瀬さんは誤っています。
③【正】
上記の通り、小田さんのみ正しいです。
④【誤】
岡村さん、渡瀬さんともに誤っています。
⑤【誤】
岡村さんは誤っています。
⑥【誤】
渡瀬さんは誤っています。
第3問
問1:正解⑤
<問題要旨>
会話文の空欄ア・イに入る文と人物名の組み合わせとして正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
空欄ア:ヴェネツィアを含むイタリア諸都市は、十字軍以降、東方との貿易(レヴァント貿易)によって香辛料などをヨーロッパにもたらし、経済的に繁栄しました。「商業革命」は、大航海時代以降に経済の中心が地中海から大西洋岸へ移った現象を指すため、文脈に合いません。よって、「い 東方貿易によって繁栄した」が適切です。
空欄イ:17世紀前半に地動説を唱え、自作の望遠鏡で天体を観測したのはガリレオ=ガリレイです。レオナルド=ダヴィンチはルネサンス期の芸術家、ニュートンは17世紀後半に万有引力の法則を発見した科学者です。よって、「Y ガリレイ」が正しいです。
したがって、文が「い」、人物が「Y」である⑤が正解です。
①【誤】
文と人物が誤っています。
②【誤】
文が誤っています。
③【誤】
文と人物が誤っています。
④【誤】
人物が誤っています。
⑤【正】
上記の通り、正しい組み合わせです。
問2:正解①
<問題要旨>
下線部②のフェニキア人に関する記述として正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
フェニキア人は地中海東岸を拠点に海上交易で活躍し、地中海各地にカルタゴなどの多くの植民市を建設しました。カルタゴは後に西地中海の覇権をめぐってローマとポエニ戦争を戦いました。これは正しい記述です。
②【誤】
六十進法を考案したのは、古代メソポタミアのシュメール人です。
③【誤】
ヴァルナと呼ばれる身分制度を形成したのは、インドに侵入したアーリヤ人です。
④【誤】
トウモロコシを栽培する農耕文化を発展させたのは、マヤ、アステカなど古代アメリカ文明の人々です。
問3:正解③
<問題要旨>
会話文の内容を参考に、ガラスの歴史に関する記述として正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
会話文には「ローマガラスの製造は、西アジアの技術を導入して1世紀頃からローマ帝国で盛んになりました」とあり、西アジアからローマへ技術が伝わったことがわかります。記述は方向が逆であり、誤りです。
②【誤】
会話文には、エナメル彩装飾のガラス器がモスクのランプに広く使われるようになったのは「13世紀頃から」とあります。預言者ムハンマドの時代は7世紀なので、年代が合いません。
③【正】
会話文には「イスラーム=ガラスはムスリム商人によって広範囲に流通し、例えばシュリーヴィジャヤ王国の遺跡やキルワの遺跡でも発見されています」とあります。シュリーヴィジャヤは東南アジア、キルワはアフリカ東岸に位置するため、この記述は正しいです。
④【誤】
万国博覧会で「水晶宮(クリスタル=パレス)」が建設されたのは、1851年のロンドン万国博覧会です。ヴェネツィアではありません。
問4:正解③
<問題要旨>
下線部③に関連して、アメリカ合衆国の奴隷制に関する記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
あ 南北戦争後の奴隷解放宣言により黒人奴隷は解放されましたが、経済的自立は困難でした。多くは、土地を借りて耕作し、収穫の半分を地主に小作料として納めるシェアクロッパー(分益小作人)となり、依然として貧しい生活を強いられました。自作農になれた者はごくわずかだったため、この記述は誤りです。
い 19世紀前半、アメリカ南部では綿花プランテーションが経済の基盤であり、その労働力として多くの黒人奴隷が利用されていました。したがって、この記述は正しいです。
以上から、「あ」が誤、「い」が正の組み合わせである③が正解となります。
①【誤】
「あ」が誤りです。
②【誤】
「あ」が誤り、「い」が正しいです。
③【正】
上記の通り、「あ」が誤、「い」が正です。
④【誤】
「い」が正しいです。
問5:正解②
<問題要旨>
20世紀初頭から半ばにかけてのアメリカの人口動態の変化の要因について、空欄ウ・エに入る語句と文の正しい組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
空欄ウ:グラフから、ヨーロッパからの移民は1910年代に大きく減少しています。この時期にヨーロッパで起こった大事件は第一次世界大戦(1914年~1918年)です。戦争により、ヨーロッパからアメリカへの移住が困難になったと考えられます。よって、「う 第一次世界大戦」が適切です。
空欄エ:グラフでは1920年代に移民数がさらに減少しています。これは、1924年に制定された移民法(排日移民法とも呼ばれる)の影響です。この法律は、出身国別に移民の数を制限するもので、特に南ヨーロッパや東ヨーロッパからの移民を大幅に制限しました。1920年代のアメリカは「永遠の繁栄」と呼ばれる経済的繁栄の時代でした。したがって、「Y 経済的繁栄の下で制定され、移民の数を減少させました」が正しい説明です。
以上から、語句が「う」、文が「Y」である②が正解です。
①【誤】
文が誤っています。
②【正】
上記の通り、正しい組み合わせです。
③【誤】
語句と文が誤っています。
④【誤】
語句が誤っています。
問6:正解④
<問題要旨>
下線部④の「1960年代末まで続いた」時期、すなわち1960年代のアメリカ合衆国の政治・経済の動きについて、最も適当なものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
ギリシアとトルコへの援助を表明するトルーマン=ドクトリンが発表されたのは1947年です。また、この政策を主導したのはトルーマン大統領であり、レーガン大統領ではありません。
②【誤】
北米自由貿易協定(NAFTA)が発効したのは1994年です。
③【誤】
マーシャル=プラン(ヨーロッパ経済復興援助計画)が発表されたのは1947年です。また、援助対象は東アジアではなく西ヨーロッパ諸国でした。
④【正】
1960年代のアメリカでは、キング牧師らに指導された公民権運動が高揚し、人種差別の撤廃を求める運動が全国的に展開されました。1964年には公民権法が制定されています。したがって、この記述は正しいです。
第4問
問1:正解②
<問題要旨>
下線部⑧に関連して、16世紀ヨーロッパの宗教改革に関する記述として正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
イグナティウス=ロヨラは、カトリックの改革運動の中心となったイエズス会を創設した人物です。予定説を唱えたのは、カルヴァンです。
②【正】
アウクスブルクの和議は、1555年に神聖ローマ帝国内で結ばれ、諸侯がカトリック(旧教)とルター派(新教)のいずれかを選択する権利(信仰の自由)を認めました。これにより、ルター派が容認されることになりました。
③【誤】
九十五か条の論題を提示して宗教改革を開始したのは、ルターです。エラスムスは人文主義者で、聖書の原典研究などを行いましたが、宗教改革の直接の担い手ではありません。
④【誤】
イギリス国教会を成立させ、国王をその首長としたのは、16世紀前半のヘンリ8世です(国王至上法/首長法)。チャールズ1世は17世紀の国王で、ピューリタン革命で処刑されました。
問2:正解③
<問題要旨>
空欄アに入るレパントの海戦(1571年)で敗れた国がオスマン帝国であることを特定し、オスマン帝国の歴史に関する記述として正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
北方戦争(1700年~1721年)でスウェーデンを破ったのは、ピョートル1世が率いるロシアです。
②【誤】
首都イスファハーンが「世界の半分」と称されるほど繁栄したのは、16世紀末から17世紀にかけてのイランのサファヴィー朝(アッバース1世の時代)です。
③【正】
オスマン帝国のセリム1世は、1517年にエジプトのマムルーク朝を滅ぼし、シリアとエジプトを支配下に置きました。これはオスマン帝国の歴史に関する正しい記述です。
④【誤】
ジズヤ(人頭税)を廃止してヒンドゥー教徒との融和を図ったのは、16世紀後半のインドのムガル帝国第3代皇帝アクバルです。
問3:正解①
<問題要旨>
フェリペ2世の治世にネーデルラントで起こった出来事(空欄イ)と、絵画から読み取れるフェリペ2世の意図(空欄ウ)の正しい組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
空欄イ:フェリペ2世のカトリック強制政策に対し、ネーデルラントの新教徒(ゴイセン)が反乱を起こし、オランダ独立戦争(八十年戦争、1568年~1648年)が始まりました。よって、「あ 独立戦争」が適切です。「ナントの王令(勅令)」は、1598年にフランスでアンリ4世がユグノー(カルヴァン派)の信仰を認めたもので、スペインとは関係ありません。
空欄ウ:父カール5世がプロテスタントに勝利した絵画と、自身がオスマン帝国(イスラーム教徒)に勝利した海戦の絵画を並べて展示したことから、カトリックの擁護者として、異端者(プロテスタント)や異教徒(イスラーム教徒)に対して断固として戦うという強い意志を示す意図があったと考えられます。よって、「X 異端者や異教徒に対して決然と戦う意志」が適切です。
以上から、出来事が「あ」、意図が「X」である①が正解です。
①【正】
上記の通り、正しい組み合わせです。
②【誤】
意図が誤っています。
③【誤】
出来事と意図が誤っています。
④【誤】
出来事が誤っています。
問4:正解③
<問題要旨>
文章と図1から、西夏文字の特徴とその成立背景として考えられることを正しく組み合わせる問題です。
<選択肢>
特徴:図1では、西夏文字が漢字の部首である「小」と「虫」を組み合わせて作られていることが示されています。これは、漢字の仕組みを意識して作られた独自の文字であることを意味します。したがって、「漢字を意識した独自の文字」が正しい特徴です。
成立背景:独自の複雑な文字を制定したことは、漢字文化圏にありながらも、漢民族とは異なる独自の民族であるという自覚や自立心の高まりを示していると考えられます。「漢」を「小」と「虫」で表現していることからも、中国に対する対抗意識がうかがえます。したがって、「民族的な自覚(自立心)の高まり」が適切な背景です。
以上から、特徴が「漢字を意識した独自の文字」、背景が「民族的な自覚(自立心)の高まり」である③が正解です。
①【誤】
特徴が誤っています。
②【誤】
特徴と背景が誤っています。
③【正】
上記の通り、正しい組み合わせです。
④【誤】
背景が誤っています。
問5:正解④
<問題要旨>
下線部①のモンゴル帝国に関する記述として、誤っているものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
モンゴル帝国は、チンギス=ハン以来の強力な騎馬軍団を中核とする軍事力によって、ユーラシア大陸の広大な領域を征服しました。
②【正】
モンゴル帝国は、駅伝制(ジャムチ)を整備し、帝国内の交通網を確保することで、広大な領域の支配と東西交易の活性化に貢献しました。
③【正】
チンギス=ハンの孫であるフラグは、西アジアに遠征して1258年にアッバース朝を滅ぼし、イル=ハン国を建国しました。
④【誤】
北宋を滅ぼしたのは、モンゴル帝国ではなく、女真族が建てた金(1127年)です。モンゴル帝国(元)は、南宋を滅ぼして(1276年)、中国全土を統一しました。したがって、この記述は誤りです。
問6:正解②
<問題要旨>
空欄エに入るロシアと清の国境を定めた河川名と、空欄オに入る琉球王国と清の関係を示す語句の正しい組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
空欄エ:図2の条約はネルチンスク条約(1689年)かアイグン条約(1858年)が考えられますが、文脈上、満洲文字が使われている清の時代の条約であることがわかります。ロシアと清の国境画定条約として知られるのは、ネルチンスク条約(スタノヴォイ山脈を国境)とアイグン条約(黒竜江(アムール川)を国境)です。図2はアイグン条約の条約文であり、国境は黒竜江(アムール川)です。
空欄オ:琉球王国は、明・清の時代を通じて中国皇帝の権威を認めて使節を派遣し、見返りに王として認められ、貿易上の利益を得るという朝貢関係にありました。清に征服されたわけではありません。よって、「清に朝貢していた」が適切です。
したがって、河川が「黒竜江(アムール川)」、関係が「清に朝貢していた」である②が正解です。
①【誤】
関係が誤っています。
②【正】
上記の通り、正しい組み合わせです。
③【誤】
河川と関係が誤っています。
④【誤】
河川が誤っています。
第5問
問1:正解⑥
<問題要旨>
大西洋憲章を発表したイギリス首相(空欄ア)を特定し、その人物に関する記述として正しいものを選ぶ問題です。大西洋憲章は1941年にアメリカのフランクリン=ローズヴェルト大統領とイギリスのチャーチル首相によって発表されました。
<選択肢>
人物:空欄アに入るのはチャーチルです。ロイド=ジョージは第一次世界大戦時のイギリス首相です。
人物についての文:
あ ラテンアメリカに対する善隣外交を展開したのは、アメリカのフランクリン=ローズヴェルト大統領です。
い 「鉄のカーテン」演説を行い、冷戦の始まりを象徴する言葉を残したのはチャーチルです(首相退任後の1946年)。
う ヤルタ会談(1945年2月)には、イギリス首相としてチャーチルが、アメリカのローズヴェルト、ソ連のスターリンとともに出席しました。
したがって、人物がチャーチルで、正しい記述が「う」である⑥が正解です。
①【誤】
人物と記述が誤っています。
②【誤】
人物と記述が誤っています。
③【誤】
人物が誤っています。
④【誤】
記述が誤っています。
⑤【誤】
記述が誤っています。
⑥【正】
上記の通り、正しい組み合わせです。
問2:正解③
<問題要旨>
下線部②の「第二次世界大戦が終わってから1950年代まで」に起こった出来事として、最も適当なものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
コミンテルン(第三インターナショナル)が結成されたのは、ロシア革命後の1919年です。
②【誤】
ロカルノ条約が結ばれ、西ヨーロッパの安全保障体制が確立したのは、第一次世界大戦後の1925年です。
③【正】
太平洋安全保障条約(ANZUS)は、冷戦下の1951年に、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドの間で締結された軍事同盟です。これは設問の時期(1945年~1950年代)に該当します。
④【誤】
中央条約機構(CENTO)は、前身であるバグダード条約機構(METO、1955年結成)からイラクが脱退したことにより、1959年に改称されたものです。設問の時期に含まれますが、③の方がより明確な選択肢です。(※共通テストでは最も適当なものを選ぶため、時期が合致する③がより正解に近いと判断されます)
問3:正解①
<問題要旨>
文章の内容を参考に、民族自決の原則に関する歴史的記述の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
え 第一次世界大戦後にウィルソンが提唱した民族自決の原則は、主に東ヨーロッパの新興国に適用されましたが、アジアやアフリカの植民地には適用されませんでした。文章中にも「第一次世界大戦直後に民族自決の原則が適用されなかった経験」が、チャーチルへの不信感の背景にあると書かれており、この記述は正しいです。
お ナイジェリアは第二次世界大戦後もイギリスの植民地でしたが、1960年に独立しました。1960年はアフリカの多くの国が独立したことから「アフリカの年」と呼ばれています。したがって、この記述も正しいです。
以上から、「え」「お」ともに正しい①が正解です。
①【正】
上記の通り、「え」「お」ともに正しいです。
②【誤】
「お」も正しいです。
③【誤】
「え」も正しいです。
④【誤】
「え」「お」ともに正しいです。
問4:正解④
<問題要旨>
会話文の内容を参考に、1950年代から1960年代にかけての米ソの宇宙開発競争と冷戦について述べた文として、最も適当なものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
大陸間弾道ミサイル(ICBM)の発射実験(1957年)や、人類初の人工衛星(スプートニク)の打ち上げ(1957年)は、ソ連がアメリカより先に成功させました。
②【誤】
有人宇宙飛行を世界で初めて成功させたのはソ連(1961年、ガガーリン)であり、アメリカはそれに続きました。記述が逆です。また、キューバにミサイル基地を建設しようとしたのはソ連であり、これは1962年のキューバ危機につながりました。記述の前半が誤りです。
③【誤】
月面着陸をめぐる競争では、1969年にアポロ11号でアメリカが先に成功し、ソ連に勝利しました。
④【正】
ソ連は人工衛星の打ち上げでアメリカに「スプートニク=ショック」と呼ばれる衝撃を与えました。この時期のソ連の指導者フルシチョフは、スターリン批判後、西側諸国との「平和共存」を掲げる外交政策を推進していました。したがって、この記述は正しいです。
問5:正解②
<問題要旨>
会話文の空欄イに入る、アポロ11号の月面着陸成功(1969年)からおよそ10年後に起こり、米ソ間の緊張を再び高めた出来事を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
アメリカ同時多発テロ事件(9.11事件)が起こったのは2001年です。
②【正】
1979年末、ソ連はアフガニスタンに軍事侵攻しました。この出来事は、1970年代のデタント(緊張緩和)を終わらせ、米ソ関係が再び緊張する「新冷戦」の始まりとされています。1969年からちょうど10年後であり、文脈に合致します。
③【誤】
リーマン=ショックと呼ばれる金融危機がアメリカで起こったのは2008年です。
④【誤】
ゴルバチョフがソ連共産党の書記長に就任したのは1985年です。彼は冷戦終結を主導した人物であり、緊張を高めた出来事ではありません。
問6:正解④
<問題要旨>
グラフを読み取り、核弾頭数の推移に関する二つの文の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
あ 核拡散防止条約(NPT)が調印されたのは1968年です。グラフを見ると、アメリカの核弾頭数は1960年代後半にピークを迎えていますが、ソ連の核弾頭数はその後も増え続け、世界の総数がピークを迎えるのは1980年代半ばです。したがって、「世界の核弾頭保有数はピークを迎えた」という記述は誤りです。
い 中距離核戦力(INF)全廃条約が調印されたのは1987年です。グラフを見ると、アメリカの保有する核弾頭数は1960年代後半にピークに達した後、減少傾向にあります。「増え続けた」という記述は明らかに誤りです。
以上から、「あ」「い」ともに誤りである④が正解です。
①【誤】
「あ」「い」ともに誤りです。
②【誤】
「あ」「い」ともに誤りです。
③【誤】
「あ」「い」ともに誤りです。
④【正】
上記の通り、「あ」「い」ともに誤りです。