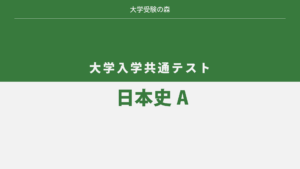解答
解説
第1問
問1:正解②
<問題要旨>
明治初期の郵便制度の創設者と、実業家渋沢栄一が設立に関わった企業についての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
アの前島密は正しいですが、イの八幡製鉄所は、1901年に操業を開始した官営の製鉄所です。渋沢栄一は設立に関わっていません。
②【正】
アの前島密は、1871年に郵便制度を創設した中心人物です。イの大阪紡績会社は、渋沢栄一が中心となって1882年に設立され、日本の紡績業の発展に大きく貢献しました。
③【誤】
アの金子堅太郎は、明治憲法の起草に関わった政治家です。郵便制度の創設者ではありません。
④【誤】
アの金子堅太郎が誤りです。
問2:正解①
<問題要旨>
明治初期に発行された二つの切手(図1と図2)を比較し、図1の切手がどのように改善されたかについて、その説明として適当でないものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
この選択肢は「料金単位を銭から厘に変更した」と記述しています。しかし、図1の日本最初の切手(竜文切手)に書かれている単位は「文(もん)」です。1871年の新貨条例で「円・銭・厘」の新しい貨幣制度が定められ、それに合わせて切手の単位も変更されましたが、変更前は「文」でした。「銭から」という記述が史実と異なるため、この文は改善点の説明として不適切です。したがって、これが正解となります。
②【正】
図1の切手には国名が明記されていませんが、図2の切手には「大日本帝国郵便」と国名が記されています。これは、特に海外郵便などを念頭に、発行国を明確にするための改善点と見なせます。したがって、これは改善点に関する適切な記述です。
③【正】
図2の切手には「IMPERIAL JAPANESE POST」という英語や、算用数字(アラビア数字)の「5」が記されています。これは図1にはない要素であり、外国人にも料金がわかりやすいようにするための改善点です。したがって、これは改善点に関する適切な記述です。
④【正】
図1の切手には、切り離すためのミシン目(目打ち)がありませんが、図2の切手には施されています。これにより、切手を一枚ずつ綺麗に切り離せるようになり、実用性が向上しました。したがって、これは改善点に関する適切な記述です。
問3:正解②
<問題要旨>
1923年の関東大震災の際に、発行予定だった記念切手が焼失を免れた理由を問う問題です。当時の日本の領土や国際関係についての知識が求められます。
<選択肢>
①【誤】
満州国が建国されたのは1932年であり、関東大震災が発生した1923年時点では存在しません。
②【正】
南洋諸島は、第一次世界大戦の結果、ヴェルサイユ条約によって日本の委任統治領となっていました。日本本土から遠隔地であるため、船便で輸送するには時間がかかります。そのため、発売予定分が事前に発送されており、東京で発生した関東大震災による焼失を免れることができました。
③【誤】
米騒動は1918年に発生した事件であり、関東大震災とは時期が異なります。
④【誤】
自由民権運動が激化したのは1880年代であり、時期が全く異なります。
問4:正解③
<問題要旨>
明治期の国粋主義者・杉浦重剛の社説を読み解き、その内容に関する二つの文の正誤を判断する問題です。史料の読解力が問われます。
<選択肢>
①【誤】
史料には、帝王の像を切手にすることは「欧米に於る慣習」であり「敢て奇とするに足らず」とあります。これは、欧米では珍しくない慣習だという意味であり、実例がないわけではありません。したがって、文Xは誤りです。
②【誤】
文Xが誤りであるため、この選択肢は不正解です。
③【正】
文Xは、史料の内容と反するため誤りです。文Yは、史料の「徒に欧風を模倣して国体の如何を弁ぜず、皇室の尊厳を冒瀆する」という部分から、むやみな西洋化を批判し、日本の伝統(国体や皇室の尊厳)を重視する国粋主義的な主張であることがわかります。したがって、文Yは正しいです。
④【誤】
文Yが正しいため、この選択肢は不正解です。
問5:正解④
<問題要旨>
日清戦争後からアジア・太平洋戦争終結までの時期に使われた三つのスローガンを、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
I「一億玉砕」は、アジア・太平洋戦争末期の1945年頃、本土決戦に備えて国民の戦意高揚のために用いられたスローガンです。
II「臥薪嘗胆」は、日清戦争後の1895年、ロシア・ドイツ・フランスによる三国干渉で遼東半島を清に返還させられた悔しさをバネに、国民が耐え忍んで軍備を拡張すべきだとして使われた言葉です。
III「満蒙は日本の生命線」は、1931年の満州事変前後から、満州(中国東北部)やモンゴルが日本の経済的・軍事的な存立に不可欠であると主張するために盛んに用いられました。
以上のことから、年代順は II → III → I となります。
問6:正解③
<問題要旨>
敗戦直後の日本の放送・メディア・大衆文化に関する記述の中から、正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
日本放送協会(NHK)は1926年に社団法人として設立され、戦後の1950年に放送法に基づく特殊法人となりました。テレビ放送が本格的に開始されたのは1953年です。敗戦直後の出来事ではありません。
②【誤】
1冊1円という低価格で文学全集などを出版した「円本」ブームは、1920年代後半の昭和初期の出来事です。
③【正】
並木路子の「リンゴの唄」は、1945年10月に公開された映画『そよかぜ』の挿入歌で、敗戦後の暗い世相の中で大ヒットしました。解放的で明るいメロディは、戦後の大衆文化を象徴するものとなりました。
④【誤】
トーキー(発声映画)は1930年代には日本でも普及しており、敗戦直後の娯楽はすでにトーキーが主流でした。無声映画が主流だったのはそれ以前の時代です。
問7:正解③
<問題要旨>
二つの絵はがきが作られた時代の歴史的背景を読み取り、それに関する説明文との正しい組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
絵はがきXは、記念印に「教育勅語渙発五十年記念」とあります。教育勅語が発布されたのは1890年なので、その50年後は1940年です。この時期は日中戦争の真っ只中であり、子どもたちが日の丸の小旗を振って行進する様子は、国家主義的な教育が浸透していることを示しています。したがって、説明文bが正しいです(aは「敗戦後」という記述が誤り)。
絵はがきYは、旗指物などから「南京陥落」を祝う提灯行列の様子を描いています。南京陥落は1937年12月の出来事です。この後、蔣介石が率いる国民政府は首都を奥地の重慶に移し、日本への抗戦を継続しました。したがって、説明文cが正しいです(dの西安事件は南京陥落の前年、1936年の出来事であり、きっかけではありません)。
以上から、Xとb、Yとcの組み合わせが正しくなります。
第2問
問1:正解④
<問題要旨>
架空の人物の生没年に基づき、その期間に起きた歴史上の出来事を特定する問題です。
<選択肢>
X:主人公の牧野りん(1860年生まれ)が4歳になるのは1864年です。この年、イギリス・フランス・アメリカ・オランダの四国連合艦隊が砲撃したのは、長州藩の下関砲台です。したがって、Xに当てはまるのはbです(aの鹿児島がイギリス艦隊に砲撃された薩英戦争は1863年)。
Y:りんが13歳になるのは1873年です。この年に新たに設立された内務省の初代長官(内務卿)に就任したのは大久保利通です。したがって、Yに当てはまるのはdです(cの寺島宗則は主に外務卿などを務めました)。
以上から、Xとb、Yとdの組み合わせが正しくなります。
問2:正解⑤
<問題要旨>
幕末から明治期にかけての服装や風俗に関する三つの出来事を、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
I:廃刀令(1876年)などに不満を持つ士族が熊本で起こした反乱は、神風連の乱(1876年)です。
II:鹿鳴館に象徴される欧化政策を推進した外務大臣・井上馨が、条約改正交渉の失敗の責任をとって辞任したのは1887年です。
III:「ええじゃないか」という民衆の乱舞が流行したのは、大政奉還(1867年)直前の1867年です。
以上のことから、年代順は III → I → II となります。
問3:正解②
<問題要旨>
自由民権運動家・岸田俊子の史料を読み、その主張と当時の教育制度に関する二つの文の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
文Yが誤りであるため、この選択肢は不正解です。
②【正】
文Xは、史料中の「男子のすぐれたるもの女子よりも多かるの理は、教うると教えざるとの差い、又世に交ることの広きと狭きとに依る」という記述に基づいています。これは、男女間の知識の差は、生まれつきの能力差ではなく、教育や社会参加の機会の差によって生じると主張しており、正しい読解です。文Yは、史料が書かれた1884年当時の義務教育について述べています。小学校で国定教科書が使用されるようになったのは1903年の小学校令改正以降であり、当時は検定教科書などが使われていました。したがって、文Yは誤りです。
③【誤】
文Xは正しいですが、文Yは誤りです。
④【誤】
文Xが正しいため、この選択肢は不正解です。
問4:正解④
<問題要旨>
明治時代の歴史を背景にした架空の人物の生涯設定について、三人の登場人物が行った時代考証の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
タクの発言:屯田兵は、当初、職を失った士族の救済(士族授産)を主な目的として募集されました。したがって、「応募できたのは平民だけ」という発言は史実に反し、誤りです。
ユキの発言:主人公りんが結婚したとされる20歳は1880年です。一方、憲政党は、自由党と進歩党が合同して1898年に結成された日本初の政党内閣を組織した政党です。したがって、「憲政党の結成は…結婚した年よりも後のこと」という発言は史実と合致しており、正しいです。
カイの発言:主人公りんがドイツに滞在したとされる期間は1881年から1889年です。伊藤博文らが大日本帝国憲法制定の参考にするため、ドイツの法学者グナイストやシュタインに学んだのは1882年から1883年にかけてであり、りんの滞在期間と重なります。したがって、「政府の要人がドイツで憲法調査を行っている」という発言は史実と合致しており、正しいです。
以上から、誤っているのはタクさんのみであるため、④が正解となります。
第3問
問1:正解①
<問題要旨>
明治初期から大正期にかけての国税収入の推移を示した表を読み取り、会話文の空欄に当てはまる最も適切な文を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
表を見ると、1875年の税収合計額は5,919万円、1880年は5,526万円で、減少しています。この間、地租改正反対一揆が各地で頻発したことを受け、政府は1877年に地租を地価の3%から2.5%に引き下げました。このことが税収合計額の減少の一因と考えられます。記述は表の数値とも史実とも合致しています。
②【誤】
表を見ると、1900年、1910年、1915年には、酒税の収入金額が地租の収入金額を上回っています。
③【誤】
1890年に帝国議会が開設されて以降、初期議会では民党(自由党・改進党など)が衆議院で多数を占め、政府に対して地租軽減を強く要求しました。「民党が…一度も多数派を形成することができず」という記述が史実と異なります。
④【誤】
1890年の地租収入は約3,971万円、1910年は約7,629万円で、金額は増加しています。しかし、国税収入に占める割合は60%から24%へと大幅に低下しています。「割合はわずかな上昇にとどまった」という記述が誤りです。
問2:正解②
<問題要旨>
地租改正後の明治政府内における財政政策の議論について、空欄に適切な語句と思想を補充する問題です。西南戦争後のインフレーションが背景となっています。
<選択肢>
西南戦争(1877年)の戦費をまかなうため、政府は不換紙幣を大量に発行しました。その結果、貨幣の価値が下がり、物価が急騰する激しいインフレーションが発生しました。したがって、空欄イには「インフレーション」が入ります。
このような状況下で、政府が地租を現金ではなく米で徴収(米納)しようと考えたのは、米価が高騰していたためです。定額の現金を徴収するよりも、現物である米を徴収し、それを市場で売却した方がより多くの現金収入を得られると考えたからです。したがって、空Gitウには「米を売却すれば政府の収入を増やせる」が入ります。
以上から、イがインフレーション、ウが米の売却で収入増となる②が正解です。
問3:正解②
<問題要旨>
地租改正に反対した農民の主張が書かれた史料を読み、その内容に関する二つの文の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
文Yが誤りであるため、この選択肢は不正解です。
②【正】
文Xは、史料の「農民をして武事に煩わしめず」「方今一変して…兵に庶民を取ると雖も、租額敢て減ぜず」という部分に基づいています。これは、江戸時代にはなかった徴兵という新たな負担(血税)を負わされたのに、税負担は軽くならないことへの不満を示しており、正しい読解です。文Yは、「秩禄処分により土地を奪われ困窮した農民」とありますが、秩禄処分は士族の俸禄を廃止した政策であり、農民の土地所有とは直接関係ありません。したがって、文Yは誤りです。
③【誤】
文Xは正しいですが、文Yは誤りです。
④【誤】
文Xが正しいため、この選択肢は不正解です。
問4:正解③
<問題要旨>
明治から大正にかけての日本の工業化の過程を示す三つの出来事を、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
I:日本の綿糸の輸出量が輸入量を上回ったのは、日清戦争(1894-95年)後の産業革命の進展によるもので、1897年のことです。
II:官営富岡製糸場は、殖産興業政策の一環として生糸の品質向上と増産を目指し、1872年に設立されました。
III:日本の工業生産額が農業生産額を初めて上回ったのは、第一次世界大戦(1914-18年)中の好景気(大戦景気)によるもので、1910年代後半のことです。
以上のことから、年代順は II → I → III となります。
問5:正解④
<問題要旨>
日露戦争期に与謝野晶子が発表した詩「君死にたまふことなかれ」を題材に、その内容や背景に関する記述として最も適切なものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
この詩が掲載されたのは、与謝野晶子が夫・鉄幹らと中心になって活動した文芸雑誌『明星』です。大衆雑誌『キング』は1925年の創刊であり、時期も雑誌の性格も異なります。
②【誤】
新聞『万朝報』は、幸徳秋水や内村鑑三らが非戦論を主張していましたが、日露開戦が近づくと社論を開戦支持に転換しました。この詩がきっかけで非戦論に転じたわけではありません。
③【誤】
この詩は、家の跡を継ぐべき弟が徴兵されたことへの嘆きを詠んだものであり、跡継ぎが兵役を免除されていたことを示すものではありません。
④【正】
「旅順の城はほろぶとも、ほろびずとても、何事ぞ」という一節からは、国家の戦争の勝敗よりも個人の生命を尊ぶ、戦争自体への疑問の念が読み取れます。また、「堺の街のあきびとの老舗を誇るあるじにて、親の名を継ぐ君なれば」という部分からは、弟が老舗の跡継ぎであることから、家の存続を願う気持ちも明確に読み取れます。
問6:正解③
<問題要旨>
明治期の条約改正と関税収入の関係について、史実と表の読解に基づき、正しい記述の組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
aは、日英通商航海条約(1894年)締結時のイギリスの意図について、「ドイツの中国大陸への進出を牽制するため」としていますが、この時期イギリスが最も警戒していたのはロシアの東アジア進出でした。したがってaは誤りです。bの「ロシアの東アジア進出に対抗するため」が正しい説明です。
cは、関税自主権の一部回復(1899年実施)により関税収入が増加したことを述べています。表を見ると、1890年の関税収入439万円に対し、1900年には1,700万円と大幅に増加しており、記述は正しいです。
dは、関税自主権の完全回復(1911年)で関税収入が増加したため、他の税を軽減したとあります。しかし、表では1910年から1915年にかけて関税収入は減少しており、地租や酒税も横ばいか微減で、積極的な軽減は見られません。したがってdは誤りです。
以上から、正しい組み合わせはbとcになります。
問7:正解①
<問題要旨>
帝国議会開設後の税制と選挙権の関係について、最も適切な説明を選ぶ問題です。当時の選挙権には直接国税の納税額による資格制限があったことがポイントです。
<選択肢>
①【正】
当時の選挙権の納税資格は「直接国税」に限られていました。酒税は、酒の価格に含まれる形で消費者が負担する「間接税」です。そのため、酒税の税収が増えても、有権者の資格要件には影響せず、有権者数の増加には直接つながらなかったと考えられます。これは正しい説明です。
②【誤】
地租が国税収入に占める割合は低下しましたが、納税額そのものが低下したとは限りません。産業の発展により、地主以外の商工業者などで納税資格を満たす人が増え、相対的に地主の有権者としての地位が低下した側面はありますが、「選挙権を失う地主が多かった」と断定するのは不適切です。
③【誤】
日清戦争後、政府の税収合計額は賠償金収入などもあって増加しており、「減税が行われ」「税収合計額が減少した」という記述は誤りです。
④【誤】
第1次加藤高明内閣は、普通選挙法を制定して納税資格を撤廃しましたが、その一方で、共産主義などの社会主義運動を取り締まることを目的とした治安維持法を同時に制定しています。これは、共産主義の台頭を強く警戒していたことの表れです。
第4問
問1:正解④
<問題要旨>
明治期から戦後にかけての日本の学校制度の変遷について、空欄に適切な語句を補充する問題です。
<選択肢>
「学制」は1872年に公布され、フランスの制度にならい、全国を画一的な学区に分けて小学校を設置することを目指しました。したがって、空欄アには「全国画一的に」が入ります。
師範学校が国立大学の教育学部などに再編されるきっかけとなった戦後の学制改革は、1947年に公布された教育基本法と「学校教育法」によって定められました。六・三・三・四制の新学制がこの時に発足しました。したがって、空欄イには「学校教育法」が入ります。
以上から、アが「全国画一的に」、イが「学校教育法」となる④が正解です。
問2:正解①
<問題要旨>
日清戦争直後の1896年に行われた修学旅行の体験記を読み、その内容に関する二つの文の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【正】
文Xは、上海が開港した時期について述べています。上海は、アヘン戦争(1840-42年)の結果として結ばれた南京条約(1842年)によって開港した5港の一つです。日本の開国につながる安政の五か国条約(1858年)よりも前に開港していました。したがって、文Xは正しいです。文Yは、体験記の内容について述べています。「戦勝の結果利権を得て新設された東華紡績工場の見物」という記述から、日清戦争の勝利で得た利権の一端を目撃したことがわかります。また、「『東洋鬼』の罵声を浴びつつ」という記述からは、当時の上海市民の日本人に対する反感を体験したことが読み取れます。したがって、文Yも正しいです。
②【誤】
文Yが正しいため、この選択肢は不正解です。
③【誤】
文Xが正しいため、この選択肢は不正解です。
④【誤】
両方の文が正しいため、この選択肢は不正解です。
問3:正解④
<問題要旨>
日中戦争中の1938年に行われた満州・朝鮮への修学旅行の行程表を見て、訪問地に関する説明として正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
京城(現ソウル)に置かれた朝鮮総督府の初代総督は寺内正毅です。桂太郎は第2代、第3代総督を務めました。
②【誤】
行程表には「新京神社」「奉天神社」「大連神社」とあり、満州国内にも神社が多数建立されていたことがわかります。
③【誤】
日中戦争のきっかけとなった盧溝橋事件(1937年)が起きたのは、北京の郊外です。訪問地の奉天(現瀋陽)郊外で起きたのは、満州事変の発端となった柳条湖事件(1931年)です。
④【正】
関東都督府は、日露戦争後に獲得した関東州(遼東半島南部)を統治するため、1906年に旅順に設置されました。後に関東庁と改編されますが、かつて旅順に設置されていたのは事実です。
問4:正解②
<問題要旨>
明治期の炭鉱労働に関する統計表と記録文を読み解き、その内容に関する正しい記述の組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
aは、表2について「いずれの炭鉱においても労働者の3分の2以上が勤続年数3年未満であり、1年未満が最も多かった」とあります。勤続3年未満の労働者の割合は、どの炭鉱も3分の2(約67%)を上回っています。しかし、「1年未満が最も多かった」のはA鉱のみで、他の多くの炭鉱では「2年未満」の階級(勤続1年以上2年未満)の労働者が最多です。したがって、aは誤りです。
bは、「他府県出身の労働者が多ければ多いほど、勤続年数が短くなる傾向があった」とありますが、表からはそのような明確な相関関係は読み取れません。例えば、他府県出身比率が最も高いC鉱(63%)よりも、比率が低いA鉱(49%)の方が「1年未満」の割合が高くなっています。したがって、bは誤りです。
cは、「炭鉱内に女性は入ることができず」とありますが、史料2には「女房は…ワレも滑らず…さがり行く」とあり、妻自身も入坑していたことがわかります。したがって、cは誤りです。
dは、史料2の「学校は間欠長欠になるわけであった」という記述から、家計の事情(幼児を他人に預ける費用を節約するため)で子どもを学校に行かせることができず、労働力としていた家庭があったことが読み取れます。したがって、dは正しいです。
以上から、正しい記述はdのみとなります。選択肢の組み合わせでは、aとdの組み合わせである②が正解とされていますが、aは表のデータと一致しない部分があり、設問に不適切な点が含まれる可能性があります。しかし、bとcが明確に誤りであり、dが正しいため、消去法的にこの組み合わせが正解となります。
問5:正解③
<問題要旨>
1912年にジャパン・ツーリスト・ビューロー(現在のJTB)が設立された歴史的背景について、最も適切な説明を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
地方改良運動は、日露戦争後の疲弊した地方を立て直すための内政上の運動であり、外国人の移住を目的としたものではありません。
②【誤】
日本で軍部が台頭しファシズム的な傾向が強まるのは1930年代以降であり、1912年時点の状況ではありません。
③【正】
1912年頃の日本は、産業革命が進む一方で、慢性的な輸入超過(貿易赤字)に悩まされていました。外国人観光客を誘致し、彼らが日本で使うお金(外貨)を獲得することは、国際収支を改善するための重要な政策と考えられていました。
④【誤】
第一次世界大戦後にアメリカのウィルソン大統領が提唱した「民族自決」原則は、1918年以降のことであり、1912年時点の状況ではありません。
問6:正解②
<問題要旨>
沖縄国際海洋博覧会(1975年開催)に関する新聞の見出し一覧から読み取れる事柄について、正しい記述の組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
aは、「1971年3月」の見出しに「1975年に『沖縄海洋博』」とあることから、海洋博の開催が沖縄返還(1972年5月)よりも前に検討・決定されていたことがわかります。したがって、aは正しいです。bは、aと逆の内容であり誤りです。
cは、博覧会開幕後に景気回復を歓迎する論調が優勢になったとありますが、見出しには「本土の人たちの祭り」「本土の資本が吸いあげ」「本土への恨み節」など、沖縄現地では経済的恩恵が少なく、本土企業への不満が高まった様子がうかがえます。したがって、cは誤りです。dは、その不信感が募った状況を正しく説明しています。
以上から、正しい組み合わせはaとdになります。
問7:正解④
<問題要旨>
第二次世界大戦後の日本とアジアの関係に関する二つの文の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
文X、Yともに誤りです。
②【誤】
文Xは正しいですが、文Yは誤りです。
③【誤】
文Xは誤りですが、文Yは正しいです。
④【正】
文Xは、冷戦期に東アジアでアメリカを中心とする多国間の共同防衛組織が結成され、日本も加盟したとしています。しかし、西ヨーロッパのNATO(北大西洋条約機構)のような多国間組織は東アジアでは結成されず、日本はアメリカとの二国間の安全保障条約(日米安全保障条約)を結びました。したがって、文Xは誤りです。文Yは、第1回アジア・アフリカ会議(バンドン会議、1955年)を日本が主催したとしていますが、主催したのはインドネシアなど5か国であり、日本は招待されて参加した国の一つです。したがって、文Yも誤りです。
第5問
問1:正解②
<問題要旨>
ミッドウェー海戦(1942年6月)から日本の敗戦(1945年8月)までの期間における国内の状況として、正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
飯米獲得人民大会(食糧メーデー)は、敗戦後の深刻な食糧難を背景に1946年5月に行われた出来事です。
②【正】
戦局が悪化し、兵力不足が深刻になる中で、それまで徴兵を猶予されていた文科系の大学生も徴兵の対象となりました(学徒出陣)。これは1943年の出来事であり、設問の期間に含まれます。
③【誤】
大東亜会議(1943年)に参加したのは、満州国やフィリピンなど、日本の影響下にあったアジア各国の代表者であり、「日本・ドイツ・イタリアの代表者」ではありません。
④【誤】
農山漁村経済更生運動は、世界恐慌の影響で困窮した農村を救済するため、1930年代前半に行われた政策です。
問2:正解③
<問題要旨>
アジア・太平洋戦争末期にアメリカ軍が散布した宣伝ビラ(伝単)の内容を読み解き、正しい説明の組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
aは、このビラを日本が作成したとしていますが、内容は日本の軍部を批判し、天皇に終戦を働きかけるよう国民に促すものであり、アメリカが日本の戦意を低下させる目的で作成したものです。したがって、aは誤りです。bは、その目的を正しく説明しています。
cは、ビラにある「三国共同宣言」(ポツダム宣言)について述べています。この宣言は、アメリカ・イギリス・ソ連の首脳が出席したポツダム会談で決定され、発表時にはアメリカ・イギリス・中国の三国の名で出されました。会談で決定されたという点で、この記述は正しいと判断できます。
dは、このビラが1945年8月6日以前に散布されたとしていますが、ビラには「広島にただ一個だけ投下された」と、広島への原爆投下を過去の事実として記述しています。したがって、散布されたのは8月6日以降であることがわかります。dは誤りです。
以上から、正しい組み合わせはbとcになります。
問3:正解④
<問題要旨>
敗戦直後から1950年代にかけての日本の政党政治の主な出来事を、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
I:保守合同により自由民主党が結成され、55年体制が成立したのは1955年です。
II:1946年4月の総選挙で第一党となった日本自由党の総裁・鳩山一郎が、組閣直前に公職追放されたのは1946年5月です。
III:1947年の総選挙で日本社会党が第一党となり、片山哲を首相とする連立内閣が成立したのは1947年5月です。
以上のことから、年代順は II → III → I となります。
問4:正解④
<問題要旨>
1950年代初頭に書かれた平和像建設の趣意書を読み、当時の国内外の情勢に関する二つの文の正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
文X、Yともに誤りです。
②【誤】
文Xは正しいですが、文Yは誤りです。
③【誤】
文Xは誤りですが、文Yは正しいです。
④【正】
史料は長岡空襲(1945年8月)から「五年有余」が経過した時期、つまり1950年代初頭のものです。文Xは、「第三次世界大戦の危機」にビキニ環礁での水爆実験が含まれるとしていますが、この実験は1954年の出来事です。1950年からは朝鮮戦争が始まっており、趣意書が指す危機はこちらと考えるのが自然です。したがって、文Xは誤りです。文Yは、平和像建設の背景に「もはや戦後ではない」とされた経済復興があったとしていますが、この言葉が登場する『経済白書』が発表されたのは1956年です。史料が書かれた1950年代初頭は、まだ経済復興の途上でした。したがって、文Yも誤りです。
問5:正解①
<問題要旨>
1970年代の日本社会に関する記述の中から、誤っているものを一つ選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
1971年のニクソン・ショック(ドル・ショック)により、日本はそれまでの1ドル=360円の固定為替相場制から、変動為替相場制へと移行しました。この選択肢は説明が逆になっており、誤りです。
②【正】
航空機の売り込みをめぐる贈収賄事件であるロッキード事件で、元首相の田中角栄が逮捕されたのは1976年のことです。
③【正】
高度経済成長期に深刻化した公害問題に対応するため、環境庁(現在の環境省)が設置されたのは1971年のことです。
④【正】
1973年の第四次中東戦争をきっかけとする第1次石油危機(オイルショック)の影響で、日本の経済は大きな打撃を受け、1974年の経済成長率は戦後初めてマイナスを記録しました。
問6:正解②
<問題要旨>
1970年に書かれた東京大空襲に関する新聞投書を読み、その内容と同時代の対外関係に関する記述として正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
投書には「今ではピンとこない人が多いだろう」「戦争しかしらない子どもたちに、戦争の真実と実態を、切実に語ってきかせたい」とあり、戦争体験の風化を憂慮しています。広く認識されているとは考えていません。
②【正】
史料で言及されているベトナム戦争(1960年代〜75年)において、沖縄をはじめとする在日米軍基地は、アメリカ軍の出撃・補給・後方支援の拠点として極めて重要な役割を果たしました。
③【誤】
日米間の新たな安全保障条約(新安保条約)が調印されたのは1960年です。
④【誤】
1945年3月10日の東京大空襲の際、B29爆撃機の多くは、アメリカ軍が占領していたマリアナ諸島の基地から飛来しました。沖縄本島がアメリカ軍の主な出撃拠点となるのは、沖縄戦で占領された同年4月以降のことです。
問7:正解③
<問題要旨>
『東京大空襲・戦災誌』の構成を示した表を用いて、特定のテーマを探究する際に参照すべき巻の組み合わせとして適切なものを選ぶ問題です。
<選択肢>
X:「1945年1月の空襲」に関する「都民の体験記」と「新聞報道」を比較する場合。
・「体験記」は、「初空襲から8・15まで」を扱う第2巻に収録されています。
・「新聞報道」は、第4巻に収録されています。
よって、Xの探究にはc(第2巻と第4巻)が必要です。
Y:「1945年3月9日から10日の東京大空襲」の「体験記が確認される都内の地域」と、その地域の「日本政府の被害状況認識」を探究する場合。
・「体験記」は、3月10日の空襲に特化した第1巻に収録されています。
・「日本政府の被害状況認識」に関する公式記録は、第3巻に収録されています。
よって、Yの探究にはb(第1巻と第3巻)が必要です。
以上から、Xとc、Yとbの組み合わせである③が正解です。