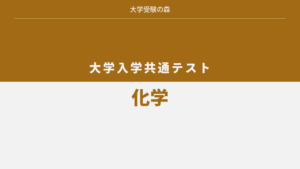解答
解説
第1問
問1:正解②
<問題要旨>
物質を構成する粒子間の結合の種類(イオン結合、共有結合、金属結合)と、それによって形成される結晶の種類(イオン結晶、共有結合結晶、金属結晶、分子結晶)を区別できるかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
パラジクロロベンゼン(C6H4Cl2)は、炭素、水素、塩素という非金属元素からなる分子です。分子同士が弱い分子間力(ファンデルワールス力)で引き合ってできており、分子結晶に分類されます。
②【正】
酸化マグネシウム(MgO)は、金属元素であるマグネシウム(Mg)と非金属元素である酸素(O)からなる化合物です。陽イオンであるマグネシウムイオン(Mg2+)と陰イオンである酸化物イオン(O2-)が、静電気的な引力(クーロン力)によるイオン結合で強く結びついてできており、イオン結晶に分類されます。
③【誤】
ダイヤモンド(C)は、非金属元素である炭素原子が、隣接する4つの炭素原子とそれぞれ強い共有結合を形成し、正四面体構造を繰り返してできた巨大な分子です。これは共有結合結晶(高分子結晶)に分類されます。
④【誤】
アルミニウム(Al)は金属元素であり、アルミニウム原子が自由電子を共有する金属結合によって結びついてできています。これは金属結晶に分類されます。
問2:正解①
<問題要旨>
理想気体と実在気体の性質に関する理解を問う問題です。ドルトンの分圧の法則や、実在気体が理想気体の状態からずれる原因(分子自身の体積と分子間力)について正しく説明できているかを確認します。
<選択肢>
Ⅰ【正】
ドルトンの分圧の法則によれば、混合気体の全圧は各成分気体の分圧の和に等しく、各成分気体の分圧は「全圧 × その気体のモル分率」で求められます。温度と圧力が同じであれば、気体の体積比は物質量比に等しくなります。したがって、体積比が1:2の気体AとBを混合すると、物質量比も1:2となり、AとBのモル分率はそれぞれ1/3と2/3になります。よって、分圧の比も1:2となります。したがって、この記述は正しいです。
Ⅱ【正】
実在気体と理想気体の最も大きな違いの一つは、分子自身の体積を考慮するかどうかです。理想気体では分子の体積を0とみなしますが、実在気体の分子には体積があります。特に圧力を高くしていくと、気体全体の体積に占める分子自身の体積の割合が無視できなくなります。これにより、分子が自由に動ける空間が理想気体で考えるよりも狭くなるため、実在気体の体積は理想気体の体積よりも大きくなります(斥力が優勢になる)。したがって、この記述は正しいです。
Ⅲ【正】
実在気体では分子間に引力(分子間力)がはたらきますが、理想気体では分子間力は0とみなします。温度が高くなると、分子の熱運動が激しくなり、分子間力の影響は相対的に小さくなります。そのため、十分に温度が高くなると、実在気体のふるまいは分子間力の影響がほとんどない理想気体に近づきます。したがって、この記述は正しいです。
以上より、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲはいずれも正しく、①が正解となります。
問3:正解⑤
<問題要旨>
ヘンリーの法則を用いて、圧力変化に伴う気体の溶解量の変化を計算する問題です。一定温度で溶媒に溶ける気体の物質量は、その気体の分圧に比例するという法則を正しく適用できるかが問われます。
<選択肢>
ヘンリーの法則より、一定温度において一定量の溶媒に溶ける気体の物質量は、その気体の分圧に比例します。 まず、問題で与えられた条件から、基準となる圧力下での溶解量を求めます。19℃、1.0×105 Paにおいて、水1Lに溶けるCO2は4.0×10-2 molです。問題では水が500mL (0.5L) なので、この条件で溶けるCO2の物質量は 4.0×10-2 mol×0.5=2.0×10-2 molとなります。これが、蓋を閉めた後の圧力(P後=1.0×105 Pa)で溶けているCO2の量(n後)です。
次に、蓋を緩める前の状態を考えます。蓋を緩めたことで発生した(溶液から出てきた)CO2は0.060 molです。これは、溶解していたCO2の減少量に等しいです。
したがって、蓋を緩める前に溶けていたCO2の物質量(n前)は、
n前=n後+0.060 mol=2.0×10-2 mol+0.060 mol=0.080 mol
となります。
ヘンリーの法則により、溶解物質量と圧力は比例関係にあるので、 P前:P後=n前:n後 の関係が成り立ちます。
蓋を緩める前の圧力 P前 を求めると、
P前=P後×n後n前=(1.0×105 Pa)×2.0×10-2 mol0.080 mol=(1.0×105 Pa)×4=4.0×105 Pa
この計算結果から、蓋を緩める前の圧力は 4.0×105 Pa となります。
①【誤】1.5×105
②【誤】2.0×105
③【誤】2.5×105
④【誤】3.0×105
⑤【正】4.0×105
⑥【誤】5.0×105
問4:正解②
<問題要旨>
コロイドの性質に関する基本的な知識を問う問題です。塩析、懸濁液・乳濁液の区別、電気泳動、ブラウン運動、チンダル現象について、誤った記述を選択します。
<選択肢>
①【正】
親水コロイド(例:デンプン、タンパク質)は、水分子を水和して安定に分散しています。この溶液に多量の電解質を加えると、コロイド粒子が水和している水分子が奪われ、粒子同士が凝集して沈殿します。この現象を塩析といいます。正しい記述です。
②【誤】
コロイドは分散媒と分散質の状態によって分類されます。分散媒が液体で、分散質も液体であるコロイドは「乳濁液(エマルション)」とよばれます(例:牛乳、マヨネーズ)。一方、「懸濁液(サスペンション)」は、分散媒が液体で、分散質が固体のコロイドを指します(例:泥水、墨汁)。したがって、この記述は誤りです。
③【正】
コロイド粒子の多くは、表面にイオンを吸着するなどして正または負に帯電しています。そのため、コロイド溶液に直流電圧をかけると、コロイド粒子は自身が帯びる電荷とは反対の符号を持つ電極に向かって移動します。この現象を電気泳動といいます。正しい記述です。
④【正】
コロイド溶液を顕微鏡で観察すると、コロイド粒子が不規則に動き回っているのが見られます。これはブラウン運動とよばれ、分散媒である水分子が、コロイド粒子に対してあらゆる方向から不規則に衝突するために起こります。正しい記述です。
⑤【正】
コロイド溶液に横から強い光を当てると、光の通路が明るく輝いて見えます。これはチンダル現象とよばれ、コロイド粒子の大きさが光の波長に近いため、粒子によって光が散乱されるために起こります。正しい記述です。
問5:(a)正解① (b)正解①
a:正解①
<問題要旨>
溶液の沸点上昇と、減圧下での沸騰の条件(蒸気圧=外圧)を結びつけて考える問題です。水の蒸気圧曲線を正しく読み取り、計算に利用できるかが問われます。
<選択肢>
液体の沸騰は、その液体の蒸気圧が外圧(その場の圧力)と等しくなったときに起こります。 問題文より、容器B内のNaCl水溶液は90℃で沸騰しています。また、この溶液の沸点上昇度は8K(=8℃)です。
沸点上昇とは、同じ圧力の下で、溶液の沸点が純粋な溶媒(この場合は水)の沸点よりも高くなる現象です。
「沸点上昇度が8K」ということは、容器B内の圧力(これをPとします)におけるNaCl水溶液の沸点(90℃)は、同じ圧力Pにおける純水の沸点よりも8℃高いことを意味します。
つまり、この圧力Pにおける純水の沸点Tbは、
Tb = (溶液の沸点)−(沸点上昇度) = 90℃−8℃ = 82℃
となります。
このことから、容器B内の圧力Pは、純水が82℃で沸騰する圧力、すなわち「82℃における水の蒸気圧」に等しいことがわかります。
ここで、図2の水の蒸気圧曲線を用いて、温度が82℃のときの蒸気圧を読み取ります。
・グラフから、温度80℃のときの蒸気圧は5.0×104 Paです。
・温度90℃のときの蒸気圧は7.0×104 Paです。 82℃は80℃に非常に近いため、その蒸気圧は5.0×104 Paにかなり近い値になります。選択肢の中から最も適当な数値を選ぶと、5.1×104 Paとなります。
①【正】5.1×104
②【誤】7.0×104
③【誤】7.6×104
④【誤】9.4×104
b:正解①
<問題要旨>
逆浸透の原理を利用して、平衡状態に達したときの溶液の濃度をファントホッフの式から求め、それによって移動した水の体積を計算する問題です。
<選択肢>
逆浸透において、溶媒(水)の移動が停止する平衡状態では、「外部から加えた圧力差」が「そのときの溶液の浸透圧」と等しくなります。
外部から加えた圧力差は、NaCl水溶液側の圧力と水側の圧力の差なので、
圧力差 = 3.1×106 Pa−1.0×106 Pa = 3.0×106 Pa
これが平衡状態におけるNaCl水溶液の浸透圧 Π となります。
次に、ファントホッフの式 Π=cRTi を用いて、このときのNaCl水溶液のモル濃度 c平衡 を求めます。
・Π = 3.0×106 Pa
・R = 8.3×103 Pa・L/(mol・K)
・T = 27℃ = 300 K
・i(ファントホッフ係数): NaClはNa+とCl-に電離するので、i = 2
3.0×106 = c平衡 × (8.3×103)×300×2
c平衡 = 3.0×106 / 8.3×103×600 = 3.0×106 / 4.98×106 ≈ 0.6024 mol/L
はじめに、NaCl水溶液は 0.50 mol/L で 10 L あったので、含まれるNaClの物質量は、
0.50 mol/L×10 L=5.0 mol
このNaClの物質量は、水が移動しても変化しません。
水側に移動した水の体積を xLとすると、平衡状態でのNaCl水溶液の体積は (10−x) L となります。
したがって、平衡時の濃度は c平衡=5.0 mol / (10−x) L と表せます。
これを先ほど求めた濃度と等しいとおいて、xを計算します。
0.6024 = 5.0 / 10−x
10−x = 5.0 / 0.6024 ≈ 8.30
x = 10−8.30 = 1.7 L
よって、水側に移動する水の体積は 1.7 L となります。
①【正】1.7
②【誤】4.2
③【誤】5.8
④【誤】7.9
⑤【誤】8.3
第2問
問1:正解③
<問題要旨>
様々な発光現象の中から、化学反応のエネルギーを光エネルギーとして放出する「化学発光」ではないものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
ルミノール反応は、ルミノールが血液中のヘモグロビンなどを触媒として過酸化水素によって酸化される際に発光する現象です。 これは化学反応による発光なので、化学発光です。
②【正】
ケミカルライトは、シュウ酸ジフェニルなどのエステルと蛍光色素、そして過酸化水素などが混合されることで化学反応が起こり、そのエネルギーで蛍光色素が励起されて発光します。 これは化学発光の一例です。
③【誤】
ネオンサインは、ガラス管に封入されたネオンなどの希ガスに高電圧をかけることで、気体原子が励起され、元の状態に戻るときに特定の色(波長)の光を放出する現象です。 これは放電による発光であり、物理発光に分類されます。化学反応を伴わないため、化学発光ではありません。
④【正】
ホタルが光るのは、体内でルシフェリンという物質が、ルシフェラーゼという酵素の働きによって酸化される化学反応(生化学反応)のエネルギーを利用しています。 生物による化学発光なので、生物発光(バイオルミネッセンス)とよばれ、化学発光の一種です。
問2:正解②
<問題要旨>
ニッケル・カドミウム電池の放電における電極反応式を用いて、電極の質量変化から消費された水の質量を求める計算問題です。酸化還元反応における物質量の関係を正確に把握することが求められます。
<選択肢>
まず、負極と正極で起こる反応と、流れる電子の物質量の関係を整理します。
負極:Cd + 2OH- → Cd(OH)2 + 2e-
正極:NiO(OH) + H2O + e- → Ni(OH)2 + OH-
電池全体で流れる電子の物質量を合わせるため、正極の反応式を2倍します。
正極(×2): 2NiO(OH) + 2H2O + 2e- → 2Ni(OH)2 + 2OH-
これにより、電子2 molが流れるとき、負極ではCd 1molがCd(OH)2 1 molに変化し、正極では水H2O 2 molが消費されることがわかります。
次に、負極の質量増加について考えます。
負極の質量増加は、CdがCd(OH)2に変化したことによるものです。その質量増加分は、反応したCdに付加したOH基2つ分、すなわちO原子2個とH原子2個の質量に相当します。
OHの式量は 16+1.0=17 なので、2×OHの質量は34 g/molです。
問題文より、負極の質量が1.7 g増加したので、反応したCd(OH)2の物質量は、
1.7g / 34 g/mol = 0.050 mol
これは、反応式から、流れた電子が 2e- のときに Cd(OH)2 が1 mol生成することから、流れた電子の物質量が 0.050 mol × 2 = 0.10 mol であることを意味します。
正極の反応では、電子1 molあたり水1 molが消費されます(上記の2倍した式では電子2 molあたり水2 mol)。
したがって、流れた電子が0.10 molのとき、消費された水の物質量も0.10 molです。
水の分子量は H2O = 1.0 × 2 + 16 = 18 なので、消費された水の質量は、
0.10 mol×18 g/mol = 1.8 g
①【誤】0.90
②【正】1.8
③【誤】2.7
④【誤】3.6
⑤【誤】4.0
問3:正解④
<問題要旨>
弱酸水溶液を水で希釈したときのpHの変化を示すグラフを選ぶ問題です。希釈によって水素イオン濃度は低下しますが、水の電離を考慮するとpHの変化は緩やかになり、7に限りなく近づいていくことを理解しているかが問われます。
<選択肢>
弱酸HAの水溶液の初期状態は、体積VoでpH=4.0です。
この水溶液を水で希釈すると、濃度が下がるため電離度αは大きくなりますが、それ以上に体積の増加の影響が大きいため、水素イオン濃度[H+]は減少します。[H+]が減少するということは、pH(= -log-10[H+])は大きくなります。したがって、希釈していくとグラフは右上がりになります。
ここで、もし弱酸を100倍に希釈(体積を100Voに)した場合を考えます。単純に濃度が1/100になると考えると、[H+]も1/100になり、pHは4から6に上昇するように思えます。しかし、弱酸の電離度は希釈によって大きくなるため、[H+]の減少は穏やかになります。さらに、pHが7に近づくと、水の自己電離によって生じる[H+](1.0×10-7 mol/L)が無視できなくなります。酸性の水溶液をどれだけ希釈しても、そのpHが中性の7を超えることはありません(塩基性になることはない)。
したがって、グラフの概形は以下のようになります。
- 体積が増加するにつれてpHは4.0から上昇する。
- 希釈してもpHが急激に変化するわけではない。
- pHは限りなく中性の7に近づいていくが、7を超えることはない。
①【誤】
pHが7に達した後、一定になっています。希釈によってpHは7に限りなく近づきますが、完全に7になるわけではありません。
②【誤】
pHが4のまま変化していません。希釈により[H+]は減少するので、pHは必ず上昇します。
③【誤】
pHの上昇が比較的急です。また、pHが5を超えた後の曲線の形が、7に漸近する様子を示していません。
④【正】
初期のpHが4.0であり、希釈するにつれてpHが緩やかに上昇し、中性であるpH=7に向かって限りなく近づいていく(漸近していく)様子を正しく表しています。
問4:(a)正解⑤ (b)正解③ (c)正解④
a:正解⑤
<問題要旨>
アンモニア合成反応 (N2+3H2⇌2NH3) における、圧平衡定数Kpと濃度平衡定数Kcの関係式を導く問題です。
<選択肢>
一般に、気体反応 aA + bB ⇌ cC + dD において、圧平衡定数Kpと濃度平衡定数Kcの関係は、気体定数をR、絶対温度をTとすると、以下の式で表されます。
Kp = Kc(RT)Δn
ここで、Δnは反応式の生成物と反応物の気体分子数の変化量で、Δn = (c+d)−(a+b) です。
アンモニアの合成反応式は
N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g) です。
この反応における気体分子数の変化量Δnは、
生成物の係数:2
反応物の係数の和:1 + 3 = 4
Δn = 2−4 = −2
となります。
したがって、この値を関係式に代入すると、
Kp = Kc(RT)-2=Kc / (RT)2
となります。
①【誤】Kp=Kc
②【誤】Kp=KcRT
③【誤】Kp=Kc(RT)2
④【誤】Kp=Kc / RT
⑤【正】Kp=Kc / (RT)2
⑥【誤】Kp=Kc / (RT)3
b:正解③
<問題要旨>
学平衡に達したときの各成分の物質量から、混合気体中のアンモニアの体積百分率(モル分率)を計算し、与えられたグラフからその条件に合う反応温度を読み取る問題です。
<選択肢>
反応前の物質量は、
N2が2.0 mol、H2が6.0 molです。
反応式
N2+3H2 ⇌ 2NH3 に従い、平衡状態でNH3が3.0 mol生成したとあります。
反応式の係数比から、各物質の物質量の変化を計算します。
・NH3が3.0 mol生成したので、反応したN2は 3.0 mol×1/2 = 1.5 mol。
・反応したH2は 3.0 mol×3/2 = 4.5 mol。
平衡状態における各気体の物質量は以下のようになります。
・N2 : 2.0 mol − 1.5 mol = 0.5 mol
・H2 : 6.0 mol − 4.5 mol = 1.5 mol
・NH3 : 3.0 mol
平衡状態での混合気体の全物質量は、
0.5 + 1.5 + 3.0 = 5.0 mol
このときのアンモニアNH3の体積百分率(=モル分率)は、
NH3の物質量 / 全物質量×100=3.0 mol / 5.0 mol × 100 = 60 %
次に、この条件を図1のグラフで探します。
全圧は1.0×108 Pa なので 、グラフの中から一番上の曲線(1.0×108 Pa)を見ます。 この曲線上で、NH3の体積百分率が60%となる点の横軸(温度)を読み取ります。 グラフから、温度は約490℃であることがわかります。
①【誤】350
②【誤】420
③【正】490
④【誤】560
⑤【誤】650
c:正解②
<問題要旨>
アンモニア合成反応の反応速度と化学平衡に関する問題です。温度を上げた場合に、反応速度と平衡の位置がどのように変化するかを正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
アンモニア合成反応 (N2 + 3H2 ⇌ 2NH3) は発熱反応です(図1から、温度が高いほどNH3の生成率が低いことから判断できます)。 反応条件のうち、温度のみを100 K(=100℃)上げた場合、以下の2つの変化が起こります。
- 反応速度の変化: 温度を上げると、反応に関わる全ての分子の運動エネルギーが増加し、活性化エネルギー以上のエネルギーを持つ分子の割合が増えるため、正反応・逆反応ともに反応速度は速くなります。これにより、平衡に達するまでの時間は短くなります。
- 化学平衡の移動: ルシャトリエの原理によれば、発熱反応において温度を上げると、熱を吸収する方向、すなわち逆反応の方向(NH3が分解してN2とH2になる方向)に平衡が移動します。その結果、平衡状態におけるNH3の体積百分率は低くなります。
これらの変化をグラフで表すと、元の破線のグラフ(図2)に比べて、
・より速く平衡に達する(グラフの立ち上がりが急になる)。
・最終的に到達する平衡でのNH3の体積百分率が低くなる(破線のグラフよりも低い位置で水平になる)。
①【誤】
平衡時のNH3の割合が元の反応より高くなっており、吸熱反応の場合の変化を示しています。
②【正】
元の反応より速く平衡に達し(立ち上がりが急)、平衡時のNH3の割合が低くなっており、発熱反応で温度を上げた場合の変化を正しく示しています。
③【誤】
平衡に達する時間が遅くなっており、反応速度が低下した場合を示しています。
④【誤】
平衡に達する時間は速くなっていますが、平衡時のNH3の割合は変わっていません。これは触媒を加えた場合の変化に相当します。
⑤【誤】
平衡時のNH3の割合は低くなっていますが、平衡に達する時間が遅くなっており、矛盾しています。
第3問
問1:正解②
<問題要旨>
遷移元素の化合物に関する、沈殿生成、呈色反応、酸化還元反応、錯イオン生成についての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
硫酸銅(II) CuSO4 水溶液に水酸化ナトリウムNaOH水溶液を加えると、水酸化銅(II) Cu(OH)2 の青白色沈殿が生じます。
反応式:CuSO + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4
②【誤】
鉄(III)イオン Fe3+を含む水溶液に、ヘキサシアニド鉄(II)酸カリウム K4[Fe(CN)6] 水溶液を加えると、濃青色沈殿(プルシアンブルー)が生じます。 問題にあるヘキサシアニド鉄(III)酸カリウム K3[Fe(CN)6] 水溶液を加えた場合、Fe3+とは反応せず、溶液は褐色のままです(錯イオン同士の反応は起こりにくい)。K3[Fe(CN)6] と反応して青白色沈殿(ターンブルブルー)を生じるのは鉄(II)イオン Fe2+です。したがって、この記述は誤りです。
③【正】
過マンガン酸カリウム KMnO4中のマンガン原子の酸化数は+7です。これが塩基性水溶液中で酸化剤としてはたらくとき、自身は還元されて酸化マンガン(IV) MnO2(酸化数+4)になります。正しい記述です。
④【正】
酸化銀 Ag2O は水に難溶ですが、過剰のアンモニア水を加えると、銀イオン Ag+がアンモニアと配位結合して、水によく溶けるジアンミン銀(I)イオン [Ag(NH3)2]+という直線形の錯イオンを生成して溶解します。
反応式:Ag2O + H2O + 4NH3 → 2[Ag(NH3)2]+ + 2OH-
問2:正解③
<問題要旨>
ケイ素とその化合物(二酸化ケイ素、ケイ酸ナトリウム、水ガラス、シリカゲル)の製法や性質に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
二酸化ケイ素 SiO2 は酸性酸化物であり、炭酸ナトリウム Na2CO3 のような塩基性塩だけでなく、水酸化ナトリウム NaOH のような強塩基とも反応してケイ酸ナトリウム Na2SiO3 を生成します。
反応式:SiO2+2NaOH→Na2SiO3+H2O
②【正】
Na2SiO3 において、Naの酸化数は+1、Oの酸化数は-2です。ケイ素Siの酸化数をxとすると、化合物の電荷の総和は0なので、
(+1)×2+x+(−2)×3 = 0
2+x−6 = 0
x = +4
よって、ケイ素の酸化数は+4です。
③【誤】
水ガラスは、ケイ酸ナトリウム Na2SiO3 を水に溶かして加熱して得られる、粘性の高い液体(コロイド溶液)です。この水ガラスに塩酸などの酸を加えて中和すると、ケイ酸 H2SiO3 のゲル状沈殿が得られます。これを洗浄・乾燥させて脱水したものが、乾燥剤として用いられるシリカゲルです。水ガラスを単に乾燥させたものではないため、この記述は誤りです。
④【正】
ケイ酸ナトリウムは弱酸(ケイ酸)と強塩基(水酸化ナトリウム)の塩です。そのため、水ガラスに強酸である塩酸を加えると、弱酸が遊離してケイ酸 H2SiO3 が生成します。
反応式:Na2SiO3+2HCl→2NaCl+H2SiO3↓
問3:正解②
<問題要旨>
化学反応式から生成する気体を特定し、それらの気体の性質(水への溶解性、捕集法、反応性、検出法)に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
まず、空欄ア~エの気体を特定します。
ア:銅と濃硝酸の反応なので、二酸化窒素 NO2 が生成します。
イ:銅と希硝酸の反応なので、一酸化窒素 NO が生成します。
ウ:フッ化カルシウムと濃硫酸を加熱すると、揮発性の酸が遊離し、フッ化水素 HF が生成します。
エ:酸素に無声放電を行うと、オゾン O3 が生成します。
次に、各気体の性質に関する記述を検証します。
①【正】
気体ア (NO2) を水に通じると、温水では以下の反応が起こり、硝酸と亜硝酸が生成するため、水溶液は酸性を示します。 2NO2+H2O→HNO3+HNO2
②【誤】
気体イ (NO) の分子量は30で、空気の平均分子量(約28.8)とほぼ同じです。そのため、上方置換や下方置換などの空気との置換ではうまく捕集できません。また、空気中の酸素と容易に反応してNO2になる (2NO+O2→2NO2) ため、水上置換で捕集するのが一般的です。したがって、下方置換で捕集するという記述は誤りです。
③【正】
気体ウ (HF) の水溶液であるフッ化水素酸は、ガラスの主成分である二酸化ケイ素 SiO2 を溶かす性質があります (SiO2+6HF→H2SiF6+2H2O)。そのため、ガラス製の容器で保存することはできず、ポリエチレンなどのプラスチック製容器で保存します。
④【正】
気体エ (O3) は強い酸化作用を持ち、ヨウ化物イオン I- を酸化してヨウ素 I2 を遊離させます。この遊離したヨウ素がデンプンと反応して青紫色を呈する(ヨウ素デンプン反応)。この反応を利用してオゾンを検出できます。
反応式:O3+2KI+H2O→I2+2KOH+O2
問4:正解③、⑤、⑧、⓪、④
a:正解③
<問題要旨> ヨウ化ナトリウム水溶液からヨウ素を生成させる反応について、酸化還元反応の観点から正しい記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
式(6)において、過酸化水素 H2O2 中の酸素原子の酸化数は-1ですが、生成物の水 H2O では-2に変化しています。自身は還元されているため、酸化剤として働いています。
②【正】
ヨウ素 I2 は無極性分子であり、極性の高い水には溶けにくいですが、無極性溶媒であるヘキサンにはよく溶けます。そのため、反応後の水溶液にヘキサンを加えて振り混ぜると、ヨウ素は水層からヘキサン層へ移動(抽出)します。このときヘキサン層はヨウ素の色である赤紫色を呈します。
③【誤】
ヨウ化ナトリウム NaI 中のヨウ化物イオン I- (酸化数-1) から単体のヨウ素 I2 (酸化数0) を生成させるには、I- を酸化する必要があります。したがって、反応させる試薬は酸化剤でなければなりません。塩化スズ(II) SnCl2 は、自身が酸化されてSn+4になりやすい還元剤であるため、この反応には用いることができません。
④【正】
ハロゲンの酸化力の強さは F2>Cl2>Br2>I2 の順です。酸化力の強いハロゲン(塩素 Cl2)は、酸化力の弱いハロゲンのイオン(ヨウ化物イオン I-)を酸化して、単体を遊離させることができます。
反応式:Cl2+2NaI→2NaCl+I2
b:正解⑤
<問題要旨>
ヨウ素酸ナトリウムと亜硫酸水素ナトリウムの酸化還元反応について、反応式を完成させ、化学量論計算を行う問題です。
<選択肢>
反応式(7) 2NaIO3+aNaHSO3→bNaHSO4+cNa2SO4+H2O+I2 における係数aを求めます。 この反応における酸化剤と還元剤の半反応式を考えます。
・還元剤:NaHSO3 中の硫黄原子Sは、酸化数が+4から、生成物(NaHSO4やNa2SO4)の+6に増加します。
HSO3-+H2O→SO42-+3H++2e-
・酸化剤:NaIO3 中のヨウ素原子Iは、酸化数が+5から、生成物I2の0に減少します。
2IO3-+12H++10e-→I2+6H2O
酸化還元反応で授受される電子の数を合わせるため、還元剤の半反応式を5倍します。
5HSO3-+5H2O→5SO42-+15H++10e-
これにより、電子10e-の授受が釣り合います。 このとき、酸化剤 2IO3- に対して、還元剤 5HSO3-が反応することがわかります。
したがって、2 molのNaIO3に対して、5 molのNaHSO3が消費されるため、係数aは5となります。
①【誤】1
②【誤】2
③【誤】3
④【誤】4
⑤【正】5
c:正解(18:⑧, 19:⓪, 20:④)
<問題要旨>
複数の反応工程を経て物質を製造する際の、全体の化学量論関係を把握し、生成物の質量から原料の濃度を算出する問題です。
<選択肢>
まず、最初の原料である NaI と最終生成物である I2 の物質量の関係を求めます。
式(8): 2NaI+…→2CuI+…
この式から、2 molのNaIから2 molのCuIが生成することがわかります (NaI : CuI = 1 : 1)。
式(9): 2CuI+O2→2CuO+I2
この式から、2 molのCuIから1 molのI2が生成することがわかります (CuI : I2 = 2 : 1)。
以上の二つの関係から、
2 mol NaI→2 mol CuI→1 mol I2
つまり、2 molのNaIから1 molのI2が生成することがわかります。
次に、生成したI2の物質量を計算します。I2の分子量は 127×2 = 254 です。
生成したI2の質量は 25.4 kg = 25400 g なので、その物質量は、
moles of I2 = 25400 g / 254 g/mol = 100 mol
このI2を生成するために必要だったNaIの物質量は、上記の化学量論関係から、
moles of NaI = 100 mol×2=200 mol
最後に、このNaIが含まれていた地下水の体積で割って、濃度を求めます。
地下水の体積は 2.50×105 L です。
Concentration = 200 mol / 2.50×105 L = 80×10-5 mol/L
有効数字2桁の形式 a.b×10n に直すと、8.0×10-4 mol/L となります。
これを問題の形式に当てはめると、 18 = ⑧, 19 = ⓪, 20 = ④ となります。
第4問
問1:正解②
<問題要旨>
酸素を含む有機化合物の典型的な反応(アルコールの性質、フェノールの性質、エーテルの生成、ヨードホルム反応、エステル化)に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
エチレングリコールはヒドロキシ基(-OH)を2つ持つアルコールです。アルコールは、ナトリウムのようなアルカリ金属と反応して、ヒドロキシ基の水素原子を置換し、水素ガスを発生します。正しい記述です。
②【誤】
酸性の強さは、カルボン酸 > 炭酸 > フェノール の順です。弱い酸の塩に強い酸を加えると、弱い酸が遊離する反応が起こります。炭酸水素ナトリウムは弱酸である炭酸の塩であり、フェノールは炭酸よりも弱い酸です。したがって、フェノールは炭酸水素ナトリウムから炭酸を遊離させることができず、二酸化炭素は発生しません。この記述は誤りです。
③【正】
エタノール2分子を、濃硫酸などを触媒として約130~140℃で加熱すると、分子間で水1分子が取れる縮合反応が起こり、ジエチルエーテルが生成します。これはエーテルの製法の一つです。正しい記述です。
④【正】
アセトン(CH3−CO−CH3)は、CH3-CO-の構造を持つため、ヨードホルム反応を示します。ヨウ素と水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱すると、特有の臭気を持つヨードホルムの黄色沈殿が生成します。正しい記述です。
⑤【正】
無水酢酸は、フェノールやアルコールのヒドロキシ基と反応して、それらをアセチル化し、酢酸エステルを生成します。フェノールと反応させると、酢酸フェニルが生成します。これはエステル化反応の一例です。正しい記述です。
問2:正解⑤
<問題要旨>
有機化合物の反応(付加反応)と、生成物の性質(エステル結合、不斉炭素原子、分子量)から、その構造式を推定する問題です。
<選択肢>
まず、反応を考えます。アクリル酸メチル (CH2=CH−COOCH3) とアニリン (C6H5−NH2) の反応です。アクリル酸メチルの炭素-炭素二重結合に、アニリンのアミノ基(-NH2)のN-H結合が付加する、1,4-付加(マイケル付加)が起こると考えられます。
CH2=CH−COOCH3+C6H5−NH2→C6H5−NH−CH2−CH2−COOCH3
この生成物が化合物Aの候補です。
次に、化合物Aが満たす3つの条件を確認します。
Ⅰ. エステル結合(-COO-)をもつ。 候補の構造には −COOCH3 というエステル結合があります。条件を満たします。
Ⅱ. 不斉炭素原子をもたない。 不斉炭素原子とは、結合する4つの原子または原子団がすべて異なる炭素原子のことです。候補の構造 (C6H5−NH−CH2−CH2−COOCH3) には、そのような炭素原子は存在しません。条件を満たします。
Ⅲ. 分子量は179.0である。 反応は付加反応なので、生成物の分子量は反応物の分子量の和になります。
アクリル酸メチルの分子量:86.0
アニリンの分子量:93.0
化合物Aの分子量 = 86.0+93.0=179.0
条件を満たします。
したがって、化合物Aの構造は C6H5−NH−CH2−CH2−COOCH3 です。 これを満たす選択肢は⑤です。
①【誤】N原子からベンゼン環に直接結合している炭素が不斉炭素原子になります。
②【誤】C=C二重結合にNH₂とベンゼン環が結合したような構造で、元の反応とは異なります。
③【誤】カルボン酸になっており、エステル結合をもちません。
④【誤】アミド結合ができており、元の反応(付加反応)とは異なります。
⑤【正】上記の推定構造と一致します。
⑥【誤】アミノ基が結合している炭素が不斉炭素原子になります。
問3:正解④
<問題要旨>
天然に存在する有機化合物であるタンパク質、アミノ酸、糖類(グルコース、フルクトース)の構造や性質に関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
タンパク質の二次構造には、ポリペプチド鎖がらせん状になったα-ヘリックス構造と、シート状になったβ-シート構造があります。これらの構造は、ポリペプチド鎖中の異なる場所にあるペプチド結合のC=O基とN-H基の間で形成される水素結合によって安定化されています。正しい記述です。
②【正】
アミノ酸は、分子内にアミノ基(-NH₂)という塩基性の官能基と、カルボキシ基(-COOH)という酸性の官能基を両方持っています。結晶中や中性の水溶液中では、カルボキシ基がプロトン(H⁺)を放出して-COO⁻となり、アミノ基がそれを受け取って-NH3+となることで、全体として電荷が0の双性イオンとして存在しています。正しい記述です。
③【正】
グルコースなどの六炭糖は、水溶液中では主に環状構造で存在しますが、ごくわずかに鎖状構造も存在し、両者は平衡状態にあります。環状構造には、1位の炭素原子のヒドロキシ基の向きが異なるα型とβ型の2つのアノマー(立体異性体)が存在します。したがって、水溶液中ではα型、β型、鎖状構造の3種類が平衡混合物として存在しています。正しい記述です。
④【誤】 フルクトースとグルコースは、どちらも分子式がC6H12O6で同じです。しかし、グルコースはアルデヒド基(-CHO)を持つアルドースであるのに対し、フルクトースはケトン基(>C=O)を持つケトースです。このように、分子式は同じでも構造が異なる(官能基の種類が異なる)化合物の関係を構造異性体といいます。立体異性体は、原子の結合順序は同じで空間的な配置のみが異なる異性体を指します。したがって、この記述は誤りです。
問4:正解⑤⑥①⑨③
a:正解⑤
<問題要旨>
アセチレンの製法、性質、反応、およびその重合体であるポリアセチレンに関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
炭化カルシウム(カルシウムカーバイド, CaC2)に水を加えると、アセチレンC2H2が発生します。これは実験室や工業でのアセチレンの一般的な製法です。
反応式:CaC2+2H2O→C2H2+Ca(OH)2
②【正】
アセチレンを酸素と共に燃焼させると、非常に高温(約3000℃)の酸素アセチレン炎が得られます。この高温を利用して、金属の溶接や切断に用いられます。
③【正】
アセチレンに、硫酸水銀(II)などを触媒として水を付加させると、不安定なビニルアルコールが生成し、これが直ちに安定なアセトアルデヒドに異性化します。
④【正】
アセチレンにシアン化水素HCNを付加させると、アクリロニトリル(CH2=CH−CN)が生成します。アクリロニトリルは、ポリアクリロニトリル(アクリル繊維)や合成ゴムの原料となる重要なモノマーです。
⑤【誤】
アセチレン(HC≡CH)が重合してできるポリアセチレンは、導電性高分子として知られます。その構造は、アセチレンの三重結合の一つが切れ、炭素原子が二重結合と単結合が交互に連なった鎖状構造 (-CH=CH-)n となっています。三重結合と単結合が交互につながっているわけではないため、この記述は誤りです。
b:正解(反応ア:⑥, 反応イ:①, 化合物B:⑨)
<問題要旨>
合成繊維ビニロンの合成経路図を読み解き、各工程の反応の種類(反応ア、イ)と中間生成物(化合物B)を特定する問題です。高分子化学の基本的な反応の知識が必要です。
<選択肢>
合成経路を順に見ていきます。
・アセチレン → 酢酸ビニル: これは付加反応です。
・酢酸ビニル → 化合物B: 酢酸ビニル(CH2=CH−OCOCH3)はモノマー(単量体)です。これが多数結合してポリマー(重合体)になる反応なので、重合反応です。二重結合が開いて次々と結合していくので、付加重合です。したがって、反応アは⑥です。 これにより生成する化合物Bは、ポリ酢酸ビニルであり、その構造は⑨となります。
・化合物B(ポリ酢酸ビニル) → ポリビニルアルコール(PVA): ポリ酢酸ビニルは側鎖にエステル結合(-OCOCH3)を持っています。これがポリビニルアルコールのヒドロキシ基(-OH)に変化しています。これはエステル結合が水などによって分解される反応であり、加水分解(けん化)です。したがって、反応イは①です。
まとめると、 反応ア:⑥ 付加重合 反応イ:① 加水分解 化合物B:⑨ ポリ酢酸ビニル
c:正解③
<問題要旨>
ポリビニルアルコール(PVA)のアセタール化反応における化学量論計算です。反応前後の質量変化から、反応したヒドロキシ基の割合を求める問題です。
<選択肢>
まず、反応によってPVAの繰り返し単位がどのように変化するかを考えます。 PVAの繰り返し単位(-CH2-CH(OH)-)が2つ、ブチルアルデヒド(CH3CH2CH2CHO)1分子と反応して、アセタール化された構造1単位と水1分子が生成します。
反応式(単位あたり): 2(−CH2−CH(OH)−)+CH3CH2CH2CHO→(−CH2−CH-O-CH(C3H7)-O-CH-CH2−)+H2O
この反応における質量の変化を計算します。
・反応するPVA 2単位の式量:44.0×2=88.0
・反応するブチルアルデヒド 1分子の分子量:12×4+1×8+16=72.0
・生成する水 1分子の分子量:18.0 反応によって、PVAの質量はブチルアルデヒドが付加し、水が脱離する分だけ変化します。 質量増加分(PVA 2単位あたり)= 72.0−18.0=54.0
次に、実験全体の質量変化を考えます。
反応前のPVAの質量:88.0 g
反応後のポリビニルブチラールの質量:120.4 g
全体の質量増加:120.4 g−88.0 g = 32.4 g
この質量増加は、アセタール化反応によって起こったものです。
アセタール化されたPVAの単位の数をNとすると、
N×54.0=32.4 N=54.032.4=0.6
これは、アセタール化反応が0.6 molスケールで起こったことを意味します。 この反応では、PVAの繰り返し単位が 2×0.6=1.2 mol分消費されたことになります。
一方、反応に用いたPVAの全量は88.0 gです。PVAの繰り返し単位の式量は44.0なので、PVAの繰り返し単位の全物質量は、 44.0 g/mol88.0 g=2.0 mol です。
したがって、全ヒドロキシ基(= 全繰り返し単位)2.0 molのうち、アセタール化されたヒドロキシ基は1.2 molです。 その割合(%)は、
全OHの物質量アセタール化されたOHの物質量×100=2.0 mol1.2 mol×100=60 %
①【誤】30
②【誤】45
③【正】60
④【誤】67
⑤【誤】82
第5問
問1:正解③
<問題要旨>
原油の分留(分別蒸留)に関する問題です。分留塔の温度と、各留出物の沸点の関係を理解しているかが問われます。分留では、沸点の低いものほど塔の上部から、沸点の高いものほど下部から取り出されます。
<選択肢>
原油の分留で得られる各留分(りゅうぶん)の沸点は、一般に以下の順で高くなります。 石油ガス(~40℃) < ナフサ(粗製ガソリン、40~180℃) < 灯油(170~250℃) < 軽油(240~350℃) < 重油(350℃~)
これを分留塔の温度と対応させます。
・留出物A:30~180℃ → 沸点が最も低いナフサに相当します。
・留出物B:180~250℃ → 次に沸点が低い灯油に相当します。
・留出物C:250~350℃ → 最も沸点が高い軽油に相当します。
この組合せと一致する選択肢は③です。
①【誤】
②【誤】
③【正】A: ナフサ、B: 灯油、C: 軽油
④【誤】
⑤【誤】
⑥【誤】
問2:正解④
<問題要旨>
ベンゼンを原料とする6,6-ナイロンの合成経路(実際には6-ナイロンの合成経路)に関する問題です。各段階での生成物(化合物D、E)の構造を正しく特定できるかが問われます。
<選択肢>
合成経路を順に追っていきます。
・ベンゼン → 化合物D: ベンゼンに触媒を用いて高温
・高圧で水素を反応させています。これはベンゼン環の二重結合がすべて単結合になる水素付加(還元)反応です。これにより、ベンゼン環はシクロヘキサン環に変化します。したがって、化合物Dはシクロヘキサンです。
・ε-カプロラクタム → 化合物E: ε-カプロラクタムが加熱によって開環重合しています。ε-カプロラクタムは、アミノ基とカルボキシ基が分子内で脱水縮合してできた環状アミド(ラクタム)です。開環重合では、このアミド結合が開裂し、直鎖状のポリアミドが生成します。このポリアミドは、炭素原子6個からなる単位が繰り返されるため、ナイロン6とよばれます。その繰り返し単位は -CO-(CH2)6-NH- となります。これが化合物Eです。
化合物Dがシクロヘキサン、化合物Eがナイロン6である組合せは④です。
①【誤】Dがシクロヘキセン、Eがナイロン6,6になっています。
②【誤】Dがシクロヘキセンになっています。
③【誤】Eがナイロン6,6になっています。
④【正】Dがシクロヘキサン、Eがナイロン6(構造式は [-NH-(CH2)6-CO-]n とも書ける)です。
⑤【誤】Eがナイロン6,10のような構造になっています。
⑥【誤】Eがナイロン6,6になっています。
問3:正解④、①、①、③
a:正解④
<問題要旨>
与えられたイオンの化学式から、構成元素の酸化数を決定する問題です。酸化数のルールに基づいて計算します。
<選択肢>
オキシドバナジウムイオン VO2+ において、バナジウムVの酸化数をxとします。 酸化数のルールより、化合物中の酸素原子Oの酸化数は、過酸化物などの例外を除き-2です。 イオン全体の電荷は+2なので、構成原子の酸化数の総和は+2になります。
x+(−2)=+2
x=+2+2=+4
したがって、バナジウムVの酸化数は+4です。
①【誤】+1
②【誤】+2
③【誤】+3
④【正】+4
⑤【誤】+5
b:正解①
<問題要旨>
芳香族炭化水素の酸化反応に関する知識を問う問題です。ナフタレンを酸化バナジウム(V) V2O5 を触媒として空気酸化した場合の生成物を特定します。
<選択肢>
ナフタレンを V2O5 触媒下で酸化すると、ベンゼン環の一つが酸化開裂し、無水フタル酸が生成します。これは、フタル酸から分子内脱水してできるカルボン酸無水物です。選択肢の中で無水フタル酸の構造式は①です。 この反応は、工業的に重要なプロセスです。
①【正】無水フタル酸です。
②【誤】フタル酸です。無水フタル酸がさらに水と反応すると生成します。
③【誤】テレフタル酸です。p-キシレンの酸化で得られます。
④【誤】安息香酸です。トルエンの酸化で得られます。
⑤【誤】マレイン酸です。ベンゼンの酸化で得られます。
c:正解①
<問題要旨>
熱化学方程式とヘスの法則(総熱量不変の法則)を用いて、複数の反応経路における反応エンタルピー(反応熱)を計算し、その大小関係を比較する問題です。
<選択肢>
ヘスの法則によれば、化学反応の反応エンタルピーは、反応の経路によらず、反応の始めの状態と終わりの状態で決まります。
経路Iと経路IIは、どちらも出発物質が「V2O5 1 molと反応に必要なCa」であり、最終生成物が「V 2 molと生成したCaO」です。(経路IIではH2が関与しますが、これは中間体を生成するために使われ、最終的にはH2Oとしてエンタルピー計算に組み込まれます)。
まず、各経路の反応エンタルピーを計算します。反応エンタルピーは「(生成物の生成エンタルピーの総和)-(反応物の生成エンタルピーの総和)」で求められます。
・経路Iの反応エンタルピー ΔHI
反応式(1): V2O5(固)+5Ca(固)→2V(固)+5CaO(固)
ΔHI=(2×ΔHf(V)+5×ΔHf(CaO))−(ΔHf(V2O5)+5×ΔHf(Ca))
単体の生成エンタルピーは0なので、ΔHf(V)=0,ΔHf(Ca)=0 です。
ΔHI=(5×(−636))−(−1550)=−3180+1550=−1630 kJ
・経路IIの反応エンタルピー ΔHII
経路IIは二段階の反応の和なので、全体の反応エンタルピーも二つの反応エンタルピーの和になります。
反応式(2): V2O5(固)+2H2(気)→V2O3(固)+2H2O(液)
ΔH2=(ΔHf(V2O3)+2×ΔHf(H2O))−(ΔHf(V2O5)+2×ΔHf(H2))
ΔH2=(−1220+2×(−286))−(−1550+0)=(−1220−572)+1550=−1792+1550=−242 kJ
反応式(3): V2O3(固)+3Ca(固)→2V(固)+3CaO(固)
ΔH3=(2×ΔHf(V)+3×ΔHf(CaO))−(ΔHf(V2O3)+3×ΔHf(Ca))
ΔH3=(0+3×(−636))−(−1220+0)=−1908+1220=−688 kJ
経路II全体のエンタルピー変化 ΔHII は、ΔH2 と ΔH3 の和です。
ΔHII=ΔH2+ΔH3=−242+(−688)=−930 kJ
計算結果を比較すると、
ΔHI=−1630 kJ
ΔHII=−930 kJ
どちらも負の値(発熱反応)であり、ΔHI<ΔHII です。
したがって、大小関係は ΔHI<ΔHII<0 kJ となります。
①【正】ΔHI<ΔHII<0 kJ
②【誤】 ③【誤】④【誤】 ⑤【誤】 ⑥【誤】 ⑦【誤】 ⑧【誤】 ⑨【誤】
d:正解③
<問題要旨>
滴定と同様の考え方を用いて、未知濃度の試料と既知濃度の試薬の反応から、試料中の特定物質の量を求める計算問題です。
<選択肢>
VO2+ とEDTAは1:1の物質量比で反応します。
まず、反応に用いたEDTAの物質量を計算します。
EDTA水溶液の濃度:1.00×10-2 mol/L
用いた体積:4.00 mL = 4.00×10-3 L
EDTAの物質量 = (1.00×10-2 mol/L)×(4.00×10-3 L) = 4.00×10-5 mol
この量のEDTAが、滴定に用いた水溶液10.0 mL中のVO2+と過不足なく反応しました。したがって、水溶液10.0mL中に含まれていたVO^{2+}$の物質量も 4.00×10-5 mol です。
このVO2+は、最初に調製した250mLの水溶液から取ったものです。したがって、250mLの水溶液全体に含まれていたVO2+の総物質量は、
(4.00×10−5 mol)×250 mL / 10.0 mL = 4.00×10-5×25 = 100×10−5 = 1.00×10-3 mol
このVO2+は、燃焼灰1.00gに含まれるすべてのバナジウムVから作られたものです。 したがって、燃焼灰1.00 gに含まれていたVの物質量は 1.00×10-3 mol です。
Vの原子量は51なので、その質量は、
(1.00×10-3 mol)×51 g/mol = 51×10-3 g = 5.10×10-2 g
①【誤】 ②【誤】 ③【正】5.10×10−2 ④【誤】 ⑤【誤】 ⑥【誤】
第6問
問1:正解③
(第5問 問1と同じ)
問2:正解④
(第5問 問2と同じ)
問3:正解④、①、⑥、③
a:正解④(第5問 問3aと同じ)
b:正解①(第5問 問3bと同じ)
c:正解⑥
<問題要旨>
熱化学方程式とヘスの法則(総熱量不変の法則)を用いて、複数の反応経路における反応熱を計算し、その大小関係を比較する問題です。(注:本設問は、第5問 問3cと用語が異なります。「生成エンタルピー」の代わりに「生成熱」が、「反応エンタルピー」の代わりに「反応熱」が用いられていますが、計算の考え方は同じです。反応熱Qは、発熱反応の場合に正の値をとります。)
<選択肢>
反応熱Qは、「(反応物の生成熱の総和)-(生成物の生成熱の総和)」で求められます。
・経路Iの反応熱 QI
反応式(1): V2O5(固)+5Ca(固)→2V(固)+5CaO(固)
QI=(生成熱(V2O5)+5×生成熱(Ca))−(2×生成熱(V)+5×生成熱(CaO))
QI=(1550+5×0)−(2×0+5×636)=1550−3180=−1630 kJ
(注:生成熱の定義では発熱反応が正となるため、Q=−ΔH の関係があります。したがって、QI=1630 kJとなります。)
・経路IIの反応熱 QII
反応式(2): V2O5(固)+2H2(気)→V2O3(固)+2H2O(液)
Q2=(生成熱(V2O5)+2×生成熱(H2))−(生成熱(V2O3)+2×生成熱(H2O))
Q2=(1550+0)−(1220+2×286)=1550−(1220+572)=1550−1792=−242 kJ
(同様に、反応熱として正の値にすると Q2=242 kJ)
反応式(3): V2O3(固)+3Ca(固)→2V(固)+3CaO(固)
Q3=(生成熱(V2O3)+3×生成熱(Ca))−(2×生成熱(V)+3×生成熱(CaO))
Q3=(1220+0)−(0+3×636)=1220−1908=−688 kJ
(同様に、反応熱として正の値にすると Q3=688 kJ)
経路II全体の反応熱 QIIは、Q2とQ3の和です。
QII=242+688=930 kJ
計算結果を比較すると、 QI=1630 kJ QII=930 kJ どちらも正の値(発熱反応)であり、QII<QI です。
したがって、大小関係は 0 kJ<QII<QI となります。
①【誤】 ②【誤】 ③【誤】 ④【誤】 ⑤【誤】 ⑥【正】0 kJ<QII<QI ⑦【誤】 ⑧【誤】 ⑨【誤】
d:正解③(第5問 問3dと同じ)