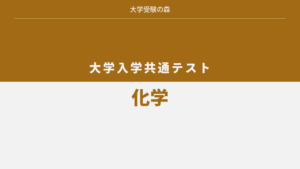解答
解説
第1問
問1:正解②
<問題要旨>
原子やイオンの大きさに関する周期律についての理解を問う問題です。原子半径やイオン半径が、周期表上の位置(周期や族)や、イオン化によってどのように変化するかを正確に把握しているかがポイントです。
<選択肢>
①【正】
同族の原子(周期表で同じ縦の列に属する原子)では、原子番号が大きくなるにつれて、電子が存在する電子殻の数が増えていきます。最も外側の電子殻が原子核から遠くなるため、原子の大きさ(原子半径)は大きくなります。
②【誤】
同一周期の原子(周期表で同じ横の行に属する原子)では、原子番号が大きくなるにつれて、原子核内の陽子の数が増え、原子核の正の電荷が大きくなります。電子は同じ電子殻に追加されていくため、原子核からの引力が強まり、原子はより小さく引き締まります。したがって、原子の大きさは原子番号とともに(希ガスを除き)小さくなる傾向があります。よって、この記述は誤りです。
③【正】
原子が電子を失って陽イオンになると、最外殻の電子がなくなるか、電子の数が陽子の数より少なくなるため、原子核が残りの電子をより強く引きつけるようになります。その結果、イオンの大きさはもとの原子よりも小さくなります。
④【正】
原子が電子を受け取って陰イオンになると、電子の数が陽子の数より多くなり、電子同士の反発が大きくなります。その結果、電子殻が広がり、イオンの大きさはもとの原子よりも大きくなります。
問2:正解②
<問題要旨>
イオン結晶の単位格子に関する問題です。単位格子に含まれるイオンの数え方と、特定のイオンに着目したときの配位数(最も近くに存在する反対符号のイオンの数)を、与えられた図から正しく読み取る能力が求められます。
<選択肢>
この結晶構造は、フッ化カルシウム(蛍石)型構造です。 まず、単位格子に含まれる陽イオンAと陰イオンBの数を数えます。
・陽イオンA(白球):単位格子の各頂点と各面の中心に位置しています。これは面心立方格子と同じ配置です。 頂点の粒子は1/8個分、面の中心の粒子は1/2個分が単位格子に含まれます。 Aの数 = (1/8) × 8(頂点) + (1/2) × 6(面心) = 1 + 3 = 4個
・陰イオンB(黒球):単位格子の内部に8個すべてが含まれています。 Bの数 = 1 × 8 = 8個
次に、陽イオンAの配位数を求めます。配位数とは、ある粒子に最も近い距離にある異符号の粒子の数のことです。 単位格子の頂点 (0, 0, 0) にあるAに着目します。このAに最も近いBは、座標 (1/4, 1/4, 1/4) の位置にあるものです。単位格子を8つの小さな立方体に分けたとき、頂点のAの周りには8つの小立方体があり、そのうちAを含む単位格子内部の小立方体の中心にBが存在します。同様に、隣接する他の7つの単位格子にも、このAに隣接する小立方体の中心にBが存在します。したがって、1つのAの周りには、最も近いBが8個存在します。よって、Aの配位数は8です。
以上の結果から、Aの配位数が8、Aの数が4、Bの数が8となる組み合わせを選びます。
①【誤】Aの配位数、Aの数、Bの数が異なります。
②【正】Aの配位数が8、Aの数が4、Bの数が8であり、計算結果と一致します。
③【誤】Aの配位数、Aの数、Bの数が異なります。
④【誤】Aの数、Bの数が異なります。
⑤【誤】Aの配位数、Aの数が異なります。
⑥【誤】Aの配位数、Aの数、Bの数が異なります。
問3:正解②
<問題要旨>
揮発性の液体を蒸発させたときの、体積と圧力の関係を問う問題です。気液平衡における飽和蒸気圧の概念と、すべての液体が気体になった後のボイルの法則の適用を理解しているかが問われます。
<選択肢>
操作の過程を二段階に分けて考えます。
・段階1(図のア→イ):
ピストンを引き上げ、液体が蒸発して気体と液体が共存している状態です。温度Tが一定に保たれているため、容器内の気体の圧力は飽和蒸気圧P₀で一定となります。この状態は、体積がV₀になり、すべての液体が気体になるまで続きます。したがって、グラフの体積0からV₀までの区間では、圧力はP₀で一定の水平な直線になります。
・段階2(図のイ→ウ):
体積V₀ですべての液体が気体になった後、さらにピストンを引き上げて体積を4V₀まで増加させます。この過程では、容器内の気体の物質量と温度は一定なので、圧力Pと体積Vの関係はボイルの法則(PV = 一定)に従います。つまり、圧力は体積に反比例して減少します。 体積がV₀のときの圧力はP₀です。 体積が2V₀になると、圧力は P₀ × (V₀ / 2V₀) = 0.5P₀ となります。 体積が4V₀になると、圧力は P₀ × (V₀ / 4V₀) = 0.25P₀ となります。
この2つの条件を満たすグラフを選びます。
②【正】体積がV₀までは圧力がP₀で一定であり、その後はボイルの法則に従って反比例で減少しています。体積2V₀で圧力0.5P₀、体積4V₀で圧力0.25P₀という関係も満たしており、正しいグラフです。
問4a:正解④
<問題要旨>
水溶液の濃度を表すモル濃度 (mol/L) と質量モル濃度 (mol/kg) の定義と性質の違いを正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【正】
モル濃度は、溶液1 L(リットル)あたりの溶質の物質量 (mol) で定義されます。溶液の体積は温度によって膨張・収縮するため変化します。したがって、温度を変化させると溶液の体積が変わり、モル濃度も変化します。
②【正】
質量モル濃度は、溶媒1 kg(キログラム)あたりの溶質の物質量 (mol) で定義されます。溶媒の質量は温度によって変化しません。したがって、温度を変化させても質量モル濃度は変化しません。沸点上昇や凝固点降下の計算で質量モル濃度が用いられるのはこのためです。
③【正】
1 mol/kgのショ糖水溶液は、水1 kgにショ糖1 molが溶けています。同様に、1 mol/kgの塩化ナトリウム水溶液は、水1 kgに塩化ナトリウム1 molが溶けています。どちらの水溶液も「溶媒1 kgあたりに溶けている溶質の物質量」は1 molで同じなので、溶質と水の物質量の比は同じになります。(塩化ナトリウムが電離して生じるイオンの総物質量は異なりますが、溶質「NaCl」としての物質量は1 molです。)
④【誤】
1 Lの水の質量は、密度を約1 g/cm³とすると1 kg = 1000 gです。1 mol/Lのショ糖水溶液1 Lを作るには、ショ糖1 molを水に溶かして全体の体積を1 Lにします。ショ糖自身の体積があるため、この溶液に含まれる水の体積は1 Lよりも少なく、質量も1000 gより小さくなります。したがって、「1 Lの水の物質量」と「1 mol/Lのショ糖水溶液1 Lに含まれる水の物質量」は同じにはなりません。
問4b:正解③
<問題要旨>
電解質水溶液の凝固点降下に関する計算問題です。凝固点降下度が、溶媒の量に溶けている溶質「粒子」の数に比例すること、そして電解質は水中で電離して粒子数が増加することを理解しているかがポイントです。
<選択肢>
凝固点降下度 ΔT は、質量モル濃度を m [mol/kg]、モル凝固点降下を Kf とすると、ΔT=Kf×m×i で表されます。ここで、i は電解質の電離によって生じる粒子の総数を表す係数(ファントホッフ係数)です。
・塩化ナトリウム (NaCl) は、水溶液中で NaCl→Na++Cl- と電離し、1つの化学式から2つのイオンが生じるため、i=2 となります。
この水溶液の凝固点降下度が0.052 Kなので、
0.052=Kf×m×2 …… (A)
・硫酸ナトリウム (Na2SO4) は、水溶液中で Na2SO4→2Na++SO42- と電離し、1つの化学式から3つのイオンが生じるため、i=3 となります。
この水溶液の凝固点降下度を ΔT′ とすると、
ΔT′=Kf×m×3 …… (B)
式(B)を式(A)で割ると、
ΔT′/0.052=(Kf×m×3)/(Kf×m×2)=3/2
ΔT′=0.052×3/2=0.078 K
したがって、硫酸ナトリウム水溶液の凝固点降下度は0.078 Kです。
①【誤】0.026 K ②【誤】0.052 K ③【正】0.078 K ④【誤】0.104 K
問4c:正解①
<問題要旨>
水溶液の冷却曲線と凝固点降下の関係から、析出した溶媒(氷)の質量を計算する問題です。溶液が凝固するにつれて溶媒の量が減り、溶液の濃度が上昇することで凝固点がさらに降下していく現象を定量的に扱います。
<選択肢>
凝固点降下度 ΔT は、質量モル濃度 m [mol/kg] と水のモル凝固点降下 Kf=1.85 K⋅kg/mol を用いて、ΔT=Kf×m で表されます。ショ糖は非電解質なので電離は考慮しません。質量モル濃度 m は、m=(溶質の物質量)/(溶媒の質量) です。
・点Aの状態:
温度は tA=−0.370℃ なので、凝固点降下度は ΔTA=0−(−0.370)=0.370 K。
このときの液相(水溶液)中の水の質量を WA [kg] とすると、
質量モル濃度は mA=0.100 mol/WA。
0.370=1.85×(0.100/WA) WA=(1.85×0.100)/0.370=0.500 kg
・点Bの状態:
温度は tB=−0.740℃ なので、凝固点降下度は ΔTB=0−(−0.740)=0.740 K。
このときの液相中の水の質量を WB [kg] とすると、
質量モル濃度は mB=0.100 mol/WB。
0.740=1.85×(0.100/WB) WB=(1.85×0.100)/0.740=0.250 kg
点Aから点Bに変化する間に増加した氷の質量は、液相中の水の質量の減少分に等しいです。
氷の質量の増加量 = WA−WB=0.500−0.250=0.250 kg
①【正】0.250 kg ②【誤】0.500 kg ③【誤】0.750 kg ④【誤】1.00 kg
第2問
問1:正解④
<問題要旨>
無機物質の基本的な性質(色、臭い、酸性、塩基性、溶解性など)に関する知識を問う問題です。典型元素や遷移元素の代表的な化合物の性質を整理しておくことが重要です。
<選択肢>
①【正】
水素(H₂)、二酸化炭素(CO₂)、ヘリウム(He)は、いずれも常温・常圧で無色・無臭の気体です。
②【正】
塩化水素(HCl)、臭化水素(HBr)、ヨウ化水素(HI)はハロゲン化水素と呼ばれ、フッ化水素(HF)が弱酸であるのに対し、これら3つの水溶液(塩酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸)はいずれも強酸です。
③【正】
リチウム(Li)、ナトリウム(Na)、カリウム(K)はアルカリ金属元素であり、水と非常に反応しやすく、反応すると水酸化物と水素(H₂)を発生します。
④【誤】
ハロゲン化銀の溶解性は、フッ化銀(AgF)のみが水によく溶け、塩化銀(AgCl)、臭化銀(AgBr)、ヨウ化銀(AgI)は水にほとんど溶けません。したがって、「AgF, AgCl, AgBr はいずれも水に溶けにくい」という記述は誤りです。
問2:正解③
<問題要旨>
非金属元素の代表的な化合物(オキソ酸、酸化物など)の性質や反応についての知識を問う問題です。酸化数の計算、酸化剤・還元剤としての働き、酸・塩基としての反応などが問われます。
<選択肢>
①【正】
過塩素酸 HClO₄ において、Hの酸化数は+1、Oの酸化数は-2です。化合物全体の酸化数の総和は0なので、Clの酸化数をxとすると、(+1) + x + (-2)×4 = 0 となり、x = +7 となります。
②【正】
二酸化硫黄 SO₂ 中のSの酸化数は+4です。S原子は-2から+6までの酸化数をとることができるため、SO₂は反応相手によって、酸化されて自身の酸化数が増加する(還元剤として働く)ことも、還元されて自身の酸化数が減少する(酸化剤として働く)こともあります。
③【誤】
金(Au)や白金(Pt)は化学的に非常に安定な金属(貴金属)であり、硝酸(HNO₃)や塩酸(HCl)のような単独の酸には溶けません。これらを溶かすことができるのは、濃硝酸と濃塩酸を1:3の体積比で混合した王水だけです。
④【正】
十酸化四リン P₄O₁₀ はリン酸 H₃PO₄ の脱水縮合によって生成する化合物(リン酸の無水物)です。したがって、P₄O₁₀ に水を加えるとリン酸 H₃PO₄ が生成します。
⑤【正】
濃硫酸 H₂SO₄ は強い脱水作用を持つことで知られています。スクロース(ショ糖) C₁₂H₂₂O₁₁ のような炭水化物に濃硫酸を加えると、分子中の水素原子と酸素原子が2:1の割合(水の組成比)で奪われ、黒色の炭素Cが残ります。これを炭化作用といいます。
問3:正解⑦
<問題要旨>
溶解度積を用いて、特定のイオン濃度の溶液で沈殿が生じるかどうかを判断する問題です。混合後の溶液中のイオン濃度を正確に計算し、イオン積と溶解度積を比較することが求められます。
<問題要旨>
まず、硫酸H₂SO₄水溶液を加えた後の混合溶液中の各イオンのモル濃度を計算します。 混合後の溶液の総体積は 5.0 mL + 0.50 mL = 5.5 mL です。
・混合後の陽イオン (Mg2+, Ca2+, Ba2+) の濃度 [M2+]:
[M2+]=(1.0×10−2 mol/L)×5.5 mL5.0 mL=1.11.0×10−2 mol/L
・混合後の硫酸イオンの濃度 [SO42-]:
[SO42-]=(1.0×10−3 mol/L)×5.5 mL0.50 mL=1.10.1×10−3=111×10−3 mol/L
次に、各試験管で沈殿が生じるか、イオン積Qを計算して溶解度積Kspと比較します。 イオン積Q > 溶解度積Ksp の場合に沈殿が生じます。
・試験管A (Mg2+):
硫酸マグネシウム MgSO₄ の溶解度は非常に大きく、飽和水溶液のモル濃度が 3.0 mol/L です。混合後のイオン濃度はこれよりはるかに小さいため、沈殿は生じません。
・試験管B (Ca2+):
硫酸カルシウム CaSO₄ のイオン積Qを計算します。 Q=[Ca2+][SO42-]=(1.11.0×10-2)×(111×10-3)=12.11×10−5≈8.3×10−7 (mol/L)² CaSO₄ の溶解度積 Ksp=1.9×10−4 (mol/L)² です。 Q<Ksp なので、沈殿は生じません。
・試験管C (Ba2+):
硫酸バリウム BaSO₄ のイオン積Qを計算します。イオン濃度は試験管Bと同じです。 Q=[Ba2+][SO42-]≈8.3×10-7(mol/L)² BaSO₄ の溶解度積 Ksp=9.2×10-11(mol/L)² です。 Q>Ksp なので、沈殿が生じます。
以上の結果から、沈殿の有無は、試験管A:無、試験管B:無、試験管C:有 となります。
①〜⑥、⑧【誤】 ⑦【正】試験管A:無、試験管B:無、試験管C:有
問4a:正解③
<問題要旨>
アルミニウムの工業的製法(バイヤー法とホール・エルー法)に関する一連の化学反応や操作原理についての正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【正】
下線部(a)では、塩基性のテトラヒドロキシドアルミン酸イオン [Al(OH)₄]⁻ を含む溶液に、酸性酸化物である二酸化炭素 CO₂ を通じています。これにより中和反応が起こり、溶液の塩基性が弱まるため、pHの値は下がります。
②【正】
下線部(b)で水酸化アルミニウム Al(OH)₃ が沈殿するのは、溶液中の化学平衡 [Al(OH)4]−⇌Al(OH)3↓+OH− において、CO₂ によって OH⁻ が消費(中和)され、平衡が右に移動するためです。(問題文中の選択肢の平衡式は逆向きに書かれていますが、この平衡が関与していることは正しいです。) ※注:選択肢②の平衡の向きと移動方向の記述には曖昧さが残りますが、他の選択肢との比較で判断します。
③【誤】
下線部(c)は、水酸化アルミニウム Al(OH)₃ を加熱して酸化アルミニウム Al₂O₃ を得る反応(熱分解)です。化学反応式は 2Al(OH)3→Al2O3+3H2O となります。この式から、2 molの Al(OH)₃ からは、1 molの Al₂O₃ と 3 mol の水 H₂O が生成します。選択肢では「2 mol の水」と記述されているため、化学量論的に誤りです。
④【正】
下線部(d)の溶融塩電解では、純粋な酸化アルミニウム Al₂O₃(融点約2000℃)を直接融解させるのではなく、融点が約1000℃の氷晶石 Na₃AlF₆ に溶かして電解します。混合物とすることで融点が下がる現象(凝固点降下)を利用しており、より低い温度で効率的に電解を行うための工夫です。
問4b:正解⑤
<問題要旨>
アルミニウムの溶融塩電解における、陰極・陽極での反応量的関係を計算する問題です。ファラデーの法則と、複数の反応が同時に起こる場合の物質量の分配を正確に計算する必要があります。
<選択肢>
まず、陰極で生成したAlの物質量を求めます。Alの原子量は27です。
生成したAlの物質量 = (2.70×105 g)/(27 g/mol)=1.00×104 mol
次に、Alが生成するために陰極で消費された電子 e⁻ の物質量を計算します。
陰極の反応式:Al3++3e-→Al より、1 molのAlの生成に3 molの電子が必要です。
陰極で流れた電子の物質量 = (1.00×104 mol)×3=3.00×104 mol
電気分解では、回路全体を流れる電子の物質量は等しいので、陽極で発生した電子の物質量も 3.00×104 mol です。
次に、陽極での反応を考えます。陽極では、COとCO₂が発生し、炭素C電極が消費されます。 消費されたCの物質量を求めます。Cの原子量は12です。
消費されたCの物質量 = (1.08×105 g)/(12 g/mol)=0.900×104 mol=9.00×103 mol
生成したCOの物質量を nCO [mol]、CO₂の物質量を nCO₂ [mol] とします。
陽極の反応式: C+O2-→CO+2e- ……(2)
C+2O2-→CO2+4e− ……(3)
消費されたCの物質量について:nCO+nCO2=9.00×103 ……(A)
陽極で流れた電子の物質量について:2nCO+4nCO2=3.00×104 ……(B)
式(A)より nCO=9.00×103−nCO2 として、式(B)に代入します。
2(9.00×103−nCO2)+4nCO2=3.00×104
1.80×104−2nCO2+4nCO2=3.00×104
2nCO2=(3.00−1.80)×104=1.20×104
nCO2=6.00×103 mol
最後に、電流の大きさを求めます。
流れた電気量 [C] = 電子の物質量 [mol] × ファラデー定数 [C/mol]
電気量 = (3.00×104 mol)×(9.65×104 C/mol)
また、電気量 [C] = 電流 [A] × 時間 [s] なので、
電流 I×9650 s=(3.00×104)×(9.65×104)
I=9650(3.00×104)×(9.65×104)=9650(3.00×104)×96500=3.00×104×10=3.00×105 A
したがって、電流は 3.00×105 A、発生したCO₂の物質量は 6.00×103 mol となります。この組み合わせは選択肢⑤です。
問4c:正解①
<問題要旨>
特定の化合物(ミョウバンの一種)を加熱したときの、段階的な熱分解による質量変化をグラフから読み取る問題です。各段階でどのような物質が生成するかを化学反応式から考え、その際の質量を化学量論計算で求める必要があります。
<選択肢>
段階的な熱分解による質量変化を計算します。 出発物質: Al(NH4)(SO4)2 (式量237)、質量100 mg
・第一段階(450℃~550℃):
Al2(SO4)3 (式量342) の生成 反応式は、Al原子の数を合わせるため、2Al(NH4)(SO4)2 から考えます。
2Al(NH4)(SO4)2→Al2(SO4)3+2NH3↑+H2O↑+SO3↑
この反応により、2 molの出発物質(質量 2 × 237 = 474)から、1 molの Al2(SO4)3(質量 342)が残ります。 したがって、質量は約 342/474 倍になります。
中間生成物の質量 = 100 mg×(342/474)≈72.15 mg
この時点で、中間体の質量が約72 mgになるグラフを探します。
グラフ①: 約75 mg グラフ②: 約72 mg グラフ③: 約53 mg グラフ④: 約53 mg グラフ⑤、⑥は質量が増加しているので除外。 この段階ではグラフ①か②が候補となります。
・第二段階(650℃~950℃):
Al2O3 (式量102) の生成 最終的に生成するのは高純度の Al2O3 です。 出発物質 100 mg に含まれるアルミニウムがすべて Al2O3 になるときの質量を計算します。 出発物質 Al(NH4)(SO4)2 2 mol (質量474) から Al2O3 1 mol (質量102) が生成します。
最終的な質量 = 100 mg×(102/474)≈21.5 mg グラフの最終的な質量を確認します。
グラフ①: 約22 mg グラフ②: 約42 mg グラフ③: 約22 mg グラフ④: 約38 mg
両方の条件を考慮すると、中間生成物の質量が約72 mg、最終生成物の質量が約22 mgとなるグラフが最も適当です。 中間生成物の質量はグラフ② (72mg) が計算値に最も近いですが、最終生成物の質量が計算値 (22mg) と大きく異なります (42mg)。 一方、グラフ①は、中間生成物の質量が約75mgと計算値から少しずれますが、最終生成物の質量は約22mgで計算値とほぼ一致します。 設問の趣旨から、最終生成物が正しく計算できていることが重要と判断し、また中間体の質量も③,④よりは計算値に近いため、①が最も適当なグラフと判断できます。
第3問
問1:正解②
<問題要旨>
有機化学における基本的な反応(付加反応、置換反応、脱離反応)の分類と、生成物の立体構造(分子の平面性)に関する知識を組み合わせた問題です。
<選択肢>
①【誤】
この反応は、アルカン(2-メチルプロパン)の水素原子が塩素原子に置き換わる「置換反応」です。生成物のC-Cl結合は単結合であり、メタンと同様に炭素原子は正四面体構造をとるため、炭素原子は同一平面上にありません。
②【正】
この反応は、アルキン(2-ブチン)の三重結合に水素(H₂)が「付加反応」し、二重結合を持つアルケン(シス-2-ブテン)が生成する反応です。生成したシス-2-ブテンでは、二重結合を形成する2つの炭素原子と、それに直接結合する4つの原子(この場合は4つの炭素原子)はすべて同一平面上に存在します。したがって、この反応は付加反応であり、かつ生成物に含まれるすべての炭素原子が同一平面上にあります。
③【誤】
この反応は、アルコール(2-ブタノール)から水(H₂O)が取れてアルケン(2-ブテン)が生成する「脱離反応」です。
④【誤】
この反応は、ベンゼン環の水素原子が塩素原子に置き換わる「置換反応」(芳香族求電子置換反応)です。
⑤【誤】
この反応は、ベンゼンの二重結合に水素(H₂)が「付加反応」し、シクロヘキサンが生成する反応です。付加反応ではありますが、生成物であるシクロヘキサンは、安定ないす形などの立体配座をとり、6つの炭素原子は同一平面上にはありません。
問2:正解⑤
<問題要旨>
環状アルカン(シクロプロパン誘導体)の開環付加反応について、結合が切断される位置によってどのような生成物が得られるか、またその生成物が不斉炭素原子を持つかどうかを判断する問題です。構造式を正確に描き、不斉炭素原子の定義(1つの炭素原子に4つの互いに異なる原子または原子団が結合している)を適用する能力が問われます。
<選択肢>
メチルシクロプロパンの炭素環が開いて、両端の炭素原子に臭素原子(Br)が付加する反応を考えます。 ・出発物質:メチルシクロプロパン (C₄H₈) ・反応:+ Br₂ → C₄H₈Br₂
・切断位置アまたはイで切断された場合:
メチル基が結合した炭素と、隣接するCH₂基との間のC-C結合が切断されます。アとイは、生成物としては同じもの(1,3-ジブロモブタン)を与えます。 生成物の構造式:CH₃-CH(Br)-CH₂-CH₂(Br) この生成物において、2番目の炭素原子には、水素原子(H)、メチル基(-CH₃)、臭素原子(-Br)、ブロモエチル基(-CH₂CH₂Br)という4つの異なる原子・原子団が結合しています。したがって、この炭素は不斉炭素原子です。 よって、切断位置ア、イともに、不斉炭素原子を持つ生成物が得られます(ア:○、イ:○)。
・切断位置ウで切断された場合:
メチル基が結合していない2つのCH₂基の間のC-C結合が切断されます。 生成物の構造式:CH₃-CH(CH₂Br)-CH₂Br (1,3-ジブロモ-2-メチルプロパン) この生成物において、中心の炭素原子には、水素原子(H)、メチル基(-CH₃)、ブロモメチル基(-CH₂Br)、ブロモメチル基(-CH₂Br)という原子・原子団が結合しています。同じ原子団(-CH₂Br)が2つ結合しているため、この炭素は不斉炭素原子ではありません。 よって、切断位置ウでは、不斉炭素原子を持つ生成物は得られません(ウ:×)。
以上の結果から、ア:○、イ:○、ウ:× の組み合わせである⑤が正解です。
問3:正解①
<問題要旨>
合成高分子化合物に関する基本的な知識を問う問題です。熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂の違い、代表的な合成繊維や合成樹脂の性質・原料を正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
ポリ酢酸ビニルは、酢酸ビニルが付加重合してできる鎖状の高分子です。このような鎖状高分子からなる樹脂は、加熱すると分子運動が活発になって軟化し、冷却すると固化する性質を持ちます。これは熱可塑性樹脂の特徴です。熱硬化性樹脂は、加熱すると網目状の構造を形成して硬化し、再加熱しても軟化しない樹脂(例:フェノール樹脂、メラミン樹脂)のことです。したがって、この記述は誤りです。
②【正】
アラミド繊維は、芳香族ポリアミド系の合成繊維で、分子鎖が規則正しく強固に配列する性質があります。そのため、鋼鉄の数倍の引っ張り強度を持ち、防弾チョッキやタイヤの補強材などに利用されます。
③【正】
メラミン樹脂は、メラミンとホルムアルデヒドを付加縮合させて得られる熱硬化性樹脂です。耐熱性や耐水性に優れ、食器や化粧板などに利用されます。
④【正】
シリコーンゴムは、ケイ素(Si)と酸素(O)が交互に結合したシロキサン結合 (-Si-O-) を主鎖(分子の骨格)としています。側鎖にはメチル基などの有機基が結合していますが、主鎖に炭素原子間の二重結合(C=C)は含みません。
問4:正解⑤
<問題要旨>
エステルの構造式から、そのエステルを合成するために用いられたカルボン酸とアルコールを推定する問題です。エステル化がカルボン酸とアルコールの脱水縮合反応であること、またカルボン酸が第一級アルコールの酸化によって得られることを理解している必要があります。
<選択肢>
まず、生成物であるエステルDの構造式から、元のカルボン酸とアルコールを特定します。
・エステルD:CH₃CH₂-CO-O-CH₂CH₂CH₃ (プロピオン酸プロピル) エステル結合 (-CO-O-) で分子を分解して考えます。
・カルボニル基(C=O)側がカルボン酸由来:CH₃CH₂-COOH (プロピオン酸)→ これがカルボン酸Bです。
・酸素原子(O)側がアルコール由来:HO-CH₂CH₂CH₃ (1-プロパノール)→ これがアルコールCです。
次に、カルボン酸B(プロピオン酸)がアルコールAの酸化によって得られることから、アルコールAを特定します。 第一級アルコールを酸化すると、同じ炭素数のカルボン酸が生成します。プロピオン酸は炭素数が3なので、元になったアルコールAも炭素数3の第一級アルコールです。
・アルコールA:CH₃CH₂CH₂OH (1-プロパノール)
したがって、アルコールAとアルコールCはどちらも1-プロパノールです。 問題で示された選択肢ア~ウは、 ア:エタノール (C₂) イ:1-プロパノール (C₃) ウ:1-ブタノール (C₄) なので、A = イ、C = イ となります。この組み合わせは⑤です。
問5a:正解③
<問題要旨>
脂肪酸の構造と物性(融点)の関係を、与えられた2つのグラフから読み解く問題です。グラフの情報を正確に解釈し、比較検討する能力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
図3で、飽和脂肪酸のnの値が2つ増える(炭素数が2つ増える)場合の変化を見ます。例えば、n=12(分子量228、融点54℃)からn=14(分子量256、融点63℃)では、融点は9℃ (9 K) 上昇しています。約20 Kずつ高くなるという記述は過大であり、誤りです。
②【誤】
CH₃(CH₂)₂₀COOHは、n=20の飽和脂肪酸です。図3はn=18(分子量298、融点約75℃)までを示しています。グラフの傾向から、炭素鎖がさらに長くなれば、分子間力が強まるため融点はさらに高くなると予想されます。約70℃という値は、n=18の時点より低いため、誤りです。
③【正】
図4で、炭素数18の脂肪酸における二重結合の数と融点の関係を見ます。 ・二重結合 0 → 1:融点は約70℃から約14℃へ、約56℃低下。 ・二重結合 1 → 2:融点は約14℃から約-5℃へ、約19℃低下。 ・二重結合 2 → 3:融点は約-5℃から約-11℃へ、約6℃低下。 二重結合が0から1になった場合(飽和から不飽和になった場合)の融点の低下が、それ以降の低下よりも大きいことがグラフから明確に読み取れます。これは、二重結合(特にシス型)によって分子が折れ曲がり、分子同士が規則正しく配列しにくくなるためです。
④【誤】
C₁₇H₃₁COOHはリノール酸で、炭化水素基に二重結合を2つ持ちます。図4から、二重結合の数が2の脂肪酸の融点は約-5℃です。常温(例えば25℃)では融点よりはるかに高いため、液体です。「固体である」という記述は誤りです。
問5b:正解④
<問題要旨>
油脂の物理的性質(常温での状態)と、それを構成する脂肪酸の種類・含有率の関係を考察する問題です。一般的に、不飽和脂肪酸を多く含む油脂は融点が低く(液体油)、飽和脂肪酸を多く含む油脂は融点が高い(固体脂)という基本原理を基に推論します。
<選択肢>
まず、与えられた情報を整理します。
・油脂の性質:ア、イは液体(不飽和脂肪酸が多い)。ウ、エは固体(飽和脂肪酸が多い)。融点はウ>エ。
・既知の脂肪酸:A = リノレン酸(C18, 二重結合3つ, 融点-11℃)、C = オレイン酸(C18, 二重結合1つ, 融点14℃)。これらはどちらも不飽和脂肪酸です。
・未知の脂肪酸:B, D, E, Fを特定する。候補はミリスチン酸(C14飽和)、パルミチン酸(C16飽和)、ステアリン酸(C18飽和)、リノール酸(C18, 二重結合2つ)。
・融点の一般傾向:飽和脂肪酸では炭素数が多いほど融点が高い(ステアリン酸>パルミチン酸>ミリスチン酸)。不飽和脂肪酸は二重結合が多いほど融点が低い(リノレン酸<リノール酸<オレイン酸)。
考察:
- 油脂アとイは液体なので、融点の低い不飽和脂肪酸を多く含むはずです。グラフを見ると、アとイはA(リノレン酸)とC(オレイン酸)に加え、Bも多く含んでいます。このことから、Bも融点の低い不飽和脂肪酸である可能性が非常に高いと推測できます。
- 候補の中で残っている不飽和脂肪酸はリノール酸のみです。
- この推測が正しいか検証します。もしBがリノール酸だとすると、A, B, Cが不飽和脂肪酸、D, E, Fが飽和脂肪酸(ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸)となります。
- 油脂ウとエは固体なので、飽和脂肪酸D, E, Fを多く含んでいるはずです。グラフを見ると、確かにウとエはD, E, Fの割合が高いです。
- この仮定は、与えられた情報と矛盾しません。したがって、脂肪酸Bはリノール酸であると判断できます。
① ミリスチン酸(飽和) ② パルミチン酸(飽和) ③ ステアリン酸(飽和) ④ リノール酸(不飽和)
第4問
問1a:正解③⑤②
<問題要旨>
建築材料である漆喰の製造から硬化に至る化学変化を問う問題です。石灰石を原料とする一連の反応(熱分解、水和、炭酸塩化)を正しく理解しているかを確認します。
<選択肢>
・アの特定:操作Iでは、石灰石(主成分は炭酸カルシウム CaCO₃)を高温で加熱します。この熱分解反応により、酸化カルシウム CaO(生石灰)と二酸化炭素 CO₂ が生成します。 化学反応式:CaCO₃→CaO+CO2 この後、生成したア(CaO)に水を加えると水酸化カルシウム Ca(OH)₂(消石灰)ができます。 したがって、アは酸化カルシウム(CaO)であり、選択肢③です。
・イとウの特定:壁や天井に塗った漆喰(主成分はCa(OH)₂)は、空気中の成分と反応して硬化します。この反応は、水酸化カルシウムが空気中の二酸化炭素 CO₂を吸収して、元の石灰石の成分である炭酸カルシウム CaCO₃に変化する反応です。 化学反応式:Ca(OH)₂+CO2→CaCO₃+H2O したがって、イは二酸化炭素(CO₂)で選択肢⑤、ウは炭酸カルシウム(CaCO₃)で選択肢②です。
問1b:正解⑤
<問題要旨>
溶解度積を用いて、難溶性塩である水酸化カルシウムの飽和水溶液のpHを計算する問題です。対数計算が含まれるため、与えられたlogの値を使って正確に計算する能力が求められます。
<選択肢>
水酸化カルシウムは水中で次のように電離します。
Ca(OH)₂⇌Ca2++2OH-
電離により、1つの Ca2+ に対して2つの OH− が生じるため、[Ca2+]=1/2[OH-] の関係が成り立ちます。
問題文で与えられた溶解度積 Ksp の式を使います。
Ksp=[Ca2+][OH-]2=1/2[OH−]3=5.00×10-6 (mol/L)³
この式から [OH-] を求めます。
[OH-]3=2×(5.00×10-6)=10.0×10-6=1.00×10-5
[OH-]=(1.00×10-5)1/3=10-5/3=101/3×10-2 mol/L
次に、pOHを計算します。
pOH=−log10[OH-]=−log10(10-5/3)=5/3≈1.67
最後に、水のイオン積の関係式 pH+pOH=14 を用いてpHを求めます。 pH=14−pOH=14−5/3=42/3−5/3=37/3≈12.33
計算結果に最も近い値は選択肢⑤の12.3です。
問2:正解①
<問題要旨>
複数の化合物を含む混合物を加熱し、分解反応によって生じた気体の量と残った固体の量から、加熱前の混合物に含まれていた特定の化合物の物質量を求める化学量論の問題です。連立方程式を立てて解く必要があります。
<選択肢>
加熱によって分解反応を起こすのは Cu3(CO3)2(OH)2 と Cu2CO3(OH)2 の2つです。加熱前のそれぞれの物質量を x [mol], y [mol] とします。
反応式: (1) Cu3(CO3)2(OH)2→3CuO+H2O+2CO2 (2) Cu2CO3(OH)2→2CuO+H2O+CO2
生成した H₂O と CO₂ の物質量について、連立方程式を立てます。
・H₂Oの物質量:x + y = 0.50 …… (A)
・CO₂の物質量:2x + y = 0.70 …… (B)
(B) – (A) を計算してyを消去します。
(2x + y) – (x + y) = 0.70 – 0.50 x = 0.20 mol
x = 0.20 を式(A)に代入してyを求めます。
0.20 + y = 0.50 y = 0.30 mol
次に、これらの分解反応によって生成した CuO の総物質量を計算します。
生成したCuOの物質量 = (3x) + (2y) = 3 × 0.20 + 2 × 0.30 = 0.60 + 0.60 = 1.20 mol
問題文より、加熱後の CuO の総物質量は 1.30 mol でした。これは、「もともと顔料Xに含まれていたCuO」と「反応によって新たに生成したCuO」の合計です。 したがって、加熱前の顔料Xに含まれていたCuOの物質量は、 (加熱後の総量) – (反応で生成した量) = 1.30 mol – 1.20 mol = 0.10 mol
よって、正解は①です。
問3a:正解③
<問題要旨>
酸化還元反応における物質量の関係を計算し、その結果をグラフとして表現する問題です。反応式から電子の授受に関わる物質のモル比を求め、滴下量と反応物の量の関係を式で表すことがポイントです。
<選択肢>
反応式(3)と(4)から、全体の反応におけるインジゴと Na2S2O4 の物質量の関係を求めます。
(3) Na2S2O4 + … → … + 2e-
(4) インジゴ + 2e- → ロイコインジゴ
この2式から、Na2S2O4 1 mol が放出した電子 2 mol を、インジゴ 1 mol が受け取ることがわかります。 つまり、インジゴ 1 mol と Na2S2O4 1 mol が過不足なく反応します。
インジゴ x [g] の物質量は、分子量が262なので、x/262 [mol] です。 これと反応する Na2S2O4 の物質量も x/262 [mol] です。 滴下した 0.20 mol/L のNa2S2O4水溶液の体積を V [mL] (= V/1000 [L]) とすると、滴下したNa2S2O4の物質量は 0.20×(V/1000) [mol] です。
両者が等しいので、 0.20×(V/1000)=x/262 V=(1000×x)/(0.20×262)=1000x/52.4≈19.08x
この関係式 V≈19.1x に、具体的なxの値を代入してVを求めます。
・x = 0.050 g のとき、V = 19.08 × 0.050 ≈ 0.95 mL
・x = 0.10 g のとき、V = 19.08 × 0.10 ≈ 1.91 mL
この計算結果とグラフを比較します。 グラフ③は、x = 0.050 g で V ≈ 1.0 mL、x = 0.10 g で V ≈ 2.0 mL となっており、原点を通る直線関係で、計算結果とほぼ一致します。 他のグラフは傾きが明らかに異なります。
問3b:正解④
<問題要旨>
いくつかの有機化学反応の中から、酸化還元反応に該当しないものを選ぶ問題です。有機化合物の酸化(酸素原子の増加、水素原子の減少)と還元(酸素原子の減少、水素原子の増加)の定義を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【酸化還元反応】
2-プロパノール(第二級アルコール)が、酸化剤であるニクロム酸カリウムによって酸化され、アセトン(ケトン)になる反応です。アルコールの酸化なので、酸化還元反応です。
②【酸化還元反応】
マルトースは還元糖であり、分子内にアルデヒド基(ヘミアセタール構造として存在)を持ちます。フェーリング液は弱い酸化剤であり、マルトースはこれによって酸化され、フェーリング液中のCu²⁺は還元されてCu₂Oの赤色沈殿を生じます。これは酸化還元反応です。
③【酸化還元反応】
ニトロベンゼンのニトロ基(-NO₂)が、触媒を用いて水素と反応し、アミノ基(-NH₂)に変化する反応です。これはアニリンを生成する反応であり、酸素原子が失われ水素原子が付加しているため、還元反応です。
④【酸化も還元もされない】
安息香酸(カルボン酸)とメタノール(アルコール)が、濃硫酸を触媒として反応し、エステル(安息香酸メチル)と水が生成する反応です。これはエステル化と呼ばれる脱水縮合反応であり、反応の前後で炭素原子の酸化数は変化していません。したがって、これは酸化還元反応ではありません。
問3c:正解④
<問題要旨>
ベンゼンから置換基を持つ芳香族化合物を合成する際の、反応の順序を決定する問題です。置換基がベンゼン環に導入される位置を決める性質(配向性)を考慮して、目的の生成物が得られる合成経路を考える必要があります。
<選択肢>
目的の化合物は p-アミノベンゼンスルホン酸で、アミノ基(-NH₂)とスルホ基(-SO₃H)がパラ(p-)の位置関係にあります。 置換基の配向性に関する性質 I〜III を利用して、正しい反応順序を考えます。
・経路1:
スルホン化 → ニトロ化 → 還元 ベンゼン →(スルホン化)→ ベンゼンスルホン酸 ベンゼンスルホン酸 →(ニトロ化)→ (性質Iより) m-ニトロベンゼンスルホン酸 これでは目的のパラ体は得られません。
・経路2:
ニトロ化 → スルホン化 → 還元 ベンゼン →(ニトロ化)→ ニトロベンゼン ニトロベンゼン →(スルホン化)→ (性質IIより) m-ニトロベンゼンスルホン酸 これでも目的のパラ体は得られません。
・経路3:
ニトロ化 → 還元 → スルホン化 ベンゼン →(反応ア:ニトロ化)→ ニトロベンゼン (化合物X) ニトロベンゼン →(反応イ:還元)→ アニリン (化合物Y) アニリン →(反応ウ:スルホン化)→ (性質IIIより) p-アミノベンゼンスルホン酸 この経路であれば、目的のパラ体が得られます。
したがって、反応ア:ニトロ化、反応イ:還元、反応ウ:スルホン化 の順である選択肢④が正解です。アミノ基はオルト・パラ配向性、スルホ基とニトロ基はメタ配向性であるという知識からもこの結論が導けます。
第5問
問1:正解③
<問題要旨>
ヘスの法則を利用して、複数の反応エンタルピーのデータから未知の反応のエンタルピー変化を計算する問題です。エンタルピー変化ΔHが負のとき発熱反応、正のとき吸熱反応であることも問われます。
<選択肢>
求めたい反応のエンタルピー変化をΔHとします。
(目的反応): C6H12O6(固)→2C2H5OH(液)+2CO2(気) ΔH=?
与えられた燃焼エンタルピーの熱化学方程式は以下の通りです。
(A) : C6H12O6(固)+6O2(気)=6CO2(気)+6H2O(液) ΔHA=−2803 kJ
(B) : C2H5OH(液)+3O2(気)=2CO2(気)+3H2O(液) ΔHB=−1368 kJ
目的の反応式を作るために、(A)式と(B)式を組み合わせます。 目的反応の左辺には C6H12O6 が1 mol あるので、(A)式をそのまま使います。 目的反応の右辺には C2H5OH が2 mol あるので、(B)式を2倍して逆向きにします。つまり、(B)式を2倍したものを(A)式から引きます。 (A) – 2×(B) を計算します。
(C6H12O6+6O2)−(2C2H5OH+6O2)=(6CO2+6H2O)−(4CO2+6H2O)
整理すると、
C6H12O6−2C2H5OH=2CO2
移項して、
C6H12O6=2C2H5OH+2CO2
となり、目的の反応式と一致します。エンタルピー変化も同様に計算します。
ΔH=ΔHA−2×ΔHB=−2803−2×(−1368)=−2803+2736=−67 kJ
エンタルピー変化ΔHが -67 kJ と負の値なので、この反応は発熱反応です。 したがって、エンタルピー変化ΔHが-67 kJ、発熱反応である③が正解です。
問2:正解④
<問題要旨>
炭酸ナトリウムと炭酸水素ナトリウムの混合水溶液を塩酸で滴定する、二段階滴定の問題です。滴定の各段階でどの化学種が反応しているかを理解し、物質量の関係から未知の濃度を算出します。
<選択肢>
滴定の過程を2つの段階に分けて考えます。
・第一段階 (pH 9.3 → 8.3):
この段階では、より塩基性の強い炭酸イオン(CO32-)が塩酸(H⁺)と反応し、炭酸水素イオン(HCO3-)に変化します。
反応式:H++CO32-→HCO3-
この反応に要した塩酸は 0.50 mL です。したがって、滴下前の溶液に含まれていた CO32-の物質量は、
1.00 mol/L×0.50/1000 L=0.500×10-3 mol
・第二段階 (pH 8.3 → 4.0):
この段階では、溶液中のすべての炭酸水素イオン(HCO3-)が塩酸(H⁺)と反応し、二酸化炭素と水に変化します。 反応式:H++HCO3-→H2O+CO2
この反応に要した塩酸は、滴下量の合計 6.00 mL から第一段階の 0.50 mL を引いた、 6.00 mL – 0.50 mL = 5.50 mL です。 したがって、第二段階で反応した HCO3-の総物質量は、
1.00 mol/L×5.50/1000 L=5.50×10-3 mol
この反応した HCO3− の総物質量は、「もともと溶液に存在した HCO3-」と「第一段階で CO32- から生成した HCO3−」の合計です。 第一段階で生成した HCO3- の物質量は、反応した CO32-と同じく 0.500×10-3 mol です。
よって、滴下前の水溶液にもともと含まれていた HCO3-の物質量は、
(総物質量) – (生成した物質量) = 5.50×10-3 mol−0.500×10-3 mol=5.00×10-3 mol
最後に、滴下前の水溶液中の HCO3-のモル濃度を計算します。溶液の体積は 100 mL (= 0.100 L) なので、
濃度 = 5.00×10-3 mol / 0.100 L = 5.00×10-2 mol/L
したがって、④が正解です。
問3:(Ⅰ)正解③ (Ⅱ)正解②
<問題要旨>
化学平衡の状態にある反応系で、条件(体積、濃度)を変化させたときに、反応速度と平衡の位置がどのように変化するかを考察し、適切なグラフを選択する問題です。
<選択肢>
条件Ⅰ:容器の体積を2倍にした。
・平衡の移動: 反応式は H2(気)+I2(気)⇌2HI(気) です。 この反応では、反応式の左辺の気体分子の総数 (1+1=2) と、右辺の気体分子の総数 (2) が等しいです。このような反応では、圧力を変化させても(体積を変化させても)化学平衡は移動しません。したがって、平衡状態に達したときのHIの物質量(グラフの最終的な高さ)は、元の実験(点線)と同じ 0.8 mol のままです。
・反応速度: 体積を2倍にすると、容器内のすべての化学種のモル濃度が半分になります。正反応速度 v1=k1[H2][I2] も逆反応速度 v2=k2[HI]2 も濃度に依存するため、両方の反応速度は遅くなります。その結果、平衡に達するまでの時間が元の実験よりも長くなります。
・グラフの選択: 最終的なHIの量は変わらず、平衡に達するまでの時間が長くなる(グラフの立ち上がりが緩やかになる)グラフは、③です。
条件Ⅱ:反応開始時のH₂のモル濃度を3倍、I₂のモル濃度を1/3倍にした。
・反応速度: 正反応の初期速度 v1 は k1[H2][I2] に比例します。元の実験の濃度を [H2]0,[I2]0 とすると、変化後の濃度は 3[H2]0,31[I2]0 となります。 速度に関わる濃度の積は (3[H2]0)×(31[I2]0)=[H2]0[I2]0 となり、元の実験と変わりません。したがって、反応開始直後の反応速度(グラフの原点での傾き)は元の実験とほぼ同じになります。
・平衡の移動: 元の実験では、H₂とI₂が同じ物質量から始まり、平衡時にHIが0.8 mol生成しました。条件Ⅱでは、H₂が過剰でI₂が少ない状態から反応が始まります。反応できる量は、少ない方のI₂の量によって制限されます。元の実験よりもI₂の量が少ないため、生成するHIの最大量も元の実験より少なくなります。したがって、平衡に達したときのHIの物質量は、0.8 molよりも大幅に少なくなります。
・グラフの選択: 反応初期の速度は元の実験とほぼ同じで、最終的なHIの量が0.8 molより大幅に少なくなるグラフは、②です。
問4a:正解②
<問題要旨>
イオン交換膜の機能について、その化学構造からイオン選択性の原理を考察する問題です。陰イオン交換膜がなぜ陰イオンを選択的に透過させ、陽イオンを排除するのかを、膜に導入された官能基の電荷に基づいて考えます。
<選択肢>
問題文の図3と説明から、陰イオン交換膜の働きを考えます。
・膜の細孔を陰イオンであるCl⁻は通過できる。
・陽イオンであるNa⁺は細孔に入り込めず、排除される。 これは、膜の内部(細孔の壁)が正の電荷を帯びているためと考えられます。正に帯電した壁が、負の電荷を持つCl⁻を引きつけて通過を助け、正の電荷を持つNa⁺を静電気的な反発力で排除するのです。
したがって、膜を構成する高分子に導入されている官能基Xは、正の電荷を持つイオン性の基である必要があります。
① -CH₃(メチル基):電荷を持たない中性の官能基です。
② -CH₂N⁺(CH₃)₃(第四級アンモニウム基):窒素原子が常に正の電荷を帯びている陽イオン性の官能基です。これが膜に固定されていれば、膜全体が正の電荷を帯びることになり、陰イオン交換膜として機能します。
③ -SO₃⁻(スルホ基):負の電荷を帯びている陰イオン性の官能基です。これは陽イオン交換膜に用いられます。
④ -NO₂(ニトロ基):電荷を持たない中性の官能基です。
したがって、陰イオン交換膜の官能基として最も適当なものは②です。
問4b:正解⑥
只今準備中です。しばらくお待ちください。
第6問
問1:正解⑤
<問題要旨>
ヘスの法則を利用して、複数の燃焼熱のデータから未知の反応の反応熱を計算する問題です。反応熱Qが正のとき発熱反応、負のとき吸熱反応であることも問われます。
<選択肢>
求めたい反応の反応熱をQ [kJ]とします。
(目的反応): C6H12O6(固)=2C2H5OH(液)+2CO2(気)+Q [kJ]
与えられた燃焼熱の熱化学方程式は以下の通りです。
(A): C6H12O6(固)+6O2(気)=6CO2(気)+6H2O(液)+2803 kJ
(B): C2H5OH(液)+3O2(気)=2CO2(気)+3H2O(液)+1368 kJ
目的の反応式を作るために、(A)式と(B)式を組み合わせます。 (A) – 2×(B) を計算します。
(左辺): (C6H12O6+6O2)−(2C2H5OH+6O2)=C6H12O6−2C2H5OH
(右辺): (6CO2+6H2O)−(4CO2+6H2O)=2CO2
(熱量): 2803−2×1368=2803−2736=67 kJ
整理すると、
C6H12O6−2C2H5OH=2CO2+67 kJ
移項して、
C6H12O6=2C2H5OH+2CO2+67 kJ
となり、目的の反応式と一致します。
反応熱Qは +67 kJ と正の値なので、この反応は発熱反応です。 したがって、反応熱Qが67 kJ、発熱反応である⑤が正解です。
問2:正解④
第5問と同様のため省略
問3:正解③②
第5問と同様のため省略
問4:正解②⑥
第5問と同様のため省略