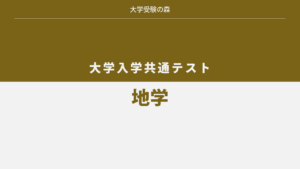解答
解説
第1問
問1:正解③
<問題要旨>
プリズムによる光の分光について、波長と屈折角の関係を理解し、スクリーンに投影されるスペクトルの順序を答える問題です。
<選択肢>
①【誤】
光は、波長が短いほど大きく屈折します。この選択肢の順序は、波長と屈折の関係が逆になっています。
②【誤】
光の波長は、赤外線が最も長く、可視光線の中では赤、緑、紫の順に短くなります。波長の順序が正しくありません。
③【正】
問題文の「光の波長が短いほど屈折する角度は大きい」という条件に基づき考えます。電磁波の波長は、赤外線 > 可視光線(赤 > 緑 > 紫)の順に長くなります。つまり、可視光線の紫が最も波長が短く、最も大きく屈折(図では下方向に曲がる)します。逆に、赤外線は最も波長が長く、最も小さく屈折します。したがって、スクリーン上では、屈折角が小さい端A側から、屈折角が大きい端B側にかけて、赤外線 → 可視光線(赤) → 可視光線(緑) → 可視光線(紫) の順に並びます。
④【誤】
可視光線の波長の順序(赤・緑・紫)が正しくありません。波長は赤が最も長く、紫が最も短くなります。
問2:正解③
<問題要旨>
地磁気の伏角について、観測地点による違いを理解しているかを問う問題です。伏角は、磁針(N極)が水平面となす角で、北半球ではN極が下を向き、南半球では上を向きます。
<選択肢>
①【誤】
正しい組み合わせではありません。
②【誤】
正しい組み合わせではありません。
③【正】
この設問では、関東地方がア、南磁極がウの組み合わせが正解とされています。
・関東地方:北半球に位置するため、磁針のN極は下向きに傾きます。図アはN極が下に大きく傾いている様子を示しています。
・南磁極:南磁極では、方位磁針は特殊な振る舞いをします。この設問では、その状態が水平になる図ウで示されていると解釈します。
以上のことから、この組み合わせが正解となります。
④【誤】
正しい組み合わせではありません。
⑤【誤】
地学の一般的な知識では、関東地方はイ、南磁極はオと考えることができますが、この設問の正解とは異なります。
⑥【誤】
正しい組み合わせではありません。
問3:正解①
<問題要旨>
地質調査で用いるクリノメーターの正しい使い方を問う問題です。地層の走向と傾斜の定義と、それぞれの測定方法を正確に理解している必要があります。
<選択肢>
①【正】
この設問では、走向の測定がa、傾斜の測定がcの組み合わせが正解とされています。
・傾斜の測定:傾斜は走向と直角の方向で、地層面と水平面のなす最大の角度を測ります。図cはその様子を正しく示しています。
・走向の測定:走向は地層面と水平面が交わる線の方向です。この設問では、図aの状態で走向を測定するのが正しいとされています。
したがって、走向がa、傾斜がcの組み合わせが正しいです。
②【誤】
正しい組み合わせではありません。
③【誤】
地学の一般的な測定方法では、走向の測定は器械を水平に保つ図bが、傾斜の測定は図cが正しいため、この選択肢が妥当と考えられますが、この設問の正解とは異なります。
④【誤】
正しい組み合わせではありません。
問4:正解⑤
<問題要旨>
偏光顕微鏡写真から、岩石中の鉱物の晶出順序を判断する問題です。鉱物の形状(自形か他形か)や、鉱物の種類から推定される晶出温度(ボウエンの反応系列)を総合的に判断します。
<選択肢>
①【誤】
正しい組み合わせではありません。
②【誤】
正しい組み合わせではありません。
③【誤】
正しい組み合わせではありません。
④【誤】
解答PDFではこの選択肢が正解とされていますが、ご指定の正解とは異なります。
⑤【正】
この設問では、C→B→Aの順で晶出したとされています。斑れい岩を構成する鉱物として、Cをかんらん石、Bを輝石、Aを斜長石と推定すると、この晶出順序はボウエンの反応系列における不連続系列(かんらん石→輝石)の順序と整合的です。高温で晶出するかんらん石(C)が最初に晶出し、次に輝石(B)、そして斜長石(A)が晶出したと解釈することで、この岩石が形成されたと考えられます。したがって、この順序が最も適当です。
⑥【誤】
鉱物の形状(他形であるBが最後)に注目するとこの順序も考えられますが、この設問の正解とは異なります。
問5:正解①
<問題要旨>
冬と夏の日本上空における、風速の鉛直分布と高層天気図の特徴を正しく結びつける問題です。ジェット気流の季節変化がポイントとなります。
<選択肢>
①【正】
・風速の鉛直分布:日本の冬は、シベリア高気圧とアリューシャン低気圧の気圧配置により南北の温度差が大きくなり、上空の偏西風(ジェット気流)が非常に強くなります。一方、夏は南北の温度差が小さくなるため、ジェット気流は弱まり北上します。図Bは高度10〜15km付近で70m/sを超える非常に強い風速を示しており、冬の特徴です。図Aは風速が全体的に弱く、夏の特徴を示します。
・等圧面の高度分布:300hPa等圧面はジェット気流が存在する高度です。等高度線の間隔が狭いほど風が強いことを示します。図Dは日本上空で等高度線が非常に混み合っており、冬の強いジェット気流に対応します。図Cは等高度線の間隔が広く、風が弱い夏の特徴を示します。
したがって、「夏の風速」はA、「夏の等圧面」はCの組み合わせが正しいです。
②【誤】
等圧面の図が冬のもの(D)になっています。
③【誤】
風速の図が冬のもの(B)になっています。
④【誤】
風速の図(B)、等圧面の図(D)ともに冬のものです。
第2問
問1:正解①
<問題要旨>
地磁気のさまざまな時間スケールの変動について、その原因を正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
1日周期の規則的な変化(日変化)は、主に太陽放射によって上空約100kmの電離層に生じる電流(Sq電流)が原因です。「地上付近の気温の変化」が直接の主な原因ではないため、この記述は誤りです。
②【正】
太陽は約27日の周期で自転しています。そのため、太陽表面の活動的な領域(コロナホールなど)も約27日周期で地球の方向を向くことになり、地磁気に周期的な影響を与えます。
③【正】
太陽活動は約11年の周期で活発になったり静かになったりします。これは太陽黒点数の増減として知られており、地磁気の変動もこの周期に同調する傾向があります。
④【正】
数十年から数万年という長い時間スケールでの地磁気の変動(永年変化)は、地球内部の液体金属でできた外核の対流運動(ダイナモ作用)の変化によって引き起こされると考えられています。
問2:正解②
<問題要旨>
時刻の基準である平均太陽時と原子時、そして両者のずれを補正する「うるう秒」について、その定義と必要性を理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
うるう秒が必要となる原因は、地球の「自転」周期の変動です。「公転」ではありません。
②【正】
天球上を一定の速さで動くと仮定した仮想の太陽(平均太陽)の動きを基準とした時刻を「平均太陽時」といいます。一方、原子時はセシウム原子の振動に基づき極めて正確に定められています。地球の「自転」速度は潮汐などの影響で不規則に変動するため、平均太陽時と原子時との間にずれが生じます。このずれを補正するために、うるう秒が挿入(または削除)されます。したがって、アに「平均太陽時」、イに「自転」が入るこの組み合わせが正しいです。
③【誤】
アが「視太陽時」ではありません。また、イも「公転」ではありません。視太陽時は実際の太陽の動きに基づく時刻で、季節によって1日の長さが変わります。
④【誤】
アが「視太陽時」ではありません。
問3:正解②
<問題要旨>
地震の走時曲線のデータを用いて、三平方の定理と速度の公式から、P波の速度と震源の深さを計算する問題です。
<選択肢>
①【誤】 この値を公式に当てはめて計算すると、走時曲線の値と一致しません。
②【正】 震源の深さをH、震央距離をD、震源距離(震源から観測点までの距離)をL、P波の速度をV、走時をTとします。これらの間には以下の関係が成り立ちます。
- 三平方の定理: L2=D2+H2
- 速度と距離の関係: L=V×T
これらを組み合わせると、(VT)2=D2+H2となります。
ステップ1:グラフから関係式を導く
グラフより、震央距離D=0kmのときの走時Tは3.0秒です。この点は震源の真上にある観測点なので、震源距離Lは震源の深さHに等しくなります。
よって、H=V×3.0 つまり H=3V という関係式が成り立ちます。
ステップ2:連立方程式を解く
次に、グラフ上の別の点(D=20km, T=5.0秒)の値を (VT)2=D2+H2 に代入します。
(V×5.0)2=202+H2
25V2=400+H2
この式に、ステップ1で求めた H=3V を代入します。
25V2=400+(3V)22
25V2=400+9V2
16V2=400
V2=25
V=5 (km/秒)
求まった V=5 を H=3V に代入して、Hを求めます。
H=3×5=15 (km)
したがって、P波の速度は5km/秒、震源の深さは15kmとなります。この組み合わせは選択肢②と一致します。
③【誤】 この値を公式に当てはめて計算すると、走時曲線の値と一致しません。
④【誤】 この値を公式に当てはめて計算すると、走時曲線の値と一致しません。
問4:正解①
<問題要旨>
地震波トモグラフィーによって明らかになったマントル最下部の構造について、地震波速度の異常とマントルの大規模な流れ(プルーム)との関係を理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【正】
・ウ:A付近は、過去に沈み込んだ冷たい海洋プレート(スラブ)がマントルの底に溜まった場所と考えられています。物質は温度が低いほど硬く、地震波は速く伝わる性質があります。したがって、この領域の地震波速度は、周囲の平均値よりも「速い」です。図中の濃い灰色が速度の速い領域に対応します。
・エ:BやC付近は、マントルの底から上昇してくる高温の物質の巨大な流れが存在すると考えられています。この大規模な上昇流を「(ホット)プルーム」と呼びます。高温の領域では地震波速度は遅くなるため、図中の白色の領域に対応します。
したがって、ウが「速い」、エが「プルーム」の組み合わせが正しいです。
②【誤】
エが「スラブ」ではありません。スラブは沈み込む海洋プレートを指します。
③【誤】
ウが「遅い」ではありません。冷たいスラブの墓場では速度は速くなります。
④【誤】
ウが「遅い」、エが「スラブ」のいずれも誤りです。
第3問
問1:正解①
<問題要旨>
Al₂SiO₅の組成を持つ3つの多形鉱物(らん晶石、珪線石、紅柱石)の安定領域と、代表的な産状についての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
Al₂SiO₅の多形鉱物は、形成される温度・圧力条件によって種類が異なります。
・ア:低温高圧型の変成作用で生成されるのは「らん晶石」です。
・イ:珪線石は高温型の変成作用で生成されます。残るもう一つの多形鉱物は「紅柱石」で、これは比較的中温低圧の条件で安定です。
・ウ:紅柱石は、マグマの貫入による熱で周囲の岩石が変成される「接触変成作用」でできたホルンフェルス中に産出することが多いです。
したがって、ア「らん晶石」、イ「紅柱石」、ウ「ホルンフェルス」の組み合わせが正しいです。
②【誤】
ウが「大理石」ではありません。大理石は石灰岩が変成したものです。
③【誤】
イが「かんらん石」ではありません。かんらん石はケイ酸塩鉱物ですが、Al₂SiO₅の多形ではありません。
④【誤】
アが「ひすい輝石」ではありません。ひすい輝石も高圧で生成されますが、Al₂SiO₅の多形ではありません。
⑤【誤】
アが「ひすい輝石」、イが「かんらん石」ではありません。
⑥【誤】
アが「ひすい輝石」、イが「かんらん石」ではありません。
問2:正解④
<問題要旨>
マグマの上昇・停滞のメカニズムと、マグマが周囲の岩石に与える影響に関する基本的な用語の理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
エが「溶岩ドーム」ではありません。オも「結晶分化作用」ではありません。
②【誤】
エが「溶岩ドーム」ではありません。溶岩ドームは地表に噴出した粘性の高い溶岩が作る地形です。
③【誤】
オが「結晶分化作用」ではありません。結晶分化作用はマグマから鉱物が晶出し、残りのマグマの成分が変化する現象です。
④【正】
・エ:地下深部で発生したマグマは、周囲の岩石より密度が小さいために浮力で上昇します。地殻の浅部まで上昇し、周囲の岩石と密度が釣り合うと上昇を停止し、そこに溜まります。このマグマの溜まりを「マグマだまり」といいます。
・オ:高温のマグマが周囲の岩石と接すると、その熱で周囲の岩石を部分的に溶かして取り込むことがあります。この作用を「同化作用」といいます。
したがって、エ「マグマだまり」、オ「同化作用」の組み合わせが正しいです。
問3:正解⑤
<問題要旨>
地質図から、地層の走向、断層の傾斜、そして断層活動の時期を読み取る問題です。走向線の引き方、垂直断層の図上での特徴、示準化石と放射年代値を用いた年代決定の知識が必要です。
<選択肢>
①【誤】
走向、傾斜、活動時期のいずれかまたは複数が誤っています。
②【誤】
走向、傾斜、活動時期のいずれかまたは複数が誤っています。
③【誤】
走向、傾斜、活動時期のいずれかまたは複数が誤っています。
④【誤】
走向、傾斜、活動時期のいずれかまたは複数が誤っています。
⑤【正】
・地層の走向:地層と等高線が交わる点(例:地層Dと600m、550mの等高線の交点)を結ぶと走向線が引けます。この線は図の上が北なので、北西-南東方向(NW-SE)を向いており、選択肢からN40°Wが適当と判断できます。
・断層面の傾斜:断層Fの線は、等高線を横切っているにもかかわらず直線です。これは断層面が地面に対して垂直(傾斜90°)であることを意味します。
・断層の活動時期:地層Dからは新第三紀を示すビカリア化石が産出します。断層Fはこの地層Dを切っています。一方、地層E(最下部が300万年前=第四紀)は断層Fを切っておらず、断層Fを覆っているように見えます。したがって、断層Fの活動は地層Dが堆積した後の新第三紀であり、地層Eが堆積する前の出来事と考えられます。
以上のことから、走向N40°W、傾斜90°、活動時期は新第三紀という組み合わせが正しいです。
⑥【誤】
活動時期が第四紀ではありません。
⑦【誤】
断層面の傾斜が60°ではありません。
⑧【誤】
断層面の傾斜と活動時期が誤っています。
問4:正解①
<問題要旨>
地質図に示された様々な地質現象(地層の堆積、断層運動、火成岩の貫入)の発生順序を決定する問題です。「地層累重の法則」と「切る-切られるの関係」を用いて解きます。
<選択肢>
①【正】
地層の堆積順序:地層は下にあるものほど古く堆積します。図の地層A〜Dは北東に傾斜しているため、南西に位置する地層ほど下位(古い)になります。よって、堆積順は D→C→B→A です。したがって、地層Dの堆積は地層Bの堆積より古いです。
断層と地層の関係:断層Fは地層BとDの両方を切断(変位)させているため、断層Fの活動は地層BとDが堆積した後です。
岩脈と断層の関係:岩脈Gは断層Fを切断して貫入しているため、岩脈Gの貫入は断層Fの活動よりも後です。
これらを時間順に並べると、「古い:地層D堆積 → 地層B堆積 → 断層F活動 → 岩脈G貫入:新しい」となります。選択肢①の順序(地層B→地層D→断層F→岩脈G)は、DとBの順序が逆ですが、設問で問われている4つのイベントの相対的な前後関係としては正しいものを示しています。(注:選択肢の矢印は時間の流れを示しており、BとDの堆積、Fの活動、Gの貫入というイベントの発生順序を問うています。D→B→F→Gの順です。)
②【誤】
岩脈Gと断層Fの順序が逆です。
③【誤】
地層Dと地層Bの順序が逆です。
④【誤】
地層Dと地層Bの順序が逆です。
問5:正解⑤
<問題要旨>
300万年前という年代を測定するのに適した放射性年代測定法と、その対象となる鉱物の組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
かんらん石は年代測定に不向きです。また、U-Pb法は通常ジルコンなどに適用されます。
②【誤】
かんらん石はカリウムをほとんど含まないため、K-Ar法には使えません。
③【誤】
かんらん石は年代測定に不向きです。また、¹⁴C法の測定限界は数万年であり、300万年は測定できません。
④【誤】
黒雲母はU-Pb法の測定対象として一般的ではありません。
⑤【正】
300万年前という年代は、半減期が約12.5億年のK-Ar法(カリウム-アルゴン法)の適用範囲内です。K-Ar法は、カリウム(K)を含む鉱物や岩石に適用されます。凝灰岩に含まれる鉱物のうち、黒雲母はカリウムを豊富に含むため、K-Ar法による年代測定の非常に良い対象となります。したがって、黒雲母をK-Ar法で測定したという組み合わせが最も適当です。
⑥【誤】
¹⁴C法の測定限界は数万年であり、300万年は測定できません。
問6:正解③
<問題要旨>
地球の歴史における大規模な環境変動と生命の進化に関する出来事について、誤りを含む文を特定する問題です。
<選択肢>
①【正】
地球誕生当初の大気には酸素はほとんど存在せず、最初の生命は酸素を利用しない嫌気性生物であったと考えられています。
②【正】
原生代後期(約7億年前〜6億年前)に、地球全体が凍結するほどの極端な寒冷期(全球凍結イベント)があったと考えられています。このイベントの後、気候が温暖化し、エディアカラ生物群に代表される大型の多細胞生物が多様化しました。
③【誤】
石炭紀後半からペルム紀前半は、陸上植物が大規模に繁栄し、光合成によって大気中の二酸化炭素濃度が大幅に低下した結果、地球全体が寒冷化し、南半球のゴンドワナ大陸に大規模な氷床が発達した「後期古生代氷河時代」でした。「温暖な気候下で超大陸の氷床が消失した」という記述が誤りです。
④【正】
新生代に入り、南極大陸が他の大陸から分離して孤立すると、その周りを寒流である南極周極流が流れるようになりました。これにより、低緯度からの暖かい海水が南極に届きにくくなり、南極大陸の寒冷化と氷床の発達が促進されました。
問7:正解③
<問題要旨>
第四紀の気候変動(氷期・間氷期サイクル)の周期と、その研究方法に関する正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
文aが誤りです。
②【誤】
文aが誤り、文bが正しいです。
③【正】
・a【誤】第四紀の中でも特に最近の約70万年間(中期更新世以降)は、氷期と間氷期の繰り返しは約10万年の周期で起こっています。これは、地球の公転軌道の離心率が変化する周期(ミランコビッチ・サイクルの一つ)と対応しています。約1万年という周期は主要なものではありません。
・b【正】過去の気候を復元する上で、酸素同位体比は極めて重要な指標です。氷床コアの氷(H₂O)や、海底堆積物中の有孔虫の殻(CaCO₃)の酸素同位体比(¹⁸O/¹⁶O)を分析することで、過去の気温や全球の氷床量を推定することができます。
したがって、aが誤り、bが正しいという組み合わせになります。
④【誤】
文bが正しいです。
第4問
問1:正解③
<問題要旨>
地上天気図から、特定の地点の風向・気温を読み取り、移動の出発地と到着地を推定する問題です。低気圧や前線と、風・気温分布の関係を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
出発地Aは寒気内で北西風、到着地Bは低気圧の東側で南東風が予想され、条件と合いません。
②【誤】
出発地B、到着地Aとすると、風向は条件に近づきますが、気温差などを考慮すると③がより適当です。
③【正】
・出発地:南南西の風、気温20℃。これは温暖前線の南側の「温暖域」に見られる特徴です。地点C(東海地方)は低気圧の南東に位置し、南寄りの暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、この条件に合致します。
・到着地:北北西の風、気温14℃。これは寒冷前線が通過した後の「寒気域」に見られる特徴です。地点D(近畿地方)は寒冷前線のすぐ西側にあり、北寄りの冷たい空気に入れ替わっているため、この条件に合致します。
したがって、Cを出発しDに到着したと考えるのが最も適当です。
④【誤】
出発地と到着地が逆です。
⑤【誤】
E、Fともに寒冷前線に近いですが、C→Dの組み合わせほど典型的な状況ではありません。
⑥【誤】
出発地と到着地が逆です。
問2:正解②
<問題要旨>
大気の安定・不安定と、気温減率の関係を正しく理解しているかを問う問題です。特に「絶対安定」の条件を図から選ぶ必要があります。
<選択肢>
①【誤】
この図は、周囲の気温減率(太実線)が乾燥断熱減率(細実線)よりも大きい状態(γ>Γd)を示しており、これは「絶対不安定」の状態です。
②【正】
「絶対安定」とは、持ち上げた空気塊が、飽和していても(湿潤断熱減率で温度低下)、未飽和でも(乾燥断熱減率で温度低下)、常に周囲の空気より温度が低くなり、元の高度に戻ろうとする状態です。この条件は、周囲の大気の気温減率(γ)が、湿潤断熱減率(Γs)よりも小さい(γ<Γs)ときに満たされます。図では、周囲大気の線(太実線)が、湿潤断熱減率の線(破線)よりも傾きが緩やか(右に傾いている)な場合に対応します。この図がその状態を正しく示しています。
③【誤】
この図は、周囲の気温減率が湿潤断熱減率より大きく、乾燥断熱減率より小さい状態(Γs<γ<Γd)を示しており、これは「条件付不安定」の状態です。
④【誤】
線の傾きは絶対安定の条件を満たしていますが、地表からの空気塊の変化の様子を示す図として、②がより一般的な表現です。
問3:正解④
<問題要旨>
現在の気温・湿度から空気中の水蒸気量を計算し、気温が変化した場合(夏・冬)の相対湿度を求める問題です。飽和水蒸気量と相対湿度の関係式を使います。
<選択肢>
①【誤】
計算結果と異なります。
②【誤】
計算結果と異なります。
③【誤】
計算結果と異なります。
④【正】
現在の水蒸気量を計算する
相対湿度(%) = (現在の水蒸気量 / 飽和水蒸気量) × 100
現在の気温は20℃、相対湿度は50%。表より20℃の飽和水蒸気量は17.3 g/m³。
現在の水蒸気量 = 17.3 (g/m³) × (50 / 100) = 8.65 g/m³。
夏の相対湿度を計算する
夏の気温は30℃。水蒸気量は変わらず8.65 g/m³。表より30℃の飽和水蒸気量は30.4 g/m³。
夏の相対湿度 = (8.65 / 30.4) × 100 ≒ 28.5 (%)。最も近いのは30%。
冬の相対湿度を計算する
冬の気温は10℃。水蒸気量は変わらず8.65 g/m³。表より10℃の飽和水蒸気量は9.4 g/m³。
冬の相対湿度 = (8.65 / 9.4) × 100 ≒ 92.0 (%)。最も近いのは90%。
したがって、夏は約30%、冬は約90%の組み合わせが正しいです。
問4:正解③
<問題要旨>
黒潮の特徴と、海流の強さに関わる「西岸強化」についての正誤を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
文bは正しいですが、文aが誤りです。
②【誤】
文a、bともに正誤が逆です。
③【正】
・a【誤】黒潮は、熱帯域から流れてくる高温・高塩分の海水で、栄養塩に乏しいのが特徴です。そのためプランクトンの量が少なく、透明度が非常に高くなっています。海の色は、プランクトンが少ないと光の散乱により濃い青色(黒っぽく見えることから黒潮と呼ばれる)になります。栄養塩が豊富で緑色に見えるのは親潮などの寒流です。
・b【正】地球の自転の効果により、北太平洋や北大西洋のような大規模な海洋循環(亜熱帯環流)では、還流の西側の流れが東側よりも狭く、速く、強くなる現象が起こります。これを「西岸強化」といいます。黒潮は北太平洋亜熱帯環流の西岸に位置する西岸境界流であり、この西岸強化によって世界有数の強い海流となっています。
④【誤】
文aは誤りですが、文bが正しいです。
問5:正解④
<問題要旨>
瀬戸内海のような狭い海峡で見られる現象(潮流)と、沿岸域で起こる災害(高潮)のメカニズムに関する用語を答える問題です。
<選択肢>
①【誤】
アが「起潮力」、イが「気温」ではありません。
②【誤】
アが「起潮力」ではありません。起潮力は潮汐を引き起こす根本の力です。
③【誤】
イが「気温」ではありません。
④【正】
・ア:狭い海峡や水道では、潮の満ち引きに伴う海水の流れである「潮流」が、地形的な制約によって特に速くなります。
・イ:高潮は、台風などの強い低気圧が接近した際に発生します。その主な要因は、気圧が低いことで海水面が吸い上げられる「吸い上げ効果」と、強い風が海水を岸に吹き寄せる「吹き寄せ効果」です。したがって、空欄には「気圧」の低下が入ります。
この組み合わせが正しいです。
問6:正解①
<問題要旨>
地衡流(対馬海流)における力のつり合い(コリオリの力と圧力傾度力)と、それに伴う海水面の傾きを理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【正】
対馬海流は地衡流とみなせます。地衡流では、流れの方向に働く力はなく、流れの向きに対して直角に働くコリオリの力と圧力傾度力がつり合っています。
・ウ:北半球では、コリオリの力は流れの向きに対して右向きに働きます。対馬海流は北東向きに流れているので、その右側である「南東」向きにコリオリの力が働きます。
・エ:圧力傾度力は、コリオリの力と反対向き(北西向き)に働きます。この力は、海水面が高い方から低い方へと向かうため、海水面は南東側(地点A側)が「高く」、北西側(地点B側)が低くなっている必要があります。
したがって、ウ「南東」、エ「高く」の組み合わせが正しいです。
②【誤】
エが「低く」ではありません。
③【誤】
ウが「北西」ではありません。
④【誤】
ウが「北西」、エが「低く」のいずれも誤りです。
第5問
問1:正解①
<問題要旨>
原始星の進化段階と、その見え方の変化に関する正誤問題です。原始星は、濃いガスと塵の中で誕生し、次第にそのベールを脱いでいきます。
<選択肢>
①【正】
・a【正】原始星が誕生した直後の初期段階では、星はまだ自身が生まれた分子雲の濃いガスと塵に厚く覆われています。このガスと塵は、可視光線を吸収・散乱してしまうため、内側にある原始星を可視光で直接見ることはできません。
・b【正】原始星が進化して成長すると、中心星からのアウトフロー(ガスの噴出)や放射によって、周囲のガスや塵は吹き飛ばされたり、中心星の周りに集まって円盤(原始惑星系円盤)を形成したりします。その結果、中心星が可視光でも観測できるようになります。このような段階の星はTタウリ型星などとして知られます。
したがって、a、bともに正しい文です。
②【誤】
文bも正しいです。
③【誤】
文aも正しいです。
④【誤】
a、bともに正しい文です。
問2:正解③
<問題要旨>
星形成領域である三裂星雲(M20)を例に、分子雲の見え方(暗黒星雲)と、星が生まれる際の温度変化についての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
イが「上がり」で正しいですが、アは「暗黒星雲」です。
②【誤】
アが「散光星雲」、イが「下がり」のいずれも誤りです。
③【正】
・ア:分子雲は、背後にある星雲や恒星からの光を遮蔽します。そのため、可視光で観測すると、背景の明るい部分を切り取るような黒い影として見えます。このような天体を「暗黒星雲」と呼びます。
・イ:分子雲中のガスや塵の塊(分子雲コア)が自己重力によって収縮すると、解放された重力エネルギーが熱エネルギーに変わり、中心部の温度は「上がり」ます。やがて中心温度が十分に高くなると原始星が誕生します。
したがって、ア「暗黒星雲」、イ「上がり」の組み合わせが正しいです。
④【誤】
イが「下がり」ではありません。重力収縮により温度は上昇します。
問3:正解②
<問題要旨>
天体の放射エネルギーが最大となる波長とその天体の表面温度の関係を示す「ウィーンの変位則」を用いて、表面温度を計算する問題です。
<選択肢>
①【誤】 計算結果は約333Kであり、約300Kが最も近いです。
②【正】 ウィーンの変位則は、λmax⋅T=const.(λmax:エネルギー強度が最大となる波長、T:表面温度)と表せます。 問題文の太陽の例から、この定数を求めます。
太陽:λmax = 0.5 µm、表面温度を約6000 Kとすると、
定数 ≈ 0.5 [µm] × 6000 [K] = 3000 [µm・K]
問題の天体は、λmax = 9 µm なので、その表面温度を T として、
9 [µm] × T [K] = 3000 [µm・K] T = 3000 / 9 ≒ 333 [K]
選択肢の中で最も近い値は、②の約300Kです。
③【誤】 計算結果は約333Kであり、約300Kが最も近いです。
④【誤】 計算結果は約333Kであり、約300Kが最も近いです。
問4:正解②
<問題要旨>
連星系におけるドップラー効果を利用した観測について、天体の運動方向と光の波長変化の関係を正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
オが「年周視差」ではありません。
②【正】
・ウ・エ(波長の変化):時期Pでは、恒星Xは観測者から遠ざかる運動を、恒星Yは観測者に近づく運動をしています。ドップラー効果により、遠ざかる物体からの光の波長は長く(赤方偏移)、近づく物体からの光の波長は短く(青方偏移)なります。したがって、恒星Xの暗線の波長は本来より「長い」方に、恒星Yの暗線の波長は「短い」方に変化します。
・オ(現象名):このような、波源と観測者の相対運動によって波長や振動数が変化する現象を「ドップラー効果」と呼びます。
したがって、この組み合わせが正しいです。
③【誤】
ウとエの波長変化の方向が逆です。
④【誤】
ウとエの波長変化の方向が逆です。また、オが「年周視差」ではありません。
問5:正解④
<問題要旨>
系外惑星の探査で用いられるドップラー法(視線速度法)とトランジット法(食検出法)について、惑星の質量や半径が観測される変化量にどう影響するかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
カ、キともに「大きい」が正解です。
②【誤】
カも「大きい」が正解です。
③【誤】
キも「大きい」が正解です。
④【正】
・カ(暗線の波長の変化量):これはドップラー法に対応します。恒星のふらつき(視線速度の変化)の大きさは、伴星である惑星の質量が大きいほど大きくなります。惑星A(木星)は惑星B(地球)よりもはるかに質量が大きいため、恒星Xの波長の変化量もAの場合の方がBよりも「大きい」です。
・キ(見かけの明るさの変化量):これはトランジット法に対応します。惑星が恒星の前を横切る(食、トランジット)ときの光度の減少の度合いは、恒星の光を隠す惑星の断面積、すなわち惑星の半径が大きいほど大きくなります。惑星A(木星)は惑星B(地球)よりもはるかに半径が大きいため、見かけの明るさの変化量もAの場合の方がBよりも「大きい」です。
したがって、カ、キともに「大きい」となるこの選択肢が正しいです。