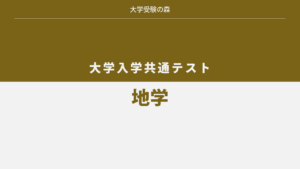解答
解説
第1問
問1:正解②
<問題要旨>
主要な造岩鉱物であるかんらん石の結晶構造と化学組成に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
カルシウムイオン(Ca2+)やナトリウムイオン(Na+)は、主に輝石、角閃石、長石などのケイ酸塩鉱物に含まれますが、かんらん石の主成分ではありません。
②【正】
かんらん石は、独立したSiO4四面体の間に金属イオンが配置された結晶構造をしています。その化学式は(Mg,Fe)2SiO4と表され、マグネシウムイオン(Mg2+)と鉄(II)イオン(Fe2+)が主成分として含まれます。これら2つのイオンはイオン半径が近いため、互いに置換しやすい性質(固溶体)があります。
③【誤】
ニッケルイオン(Ni2+)はかんらん石に含まれることがありますが、主成分ではありません。チタンイオン(Ti4+)は、チタン鉄鉱などの鉱物に含まれます。
④【誤】
カリウムイオン(K+)とナトリウムイオン(Na+)は、アルカリ長石や雲母などの鉱物に含まれるアルカリ金属イオンであり、かんらん石の主成分ではありません。
問2:正解③
<問題要旨>
地震の基本的な用語と、地震の規模(マグニチュード)と断層運動の関係についての理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
ア:アスペリティは、断層面の中でも特に固着が強く、地震時に大きく滑って強い地震波を放出する領域を指します。断層のずれが始まった場所は「震源」です。
イ:計算が異なります。
②【誤】
ア:アスペリティではなく「震源」です。
イ:計算が異なります。
③【正】
ア:地震の断層のずれが始まった場所を「震源」といいます。地図上の×印は、震源の真上の地表の点である「震央」を示しますが、ずれの開始点そのものは震源です。
イ:マグニチュードが2大きくなると、断層面積とずれの量の積が1000倍になります。関東地震(M8)は、基準となる地震(M4)よりマグニチュードが4大きいです。これは、マグニチュードが2大きくなる変化が2回あったことと同じです。したがって、断層面積とずれの量の積は、1000×1000=1,000,000倍になります。
M4の地震:断層面積 1km2、ずれの量 3cm=0.03m
M8の関東地震:断層面積 140km×70km=9800km2
ずれの量をx mとすると、
(9800km2×x m) = 1,000,000×(1km2×0.03 m)
9800×x=30000
x=30000/9800≈3.06 m
したがって、ずれの量は約3mとなります。
④【誤】
イ:計算結果が異なります。ずれの量は約3mです。
問3:正解④
<問題要旨>
線状降水帯を構成する雲の種類と、気象レーダーの観測データ(ある時刻の雨量と積算雨量)の解釈を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
ウ:線状降水帯は、数十分程度の寿命を持つ発達した「積乱雲」が次々と発生・発達することで形成されます。高積雲は中層雲であり、強い雨を降らせることはありません。
②【誤】
ウ:「積乱雲」が適切です。
③【誤】
エ:右図の3時間積算雨量分布を見ると、領域Aよりも領域Bの方が積算雨量がはるかに多くなっています(領域Bは100mmを超える濃い灰色)。積算雨量が多いということは、それだけ多くの発達した積乱雲が通過したことを意味します。
④【正】
ウ:線状降水帯は、強い雨を降らせる発達した「積乱雲」が、風上側で次々と発生し、ベルトコンベアのように同じ場所を通過していく現象です。
エ:右図の3時間積算雨量の分布を見ると、領域Bは積算雨量が100mmを超えている一方、領域Aは50mm程度です。これは、領域Bの方により多くの発達した積乱雲が通過したことを示しています。
問4:正解②
<問題要旨>
地層の年代決定に用いられる化石(示準化石)の名称と、その化石が持つべき条件についての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
示準化石は、地層の年代を特定するために用いられるため、その生物の生存期間は短い必要があります。生存期間が長いと、その化石が含まれる地層の年代を絞り込むことができないためです。
②【正】
遠く離れた地域の地層の年代を比較(対比)するために有効な化石を「示準化石」といいます。示準化石の条件は、①広い地域に分布していること、②生存期間が短いこと、③個体数が多いこと、などが挙げられます。三葉虫やアンモナイトは、これらの条件を満たす代表的な示準化石です。
③【誤】
「示相化石」は、地層が堆積した当時の環境(気候や水深など)を示す化石です。サンゴやシジミなどが代表例です。示相化石となる生物は、特定の環境で長期間にわたって生息することが多いため、年代決定には不向きです。
④【誤】
示相化石は、年代決定ではなく、堆積環境の推定に用いられます。
問5:正解③
<問題要旨>
ハッブル・ルメートルの法則を用いた銀河までの距離計算と、距離測定に用いられる標準光源(標準的な明るさの天体)に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
オ:ハッブル・ルメートルの法則 (v=H0×d) を用いて距離(d)を計算します。ここで、vは後退速度、H0はハッブル定数です。
d=v/H0=7000 km/s / 70 km/s/メガパーセク = 100 メガパーセク
したがって、オに入る数値は100です。
②【誤】
オ:計算結果が異なります。
カ:「超巨星」は明るい星ですが、その明るさ(絶対等級)にはばらつきがあるため、正確な距離測定の基準としては使えません。
③【正】
オ:計算の通り、距離は約100メガパーセクです。
カ:遠方銀河の距離測定に用いられる「標準光源」として、「Ia型超新星」が知られています。これは、白色矮星が起こす爆発現象で、最大光度が常にほぼ一定であるため、見かけの明るさを測定することで、その超新星が属する銀河までの距離を非常に精度良く求めることができます。
④【誤】
カ:「超巨星」は標準光源としては不適切です。
第2問
問1:正解①
<問題要旨>
ジオイドの凹凸分布図を解釈し、それがマントル内の密度構造とどのように関連しているかを理解する問題です。
<選択肢>
①【正】
ジオイドは地球の重力が等しい面であり、その凹凸は地下の質量分布を反映します。質量が大きい(密度が高い)場所では重力が強くなり、ジオイドは地球楕円体より高くなります(正の異常)。逆に質量が小さい(密度が低い)場所ではジオイドは低くなります(負の異常)。
問題文に「領域Bのジオイドは、マントル深部に沈み込んだ冷たく重い海洋プレートを反映している」とあるため、領域Bは正の異常です。図を見ると領域Bは実線で囲まれており、これが正の値を示します。
一方、インド半島の南にある領域Aは破線で囲まれています。これは負の異常を示し、マントル内の高温で密度の低い物質の存在が示唆されています。このインド洋のジオイドのへこみは「インディアンオーシャン・ジオイドロー」として知られています。
したがって、Aは大きな負の値、Bは大きな正の値を持つ選択肢が適切です。
②【誤】
ジオイドの凹凸は最大で100m程度に達します。1m程度の値は小さすぎます。
③【誤】
AとBの正負が逆です。Aは負、Bは正の異常です。
④【誤】
Aは負の異常であるため、正の値となっているこの選択肢は誤りです。
問2:正解④
<問題要旨>
地下の温度分布のグラフから地温勾配を読み取り、地殻熱流量を比較する問題です。
<選択肢>
①【誤】
計算結果が異なります。
②【誤】
計算結果が異なります。
③【誤】
グラフから、地点aの方が地点bよりも同じ深さでの温度上昇が急であることがわかります。地温勾配が異なるため、地殻熱流量も同じではありません。
④【正】
地殻熱流量は、熱伝導率と地温勾配(深さによる温度変化の割合)の積で表されます。問題文より熱伝導率は両地点で同じなので、地殻熱流量の比は地温勾配の比に等しくなります。
グラフから、それぞれの地温勾配を求めます。
・地点a:例えば、深さ100mで温度12.5℃、深さ200mで温度17.5℃です。
地温勾配a = (17.5−12.5)℃/(200−100)m=5℃/100m=0.05℃/m
・地点b:例えば、深さ100mで温度15℃、深さ300mで温度20℃です。
地温勾配b = (20−15)℃/(300−100)m=5℃/200m=0.025℃/m
地点aと地点bの地殻熱流量の比は、地温勾配の比に等しいので、
比 = (地温勾配a) / (地温勾配b) = 0.05/0.025=2
よって、地点aの地殻熱流量は地点bの2倍です。
⑤【誤】
計算結果が異なります。
問3:正解①
<問題要旨>
P波の性質(縦波)を理解し、震源と観測点の位置関係から地震計に記録される初期の揺れ(初動)の向きを判断する問題です。
<選択肢>
①【正】
P波は縦波であり、波の進行方向と平行に媒質(地面)が振動します。地震波は震源から観測点に向かって伝わります。
図3から、震源は観測点の「西側」で、かつ「地下」にあります。したがって、P波は観測点に対して「西の地下」から「東の地上」に向かって進んできます。
この進行方向を3つの成分に分解すると、
・上下方向:地下から地上へ向かうので「上」向き。
・東西方向:西から東へ向かうので「東」向き。
・南北方向:震央と観測点は同じ緯度にあるため、南北方向の成分はほとんどありません。
したがって、初動は「上」・「北でも南でもない」・「東」となります。これに合致する記録は①です。
②【誤】
東西方向の初動が「西」向きになっており、誤りです。
③【誤】
上下方向の初動が「下」向きになっており、誤りです。
④【誤】
上下方向の初動が「下」向きになっており、誤りです。
問4:正解③
<問題要旨>
海洋底拡大説と地磁気逆転の歴史に基づいて、海嶺軸付近に形成される磁気異常の縞模様を予測する問題です。
<選択肢>
①【誤】
縞模様の幅が、地磁気逆転の歴史(図4)と整合しません。
②【誤】
現在(海嶺軸)は正磁極期なので、地磁気が強め合う正の異常(黒色)になるはずです。この選択肢は中央が灰色(負の異常)なので誤りです。
③【正】
海嶺軸では現在も新しい海洋底が作られているため、現在の地磁気の向き(正磁極)が記録されます。地磁気の測定では、現在の地球磁場にこの記録が加わるため、磁気が相対的に強い「正の異常」となります。したがって、海嶺軸の中心は黒色になります。
海嶺から離れるにつれて、過去に形成された海洋底になります。その岩石に記録された地磁気の向きが、逆磁極期のものであれば「負の異常」(灰色)、正磁極期のものであれば「正の異常」(黒色)となります。
図4の地磁気逆転の歴史を見ると、現在から約90万年前までは正磁極期(幅が広い)、その前は約170万年前まで逆磁極期(幅が広い)、さらにその前は約190万年前まで正磁極期(幅が狭い)となっています。
この正(広)・逆(広)・正(狭)…という時間的なパターンが、海嶺軸から離れるにつれて、黒(広)・灰(広)・黒(狭)…という空間的な縞模様のパターンとして現れます。選択肢③の縞模様の幅のパターンは、この地磁気逆転の歴史とよく一致しています。
④【誤】
海嶺軸の中心が灰色(負の異常)なので誤りです。
第3問
問1:正解③
<問題要旨>
地質図(ルートマップ)に示された走向・傾斜のデータから地質構造を読み取り、地層の重なり順を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
地質構造は背斜ですが、最上位(最も新しい)の地層はCです。
②【誤】
地層Bは背斜の軸部に位置するため、最も古い地層となります。
③【正】
・地質構造の判断:ルートマップを見ると、地層Bを中央の軸として、その西側の地層(地層A)は西に、東側の地層(地層A、C)は東に傾斜しています。このように、地層が中央の軸から外側に向かって傾斜する構造を「背斜」と呼びます。
・地層の上下関係の判断:背斜構造では、その中心(軸部)に最も古い地層(最下位の地層)が露出します。このマップでは地層Bが中心にあるため、地層Bが最も古く、そこから外側に向かって地層A、地層Cの順に新しくなります。したがって、地層の重なり順は古い方から B → A → C となります。
・最上位の地層の判断:「最上位の地層」とは、最も新しい地層を指します。したがって、最も新しい地層は地層Cです。
以上のことから、地質構造は「背斜」、最上位の地層は「地層C」となり、③が正しい組み合わせです。
④【誤】
地質構造は、地層が中心に向かって傾く「向斜」ではないため誤りです。
⑤【誤】
地質構造は向斜ではないため誤りです。
⑥【誤】
地質構造は向斜ではないため誤りです。
問2:正解③
<問題要旨>
化石の写真からその名称を同定し、それが示す地質時代を答える問題です。示準化石に関する知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
化石の名称が異なります。また、トリゴニア(三角貝)は中生代の示準化石ですが、写真の化石とは特徴が異なります。
②【誤】
化石の名称および地質時代が異なります。
③【正】
写真の化石は、大きく厚い殻と、同心円状の粗い成長線が特徴的な二枚貝です。これは中生代、特に白亜紀に繁栄したイノセラムスの特徴と一致します。イノセラムスは中生代の示準化石として重要です。
④【誤】
イノセラムスが示す地質時代は中生代です。
⑤【誤】
化石の名称が異なります。ビカリアは新生代の巻貝の化石です。
⑥【誤】
化石の名称が異なります。
問3:正解③
<問題要旨>
堆積岩(礫岩)に含まれる礫の種類から、その供給源となった後背地の地質・テクトニクス環境を推定する問題です。
<選択肢>
①【誤】
先カンブリア時代の安定地塊は、主に古い花こう岩や片麻岩などの深成岩・変成岩で構成されます。写真の岩石の組み合わせとは異なります。
②【誤】
火山岩や火山砕屑岩類からなる地域からは、写真cのような火山岩の礫は供給されますが、写真bの放散虫化石岩(チャート)や写真dのフズリナ石灰岩といった海洋性の堆積岩は供給されにくいです。
③【正】
写真に示された4種類の岩石は、以下のような特徴を持ちます。
a: 砂岩(砕屑性堆積岩)
b: 放散虫化石岩(遠洋の深海底で堆積したチャート)
c: かんらん石斑晶を含む火山岩(海洋地殻を構成する玄武岩など)
d: フズリナ石灰岩(古生代の暖かい浅海にできたサンゴ礁などの上に堆積)
このような、海洋プレート上で形成された多様な時代の多様な岩石(玄武岩、チャート、石灰岩など)が、陸源の砂岩などと混じり合って存在するのは、海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む際に、その一部が剥ぎ取られて大陸側に付け加わる「付加体」と呼ばれる地質体の特徴です。したがって、供給源は付加体の分布地域と考えられます。
④【誤】
深成岩が広く露出した地域からは、花こう岩や閃緑岩などの礫が供給されます。写真の岩石の組み合わせとは異なります。
問4:正解⑧
<問題要旨>
日本列島に見られる広域変成帯(対の変成帯)の配置と、それぞれの変成帯を特徴づける変成岩の名称、組織を理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①~④【誤】
低温高圧型変成帯は領域Bです。
⑤~⑧【正・誤の判断】
・分布領域:日本列島のような沈み込み帯では、海溝側に低温高圧型変成帯、大陸(火山フロント)側に高温低圧型変成帯が対になって分布します。図4では、領域Bが海溝側(太平洋側)に位置するため、こちらが低温高圧型変成帯です。領域Aは大陸側なので高温低圧型です。
・変成岩の名称:低温高圧型変成作用では、圧力が卓越するため、鉱物が一定方向に配列した「片理(へんり)」が発達した結晶片岩(片岩)が主に形成されます。一方、高温低圧型では、温度の影響が強く、粗粒で縞模様が特徴的な片麻岩が形成されます。したがって、低温高圧型変成帯の岩石は片岩です。
・偏光顕微鏡写真:写真Xは、鉱物が比較的粗粒で、明瞭な縞状構造(片麻状組織)が見られます。これは片麻岩の特徴です。写真Yは、鉱物が細粒で、一方向に強く引き伸ばされたような明瞭な層状構造(片理)が見られます。これは結晶片岩の特徴です。
・結論:低温高圧型変成帯は、「領域B」に分布し、代表的な岩石は「片岩」で、その組織は写真「Y」で示されるものです。これら全てが一致するのは選択肢⑧です。
問5:正解①
<問題要旨>
マントルにおけるマグマの生成メカニズムである「減圧融解」と「加水融解(フラックス融解)」についての基本的な理解を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
a: 正。マントル対流によって高温のマントル物質が上昇すると、圧力は低下します。岩石の融解温度は圧力に依存し、圧力が低いほど融解温度も低くなります。そのため、温度を保ったまま圧力が低下すると、岩石が融解を開始する条件(ソリダス線を超える)に達し、部分的に融解してマグマが生成されます。これを減圧融解といい、中央海嶺やホットスポットでのマグマ生成の主要なメカニズムです。
b: 正。マントルを構成するかんらん岩などに水が加わると、鉱物間の結合を弱める働きをし、岩石全体の融解開始温度が大幅に低下します。これにより、温度や圧力が変わらなくてもマグマが生成されやすくなります。これを加水融解(フラックス融解)といい、沈み込み帯でのマグマ生成の主要なメカニズムです。
②【誤】文bも正しいです。
③【誤】文aも正しいです。
④【誤】両方の文とも正しいです。
問6:正解⑤
<問題要旨>
火山の噴火様式と、それを支配するマグマの性質(粘性、SiO₂含有量、揮発性成分量)との関係を問う問題です。
<選択肢>
①~④、⑥【誤】
図の噴火様式は、上から下へ(アイスランド式→プリニー式)と、穏やかな噴火から爆発的な噴火へと変化しています。この変化はマグマの性質によって決まります。
・マグマの粘性:穏やかな噴火は、マグマの粘性が低く(サラサラで)、ガスが抜けやすいために起こります。爆発的な噴火は、粘性が高く(ネバネバで)、ガスが抜けずに内部に溜め込まれ、圧力が一気に解放されることで起こります。よって、矢印の方向(下へ)に粘性は「高くなる」。
・SiO₂の割合:マグマの粘性は、主にケイ酸(SiO₂)の割合によって決まります。SiO₂の割合が低い玄武岩質マグマは粘性が低く、割合が高い流紋岩質マグマは粘性が高くなります。よって、矢印の方向にSiO₂の割合は「大きくなる」。
・揮発性成分の割合:噴火の爆発力を生むのは、マグマに含まれる水などの揮発性成分です。これが減圧によって気化し、体積が急膨張することで爆発的な噴火が起こります。プリニー式のような大規模な爆発的噴火は、揮発性成分を多く含んだ粘性の高いマグマで起こります。よって、矢印の方向に揮発性成分の割合は「大きくなる」。
これら3つの条件(高くなる、大きくなる、大きくなる)が揃っているのは選択肢⑤です。
問7:正解③
<問題要旨>
ボーリング調査で得られた柱状図から、最終氷期以降の海水準変動と堆積環境の変化を読み解く問題です。
<選択肢>
①【誤】
砂層は、浅い海の貝化石を含み、7000年前の火山灰層Aより新しい時代に堆積しています。最終氷期(最寒冷期は約2万年前)は海水準が最も低下した時期であり、この場所は陸地であったと考えられます。砂層は氷期後の海面上昇(縄文海進)によって形成された海成層です。
②【誤】
火山灰層A(7000年前)は、浅い海の貝化石を含む泥層の中に挟まれています。したがって、火山灰は海中に降下して堆積したと考えられます。
③【正】
火山灰層Bの堆積年代は29000年前です。縄文海進は最終氷期が終わった後、約7000年前にピークを迎えた温暖化に伴う海面上昇期を指します。29000年前は縄文海進よりもはるかに前の時代(最終氷期の中)にあたります。したがって、この記述は正しいです。
④【誤】
下部の礫層(陸成層)の上に泥層(海成層)が重なっていることは、海水準が上昇して陸地が海に覆われたこと、すなわち「海進」があったことを示します。「海退」(海水準の低下)ではありません。
第4問
問1:正解③
<問題要旨>
火星と地球の平均気温の高度分布図を比較し、両惑星の大気構造の違いを正しく説明した文を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
火星の表面の平均気温は、図1の高度0kmを見ると約210K(約-63℃)です。これは水の融点(273K, 0℃)よりもはるかに低いため、水のほとんどは液体ではなく、氷(固体)や水蒸気(気体)として存在します。
②【誤】
地球の下層(対流圏)の気温が高いのは、太陽放射によって温められた地表面からの熱(赤外線)を、水蒸気や二酸化炭素などの温室効果ガスが吸収するためです。オゾン層は成層圏にあり、紫外線を吸収してその高度の気温を上昇させます。
③【正】
気温減率とは、高度が上がるにつれて気温が下がる割合のことです。図1を見ると、高度0kmから10kmまでの間で、地球の気温は約290Kから220Kまで約70K低下しているのに対し、火星の気温は約210Kから200Kまで約10Kしか低下していません。したがって、地球の対流圏の気温減率は火星の同高度の気温減率より大きいです。
④【誤】
地球の成層圏(高度約10km~50km)で気温が高度とともに上昇するのは、オゾン層が太陽からの紫外線を吸収して大気を加熱するためです。水蒸気は主に対流圏に存在します。
問2:正解②
<問題要旨>
火星大気の運動(地衡風)に関する文章の空欄を補充する問題です。地衡風が吹く原理と、等圧面高度分布図から風向を判断する知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
イ:風向の判断が誤りです。
②【正】
ア:地衡風は、気圧傾度力(気圧の高い方から低い方へ働く力)と、惑星の自転によって生じる見かけの力である「コリオリの力(転向力)」が釣り合うことで吹く風です。火星も地球とほぼ同じ周期・向きで自転しているため、コリオリの力が働きます。
イ:図2は北半球の等圧面の高度分布を示しており、等高線は等圧線と同じように考えられます。気圧傾度力は高度が高い方(南側)から低い方(北側)へ向かって働きます。北半球では、コリオリの力は風の進行方向に対して右向きに働きます。気圧傾度力とコリオリの力が釣り合うためには、風は等圧線に平行に、高度が高い方を右手に見るように吹きます。したがって、点Aでは西から東へ向かう「西風」が吹いていると判断できます。
③【誤】
ア:地衡風の釣り合いに関わる力はコリオリの力です。遠心力ではありません。
④【誤】
ア:コリオリの力が適切です。
問3:正解④
<問題要旨>
赤道上空の成層圏における東西風の周期的な変動(QBO)に関する図を解釈する問題です。
<選択肢>
①【誤】
ウ:周期の読み取りが誤りです。
②【誤】
ウ:周期の読み取りが誤りです。エ:高度の変化の読み取りが誤りです。
③【誤】
エ:高度の変化の読み取りが誤りです。
④【正】
ウ:図3の高度25km付近に注目すると、東風(E、灰色)と西風(W、白色)が交互に現れています。例えば、1954年初頭に東風のピークがあり、次の東風のピークは1956年初頭に見られます。その周期は約2年(24ヶ月)です。この現象は「準2年周期振動(Quasi-Biennial Oscillation, QBO)」と呼ばれています。
エ:図を見ると、例えば1955年に見られる西風(W)の領域は、時間とともに高度が下がってきていることがわかります。同様に、東風(E)の領域も、時間とともに徐々に高度が「下がる」傾向が見られます。
問4:正解④
<問題要旨>
図で示された地球表層における炭素循環のデータを用いて、各リザーバー(貯蔵庫)の炭素存在量の比較と、大気中の炭素の平均滞留時間を計算する問題です。
<選択肢>
①【誤】
両方の計算が誤りです。
②【誤】
カ:平均滞留時間の計算が誤りです。
③【誤】
オ:存在量の比の計算が誤りです。
④【正】
オ:図4の括弧内の数値は存在量(百億トン)を示しています。
・海洋の炭素存在量:3600
・大気の炭素存在量:60
海洋の炭素存在量は、大気中の存在量の何倍かを計算すると、
3600/60=60 倍となります。
カ:平均滞留時間は、「存在量」を「(出ていく量 または 入ってくる量)の合計」で割ることで求められます。
・大気中の炭素存在量:60
・大気から出ていく量(移動量):陸上に吸収される量(12)+ 海洋に吸収される量(8) = 20
・平均滞留時間 = 存在量 / 移動量 = 60/20=3 年となります。
問5:正解③
<問題要旨>
太陽、地球、月の位置関係と、潮の干満の大きさ(大潮・小潮)の関係を理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
位置関係と潮の名称の組み合わせが逆です。
②【誤】
位置関係と潮の名称の組み合わせが逆です。
③【正】
潮の干満を引き起こす起潮力は、主に月の引力によって生じますが、太陽の引力も影響します。
・大潮:月と太陽が地球に対して一直線に並ぶとき(朔:新月、望:満月)、月と太陽の起潮力が重なり合って強められ、干満の差が最も大きくなります。図5では、a(新月)とc(満月)の位置がこれにあたります。
・小潮:月と太陽が地球から見て直角の方向に位置するとき(上弦の月、下弦の月)、月と太陽の起潮力が互いに打ち消し合うため、干満の差が最も小さくなります。図5では、b(下弦の月)とd(上弦の月)の位置がこれにあたります。
したがって、大潮の時期はaとc、小潮の時期はbとdとなります。
④【誤】
大潮と小潮の組み合わせが逆です。
第5問
問1:正解①
<問題要旨>
ハビタブルゾーンにある惑星の公転周期が、主星の種類によってどう変わるかを、物理法則に基づいて考察する問題です。
<選択肢>
①【正】
(II)について:ケプラーの第3法則は、「惑星の公転周期の2乗は、軌道長半径の3乗に比例する」というものですが、より厳密には、その比例定数は中心天体(主星)の質量に依存します。したがって、アには「主星と惑星の質量」が入ります(惑星の質量は主星に比べて通常無視できるほど小さいので、実質的には主星の質量に依存します)。
(I)について:ハビタブルゾーンとは、惑星の表面で水が液体として存在できる温度になる、主星からの距離の範囲です。M型星はG型星(太陽など)に比べて、光度が低く暗い星です。したがって、同じ温度になるためには、M型星のハビタブルゾーンはG型星の場合よりも主星にずっと近い位置になります。つまり、主星との平均距離は「短く」なります。イには「短く」が入ります。
②【誤】
イ:M型星は暗いため、ハビタブルゾーンの距離はG型星より「短く」なります。
③【誤】
ア:ケプラーの法則は、主星の元素組成ではなく質量に関係します。
④【誤】
ア、イともに誤りです。
問2:正解④
<問題要旨>
恒星の表面温度と放射エネルギーが最大になる波長の関係(ウィーンの変位則)、および恒星フレアで発生する現象に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
すべての空欄が誤りです。
②【誤】
ウが誤りです。
③【誤】
エ、オが誤りです。
④【正】
ウ:ウィーンの変位則によれば、黒体放射のエネルギーが最大になる波長は、その表面温度に反比例します。M型星は表面温度が3300K程度と、太陽(約6000K)より低温です。温度が低いほど、放射エネルギーが最大になる波長は長波長側にずれます。太陽が可視光で最も輝くのに対し、M型星はそれより波長の長い「赤外線」で最も多くのエネルギーを放射します。したがって、観測には赤外線が適しています。
エ・オ:フレアは、恒星の磁場活動によって蓄えられたエネルギーが爆発的に解放される現象で、コロナの一部などが数百万~数千万Kという「高温」にまで加熱されます。このような高温のプラズマからは、X線や紫外線といった非常にエネルギーの高い(波長の短い)電磁波が強く放射されます。
問3:正解①
<問題要旨>
恒星の質量、数、寿命の関係を理解し、太陽近傍の恒星の分布図を解釈する問題です。
<選択肢>
①【正】
カ・キ:恒星の性質として、一般に質量が小さい恒星ほど、誕生する数は「多く」、核融合反応が穏やかに進むため寿命は「長い」という傾向があります。M型星は太陽(G型星)よりもはるかに小質量なので、数も多く、寿命も長いです。
ク:以上のことから、M型星はG型星よりも宇宙に圧倒的に多く存在します。したがって、太陽から50光年以内という近傍の恒星をプロットした場合、数の多い図AがM型星の分布、数の少ない図BがG型星の分布を表していると判断できます。
②【誤】
ク:M型星は数が多いため、分布図はAが適切です。
③【誤】
カ、キ:小質量の恒星は「多く」て「長い」寿命を持ちます。
④【誤】
カ、キ、クすべてが誤りです。
問4:正解②
<問題要旨>
銀河系の構造(円盤部、バルジ、ハロー)と、そこに分布する恒星の種族(年齢や性質)をHR図と関連付けて理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
A、Bともに分布領域の解釈が異なります。
②【正】
HR図上の主系列星は、左上(Aの方向)ほど高温・大質量・高光度で寿命が短く、右下(Bの方向)ほど低温・小質量・低光度で寿命が長いという特徴があります。
・領域Aの主系列星:大質量で寿命が短い青い星です。このような星は、星形成が活発に行われている場所でしか見られません。銀河系では、星間ガスが豊富な「円盤部」で現在も星形成が続いています。
・領域Bの主系列星:小質量で寿命が非常に長い赤い星です。このような星は、銀河系形成の初期に生まれた古い星でも現在まで生き残っています。銀河系の「バルジ」や「ハロー」は、主に年齢の古い星々から構成されています。また、円盤部にももちろん多数存在します。
したがって、Aの星が数多く存在するのは円盤部、Bの星が数多く存在するのは円盤部・バルジ・ハローのすべてとなります。この組み合わせに合致するのが②です。
③~⑥【誤】
AとBの星が分布する領域の組み合わせが誤っています。
問5:正解②
<問題要旨>
銀河系の回転曲線について、その観測的な事実として正しいグラフを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
これは中心に質量の大部分が集中している場合の剛体回転に近いモデルで、観測事実と異なります。
②【正】
銀河系の回転速度は、中心部で急激に上昇した後、中心からかなり離れた場所でも速度が落ちずにほぼ一定の値(平坦)を保ちます。これは「銀河の回転曲線問題」として知られており、光で見える物質だけでは説明できない質量(ダークマター)の存在を示唆する重要な観測事実です。太陽の位置(中心から約2.8万光年)でも回転速度は高いままです。
③【誤】
これは中心に質量の大部分が集中している惑星系(ケプラー回転)のモデルで、外側ほど速度が遅くなります。銀河系の観測事実とは異なります。
④【誤】
太陽の位置より外側で急激に速度が落ちており、観測事実と異なります。
問6:正解①
<問題要旨>
銀河の回転曲線問題から導かれる、銀河系の質量の大部分を占める未知の物質についての知識を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
問5で見たように、銀河の回転曲線は、恒星や星間ガスなど光で観測できる物質の質量だけでは説明できません。この矛盾を解決するために、光(電磁波)では観測できないが、重力は及ぼしている未知の物質が存在すると考えられています。これを「ダークマター(暗黒物質)」と呼びます。ダークマターは銀河を包むようにハローに広く分布していると考えられており、銀河の総質量の大部分を担うとされています。
②【誤】
ボイドは、銀河がほとんど存在しない宇宙の大規模構造における巨大な空洞領域のことであり、銀河内の質量を担うものではありません。
③【誤】
暗黒星雲は、星間ガスや塵が濃く集まり、背後の星の光を隠している領域です。これらも銀河の質量の一部ですが、総質量の大半を説明することはできません。
④【誤】
銀河系中心には太陽質量の約400万倍という巨大ブラックホールが存在しますが、その質量は銀河系全体の質量(太陽の数千億~1兆倍)のごく一部にすぎず、銀河全体の回転運動を説明することはできません。