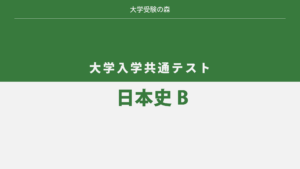解答
解説
第1問
問1:正解④
<問題要旨>
古代における国・郡の成立や行政区画の変更について、複数の史料から読み取る問題です。史料がどの時代のものか、誰が何を行ったのかを正確に把握することが求められます。
<選択肢>
①【誤】
史料1では、国造(地方豪族)が「総領」(朝廷から派遣された官人)に「請いて」(お願いして)郡を設置しています。地方豪族の話し合いだけで決定したのではなく、中央政府の承認や命令があったことを示しています。
②【誤】
史料3には、石城国が「陸奥国の石城・標葉・行方・宇太・日理と常陸国の菊多との六郡を割きて」設置されたとあります。つまり、陸奥国と常陸国という二つの国の一部を合わせて作られており、一つの国を分割したわけではありません。
③【誤】
史料1の行方郡の設置は「癸丑の年」、注釈から653年の出来事であることがわかります。大化改新は645年なので、行方郡の設置は大化改新よりも後の出来事です。
④【正】
史料3の石城国設置は「養老2年」、すなわち718年の出来事です。大宝律令は701年に制定されているため、国や郡といった行政区画の変更は、大宝律令の制定後にも行われていたことがわかります。
問2:正解③
<問題要旨>
中世の日本と東アジア諸国との関係史について、出来事の発生順を問う年代整序問題です。それぞれの出来事が何世紀頃の出来事かを大まかに把握する必要があります。
<選択肢>
Ⅰ【14世紀】
天龍寺は、足利尊氏が後醍醐天皇の霊を慰めるために建立を計画した寺です。その造営費用を得るために、元に貿易船(天龍寺船)が派遣されたのは1342年のことです。
Ⅱ【13世紀】
三別抄は、元に服属した高麗の政府に抵抗した軍事組織です。彼らが反乱を起こし、日本に援軍を求めてきたのは、元の日本侵攻(元寇)直前の1270年から1273年にかけてのことです。
Ⅲ【15世紀】
尚巴志が、沖縄本島にあった北山・中山・南山の三つの勢力(三山)を統一し、琉球王国を建国したのは1429年のことです。
したがって、古い順に並べるとⅡ(13世紀)→Ⅰ(14世紀)→Ⅲ(15世紀)となります。
問3:正解②
<問題要旨>
古代・中世における「関」や「境界」の役割、そして境界の外側に対する人々の意識について、説明文を正しく読み解く問題です。
<選択肢>
X【正】
先生の説明文に、逢坂の関について「国家の非常時に関を封鎖し、都からの交通路を遮断している」とあり、その例として「平城太上天皇の変(薬子の変)」が挙げられています。これは、反乱などの際に、関係者が都から地方へ逃亡したり、地方の兵力を都へ集結させたりするのを防ぐ目的があったことを示唆しています。
Y【誤】
先生の説明文に、中世の日本の東端とされた外浜(津軽半島)について、「安藤(安東)氏が…この境界地域の管轄を任されていて、彼らを通じて、昆布や、アザラシの毛皮などの北方産物が交易されていた」とあります。境界の外側の産物が交易されていたことから、それらが「忌避された」という記述は誤りです。
問4:正解①
<問題要旨>
江戸時代の国絵図の目的と、伊能忠敬による地図作成の背景に関する知識を問う空欄補充問題です。
<選択肢>
ア【各地の村高】
地図3の拡大図には「酒寄村 八百八十一石余」とあり、村名とともに石高(村高)が記されています。江戸幕府が諸藩に国絵図や郷帳を提出させた主な目的は、全国の石高を把握し、それに基づいて軍役などを課すことで、全国支配を確固たるものにすることでした。したがって「各地の村高」が適切です。
イ【幕府が東蝦夷地を直轄地としたこと】
伊能忠敬が蝦夷地の測量を始めたのは1800年です。18世紀末からロシア船が日本近海に来航するようになり、幕府は北方への警戒を強めていました。その一環として、1799年に松前藩から東蝦夷地を取り上げ、幕府の直接支配地(天領)としました。この北方防備の必要性から、正確な地図の作成が急務となったのです。「ロシアとの間で国境が定められた」のは、日露和親条約(1854年)や樺太・千島交換条約(1875年)であり、時代が異なります。
以上のことから、正しい組合せは①となります。
問5:正解②
<問題要旨>
近代日本の測量や海図作成に関連する歴史的事件を特定する問題です。
<選択肢>
X【a 江華島事件】
日本の軍艦が朝鮮沿岸の無許可測量を強行し、挑発行為を行った結果、朝鮮側と武力衝突に至った事件は、1875年の江華島事件です。この事件をきっかけに、日本は日朝修好条規を締結し、朝鮮を開国させました。
Y【d 第一次世界大戦】
第一次世界大戦(1914~1918年)中、日本は連合国の一員として参戦しましたが、主戦場がヨーロッパであったため、直接的な被害はほとんどありませんでした。むしろ、ヨーロッパ諸国が戦争で生産力を低下させたため、日本製品の輸出が急増し、海運業などが空前の好景気(大戦景気)を迎えました。これにより、船舶の安全な航行に不可欠な海図や水路図誌の需要も高まりました。
以上のことから、正しい組合せは②となります。
問6:正解③
<問題要旨>
古代から近代にかけての地図の役割や、それに対する人々の認識の変化について、会話文全体の内容を踏まえて総合的に判断する問題です。
<選択肢>
a【誤】
問1の史料2に、天武天皇の時代(7世紀後半)に「諸国の堺を定めしむ」とあるように、古代律令制下では国境は明確に定められていました。したがって、「国と国との境は確定されなかった」という記述は誤りです。
b【正】
会話文Aで取り上げられた地図2には、「羅刹国」や「雁道」といった想像上の国が描かれています。このように、中世の地図には、当時の人々の世界観や想像力が反映されたものも存在したことがわかります。
c【正】
会話文Bで、国絵図は幕府が「各地の村高を確認していた」ものだと述べられています。これは、幕府が全国の土地と人民、生産力を把握することで、その支配の正当性と実態を内外に示すという目的があったことを意味します。
d【誤】
会話文Bの最後で、伊能忠敬が作成した地図が「幕末に日本に来航した外国船が日本近海を測量して海図を作製した際にも利用された」とあります。これは、近世以前の日本の地図が、近代においてもその正確性を高く評価され、活用されていたことを示しています。したがって、「顧みられなくなった」という記述は誤りです。
正しい文はbとcなので、その組合せである③が正解です。
第2問
問1:正解②
<問題要旨>
陰陽道が成立する以前の、縄文時代から古墳時代にかけての日本列島の信仰に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
縄文時代に作られた土偶は、乳房や妊娠した腹部が表現されているものが多く、一般的に女性をかたどったものと考えられています。豊かな収穫や子孫繁栄を祈るためのものとされています。
②【正】
3世紀の日本の様子を記した中国の歴史書『魏志』倭人伝には、邪馬台国の女王・卑弥呼が「鬼道(きどう)」という呪術を用いて人々を統治していたと記されています。これは、彼女が司祭者的な性格を持つシャーマンであったことを示しています。
③【誤】
宗像大社が神体として祀っているのは、福岡県の沖ノ島です。この島からは、4世紀後半から9世紀末にかけての古代祭祀の遺物が多数発見されており、「海の正倉院」とも呼ばれています。壱岐島にも古墳時代の遺跡はありますが、宗像大社の信仰の中心ではありません。
④【誤】
鹿の骨を焼いて、そのひび割れの形で吉凶を占う行為は「太占(ふとまに)」といいます。「祓(はらえ)」は、罪や穢(けがれ)を神への祈りや儀式によって取り除くことです。
問2:正解③
<問題要旨>
律令制度における官制(役所の仕組み)と、平安時代の令外官(りょうげのかん)に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
X【b 中務省】
律令制の二官八省のうち、天皇に最も近い位置で、詔勅(天皇の命令書)の作成など、朝廷の機密事務を司ったのは八省の筆頭である中務省です。陰陽寮は、この中務省に所属する機関の一つでした。
Y【c 蔵人所】
蔵人所(くろうどどころ)は、嵯峨天皇の時代に設置された令外官です。天皇の秘書官として、機密文書の管理や天皇への奏上・伝達などを担当しました。陰陽師であった安倍晴明は、その専門知識を活かして蔵人所でも活動し、天皇や貴族から厚い信頼を得ていたとされています。
以上のことから、正しい組合せは③となります。
問3:正解④
<問題要旨>
政争に敗れ、死後に怨霊として恐れられた歴史上の人物に関する出来事を、年代順に並べる問題です。それぞれの出来事が誰に関するもので、いつ起きたのかを特定する必要があります。
<選択肢>
Ⅰ【10世紀初頭】
藤原氏を外戚としない宇多天皇・醍醐天皇に重用され右大臣にまで昇進しましたが、藤原時平らの讒言(ざんげん)によって大宰府に左遷された人物は、菅原道真です。彼が左遷されたのは901年(昌泰の変)のことです。
Ⅱ【8世紀前半】
左大臣として権勢を振るいましたが、皇族出身であったため藤原氏と対立し、藤原四子の策謀によって謀反の罪を着せられ、自殺に追い込まれた人物は長屋王です。この事件は729年(長屋王の変)に起こりました。
Ⅲ【8世紀後半】
桓武天皇の弟で皇太子でしたが、長岡京造営の責任者であった藤原種継の暗殺事件に連座したとされ、廃太子となり淡路国へ流される途中で憤死した人物は早良親王です。この事件は785年に起こりました。
したがって、古い順に並べるとⅡ(729年)→Ⅲ(785年)→Ⅰ(901年)となります。
問4:正解①
<問題要旨>
平安時代の貴族社会において、「暦」が政治や日常生活にどのような影響を与えていたかを、史料から読み解く問題です。
<選択肢>
X【正】
史料1には、新たに任命された国司が、任国へ出発する日時、現地の役所(館)に入る日時、前任者との業務引き継ぎ(交替政)を始める日時などを、すべて陰陽家に吉日を選ばせていたことが記されています。これは、地方における政治・行政の運営に暦の吉凶が深く関わっていたことを示しています。
Y【正】
史料2は、摂政・関白を務めた藤原師輔が子孫に残した家訓です。毎朝、暦を見てその日の吉凶を確認することや、髪をとかしたり入浴したりする日も吉日を選ぶこと、年間の行事を暦に書き込んで準備することなどが記されています。これは、貴族の日常生活の細部に至るまで、暦注(暦に書かれた吉凶などの注記)が影響を及ぼしていたことを示しています。
問5:正解①
<問題要旨>
古代の陰陽道や貴族の生活について、問題文全体と史料から読み取れる内容を総合的に判断し、適切な説明を選ぶ問題です。
<選択肢>
a【正】
文章Bに「作成された具注暦は、まず天皇に奏上され、天皇から…各官司などに下賜され」たとあります。暦の作成と頒布を国家、特に天皇が管理することは、時間そのものを支配するという権威の象徴であり、国家統治の重要な要素でした。
b【誤】
文章Aによれば地方の役所(大宰府など)にも陰陽師は置かれましたが、文章Bでは暦は中央の陰陽寮で作成され、地方ではそれを「書き写して備えられた」とあります。地方が独自に暦を作成していたわけではありません。
c【正】
史料2(九条殿遺誡)に「年中の行事は、ほぼ件の暦に注し付け、日ごとに視るの次に先ずその事を知り、兼ねてもって用意せよ」とあります。これは、貴族が具注暦を日記兼スケジュール帳のように用い、年中行事を書き込んで計画的に準備を進めていたことを示しています。
d【誤】
文章Aの後半に「10世紀になると陰陽師は、天皇や貴族たち個人の要請にも応え、事の吉凶を占ったり、呪術を施したりした」とあります。物忌(ものいみ)や方違(かたたがえ)は、まさに貴族の個人的な吉凶判断に関わることであり、陰陽師の重要な仕事でした。
正しい文はaとcなので、その組合せである①が正解です。
第3問
問1:正解①
<問題要旨>
戦国時代の京都における商業活動の中心地を、考古学的調査と文献・絵画史料から探る方法について問う問題です。
<選択肢>
X【a 甕】
会話文中に「地中にはものすごい量の銭の入った容器が眠っているかも」とあります。当時、大量の銭を貯蔵するために甕(かめ)が使われることが多く、これらは埋蔵銭として発掘調査で出土します。まとまった埋蔵銭の出土は、その周辺が金融業などで栄えた商業地であった可能性を示唆します。
Y【c 見世棚】
商業活動の様子を具体的に知るためには、商品を並べて販売するための常設の棚である「見世棚(みせだな)」の存在が重要な手がかりとなります。『洛中洛外図屏風』などの絵画史料や、当時の記録から、見世棚がどこに集中していたかを調べることで、商業の中心地を特定できます。
以上のことから、正しい組合せは①となります。
問2:正解③
<問題要旨>
平安時代後期から鎌倉時代にかけて、京都およびその周辺に建立された主要な寺院の建立年代を問う、年代整序問題です。
<選択肢>
Ⅰ【11世紀後半】
法勝寺は、白河天皇が譲位して上皇となった後、1077年に建立した六勝寺の筆頭寺院です。院政期の仏教文化を象徴する寺院として知られています。
Ⅱ【11世紀前半】
法成寺は、摂関政治の最盛期を築いた藤原道長が、晩年に建立した寺院です。1020年に金堂が、1022年に無量寿院(阿弥陀堂)が建立され、極楽浄土を現世に再現しようとした壮大な寺院でした。
Ⅲ【13世紀初頭】
禅宗は鎌倉時代に本格的に日本に伝わりました。宋から臨済宗を伝えた栄西が、京都に建仁寺を建立したのは1202年のことです。これ以降、京都や鎌倉に多くの禅宗寺院が建てられるようになります。
したがって、古い順に並べるとⅡ(11世紀前半)→Ⅰ(11世紀後半)→Ⅲ(13世紀初頭)となります。
問3:正解④
<問題要旨>
室町時代後期(戦国時代)における貨幣経済の混乱を示す「撰銭(えりぜに)」について、中央の室町幕府と地方の有力大名である大内氏が出した撰銭令を比較し、その内容を正確に読み解く問題です。
<選択肢>
a【誤】
史料1(室町幕府)では「洪武銭」の使用を認めていますが、史料2(大内氏)では「洪武銭」を選んで排除する(使用を禁止する)対象としています。使用禁止の対象が一致していないため、この記述は誤りです。
b【正】
上記の通り、洪武銭に対する規制が幕府と大内氏で異なっています。これは、大内氏が幕府の法令に必ずしも従わず、自身の領国内の経済実態に合わせて独自に法令を定めていたことを示しており、この記述は正しいです。
c【誤】
もし永楽銭が京都と山口でともに問題なく「好んで受け取ってもらえ」ていたのであれば、幕府が「取引に使用しなさい」と命令したり、大内氏が「選別して排除してはならない」と禁止したりする必要はありません。わざわざ法令で流通を強制しているということは、実際には人々が良貨である永楽銭を退蔵(貯め込んで市場で使わないこと)して市中に出回らなかったり、何らかの理由で受け取りを敬遠したりして、円滑な取引が妨げられていたことを示唆しています。したがって、この記述は誤りです。
d【正】
cの解説の通り、幕府や大内氏が法令で使用を強制しなければならないほど、永楽銭は日常の決済手段として「好んで受け取ってもらえず」、その流通が滞っていたと考えられます。したがって、この記述は史料から読み取れる内容として正しいです。
正しい文はbとdなので、その組合せである④が正解です。
問4:正解④
<問題要旨>
中世の京都で花開いた文化・芸術に関する知識を問う問題です。誤っている選択肢を一つ選びます。
<選択肢>
①【正】
『鳥獣戯画』は、京都市右京区の高山寺に伝わる絵巻物で、動物を擬人化して当時の世相を風刺したものです。平安時代末期から鎌倉時代前期の作とされています。
②【正】
『愚管抄』は、鎌倉時代初期に天台座主の慈円が著した歴史書です。末法思想に基づき、「道理」という独自の歴史観で日本の歴史の推移を論じています。
③【正】
立花(りっか)は、室町時代に京都の六角堂頂法寺の僧侶であった池坊専慶によって大成されたとされます。後の華道の源流の一つとなりました。
④【誤】
『瓢鮎図(ひょうねんず)』は、室町幕府4代将軍足利義持の命により、相国寺の画僧・如拙が描いたものです。主題は禅の公案(問い)であり、画法は宋・元の影響を受けた水墨画(漢画)です。日本の伝統的な絵画様式である「大和絵」ではありません。
問5:正解①
<問題要旨>
中世の経済活動の仕組みを模式図で表し、それぞれの財貨の動き(矢印)に当てはまる適切な経済用語を選ぶ問題です。
<選択肢>
X【a 鋳造された銭】
中国大陸から日本列島への矢印は、日宋貿易や日明貿易によって大量に輸入された銅銭(宋銭、明銭)の流れを示しています。これらの輸入銭は、日本における貨幣経済の発展を大きく促進しました。
Y【c 為替】
地方の都市や荘園と、中央の京都市場との間の矢印は、遠隔地間の商取引を表しています。中世には、現金を直接輸送する危険を避けるため、手形である「為替」を利用した送金システムが発達しました。
Z【e 代銭納】
荘園から荘園領主への矢印は、年貢の納入を示しています。荘園制が変質していく中で、農民は収穫物(米や布など)の現物で年貢を納める代わりに、それを貨幣に換えて納入する「代銭納」が一般化していきました。
以上のことから、正しい組合せは①となります。
第4問
問1:正解②
<問題要旨>
江戸時代の交通網の発達の背景に関する空欄補充問題です。陸上交通と水上交通がそれぞれどのような目的で整備されたかを理解しているかが問われます。
<選択肢>
ア【a 諸大名が江戸に屋敷をかまえ国元との間を往来するようになった】
江戸幕府は、参勤交代の制度によって諸大名に江戸と領国の定期的な往来を義務付けました。これにより、大名行列が通行するための五街道などの陸上交通網が整備されました。
イ【d 年貢米や材木など大量の物資を運ぶ】
江戸や大坂などの大都市の発展に伴い、全国から大量の物資を輸送する必要が生じました。特に、年貢米などの重くてかさばる荷物を効率よく運ぶためには、船を利用する水上交通(西廻り航路、東廻り航路など)が不可欠でした。
以上のことから、正しい組合せは②となります。
問2:正解①
<問題要旨>
江戸時代の商業政策や商人組織の変遷について、年代順に並べる問題です。それぞれの出来事がどの時期(17世紀、18世紀など)に対応するかを把握する必要があります。
<選択肢>
Ⅰ【17世紀前半】
糸割符制度は、特定の商人(糸割符仲間)にポルトガル商人がもたらす中国産の生糸を一括購入させることで価格の安定を図った制度で、江戸幕府初期の1604年に始まりました。
Ⅱ【18世紀前半】
十組問屋(とくみどいや)は、江戸の主要な問屋仲間が享保年間(1716~1736年)に結成した組合です。幕府の経済政策にも協力しました。
Ⅲ【18世紀後半】
田沼意次が老中であった時代(1772~1786年)、幕府は財政収入を増やすため、商人や職人の同業組合である仲間を「株仲間」として積極的に公認し、運上・冥加といった営業税を納めさせました。また、銅座などの専売制度も強化しました。
したがって、古い順に並べるとⅠ→Ⅱ→Ⅲとなります。
問3:正解③
<問題要旨>
江戸時代後期に刊行された文化人名簿の史料を読み解き、当時の文化の担い手やその活動の実態について考察する問題です。
<選択肢>
X【誤】
史料1を見ると、「蘭学」の伊藤深造は津山藩(現在の岡山県)に、「書画鑑定」の内山林蔵は備前藩(現在の岡山県)に仕えていたことがわかります。このように、江戸に居住しながらも、関東以外の藩に仕える文化人も存在しました。したがって、「関東以外の場所に領地を有する大名には仕えることができなかった」という記述は誤りです。
Y【正】
史料1の右肩にあるジャンル名を見ると、「書」「儒」「画」といった伝統的な学問・芸術の担手だけでなく、「蘭学」という西洋の学術を研究する者も含まれていることがわかります。これは、江戸時代後期には西洋の学問・文化への関心も高まっていたことを示しています。
問4:正解①
<問題要旨>
江戸時代の日本と中国(清)との間の、漂流民送還に関する史料を読み解き、当時の両国関係の実態について考察する問題です。
<選択肢>
a【正】
史料2には、中国の役所である「厦門海防庁」や「寧波府鄞県」から「咨文(しぶん)」(公文書)が送られ、それに対して日本の「長崎奉行菅沼氏」から「回咨(かいし)」(返書)が渡されたと記されています。これにより、漂流民の送還に際して、両国の役人の間で公文書のやり取りがあったことがわかります。
b【誤】
史料2によれば、漂流民を送還する船には、中国の商人である「信公興」や、船頭の「鄭青雲」らが乗り組んでいますが、中国の役人が日本まで同行したという記述はありません。
c【正】
この事件が起きた1751年当時、日本(江戸幕府)と中国(清)との間には、国交としての正式な外交関係(国書を交換するような関係)はありませんでした。貿易は長崎の唐人屋敷を通じて、民間貿易の形で行われていました。
d【誤】
1715年に海舶互市新例(正徳新令)が出され、長崎に入港する清国船の数を年間30隻に、貿易額を銀6000貫に制限していました。したがって、「貿易額はまだ制限されていなかった」という記述は誤りです。
正しい文はaとcなので、その組合せである①が正解です。
問5:正解②
<問題要旨>
江戸時代の人々の間の様々な「結びつき」について、総合的に理解しているかを問う問題です。武士、農民、町人それぞれの社会の特徴を正しく把握する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
大名の家臣団は、主君と家臣という主従関係(御恩と奉公)によって結ばれており、必ずしも血縁関係にあるわけではありません。擬似的な家族関係と見なされることはあっても、実際の血のつながりとは異なります。
②【正】
江戸時代の村は、年貢の納入や用水路の管理などを村全体で共同で行う運命共同体でした。幕府や藩は、この村の自治的な仕組みを利用し、年貢を個人ではなく村単位で割り当てる村請制(むらうけせい)を採用しました。
③【誤】
江戸では武士と町人の居住区は基本的に分けられていましたが、文化的な交流が全くなかったわけではありません。例えば、俳諧は武士の松永貞徳や西山宗因が基礎を築きましたが、町人の井原西鶴や松尾芭蕉によって大きく発展しました。武士も町人も身分を超えて文化を享受していました。
④【誤】
寄場組合(よせばくみあい)は、天保の改革の一環として、関東地方の治安維持のために作られたもので、特定の村々を一つの組合として組織し、無宿人や博徒を取り締まらせた制度です。奉公人や出稼ぎ人の風俗を取り締まるための組合ではありません。
第5問
問1:正解④
<問題要旨>
主人公・牧野りんの生没年(1860年~1910年)の間に起こった出来事と、その関連事項を正しく結びつける問題です。
<選択肢>
X【b 下関】
牧野りんが4歳になるのは1864年です。この年、長州藩が前年に関門海峡を通過する外国船を砲撃したことへの報復として、イギリス・フランス・アメリカ・オランダの四国連合艦隊が下関の砲台を攻撃・占領しました(四国艦隊下関砲撃事件)。
Y【d 大久保利通】
牧野りんが13歳になるのは1873年です。この年、政府の組織改編に伴い、内政全般を統括する内務省が新設され、その初代長官(内務卿)に就任したのは大久保利通です。彼はこの強大な権限を背景に、殖産興業政策などを推進しました。
以上のことから、正しい組合せは④となります。
問2:正解⑤
<問題要旨>
幕末から明治にかけての服装や身なりに関する出来事を、年代順に並べる問題です。それぞれの出来事がいつ頃起こったのかを把握する必要があります。
<選択肢>
Ⅰ【1876年】
士族の反乱の一つである神風連の乱(敬神党の乱)は、1876年に熊本で起こりました。この反乱は、同年に出された廃刀令(軍人・警察官以外の帯刀を禁止)などが直接的なきっかけとなりました。
Ⅱ【1887年】
外務大臣(当時は外務大蔵)井上馨は、条約改正交渉を有利に進めるため、鹿鳴館を建設して舞踏会を開くなどの極端な欧化政策を推進しました。しかし、その交渉内容(外国人判事の任用など)が知られると国民的な反発を招き、1887年に辞任に追い込まれました。
Ⅲ【1867年】
「ええじゃないか」は、江戸時代末期の慶応3年(1867年)後半、東海地方から近畿、四国へと広がった民衆の熱狂的な乱舞です。伊勢神宮などのお札が降ってきたことをきっかけに、人々は仮装などもして踊り狂いました。
したがって、古い順に並べるとⅢ(1867年)→Ⅰ(1876年)→Ⅱ(1887年)となります。
問3:正解②
<問題要旨>
明治時代の自由民権運動家・岸田俊子の文章を読み解き、当時の女性の置かれた状況について考察する問題です。史料の読解力と、明治期の教育制度に関する知識が問われます。
<選択肢>
X【正】
史料で岸田俊子は、男性と女性の知識に差があるのは「教うると教えざるとの差い、又世に交ることの広きと狭きと」が原因であり、生まれつきの精神力に差があるわけではない、と主張しています。これは、男女間の知識の差が、教育や社会参加の機会の差によって生じているという考え方を示しています。
Y【誤】
この史料が書かれたのは1884年です。国定教科書制度が始まったのは1903年のことであり、それ以前は検定教科書が使われていました。また、小学校の義務教育が完全に無償化され、就学率が大きく向上するのは1900年の小学校令改正以降のことです。したがって、この当時にすべての女性が国定教科書で義務教育を受けていたわけではありません。
問4:正解④
<問題要旨>
架空の人物の生涯設定に含まれる歴史的な誤りを、複数の視点から指摘し、その指摘の正誤を判断する問題です。明治時代の制度や政党史に関する正確な知識が必要です。
<選択肢>
タク【誤】
屯田兵制度は、北海道の開拓と警備を目的として、1874年に始まりました。当初は旧東北諸藩の士族を募集対象としていましたが、1890年からは平民も募集対象に加えられました。設定ではりんの父は士族であり、16歳で亡くなる(1876年)前に屯田兵になったとされているため、士族が応募できた時期と一致します。「平民だけだよね」というタクさんの指摘は誤りです。
ユキ【正】
憲政党は、1898年に、自由党と進歩党が合同して結成された日本初の政党内閣(隈板内閣)の与党です。設定では、りんが20歳の時(1880年)に憲政党員の男性と結婚したことになっていますが、憲政党が結成されたのはその18年も後のことです。したがって、ユキさんの「りんが設定上で結婚した年よりも後のことだよね」という指摘は正しいです。
カイ【正】
設定で、りんがドイツに滞在していたのは21歳から8年間、つまり1881年から1889年です。この期間中の1882年から1883年にかけて、伊藤博文らが憲法調査のためにドイツやオーストリアを訪問しています。したがって、カイさんの「明治政府の要人がドイツで憲法調査を行っているよね」という指摘は正しいです。
結論として、タクさんの指摘のみが間違っているため、④が正解となります。
第6問
問1:正解④
<問題要旨>
明治から昭和戦前期にかけての教員養成機関である師範学校と、それに関連する学制の変遷についての空欄補充問題です。
<選択肢>
ア【全国画一的に】
1872年(明治5年)に公布された「学制」は、フランスの学区制をモデルとし、全国を大・中・小の学区に分け、それぞれの学区に大学校・中学校・小学校を設置するという、中央集権的で全国画一的な学校制度を目指したものでした。
イ【学校教育法】
師範学校は、戦後の学制改革の中で、1947年に公布された学校教育法によって、新制国立大学の教育学部や学芸学部に再編される形で廃止されました。六・三・三・四制の新学制を定めたのが学校教育法です。
以上のことから、正しい組合せは④となります。
問2:正解①
<問題要旨>
1896年に行われた長崎商業学校の上海への修学旅行に関する体験記を読み、当時の日中関係や上海の状況について考察する問題です。
<選択肢>
X【正】
史料では上海を「国際的繁栄の都市」と表現しています。上海は、1842年の南京条約(アヘン戦争の講和条約)によって開港し、イギリスをはじめとする欧米列強の租界が置かれ、国際的な貿易都市として発展していました。日本の安政の五か国条約(1858年)による開港よりも前のことです。
Y【正】
史料には「戦勝の結果利権を得て新設された東華紡績工場の見物」とあります。この「戦勝」とは、修学旅行の前年、1895年に終結した日清戦争を指します。下関条約で、日本は清国内での工場経営権などを獲得しており、修学旅行生はその利権の一端を目の当たりにしたことになります。また、「『東洋鬼』の罵声を浴び」たとあることから、敗戦国となった清の民衆の、日本人に対する敵愾心(てきがいしん)を体験したこともわかります。
問3:正解④
<問題要旨>
1938年(昭和13年)に行われた大阪府女子師範学校の満州・朝鮮への修学旅行の行程表から、当時の日本の対外進出の状況を読み解く問題です。
<選択肢>
①【誤】
訪問地である京城(現在のソウル)には、朝鮮統治の拠点である朝鮮総督府が置かれていました。初代総督は、1910年の韓国併合時の首相であった寺内正毅です。桂太郎は、韓国併合時の首相ではありません。
②【誤】
行程表には、新京(満州国の首都)で「新京神社」、奉天で「奉天神社」、大連で「大連神社」を訪れたと記されています。このことから、当時、満州国の主要都市にも日本の神社が建立されていたことがわかります。
③【誤】
日中戦争のきっかけとなった盧溝橋事件が起きたのは、北京郊外です。訪問地である奉天の郊外で起きたのは、満州事変のきっかけとなった柳条湖事件(1931年)です。
④【正】
日露戦争の勝利後、日本はポーツマス条約でロシアから遼東半島南部の租借権などを譲り受け、この地域を関東州と名付けました。そして、その統治と南満州鉄道の管理のために、1906年に旅順に関東都督府を設置しました(後に関東庁、関東局と改編)。旅順は訪問地の一つに含まれています。
問4:正解②
<問題要旨>
明治時代の炭鉱労働者の実態について、統計表と記録画からその過酷な労働環境や生活を読み解く問題です。
<選択肢>
a【正】
表2の「勤続年数別比率(%)」を見ると、炭鉱A~Fのいずれにおいても、「1年未満」「2年未満」「3年未満」の合計が3分の2(約67%)を超えています(例えば炭鉱Aは61+29+8=98%)。また、いずれの炭鉱でも「1年未満」の比率が最も高くなっています。これは労働者の定着率が非常に低かったことを示しています。
b【誤】
「他府県出身比率」が最も高い炭鉱D(63%)の「3年以上」の勤続年数比率は15%ですが、それより他府県出身比率が低い炭鉱F(56%)の「3年以上」の比率は21%です。このように、他府県出身者が多いほど勤続年数が短くなるという明確な相関関係は、この表からは読み取れません。
c【誤】
史料2の文章には、切羽で働く「亭主」の後から、「女房は…(中略)…ワレも滑らず…(中略)…さがり行く」とあり、妻も坑内に入って働いていたことがわかります。炭鉱内に女性が入れたことを示しており、記述は誤りです。
d【正】
史料2には、幼い子供に赤ん坊を背負わせて坑内に連れて行く理由として、他人に預けると費用がかかるからだと説明されています。その結果、子供は学校を休みがちになる(間欠長欠になる)とあり、家計の厳しさから子供の教育が犠牲になっていた状況がうかがえます。
正しい文はaとdなので、その組合せである②が正解です。
問5:正解③
<問題要旨>
1912年(明治45年)にジャパン・ツーリスト・ビューロー(現在のJTB)が設立された歴史的背景を考察する問題です。当時の日本の経済状況と国際関係を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
地方改良運動は、日露戦争後の地方の疲弊を立て直すために、内務省主導で行われた運動であり、外国人移住を目的としたものではありません。
②【誤】
ファシズムという言葉が政治的に使われるようになるのは、第一次世界大戦後のイタリアが発端であり、日露戦争(1904~1905年)の時点では適切ではありません。
③【正】
日本は日清戦争後に産業革命を本格化させましたが、機械類の輸入などがかさみ、慢性的な貿易赤字に悩まされていました。ジャパン・ツーリスト・ビューローは、外国人観光客を誘致し、彼らが日本で使う外貨を獲得することで、この国際収支の赤字を改善する目的で、鉄道院(国の機関)などの主導で設立されました。
④【誤】
民族自決の原則が国際的に提唱されたのは、第一次世界大戦後のパリ講和会議(1919年)でのアメリカ大統領ウィルソンの発言がきっかけであり、1912年時点ではまだ一般的ではありませんでした。
問6:正解②
<問題要旨>
1975年に開催された沖縄国際海洋博覧会に関する新聞の見出しから、開催決定から閉幕後に至るまでの沖縄県内の期待や葛藤、そしてその結果を読み解く問題です。
<選択肢>
a【正】
最初期の見出しは1971年3月付で、「1975年に『沖縄海洋博』」と報じています。沖縄の日本復帰が実現したのは1972年5月15日なので、博覧会の開催は、沖縄がまだアメリカの施政権下にあった時期から検討・決定されていたことがわかります。
b【誤】
上記の通り、開催の検討・決定は日本復帰前からのものです。
c【誤】
1975年7月の見出しには「景気浮揚の起爆剤に」という期待の声がある一方で、「本土の人たちの祭り」という冷めた見方もあることが記されています。また、同年9月には「観光客は増えても本土の資本が吸いあげ」という批判的な見出しが出ており、歓迎一色になったわけではないことがわかります。
d【正】
1975年9月の「本土の資本が吸いあげ」や、1976年9月の「聞こえてくる本土への恨み節」といった見出しから、博覧会による経済的利益が沖縄県民に十分還元されず、本土の企業に独占されているという不満や不信感が募っていたことがうかがえます。
正しい文はaとdなので、その組合せである②が正解です。
問7:正解④
<問題要旨>
第二次世界大戦後のアジアにおける国際関係と日本の立場について、その正誤を問う問題です。冷戦期の国際政治の枠組みを正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
X【誤】
冷戦下、西ヨーロッパではアメリカを中心とする多国間の集団安全保障組織として北大西洋条約機構(NATO)が結成されました。しかし、東アジアでは、アメリカは日本、韓国、台湾、フィリピンなどと個別に相互防衛条約を結ぶ形をとり、NATOのような多国間の共同防衛組織は結成されませんでした。東南アジアでは東南アジア条約機構(SEATO)が結成されましたが、日本は加盟していません。
Y【誤】
第1回アジア・アフリカ会議(バンドン会議)は、1955年にインドネシアのバンドンで開催されました。主催したのはインドネシア、インド、パキスタン、ビルマ(現ミャンマー)、セイロン(現スリランカ)の5か国であり、日本は招待されて参加した国の一つです。日本が主催したわけではありません。