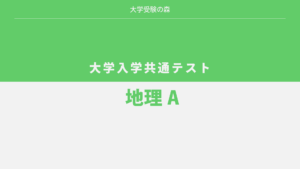解答
解説
第1問
問1:正解④
<問題要旨>
メルカトル図法の地図の特徴に関する正誤を判断する問題です。メルカトル図法がどのような特性(角度、面積、距離、方位など)を正しく表現し、何を歪めて表現するのかを理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【正】
メルカトル図法は、高緯度になるほど面積が実際よりも大きく拡大されて描かれます 。図中のaとbは同じ大きさで描かれていますが、aの方がbよりも高緯度に位置しています。したがって、実際の地球上での面積は、より低緯度にあるbの方がaよりも大きくなります 。
②【正】
メルカトル図法では、経線は平行な直線として、緯線は経線と直交する平行な直線として描かれます。したがって、緯線と経線は必ず直角に交わります 。
③【正】
地図上の任意の2点を結んだ直線が、出発点と目的地の角度を一定に保って進むことができる航路(等角コースまたは航程線)と一致するのがメルカトル図法の大きな特徴です 。このため、航海図として古くから利用されてきました。
④【誤】
地球上の2点間の最短距離は「大圏コース」と呼ばれます。図中のアは大圏コースを、イは等角コース(メルカトル図法上の直線)を表しています 。2点間の距離は、特別な場合を除き、常に大圏コースの方が等角コースよりも短くなります。したがって、「アはイよりも長い」という記述は誤りです 。
問2:正解③
<問題要旨>
地形図と風景写真の読解を通じて、地形の種類を特定する問題です。地形図から土地の起伏や特徴的な地形を読み取り、それが写真の景観と一致するか、また、どのような営力で形成された地形かを判断する能力が求められます。
<選択肢>
まず、地形の種類を判断します。図2の地形図には、山頂部に円形の凹地(火口やカルデラ)が見られます 。また、全体的に傾斜が緩やかな斜面が広がっています 。これらは火山活動によって形成された地形(火山地形)の典型的な特徴です 。したがって、文章中の空欄eは「火山」となります 。これにより、選択肢は①、③、⑤に絞られます。
次に、写真1の撮影地点を特定します 。
地点Aから矢印の方向(北西)を見ると、尾根から湿地に向かって下る方向になります。写真1は山頂を見上げる風景なので、Aではありません。
地点Bは湿地の端に位置しており、矢印の方向(北東)を見ると、湿地から緩やかな斜面を経て、円形の凹地を持つ山々を見上げる形になります 。これは写真1の風景と一致します 。
地点Cから矢印の方向(北)を見ると、急な斜面を登る方向になりますが、Bからの眺めの方が写真全体の構成とより合致します。
したがって、撮影地点はB、地形は火山地形となり、正しい組合せは③です。
問3:正解④
<問題要旨>
日本の気候要素(気温、風、日照)の地域的な分布を理解しているかを問う問題です。それぞれの気候要素が日本のどの地域で高く(多く)、どの地域で低く(少なく)なるかの一般的な傾向を把握しているかがポイントです。
<選択肢>
①は真夏日の年間日数です。真夏日(最高気温30℃以上)は、南の地域ほど、また内陸部ほど日数が多くなります 。図を見ると、南西諸島や西日本の太平洋側で値が高く、北日本では低くなっており、特徴と一致します 。
②は気温の年較差です。気温の年較差(最暖月と最寒月の平均気温の差)は、緯度が高いほど、また内陸の地域ほど大きくなります。図を見ると、北海道や東日本の内陸部で値が高く、沿岸部や南西諸島で低くなっており、特徴と一致します 。
③は日最大風速15m/s以上の年間日数です。風が強い日は、季節風の影響を受ける冬の日本海側や北海道、台風が通過しやすい南西諸島、そして岬などの突出した地形で多くなります 。図の分布はこれらの特徴と一致します 。
④は年間の日照時間です。年間の日照時間は、太平洋側の地域や、年間を通じて降水量が少ない瀬戸内海沿岸で長くなります 。逆に、冬に曇りや雪の日が多い日本海側では短くなります。図を見ると、瀬戸内や関東平野、東海地方で値が高く、日本海側や東北地方で低くなっており、これは年間の日照時間の分布の特徴と一致します 。
問4:正解③
<問題要旨>
地形分類図と高潮による浸水継続時間予測図という2つの地図を重ね合わせ、土地の成り立ちと災害リスクの関係を読み解く問題です。それぞれの選択肢について、図4で示された地形の範囲と、図5で示された浸水状況を正確に対応させて判断する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
図4の左側にある「干拓地」の範囲を確認し、図5の同じ場所を見ると、ほぼ全域が「3日以上」の濃い色で示されており、南北で浸水継続時間に大きな違いは見られません。
②【誤】
「干拓地」はほぼ全域が「3日以上」浸水する予測です。一方、海岸沿いの「盛土地・埋立地」は、「12時間未満および浸水なし」や「12時間以上3日未満」の範囲が多くを占めています。したがって、浸水継続時間は**「干拓地」の方が長い**です。
③【正】
図4で「砂州・砂丘」(点々模様)の西側に広がる「後背湿地」(薄い灰色)の範囲を確認します。次に対応する場所を図5で見ると、「3日以上」の浸水を示す最も濃い色の範囲が、この後背湿地の北部から中央部にかけて広く分布しています。南部に浸水しないエリアもありますが、全体として濃い色の範囲が面積の半分以上を占めていることが読み取れます。したがって、この記述は正しいです。
④【誤】
「台地」(格子模様)の範囲を図5で見ると、ほとんどが「12時間未満および浸水なし」となっており、浸水のリスクが非常に低いことがわかります。したがって、「浸水継続時間が12時間以上3日未満である範囲は、砂州・砂丘よりも台地の方で広い」という記述は明確に誤りです。
問5:正解⑤
<問題要旨>
陰影段彩図と等高線が重ねられた地図から、洪水時の避難経路の特徴とリスクを読み取る問題です。出発点と各避難場所との位置関係、標高差、周辺の地形(崖や谷など)を総合的に判断する必要があります。
<選択肢>
まず、各避難場所と文章カ~クを対応させます。出発点tは標高5mの地点です 。
キとL:文章キは「標高の低い方へ避難する」「最も浸水深が大きくなる可能性が高い」とあります 。避難場所Lは標高5m地点にあり、3つの中で最も標高が低いため、この記述と一致します 。
クとJ:文章クは「比高が最も大きく、標高の高い避難場所へ向かう」とあります 。避難場所Jは標高10mより高い場所にあり、出発点tとの標高差が最も大きいため、この記述と一致します 。
カとK:消去法により、文章カが避難場所Kに対応します 。Kへ向かう経路は谷沿いを進み、脇には陰影で示された急な斜面があります 。このような地形は
崖崩れのリスクが高いため、文章カの記述と合致します 。
したがって、J-ク、K-カ、L-キの組合せである⑤が正解です。
問6:正解④
<問題要旨>
日本で起こる自然現象が、災害(負の側面)と資源(正の側面)の両方をもたらすことをテーマに、不適切な記述を見つけ出す問題です。
<選択肢>
①【正】
火山は、噴火による溶岩流や火山灰などで災害をもたらしますが、その独特な地形(カルデラなど)や温泉は、観光資源として活用されています 。
②【正】
河川は、大雨時に氾濫して水害をもたらしますが、上流から運ばれた土砂が堆積してできた沖積平野は、肥沃な土壌となり農業に適した土地となります 。
③【正】
山地の積雪は、雪崩や交通障害などの原因となりますが、春先の雪解け水は、水田のかんがい用水や水力発電の重要な水源として利用されています 。
④【誤】
竜巻は、局地的に発生する極めて強力で破壊的な突風であり、甚大な被害をもたらします 。その風は突発的で予測が困難なため、風力発電のエネルギー源として安定的に利用することはできません。風力発電は、持続的に吹く季節風や恒常風などを利用するものです。
第2問
問1:正解③
<問題要旨>
世界の地域別の水利用(農業用、工業用、その他)の統計を読み解く問題です。各地域の産業構造や農業形態から、水利用の特色を推測する知識が求められます。
<選択肢>
凡例AとBの特定:
世界全体で見ると、水利用で最も大きな割合を占めるのは農業用水です。グラフを見ると、ヨーロッパは工業が発達しているため、工業用水の割合が高く、農業用水の割合は相対的に低くなります 。ヨーロッパのグラフではBの割合がAより高いことから、Bが工業用、Aが農業用と判断できます。
地域アとイの特定:
東アジアは人口が多く、米作を中心とした灌漑農業が盛んなため、農業用水の使用量が非常に多くなります 。一方、北アメリカも灌漑農業が行われますが、工業も非常に発達しているため、工業用水の使用量も多くなります 。グラフを見ると、アはA(農業用)が突出して多く、イはA(農業用)とB(工業用)のどちらも多くなっています。このことから、アが東アジア、イが北アメリカと判断できます。
組合せの確認:
問題は「北アメリカ」と「農業用」の組合せを問うています 。上記より、北アメリカは「イ」、農業用は「A」となるため、正解は③です。
問2:正解②
<問題要旨>
写真に写された生活風景から気候帯を推測し、それに合致する気候グラフを選ぶ問題です。植生や住居の様子から気候の特徴を読み取る観察力が重要です。
<選択肢>
写真の分析:写真1には、タロイモのような熱帯性の作物や、ヤシの木といった熱帯の植生が写っています 。また、家屋は高床式で壁が少なく、風通しの良い構造になっています 。これらは、年間を通じて気温が高く、降水量が多い熱帯雨林気候(Af)の地域の典型的な風景です。
気候グラフの分析:熱帯雨林気候は、①年間を通じて高温(最寒月の平均気温が18℃以上)、②気温の年較差が小さい、③年間を通じて降水量が多い(最も雨が少ない月でも60mm以上)、という特徴があります。
Dは降水量が少なく、乾燥帯の気候です 。
Eは、最寒月でも平均気温が28℃近くと非常に高く、気温の年較差がほとんどありません 。また、最も雨の少ない月でも200mm以上の降水があり、熱帯雨林気候の条件と完全に一致します 。
Fは気温の年較差がやや大きく、冬は少し涼しくなります 。
Gは冬の気温が0℃近くまで下がり、温帯または冷帯の気候です 。
したがって、写真の風景に合致する気候グラフはEであり、正解は②です。
問3:正解②、④
<問題要旨>
写真で示された2つの異なる交通手段(水路橋、都市型ロープウェイ)について、その機能や目的を正しく説明した文章を選ぶ問題です。
<選択肢>
写真カ:イギリスで見られる**水路橋(アクアダクト)**です 。運河が谷や川を越えるために建設されたもので、産業革命期に物資を運ぶために作られました。
写真キ:ボリビアの都市ラパスで見られるロープウェイです 。急峻なすり鉢状の地形の都市で、市民の足として機能する公共交通機関です。
カとキの両方に当てはまるもの:
①【誤】ロープウェイは強風に弱く、運河は冬に凍結することがあり、どちらも天候の影響を受けます。
②【正】水路橋(カ)は谷を越えるために、ロープウェイ(キ)は急な坂を克服するために作られており、どちらも「起伏のある地形を移動できるようにした手段」と言えます 。
③【誤】水路橋を行く船(ナロウボート)の輸送量は鉄道よりはるかに少ないです。
④【誤】道路の交通渋滞緩和はロープウェイ(キ)の目的ですが、産業革命期の水路橋(カ)の目的ではありません。
したがって、両方に当てはまるのは②です。
キのみに当てはまるもの:
④【正】ラパスのロープウェイ(キ)は、山岳地形による慢性的な
道路の交通渋滞を緩和することを大きな目的として導入された、現代的な都市交通システムです 。この目的は、歴史的な物資輸送路である水路橋(カ)には当てはまりません。
したがって、キのみに当てはまるのは④です。
問4:正解②
<問題要旨>
空港の出発案内表示の言語から国を特定し、地理的な位置や経済的な結びつきから東京との間の航空便数を推測して、正しく組み合わせる問題です。
<選択肢>
国の特定:
サ:表示に「Perlepasan Antarabangsa」とあり、これはマレー語です 。したがって、サはマレーシアです。
シ:表示に「المغادرة الدولية」とあり、これはアラビア語です 。選択肢から、シはカタールです。
ス:表示に「Salidas Internacionales」とあり、これはスペイン語です 。したがって、スはメキシコです。
便数の推測と組み合わせ:東京との間の航空便の週当たり往復便数を考えます 。
J (38便):最も便数が多いです。東南アジアの主要国であり、日本との経済的な結びつきや観光客の往来が非常に多いマレーシアが該当すると考えられます。
K (14便):中程度の便数です。日本企業(特に自動車産業)が多く進出し、ビジネスでの往来が活発なメキシコが該当します。
L (5便):最も便数が少ないです。地理的に遠く、他の2カ国と比べると直接的な人的交流の規模が小さいカタールが該当すると考えられます。(※2017年時点のデータであり、現在とは異なる場合があります )
結論:以上のことから、サ(マレーシア)-J、シ(カタール)-L、ス(メキシコ)-Kという組み合わせになります。これは選択肢②と一致します。
問5:正解③
<問題要旨>
サケ・マス類の輸出入に関する統計地図を読み解く問題です。輸出国と輸入国の地理的分布、そして鮮魚・冷蔵品と冷凍品の貿易形態の違いを理解しているかが問われます。
<選択肢>
輸出(X)と輸入(Y)の特定:
サケ・マス類は、ノルウェー、チリ、カナダ、アメリカ(アラスカ)などの冷たい海で主に生産(漁獲・養殖)されます。主な消費地(輸入国)は、日本、EU諸国、アメリカ、中国などの先進国や人口大国です。
地図Xは、北欧(ノルウェー)、北米、南米(チリ)に大きな円があり、輸出国の分布と一致します 。
地図Yは、東アジア(日本、中国)、ヨーロッパ、北米(アメリカ)に大きな円があり、輸入国の分布と一致します 。
鮮魚・冷蔵品(タ)と冷凍品(チ)の特定:
鮮魚・冷蔵品は鮮度が重要で、空輸されることが多く、近距離の貿易で割合が高くなる傾向があります。
冷凍品は船で長距離輸送が可能なため、遠距離の貿易で割合が高くなります。
輸出地図Xを見ると、ヨーロッパ市場に近いノルウェーは、円の大部分を薄い色のタが占めています。一方、主要市場から遠いチリは、円の大部分を濃い色のチが占めています。
このことから、タが鮮魚・冷蔵品、チが冷凍品と判断できます。
組合せの確認:問題は「輸入量の図」と「鮮魚・冷蔵品の凡例」の組合せを問うています 。上記より、輸入量の図は「Y」、鮮魚・冷蔵品は「タ」となるため、正解は③です。
問6:正解③
<問題要旨>
3つの国の製造業に関する統計データと、その特徴を述べた文章を正しく結びつける問題です。各国の経済発展の段階や産業構造の特徴を把握しているかが鍵となります。
<選択肢>
統計データ(表1)の分析:
P:出荷額が圧倒的に大きく(9兆ドル超)、輸送用機械の割合が高いです 。これは、自動車産業などが基幹産業となっている先進工業国の特徴です。
Q:出荷額は中位で、石油製品の割合が突出して高いです 。これは、産油国など天然資源の加工が製造業の中心となっている国の特徴です。
R:出荷額は最も小さく、繊維・衣類の割合が半分以上を占めています 。これは、安価な労働力を活かした労働集約型産業が中心の発展途上国の特徴です。
文章(マ~ム)の分析:
マ:「国内で豊富にとれる天然資源を加工して輸出する」とあり、Qの特徴と一致します 。
ミ:「人件費の高さなどに対応するため、付加価値が高く高度な技術や知識を必要とする製造業へと移行」とあり、先進工業国であるPの特徴と一致します 。
ム:「低賃金で雇用できる国内の豊富な労働力をいかした」製品の生産とあり、労働集約型の発展途上国であるRの特徴と一致します 。
組合せの確認:P-ミ、Q-マ、R-ムの組合せとなります。これは選択肢③と一致します。
第3問
問1:正解⑥
<問題要旨>
北アメリカの地図と3つの風景写真から、国立公園の位置と景観を正しく結びつける問題です。地図から気候帯や地形を大まかに読み取り、写真の植生や地形と対応させる能力が問われます。
<選択肢>
地点A:カナダのロッキー山脈東麓に位置します 。内陸で緯度が高いため、気候は冷帯(亜寒帯)です。写真ウには、タイガ(亜寒帯針葉樹林)や湿地が広がっており、冷帯の景観と一致します 。
地点B:アメリカ南西部、メキシコとの国境付近に位置します 。この地域は乾燥帯に属し、砂漠気候やステップ気候が広がります。写真イには、サボテンが多数見られ、乾燥した地域の景観であることがわかります 。
地点C:カナダ東部、ニューファンドランド島に位置します 。この地域はフィヨルドなど氷河によって削られた険しい地形が見られます。写真アは、深い谷(フィヨルドやU字谷)の景観であり、この地域の特徴と一致します 。
したがって、A-ウ、B-イ、C-アの組合せとなり、正解は⑥です。
問2:正解①
<問題要旨>
アメリカ合衆国における特定の農産物の生産地域を、分布図から判断する問題です。各作物の栽培に適した自然条件(気候、地形)と、アメリカの主な農業地域を結びつけて考える知識が必要です。
<選択肢>
① ブドウ:ブドウは、夏に高温で乾燥し、冬に温暖で湿潤な地中海性気候での栽培に適しています。アメリカではカリフォルニア州がこの気候に該当し、ブドウ(ワイン用、生食用、干しブドウ用)の一大産地となっています。地図①は、生産がカリフォルニア州に極端に集中しており、ブドウの分布を示していると判断できます 。
② メープルシロップ:原料となるサトウカエデは、冷涼な気候を好みます。アメリカではカナダとの国境に近い北東部(バーモント州など)が主産地です。地図②はこの地域の生産量が多くなっています 。
③ トウモロコシ:アメリカ中西部のコーンベルトと呼ばれる地域(アイオワ州、イリノイ州など)で大規模に生産されています。地図③はこの地域の生産量が多くなっています 。
④ 綿花:高温・乾燥を好む作物で、かつては南東部が中心でしたが、現在は灌漑設備が整ったテキサス州から西部のカリフォルニア州にかけてのサンベルト地帯で多く生産されています。地図④はこの地域の生産量が多くなっています 。
したがって、ブドウに該当するのは①です。
問3:正解①
<問題要旨>
アメリカ合衆国における人種・民族の地理的分布を、統計グラフから読み解く問題です。各民族集団が歴史的にどの地域に多く住んでいるかという知識が問われます。
<選択肢>
アジア系:アジアからの移民は、歴史的に太平洋岸の玄関口である西部(カリフォルニア州など)に多く定住してきました。グラフでアジア系の割合が最も高いのはカであり、カが西部と判断できます 。
アフリカ系:アフリカ系の人々は、かつて奴隷として強制的に連れてこられた歴史的経緯から、南部のプランテーション地帯に多く居住していました。現在もその子孫が南部に多く住んでいます。グラフでアフリカ系の割合が突出して高いのはキであり、キが南部と判断できます 。
先住民:先住民は、かつては全米に分布していましたが、現在は政府が設定した居留地などに多く住んでいます。
北東部と中西部:消去法により、残ったクが北東部となります 。
したがって、カ=西部、キ=南部、ク=北東部の組合せとなり、正解は①です。
問4:正解②
<問題要旨>
カナダの都市で見られる多文化的な景観の写真から、そこに住む人々の文化や慣習を推測し、不適切な記述を選ぶ問題です。写真の文字や建物の様式が大きなヒントになります。
<選択肢>
①【正】
写真サには、ハングルで書かれた看板が見えます 。これはコリアタウン(韓国系住民の集住地区)の景観です。韓国では、日本や中国と同様に箸やスプーンを用いて食事をする文化があります 。
②【誤】
写真シは、キリスト教の教会(ゴシック様式)と近代的な高層ビルが共存する景観です 。キリスト教文化圏では、牛を神聖視する慣習は広くみられません。牛を神聖な動物とするのは、主にヒンドゥー教です。したがって、この記述は誤りです。
③【正】
写真スは、イスラム教のモスクです 。イスラム教徒は、教義に則って処理されたハラール食材を食します。モスク周辺には、ハラール食材を扱う店が集まっていることが一般的です 。
④【正】
写真セには、「海鮮」「酒家」といった漢字の看板が見え、チャイナタウン(中国系住民の集住地区)の景観です 。中国文化圏では、旧暦の新年(春節)を盛大に祝う行事が行われます 。
問5:正解④
<問題要旨>
アメリカの2つの都市(デトロイト、サンノゼ)の産業構造を統計から読み取り、現代の都市問題と結びつける問題です。各都市の歴史的背景と現在の産業の特色を知っているかが鍵となります。
<選択肢>
都市の特定(タとチ):
デトロイト:かつて「自動車の都」として栄えた伝統的な工業都市です。現在も自動車産業は主要産業であり、「生産工程従事者」の割合が高いと考えられます。
サンノゼ:世界的なIT企業が集積するシリコンヴァレーの中心都市です。先端技術産業が盛んであり、「情報処理・通信技術者」の割合が非常に高いと考えられます。
表1を見ると、タは「生産工程従事者」の割合が高く(10.1%)、チは「情報処理・通信技術者」の割合が突出して高いです(12.7%) 。したがって、タがデトロイト、チがサンノゼと判断できます。
文章の空欄補充(EとF):
文章は「経済発展が著しい都市」の問題について述べています 。デトロイト(タ)は産業の衰退(ラストベルト)を経験した都市であり、一方サンノゼ(チ)はIT産業の集積により著しい経済発展を遂げました。したがって、Eにはチ(サンノゼ)が入ります。
シリコンヴァレーのような先端技術産業の集積地では、高所得者が集まることで地価や家賃が急激に上昇し、
住居費の高騰が深刻な社会問題となっています 。したがって、Fには住居費が入ります。
組合せの確認:
E-チ、F-住居費の組合せとなり、正解は④です。
問6:正解③
<問題要旨>
カナダの閣僚構成の変化を示した2つの地図から、2015年の状況を特定し、その背景にあるカナダの国家方針を答える問題です。カナダの多文化主義政策と、近年のジェンダー平等への配慮を理解しているかが問われます。
<選択肢>
地図の特定(マ):文章には「2015年に就任した首相は、性の平等性に配慮し、様々な背景のある議員を閣僚に任命した」とあります 。2つの地図MとNを比較すると、
Nの方が、女性閣僚(黒塗りの記号)の数がMよりも明らかに多い 。
マイノリティ(△)や先住民(◇)出身の閣僚の数もMより多い 。
という特徴があり、文章の内容と一致します。したがって、2015年を示している図(マ)はNです。
語句の特定(ミ):カナダは、様々な民族(ルーツ)を持つ移民で構成される国家として、それぞれの文化の違いを尊重し共存していこうとする「多文化主義」を国策として掲げてきました 。2015年の多様な背景を持つ人々を閣僚に登用した人事は、この多文化主義をさらに推進したものと言えます。
したがって、マ-N、ミ-多文化主義の組合せとなり、正解は③です。
第4問
問1:正解②
<問題要旨>
地球温暖化に関する国際会議における各国の立場をグループ分けした地図をもとに、生徒たちの会話から誤った発言を指摘する問題です。各グループに属する国々の地理的・経済的特徴から、その主張を推測する必要があります。
<選択肢>
①【正】
グループAは、モルディブやツバル、マーシャル諸島といった海抜の低い島嶼国(とうしょこく)が多く含まれます 。これらの国々は、温暖化による海面上昇で水没の危機に瀕しているため、温室効果ガスの大幅な排出削減を強く主張しています 。この発言は正しいです。
②【誤】
グループBは、サウジアラビア、ロシア、ベネズエラなど、石油や天然ガスの生産・輸出国が多く含まれます 。これらの国々の経済は化石燃料に大きく依存しています。世界的に温暖化対策が進み、化石燃料の消費が抑制されると、自国の資源の経済的価値は下落してしまいます。そのため、これらの国々は急進的な温暖化対策には消極的な立場をとることが多いです。「価値の上昇を期待して」「早急な対策を求めている」という発言は誤りです 。
③【正】
グループCは、中国やインド、ブラジルなど、近年急速な経済成長を遂げている新興国が多く含まれます 。これらの国々は、歴史的に温室効果ガスを大量に排出してきたのは先進国であるとして、先進国に率先した排出削減と、発展途上国への技術・資金援助を要求する立場をとることが多いです 。この発言は正しいです。
④【正】
グループDは、日本、EU諸国、カナダ、オーストラリアなどの先進国が多く含まれます 。これらの国々は、環境技術も進んでおり、国際社会において温室効果ガスの排出削減を主導する立場にあります 。この発言は正しいです。
問2:正解⑤
<問題要旨>
プラスチックごみの国際的な貿易量の変化を示す図を読み解き、国名と年代を特定する問題です。資料中の「中国が2017年に輸入を厳しく制限した」という情報が最大のヒントとなります。
<選択肢>
年代の特定(F年とG年):
資料文に「中国が2017年に輸入を厳しく制限した」とあります 。F年とG年の図を比較すると、F年ではアと日本からイへの輸出量が非常に多い(942、769)のに対し、G年ではイへの輸出が激減しています 。この大きな変化が中国の輸入制限によるものだと考えられるため、規制前のF年が2010年、規制後のG年が2019年と判断できます。
国の特定(ア~ウ):
イ:F年(2010年)に、ア(アメリカ)と日本から大量のプラスチックごみを受け入れていることから、イが中国です 。
ア:日本や中国(イ)との貿易量が多いことから、先進国であるアがアメリカ合衆国と判断できます。
ウ:G年(2019年)に、中国(イ)の輸入制限後、日本やアメリカ(ア)からのプラスチックごみの新たな受け入れ先(受け皿)として輸出量が増加しています 。これは東南アジア諸国の状況と一致し、ウがマレーシアです 。
組合せの確認:
問題は「マレーシア」と「2010年」の組合せを問うています 。上記より、マレーシアは「ウ」、2010年は「F年」となるため、正解は⑤です。
問3:正解③
<問題要旨>
国際河川で発生した水質汚染事故に関する資料を読み解き、文章中の記述の正誤を判断する問題です。グラフと地図を照合し、数値を正確に読み取る能力が求められます。
<選択肢>
下線部J:「有害物質は、地点dでは流出した日から8日目に濃度が最大値となった」。
グラフを見ると、地点dの濃度変化を示す線(一点鎖線)は、横軸の「8日目」でピーク(最大値)を迎えています 。したがって、この記述は正です。
下線部K:「有害物質の移動の速度は、地点a-b間よりも地点b-c間の方が4倍以上速い」 。
地点aでのピークは4日目、地点bでのピークは5日目です。a-b間ではピークが移動するのに1日かかっています 。
地点bでのピークは5日目、地点cでのピークは6日目です。b-c間でもピークが移動するのに1日かかっています 。
移動速度に大きな差はないため、「4倍以上速い」という記述は誤です。
下線部L:「観測された濃度の最大値は、流出地点から離れるほど小さくなっている」 。
グラフのピークの高さ(濃度の最大値)を見ると、a → b → c → d の順、つまり流出地点から下流へ離れるにつれて、ピークが低く(小さく)なっています 。これは、有害物質が川の水で薄められながら流れていくためです。したがって、この記述は正です。
以上のことから、J-正、K-誤、L-正の組合せとなり、正解は③です。
問4:正解⑥
<問題要旨>
バイオ燃料の生産拡大がもたらす、食料需給や生態系への影響について、国とその主原料、懸念される問題を正しく結びつける問題です。
<選択肢>
P ブラジル:ブラジルは世界有数のサトウキビ生産国であり、古くからサトウキビを原料とするバイオエタノール(ガソリン代替燃料)の生産・利用が盛んです 。サトウキビプランテーションの拡大が、アマゾンの
熱帯雨林破壊の一因となっていることが懸念されています。
Q インドネシア:インドネシアやマレーシアは、パーム油の原料となるアブラヤシの世界的な生産地です 。パーム油はバイオディーゼル燃料の原料としても注目されており、アブラヤシ農園の開発が、
熱帯雨林や泥炭地の破壊につながっています。
R アメリカ合衆国:アメリカ合衆国は世界最大のトウモロコシ生産国です 。政府の政策によりトウモロコシを原料とするバイオエタノールの生産が急増した結果、家畜の
飼料用や食用のトウモロコシと競合し、国際的な穀物価格の高騰を招く一因となりました(「食料との競合」問題)。
したがって、アメリカ合衆国-R、インドネシア-Q、ブラジル-Pの組合せとなり、正解は⑥です。
問5:正解③
<問題要旨>
日本の大都市圏における、人口密度と自家用車利用率の関係をグラフから読み解き、通勤時の環境負荷を計算する問題です。
<選択肢>
空欄カ:「周辺都市では、郊外化によって自家用車に依存した生活様式が定着してきた」とあります 。これは、公共交通機関が中心市街地ほど発達していない郊外では、
自家用車利用の割合が高くなることを意味します。
グラフを見ると、Y(白丸)は全体的にX(黒丸)よりも自家用車利用の割合が高い位置に分布しています 。したがって、Yが周辺都市、Xが中心都市を示しています。カにはYが入ります。
空欄キ:環境負荷を二酸化炭素排出量で計算します 。
ルートA(自家用車のみ):
40km × 150g/km = 6000g
ルートB(自家用車+鉄道):
自家用車部分:4km × 150g/km = 600g
鉄道部分:30km × 20g/km = 600g
合計:600g + 600g = 1200g
比較:ルートAはルートBの 6000g ÷ 1200g = 5倍の環境負荷となります。キには5が入ります。
組合せの確認:カ-Y、キ-5の組合せとなり、正解は③です。
問6:正解②
<問題要旨>
4つの班が探究した環境問題と、それに対する取組みの例の組み合わせの中から、不適切なものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【適切】
「先進国から発展途上国へのプラスチックごみの移動」という国境を越える問題に対しては、バーゼル条約のような「廃棄物の流通を管理する国際的なルールを策定する」ことが有効な対策となります 。
②【不適切】
「有害物質の流出事故による国際河川の汚染の拡大」という課題に対し、「きれいな飲用水を供給できるよう浄水施設を整備する」ことは、汚染された水を安全に利用するための対症療法的な取組みです 。しかし、これは汚染の拡大そのものを防ぐ対策ではありません。汚染拡大を防ぐには、発生源での管理強化や、国際的な協力による監視・通報体制の構築などがより直接的な取組みとなります。したがって、この例は課題に対してややずれています。
③【適切】
「バイオ燃料の導入拡大に伴う食料や生態系への影響」(食料との競合や森林破壊)という課題に対しては、食料とならない「廃棄物や廃材を活用したバイオ燃料の開発」(第2世代バイオ燃料)を進めることが、解決策の一つとなります 。
④【適切】
「日常生活における過度な自家用車利用による環境負荷」という課題に対しては、自家用車に頼らなくても移動しやすいように「利便性の高い公共交通ネットワークを整備する」(モーダルシフト)ことが有効な対策です 。
第5問
問1:正解⑤
<問題要旨>
利根川の流域や地形的な特徴に関する文章の空欄を補充する問題です。地図から流域の範囲を読み取り、簡単な計算を行う必要があります。
<選択肢>
空欄ア(流域の範囲)
「流域」とは、ある河川に雨水が流れ込む範囲全体を指し、その川の支流(しりゅう)が含まれるすべての地域を意味します。
地点B(群馬県)は烏川(からすがわ)、地点C(栃木県)は渡良瀬川(わたらせがわ)の流域にありますが、これらはどちらも利根川の主要な支流です。したがって、BとCは利根川の流域に含まれます。
地点A(埼玉県)は荒川の流域にあり、現在の荒川は利根川とは別の水系として東京湾に注いでいるため、Aは「現在の利根川の流域」には含まれません。
よって、空欄アには「BとC」が入ります。
空欄イ(標高差の計算)
文章に「取手から佐原までの区間における河川の勾配は、1万分の1程度」とあります。
まず、地図の縮尺(スケール)から、取手と佐原の間の河川に沿った距離は約40kmであることがわかります。
40kmは40,000mです。
勾配が1/10000なので、標高差は「距離 × 勾配」で計算できます。
計算式: 40,000m × (1 / 10000) = 4m
よって、空欄イには「4m」が入ります。
組合せの確認
以上のことから、アに「BとC」、イに「4m」が入る選択肢⑤が正解となります。
問2:正解②
<問題要旨>
地形図と土地利用の統計グラフを対応させる問題です。地図から各範囲(E~H)の地形(低地か台地か)を読み取り、それに応じた土地利用の特色を推測する力が求められます。
<選択肢>
地形の分析(図2):
E, F:利根川沿いの低地(沖積平野)に位置します。特にFは鉄道駅や市役所に近く、市街地が広がっていると推測されます 。
G, H:利根川から離れた、陰影が示すように標高の高い台地(洪積台地)上に位置します。畑や森林が広がっていると推測されます 。
土地利用グラフの分析(図3):
①:田の割合が8割以上を占めています 。これは低地の水田地帯であるEに対応します。
②:田の割合が最も高いですが、建物用地の割合も2割程度とかなり高くなっています 。これは、低地にありながら市街化が進んでいるFに対応します。
③, ④:畑・果樹園や森林の割合が高いです 。これは台地上のG, Hに対応します。
結論:問題はFに該当するものを問うています 。上記より、Fは②となります。
問3:正解⑤
<問題要旨>
新旧の地形図と、河川の交通手段(渡船、橋)の変遷を示す地図を読み解き、都市の発達と交通網の変化について考察する問題です。
<選択肢>
空欄J:「より古くから中心地として発達していたのは(J)だね」 。
1931年の地形図を見ると、bの範囲は小野川沿いにあり、すでに密集した市街地が形成されています 。一方、aの範囲は佐原駅の西側で、当時はまだ市街地化が進んでいません 。佐原は江戸時代に利根川水運の中継地として栄えた町であり、川沿いのbが古くからの中心地です。したがって、Jにはbが入ります。
空欄K:「自動車交通の増加に対応して道路網が整備されてきたことを考えると、1981年の橋の分布は、(K)の図である」 。
サは1932年の渡船の分布です 。
時代が進むにつれて、渡船は橋に置き換えられ、橋の数は増加するはずです。
シとスを比べると、点の数(橋の数)はシの方がスよりも多くなっています 。自動車交通が増加した1981年には、多くの橋が架けられていると考えられるため、
1981年の橋の分布はシとなります。スは1932年の橋の分布を示していると考えられます。したがって、Kにはシが入ります。
組合せの確認:J-b、K-シの組合せとなり、正解は⑤です。
問4:正解③
<問題要旨>
地域の水害史と対策施設の資料を読み解き、治水対策について考察する問題です。資料に示された地名と地図上の位置を正確に対応させ、治水の基本的な考え方を理解しているかが問われます。
<選択肢>
空欄P:学芸員は「利根川の支流への逆流などにより、水害が発生」し、それを防ぐために水門が設置されたと説明しています 。
水門は、本流(利根川)の水位が上昇した際に、支流へ水が逆流するのを防ぐために、支流が本流に合流する地点の近くに設置されます。
年表を見ると、十六島で繰り返し浸水被害が起こっています 。地図を見ると、地点チは十六島にあり、支流が利根川本流に合流する手前の位置にあります 。したがって、水門が設置されたのは地点チと判断できます。Pにはチが入ります。
空欄Q:大きな河川の下流域における洪水対策について述べています 。
f:「決壊を防ぐため、堤防を補強する」 。河川の下流域は、堤防によって洪水を防いでいるため、堤防の強化は最も基本的な洪水対策です。
g:「土砂の流出や流木を防ぐため、ダムを建設する」 。ダム(特に砂防ダム)は、主に土砂災害を防ぐ目的で、
河川の上流や中流域に建設されるものです。
したがって、下流域の対策としてより一般的なのはfです。Qにはfが入ります。
組合せの確認:P-チ、Q-fの組合せとなり、正解は③です。
問5:正解②
<問題要旨>
日本のウナギ供給に関する統計資料と、河川環境保全の取組みに関する写真を結びつける問題です。統計の傾向を読み取り、生態系に配慮した河川構造物を特定する知識が問われます。
<選択肢>
マとミの特定:資料文に「1970年代以降、日本国内のウナギの漁獲量は減少し、現在、日本国内で消費されるウナギのほとんどは、国内での養殖生産と輸入によってまかなわれている」とあります 。
表を見ると、1973年以降、国内漁獲量は一貫して減少しています 。
マは1985年にピークを迎え、その後はやや減少傾向にあります。これは、稚魚(シラスウナギ)の不漁などの影響を受けやすい国内の養殖生産量の推移と考えられます 。
ミは2000年にかけて急激に増加し、その後も高い水準を保っています。これは、中国などからの国外からの輸入量の推移と考えられます 。
したがって、国内の養殖生産量はマです。
空欄Xの特定:資料文は、ウナギなどの水産資源の回復に寄与する取組みについて述べています 。
ニホンウナギは、川と海を行き来して生活する回遊魚です。
写真sの「石材を用いて整備された護岸」は、コンクリート護岸に比べて生物の生息には配慮していますが、川の連続性を保つものではありません 。
写真tは、堰(せき)によって川の流れが分断されている場所に、魚が遡上・降下できるように設置された「
魚道」です 。これは、ウナギのような回遊魚の生態系を保全するための重要な取組みです。
したがって、Xにはtが入ります。
組合せの確認:国内の養殖生産量-マ、X-tの組合せとなり、正解は②です。
問6:正解③
<問題要旨>
地域調査で立てた新たな課題と、その調査方法の組み合わせとして、不適切なものを選ぶ問題です。地理的な課題を探究する上で、どのような調査手法が有効かを判断する力が求められます。
<選択肢>
①【適切】
「農地の分布の変化」という土地利用の変遷を調べるには、「撮影年代の異なる空中写真」や古地図を比較し、土地利用図を作成することが非常に有効な方法です 。
②【適切】
「橋の開通による住民の生活行動の変化」という、人々の行動や意識の変容を調べるには、統計データだけではわからない質的な情報を得るために、周辺住民への「聞き取り調査」(インタビュー)やアンケート調査が有効です 。
③【不適切】
「防災施設の整備により、住民の防災意識はどのように変化したか?」という課題を調べています 。GIS(地理情報システム)を用いて「防災施設から一定距離内に住む人口の変化を調べる」ことは、人口分布の変化を調べる方法ではありますが、住民の「意識」そのものを直接調べる方法ではありません。防災意識を調べるには、アンケート調査や聞き取り調査、地域の防災訓練への参加率の推移を調べるなどの方法が適しています。
④【適切】
「利根川流域の漁獲量の変化」という、過去からの量の推移を調べるには、漁業協同組合の統計や、自治体や国の機関が発行している統計資料などを図書館やインターネットで入手して調べることが基本的な調査方法となります 。