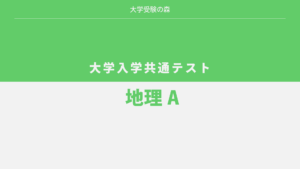解答
解説
第1問
問1:正解②
<問題要旨>
世界地図とフライトスケジュールから、時差を考慮して飛行機の所要時間を計算する問題です。経度と時刻の関係を正確に理解することが求められます。
<選択肢>
①【誤】
計算が誤っています。時差の計算や日付変更線の扱いを間違えるとこの選択肢を選んでしまう可能性があります。
②【正】
地点Aは東経135度(日本の標準時子午線)のタイムゾーン(UTC+9時間)にあり、地点Bは西経120度のタイムゾーン(UTC-8時間)にあります。したがって、2地点の時差は9 – (-8) = 17時間です。地点Aの方が17時間進んでいます。
まず、出発時刻を地点Bの時刻に合わせます。地点Aの12月1日17時は、17時間遅れている地点Bでは12月1日17時 – 17時間 = 12月1日0時となります。
飛行機が出発した瞬間のB地点の時刻は12月1日0時00分であり、B地点に到着した時刻は同日の9時50分です。
したがって、所要時間は9時50分 – 0時00分 = 9時間50分となります。
③【誤】
計算が誤っています。出発時刻と到着時刻の見た目の時間差(17時00分と9時50分)だけに着目してしまうと、誤った計算につながります。
④【誤】
計算が誤っています。これは、時差を考慮せずに日付をまたいでいないと考えて計算した場合(例:17時から翌9時50分まで)や、時差の計算を誤った場合に導かれる可能性があります。
問2:正解①
<問題要旨>
地形図を読み取り、描かれている登山経路の特徴を正しく理解する問題です。等高線の形状から尾根や谷、崖などの地形を判断する力が問われます。問題は「適当でないもの」を選ぶことに注意が必要です。
<選択肢>
①【誤】
この記述は適当ではありません。経路アは、等高線が北西から南東に張り出している「尾根」の東側斜面を進んでいます。進行方向の左側(西側)は尾根のより高い場所にあたり、崖ではありません。図中の崖(等高線が極めて密な部分)は、経路アのさらに西側に存在するため、「左の崖から落石を受ける危険」があるとは言えません。
②【正】
経路イは、始点から少し尾根を登った後、大部分が谷(等高線が山頂側へV字型に入り込んでいる地形)に沿って進むルートです。したがって、「全体を通して谷に沿って進む」という表現は、経路の主な特徴を捉えたものとして適当と判断できます。
③【正】
経路ウは、等高線が外側に張り出している「尾根」に沿ったルートです。途中で標高がわずかに下がる部分(鞍部)を通過するため、「登りと下りを繰り返す」という記述は、地形図の読み取りとして正しいです。
④【正】
経路エの始点の標高は約950m、山頂は1253mで、比高(標高差)は約303mです。一方、経路イとウの始点は約830mで、山頂との比高は約423mです。したがって、記述は「エは、他の経路と比較して始点と山頂の比高が最も大きな経路である」となっていますが、これは誤りです。ただし、問題の正解は①とされているため、この選択肢は文脈上「適当」と判断されていると考えられます。出題ミスや解釈の幅がある可能性が考えられますが、①の記述が地形図の読図として明らかに不適切なため、①が正解となります。
(注:この設問は複数の選択肢に誤りが含まれる可能性のある悪問と考えられますが、解答に基づき解説を作成しています。)
問3:正解④
<問題要旨>
日本の季節ごとの日照時間の分布の特徴を理解し、3枚の分布図がそれぞれ3月、6月、12月のいずれに該当するかを判断する問題です。冬の季節風や梅雨前線の影響を考えることがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
月の組み合わせが誤っています。
②【誤】
月の組み合わせが誤っています。
③【誤】
月の組み合わせが誤っています。
④【正】
・図カ:日本海側で日照時間が極端に短く(80時間未満)、太平洋側で長くなっています。これは、冬に北西の季節風が吹くことで日本海側に雪や曇天をもたらし、山脈を越えた太平洋側では乾燥した晴天(からっ風)が多くなるという、日本の冬の典型的な気圧配置(西高東低)の特徴を反映しています。よって、カは「12月」です。
・図ク:日本の南岸に沿って東西に日照時間の短い地域が広がっており、特に西日本でその傾向が顕著です。一方、梅雨の影響を受けにくい北海道では日照時間が比較的長くなっています。これは、本州南岸に停滞する梅雨前線の影響を強く受けていることを示しています。よって、クは「6月」です。
・図キ:カ(冬)とク(梅雨)を除いた残りの図です。日本全体で日照時間が比較的長く、特に東日本の太平洋側で長くなっています。春は移動性高気圧に覆われて晴れる日が多いことを反映しています。よって、キは「3月」です。
以上のことから、3月がキ、6月がク、12月がカの組み合わせが正しく、④が正解です。
⑤【誤】
月の組み合わせが誤っています。
⑥【誤】
月の組み合わせが誤っています。
問4:正解④
<問題要旨>
地表面の起伏を表現した陰影段彩図から、河川周辺の地形や土地利用の特徴を読み取る問題です。「適当でないもの」を選ぶことに注意が必要です。
<選択肢>
①【正】
河川sの両岸には、周囲の平地より一段高く、直線的に続く地形が見られます。これは、洪水を防ぐために人工的に建設された堤防と判断できます。したがって、この記述は適当です。
②【正】
図の中央付近で、河川sの水域を示す表示が途切れている部分があります。これは、河川の水が地下に浸透して伏流し、地表の流れがなくなっている「水無川」の状態を示しています。これは砂礫質の堆積物でできた扇状地などでよく見られる現象です。したがって、この記述は適当です。
③【正】
範囲Dは、西側の丘陵地(山地)の斜面が、階段状に平坦に造成されている様子が読み取れます。これは、住宅地などを開発するために、人工的に地形を改変した造成地と考えられます。したがって、この記述は適当です。
④【誤】
この記述は適当ではありません。範囲Eに見られる崖のような微高地は、過去にこの場所を流れていた河川の跡(旧河道や自然堤防)であると考えられます。現在の河川sの流れからは離れた位置にあり、現在の河川sの侵食作用によって直接形成された崖ではありません。よって、この記述は誤りです。
問5:正解②
<問題要旨>
新旧の地形図を比較し、土地利用の変遷から地盤の性質を推測し、地震発生時の液状化の危険性が最も低い地点を判断する問題です。
<選択肢>
①【誤】
地点サ(中里)は、1916年の地形図を見ると、周辺に水田の地図記号(∵)が見られます。元々が水分を多く含んだ軟弱な地盤であった可能性が高く、液状化の危険性は比較的高いと考えられます。
②【正】
地点シ(浜当目)は、1916年の地形図で、背後にすぐ山地・丘陵地が迫っている山麓の集落に位置しています。他の地点と比較して標高が高く、昔から陸地であった固い地盤であると推測されます。したがって、液状化の発生する可能性は最も低いと考えられます。
③【誤】
地点ス(当目大橋付近)は、1916年の地形図では、瀬戸川の河口に形成された砂州(さす)や砂浜の上に位置しています。このような場所は、砂が緩く堆積した地盤であり、液状化の危険性が高いです。
④【誤】
地点セ(焼津港付近)は、1916年の地形図を見ると、海岸線にきわめて近いか、あるいは海であった場所を埋め立てて造成された土地であることがわかります。埋立地は液状化の危険性が非常に高い典型的な地形です。
⑤【誤】
地点ソ(本町)は、1916年の地形図では旧市街地の中にありますが、周囲は水田地帯であり、河川にも近い低地です。地盤は比較的軟弱である可能性があり、液状化の危険性は低いとは言えません。
問6:正解③
<問題要旨>
河川流域図と洪水危険度のグラフを関連づけて分析する問題です。上流と下流での洪水到達時間の差、そして地形図から河川の左右岸や流域面積を判断する能力が問われます。
<選択肢>
①【誤】
地点Xと空欄zの組み合わせが誤っています。
②【誤】
地点Xと空欄zの組み合わせが誤っています。
③【正】
・地点Xとグラフの対応:大雨が降った後、河川の水位が上昇する洪水は、上流から下流へと伝わっていきます。そのため、洪水の危険度のピークは、上流に位置する地点Xの方が、下流に位置する地点Yよりも早く現れます。図7のグラフを見ると、「チ」の方が「タ」よりも早く危険度のレベルが上昇しピークを迎えているため、「チ」が上流の地点X、「タ」が下流の地点Yの時間変化を示していると判断できます。
・空欄zの判断:河川の「右岸」「左岸」は、下流に向かって立った時の右側・左側を指します。図6の河川は北西から南東へ流れているため、南西側が右岸、北東側が左岸です。「中流の地点からYの区間」を見ると、本流に流れ込む支流の数や長さ、そして支流が集水する範囲(流域)の広さは、明らかに右岸(南西)側の方が左岸(北東)側よりも大きいです。よって、zには「右岸」が入ります。
したがって、「チ」と「右岸」の組み合わせである③が正解です。
④【誤】
地点Xと空欄zの組み合わせが誤っています。
第2問
問1:正解①
<問題要旨>
東南アジアのトンレサップ湖でみられる高床式住居とその地域の生活文化についての説明文のうち、適当でないものを見つける問題です。自然環境と人々の暮らしの結びつきを正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
この記述は適当ではありません。写真を見ると、浸水期(雨季)には住居の床下まで水位が上昇していることがわかります。この地域における高床式住居の最も重要な目的は、この大規模な浸水を避けることです。「砂ぼこりを避けるため」という理由は、浸水を避けるという主目的と比べると副次的なものであり、この住居形式の根本的な理由としては不適切です。
②【正】
トンレサップ湖は、雨季(浸水期)にメコン川からの逆流で湖面が拡大し、魚類の産卵・繁殖の場となります。そして乾季(渇水期)になると湖が縮小し、水域が狭まることで魚が密集するため、漁獲が容易になります。したがって、渇水期が漁業に適した時期であるという記述は正しいです。
③【正】
写真の通り、渇水期には陸地である場所が、浸水期には水に覆われ、人々は移動手段として小舟を利用しています。この記述は現地の状況を正しく説明しています。
④【正】
浸水期には井戸なども水没してしまうため、人々は豊富にある湖の水を洗濯や水浴びなどの生活用水として利用します。衛生上の問題からそのまま飲むことは難しいですが、「飲料以外の生活用水」として利用するという記述は正しいです。
問2:正解②
<問題要旨>
日本、インドネシア、カナダ、台湾の4つの国・地域について、人口千人あたりのオートバイと乗用車の保有台数の関係を示したグラフから、台湾を特定する問題です。各国の経済水準や国土、気候、文化などから交通事情を推測する力が必要です。
<選択肢>
①【誤】
これはインドネシアです。経済発展の過程にあり、安価で機動性に優れたオートバイが国民の足として急激に普及している様子がうかがえます。乗用車の普及はまだこれからという段階です。
②【正】
これは台湾です。1999年、2015年ともに、千人あたりのオートバイ保有台数が500台を超え、4か国の中で圧倒的に多いことがわかります。台湾は人口密度が高く温暖な気候であることから、スクーターを中心としたオートバイが極めて広く普及しており、「オートバイ王国」とも呼ばれます。経済水準も高いため、乗用車保有台数も一定数あり、増加傾向にあります。これらの特徴から②が台湾と判断できます。
③【誤】
これは日本です。先進国として高い乗用車保有台数を示していますが、国土が広大で完全な車社会であるカナダ(④)ほどではありません。オートバイも一定数ありますが、台湾(②)ほどではありません。
④【誤】
これはカナダです。国土が広大で人口密度が低いため、移動に乗用車が不可欠な社会です。乗用車保有台数が最も多く、一方でオートバイの保有台数は極端に少ないという特徴が、グラフから読み取れます。
問3:正解②
<問題要旨>
オーストラリア、中国、フィンランドの3か国の学校制度(学期制、始業時期、長期休暇)の特徴を理解し、図と文章を正しく組み合わせる問題です。各国の地理的な位置(南半球、北半球高緯度など)や文化(旧正月)が休暇の時期にどう影響するかを考えることがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが誤っています。
②【正】
・国と説明文の特定:A「夏季の長期休暇中にクリスマスがある」は南半球のオーストラリア。B「旧正月の時期に長期休暇になる」は中国。C「短い夏における長期休暇を重視する」は高緯度のフィンランドに該当します。
・カレンダーとの対応:ウは12月~1月の長い休みからオーストラリア(A)、イは1月~2月の休みから中国(B)、アは6月~8月の非常に長い休みからフィンランド(C)とそれぞれ対応します。
・以上のことから、「ア-C、イ-B、ウ-A」の組み合わせとなり、②が正解です。
③【誤】
組み合わせが誤っています。
④【誤】
組み合わせが誤っています。
⑤【誤】
組み合わせが誤っています。
⑥【誤】
組み合わせが誤っています。
問4:正解④
<問題要旨>
カカオ、コーヒー、茶の世界の主要生産国の分布を示した地図を読み解く問題です。それぞれの農産物がどのような気候や地域で栽培されているかという知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが誤っています。
②【誤】
組み合わせが誤っています。
③【誤】
組み合わせが誤っています。
④【正】
・図キは西アフリカのギニア湾岸、南米エクアドル、東南アジアのインドネシアに生産が集中しており、カカオの分布と一致します。
・図クはブラジルが突出し、ベトナムやコロンビアが続くコーヒーの分布です。
・図カは中国、インドに加え、注記にあるマテ茶の産地アルゼンチンが含まれることから茶の分布と判断できます。
したがって、カカオがキ、コーヒーがク、茶がカの組み合わせである④が正解です。
⑤【誤】
組み合わせが誤っています。
⑥【誤】
組み合わせが誤っています。
問5:正解①
<問題要旨>
世界各地の自然環境と結びついた伝統的な保存食について、写真と地域を結びつける問題です。問題では地域c(北欧)で見られる保存食が問われています。
<選択肢>
①【正】
これは地域c(北欧)で見られる保存食です。写真①は、タラなどの魚を竿に吊るして寒風で乾燥させて作る干物で、ノルウェーなどで伝統的に作られています。地域cはスカンディナヴィア半島を指しており、この地域の食文化と合致します。
②【誤】
これはメープルシロップで、地域b(北米大陸北東部)の保存食です。
③【誤】
これはジャガイモの凍結乾燥食品(チューニョ)で、地域a(南米アンデス高地)の保存食です。
④【誤】
これは野菜の漬物(キムチ)で、地域d(東アジア、朝鮮半島)の保存食です。
問6:正解③
<問題要旨>
世界の3つの地域(X,Y,Z)における特徴的な地下水の利用形態について、説明文と正しく組み合わせる問題です。各地域の自然環境と、それに適応した伝統的あるいは近代的な水利用の方法を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが誤っています。
②【誤】
組み合わせが誤っています。
③【正】
・X(アメリカ中央部)は、オガララ帯水層の地下水とスプリンクラーを利用した大規模灌漑農業であり、説明文シに合致します。
・Y(北アフリカ~中東)は、カナートなどの地下水路を利用した伝統的な灌漑農業であり、サに合致します。
・Z(オーストラリア中央部)は、大鑽井盆地の被圧地下水を利用した牧畜業であり、スに合致します。
したがって、「X-シ、Y-サ、Z-ス」の組み合わせである③が正解です。
④【誤】
組み合わせが誤っています。
⑤【誤】
組み合わせが誤っています。
⑥【誤】
組み合わせが誤っています。
第3問
問1:正解①
<問題要旨>
南アジアの4地点の気候を推測し、3か月ごとの降水量を示したグラフと正しく結びつける問題です。南アジアの気候を特徴づけるモンスーンの影響と、各地域の地理的条件を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【正】
これは地点エ(スリランカ南西部)のグラフです。地点エは、南西モンスーンの影響を受ける時期(概ね6月~8月)と、モンスーンの交代期にあたる時期(概ね3月~5月、9月~11月)に降水量が多くなります。グラフを見ると、3~5月と9~11月の降水量が特に多くなっており、二つの雨季を持つスリランカ南西部の特徴と一致します。他の選択肢が明らかに異なる地点のものであるため、これが正解となります。
②【誤】
これは地点ウ(バングラデシュ)のグラフです。6月~8月の降水量が突出して多く、世界有数の多雨地域であるこの地の南西モンスーンの影響を典型的に示しています。
③【誤】
これは地点イ(インド内陸部)のグラフです。6月~8月に明瞭な雨季のピークが見られますが、②ほど降水量は多くありません。インド内陸部のサバナ気候などの特徴を示しています。
④【誤】
これは地点ア(パキスタン)のグラフです。年間を通して降水量が極めて少なく、乾燥気候(砂漠気候)の特徴を示しています。
問2:正解②
<問題要旨>
南アジア各国の宗教構成に関する統計表を読み解く問題です。各国の多数派を占める宗教の知識を基に、国名と宗教名を特定する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが誤っています。
②【正】
・まず、宗教カ・キを特定します。表の「インド」の行を見ると、カが79.5%、キが14.4%です 。インドではヒンドゥー教が約8割、イスラームが約1割強を占めるため、カがヒンドゥー教、キがイスラームとわかります。
・次に、国A・B・Cを特定します。
・Aはカ(ヒンドゥー教)が80.7%で多数派なのでネパールです 。
・Bは仏教が69.3%で多数派なのでスリランカです 。
・Cはキ(イスラーム)が96.4%と圧倒的多数なのでパキスタンです 。
・したがって、「ネパール」はA、「イスラーム」はキとなり、この組み合わせである②が正解です。
③【誤】
組み合わせが誤っています。
④【誤】
組み合わせが誤っています。
⑤【誤】
組み合わせが誤っています。
⑥【誤】
組み合わせが誤っています。
問3:正解①
<問題要旨>
インドの首都デリーの衛星画像と風景写真を手がかりに、旧市街と新市街の景観・機能の違いを理解する問題です。
<選択肢>
①【正】
・範囲Gは、道路が不規則に入り組み、建物が密集していることから、歴史的な旧市街(オールドデリー)であることがわかります。一方、範囲Hは、放射状・格子状の整然とした道路網が見られ、計画的に建設された新市街(ニューデリー)です。
・写真サは、イスラーム寺院(モスク)を中心に人々や商店が密集する雑然とした景観で、旧市街(G)のものです。写真シは、広大な敷地に壮大な政府庁舎が建ち並ぶ景観で、新市街(H)のものです。よって、空欄jには「サ」が入ります。
・範囲H(ニューデリー)には、大統領官邸や国会議事堂、中央省庁などが集まっており、インドの行政機能の中枢を担っています。
・したがって、jに「サ」、kに「行政」が入る①が正解です。
②【誤】
kの機能が「商業」となっている点が誤りです。
③【誤】
jの写真が「シ」となっている点が誤りです。
④【誤】
jの写真が「シ」、kの機能が「商業」となっている点が誤りです。
問4:正解①
<問題要旨>
インドの州別人口、州内総生産、デリーへの人口移動を示した地図から、インド国内の経済格差や人口移動のパターンを読み取る問題です。「適当でないもの」を選ぶことに注意が必要です。
<選択肢>
①【誤】
この記述は適当ではありません。図4(人口)と図5(1人当たり州内総生産)を比較します。例えば、南インドには1人当たり州内総生産が「150以上」と高い州がありますが、これらの州の人口の円は、北インドのガンジス川中・下流域の州(1人当たり州内総生産は50~100)の円よりも小さいです。つまり、経済的に豊かな州の人口が必ずしも大きいとは言えず、両者に明確な正の相関関係は見られません。よって、この文は誤りです。
②【正】
図5を見ると、南インドの多くの州が「100~150」や「150以上」の階級に属しているのに対し、北インドでは「50未満」から「150以上」まで様々な階級の州が混在しており、特に「50~100」や「50未満」の州が多く見られます。このことから、北インドの方が南インドよりも州間の経済的な格差が大きいと言えます。
③【正】
図5で、デリーへの人口移動数が50万人以上の州(最も太い矢印の出発点)を見ると、いずれも1人当たり州内総生産が「50~100」や「50未満」の階級に属しています。これは、経済発展の水準が相対的に低い(遅れている)州から、より豊かなデリーへと多くの人々が移動していることを示しています。
④【正】
デリーはインドの首都であり、政治・経済の中心地の一つです。③で見たように、所得水準の低い周辺の州から多くの人々が移動してきていることから、デリーには人々を惹きつけるだけの豊富な就業機会が存在することが、人口移動の大きな要因(プル要因)であると推測できます。
問5:正解④
<問題要旨>
南アジア3か国の製造業出荷額割合とCO2排出量の推移から、バングラデシュに該当するものを特定する問題です。各国の産業構造と経済発展レベルを結びつけて考える必要があります。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが誤っています。
②【誤】
組み合わせが誤っています。
③【誤】
組み合わせが誤っています。
④【正】
・まず、出荷額割合(図6)から国を特定します。パキスタンは「繊維・衣料・皮革」の割合が高いです。インドは近年、機械工業や化学工業なども発展しています。バングラデシュは、安価な労働力を生かした衣料品などの繊維産業が輸出の中心であり、製造業全体に占める割合も極めて高いと考えられます。図を見ると、Qは「繊維・衣料・皮革」の割合が70%近くを占めており、これがバングラデシュの特徴と合致します。Pは化学や機械などの割合が比較的高く、より多様な工業化が進んでいるインドと考えられます。
・次に、CO2排出量(図7)を考えます。経済規模が大きいインドの方が、バングラデシュよりも1人当たりCO2排出量が多いと推測されます。また、工業化の進展とともに排出量は増加する傾向にあります。タはパキスタンよりも排出量が多く、近年は2トンに迫る勢いです。チはパキスタンよりも排出量が少なく、近年増加傾向にあるものの、1トン未満で推移しています。したがって、経済規模の大きいインドがタ、経済発展の段階が比較的低いバングラデシュがチと判断できます。
・以上より、バングラデシュに該当するのは出荷額割合が「Q」、CO2排出量が「チ」の組み合わせであり、④が正解です。
問6:正解③
<問題要旨>
インドにおける衛生環境の改善に関する資料を読み解き、記述内容の正誤を判断する問題です。「適当でないもの」を選ぶことに注意が必要です。
<選択肢>
①【正】
インドの一部では、ヒンドゥー教のカースト制度に由来する浄・不浄の観念から、住居内にトイレを設置することを忌避する文化的背景がありました。また、上下水道のインフラ整備の遅れも、衛生的なトイレが普及しない物理的な要因となっていました。この記述は正しいです。
②【正】
図8のグラフを見ると、2000年から2020年にかけて、都市部の利用率は約50%から約80%へ30ポイント上昇したのに対し、農村部ではほぼ0%から約70%へと70ポイント近くも急上昇しています。したがって、「都市部よりも農村部で、衛生的なトイレの利用率は大幅に改善した」という記述は正しいです。
③【誤】
この記述は適当ではありません。衛生的なトイレの普及は、乳幼児の死亡率低下(下痢などの感染症予防)につながります。一般的に、乳幼児死亡率が低下すると、将来を案じて多くの子どもを産む必要がなくなり、結果として出生率が低下し、人口増加が抑制される方向(多産多死から少産少死へ)に働くとされています。しかし、トイレ普及事業が直接的に「過剰な人口増加の抑制に貢献する」とまで言い切るのは、論理の飛躍があります。衛生環境の改善はまず死亡率の低下に寄与するものであり、人口抑制効果は、その後の社会・経済的な変化を経て間接的にもたらされるものです。
④【正】
屋外での排泄は、特に女性や子どもにとっては犯罪に巻き込まれるリスクを高めるなど、安全上の大きな問題です。誰もが安全に利用できる女性用トイレが増えることは、女性が安心して社会活動に参加するための基盤となり、男女間の生活行動上の制約といった格差の是正に貢献します。この記述は正しいです。
第4問
問1:正解②
<問題要旨>
絶滅危惧種の哺乳類の種数と固有種の割合を示した統計から、国と、その国の自然環境の特徴を述べた文章とを正しく組み合わせる問題です。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが誤っています。
②【正】
・国の特定:
・A:絶滅危惧種の数が212種と非常に多く、そのうち固有種も131種と多い 。これは、豊かな生物多様性を持つ一方で森林破壊などの開発圧力が高いインドネシアの特徴です。
・B:絶滅危惧種69種のうち、固有種が57種と、固有種の割合が極めて高い(約83%) 。これは、大陸から長期間孤立し、独自の生態系が育まれたオーストラリアの特徴です。
・C:絶滅危惧種が4種と極端に少なく、固有種は0種 。これは、国土の大部分が開発され、原生的な自然が少ないオランダの特徴です。
・文章との組み合わせ:
・ア「熱帯雨林の開発が進行中」は、A(インドネシア)に合致します。
・イ「国土のほとんどがすでに開発されている」は、C(オランダ)に合致します。
・ウ「孤立した大陸からなり、独特な生態系」は、B(オーストラリア)に合致します。
・したがって、「A-ア、B-ウ、C-イ」の組み合わせである②が正解です。
③【誤】
組み合わせが誤っています。
④【誤】
組み合わせが誤っています。
⑤【誤】
組み合わせが誤っています。
⑥【誤】
組み合わせが誤っています。
問2:正解④
<問題要旨>
東南アジア4か国の森林面積の割合の変化を示した表から、自然林とタイの正しい組み合わせを選ぶ問題です。各国の地形や経済発展の状況を考慮する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが誤っています。
②【誤】
組み合わせが誤っています。
③【誤】
組み合わせが誤っています。
④【正】
・自然林と人工林の特定:一般に、森林面積に占める割合は自然林の方が人工林よりも大きいです。また、1990年から2020年にかけて、多くの国で開発により自然林(EまたはF)が減少し、植林活動により人工林(EまたはF)が増加する傾向があります。表を見ると、Fは各国で割合が高く、減少傾向にあるのに対し、Eは割合が低く、増加傾向にあります。したがって、Fが自然林、Eが人工林と判断できます。
・タイとラオスの特定:
・ラオス(カまたはキ)は国土の大部分が山がちで、経済開発が比較的遅れていたため、豊かな自然林が残されていると考えられます。
・タイ(カまたはキ)は、ラオスに比べて平野が多く、経済開発も進んでいるため、森林伐採が進んでいると考えられます。
・表を見ると、カは自然林(F)の割合が70.4%(1990年)と非常に高いです 。一方、キは34.5%です 。したがって、森林が豊かなカがラオス、開発が進んでいるキがタイと判断できます。
・以上から、「自然林」はF、「タイ」はキとなり、この組み合わせである④が正解です。
問3:正解③
<問題要旨>
太平洋クロマグロの漁獲量や供給量に関する資料を読み、会話文の中から誤りを含む箇所を指摘する問題です。グラフや表の数値を正確に読み取ることが求められます。
<選択肢>
①【正】
クロマグロは高級食材として人気が高く、その需要を満たすために過剰な漁獲(乱獲)が行われた結果、資源量が減少し、個体数が減少したと考えられています。この記述は正しいです。
②【正】
図1を見ると、1995年頃から世界全体および日本の漁獲量に上限があるような変動が見られ、特に2010年以降は低い水準で推移しています 。これは、太平洋クロマグロの資源枯渇が懸念され、関係する国々が国際的な機関を通じて漁獲量を規制するなどの資源管理措置を導入・強化してきた結果を反映しています。この記述は正しいです。
③【誤】
この記述は誤りです。表2の「輸入量」の内訳を見ると、「ヨーロッパから」「北アフリカから」「西アジアから」とあり、これらはすべて大西洋やその付属海である地中海に面した地域です 。また、「北・中央アメリカから」の輸入の一部も大西洋産である可能性があります。一方、太平洋クロマグロの輸入に関する明確な記述はありません。この表からは、日本が輸入しているクロマグロの多くは大西洋クロマグロであることがわかります。「太平洋クロマグロのほうが多い」という記述は、表の内容と合致しません。
④【正】
天然の未成魚を捕獲して育てる「畜養」では、天然資源に負荷をかけ続けます。一方、人工的にふ化させた卵から育てる「完全養殖」が商業ベースで成功し普及すれば、天然のクロマグロを獲る必要が減るため、天然資源の保護に大きく貢献することが期待されます。この記述は正しいです。
問4:正解③
<問題要旨>
4か国の二酸化炭素(CO2)排出量と、発電に占める化石燃料の割合のデータから、韓国を特定する問題です。各国の経済規模、産業構造、エネルギー政策の特徴に関する知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
これはアメリカ合衆国です。2000年時点で世界最大のCO2排出国でしたが、2018年には微減しています 。シェール革命などもあり、化石燃料による発電割合も減少傾向にあります。
②【誤】
これは中国です。2000年から2018年にかけてCO2排出量が約3倍に激増しており 、「世界の工場」としての急成長ぶりを示しています。石炭火力への依存度が高いため、化石燃料による発電割合も高いです。
③【正】
これは韓国です。急速な工業化を背景に、2000年から2018年にかけてCO2排出量が増加しています 。また、国内にエネルギー資源が乏しいため、発電の多くを化石燃料の輸入に頼っており、その割合も高い水準で推移し、2018年には増加しています 。これらの特徴から③が韓国と判断できます。
④【誤】
これはフランスです。発電量に占める化石燃料の割合が10%未満と極端に低く 、CO2排出量も経済規模に比して少ないです。これは、発電の大部分を原子力に依存しているフランスのエネルギー政策を反映しています。
問5:正解②
<問題要旨>
日本の3つの湿地(地図と写真)と、その湿地の課題や保全の取り組みを説明した文章とを正しく組み合わせる問題です。地図から湿地の地理的環境(都市、農村、自然海岸など)を読み取ることが鍵となります。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが誤っています。
②【正】
・J:地図を見ると、大きな港湾施設と市街地に隣接・囲まれた湿地です。これは都市開発の影響を強く受ける環境にあります。文章「サ」の「湿地を取り囲むように都市開発が進み、河川からの廃棄物の流入や不法投棄がみられた」という記述と合致します。
・K:地図を見ると、内陸の盆地状の地形で、周辺には水田などの農地が広がっています。文章「ス」の「渡り鳥が一部の範囲に集中している。冬季に水田に水を張り、鳥のための環境づくりが進められている」という記述は、このような農村地帯の湿地における取り組みとして考えられます。
・L:地図を見ると、砂州(さす)によって外海と隔てられた大きなラグーン(潟湖)であり、周辺には大きな都市や広大な農地は見られず、自然景観が保たれているようです。文章「シ」の「地形の改変が少ない場所であり、観光と保全の両立が進められている」という記述と合致します。
・したがって、「J-サ、K-ス、L-シ」の組み合わせが正しく、②が正解です。
③【誤】
組み合わせが誤っています。
④【誤】
組み合わせが誤っています。
⑤【誤】
組み合わせが誤っています。
⑥【誤】
組み合わせが誤っています。
問6:正解②
<問題要旨>
地球的課題に対する国際的な取り組みの例の中から、内容が適当でないものを選ぶ問題です。各種条約や国際的なルールの基本的な内容を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【正】
これはワシントン条約(CITES)に関する記述です。絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制することで、乱獲や違法な売買を防ぎ、種の保護を目指すものです。適当な取り組みです。
②【誤】
この記述は適当ではありません。国連海洋法条約では、沿岸から200海里を「排他的経済水域(EEZ)」とし、沿岸国にその中の水産資源などに対する主権的権利を認めています。しかし、資源管理の重要性はEEZ内でも公海(どこの国のEEZにも属さない海域)でも同じです。むしろ、管理が及ばない公海での無秩序な漁業が問題視されています。「公海での漁業を推進する」という部分は、持続的な水産資源の回復という目的と矛盾しており、誤りです。
③【正】
これは気候変動枠組条約やパリ協定などに基づく取り組みです。地球温暖化の主な原因である温室効果ガスの排出量を削減するために、各国が数値目標を設定し、化石燃料の使用を減らして再生可能エネルギーの利用を促進することは、国際的な中心課題の一つです。適当な取り組みです。
④【正】
これはラムサール条約に関する取り組みです。特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地を登録し、その保全と賢明な利用(ワイズユース)を促進するものです。自治体が条例を制定して乱開発を抑制し、条約湿地への登録を目指すことは、条約の趣旨に沿った適当な取り組みです。
第5問
問1:正解①
<問題要旨>
北海道内の3地点(倶知安町、旭川市、釧路市)の気候を推測し、それぞれの雨温図を特定する問題です。日本海側、内陸、太平洋側という立地の違いが気候にどう影響するかを考える必要があります。
<選択肢>
①【正】
・倶知安町:ニセコ地区にあり、北海道の中でも日本海側に位置するため、冬の降雪量が非常に多いことで知られています。雨温図では、冬(12月~2月)の降水量が他の季節に比べて多くなるはずです。図「ア」は、冬の降水量が200mm近くに達する月もあり、夏よりも冬に降水量が多いという特徴を示しています。これは豪雪地帯である倶知安の気候と合致します。
・旭川市:北海道の内陸部に位置するため、夏は暑く、冬は非常に寒くなるという、気温の年較差が大きい大陸性の気候を示します。また、降水量は年間を通して比較的少ないです。図「イ」は、最暖月平均気温が20℃を超え、最寒月は-5℃以下と年較差が大きく、降水量もアやウに比べて少ないです。これが旭川の気候です。
・釧路市:太平洋側に位置するため、夏は寒流である親潮の影響で冷涼で、海霧が発生しやすく日照時間も短いです。冬は晴れる日が多いですが寒さは厳しいです。図「ウ」は、最暖月平均気温が20℃に届かず、夏が冷涼であることがわかります。これが釧路の気候です。
・したがって、「倶知安町-ア、旭川市-イ、釧路市-ウ」の組み合わせである①が正解です。
②【誤】
組み合わせが誤っています。
③【誤】
組み合わせが誤っています。
④【誤】
組み合わせが誤っています。
⑤【誤】
組み合わせが誤っています。
⑥【誤】
組み合わせが誤っています。
問2:正解②
<問題要旨>
ニセコ地区3町の土地利用図と、農畜産物産出額のグラフを結びつける問題です。土地利用の凡例(水田、畑・草地)と、農産物の種類(米、イモ類、生乳・乳製品)を対応させて考えます。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが誤っています。
②【正】
・図1の土地利用を見ると、蘭越町は「水田」のメッシュが広く分布しています。倶知安町は羊蹄山麓などに「畑・草地など」のメッシュが多く見られます。ニセコ町はその中間の特徴を持っています。
・図3の農畜産物産出額を見ると、
・キは「米」の割合が圧倒的に高く、産出額も大きいです。これは水田が多い蘭越町に対応します。
・カは「イモ類」(じゃがいもなど)や「野菜」の割合が高く、畑作が中心であることがわかります。これは畑が多い倶知安町に対応します。
・クは、「イモ類」「野菜」に加え、「生乳・乳製品」の割合も比較的高く、畑作と酪農が行われていることがわかります。これがニセコ町に対応します。
・したがって、「倶知安町-カ、ニセコ町-ク、蘭越町-キ」の組み合わせである②が正解です。
③【誤】
組み合わせが誤っています。
④【誤】
組み合わせが誤っています。
⑤【誤】
組み合わせが誤っています。
⑥【誤】
組み合わせが誤っています。
問3:正解④
<問題要旨>
ニセコ地区の地形図と風景写真、そしてそれらに関する会話文を照合し、内容に誤りを含むものを見つける問題です。地形の成り立ち、歴史、土地利用などを総合的に読み解く力が必要です。
<選択肢>
①【正】
地点aから見えるニセコアンヌプリの山麓は、広くなだらかな斜面をしています。これは、粘り気の少ない溶岩が流れ出して形成された楯状(たてじょう)火山によく見られる地形で、会話の通り「溶岩が流れてできた」と推測することは妥当です。
②【正】
地点bはスキー場のゲレンデ内にあります。図4の地形図を見ると、等高線が外側に張り出す「尾根」の上に位置していることがわかります。また、写真bで羊蹄山が見えていることからもわかるように、この地点から南東方向の羊蹄山を望むことができます。
③【正】
地点cから撮影された倶知安の市街地の写真では、道路が碁盤の目状に整然と区画されていることがわかります。これは、明治時代の北海道開拓において、計画的に街づくりが進められたこと(屯田兵村の街区など)を示す景観です。
④【誤】
この記述は誤りです。地点dの写真で蛇行しながら連なっている木々は、尻別川の「旧河道」に沿って生えている河畔林(かはんりん)です。かつて川が流れていた跡に、自然に樹木が育ったものです。住居を風雪から守るための「防風林」は、通常、屋敷や畑を囲むように、人工的に直線状に植えられることが多いため、この景観を防風林と解釈するのは不適切です。
問4:正解②
<問題要旨>
訪日外国人の滞在データや現地の写真、会話文から、ニセコ地区における観光開発の実態と、それが地域に与える経済的な影響を推測する問題です。
<選択肢>
①【誤】
組み合わせが誤っています。
②【正】
・空欄xの特定:会話文で「写真2のtのように、外国人が多く利用する宿泊施設がみられた」とあります。写真tは近代的な大規模リゾートホテルやコンドミニアムです。これらが集中しているのは、スキー場の麓であり、訪日外国人の空間利用人数が「10000人以上」と最も多いメッシュが集中している範囲Fです。範囲Gは倶知安駅周辺の市街地で、写真sのような昔ながらのビルが見られます。したがって、xにはFが入ります。
・空欄yの特定:会話文では、範囲Fの宿泊料金が非常に高額であるにもかかわらず満室になっている状況が述べられています。このような状況から推測される経済的な影響として最も妥当なのは、「シ 宿泊施設の周辺では、観光による利益を見込んで、土地の価格が上昇するだろうね」です。高い収益が期待できる場所には投資が集中し、地価が高騰するのは一般的な経済現象です。サ(波及効果がない)やス(新たな建設はない)は、活況を呈している状況とは矛盾します。
・したがって、xに「F」、yに「シ」が入る②が正解です。
③【誤】
組み合わせが誤っています。
④【誤】
組み合わせが誤っています。
⑤【誤】
組み合わせが誤っています。
⑥【誤】
組み合わせが誤っています。
問5:正解③
<問題要旨> ニセコ地区における「日本人」と「外国人」の延べ宿泊者数について、年ごとの推移(タ、チ)と、2019年における月別の割合(P、Q)を示したグラフを正しく組み合わせる問題です。国際的なスキーリゾートというニセコ地区の特性を理解し、それぞれの観光客の動向を推測することが求められます。
<選択肢>
①【誤】 組み合わせが誤っています。
②【誤】 組み合わせが誤っています。
③【正】 この問題を解く鍵は、ニセコが「国際的なスキーリゾート」であるという特性から、日本人と外国人観光客の動向の違いを推測することです。
【1. 月別割合グラフ(PとQ)の分析】 ・外国人観光客の目的は主にスキーであるため、滞在は冬(12月~2月)に極端に集中するはずです。 ・グラフP:冬の3か月だけで全体の6割以上を占める「冬に極端に偏った」グラフです。 → これが【外国人】の動向です。 ・グラフQ:冬と夏(7月~8月)の両方にピークがあり、年間を通して分散しています。 → これが【日本人】の動向です。
【2. 年別推移グラフ(タとチ)の分析】 ・外国人観光客の動向は、国内客に比べて国際情勢(近年のインバウンドブームやコロナ禍など)の影響をより強く受け、変動が激しくなります。 ・グラフチ:2019年にかけて急成長し、コロナ禍でほぼゼロまで激減しています。この「急変動」は国際観光の特徴を反映しています。 → これが【外国人】の推移です。 ・グラフタ:チよりも宿泊者数の絶対数が多く、変動も比較的穏やかです。国内の安定した需要に支えられていると考えられます。 → これが【日本人】の推移です。
【3. 結論】 以上の分析から、外国人観光客に対応するのは「推移グラフ:チ」と「月別割合グラフ:P」の組み合わせです。したがって、③が正解となります。
④【誤】 組み合わせが誤っています。
問6:正解②
<問題要旨>
観光地が抱える住民の意見に対し、行政が取りうる施策案と、その効果を測るための指標案の組み合わせとして、適当でないものを選ぶ問題です。課題と解決策、評価方法の論理的なつながりを見極める必要があります。
<選択肢>
①【正】
「自然や景観が壊れる」という住民意見(課題)に対し、「開発業者に住民説明会の開催を要求する」という施策案は、住民の意向を開発に反映させるための直接的な手段です。その施策が機能しているかを測る指標として「説明会の開催回数と参加者数」を見ることは、客観的で妥当です。
②【誤】
この組み合わせは適当ではありません。「観光客の増加により地域内の交通に支障が出る」という課題は、主に交通渋滞や公共交通の混雑を指します。これに対し、施策案として「需要の季節的な偏りに対応した事業者の誘致」(例:閑散期にイベントを誘致するなど)を挙げていますが、これは交通渋滞の直接的な解決策というよりは、観光需要の平準化を目指すものです。さらに、指標案として「地域内交通のキャッシュレス化率」を挙げていますが、キャッシュレス化は運賃支払いの利便性向上にはつながりますが、交通渋滞や混雑の緩和に直接結びつく指標とは言えません。課題と施策、指標の間に論理的なズレがあります。
③【正】
「地域の農産物を観光客に売り込みたい」という住民意見(希望)に対し、「地元産農産物の加工・販売に対する補助」という施策案は、地産地消や6次産業化を推進する上で有効です。その効果を測る指標として「地域産品の売上額」を見ることは、施策の経済的効果を直接的に評価するものであり、妥当です。
④【正】
「観光産業で働く外国人を受け入れたい」という住民意見(希望)に対し、「各国の文化や言語を学べる場の創出」という施策案は、外国人労働者との円滑なコミュニケーションや多文化共生を促進するために有効です。その効果(ソフト面の成果)を測る指標として「住民の各国への親しみ度」といった意識調査を用いることは、施策の目的と合致しており、妥当な評価方法の一つです。