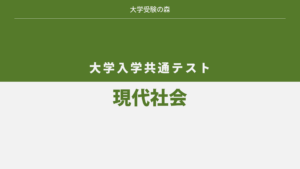解答
解説
第1問
問1:正解⑦
<問題要旨>
青年期における自我の形成と、自己実現に向けた現代の課題に関する問題です。エリクソンのライフサイクル論や、マズローの欲求階層説といった基本的な概念の理解が問われています。
<選択肢>
①【誤】アパシーは、政治的無関心や社会的無気力を指す言葉であり、青年が自らの生き方を見いだした状態ではありません。むしろ、目標を見失った状態を表します。
②【誤】アイデンティティの確立とは、自分自身の連続性や他者との違いを認識し、社会における自己の役割や位置づけを明確にすることです。拡散は、そのアイデンティティが未確立で混乱した状態を指します。
③【誤】マズローの欲求階層説では、自己実現の欲求は最も高次の欲求とされていますが、それが社会の発展に直接的に比例するわけではありません。個人の内面的な成熟に関わる問題です。
④【誤】モラトリアムは、社会的な責任や義務を一時的に猶予され、自己を探求する期間を指します。アイデンティティを確立した青年が、猶予期間なしに社会参加することとは逆の状態です。
⑤【誤】ピアグループは、年齢や関心が近い仲間集団を指します。重要な他者(親や教師など)の影響から完全に自立しているわけではなく、相互に影響を与え合う関係です。
⑥【誤】ボランティア活動は、自己実現や社会貢献につながる有意義な活動ですが、それが唯一の手段というわけではありません。学業、文化活動、職業など、自己実現の道は多様です。
⑦【正】エリクソンは、青年期を「アイデンティティ確立対アイデンティティ拡散」の時期と位置づけました。この時期に、自分は何者であり、何をすべきかという問いに向き合い、自己を確立することが重要な発達課題であるとされます。
⑧【誤】自己実現の欲求は、他者からの評価や称賛を求める「承認の欲求」とは異なります。承認の欲求が満たされた後、さらに高次の欲求として現れるのが自己実現の欲求です。
問2:正解②
<問題要旨>
世論の形成過程と、それを動かす要因についての問題です。特に、マスメディアが人々の意見や投票行動に与える影響(アナウンスメント効果)についての理解が問われています。
<選択肢>
①【誤】「沈黙の螺旋」理論は、自分の意見が少数派だと感じた人々が孤立を恐れて沈黙し、結果的に多数派の意見がさらに優勢になるという現象です。少数意見が影響力を増すという記述は逆です。
②【正】アナウンスメント効果とは、選挙前の情勢報道などが有権者の投票行動に影響を与える現象の総称です。特に、優勢と報じられた候補者に票が集まる現象を「バンドワゴン効果(便乗効果)」と呼びます。
③【誤】「議題設定機能(アジェンダ設定機能)」とは、マスメディアが特定の争点を繰り返し報道することで、人々がそれを重要な問題だと認識するようになる働きを指します。報道内容を無批判に受け入れることとは少し意味合いが異なります。
④【誤】オピニオンリーダーは、身近な集団内で人々の意見形成に影響を与える人物を指します。政治家や評論家など、社会的に著名な人物に限定されるわけではありません。
問3:正解④
<問題要旨>
さまざまな社会思想家の思想、特に社会契約説に関する問題です。ホッブズ、ロック、ルソーのそれぞれの思想内容を正確に区別できているかがポイントです。
<選択肢>
①【誤】「万人の万人に対する闘争」という言葉で自然状態を表現したのはホッบズです。彼は、この混乱状態を避けるために、人々が自然権を国家(主権者)に全面譲渡すべきだと考えました。
②【誤】抵抗権(革命権)を明確に主張したのはロックです。彼は、政府が人民の信託に反して生命や財産を侵害した場合には、人民は政府に抵抗し、新しい政府を樹立する権利を持つとしました。
③【誤】一般意志(普遍意志)という概念を提唱したのはルソーです。彼は、個人の特殊な利害(特殊意志)の総和である全体意志とは区別され、共同体全体の共通の利益を目指す一般意志にこそ主権があるべきだと主張しました。
④【正】ロックは、人間が生まれながらに持つ権利(自然権)として生命、自由、財産を挙げ、これらは国家成立以前から存在し、誰もが保障されるべきものだと考えました。国家の役割は、この自然権をより確実に保障することにあるとしました。
問4:正解⑧
<問題要旨>
民主主義の基本原理と、それに基づく政治制度に関する問題です。リンカーンの演説や権力分立の思想など、民主政治の基礎知識が問われています。
<選択肢>
①【誤】法の支配とは、専断的な権力者の支配ではなく、全ての人が公平な法に従うべきだという原理です。権力者も法の下にあるという点で、「人による支配」と対置されます。
②【誤】三権分立を提唱したのはモンテスキューです。彼は『法の精神』の中で、国家権力を立法・行政・司法の三つに分け、抑制と均衡(チェック・アンド・バランス)を図ることで権力の濫用を防ぐべきだと説きました。
③【誤】直接民主制は、国民が直接政治的意思決定に参加する制度です。一方、国民が選んだ代表者を通じて政治を行うのは間接民主制(議会制民主主義)です。
④【誤】普通選挙の原則は、一定の年齢に達した全ての国民に選挙権を保障するものです。財産や納税額によって選挙権を制限するのは制限選挙です。
⑤【誤】多数決は、意思決定を効率的に行うための重要な原理ですが、常に正しいとは限りません。少数意見の尊重も、民主主義の重要な要素です。
⑥【誤】デュー・プロセス・オブ・ロー(法の適正な手続き)は、法の内容だけでなく、その適用手続きも公正でなければならないという原則です。主に刑事手続きにおいて、人権保障の観点から重要視されます。
⑦【誤】ワイマール憲法は、世界で初めて社会権(生存権)を保障した画期的な憲法として知られていますが、ファシズムの台頭を許してしまった歴史的経緯もあります。
⑧【正】「人民の、人民による、人民のための政治」は、エイブラハム・リンカーンがゲティスバーグ演説で述べた言葉で、国民主権という民主主義の理念を最も簡潔に表現したものとして知られています。
問5:正解①
<問題要旨>
日本の選挙制度、特に衆議院議員総選挙で採用されている小選挙区比例代表並立制の特徴に関する問題です。小選挙区制と比例代表制のそれぞれの長所・短所を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【正】小選挙区比例代表並立制では、有権者は小選挙区の「候補者名」と、比例代表の「政党名」をそれぞれ記入して投票します。これにより、人物本位の選択と政党本位の選択を同時に行うことができます。
②【誤】小選挙区で落選した候補者が、比例代表で復活当選することは可能です。これを重複立候補制度といい、多くの候補者が利用しています。
③【誤】小選挙区制は、一つの選挙区から一人しか当選しないため、大政党に有利な制度であり、二大政党制を促進しやすいとされています。死票が多くなるという短所があります。
④【誤】比例代表制は、各政党の総得票数に応じて議席を配分するため、小選挙区制に比べて死票が少なく、少数政党でも議席を獲得しやすいという特徴があります。多様な民意を反映しやすい反面、多くの小政党が乱立し、政権が不安定になりやすいという指摘もあります。
問6:正解②
<問題要旨>
日本の国会(立法府)の地位と権能についての問題です。衆議院と参議院の関係や、国会の持つ重要な権限についての正確な知識が求められます。
<選択肢>
①【誤】内閣不信任決議を議決できるのは衆議院のみです。この決議が可決された場合、内閣は10日以内に衆議院を解散するか、総辞職しなければなりません。参議院には問責決議の権限がありますが、法的拘束力はありません。
②【正】国会は「国権の最高機関」と憲法で定められており、その中心的な役割は、法律を制定する立法権です。また、内閣総理大臣の指名、予算の議決、条約の承認、弾劾裁判所の設置など、多くの重要な権限を持っています。
③【誤】法律案や予算、条約の承認について衆議院と参議院の議決が異なった場合、両院協議会で協議されますが、合意に至らない場合は衆議院の議決が優先されます(衆議院の優越)。常に両院の議決が一致する必要はありません。
④【誤】国会議員には「不逮捕特権」があり、国会の会期中は、院外での現行犯を除き、その議院の許諾がなければ逮捕されません。また、院内での発言・表決について院外で責任を問われない「免責特権」もあります。
問7:正解③
<問題要旨>
日本の内閣(行政府)の役割と、議院内閣制の仕組みに関する問題です。国会と内閣の関係、特に内閣総理大臣の権限や内閣の連帯責任について問われています。
<選択肢>
①【誤】内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決によって指名されます。国民が直接選挙で選ぶわけではありません。これは議院内閣制の大きな特徴です。
②【誤】国務大臣の過半数は、国会議員でなければならないと憲法で定められています。したがって、全員を民間から任命することはできません。
③【正】議院内閣制は、内閣が国会の信任に基づいて成立し、国会に対して連帯して責任を負う制度です。内閣は行政権の行使について、一体として国会に責任を負います。
④【誤】法律や予算を国会に提出するのは、内閣の重要な権能の一つです(内閣の法律案・予算案提出権)。立法は国会の専権事項ですが、その議案を提出する権限は内閣が持っています。
第2問
問1:正解①
<問題要旨>
人権思想の歴史的発展と、現代における人権保障の課題に関する問題です。特に、人権が持つ普遍性と、それが国家の枠組みを超える考え方(自然権思想)を理解しているかが問われています。
<選択肢>
①【正】人権は、人間が生まれながらにして持つ、国家や憲法以前に存在する普遍的な権利(自然権)であると考えられています。憲法は、この人権を確認し、保障するために制定されるものです。この考え方は、近代憲法の基本的人権尊重の根底にあります。
②【誤】国際人権規約は、国際連合で採択された条約であり、締約国に対して人権保障の義務を課すものです。国内法と同様の効力を持つ場合もありますが、あくまで国家間の合意に基づくものであり、全ての国家の憲法より常に優先されるわけではありません。
③【誤】「公共の福祉」による人権の制約は、人権相互の衝突を調整するために認められるものであり、無制限ではありません。その制約は必要最小限度でなければならず、人権の本質的な内容を侵すことは許されません。
④【誤】プライバシーの権利や環境権などの「新しい人権」は、社会の変化に対応して主張されるようになった重要な権利です。しかし、これらの権利が常に経済的な権利(社会権)よりも優先されるという一般的な原則はありません。事案ごとに比較衡量されます。
問2:正解②
<問題要旨>
日本国憲法における平等権(法の下の平等)の具体的な内容に関する問題です。どのような差別が禁止されているか、また、平等に関連する訴訟の判例についての知識が問われています。
<選択->
①【誤】憲法第14条は、法の下の平等を定めていますが、絶対的な平等を保障するものではありません。合理的な理由があれば、区別して取り扱うこと(合理的差別)は許されると解されています。例えば、選挙権の年齢制限などがこれにあたります。
②【正】尊属殺重罰規定は、親殺しの刑罰を普通殺人よりも重く定めた刑法の規定でした。最高裁判所は、この規定が、普通殺人と比べて不合理な差別であるとし、法の下の平等を定めた憲法第14条に違反するとして無効と判断しました。
③【誤】議員定数不均衡問題は、選挙区間の人口差によって一票の価値に格差が生じる問題であり、主に「投票価値の平等」の問題として争われます。個人の信条による差別とは直接関係ありません。
④【誤】アファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)は、過去の差別によって不利益を被ってきた人々に対し、実質的な機会均等を実現するために特別な措置を講じるものです。これは「逆差別」であるとの批判もありますが、形式的な平等ではなく実質的な平等を達成する手段として議論されます。
問3:正解①
<問題要旨>
日本国憲法で保障される精神的自由権のうち、特に学問の自由に関する問題です。大学の自治との関連や、過去の判例についての理解が試されています。
<選択肢>
①【正】東大ポポロ事件の最高裁判所判決では、大学における学問の自由と自治を認めつつも、大学内での政治活動が学生の本来の目的を逸脱し、社会一般の政治活動と変わらないレベルに達した場合には、警察の介入も許されると判断しました。これにより、大学の自治には一定の限界があることが示されました。
②【誤】思想・良心の自由(憲法第19条)は、内心にとどまる限り絶対的に保障されます。しかし、それが外部的な行為として現れた場合には、公共の福祉による制約を受けることがあります。
③【誤】信教の自由(憲法第20条)は、国が特定の宗教を優遇したり、宗教教育を強制したりすることを禁じる政教分離原則によって支えられています。国が宗教団体を支援することは、この原則に抵触する可能性があります。
④【誤】表現の自由(憲法第21条)には、報道の自由や取材の自由も含まれると解されています。国家権力が報道内容を事前に審査し、発表を禁止する「検閲」は、憲法で絶対に禁止されています。
問4:正解⑦
<問題要旨>
社会権(生存権)の法的性格と、それに関連する重要な訴訟の判例に関する問題です。プログラム規定説や朝日訴訟、堀木訴訟といったキーワードの正確な理解がポイントです。
<選択肢>
①【誤】ワイマール憲法は世界で初めて生存権を明記した憲法ですが、その保障は抽象的なものでした。
②【誤】社会権は、国家に対して積極的な配慮や給付を求める権利であり、国家からの干渉を排除する自由権とは性格が異なります。
③【誤】朝日訴訟の最高裁判決は、生存権について、国の財政事情などを考慮して政策的に判断されるべきものとしました。
④【誤】堀木訴訟では、障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止が争われましたが、最高裁はこれを合憲と判断しました。
⑤【誤】プログラム規定説は、憲法25条の規定は国の政治的・道義的責務を定めたもので、個々の国民に具体的な権利を保障したものではないとする考え方です。
⑥【誤】国民年金や医療保険は、社会権を具体化するための社会保障制度の中心的な柱です。
⑦【正】憲法第25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めています。この生存権の保障を実現するため、国は生活保護制度や社会保険、公衆衛生などの社会保障政策を推進する義務を負います。
⑧【誤】教育を受ける権利は、社会権の一つとして重要な権利ですが、義務教育の無償の範囲は授業料に限られ、教科書代や給食費などは含まれないと解されています。
問5:正解③
<問題要旨>
労働者の権利である労働基本権(労働三権)の具体的な内容に関する問題です。団結権、団体交渉権、団体行動権のそれぞれが何を保障しているのかを正確に理解する必要があります。
<選択肢>
①【誤】団結権は、労働者が使用者と対等な立場で交渉するために労働組合を結成する権利です。一人で交渉する権利も当然保障されますが、団結権の核心は組合を結成する権利にあります。
②【誤】団体行動権(争議権)は、ストライキなど、要求を貫徹するために争議行為を行う権利です。ただし、この権利は法律で一定の制約を受けることがあります。例えば、公務員の一部には争議権が認められていません。
③【正】団体交渉権は、労働組合が使用者と、賃金や労働時間などの労働条件について交渉する権利です。使用者は、正当な理由なくこの交渉を拒否することはできず、誠実に交渉に応じる義務(誠実交渉義務)を負います。
④【誤】不当労働行為とは、使用者が労働者の団結権などを妨害する行為を指し、法律で禁止されています。労働組合が会社の経営方針そのものに介入することは、原則として団体交渉の対象外とされています。
問6:正解④
<問題要旨>
刑事手続における被疑者・被告人の権利保障(デュー・プロセス)に関する問題です。令状主義や黙秘権、弁護人依頼権など、日本の刑事司法の基本原則が問われています。
<選択肢>
①【誤】令状主義の例外として、現行犯逮捕の場合は逮捕状なしで逮捕が可能です。また、逮捕後に捜索・差押えを行う場合にも令状が不要な場合があります。
②【誤】黙秘権は、被疑者・被告人が自己に不利益な供述を強要されない権利です。この権利の行使自体を、本人にとって不利益な証拠とすることは許されません。
③【誤】身体の拘束を受けている被疑者・被告人は、国選弁護人を選任してもらうことができます。資力がない場合でも弁護人による援助を受ける権利が保障されています。
④【正】「疑わしきは被告人の利益に」とは、刑事裁判における鉄則です。検察官が提出した証拠によって、合理的な疑いを差し挟む余地がない程度にまで有罪であると証明されない限り、裁判所は被告人に対して無罪の判告をしなければなりません。
問7:正解④
<問題要旨>
情報化社会の進展に伴う課題と、それに対応するための法整備に関する問題です。個人情報保護、情報公開、知的財産権など、現代社会における重要なテーマが含まれています。
<選択肢>
①【誤】情報公開制度は、国や地方公共団体が保有する行政文書を、国民の請求に応じて原則として公開する制度です。国民の「知る権利」にこたえ、行政の透明性を確保することを目的としています。プライバシー情報など、公開されない例外もあります。
②【誤】個人情報保護法は、事業者が個人情報を扱う際のルールを定めた法律です。個人のプライバシー保護が目的であり、情報の自由な利用を最優先するものではありません。
③【誤】著作権は、文芸、学術、美術、音楽などの著作物を創作した著作者に与えられる権利で、財産的な権利(著作財産権)と人格的な権利(著作者人格権)からなります。原則として、著作者の死後70年まで保護されます。
④【正】デジタル・デバイド(情報格差)とは、インターネットなどの情報通信技術(ICT)を利用できる人とできない人との間に生じる、経済的・社会的な格差を指します。高齢や障害、所得、地理的条件などがその要因とされています。
第3問
問1:正解①
<問題要旨>
市場経済の基本的な仕組みである価格メカニズム(市場メカニズム)についての問題です。アダム・スミスの「見えざる手」の考え方や、需要と供給の関係についての理解が問われています。
<選択肢>
①【正】市場経済において、価格は需要と供給の関係によって変動します。この価格の動きが、生産者や消費者の行動を導き、社会全体で資源が効率的に配分されるように機能します。アダム・スミスは、この働きを「見えざる手」と表現しました。
②【誤】需要量が供給量を上回る「超過需要」の状態では、価格は下落するのではなく上昇します。価格が上昇することで、需要が減少し供給が増加し、需給の均衡が図られます。
③【誤】独占や寡占が進んだ市場では、少数の企業が価格を自由に設定できる(価格支配力を持つ)ため、価格メカニズムが有効に機能しにくくなります。これを「市場の失敗」の一つと呼びます。
④【誤】計画経済(社会主義経済)は、国家が生産量や価格を計画的に決定する経済システムです。個々の生産者や消費者が自由に決定する市場経済とは対極の考え方です。
問2:正解④
<問題要旨>
現代の企業形態、特に株式会社の仕組みと資金調達の方法に関する問題です。株式、有限責任、企業の社会的責任(CSR)といった基本用語の理解が求められます。
<選択肢>
①【誤】企業の社会的責任(CSR)は、企業が利益を追求するだけでなく、環境保護、人権尊重、消費者保護、地域社会への貢献など、幅広い社会的な責任を果たすべきだという考え方です。法令遵守(コンプライアンス)はその一部に含まれます。
②【誤】株式会社の株主は、所有する株式の引き受け価額を限度として責任を負う「有限責任」を負います。会社の債務に対して、個人の全財産で責任を負うのは無限責任社員です。
③【誤】企業が事業拡大などのために行う設備投資は、企業の資本(自己資本)や金融機関からの借入れ、社債の発行などで賄われます。家計の消費は、企業の売上にはなりますが、直接的な投資資金ではありません。
④【正】株式会社は、株式を発行することによって、投資家から広く資金を調達します。投資家は株主となり、株主総会での議決権や、利益の一部を配当として受け取る権利などを持ちます。
問3:正解③
<問題要旨>
市場経済がうまく機能しない「市場の失敗」の事例と、それに対する政府の役割についての問題です。公共財、外部不経済、情報の非対称性といった概念を理解しているかがポイントです。
<選択肢>
①【誤】公園や警察、消防のように、対価を支払わない人も利用でき(非排除性)、多くの人が同時に利用できる(非競合性)財やサービスを「公共財」といいます。これらは利益を上げにくいため、市場に任せると供給が不足しがちになり、政府(税金)によって供給されることが多いです。
②【誤】売り手と買い手の間に情報の量や質に格差がある状態を「情報の非対称性」といいます。例えば、中古車市場や医療サービスなどが挙げられ、これも市場の失敗の一因となります。
③【正】ある経済主体の行動が、市場を介さずに他の経済主体に不利益を与えることを「外部不経済」といいます。工場の生産活動によって発生する公害は、その典型例です。この場合、企業は公害対策の費用を十分に負担しないため、政府が税金を課す(ピグー税)などの介入を行うことがあります。
④【誤】独占禁止法は、公正で自由な競争を促進するための法律です。特定の企業による市場の独占や、企業間の不公正な取引(カルテルなど)を規制し、消費者の利益を守ることを目的としています。
問4:正解②
<問題要旨>
経済のグローバル化と、それに伴う多国籍企業の役割や課題に関する問題です。国際分業のメリットや、途上国が抱える問題についての知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】多国籍企業が、人件費の安い発展途上国に生産拠点を移すことで、現地の雇用機会が創出されるというメリットがあります。国内の雇用が失われる(産業の空洞化)というデメリットと表裏一体の関係です。
②【正】多国籍企業は、世界中に生産・販売拠点を持ち、それぞれの国や地域の比較優位(労働力、技術、資源など)を活かして国際的な分業体制を構築し、利益の最大化を図っています。
③【誤】発展途上国の中には、先進国からの投資を呼び込むために、法人税率を引き下げたり、労働・環境基準を緩和したりする動きが見られます。これを「底辺への競争」と呼び、問題視されています。
④【誤】フェアトレードは、発展途上国の生産者から、その労働や産物に見合った適正な価格で商品を継続的に購入することで、生産者の生活改善や自立を支援する貿易の仕組みです。
問5:正解①
<問題要旨>
日本銀行が担う金融政策の役割と具体的な手段に関する問題です。公開市場操作(オープン・マーケット・オペレーション)や、景気との関連を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【正】日本銀行は、景気が過熱している(インフレーションの懸念がある)と判断した場合、金融引き締め政策をとります。公開市場操作(売りオペ)によって市中の金融機関から国債などを買い戻し、市場に出回る資金量を吸収することで、金利の上昇を促し、経済活動を抑制しようとします。
②【誤】国債や地方債を発行して、公共事業などを行うのは政府の役割(財政政策)です。日本銀行は金融政策を担い、直接国債を発行することはありません。
③【誤】預金準備率操作は、民間金融機関に日本銀行へ預け入れることを義務付けている預金の割合を操作する政策です。不況時には、この準備率を引き下げて、金融機関が貸し出しに回せる資金を増やし、金融緩和を図ります。
④【誤】ゼロ金利政策や量的緩和政策は、不況(デフレーション)に対応するための金融緩和策です。市場に大量の資金を供給することで、金利を極めて低い水準に抑え、企業や個人の経済活動を活発にすることを目的とします。
問6:正解③
<問題要旨>
国の財政の仕組みと、税金の種類に関する問題です。直接税と間接税の区別や、所得再分配機能についての理解が求められます。
<選択肢>
①【誤】財政の三大機能は、「資源配分の調整」「所得の再分配」「経済の安定化」です。金融の安定化は、主に日本銀行が担う金融政策の役割です。
②【誤】所得税や法人税のように、納税者と担税者(税を実質的に負担する人)が一致する税を「直接税」といいます。消費税のように、納税者(事業者)と担税者(消費者)が異なる税は「間接税」です。
③【正】所得税で採用されている累進課税制度は、所得が高い人ほど高い税率が適用される仕組みです。これにより、高所得者からより多くの税を徴収し、社会保障などを通じて低所得者へ再分配することで、経済的な格差を是正する機能(所得再分配機能)を果たしています。
④【誤】建設国債は、道路や橋など、公共事業の財源として発行される国債です。一方、赤字国債(特例国債)は、歳入不足を補うために発行されるもので、その発行には特例法の制定が必要です。
問7:正解⑥
<問題要D>
日本の社会保障制度の全体像と、その4つの柱(社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生)についての問題です。特に、中心的な役割を担う社会保険の種類と特徴が問われています。
<選択肢>
①【誤】日本の社会保障制度は、「社会保険」「公的扶助」「社会福祉」「公衆衛生」の4つの柱から成り立っています。
②【誤】生活保護制度は「公的扶助」にあたります。これは、生活に困窮する人々に対し、国が最低限度の生活を保障する最後のセーフティネットです。
③【誤】介護保険は、高齢化の進展に対応するため2000年に導入された制度です。財源は、40歳以上の国民が支払う保険料と税金で賄われています。
④【誤】児童福祉や障害者福祉、母子福祉などは、「社会福祉」に含まれます。社会的に弱い立場にある人々が自立した生活を送れるよう支援することを目的としています。
⑤【誤】国民皆保険・国民皆年金は、全ての国民が何らかの公的な医療保険と年金保険に加入している状態を指し、日本の社会保障制度の大きな特徴です。
⑥【正】社会保険は、病気、高齢、失業、労働災害、介護といった生活上のリスクに備え、加入者が保険料を出し合い、必要な人が給付を受けられる相互扶助の仕組みです。具体的には、「医療保険」「年金保険」「雇用保険」「労災保険」「介護保険」の5種類があります。
⑦【誤】後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者が加入する独立した医療保険制度です。
第4問
問1:正解⑥
<問題要旨>
第二次世界大戦後の冷戦期の国際関係史に関する問題です。東西両陣営の対立を示す具体的な出来事の知識が問われています。
<選択肢>
①【誤】北大西洋条約機構(NATO)は、アメリカを中心とする西側陣営の軍事同盟です。
②【誤】ワルシャワ条約機構は、ソ連を中心とする東側陣営が、NATOに対抗して結成した軍事同盟です。
③【誤】マーシャル・プランは、第二次世界大戦後にアメリカが西ヨーロッパ諸国の経済復興を支援した計画です。
④【誤】ベルリンの壁は、東ドイツが西ベルリンへの人口流出を防ぐために建設したもので、東西冷戦の象徴でした。
⑤【誤】キューバ危機は、ソ連がキューバに核ミサイル基地を建設したことをめぐり、米ソ間の核戦争の寸前まで至った事件です。
⑥【正】朝鮮戦争は、第二次世界大戦後に南北に分断された朝鮮半島で起こった、北朝鮮(ソ連・中国が支援)と韓国(アメリカ中心の国連軍が支援)との間の戦争です。東西両陣営が直接的・間接的に関与し、冷戦が熱い戦争(熱戦)へと転化した代表的な事例です。
⑦【誤】ベトナム戦争も、南北ベトナムの統一をめぐる代理戦争の側面を持ちますが、朝鮮戦争の後、1960年代から70年代にかけて続いた戦争です。
問2:正解④
<問題要旨>
国際連合の組織と機能に関する問題です。特に、主要機関の役割と権限について正確に理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】安全保障理事会(安保理)は、世界の平和と安全の維持に主要な責任を負う機関です。常任理事国(米、英、仏、露、中)と、任期2年の非常任理事国10か国で構成されます。
②【誤】総会は、全加盟国で構成され、一国一票の投票権を持ちます。世界の様々な問題について討議し、勧告を採択しますが、その決議に法的な拘束力はありません。
③【誤】国際司法裁判所(ICJ)は、国家間の法律的な紛争を裁判によって解決する国連の主要な司法機関です。ただし、その判決に従うかどうかは当事国の同意が前提となります。
④【正】経済社会理事会は、経済、社会、文化、教育、保健など、幅広い分野で国際協力を促進する役割を担う国連の主要機関です。専門機関である世界保健機関(WHO)や国連教育科学文化機関(UNESCO)などと連携しながら活動しています。
問3:正解④
<問題要旨>
国際法の性質と、その担い手である国家についての問題です。国際法の成立根拠(条約と国際慣習法)や、国家の三要素についての基礎知識が問われています。
<選択肢>
①【誤】国際法には、世界全体を統括する中央政府や、法を強制的に執行する警察・軍隊のような統一的な機関が存在しません。そのため、国内法と比べて強制力が弱いとされています。
②【誤】国際司法裁判所(ICJ)が紛争を裁判するためには、紛争当事国双方の同意(付託への同意)が必要です。一方の国が拒否すれば、裁判は開かれません。
③【誤】国家が成立するための三要素は、「領域(領土・領海・領空)」「国民」「主権(統治権)」です。国連への加盟は国家承認の指標にはなりますが、成立の必須要件ではありません。
④【正】国際法の主な法源(成立形式)は、国家間の文書による合意である「条約」と、長年にわたる国家間の慣行が法的な拘束力を持つと認識されるようになった「国際慣習法」の二つです。
問4:正解②
<問題要旨>
地球環境問題とその対策に関する国際的な取り組みについての問題です。オゾン層保護、気候変動、生物多様性など、各テーマに対応する国際条約や会議の知識が求められます。
<選択肢>
①【誤】ワシントン条約は、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制するための条約です。
②【正】モントリオール議定書は、オゾン層を破壊するフロンガスなどの特定物質の生産と消費を規制することを目的とした国際的な取り決めです。この取り組みにより、オゾン層の破壊は抑制されつつあります。
③【誤】京都議定書は、気候変動枠組条約に基づき、先進国に対して温室効果ガスの削減目標を定めたものです。発展途上国には具体的な削減義務が課せられていませんでした。
④【誤】ラムサール条約は、水鳥の生息地として国際的に重要な湿地を保全するための条約です。
問5:正解①
<問題要旨>
世界の経済格差の問題である「南北問題」と、それに対する国際協力のあり方に関する問題です。政府開発援助(ODA)や非政府組織(NGO)の役割が問われています。
<選択肢>
①【正】発展途上国(南)と先進工業国(北)の間の経済的な格差を「南北問題」といいます。この問題の背景には、植民地支配の歴史や、途上国が工業製品を高く買い、自国の安価な一次産品を売らざるを得ないといった貿易構造の問題などがあります。
②【誤】政府開発援助(ODA)は、先進国政府が発展途上国の開発を支援するために行う公的な資金協力や技術協力です。二国間援助と、国際機関を通じた多国間援助があります。
③【誤】近年、発展途上国の中でも、急速な経済成長を遂げた国・地域(新興工業経済地域:NIESなど)が現れ、途上国間の経済格差も拡大しています。これを「南南問題」といいます。
④【誤】非政府組織(NGO)や非営利組織(NPO)は、政府とは異なる民間の立場で、貧困、環境、人権、災害支援など、様々な分野で国際的に活動しています。
問6:正解②
<問題要旨>
冷戦終結後の世界で多発する地域紛争、特に民族問題やそれに伴う難民問題に関する問題です。
<選択肢>
①【誤】パレスチナ問題は、ユダヤ人とアラブ人との間の宗教的・民族的な対立であり、イスラエル建国をめぐって現在も続いています。
②【正】ある国家の多数派民族とは異なる、言語、宗教、文化などを持つ少数派の集団を「少数民族(エスニック・マイノリティ)」と呼びます。彼らに対する差別や抑圧が、紛争や人権問題の原因となることがあります。
③【誤】ユーゴスラビア紛争は、冷戦終結後に連邦が解体する過程で、セルビア人、クロアチア人、イスラム教徒などが互いに独立や領土をめぐって争った、複雑な民族紛争でした。
④【誤】難民とは、人種、宗教、国籍、政治的意見などを理由に迫害を受けるおそれがあり、自国外に逃れた人々を指します。彼らを保護し、支援する中心的な役割を担っているのが国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)です。
問7:正解③
<問題要旨>
国際社会における日本の役割と貢献に関する問題です。憲法との関係で議論されることが多い、PKO協力やODAのあり方が問われています。
<選択肢>
①【誤】日本の政府開発援助(ODA)は、かつては世界トップクラスの拠出額でしたが、近年は減少傾向にあり、GNI(国民総所得)比で見ると、国際的な目標(0.7%)を大きく下回っています。
②【誤】日本の国際平和協力法(PKO協力法)では、自衛隊の海外派遣にあたり、紛争当事者間の停戦合意や、日本の参加に対する当事国の同意など、厳格な「参加5原則」が定められています。
③【正】人間の安全保障とは、国家の安全保障だけでなく、一人ひとりの人間が恐怖(紛争、迫害など)や欠乏(貧困、飢餓など)から免れ、尊厳を持って生きることを保障すべきだという考え方です。日本政府は、この理念を外交の柱の一つに掲げています。
④【誤】日本は唯一の戦争被爆国として、核兵器廃絶を国際社会に訴えていますが、アメリカの「核の傘」に依存しているという現実もあります。核兵器禁止条約には参加していません。
第5問
問1:正解④
<問題要旨>
持続可能な社会の実現に向けた理念と具体的な取り組みに関する問題です。「持続可能な開発」という概念の理解が中心となります。
<選択肢>
①【誤】環境アセスメント(環境影響評価)は、大規模な開発事業が環境に与える影響を事前に調査・予測・評価する手続きです。環境保全の観点から重要な制度です。
②【誤】ゼロ・エミッションは、生産活動から出る廃棄物を別の産業の資源として活用するなどして、全体として廃棄物を出さないことを目指す考え方です。
③【誤】循環型社会形成推進基本法は、3R(リデュース、リユース、リサイクル)を推進し、廃棄物の発生を抑制し、資源の循環的な利用を目指す社会の枠組みを定めています。
④【正】「持続可能な開発」とは、「将来の世代の欲求を満たしうる能力を損なうことなしに、現在の世代の欲求を満たすような開発」と定義されています。環境保全と開発を両立させ、世代を超えて豊かな社会を維持していこうという考え方です。
問2:正解③
<問題要旨>
日本の少子高齢化の現状と、社会に与える影響についての問題です。人口ピラミッドの形状の変化や、社会保障への影響の理解が問われています。
<選択肢>
①【誤】合計特殊出生率とは、一人の女性が生涯に産む子どもの数の平均を示す指標です。日本の人口を長期的に維持するためには、この数値が2.07程度必要(人口置換水準)とされていますが、現状はこれを大きく下回っています。
②【誤】高齢化率とは、総人口に占める65歳以上の老年人口の割合です。7%を超えると「高齢化社会」、14%を超えると「高齢社会」、21%を超えると「超高齢社会」と呼ばれます。
③【正】少子高齢化が進行すると、生産年齢人口(15〜64歳)が減少し、老年人口が増加します。これにより、年金や医療などの社会保障制度において、現役世代の保険料負担が増大する一方、高齢者一人当たりの給付水準を維持することが困難になります。
④【誤】日本の人口ピラミッドは、戦後のベビーブーム期には「富士山型」、その後の経済成長期には「つりがね型」、そして現在は少子高齢化を反映した「つぼ型(逆富士型)」となっています。
問3:正解②
<問題要旨>
男女共同参画社会の実現に向けた課題と法制度に関する問題です。固定的役割分担意識や、関連する法律についての知識が問われています。
<選択肢>
①【誤】男女共同参画社会基本法は、男女が互いに人権を尊重し、性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮できる社会を目指すための基本法です。
②【正】「男は仕事、女は家庭」といった、性別によって役割を固定的に捉える考え方を「固定的性別役割分担意識」といいます。これは、女性の社会進出を妨げたり、男性が育児に参加しにくくしたりするなど、男女共同参画を阻む大きな要因の一つとされています。
③【誤】男女雇用機会均等法は、募集・採用、配置、昇進など、雇用における男女差別を禁止する法律です。この法律の制定・改正により、職場での女性の地位は向上してきましたが、課題もまだ多く残されています。
④【誤】リプロダクティブ・ヘルス/ライツは、性と生殖に関する健康と権利を指します。いつ、何人子どもを産むか、産まないかなどを、女性自身が決定する権利などが含まれます。
問4:正解②
<問題要旨>
自然災害の多い日本における防災・減災の考え方に関する問題です。ハザードマップや自助・共助・公助の考え方がポイントです。
<選択肢>
①【誤】ハザードマップは、自然災害による被害の範囲や程度を予測し、地図上に示したものです。住民が地域の災害リスクを認識し、避難行動などに役立てることを目的としています。
②【正】防災・減災においては、まず自分自身の命を守る「自助」、次に地域コミュニティで助け合う「共助」、そして行政による救助や支援である「公助」が重要とされています。これらを適切に組み合わせることで、災害による被害を最小限に抑えることができます。
③【誤】災害対策基本法は、日本の防災に関する基本的な法律です。防災計画の策定、災害予防、災害応急対策、復旧・復興などについて定めています。
④【誤】近年の防災・減災の考え方では、ハード面の対策(堤防の建設など)だけでなく、避難訓練や防災教育といったソフト面の対策も同様に重視されています。