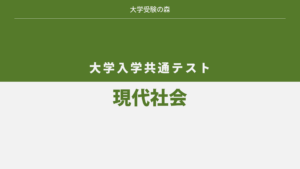解答
解説
第1問
問1:正解④
<問題要旨>
ポジティブ・アクション(アファーマティブ・アクション)の具体的な手法について、その内容を正しく理解できているかを問う問題です。クオータ制、プラスファクター方式、そしてそれらとは異なる基盤整備を推進する方式の違いを、仮想例から判断する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
アは、能力が同等である場合に特定の属性(この場合は女性)を優先的に扱う「プラスファクター方式」に該当します。そのため、Cの「基盤整備を推進する方式」には当てはまりません。
②【誤】
アは「プラスファクター方式」に該当するため、Cの「基盤整備を推進する方式」には当てはまりません。
③【誤】
アは「プラスファクター方式」に該当するため、Cの「基盤整備を推進する方式」には当てはまりません。
④【正】
アは、能力同等の場合に女性を優先する「B プラスファクター方式」に該当します。一方、イは、女性が働きやすい環境を周知することで応募しやすくする「C 基盤整備を推進する方式」です。また、ウも、育児や介護などの事情を抱える人が不利にならないようキャリア形成を柔軟にするものであり、参画しやすくするための環境整備、すなわち「C 基盤整備を推進する方式」に該当します。したがって、Cに該当するのはイとウの組合せです。
問2:正解②
<問題要旨>
女子差別撤廃委員会の日本への指摘事項のうち、2025年現在までに民法が改正されたものを選択する問題です。婚姻制度に関する近年の法改正についての知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
ウの夫婦同姓制度については、選択的夫婦別姓制度の導入が議論されていますが、2025年現在、民法は改正されていません。
②【正】
アの男女の婚姻適齢については、2022年4月1日の民法改正により、女性の婚姻年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに18歳に統一されました。また、イの女性の再婚禁止期間については、2024年4月1日の民法改正により撤廃されました。したがって、アとイはともに改正が行われています。ウの夫婦同姓制度は改正されていません。
③【誤】
イの女性の再婚禁止期間は改正されましたが、ウの夫婦同姓制度は改正されていません。
④【誤】
アの男女の婚姻適齢は改正されましたが、ウの夫婦同姓制度は改正されていません。
問3:正解③
<問題要旨>
高齢者の「近所の人たちとの付き合い方」に関する国際比較調査の表を正確に読み取り、正しい記述を選択する問題です。数値を比較し、選択肢の正誤を判断する情報処理能力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
表を見ると、「外でちょっと立ち話をする程度」の割合が最も高いのはスウェーデン(89.7%)と日本(67.3%)ですが、アメリカでは45.9%であり、最も高くありません。ドイツでは「お茶や食事を一緒にする」(50.1%)の方が高いため、4か国すべてに当てはまるわけではありません。
②【誤】
「物をあげたりもらったりする」の割合は、日本が41.9%です。アメリカ(18.4%)、ドイツ(14.3%)、スウェーデン(24.3%)と比較すると、日本は他国より高いですが、スウェーデンとの差は17.6ポイントであり、「20ポイント以上高い」という条件を満たしません。
③【正】
「相談ごとがあった時、相談したり、相談されたりする」の割合は、日本が18.6%で4か国中最も低いです。また、「病気の時に助け合う」の割合も、日本が5.9%で4か国中最も低いです。したがって、この記述は表の内容と合致します。
④【誤】
「家事やちょっとした用事をしたり、してもらったりする」の割合について、アメリカでは15.2%ですが、「趣味をともにする」が13.5%でより低いため、アメリカでは最も低いとは言えません。したがって、4か国すべてに当てはまるわけではありません。
問4:正解②
<問題要旨>
日本のプライバシーの権利に関する判例の知識を問う問題です。肖像権やプライバシーの権利が裁判でどのように認められてきたか、基本的な判例の理解が必要です。
<選択肢>
①【誤】
イの『宴のあと』事件判決は、プライバシーの権利を日本で初めて認めた画期的な判決です。「認めなかった」という記述が誤りです。
②【正】
アは、京都府学連事件(最大判昭和44年12月24日)に関する記述です。この判決で最高裁は、個人の私生活上の自由の一つとして、承諾なしにみだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由(肖像権)を認めました。これは正しい記述です。一方、イの『宴のあと』事件(東京地判昭和39年9月28日)では、裁判所は「私生活をみだりに公開されない」権利、すなわちプライバシーの権利を日本で初めて法的に認めました。したがって、「認めなかった」とするイの記述は誤りです。よって、正しいものはアのみです。
③【誤】
イの『宴のあと』事件判決は、プライバシーの権利を「認めなかった」のではなく、日本で初めて法的に「認めた」判決です。
④【誤】
アの記述は正しいです。
問5:正解①
<問題要旨>
欲求不満に対処するための心の働きである「防衛機制」について、具体的な事例がどの防衛機制に該当するかを判断する問題です。昇華、反動形成、投射などの代表的な防衛機制の概念を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【正】
Aは、社会的に認められない欲求や衝動を、学問、芸術、スポーツなど社会的に価値のあるものに置き換える「昇華」の例です。Bは、受け入れがたい感情や欲求とは正反対の行動をとる「反動形成」の例です。Cは、自分が抱いている受け入れがたい感情を、相手が自分に対して抱いているものだと思い込む「投射(投影)」の例です。したがって、この組合せは正しいです。
②【誤】
Cは、現実から目をそらす「逃避」ではなく、自分の感情を相手のものだと見なす「投射」です。
③【誤】
Bは、もっともらしい理由をつけて自分を正当化する「合理化」ではなく、本心とは逆の行動をとる「反動形成」です。
④【誤】
Bは「合理化」、Cは「逃避」ではなく、それぞれ「反動形成」、「投射」です。
⑤【誤】
Aは、優れた他者と自分を重ね合わせる「同一視(同一化)」ではなく、社会的に価値ある活動へ欲求を向ける「昇華」です。
⑥【誤】
Aは「同一視」、Cは「逃避」ではなく、それぞれ「昇華」、「投射」です。
⑦【誤】
Aは「同一視」、Bは「合理化」ではなく、それぞれ「昇華」、「反動形成」です。
⑧【誤】
Aは「同一視」、Bは「合理化」、Cは「逃避」ではなく、それぞれ「昇華」、「反動形成」、「投射」です。
問6:正解③
<問題要旨>
マズローの欲求階層説(5段階説)を理解し、具体的な事例を低次の欲求から高次の欲求へと正しく並べ替える問題です。生理的欲求、安全の欲求、社会的欲求、承認の欲求、自己実現の欲求の各段階の内容を把握している必要があります。
<選択肢>
①【誤】
欲求の階層は、低次からD(生理的)→A(安全)→C(社会的)→B(承認)→E(自己実現)となります。2番目はA、3番目はC、4番目はBです。この選択肢では3番目と4番目が逆になっています。
②【誤】
欲求の階層は、低次からD(生理的)→A(安全)→C(社会的)→B(承認)→E(自己実現)となります。2番目はA、3番目はC、4番目はBです。この選択肢では3番目以降が異なります。
③【正】
マズローの欲求階層説では、欲求は低次から①生理的欲求、②安全の欲求、③社会的欲求(所属と愛)、④承認(尊重)の欲求、⑤自己実現の欲求の順に満たされていくとされます。
Dは飢えをしのぐ「生理的欲求」(1番目)。
Aは災害に備え安心を得る「安全の欲求」(2番目)。
Cは友人関係やクラスでの居場所を求める「社会的欲求」(3番目)。
Bは他者からの承認や自信を得る「承認の欲求」(4番目)。
Eは夢を実現し生きがいを感じる「自己実現の欲求」(5番目)。
したがって、低次から2番目はA、3番目はC、4番目はBとなります。
④【誤】
欲求の階層は、低次からD(生理的)→A(安全)→C(社会的)→B(承認)→E(自己実現)となります。2番目はA、3番目はC、4番目はBです。この選択肢では4番目が異なります。
⑤【誤】
最も低次なのはD(生理的欲求)であり、2番目はA(安全の欲求)です。
⑥【誤】
最も低次なのはD(生理的欲求)であり、2番目はA(安全の欲求)です。
⑦【誤】
最も低次なのはD(生理的欲求)であり、2番目はA(安全の欲求)です。
⑧【誤】
最も低次なのはD(生理T的欲求)であり、2番目はA(安全の欲求)です。
第2問
問1:正解③
<問題要旨>
国際分業の形態(垂直的・水平的)と、産業の空洞化の定義について正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
アに入るのは「垂直的」分業(Q)です。水平的分業は、先進国同士で工業製品を輸出しあうような分業形態を指します。
②【誤】
アに入るのは「垂直的」分業(Q)であり、αの産業空洞化の説明はXが正しいですが、組合せが誤りです。
③【正】
アは、先進国が工業製品を輸出し、開発途上国が原材料や食料品を輸出するといった、異なる産業間での分業であるため「垂直的」分業(Q)が入ります。αの「産業の空洞化」とは、国内企業の生産拠点が海外へ移転することによって、国内の製造業が衰退し、失業が増える現象のことです。したがって、Xの記述が正しく、組合せとして適切です。
④【誤】
αの記述Yは、第一次産業から第二次・第三次産業へと経済の中心が移っていく「産業構造の高度化」を説明したものであり、産業の空洞化の説明ではありません。
問2:正解①
<問題要旨>
開発途上国に関連する国際機関や経済問題についての基本的な知識を問う問題です。各選択肢の正誤を判断する必要があります。
<選択肢>
①【正】
国連人口基金(UNFPA)は、人口問題、特に途上国の家族計画やリプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)の推進などを支援する国連の専門機関です。
②【誤】
新国際経済秩序(NIEO)樹立宣言は、1974年に国連資源特別総会で、発展途上国のグループである「77か国グループ(G77)」の主導によって採択されました。国連開発計画(UNDP)が採択したものではありません。
③【誤】
1970年代以降に急速な工業化を遂げた開発途上国・地域は、新興工業経済地域(NIES)と呼ばれます。後発開発途上国(LDC)は、開発途上国の中でも特に開発の遅れた国々を指す区分であり、記述は逆の内容です。
④【誤】
先進国(北)と開発途上国(南)の間の経済格差を「南北問題」と呼びます。開発途上国間での経済格差(例えば、資源国と非資源国、NIESとLDCなど)は「南南問題」と呼ばれます。
問3:正解⑥
<問題要旨>
現代中国の経済史における重要な出来事を、正しい時系列で配置する問題です。WTO加盟やGDP世界第2位といった画期的な出来事がいつ起きたかを知っている必要があります。
<選択肢>
①【誤】
カードX(GDP世界第2位)は2010年、カードY(WTO加盟)は2001年の出来事です。時系列の配置が誤っています。
②【誤】
カードX(GDP世界第2位)は2010年の出来事であり、ウの位置は正しいですが、カードY(WTO加盟)は2001年の出来事であり、イの位置に入るべきです。
③【誤】
カードXとYの時系列上の位置が逆です。
④【誤】
カードY(WTO加盟)は2001年の出来事であり、イの位置に入るべきです。
⑤【誤】
カードX(GDP世界第2位)は2010年の出来事であり、ウの位置に入ります。カードY(WTO加盟)は2001年の出来事であり、イの位置に入ります。
⑥【正】
中国の改革開放政策は1978年に開始されました。その後、2001年に世界貿易機関(WTO)に加盟(カードY)し、世界経済への統合を進めました。これは1993年と2005年の間の出来事なので、イに該当します。そして、2010年に名目GDPで日本を抜き、世界第2位の経済大国となりました(カードX)。これは2005年より後の出来事なので、ウに該当します。したがって、この組合せが正しいです。
問4:正解④
<問題要旨>
名目経済成長率と実質経済成長率の関係を理解し、表と会話文から数値を計算・判断する問題です。経済成長率の基本的な計算式と思考力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
ア(X国の物価変動率)の計算が誤っています。また、イに入るのはZ国です。
②【誤】
ア(X国の物価変動率)の計算が誤っています。
③【誤】
イに入るのはY国ではなくZ国です。Y国の実質経済成長率は4.0%で、X国の3.0%よりも高くなります。
④【正】
まず、X国の名目経済成長率を計算します。(210 – 200)÷ 200 × 100 = 5.0% となります。会話文から、X国の実質経済成長率は3.0%なので、「実質成長率 = 名目成長率 – 物価変動率」の式に当てはめると、3.0% = 5.0% – ア となり、アは2.0%と求められます。次に、Y国とZ国の実質経済成長率を計算します。Y国は名目成長率が(108 – 100)÷ 100 × 100 = 8.0%、物価変動率が4.0%なので、実質成長率は4.0%です。Z国は名目成長率が(110 – 100)÷ 100 × 100 = 10.0%、物価変動率が8.0%なので、実質成長率は2.0%です。X国の実質成長率(3.0%)より低くなるのはZ国(2.0%)なので、イにはZが入ります。
⑤【誤】
ア(X国の物価変動率)は2.0%です。
⑥【誤】
ア(X国の物価変動率)は2.0%です。また、イに入るのはZ国です。
問5:正解①
<問題要旨>
WTO体制下の多角的貿易交渉と、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)に関する基本的な知識を問う問題です。GATT/WTOの歴史と近年の地域経済統合の動きを理解しているかがポイントです。
<選択肢>
①【正】
アには、2001年に開始されたWTOの多角的貿易交渉である「ドーハ・ラウンド」(P)が入ります。ケネディ・ラウンドは1960年代のGATT時代の交渉です。イには、TPP交渉から離脱した国が入ります。2017年にトランプ政権下のアメリカ(S)が離脱を表明し、その後、日本などが主導して11か国でCPTPP(TPP11協定)が結ばれました。したがって、この組合せは正しいです。
②【誤】
イに入るのはアメリカ(S)です。オーストラリア(T)はCPTPPの原署名国です。
③【誤】
アにはドーハ・ラウンド(P)が入ります。ケネディ・ラウンド(Q)はGATT時代の交渉です。
④【誤】
アにはドーハ・ラウンド(P)、イにはアメリカ(S)が入ります。
問6:正解①
<問題要旨>
GATT/WTOの基本原則である「最恵国待遇」と「内国民待遇」の定義を理解し、具体的な事例と正しく結びつける問題です。この二つの原則の違いを明確に区別できるかが問われます。
<選択肢>
①【正】
原則αは、ある国に与えた最も有利な待遇(関税など)を他の全ての加盟国にも適用する「最恵国待遇」の説明です。原則βは、輸入品を国内品と差別しない「内国民待遇」の説明です。したがって、アにはαが入ります。
事例Xは、国産車と輸入車で国内税(自動車税)を差別しないことを求めているため、「内国民待遇」の例です。事例Yは、ある国(B国)への関税引き下げを他の国(C国)にも適用することを求めているため、「最恵国待遇」の例です。したがって、内国民待遇に当てはまるイにはXが入ります。組合せとして正しいです。
②【誤】
内国民待遇の原則に当てはまる事例はXです。Yは最恵国待遇の事例です。
③【誤】
アには最恵国待遇を説明するαが入ります。
④【誤】
アにはα、イにはXが入ります。
問7:正解⑦
<問題要旨>
日本の経済連携協定(EPA)の歴史と、地域経済統合がもたらす効果(特に貿易転換効果)についての理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
日本が初めてEPAを締結したのはシンガポール(Q)です。
②【誤】
日本が初めてEPAを締結したのはシンガポール(Q)です。
③【誤】
日本が初めてEPAを締結したのはシンガポール(Q)です。イの記述は正しいですが、組合せが誤りです。
④【誤】
日本が初めてEPAを締結したのはシンガポール(Q)です。
⑤【誤】
イの記述が誤っています。Wは輸出先の話であり、貿易転換効果の説明ではありません。
⑥【誤】
イの記述が誤っています。Xは輸出先の話であり、貿易転換効果の説明ではありません。
⑦【正】
アについて、日本が初めて経済連携協定(EPA)を締結したのは、2002年のシンガポール(Q)です。イについて、文章中では「効率の良い域外国の生産を効率の悪い域内貿易が代替するという非効率性」と説明されています。これは「貿易転換効果」のことで、FTA/EPA締結により、本来なら関税を払っても安く輸入できた効率的な域外国からの輸入が、関税が撤廃された非効率な域内国からの輸入に切り替わってしまう現象を指します。したがって、「輸入先が、関税が課される域外国から、関税が課されない域内国へ」と変わるYの記述が当てはまります。
⑧【誤】
イの記述Zは、貿易転換効果とは逆の動きを示しています。
第3問
問1:正解③
<問題要旨>
NIMBY(ニンビー)、PIMBY/YIMBY(ピンビー/インビー)、NOPE(ノープ)という、施設の受け入れに対する住民の態度の類型を、具体的な事例に正しく当てはめる問題です。それぞれの言葉の意味を正確に理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
Xさんの姿勢は、負担を積極的に引き受ける「イ:PIMBY/YIMBY」です。
②【誤】
Xさんの姿勢は「イ:PIMBY/YIMBY」、Yさんの姿勢は「ア:NIMBY」です。
③【正】
アのNIMBYは「Not In My Back Yard(私の裏庭にはやめて)」の略で、施設の必要性は認めつつも自地域への設置には反対する態度です。Yさんは「施設設置は望ましい」としつつも「B市における設置には反対」しており、NIMBYに該当します。イのPIMBY/YIMBYは「Please (Yes) In My Back Yard」の略で、施設の必要性を認め、自地域への設置を積極的に受け入れる態度です。Xさんは「自ら引き受ける覚悟」で取り組んでおり、PIMBY/YIMBYに該当します。ウのNOPEは「Not On Planet Earth(地球上に不要)」の略で、施設の存在自体に反対する態度です。Zさんは「そもそも…対策とは言えず、設置には賛同できない」としており、NOPEに該当します。
④【誤】
Yさんの姿勢は「ア:NIMBY」、Zさんの姿勢は「ウ:NOPE」です。
⑤【誤】
Zさんの姿勢は「ウ:NOPE」、Xさんの姿勢は「イ:PIMBY/YIMBY」です。
⑥【誤】
Zさんの姿勢は「ウ:NOPE」です。
問2:正解②
<問題要旨>
経済学における財・サービスの分類(私的財、公共財、共有資源、クラブ財)を理解し、具体的な事例を正しく分類する問題です。財の持つ「競合性」と「排除可能性」の二つの性質で分類します。
<選択肢>
①【誤】
Ⅱは「非排除性」と「競合性」を持つ財(共有資源)なのでAが入りますが、Ⅲは「排除可能性」と「非競合性」を持つ財(クラブ財)なのでCが入ります。
②【正】
この分類は、対価を支払わない人を排除できるか(排除可能性)と、誰かが消費すると他の人の消費量が減るか(競合性)の2軸で分けられます。
I(排除可能、競合性あり):私的財。例:Bのチョコレート。
II(排除不可能、競合性あり):共有資源。誰でも利用できるが、使いすぎると枯渇する。例:Aの無料の釣り池の魚。
III(排除可能、非競合性あり):クラブ財(料金財)。お金を払えば利用できるが、他人が利用しても自分の便益は減らない。例:Cの混雑していない有料展望台。
IV(排除不可能、非競合性なし):公共財。例:公園、国防。
したがって、IIにA、IIIにCが入るこの選択肢が正しいです。
③【誤】
ⅢにはCが入ります。
④【誤】
ⅡにはAが入ります。
⑤【誤】
ⅡにはA、ⅢにはCが入ります。
⑥【誤】
ⅡにはAが入ります。
問3:正解③
<問題要旨>
自然環境の保全に関する国際条約についての基本的な知識を問う問題です。ワシントン条約、世界遺産条約、生物多様性条約、砂漠化対処条約など、それぞれの条約の目的と内容を正確に把握しているかが試されます。
<選択肢>
①【誤】
絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制するのは「ワシントン条約」です。「バーゼル条約」は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分を規制する条約です。
②【誤】
ユネスコの世界遺産条約は、普遍的な価値を持つ「文化遺産」、「自然遺産」、そしてその両方の価値を兼ね備えた「複合遺産」を登録・保全の対象としています。「文化遺産は含まれない」という記述は誤りです。
③【正】
生物多様性条約は、①生物多様性の保全、②生物資源の持続可能な利用、③遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分、を目的としており、記述は正しいです。
④【誤】
砂漠化対処条約(正式名称:深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国際連合条約)は、1994年に採択され、1996年に発効しています。「いまだ発効していない」という記述は誤りです。
問4:正解②
<問題要旨>
日本の統治機構に関する基本的な知識を問う問題です。国会、内閣、裁判所、行政制度についての正確な理解が求められます。
<選択肢>
①【誤】
憲法第53条によれば、内閣が臨時会の召集を決定でき、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければなりません。また、憲法第54条では、衆議院の解散中に国に緊急の必要があるとき、内閣は「参議院の緊急集会」を求めることができます。「衆議院に求める」が誤りです。
②【正】
行政手続法は、許認可や不利益処分などの行政運営における手続きを定めることで、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護を目的としています。記述は正しいです。
③【誤】
知的財産高等裁判所は、知的財産権に関する事件を専門的に扱う裁判所として、東京高等裁判所の特別の支部として設置されています。「すべての高等裁判所に設置された」という記述は誤りです。
④【誤】
国会審議活性化法(1999年)によって、政府委員制度は「廃止」され、代わりに副大臣・大臣政務官制度が導入されました。これにより、国会答弁は原則として大臣、副大臣、大臣政務官が行うことになりました。「導入された」という記述は誤りです。
問5:正解②
<問題要旨>
地方自治法に定められた住民の直接請求制度(リコール、イニシアティブ)に必要な署名数や議決要件についての知識を問う問題です。具体的な数字を正確に覚えているかがポイントになります。
<選択肢>
①【誤】
ウの議会の解散を決める住民投票では、「過半数」の同意が必要です。「3分の2以上」ではありません。
②【正】
地方自治法に基づき、条例の制定・改廃請求(イニシアティブ)には、有権者の「50分の1以上」の署名が必要です。X市の有権者は6万人なので、60,000 ÷ 50 = 1,200人以上の署名が必要となり、アは正しいです。議会の解散請求(リコール)には、有権者の「3分の1以上」の署名が必要で、イは正しいです。その後の住民投票で議会を解散させるには、有効投票の「過半数」の同意が必要であり、ウも正しいです。
③【誤】
イの議会の解散請求に必要な署名数は「3分の1以上」です。「過半数」ではありません。また、ウの住民投票での同意は「過半数」です。
④【誤】
イの議会の解散請求に必要な署名数は「3分の1以上」です。
⑤【誤】
アの条例制定請求に必要な署名数は「50分の1以上」です。「30,000人以上」は有権者の2分の1であり、多すぎます。
⑥【誤】
アの条例制定請求に必要な署名数は「50分の1以上」です。
⑦【誤】
アの条例制定請求に必要な署名数は「50分の1以上」、イの議会解散請求に必要な署名数は「3分の1以上」です。
⑧【誤】
アの条例制定請求に必要な署名数は「50分の1以上」、イの議会解散請求に必要な署名数は「3分の1以上」です。
問6:正解②
<問題要旨>
税の分類(直接税・間接税)、課税方式(累進課税)、租税の公平原則(水平的公平・垂直的公平)についての基本的な理解を問う問題です。所得税を例に、これらの概念を正しく結びつける必要があります。
<選択肢>
①【誤】
ウの累進課税が目指すのは、所得の多い人ほど重い負担を求める「垂直的公平」です。同じ所得の人が同じ税負担をするのが「水平的公平」です。
②【正】
アの所得税は、納税者と担税者が一致する「直接税」(P)に分類されます。イの累進課税制度は、所得が多くなるほど「高く」(R)なる税率が適用される仕組みです。ウの、所得の多い人により重い税負担を求める考え方は、異なる経済力の人々の間に税負担の公平を図る「垂直的公平」(U)に基づいています。したがって、この組合せは正しいです。
③【誤】
イの累進課税では、所得が多いほど税率は「高く」なります。ウは「垂直的公平」です。
④【誤】
イの累進課税では、所得が多いほど税率は「高く」なります。
⑤【誤】
アの所得税は「直接税」です。
⑥【誤】
アの所得税は「直接税」です。
⑦【誤】
アの所得税は「直接税」です。イの税率は「高く」なります。
⑧【誤】
アの所得税は「直接税」です。イの税率は「高く」なります。
問7:正解④
<問題要旨>
太陽光パネルの廃棄・リサイクルに関する現代的な課題と、その対策を正しく結びつける問題です。課題の内容を的確に読み取り、それに対応する最も効果的な解決策を判断する読解力と論理的思考力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
課題ア(含有物質の情報不足)にはB(情報データベース化)、課題イ(不法投棄)にはC(廃棄費用積立)、課題ウ(技術不足)にはA(技術開発支援)が対応します。組合せが異なります。
②【誤】
組合せが異なります。
③【誤】
組合せが異なります。
④【正】
課題アは、パネルに含まれる有害物質の情報が不明で、適切な処理が困難という問題です。これには、製品ごとに含有物質情報をデータベース化する対策Bが直接的に対応します。
課題イは、事業者の資金不足によるパネルの放置(不法投棄)の問題です。これには、発電事業開始時から廃棄費用を積み立てておく仕組みを創設する対策Cが有効です。
課題ウは、レアメタルなどを回収・利活用するためのリサイクル技術が未確立という問題です。これには、技術開発を支援し、その普及を図る対策Aが対応します。
したがって、ア-B、イ-C、ウ-Aの組合せが正しいです。
⑤【誤】
組合せが異なります。
⑥【誤】
組合せが異なります。
問8:正解①
<問題要旨>
循環型社会に関連する用語や法律についての基本的な知識を問う問題です。グリーンコンシューマー、家電リサイクル法、循環型社会形成推進基本法、コージェネレーションといったキーワードの意味を正しく理解しているかが試されます。
<選択肢>
①【正】
環境への負荷が少ない製品を意識して選択・購入する消費者のことを「グリーンコンシューマー」と呼びます。この記述は正しいです。
②【誤】
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)が制定されたのは1998年(施行は2001年)であり、高度経済成長期(おおむね1955年~1973年)ではありません。
③【誤】
循環型社会形成推進基本法で定められている廃棄物処理・リサイクルの優先順位は、①発生抑制(リデュース)、②再使用(リユース)、③再生利用(リサイクル)、④熱回収、⑤適正処分の順です。再使用(リユース)は、再生利用(リサイクル)より優先されますが、発生抑制(リデュース)が最も優先されます。「再使用(リユース)が…最も優先される」というわけではないため、誤りです。
④【誤】
「コージェネレーション」とは、発電と同時に発生する排熱を冷暖房や給湯などに利用する、エネルギー効率の高いシステムのことです。企業の廃棄物をゼロにする取り組みは「ゼロ・エミッション」と呼ばれます。
第4問
問1:正解③
<問題要旨>
環境問題や科学技術と人間のかかわりについて論じた思想家や著作に関する知識を問う問題です。レイチェル・カーソンやフランシス・ベーコンといった重要人物とその思想を結びつける必要があります。
<選択肢>
①【誤】
アに入るのは『沈黙の春』(Q)です。『野生の思考』は文化人類学者レヴィ=ストロースの著作です。
②【誤】
アには『沈黙の春』(Q)、イには「知は力なり」と唱えたベーコン(R)が入ります。
③【正】
アは、化学物質による環境汚染に警鐘を鳴らしたレイチェル・カーソンの著作『沈黙の春』(Q)です。イは、「知は力なり」という言葉で知られ、観察や実験に基づく知によって自然を支配し、人間の生活を豊かにしようと考えたイギリスの哲学者フランシス・ベーコン(R)です。したがって、この組合せは正しいです。
④【誤】
イの「知は力なり」はベーコンの言葉です。パスカルは「人間は考える葦である」という言葉で知られるフランスの思想家です。
問2:正解①
<問題要旨>
自然観や環境倫理に関する重要な概念である「宇宙船地球号」と「アニミズム」について、その説明と用語を正しく結びつける問題です。
<選択肢>
①【正】
aは、地球を閉鎖された宇宙船にたとえ、その資源の有限性を説き、持続可能な社会の必要性を訴えた経済学者ボールディングの概念「宇宙船地球号」(ア)の説明です。bは、自然物や自然現象に霊的な存在を認める原始的な信仰の形態「アニミズム」(イ)の説明です。したがって、この組合せは正しいです。
②【誤】
bは「アニミズム」の説明です。「機械論的自然観」は、自然を法則に従って動く機械のようにとらえる近代科学の基礎となった考え方です。
③【誤】
aとbの説明が逆になっています。
④【誤】
aは「宇宙船地球号」、bは「アニミズム」の説明です。
⑤【誤】
aは「宇宙船地球号」の説明です。
⑥【誤】
aは「宇宙船地球号」、bは「アニミズム」の説明です。
問3:正解④
<問題要旨>
第二次世界大戦後のヨーロッパ統合の歴史に関する知識を問う問題です。ECSCからEUに至るまでの主要な条約や組織の役割を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【誤】
常任の欧州理事会議長(EU大統領)や外務・安全保障政策上級代表(EU外相)の職を創設したのは、2009年に発効した「リスボン条約」です。「マーストリヒト条約」は、EUの創設を定めた条約です。
②【誤】
イギリスは、2016年に行われた国民投票の結果、EUからの「離脱」を決定し、2020年に正式に離脱しました。「残留することを決めた」という記述は誤りです。
③【誤】
ユーロ圏の金融政策を担っているのは「欧州中央銀行(ECB)」です。欧州経済共同体(EEC)はEUの前身の一つです。
④【正】
ヨーロッパ統合の第一歩は、フランスのシューマン外相の提唱(シューマン・プラン)に基づき、1952年に設立された欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)です。これにより、戦争の原因となり得た石炭と鉄鋼の生産を共同管理することになりました。この記述は正しいです。
問4:正解⑤
<問題要旨>
金融の決済システムについて、多額の現金を動かすリスクを避けるための銀行間決済の仕組みと、その安定性を支える日本銀行の役割に関する理解を問う問題です。図を基に取引総額や決済額を読み解き、適切な金融用語を選択する能力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
アの取引総額は1130万円です。
②【誤】
アの取引総額は1130万円です。また、ウはペイオフではなく「最後の貸し手機能」です。
③【誤】
アの取引総額は1130万円、イの決済額は150万円です。
④【誤】
アの取引総額は1130万円、イの決済額は150万円です。また、ウはペイオフではなく「最後の貸し手機能」です。
⑤【正】
アは、企業A・B・C間で行われる取引の合計額です。図中の細い矢印で示された数値をすべて合計すると、390+230+190+130+120+70 = 1130万円となります。
ウは、市中銀行が破綻するリスクを軽減するための日本銀行の機能です。文中の「市中銀行が破綻すると、企業は代金を受け取れなくなるリスクがある」状況に対し、日本銀行が金融システム全体の安定を守るために発動するのは「最後の貸し手機能」です。ペイオフは預金保険制度による預金者保護の仕組みであり、文脈に合いません。
アが1130万円、ウが「最後の貸し手機能」であることから、選択肢は⑤に絞られます。したがって、イには150万円が入ります。これは、1130万円もの現金取引をせずとも、銀行間の決済ネットワークを使えば、より少額の資金移動で決済が完了することを示しています。
⑥【誤】
ウはペイオフではなく「最後の貸し手機能」です。
⑦【誤】
イは150万円です。企業間の取引を銀行ごとに純額で計算すると決済額は300万円となりますが、図の描写や選択肢の組合せを考慮すると、⑤が最も適当です。
⑧【誤】
イは150万円、ウは「最後の貸し手機能」です。
問5:正解②
<問題要旨>
リスク分析の3要素(リスク評価、リスク管理、リスクコミュニケーション)の定義を理解し、具体的な事例を正しく分類する問題です。それぞれの活動がどの段階に当たるかを判断する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
Aは科学的データに基づいてリスクの程度を評価する「リスク評価」です。Bは意見交換会であり「リスクコミュニケーション」です。
②【正】
ア「リスク評価」は、ハザードによる悪影響の確率や程度を科学的に評価することです。事例Aは、化学物質の摂取量と健康影響の関係を実験・調査で明らかにしているため、リスク評価に該当します。
イ「リスク管理」は、評価結果に基づきリスクを低減するための措置を決定・実施することです。事例Cは、食品の安全基準を定めて細菌のリスクを管理しているため、リスク管理に該当します。
ウ「リスクコミュニケーション」は、関係者間で情報や意見を交換することです。事例Bは、報道関係者などとの意見交換会であり、リスクコミュニケーションに該当します。
したがって、A-ア、B-ウ、C-イの組合せとなり、選択肢の中ではAがア、Cがイ、Bがウに対応する②が正解です。(選択肢の並び順に注意)
③【誤】
Aは「リスク評価」、Bは「リスクコミュニケーション」、Cは「リスク管理」です。
④【誤】
Aは「リスク評価」、Cは「リスク管理」です。
⑤【誤】
Cは「リスク管理」、Aは「リスク評価」です。
⑥【誤】
Cは「リスク管理」です。
問6:正解④
<問題要旨>
生命倫理における自己決定権に関連する用語、「リヴィング・ウィル」と「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」の定義を正しく理解しているかを問う問題です。二つの用語が入れ替わっていることに気づけるかがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
アとイの両方の記述が、用語と説明が入れ替わっているため誤りです。
②【誤】
アの記述は「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」の説明です。
③【誤】
イの記述は「リヴィング・ウィル」の説明です。
④【正】
アで説明されている「妊娠や出産、避妊など性や生殖に関する事柄について、女性が自ら決定する権利」は、「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」の内容です。
イで説明されている「将来、自身の意思を表明できなくなったときのために、延命治療を含む死のあり方に関する意向を事前に意思表示しておくこと」は、「リヴィング・ウィル(尊厳死の宣言書)」の内容です。
したがって、アとイの記述はどちらも用語と説明が入れ替わっており、正しいものはありません。
問7:正解④
<問題要旨>
2009年に改正された日本の臓器移植法の内容を理解し、本人の意思表示がない場合の臓器提供の要件を判断する問題です。改正後の法律では、本人の意思が不明でも、家族の承諾があれば臓器提供が可能になった点が重要です。
<選択肢>
①【誤】
BとDのように、家族の承諾がない場合は臓器提供はできません。
②【誤】
Bのように、家族の承諾がない場合は臓器提供はできません。
③【誤】
Bのように、家族の承諾がない場合は臓器提供はできません。
④【正】
2009年の臓器移植法改正により、本人が生前に臓器提供を拒否する意思表示をしていなければ、本人の意思が不明な場合でも、家族の承得があれば臓器提供が可能になりました。この規定はドナー候補の年齢に関わらず適用されます。したがって、ドナー候補の年齢が15歳以上(ケースA)でも15歳未満(ケースC)でも、家族の承諾があれば脳死判定後の臓器提供が可能です。家族の承諾がないケースBとDでは提供できません。よって、提供できるのはAとCの組合せです。
⑤【誤】
Cのケースも可能です。
⑥【誤】
Bのケースはできません。
⑦【誤】
Aのケースも可能です。
⑧【誤】
Dのケースはできません。
第5問
問1:正解④
<問題要旨>
2つの資料(若者の居場所に関する意識調査)を正確に読み取り、比較・計算して、正しい記述を選択する問題です。数値を丁寧に追い、選択肢の主張と合致するかを判断する情報処理能力が求められます。
<選択肢>
①【誤】
「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計値を見ると、「職場」が8.8% + 26.3% = 35.1%となり、これが最も低い値です。「地域」(13.9% + 39.3% = 53.2%)ではありません。
②【誤】
「学校」のネガティブな回答(「そう思わない」「どちらかといえばそう思わない」)の合計は、24.8% + 27.1% = 51.9%です。「インターネット空間」のネガティブな回答の合計は、18.6% + 24.9% = 43.5%です。その差は51.9 – 43.5 = 8.4ポイントであり、「5ポイント未満である」という記述は誤りです。
③【誤】
年齢区分別で「インターネット空間」のポジティブな回答(「そう思う」「どちらかといえばそう思う」)の合計を見ると、「13~14歳」は12.5% + 42.6% = 55.1%、「15~19歳」は27.4% + 36.1% = 63.5%です。最も多いのは「15~19歳」であり、「13~14歳」ではありません。
④【正】
年齢区分別で「インターネット空間」のネガティブな回答(「そう思わない」「どちらかといえばそう思わない」)の合計を比べます。「15~19歳」は16.1% + 20.5% = 36.6%です。「25~29歳」は20.7% + 27.8% = 48.5%です。その差は48.5 – 36.6 = 11.9ポイントであり、「10ポイント以上の差がある」という記述と合致します。
問2:正解⑤
<問題要旨>
インターネットが人間関係に与える二つの効果(A:既存のつながりの強化、B:新しいつながりの創出)を理解し、具体的な事例を正しく分類する問題です。事例の内容を読み解き、どちらの効果に当てはまるか、あるいはどちらにも当てはまらないかを判断する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
イは既存の友人との関係が深まる例なのでAに、アとエは面識のない人との新たな関係構築なのでBに該当します。この選択肢はアとエを含んでいません。
②【誤】
ウは関係が悪化しており、A・Bどちらの効果にも当てはまりません。
③【誤】
ウは関係が悪化しており、A・Bどちらの効果にも当てはまりません。
④【誤】
イはAの効果、アとエはBの効果です。
⑤【正】
効果Aは「既存のつながりを強くする」ものです。事例イは、もともと面識のあった友人との関係がオンラインゲームを通じて深まった例なので、Aに該当します。
効果Bは「新しいつながりをつくる」ものです。事例アは、ブログを通じて面識のなかった人と悩みを共有する関係ができた例なので、Bに該当します。事例エも、動画投稿をきっかけに面識のなかった人々とオンライン掲示板で議論する関係ができた例なので、Bに該当します。
事例ウは、逆に関係が悪化して断絶しており、A・Bのどちらの効果にも当てはまりません。
したがって、Aにイ、Bにアとエが当てはまるこの選択肢が正しいです。
⑥【誤】
ウはどちらの効果にも当てはまりません。
⑦【誤】
ウはどちらの効果にも当てはまりません。
⑧【誤】
イはAの効果、エはBの効果です。
⑨【誤】
ウはどちらの効果にも当てはまりません。
問3:正解③
<問題要旨>
民主的な意思決定のプロセスを「個人の意見の形成方法(熟議/生の選好)」と「集団の意思決定ルール(集計/合意)」の2軸で分類した図を理解し、具体的な事例を正しく当てはめる問題です。それぞれの事例がどの象限に位置するかを論理的に判断する必要があります。
<選択肢>
①【誤】
Iは「熟議+集計」、IIは「熟議+合意」、IIIは「生の選好+集計」です。アは「熟議+合意」なのでII、イは「熟議+集計」なのでI、ウは「生の選好+集計」なのでIIIに該当します。組合せが異なります。
②【誤】
組合せが異なります。
③【正】
図の分類は以下の通りです。
I:熟議(議論・対話)+集計(多数決など)。事例イは、ワークショップ(熟議)で案を練り、最終的に投票(集計)で決めるため、Iに該当します。
II:熟議(議論・対話)+合意(全会一致)。事例アは、陪審員が話合い(熟議)を重ね、全会一致(合意)で結論を出すため、IIに該当します。
III:生の選好(直感的判断)+集計(多数決など)。事例ウは、議論を経ずにオンラインアンケート(生の選好)で多数(集計)の意見を採用するため、IIIに該当します。
IV:生の選好(直感的判断)+合意(全会一致)。
したがって、I-イ、II-ア、III-ウの組合せが正しいです。
④【誤】
組合せが異なります。
⑤【誤】
組合せが異なります。
⑥【誤】
組合せが異なります。
問4:正解④
<問題要旨>
インターネットが社会や議論に与える影響(フィルターバブル、表現の自由と規制、ナッジ的な介入)についての会話文を読み、文脈に合う記述を選択する問題です。現代の情報社会が抱える課題についての理解と論理的思考が問われます。
<選択肢>
①【誤】
Yの「介入せず、あらゆる発言を認めるべき」という考えは、ヘイトスピーチなどを放置することにつながりかねず、Zの「投稿が見えないようにする」という介入策とは方向性が異なります。
②【誤】
Yの「介入せず、あらゆる発言を認めるべき」という考えは、ヘイトスピーチなどを放置することにつながりかねず、Zの「投稿取消の猶予を与える」という介入策とは方向性が異なります。
③【誤】
Zの選択肢が不適切です。オカノさんの「その人自身が気づくことを重視する」という考え方には、カの「投稿が本当に適切かを問う」という、自省を促す工夫が合致します。
④【正】
X:同じ意見の動画ばかり推薦されると、他の意見の存在に「気づきにくく」(ア)なります。これはフィルターバブルやエコーチェンバーと呼ばれる現象です。
Y:ウエダさんは「攻撃的な言動」を問題視し、議論が成り立たなくなることを心配しています。その極端な対策として、「他者を攻撃している人を排除するよう、国が事業者に命じる法律を制定すべき」(エ)という考えが文脈に合います。これに対し先生は「国家が表現の自由を制約するおそれ」を指摘しており、話が繋がります。
Z:オカノさんは「その人自身が気づくことを重視する」と述べています。これに合致するのは、攻撃的な投稿をしようとした際に「その投稿が本当に適切かを問う画面を表示し、投稿取消操作を行うことのできる猶予時間を設定する」(カ)という、利用者に自省を促す(ナッジ的な)工夫です。
したがって、X-ア、Y-エ、Z-カの組合せが正しいです。
⑤【誤】
Xは「気づきにくく」(ア)なるのが文脈に合います。
⑥【誤】
Xは「気づきにくく」(ア)なるのが文脈に合います。
⑦【誤】
Xは「気づきにくく」(ア)なるのが文脈に合います。
⑧【誤】
Xは「気づきにくく」(ア)なるのが文脈に合います。