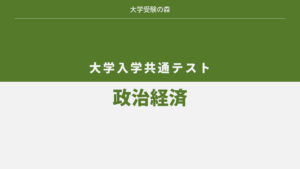解答
解説
第1問
問1:正解⑤
<問題要旨>
労働者の権利保護に関する、労働三法(労働基準法、労働組合法、労働関係調整法)のうち、特に労働基準法とその関連制度(労働基準監督署、労働審判制度)についての理解を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
アが「労働組合法」である点が誤りです。賃金の支払いは労働条件の最低基準に関わる事項であり、労働基準法で定められています。
②【誤】
アが「労働組合法」、ウが「労働争議の解決のために強制力のある仲裁裁定が出される」である点が誤りです。ウは労働委員会の権限の一つであり、労働審判の説明ではありません。
③【誤】
アが「労働組合法」、イが「公共職業安定所(ハローワーク)」である点が誤りです。ハローワークは職業紹介などを行う機関です。
④【誤】
アが「労働組合法」、イが「公共職業安定所(ハローワーク)」、ウが「労働争議の解決のために強制力のある仲裁裁定が出される」である点が誤りです。
⑤【正】
ア:賃金の不払いは、労働条件の最低基準を定めた「労働基準法」違反です。よってbが正しいです。
イ:労働基準法違反について労働者からの相談を受け付け、企業への監督・指導を行う行政機関は「労働基準監督署」です。よってcが正しいです。
ウ:労働審判制度は、裁判官と労働問題の専門家である労働審判員が協力し、個別労働紛争を原則3回以内の期日で審理する制度であり、「通常の訴訟よりも簡易で迅速な解決がめざされている」のが特徴です。よってeが正しいです。
したがって、b-c-eの組み合わせである⑤が正解です。
⑥【誤】
ウが「労働争議の解決のために強制力のある仲裁裁定が出される」である点が誤りです。
⑦【誤】
イが「公共職業安定所(ハローワーク)」である点が誤りです。
⑧【誤】
イが「公共職業安定所(ハローワーク)」、ウが「労働争議の解決のために強制力のある仲裁裁定が出される」である点が誤りです。
問2:正解⑤
<問題要旨>
リカレント教育(学び直し)を支援する雇用保険制度の一つである「教育訓練給付金」に関する資料を正確に読み解く能力を問う問題です。
<選択肢>
ア【正】
メモ中の表の「支給額」の欄を見ると、「専門実践教育訓練」は受講費用の50%、「特定一般教育訓練」は40%、「一般教育訓練」は20%と、教育訓練の種類によって給付金の支給割合が異なることがわかります。したがって、この記述は正しいです。
イ【誤】
メモ中の表によれば、「税理士の資格取得を目標とする講座」は「特定一般教育訓練」に分類されます。その支給時期は「修了後」と定められています。受講中に支給されるのは「専門実践教育訓練」です。したがって、この記述は誤りです。
ウ【正】
メモ中の「申請先」の項目に「公共職業安定所」と明記されています。したがって、この記述は正しいです。
アとウが正しい記述であるため、その組み合わせである⑤が正解となります。
問3:正解②
<問題要旨>
国政選挙における投票制度と、インターネットを利用した選挙運動のルールについての正確な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
イが誤りです。公職選挙法上、一般の有権者が有権者に対して投票を依頼する目的で電子メールを送信することは禁止されています。
②【正】
ア:会話文にある「海外旅行の予定と選挙の投票日とが重なってしまったときに」「出国前に住民票がある地元の町で投票を済ませることができた」という状況は、投票日当日に投票所へ行けない有権者が、事前に投票できる「期日前投票制度」を利用した例です。よってaが正しいです。
イ:インターネット選挙運動において、一般の有権者がウェブサイトやSNS(ブログ、X(旧Twitter)、Facebookなど)を利用して特定候補者への投票を呼びかけることは認められています。よってdが正しいです。
したがって、a-dの組み合わせである②が正解です。
③【誤】
アが誤りです。「在外選挙制度」は、仕事や留学などで海外に住んでいる日本国民が、国政選挙で投票するための制度です。
④【誤】
アが誤りです。
問4:正解④
<問題要旨>
少年による犯罪の推移を示すグラフの読解と、成年年齢引下げに伴う改正少年法の「特定少年」に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
イが誤りです。
②【誤】
アは正しいですが、イが誤りです。
③【誤】
アは正しいですが、イが誤りです。
④【正】
ア:グラフを見ると、1980年代前半にピークを迎えるなど増減はありますが、「2005年以降の時期では、どの年齢層もおおむね減少傾向にある」ことが読み取れます。会話の流れにおいても、Yが「近年の刑法犯検挙人数の推移」に言及していることから、この減少傾向について話していると判断するのが自然です。よってbが正しいです。
イ:2022年4月1日に施行された改正少年法では、18歳と19歳の者を「特定少年」と新たに位置づけました。少年法の適用対象であることに変わりはありませんが、一部の事件では20歳以上の者と同様の刑事手続きがとられる(原則逆送致事件の範囲が拡大される)など、扱われる範囲が拡大されています。よってdが正しいです。
したがって、b-dの組み合わせである④が正解です。
問5:正解⑦
<問題要旨>
日本国憲法第14条「法の下の平等」に違反するとして、最高裁判所が違憲判決を下した判例についての知識を問う問題です。
<選択肢>
ア【正】
最高裁判所は2013年、婚外子(嫡出でない子)の法定相続分を婚内子(嫡出子)の半分とする民法の規定は、子にとって自ら選択・修正できない事柄を理由に不利益を及ぼすものであり、法の下の平等に反し違憲であるとの判断を示しました。
イ【正】
最高裁判所は2008年、日本人の父と外国人の母との間に生まれ、出生後に父から認知された子について、父母が婚姻していないと日本国籍の取得を認めない国籍法の規定は、法の下の平等に反し違憲であるとの判断を示しました。
ウ【正】
最高裁判所は2015年、女性にのみ6か月の再婚禁止期間を設けた民法の規定について、離婚後100日間の禁止は前の夫の子と後の夫の子の父子関係の重複を避けるために合理的であるものの、それを超える部分は合理的根拠を欠き、法の下の平等に反し違憲であるとの判断を示しました。
ア、イ、ウはいずれも最高裁によって違憲と判断された規定です。したがって、すべてを含む⑦が正解となります。
問6:正解⑦
<問題要旨>
為替相場と金利の変動要因について、グラフを読み解きながら、為替介入や国際的な経済事象が為替レートに与える影響を理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
ア、イ、ウのいずれも誤りです。
②【誤】
ア、イが誤りです。
③【誤】
イが誤りです。
④【誤】
ア、イが誤りです。
⑤【誤】
イが誤りです。
⑥【誤】
ア、イが誤りです。
⑦【正】
ア:円高(円の価値を上げる)を目的とした為替介入は、政府・日本銀行が外国為替市場でドルを売って円を買うことで行われます。このとき、介入の原資となるのは政府・日銀が保有するドルなどの外貨(外貨準備)であるため、介入によって外貨準備は「減少」します。
イ・ウ:サブプライムローン問題が深刻化した2008年以降、アメリカは景気対策として大幅な金融緩和を行い、政策金利であるFFレート(グラフの実線)をゼロ近くまで引き下げました。一方、日本の無担保コールレート(グラフの点線)はもともと低水準で大きな変動はありませんでした。その結果、日米の金利差は「縮小」しました。一般的に、金利の高い国の通貨は買われやすくなりますが、この場合はアメリカの金利が低下したため、ドルを売って円を買う動きが強まり、為替相場は「円高」の方向に進みました。グラフでも、2008年以降、ドル円レート(左軸)の数値が下落(円高)していることが確認できます。
したがって、ア「減少」、イ「縮小」、ウ「円高」の組み合わせである⑦が正解です。
⑧【誤】
ウが誤りです。
問7:正解④
<問題要旨>
インフレーションの種類(コスト・プッシュ/ディマンド・プル)と、物価変動が資産・負債の実質価値に与える影響について、資料と関連付けて理解できているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
ア、イともに誤りです。
②【誤】
アが誤りです。
③【誤】
イが誤りです。
④【正】
ア:会話文にある「原材料の値上がりなどが原因となるインフレーション」は、生産費用(コスト)の上昇が物価全体を押し上げる(プッシュする)ため、「コスト・プッシュ・インフレーション」と呼ばれます。よってアは正しいです。
イ:インフレーションは貨幣価値の下落を意味します。そのため、預貯金などの金融資産を多く持つ人は実質的な資産価値が目減りして不利益を受け、逆に、住宅ローンなどの負債を多く持つ人は実質的な返済負担が軽くなるため利益を受けます。図を見ると、「30歳代」の家計は預貯金より負債が多く、「60歳代」の家計は負債より預貯金が大幅に多くなっています。したがって、インフレーションによって経済的により不利益を受けるのは、多くの預貯金を持つ「60歳代」の家計となります。よってイは正しいです。
したがって、ア「コスト・プッシュ・インフレーション」、イ「60歳代」の組み合わせである④が正解です。
問8:正解③
<問題要旨>
消費者の権利保護や、公正な市場経済を維持するための法制度に関する知識について、誤っているものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
特定商取引法は、訪問販売や電話勧誘販売など、トラブルが生じやすい特定の取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと消費者を守るルールを定めています。その中で、消費者が冷静に考える期間を与えるために、一定期間内であれば無条件で契約の申し込み撤回や解除ができる「クーリング・オフ制度」が規定されています。これは正しい記述です。
②【正】
大気汚染防止法や水質汚濁防止法では、工場などから排出された有害物質によって人の生命や身体に損害が生じた場合、事業者に故意や過失がなくても損害賠償責任を負わせる「無過失責任」の原則が採用されています。これは正しい記述です。
③【誤】
ペイオフとは、預金保険制度により、金融機関が破綻した場合に預金者の預金を保護する仕組みのことです。保護される範囲は、当座預金や利息のつかない普通預金などの決済用預金は全額保護されますが、定期預金や利付普通預金などの一般預金等は、1金融機関につき預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息等に限られます。「金額にかかわらず全額の払戻しを保証する」という記述は、一般預金等については当てはまらないため、誤りです。
④【正】
公正取引委員会は、市場における公正かつ自由な競争を促進することを目的とする独占禁止法を運用するための行政機関です。企業のカルテル(不当な取引制限)や私的独占などを監視し、排除措置命令などを出す権限を持っています。これは正しい記述です。
第2問
問1:正解③
<問題要旨>
ユーゴスラビア紛争に至る背景を説明した文章の内容を、正しく読み取れているかを問う問題です。
<選択肢>
ア【誤】
メモの(1)には「合議制への移行は共和国・自治州の政治指導者間の対立につながった」とあり、対立が解消したわけではないため、この記述は誤りです。
イ【誤】
メモの(2)には、ユーゴスラビアは「国際通貨基金(IMF)による融資を受けながら経済改革を進めた」とあります。「融資を拒否した」という記述は内容と合致しないため、誤りです。
ウ【正】
メモの(1)に「一部の政治指導者たちは、自らの権力基盤を強化するためにナショナリズムを扇動し、連邦制度の再編をめぐる共和国・自治州それぞれの間の対立を民族問題と結びつけた」とあり、この記述の内容と一致します。
したがって、正しい記述はウのみであり、③が正解です。
問2:正解③
<問題要旨>
国の政策への民意の反映に関する意識調査の結果を示した2つの表から、内容を正確に読み取ることができるかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
表1で「ある程度反映されている」と答えた人の割合を見ると、年齢区分が下がるにつれて一貫して低くなっているわけではありません。例えば、50-59歳(21.6%)は40-49歳(15.4%)よりも高くなっています。したがって、この記述は誤りです。
②【誤】
表1で「あまり反映されていない」と答えた人の割合を見ると、70歳以上(46.6%)や18-29歳(51.7%)など、全ての年齢区分で半数(50%)を超えているわけではありません。特に70歳以上は半数を下回っています。したがって、この記述は誤りです。
③【正】
表2で「政治家が国民の声をよく聞く」と答えた人の割合を見ると、18-29歳(23.0%)、30-39歳(25.0%)、40-49歳(25.0%)、50-59歳(34.3%)、60-69歳(30.9%)、70歳以上(30.2%)となっており、いずれの年齢区分においても、他の選択項目の中で最も高い割合を占めています。したがって、この記述は正しいです。
④【誤】
表2で「国民が参加できる場をひろげる」と答えた人の割合を見ると、年齢が低い区分になるほど一貫して高くなっているわけではありません。例えば、40-49歳(15.8%)は30-39歳(13.9%)よりも高くなっています。したがって、この記述は誤りです。
問3:正解②
<問題要旨>
日本国憲法や国会法における、国会の構成や国会議員の地位、権能に関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
ア【誤】
日本国憲法第43条第1項は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」と定めています。「選挙区を代表する」のではなく、「全国民を代表する」とされている点が重要です。したがって、この記述は誤りです。
イ【正】
日本国憲法第51条は「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」と定めています。これは議員の免責特権と呼ばれるもので、記述の内容は正しいです。
ウ【誤】
議員立法(議員が法律案を提出すること)には、所属する議院の議員の一定数以上の賛成が必要です。衆議院議員が法律案を提出する場合、参議院議員の賛成は不要です(逆も同様です)。したがって、この記述は誤りです。
正しい記述はイのみであるため、②が正解となります。
問4:正解③
<問題要旨>
民主化の度合いを測る指標(自由民主主義指数)について、資料の表と会話文をヒントに、民主主義を支える要素と考え方を理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
イが誤りです。
②【誤】
イが誤りです。
③【正】
ア:会話文でXは「選挙で選ばれた指導者が大衆迎合的な政治を行いながら独裁的に権力を振るうことを防げる」仕組みについて話しています。これは、権力が一つの機関に集中するのを防ぎ、相互に監視・抑制させる「権力の抑制と均衡(チェック・アンド・バランス)」の考え方を指します。資料にある「司法権の独立」もその一例です。よってアは「権力の抑制と均衡」です。
イ:会話文でYは「1990年の時点では三つの国の中で最も高い評価だったのに、2020年の時点では最も低い評価に変わっている」国を指摘しています。表を見ると、1990年の指数が最も高いのはL国(0.72)であり、2020年の指数が最も低いのもL国(0.36)です。この条件に当てはまるのはL国です。よってイは「L国」です。
したがって、ア「権力の抑制と均衡」、イ「L国」の組み合わせである③が正解です。
④【誤】
ア、イともに誤りです。
⑤【誤】
ア、イともに誤りです。
⑥【誤】
アが誤りです。
問5:正解④
<問題要旨>
国際的な人権保障に関する条約や取り組みについて、日本の批准状況も含めた正確な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
クラスター爆弾禁止条約(オスロ条約)は、NGO(非政府組織)などが主導した国際交渉の結果、2008年に採択され、2010年に発効しています。「採択されなかった」という記述は誤りです。
②【誤】
集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約(ジェノサイド条約)は1948年に採択されましたが、日本は2024年現在、この条約を批准していません。「日本は批准している」という記述は誤りです。
③【誤】
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)は、条約の目的及び趣旨に両立しない留保(条約の一部条項の適用を拒否すること)を禁止していますが、すべての留保を禁止しているわけではありません。「留保付きで…批准を行うことを禁止している」という記述は不正確であり、誤りです。
④【正】
市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約、B規約)には、締約国の国民が自国の人権侵害を国連の規約人権委員会に通報できる制度を定めた「第1選択議定書」と、死刑制度の廃止を定めた「第2選択議定書」があります。日本はB規約本体は批准していますが、これら二つの選択議定書はいずれも批准していません。したがって、この記述は正しいです。
問6:正解③
<問題要旨>
公害苦情件数の推移を示した棒グラフと、日本の公害・環境問題の歴史(関連法の制定など)を照らし合わせ、グラフから読み取れる内容として誤っている記述を特定する問題です。
<選択肢>
①【正】
環境基本法の制定年(1993年)を含む「期間c(1990-2000)」を見ると、公害苦情件数の合計は1990年の7.4万件(4.9+2.5)から2000年の8.4万件(6.4+2.0)へと増加しています。また、合計に占める典型7公害の割合は1990年の約66%(4.9/7.4)から2000年の約76%(6.4/8.4)へと上昇しています。よって、この記述は正しいです。
②【正】
環境庁の設置年(1971年)を含む「期間b(1970-1980)」を見ると、合計件数は1970年の6.3万件(5.9+0.4)から1980年の6.5万件(5.5+1.0)へと増加しています。また、典型7公害の割合は1970年の約94%(5.9/6.3)から1980年の約85%(5.5/6.5)へと低下しています。よって、この記述は正しいです。
③【誤】
環境省の設置年(2001年)を含む「期間d(2000-2010)」を見ると、公害苦情件数の合計は2000年の8.4万件(6.4+2.0)から2010年の8.0万件(5.5+2.5)へと「減少」しています。記述にある「合計は増加し」という部分がグラフから読み取れる内容と異なるため、この記述は誤りです。
④【正】
公害対策基本法の制定年(1967年)を含む「期間a(1966-1970)」を見ると、合計件数は1966年の2.1万件(2.0+0.1)から1970年の6.3万件(5.9+0.4)へと増加しています。また、典型7公害の割合は1966年の約95%(2.0/2.1)から1970年の約94%(5.9/6.3)へとわずかに低下しています。よって、この記述は正しいです。
問7:正解⑤
<問題要旨>
地方自治法における地方公共団体の事務の区分(自治事務と法定受託事務)について、その定義と具体例を正しく理解できているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
イ、ウが誤りです。
②【誤】
ウが誤りです。
③【誤】
ウが誤りです。
④【誤】
イ、ウが誤りです。
⑤【正】
ア・ウ:地方公共団体の事務は、自治事務と法定受託事務に大別されます。会話文で「国などが本来果たすべき役割に関連し、国などが実施方法を指示して」行われると説明されているのは「法定受託事務」です。それ以外の地方公共団体の事務が「自治事務」です。よって、アには「法定受託」、ウには「自治」が入ります。
イ・エ:法定受託事務の具体例としては、国が本来行うべき事務である「旅券(パスポート)の交付」や国政選挙の執行などがあります。一方、自治事務の例としては、「都市計画の決定」や公園・学校の設置管理、ごみ処理、そして「病院や薬局の開設許可」などの保健衛生に関する事務があります。会話文の流れから、イには法定受託事務の例である「旅券の交付」が、エには自治事務の例である「病院や薬局の開設許可」が入ると考えられます。
これらの組み合わせを見ると、イに「旅券の交付」、ウに「自治」が入る⑤が正解となります。
⑥【誤】
イが誤りです。
問8:正解①
<問題要旨>
イギリスの政治学者ジェームズ・ブライスの有名な言葉「地方自治は民主政治の最良の学校である」が意味するところを、正しく説明している選択肢を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
この言葉は、住民が自分たちの身近な地域の問題について考え、議論し、決定に参加する「地方自治」という経験を通じて、主権者として政治に参加するために必要な知識や能力、責任感を身につけることができる、ということを意味しています。つまり、地方自治が国全体の民主政治を担う市民を育てる訓練の場(学校)になる、という比喩です。この記述は、その趣旨を最も的確に説明しています。
②【誤】
「中央政府をモデルとして」という部分が誤りです。地方自治の価値は、中央政府の模倣ではなく、地域住民の自発的な参加にあります。
③【誤】
これは「地方分権」や「補完性の原則(住民に最も近い基礎自治体が優先的に役割を担うべきという考え)」を説明するものであり、「学校」という比喩が持つ「市民の教育・育成」という側面を捉えていません。
④【誤】
この言葉が重視するのは、代表者に任せる(間接民主制)ことよりも、住民自身が担い手として政治に参加する(直接民主主義的な)経験です。「代表者に決定を任せることが重要」という記述は、その趣旨とは異なります。
第3問
問1:正解③
<問題要旨>
名目GDPと実質GDPの関係、および名目経済成長率の計算方法についての基本的な理解を問う計算問題です。
<問題の解き方>
ア(名目経済成長率):
名目経済成長率は、基準年の名目GDPから比較年の名目GDPがどれだけ増加したかの割合です。
計算式:( (比較年の名目GDP – 基準年の名目GDP) / 基準年の名目GDP ) * 100
問題の数値を当てはめると、( (110 – 88) / 88 ) * 100 = ( 22 / 88 ) * 100 = 0.25 * 100 = 25 (%) となります。
よって、アは25です。
イ(2021年の実質GDP):
実質GDPは、名目GDPをGDPデフレーター(物価変動の影響を示す指数)で割ることで求められます。基準年(2020年)の物価を100として計算します。
計算式:比較年の実質GDP = ( 比較年の名目GDP / 比較年のGDPデフレーター ) * 100
問題の数値を当てはめると、2021年の実質GDP = ( 110 / 110 ) * 100 = 1 * 100 = 100 (億ドル) となります。
よって、イは100です。
したがって、アが25、イが100となる③が正解です。
<選択肢>
①【誤】
アが誤りです。
②【誤】
ア、イともに誤りです。
③【正】
上記の計算の通りです。
④【誤】
イが誤りです。
問2:正解②
<問題要旨>
企業の財務諸表の一つである貸借対照表(バランスシート)の仕組みと、それを用いて計算される自己資本比率について理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
イが誤りです。
②【正】
ア:表は、左側に「資産」、右側に「負債・純資産」を記載し、左右の合計額が必ず一致する(バランスする)形式になっています。これは企業の特定の時点での財政状態を示す「貸借対照表(バランスシート)」です。よってaが正しいです。
イ:自己資本比率は、総資産に占める純資産(自己資本)の割合を示す指標で、企業の財務の健全性を測るために用いられます。
計算式:自己資本比率 (%) = ( 純資産 / 総資産 ) * 100
表から、純資産は「資本金4億円+利益剰余金2億円=6億円」です。
総資産は、負債と純資産の合計額(または資産の合計額)なので、「借入金6億円+純資産6億円=12億円」です。
これを式に当てはめると、( 6 / 12 ) * 100 = 0.5 * 100 = 50 (%) となります。よってdの50が正しいです。
したがって、a-dの組み合わせである②が正解です。
③【誤】
アが誤りです。「損益計算書」は、一定期間の収益と費用を対比させて利益や損失を示す財務諸表です。
④【誤】
アが誤りです。
問3:正解④
<問題要旨>
財・サービスを、その性質である「競合性(ある人の消費が他人の消費を妨げるか)」と「排除性(対価を支払わない人を消費から排除できるか)」によって4種類に分類する問題です。
<財の分類>
・私的財:競合性あり、排除性あり(例:ハンバーガー、衣服)
・公共財(純粋公共財):競合性なし、排除性なし(例:国防、警察)
・共有資源(コモンズ):競合性あり、排除性なし(例:混雑した無料道路、漁場の魚)
・料金財(クラブ財):競合性なし、排除性あり(例:ケーブルテレビ、空いている有料道路)
<選択肢の検討>
ア:競合性あり、排除性なしの財(共有資源)
bの「渋滞している無料の一般道路」は、誰でも無料で利用できるので排除性はありませんが、誰かが利用すると他の人が利用しにくくなる(渋滞が悪化する)ため、競合性があります。これが当てはまります。
イ:競合性なし、排除性ありの財(料金財)
cの「有料で確実に視聴できる動画配信サービス」は、料金を払った人だけが利用できるので排除性があり、デジタルコンテンツなので基本的に何人が同時に視聴しても他の人の視聴を妨げないため、競合性はありません。これが当てはまります。
ウ:競合性なし、排除性なしの財(公共財)
aの「国防」は、料金を払っていない国民も利益から排除できず(排除性なし)、ある国民が国防の利益を受けても他の国民が受ける利益が減るわけではない(競合性なし)ので、典型的な公共財です。これが当てはまります。
したがって、ア-b, イ-c, ウ-a の組み合わせである④が正解です。
問4:正解③
<問題要旨>
日本の財政における国債発行のルールや現状についての正確な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
特例国債(赤字国債)は、税収だけでは歳出をまかなえない場合に、財政法の特例として法律を制定して発行される国債です。1990年代初頭のバブル崩壊後の数年間(平成3~6年度)は、景気が良く税収が多かったため、発行されなかった時期があります。「発行しなかった年度はない」は誤りです。
②【誤】
国債依存度(歳入総額に占める国債発行額の割合)は、リーマン・ショック後の2009年度や、近年のコロナ禍対応などで50%を超えた年度があります。「50%を超えた年度はない」は誤りです。
③【正】
財政法第4条では、国の歳出は原則として国債以外の歳入でまかなう(国債発行の原則禁止)と定めています。ただし、例外として、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で「建設国債」を発行することが認められています。これは正しい記述です。
④【誤】
基礎的財政収支(プライマリーバランス)は、国債費(過去の借金の元利払い)を除いた歳出と、国債発行収入を除いた歳入(税収など)との収支のことです。「歳出」が「歳入」を上回る場合に赤字となります。記述は「下回ると」赤字になる、と逆の説明をしているため誤りです。
問5:正解③
<問題要旨>
外国為替レートの変動(円安・円高)が、外貨と円を両替する際にどのような影響を与えるかを計算する問題です。
<問題の解き方>
支払時の為替レートを計算する
60万円を両替して5,000米ドルになったので、
600,000 (円) ÷ 5,000 (ドル) = 120 (円/ドル)
支払時のレートは1ドル120円でした。
返金時の為替レートを計算する
5,000米ドルを両替して70万円になったので、
700,000 (円) ÷ 5,000 (ドル) = 140 (円/ドル)
返金時のレートは1ドル140円でした。
為替レートの変動を計算・判断する
ア(レートの変動幅):140円/ドル – 120円/ドル = 20円/ドル。レートは20円変動しました。よって、アはbの20です。
イ(円安か円高か):1ドルを得るために必要な円の額が120円から140円に増えています。これは円の価値がドルに対して下がったこと、つまり「円安」になったことを意味します。よって、イはeの円安です。
したがって、アが20、イが円安となる③が正解です。
問6:正解⑥
<問題要旨>
中小企業基本法とその目的、および日本経済における中小企業の役割や特徴についての知識を問う問題です。
<選択肢>
ア【誤】
中小企業基本法は1963年に制定され、当初の目的は大企業との生産性の格差是正などでした。その後、1999年の改正で、画一的な保護政策から転換し、多様で活力ある中小企業の自主的な努力を支援する方針(起業促進や経営革新など)へと目的が変更されました。記述は制定当初と改正後の目的が逆になっています。
イ【正】
日本の企業数全体に占める中小企業の割合は99%以上、従業員数全体に占める割合も約7割にのぼり、いずれも大企業を大きく上回っています。これは日本経済の大きな特徴です。したがって、この記述は正しいです。
ウ【正】
消費者のニーズが多様化する中で、大企業では対応しきれない小規模な市場(ニッチ市場)が生まれています。こうした市場で、独自の技術力やアイデアを活かして活躍する中小企業が多く存在します。したがって、この記述は正しいです。
正しい記述はイとウであるため、その組み合わせである⑥が正解となります。
問7:正解③
<問題要旨>
経済学の基本的な概念である「機会費用」の意味を、具体的な事例に当てはめて正しく理解できているかを問う問題です。
<機会費用の考え方>
機会費用とは、ある選択をしたことによって、選ばなかった選択肢のうち「最も価値の高いもの」から得られたであろう利益のことを指します。
<問題の分析>
生徒Xは「ボランティア活動に従事する」という選択をしました。
このとき、選ばなかった選択肢は以下の二つです。
・アルバイトJに従事して8,000円の給与を得る
・アルバイトKに従事して12,000円の給与を得る
このうち、価値がより高いのは「アルバイトKの12,000円」です。
したがって、Xがボランティア活動に従事することの機会費用は、得られなかった最大の利益である12,000円となります。
<選択肢>
①【誤】
8,000円は、選ばなかった選択肢のうち価値が最大のものではありません。
②【誤】
10,000円という数値は問題文に登場しません。
③【正】
上記の通り、選ばなかった選択肢の中で最大の価値は12,000円です。
④【誤】
20,000円(8,000円+12,000円)は、機会費用の定義には当てはまりません。機会費用は、失った選択肢の価値の合計ではなく、失った最善の選択肢の価値を指します。
問8:正解⑤
<問題要旨>
需要曲線を示したグラフから、特定の条件下での価格を読み取ることと、需要の価格弾力性(価格の変化に対する需要量の変化の度合い)を比較する問題です。
<問題の解き方>
ア:
SKバーガーは200個だけ販売されます。「すべて売り切ることができる最も高い価格」とは、需要量がちょうど200個以上になるような価格の中で、最も高い価格を指します。
グラフの「●:今年度の需要の予測」を見ると、
・価格400円のとき、需要量は100個
・価格300円のとき、需要量は200個
・価格200円のとき、需要量は300個
・価格100円のとき、需要量は400個
となっています。
需要量が200個以上になる価格は、300円、200円、100円です。この中で最も高い価格は300円です。300円で売れば、予測上はちょうど200個売れて完売します。よって、アはcの300円です。
イ:
需要の価格弾力性、つまり「同じ大きさの価格の変化に対して」「需要量の変化が大きい」のはどちらかを比較します。これは、需要曲線の傾きがより緩やか(水平に近い)な方が、弾力性が大きい(需要量の変化が大きい)ことを意味します。
・今年度(●):価格が400円→300円に100円下がると、需要量は100個→200個に100個増える。
・昨年度(×):価格が400円→300円に100円下がると、需要量は250個→300個に50個増える。
同じ100円の価格変化に対して、今年度の方が需要量の変化(100個)が昨年度(50個)よりも大きいです。グラフを見ても、今年度(●を結んだ線)の方が昨年度(×を結んだ線)よりも傾きが緩やかです。
よって、需要量の変化が大きいのは「e 今年度」です。
したがって、アが300円、イが今年度となる⑤が正解です。
第4問
問1:正解①
<問題要旨>
日本の労働市場における女性の労働力率の特徴と、高齢者雇用に関する法律についての知識を組み合わせる問題です。
<選択肢>
①【正】
ア:日本の女性の年齢階級別労働力率グラフは、結婚・出産期にあたる30代で一度労働力率が低下し、子育てが一段落する40代で再び上昇するという、アルファベットのMの字に似た形を描くことが特徴で、これは「M字型カーブ」と呼ばれています。近年、このM字の谷は浅くなる傾向にありますが、依然として特徴として残っています。よってアは「M字型」です。
イ:高齢者の就労を促進するため、企業に対して65歳までの雇用確保措置(定年制の廃止、定年の引上げ、継続雇用制度の導入のいずれか)を義務付けている法律は「高年齢者雇用安定法」です。2021年の改正では、さらに70歳までの就業機会確保が努力義務とされました。よってイは「高年齢者雇用安定法」です。
したがって、ア「M字型」、イ「高年齢者雇用安定法」の組み合わせである①が正解です。
②【誤】
イが誤りです。「職業安定法」は、職業紹介や労働者募集に関するルールを定める法律です。
③【誤】
アが誤りです。「逆U字型」は、一般的に経済発展と環境汚染の関係(環境クズネッツ曲線)などで見られるカーブの形状です。
④【誤】
ア、イともに誤りです。
問2:正解③
<問題要旨>
日本における外国人労働者の受け入れ制度(技能実習、EPAに基づく特定活動、特定技能)について説明した文章の内容を、正しく読み取れているかを問う問題です。
<選択肢>
ア【誤】
メモには「技能実習生に『転籍』(同じ業種の他の企業に移ること)が認められないことなどが人権侵害にあたるといった指摘もある」とあり、「転籍は認められない」ことが読み取れます。しかし、「実習できる職種は限定されない」という部分が誤りです。メモには「技能評価制度が整備されている一定の職種での実習が認められる」とあり、職種は限定されています。
イ【誤】
メモには、EPAに基づく「特定活動」の在留資格について、「一定の在留期間のうちにそれらの資格試験に合格できなかったときには、帰国を余儀なくされる」とあります。「上限なく在留期間の更新が認められる」わけではないため、この記述は誤りです。
ウ【正】
メモには、在留資格「特定技能」について、「『特定技能』第2号に認定されると、『転籍』が認められ、在留期間の更新の上限がなくなり、一緒に暮らすために海外から家族を呼び寄せることもできる」と明記されています。したがって、この記述は正しいです。
正しい記述はウのみであるため、③が正解となります。
問3:正解④
<問題要旨>
日本の出生数と合計特殊出生率の推移を示したグラフを読み解き、その内容に関する記述として誤っているものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
グラフから、1949年の出生数は約270万人(2,696,638人)、2020年の出生数は約84万人(840,835人)です。270万 ÷ 84万 ≒ 3.2 であり、「3倍以上となっている」という記述は正しいです。
②【正】
第1次ベビーブーム(1947~49年)、第2次ベビーブーム(1971~74年)では、出生数が顕著に増加する山が形成されています。しかし、第2次ベビーブーム世代が親となる1990年代後半以降、グラフに出生数の明確な山は見られず、「第3次ベビーブームと呼べるような出生数の増加はなかった」という記述は正しいです。
③【正】
グラフの線(合計特殊出生率、右軸)を見ると、2005年(約1.26)から2015年(約1.45)にかけて上昇しています。一方、棒グラフ(出生数、左軸)を見ると、2005年(約106万人)から2015年(約100万人)にかけて減少しています。したがって、この記述は正しいです。合計特殊出生率が上昇しても、その率をかける対象となる女性人口(特に15~49歳)が減少していれば、出生数は減少することがあります。
④【誤】
人口を長期的に維持するために必要とされる合計特殊出生率の水準は、一般的に2.07~2.08程度(人口置換水準)とされています。グラフを見ると、1980年の合計特殊出生率は約1.75であり、この人口置換水準を大きく下回っています。「人口水準を安定的に維持する値を上回っている」という記述は誤りです。
問4:正解⑥
<問題要旨>
日本の地方自治制度における住民の直接請求権(リコール)や、オンブズマン(オンブズパーソン)制度、首長の再議権などに関する知識を問う問題です。
<選択肢>
ア【誤】
地方自治法に基づき、有権者は、規定数の署名を集めることで、首長(市町村長や都道府県知事)の解職(リコール)を請求できるだけでなく、地方議会の議員の解職も請求することができます。したがって、この記述は誤りです。
イ【正】
オンブズマン(オンブズパーソン)制度は、住民からの行政に対する苦情を受け付け、中立的な立場から調査し、問題があれば行政機関に対して是正や改善の勧告を行う制度です。法律による全国一律の制度ではなく、一部の地方公共団体が条例によって設置しています。したがって、この記述は正しいです。
ウ【正】
地方公共団体の首長は、議会の議決に異議がある場合、その理由を示して議決をやり直すよう求める「再議」に付すことができます。特に予算や条例に関する議決に対して行使される拒否権の一種です。したがって、この記述は正しいです。
正しい記述はイとウであるため、その組み合わせである⑥が正解となります。
問5:正解②
<問題要旨>
過疎化・高齢化が進む地域(限界集落)の状況を、表のデータから読み解き、地域活性化の取り組み(六次産業化)と結びつける問題です。
<選択肢>
①【誤】
イが誤りです。「転作」は、米など特定の作物から別の作物へ栽培を転換することです。
②【正】
ア:限界集落の問題がより深刻な地域を判断します。表を見ると、地域Jは地域Kに比べて、2020年時点での人口増減率のマイナス幅が大きく(-27.4%)、高齢化率は低いものの、共同生活の維持の困難さを示す「農業用水路の保全率」が著しく低く(33.3%)、回復の兆しも見えません。一方、地域Kは高齢化率が非常に高いものの、農業用水路の保全率は一時低下した後に回復しており、地域コミュニティ機能が比較的維持されている可能性があります。したがって、問題がより深刻化しているのは「地域J」と判断できます。
イ:会話文にある「農作物の生産だけでなく、農作物の製品への加工や製品の流通・販売などと一体化させて付加価値を高める」取り組みは、「六次産業化」と呼ばれます(農業(1次)×加工(2次)×流通・販売(3次)=6次)。よってイは「六次産業化」です。
したがって、ア「地域J」、イ「六次産業化」の組み合わせである②が正解です。
③【誤】
ア、イともに誤りです。
④【誤】
アが誤りです。
問6:正解⑤
<問題要旨>
日本の人口動態(高齢化社会、人口減少社会)と社会保障給付費の推移に関する複数の資料を統合的に分析し、発表原稿の空欄を埋める問題です。
<選択肢の解き方>
ア:
「高齢化社会」(高齢化率7%超)、「高齢社会」(同14%超)、「超高齢社会」(同21%超)という区分に従って判断します。資料1の「高齢化率」を見ると、14%を超えたのは「1995年」(14.6%)です。よってアは「1995年」です。
イ:
「死亡者数が出生者数を上回る状態に転換した」年を判断します。資料1で「出生者数」と「死亡者数」を比較すると、2000年までは出生者数が上回っていますが、「2005年」には出生者数106.3万人に対して死亡者数が108.4万人となり、初めて死亡者数が出生者数を上回る「自然減」に転じています。したがって、人口減少社会に移行したのは「2000年代」と考えられます。
ウ:
資料2の図aと図bのどちらが高齢者関係給付費かを見分けます。高齢化の急速な進展に伴い、年金や医療・介護にかかる費用である高齢者関係給付費は、児童手当などを含む児童・家族関係給付費に比べて、金額の規模が圧倒的に大きいはずです。図aは給付費が最大で90兆円近くに達しているのに対し、図bは最大でも12兆円に届きません。したがって、金額の大きい図aが「高齢者関係給付費」を示していると判断できます。
以上の分析から、ア「1995年」、イ「2000年代」、ウ「図a」の組み合わせである⑤が正解となります。