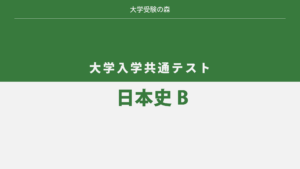解答
解説
第1問
問1:正解②
<問題要旨>
会話文とメモを参考に、空欄ア(北条政子の名前の構成)と空欄イ(明治政府が平民に苗字を名乗らせた目的)に当てはまる正しい文の組合せを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
ア:会話文とメモから、「北条」は地名に由来する「苗字(名字)」であり、「姓」は「平」であることがわかります。 したがって「苗字(名字)+名(個人名)」 です。
イ:明治政府が平民に苗字を名乗らせた(平民苗字許容令1870年、平民苗字必称令1875年)のは、戸籍(壬申戸籍1871年)を整備し、国民を正確に把握するためです。 身分の撤廃 はその後の四民平等の流れの中で進みますが、苗字を名乗らせた直接の目的ではありません。
②【正】
ア:「北条政子」は、「北条」という苗字(名字)と「政子」という名(個人名)の組合せです。
イ:明治政府は、徴兵(徴兵令1873年)や徴税(地租改正1873年~)などを確実に行うため、戸籍制度を整え、国民一人ひとりを「近代国家の国民として把握する」 必要がありました。その一環として平民にも苗字を義務付けました。
③【誤】
ア:「北条」は「姓」ではなく「苗字(名字)」です。
イ:理由は①と同じです。
④【誤】
ア:「北条」は「姓」ではなく「苗字(名字)」です。
イ:内容は正しいですが、アが誤りです。
問2:正解④
<問題要旨>
中世の二人の武士(X・Y)に関する説明文を読み、それぞれに当てはまる「姓」や「苗字」をa~dから選ぶ問題です。
<選択肢>
X:信濃国(長野県)の地名(木曽)で通称され、「朝日(旭)将軍」とも呼ばれ、従兄弟(源義経・範頼)との合戦で敗死した人物は、木曽義仲です。 木曽義仲の「姓」は「源」(b)です。
Y:「姓」は源氏 だが、所領の地名(足利)を「苗字」として名乗り、室町幕府(将軍足利義教)と対立して自害(永享の乱、1438年)した東国支配者(関東公方)は、足利持氏です。 よって、Yの「苗字」は「足利」(d)です。
したがって、正しい組合せは X-b 、Y-d となります。
①【誤】X-a , Y-c ②【誤】X-a , Y-d ③【誤】X-b , Y-c ④【正】X-b , Y-d
問3:正解⑤
<問題要旨>
近世(江戸時代)に活躍した3人の人物の名前に関する出来事(I 近松門左衛門、II 江川英竜、III 三浦按針)を、年代の古いものから順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
I:近松門左衛門(本名:杉森信盛)は、江戸時代前期の元禄文化期(17世紀末~18世紀初頭)に活躍した浄瑠璃・歌舞伎の作者です。
II:江川英竜(太郎左衛門)は、江戸時代後期の幕末(19世紀半ば)に活躍した伊豆韮山代官です。ペリー来航(1853年)後、幕府の命で伊豆韮山に反射炉を築きました(1857年完成)。
III:三浦按針(ウィリアム=アダムズ)は、江戸時代初期(17世紀初頭)に来日(1600年)したイギリス人で、徳川家康の外交・貿易顧問として活躍しました。
年代順に並べると、III(江戸初期)→ I(江戸前期・元禄)→ II(江戸後期・幕末)となります。 したがって、正解は⑤(III – I – II)です。
問4:正解③
<問題要旨>
嵯峨天皇の子どもの名前の特徴(系図参照) とその背景(下線部d) に関して述べた文a~dから、最も適当なものの組合せを選ぶ問題です。
<選択肢>
a【誤】会話文にあるように、嵯峨天皇以前の「山部」(桓武天皇)や「大伴」(淳和天皇)といった養育氏族の名称が消滅した のは正しいです。しかし、「正良」「正子」 のような良い意味を持つ漢字一字を共通して用いる命名法は、和風化ではなく、当時の唐風化(弘仁・貞観文化)の影響です。
b【正】aの通り、養育氏族の名称が消滅し、 唐風化の影響(良い意味を持つ漢字の使用)が認められます。
c【正】系図を見ると、嵯峨天皇の子どもには「信(源)」「弘(源)」「潔姫(源)」 など、「源」の姓を与えられて臣下となった者(臣籍降下)がいたことがわかります。 これは皇族の増加による財政圧迫を避けるためなどの理由がありました。
d【誤】「正良親王」「業良親王」「秀良親王」 のように兄弟で同じ漢字(この場合は「良」)が使われていますが、これは兄弟関係を示すためであり、皇位継承の順番を明確にするものではありません。 実際、皇位は正良親王(仁明天皇) が継いでいます。
したがって、正しい組合せは b と c です。 ①【誤】a , c ②【誤】a , d ③【正】b , c ④【誤】b , d
問5:正解①
<問題要旨>
1925年~1950年の生まれ年別男性名ベスト3の表(下線部e) から読み取れる内容に関して述べた文X・Yの正誤を判定する問題です。
<選択肢>
X【正】
日本がアメリカ・イギリスに宣戦布告し、太平洋戦争が始まったのは1941年12月です。表を見ると、翌年の1942年から終戦の1945年にかけて、「勝」や「勝利」といった、戦局や勝利を意識した名前がベスト3に頻繁に登場しています。 したがって、戦場の拡大とともに勝利を祈願するような名前が優勢になったというのは正しいです。
Y【正】
1925年(大正14年)の翌年、1926年(大正15年)12月に昭和天皇が即位し、元号が「昭和」に改元されました。表を見ると、改元直後の1927年、1928年に、新元号「昭和」の一字である「昭」を用いた「昭二」「昭三」「昭」がベスト3に入っています。 したがって、改元の影響で新元号の一字を冠した名前が登場したというのは正しいです。
両方とも正しいため、正解は①です。
問6:正解①
<問題要旨>
会話文とメモ の内容を踏まえ、「人名から見た日本の歴史」について述べた意見a~dから、最も適当なものの組合せを選ぶ問題です。
<選択肢>
a【正】大輝さんのメモに「天皇は姓を持たない」 、「姓(かばね)は大王から氏に与えられた称号」 とある通り、天皇は臣下に「姓(せい・かばね)」を与える存在であり、自らは姓を持たないとされています。
b【誤】江戸時代以前の支配階層、例えば北条政子(平氏)と源頼朝(源氏)のように 、夫婦はそれぞれの「姓(せい)」や「氏(うじ)」を名乗っており、夫婦同姓が原則ではありませんでした。 明治の民法で「家」の姓(苗字)に統一されるようになります。
c【正】会話文に「苗字帯刀の禁止というように、あくまでも公称が許されなかっただけ」 とあるように、百姓・町人が苗字を公称することを禁じたのは、苗字帯刀を武士の特権とすることで、武士身分とそれ以外の身分との差別化を図り、身分秩序を維持するためと考えられます。
d【誤】明治の民法(1898年)が女性に嫁ぎ先の苗字(家の氏)を使用させたのは、家父長制に基づく「家」制度を法的に確立するためです。 個人の権利や理性を重視する啓蒙思想は、むしろ「家」制度の束縛とは相反する側面を持ちます。
したがって、正しい組合seは a と c です。
①【正】a , c ②【誤】a , d ③【誤】b , c ④【誤】b , d
第2問
問1:正解①
<問題要旨>
600年に派遣された遣隋使(年表の下線部①) や、その前後の日本の出来事について述べた文として正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
『宋書』倭国伝によると、5世紀に倭の五王(讃・珍・済・興・武)が中国の南朝(宋)に使節を送っています。最後の「武」(雄略天皇とされる)の上表が478年です。600年の遣隋使 は、それから100年以上(約122年)経過した、久しぶりの中国王朝への公式な使節派遣でした。
②【誤】
曇徴は高句麗の僧で、610年に来日し、紙や墨の技法を伝えたとされます。600年の遣隋使とは関係ありません。
③【誤】
冠位十二階は603年、憲法十七条(十七条憲法)は604年に制定されたとされ、いずれも600年の遣隋使派遣より後の出来事です。
④【誤】
日本初の本格的な律令である大宝律令が施行されたのは701年です。 600年の時点では、まだ律令は施行されていません。
問2:正解④
<問題要旨>
年表中のX(8世紀の遣唐使) とY(9世紀の遣唐使) が日本にもたらした文化について述べた次の文a~dとの組合せとして正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
a【誤】真言宗を広めたのは空海です。 空海が遣唐使として唐に渡ったのは804年で、これは年表のY(804~06年の遣唐使)に該当します。
b【正】日本に正式な戒律を伝えた唐僧は鑑真です。 鑑真は度重なる渡航の失敗を経て、753年に日本に到着しました。これは年表のXの期間中(752~54年の遣唐使 が派遣されていた時期)にあたります。
c【誤】阿弥陀如来が迎えに来る情景を描いた来迎図は、平安時代中期以降(10世紀後半~11世紀)、浄土信仰が貴族社会に広まる中で盛んに作られました(例:平等院鳳凰堂)。 X・Yの時期(8~9世紀)ではありません。
d【正】密教の世界を図像として描いた両界曼荼羅は、aの空海が唐から持ち帰りました。 したがって、これはY(9世紀初頭)に関連します。
正しい組合せは X-b、Y-d となります。
①【誤】X-a , Y-c ②【誤】X-b, Y-c ③【誤】X-a , Y-d ④【正】X-b, Y-d
問3:正解④
<問題要旨>
年表の下線部②(庚午年籍) に関連し、正倉院に残る古代の計帳の史料(天平五年=733年) について述べた後の文a~dから、最も適当なものの組合せを選ぶ問題です。
<選択肢>
a【誤】史料には「課口一人」 「現に輸す 一人」 と明記されており、この戸で調・庸を納めるのは戸主(従六位上於伊美吉子首、年七十九) の1人のみです。
b【正】史料には「去年の計帳に定むる良賤の口十五人」 と「今年の計帳に現に定むる良賤の大小口十五人」 との記載があり、前年と当年の人数を比較・記載していることから、計帳によって年ごとの戸の人数の変動が把握されていたことがわかります。
c【誤】史料には「男於伊美吉伊賀麻呂 年四十七 和銅七年逃」 、「奴尼麻呂 年六十一 和銅七年逃」 と記載されています。和銅7年(714年)に逃亡した人物が、天平5年(733年)の計帳 にも依然として記載され続けていることから、逃亡しても計帳から削除されていなかったことがわかります。
d【正】史料には「正丁 左下唇黒子」 、「正女左頬黒子」 と、課役対象者の身体的特徴(ほくろの位置)が記されています。これは、本人を特定するためと考えられます。
したがって、正しい組合せは b と d です。
①【誤】a , c ②【誤】a , d ③【誤】b , c ④【正】b , d
問4:正解③
<問題要旨>
税に関する3つの文章(I・II・III)が、それぞれ憲法十七条・養老令・延喜式のいずれかの一部であるかを判断し、古いものから年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
I:「凡そ調の絹・純・糸・綿・布は、並びに郷土の所出に随えよ。」 これは、調として納める物品はその土地の産物でよいとする律令(行政法)の具体的な規定です。これは「養老令」(718年撰定開始、757年施行) の一部(賦役令)にあたります。
II:「国司 国造、百姓に斂る(税をとる)ことなかれ。国に二の君なし、民に両の主なし。」 これは、地方官による恣意的な徴税を戒める内容で、聖徳太子が定めたとされる「憲法十七条」(604年)の一部(第十二条)です。
III:「凡そ諸国の調・庸の米・塩は、令条の期(律令で定められた期限)の後、七箇月の内に納め訖(おわ)えよ。」 これは、律令(令条)で定められた納入期限をさらに具体的に定めた施行細則(式)の規定です。これは「延喜式」(905年撰定開始、927年完成) の一部にあたります。
年代順に並べると、II(憲法十七条:604年)→ I(養老令:718年~)→ III(延喜式:905年~)となります。
したがって、正解は③(II – I – III)です。
問5:正解②
<問題要旨>
年表 とこれまでの学習を踏まえ、日本古代の法整備(律令格式)について述べた文として誤っているものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
年表を見ると、中国(隋・唐)では「律令格式」の順で整備されたのに対し 、日本では「飛鳥浄御原令」(689年頃)、「大宝律令」(701年)、「養老律令」(718年撰定)と、行政法である「令」が刑法である「律」と同時か、あるいは先行して整備されました。 これは、国家機構の整備を急いだためと考えられています。
②【誤】
律令の編纂は、年表にある通り、飛鳥浄御原令(天武・持統朝)、大宝律令(文武朝)、養老律令(元正・元明朝)と、数十年隔てて行われています。 天皇の代替わりごとに行われたわけではありません。
③【正】
年表によれば、大宝律令の編纂は701年です。 律令を補足・修正する「格」と、施行細則である「式」をまとめた法典(格式)が日本で初めて体系的に編纂されたのは、「弘仁格式」(820年成立)です。 701年から820年まで100年以上が経過しており、記述は正しいです。
④【正】
年表によれば、遣唐使中止の提言(菅原道真の建議)は894年です。 「延喜格式」の編纂は905年に開始され、927年に完成しています。 したがって、格式の編纂は遣唐使が派遣されなくなった後にも行われています。
第3問
問1:正解④
<問題要旨>
会話文 を踏まえ、中世の海と人々との関わりについて述べた文として誤っているものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
会話文に「やがてはヨーロッパ人まで交流に加わる」 、「鉄砲などの新しい軍事技術」「アジアやヨーロッパから出版文化がもたらされます」 とあり、アジアやヨーロッパとの交易が新しい製品や技術をもたらしたことがわかります。
②【正】
会話文に「戦国の争乱は列島各地で人・物・文化の移動を加速させました。鉄砲などの新しい軍事技術を普及させ」 とあり、戦争が新しい道具・技術の導入や普及を促したことがわかります。
③【正】
会話文に「各地に港町ができて、海上交通がより発達します」 、「国内外の流通が活発になっ」た とあり、大量の物資を遠隔地に運搬・輸送するための海上交通が発達し、関連する技術が改良されたことは文脈から正しいと判断できます。
④【誤】
倭寇は「海をまたいで活動する人たち」 であり、会話文でも「ただの海賊だと思っていました」 とあるように、国家権力の統制から外れた(あるいは反発した)存在でした。特に前期倭寇は海賊的性格が強く、後期倭寇も密貿易商人などが中心でした。国家権力による「保護」を得ていたわけではなく、むしろ取締りの対象でした。
問2:正解⑥
<問題要旨>
中世(平安末期~戦国時代)の海上交通(下線部a) に関連する3つの出来事(I 毛利氏の兵糧搬入、II 重源の材木輸送、III 平忠盛の海賊鎮圧)を、年代の古いものから順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
I:毛利輝元が、織田信長と敵対する石山(大坂)本願寺に海上から兵糧を搬入したのは、石山戦争中の出来事(例:第一次木津川口の戦い、1576年)です。 これは戦国時代(16世紀後半)にあたります。
II:重源は、治承・寿永の乱(源平合戦)で焼失した東大寺の再建(勧進)のため、鎌倉時代初期(12世紀末~13世紀初頭)に周防国(山口県)から瀬戸内海を通じて材木を輸送しました。
III:平忠盛(平清盛の父)は、平安時代末期(院政期、12世紀前半)に瀬戸内海の海賊を鎮圧するなどの功績で、鳥羽上皇の信任を得て昇進しました。
年代順に並べると、III(平安末期)→ II(鎌倉初期)→ I(戦国時代)となります。
したがって、正解は⑥(III – II – I)です。
問3:正解①
<問題要旨>
『石山寺縁起絵巻』 に描かれた室町時代の運送業者(下線部b、図) について述べた文X・Yの正誤を判定する問題です。
<選択肢>
X【正】図に描かれているのは、馬の背に荷物(米俵など)を載せて陸路を運ぶ運送業者、すなわち馬借です。 室町時代、特に正長の徳政一揆(1428年)では、近江坂本の馬借らが中心となり、徳政(借金の帳消し)を求めて蜂起しました。
Y【正】図は『石山寺縁起絵巻』 の一部であり、石山寺のある近江国(滋賀県)の大津や坂本は、琵琶湖の水運と京都への陸路を結ぶ水陸交通の要衝でした。馬借はこうした要衝を拠点として活躍していました。
両方とも正しいため、正解は①です。
問4:正解④
<問題要旨>
16世紀の朝鮮王朝内で述べられた日朝貿易(下線部c) に関する史料 を踏まえ、当時の貿易について述べた文a~dから、正しいものの組合せを選ぶ問題です。
<選択肢>
a【誤】史料には「日本国使」「多く商物を齎し、銀両八万に至る」 とあり、日本が銀を朝鮮に「輸出」していたことがわかります。 銀は日本の輸入品ではありません。(当時、日本では石見大森銀山などで銀が増産されていました。)
b【正】史料には、朝鮮では「綿布」が民の生活に不可欠なもの であり、日本が「無用の物」(銀) と引き換えに「民の頼る所」(綿布) を輸入している状況が記されています。当時、日本は朝鮮から綿布や木綿を輸入し、衣類として普及し始めた時期にあたります。
c【誤】史料の筆者は、この貿易によって「利は彼(日本)に帰し、我れ其の弊を受く。甚だ不可たり」 と述べており、このままでは日本の利益が倍増し、朝鮮にとっては大きな「弊害」となると懸念しています。 未来に利益をもたらすとは主張していません。
d【正】cの通り、史料の筆者は、生活必需品である綿布が流出し、実用性のない銀が流入するこの貿易を続けることは、朝鮮にとって将来的に大きな弊害を及ぼすと主張(警告)しています。
したがって、正しい組合せは b と d です。
①【誤】a , c ②【誤】a , d ③【誤】b , c ④【正】b , d
問5:正解①
<問題要旨>
中世の海底の発掘調査(下線部d) に関連して、中世の遺跡を示した文X・Yと、その場所を示した地図上の位置a~dとの組合せとして正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
X:和人(本州側の人々)を館主とする館の跡で、越前焼と珠洲焼の大甕に入った大量(37万枚余り)の銅銭が発見された遺跡 は、北海道(渡島半島)函館市にある志苔館跡(しのりたてあと)です。これは中世に蝦夷地に進出した和人の拠点のひとつです。地図上のaは渡島半島の南端付近を指しており、志苔館跡の位置と一致します。
Y:沖合の海底の沈没船から元軍や高麗軍が使用したてつはうや武具、陶磁器などが発見された遺跡 は、元寇(文永・弘安の役)の激戦地であり、暴風雨で多くの船が沈んだとされる九州北部の長崎県鷹島沖が有名です。地図上のcは鷹島を含む長崎県松浦半島沖(伊万里湾口)を指しています。 (bは敦賀、dは種子島付近を指します。)
したがって、正しい組合せは X-a、Y-c です。
①【正】X-a , Y-c ②【誤】X-a, Y-d ③【誤】X-b , Y-c ④【誤】X-b , Y-d
第4問
問1:正解③
<問題要旨>
メモに記された近世の村・町(下線部a) の運営について述べた文として、誤っているものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
近世の村(むら)は、村役人(名主・庄屋、組頭、百姓代)と、検地帳に登録された土地所有者である本百姓(高持百姓)が中心となって運営されました。
②【正】
近世の村は、領主に対して年貢の納入や夫役(労働)の提供を村単位で共同で請け負いました(村請制)。
③【誤】
近世の町(ちょう)は、町役人(町名主、町年寄など)や、土地・家屋を所有する家持(いえもち)によって運営されました。家屋を借りて住む地借(じがり)・店借(たながり)といった町人は、運営に参加する権利を持たないのが一般的であり、「居住する人々の総意」 で運営されたわけではありません。
④【正】
町人は、町の共同体(町内)の成員として、上水・下水の管理、道の清掃、防火(町火消)などの役割(町人足役)を共同で担っていました。
問2:正解④
<問題要旨>
メモに記された近世の芸能・文化(下線部b) に関して述べた文I~IIIについて、古いものから年代順に正しく配列したものを選ぶ問題です。
<選択肢> I:浮世絵が多色刷りの木版画(錦絵)として広まり、東洲斎写楽が歌舞伎の役者絵を描いた のは、江戸時代中期の田沼時代~寛政の改革期(18世紀後半)です。
II:出雲阿国(出雲の阿国)の演じた踊り(かぶき踊り)が京都で好評を博した のは、江戸時代初期(17世紀初頭)です。
III:荒々しい演技(荒事)で知られる歌舞伎役者の初代市川団十郎が活躍した のは、江戸時代前期の元禄文化期(17世紀末~18世紀初頭)です。
年代順に並べると、II(江戸初期)→ III(元禄期)→ I(江戸中期)となります。
したがって、正解は④(II – III – I)です。
問3:正解②
<問題要旨>
メモに記された近世後期の支配の動揺(下線部c) に関連して、史料1(天保7年の一揆) と史料2(天明7年の打ちこわし) に関して述べた文X・Yの正誤の組合せとして正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
X【正】 史料1(天保七年=1836年の三河国での一揆)には、「もし不承知の村は、一千人の者ども押し寄せ、家々残らず打ち崩し申すべし」 とあり、一揆への参加を拒否する村に対しては、実力行使(打ちこわし)を行うと警告していることがわかります。
Y【誤】 史料2(天明七丁未年=1787年の打ちこわし)は、民衆が「米屋」や「富商人」を襲撃し、米俵や家財道具を破壊する「打ちこわし」の様子を描写しています。 これは主に都市部で発生した騒擾(そうじょう)です。「百姓たち」が「庄屋」を襲撃した とは史料から読み取れず、農村の「世直し一揆」 と断定することもできません。
したがって、Xは正、Yは誤です。
問4:正解④
<問題要旨>
メモに記された「野非人」の増加(下線部d) に関連して、1836年に江戸の町奉行所が出させた報告書(史料3) と幕府の政策に関して述べた文a~dから、最も適当なものの組合せを選ぶ問題です。
<選択肢>
a【誤】 史料3によれば、江戸の場末(町はずれ)に住んでいた「其日稼ぎの者ども」 が、家賃(店賃)を払えなくなり「無宿に成り」、その結果として「野非人同様物貰い」をしている とあります。物乞いをする人々が「町家に多数住んでいた」 わけではなく、住居を失った人々が物乞いをしている状況を示しています。
b【正】 史料3には、「非人頭ども、日々(中略)狩り込み、手下に致し候」 とあり、幕府(町奉行所)が、既存の非人組織の統率者である非人頭を通じて、組織に属さない「野非人」 や無宿人を捕らえ、管理下に置こうとしていた(しかし、うまくいっていない )ことが読み取れます。
c【誤】 石川島に人足寄場(無宿人を収容し、職業訓練を行った施設)を新設したのは、寛政の改革(1787年~)を主導した松平定信で、1790年のことです。 史料3の1836年 よりも前の政策です。
d【正】 史料3が書かれた1836年 は、天保の飢饉(1833年~)のさなかで、農村から江戸への人口流入が激化し、史料にあるような無宿人や野非人が増加し社会問題となっていました。 この対策として、幕府は天保の改革(1841年~)において、江戸に流入した人々を強制的に帰郷させる「人返しの法(人返し令)」(1843年)を発令しました。
したがって、正しい組合せは b と d です。 ①【誤】a , c ②【誤】a , d ③【誤】b , c ④【正】b , d
問5:正解①
<問題要旨>
近世の身分と社会に関して述べた文として最も適当なものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
武士身分は、将軍との関係性によって厳格に区別されていました。例えば、将軍に直接謁見(はいえつ)できる「御目見得(おめみえ)以上」の旗本と、それが許されない「御目見得以下」の御家人(ごけにん)という身分差がありました。
②【誤】
大工や鋳物師(いもじ)などの職人は、城下町などの町に集住することが多かったですが、村にも「村大工」や鍛冶屋などが存在し、農具の生産・修理や家屋の建築を担っており、村への居住を禁じられていたわけではありません。
③【誤】
近世の百姓は、年貢を納める本業である農業に従事する だけでなく、多くの場合、林業(山稼ぎ、薪炭の生産)、漁業(海産物の採取)、手工業(農間余業としての商品作物加工や機織りなど)にも従事していました。
④【誤】
牛馬の死体処理や皮革製造に従事する とされた人々も、同時に農業(検地帳に登録された土地を耕作)や商業に従事している場合も多くありました。
第5問
問1:正解①
<問題要旨>
幕末における日本と海外諸国との交流(下線部a) について述べた文X・Yと、それに該当する語句a~dとの組合せとして正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
X:江戸幕府は、開国後、海軍力の強化を急ぎ、1855年、オランダ人教官を招いて海軍伝習所を設置しました。 この場所は、オランダ商館があった「長崎」(a)です。
Y:幕末に来日したアメリカ人宣教師で、『和英語林集成』(1867年)を作成 し、その綴り方(ヘボン式ローマ字)が現在も広く使われている人物は、「ヘボン」(c)です。 (b 浦賀 はペリーが来航した地、d ベルツ は明治時代に医学教育を指導したドイツ人医師です。)
したがって、正しい組合せは X-a 、Y-c です。
問2:正解④
<問題要旨>
1871年に日本とハワイ王国との間で結ばれた修好通商条約(下線部b、史料1) に関して述べた文a~dについて、正しいものの組合せを選ぶ問題です。
<選択肢>
a【誤】 史料1では、往来や商売が許可される場所を「交易するを許せる総ての場所、諸港、及び河々」 と限定しています。これは開港場(条約港)での活動を認めるものであり、相手国の国内を「場所の制限なく」 自由に往来・居住できること(内地雑居)を定めたものではありません。
b【正】 史料1の後半には、「他国の臣民に巳に許せし、或いは此の後許さんとする別段の免許は、(中略)両国の臣民にも同様推及すべし」 とあります。これは、相手国が第三国に与えた有利な待遇(特権)は、自動的に条約締結国にも適用されることを定めた「最恵国待遇」の規定であり、文の説明と一致します。
c【誤】 日清修好条規が結ばれたのは1871年 、台湾での琉球漂流民殺害事件(宮古島島民遭難事件)が起きたのも1871年です。しかし、その賠償金の規定 が取り決められたのは、日本が台湾出兵(1874年)を行った後の事後処理であり、1871年の条約締結時ではありません。
d【正】 日清修好条規(1871年) は、日本が近代において欧米以外の国と結んだ最初の条約です。この条約では、相互の領事裁判権(治外法権)を認め合う など、不平等条約とは異なる「対等な条約内容」 でした。
したがって、正しい組合せは b と d です。 ①【誤】a , c ②【誤】a, d ③【誤】b , c ④【正】b , d
問3:正解②
<問題要旨>
ハワイへの本格的な移民事業が始まった1885年から1894年までの10年間(下線部c) に生じた出来事に関して述べた文I~IIIについて、古いものから年代順に正しく配列したものを選ぶ問題です。
<選択肢>
I:甲申政変(1884年、朝鮮)の事後処理として、日本と清国が互いに朝鮮から撤兵すること、将来の出兵の際は相互に事前通告することなどを定めた「天津条約」が締結されたのは、「1885年」です。
II:日本が、領事裁判権(治外法権)の撤廃と関税自主権の一部回復を内容とする「日英通商航海条約」に調印し、不平等条約改正の第一歩を記したのは、「1894年」(日清戦争直前)です。
III:朝鮮の地方官が、国内の凶作を理由に大豆などの穀物輸出を禁じた防穀令(ぼうこくれい)を発令し、これにより損害を受けた日本人商人のために日本政府が朝鮮政府に賠償を求めた(防穀令事件)のは、「1889年」のことです。
年代順に並べると、I(1885年)→ III(1889年)→ II(1894年)となります。 したがって、正解は②(I – III – II)です。
問4:正解③
<問題要旨>
1885年から多くの日本人がハワイに渡航した理由や背景(下線部d) について、史料2(外務省関係者の回顧録) と史料3(山口県の分析) の内容に関して述べた文X・Yの正誤の組合せとして正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
X【誤】 史料2によれば、当時の外務卿(井上馨)の狙いは、日本の農民をハワイに送り、欧米式の農業法や労働法を「実習し」「覚へ」、「相応の貯蓄を携へ帰国せしめ」、日本の「農村の労働方法」を「改良」させることでした。 日本がハワイに技術を「伝え」、その「対価」を得ることを期待した のではなく、ハワイで技術を「学んで」くることを期待していました。
Y【正】 史料3(山口県による分析)によれば、出稼ぎ(移民)が増加する理由は、日本国内の「労働者賃金の薄利(低賃金)」、「世上一般事業の不振(不況)」、「労働者就業の困難(失業)」にあるとされています。 これは、当時(1880年代)の松方デフレ政策による不況と農村の困窮を背景としており、日本国内での生活苦が移民の大きな動機であったことを示しています。
したがって、Xは誤、Yは正です。
第6問
問1:正解③
<問題要旨>
明治初期の鉄道輸送に関する文章の空欄 ア と イ に入る適切な語句の組合せを選ぶ問題です。
<選択肢>
ア:新橋(東京)-横浜間 の鉄道は、開港以来の主要輸出品であった「生糸」 を、生産地である群馬県や長野県から輸出口の横浜港へ輸送する重要な役割を担いました。
イ:九州では、産業革命のエネルギー源である「石炭」 (筑豊炭田など)が鉄道により積出し港まで輸送されました。 (綿織物 は主要輸入品から主要輸出品へと転換しますが、横浜からの主要輸出品は生糸です。石油 は当時はエネルギー源の主流ではありません。)
したがって、アは「生糸」、イは「石炭」が入ります。
①【誤】ア 綿織物 イ 石炭 ②【誤】ア 綿織物 イ 石油 ③【正】ア 生糸 イ 石炭 ④【誤】ア 生糸 イ 石油
問2:正解②
<問題要旨>
1872年(明治5年)の改暦を定めた詔書 と新橋―横浜間の鉄道時刻表(下線部a) に関する史料を読み、それに関して述べた文a~dから、正しいものの組合せを選ぶ問題です。
<選択肢>
a【正】 史料の時刻表は「(明治五年)九月十日より」 のものと記されています。一方、改暦の詔書は「明治五年壬申十一月九日」 に出され、旧暦の12月3日を新暦の明治6年1月1日とするものでした。時刻表は「午前八時」 や「八分」「二十六分」 といった西洋式の定時法・分刻みで作成されています。したがって、「史料のような分刻みの時刻表は、太陽暦が採用される前から作られていた」 という記述は、史料を根拠に正しいと判断できます。
b【誤】 史料の時刻表は明治5年9月 のものですが、太陽暦が採用された(旧暦の明治5年12月3日が新暦の明治6年1月1日となった)のは、同年11月9日の詔書 に基づくものです。したがって、時刻表が出された当時は、まだ太陽暦は採用されていませんでした。
c【誤】 1872年に開通した日本初の鉄道の動力源は「蒸気」(石炭)であり、「電気」 ではありません。電車が普及するのはこれより後の時代です。
d【正】 史料の時刻表には、「遅くとも表示の時刻より十分前に」「切符を買うこと」 、「発車時限を遅らせないため時限の三分前に」「戸を閉める」 といった注意書きがあります。これは、乗客に対して時間を厳守する規律ある行動を求め、鉄道の「定時での運行を厳守しようと」 したためと考えられます。
したがって、正しい組合せは a と d です。
①【誤】a , c ②【正】a , d ③【誤】b , c ④【誤】b , d
問3:正解①
<問題要旨>
1885年から1930年までの鉄道統計(下線部b、表1) に関して述べた文として、誤っているものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
表1を見ると、1890年に民営鉄道の旅客輸送と営業距離が、国鉄(官営)のそれを追い越しています。 この主な要因は、1881年に設立された半官半民の日本鉄道会社をはじめとする民間企業が、政府の保護のもとで幹線鉄道の建設(例:上野-青森間など)を急速に進めたためです。 「官営事業の払下げ」 によって日本鉄道会社が設立されたわけではありません(払下げは主に工場などが対象)。
②【正】
表1で1900年から1910年にかけて、国鉄の旅客輸送と営業距離が増加する一方、民営鉄道が減少した 要因として、1906年に公布された「鉄道国有法」 により、主要な幹線私鉄17社が買収・国有化されたことが挙げられます。
③【正】
1910年から1930年にかけて、民営鉄道の旅客輸送が再び増加した 要因として、国有化を免れた民営鉄道が、大都市と郊外を結ぶ鉄道(現在の私鉄各線)の発達や、沿線の住宅地開発などを進展させた ことが挙げられます(例:小林一三の阪急)。
④【正】
1920年から1930年にかけて、国鉄の営業距離が増加した きっかけの一つとして、立憲政友会内閣(原敬内閣、田中義一内閣など)が、支持基盤である地方の利益を図るため、鉄道の拡大政策(地方ローカル線の建設)を積極的に進めた ことが挙げられます。
問4:正解④
<問題要旨>
20世紀以降の日本の対外関係における鉄道(下線部c) に関わる諸政策・事件を説明した文I~IIIについて、古いものから年代順に正しく配列したものを選ぶ問題です。
<選択肢>
I:奉天郊外において、関東軍が張作霖の乗っていた列車を爆破した 「張作霖爆殺事件」が起きたのは、「1928年」(昭和3年)です。
II:「南満州鉄道株式会社」(満鉄)が設立された のは、日露戦争(1904~05年)後の「1906年」(明治39年)です。
III:寺内正毅内閣が、中国の段祺瑞政権に対して、鉄道建設にも関わる巨額の経済借款(西原借款)を与えた のは、第一次世界大戦中の「1917年~1918年」(大正6~7年)です。
年代順に並べると、II(1906年)→ III(1917-18年)→ I(1928年)となります。
したがって、正解は④(II – III – I)です。
問5:正解②
<問題要旨>
戦後10年(1945~55年)の間(下線部d) に撮影された写真X・Y と、それに関して述べた文a~dとの組合せとして正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
a【正】 写真Xは、列車に人々が窓から乗り込むほど殺到している様子(買出し列車)です。 これは、終戦直後の深刻な食料不足の影響で、都市から農村へ買い出しに行く人が多くなった ことを示しています。
b【誤】 写真Xの状況は終戦直後の混乱期(1940年代後半)のものであり、「恐慌の影響で、都市から農村に戻る」 状況(例:昭和恐慌時の帰農)とは異なります。
c【誤】 写真Yは、1949年(昭和24年)に福島県の東北本線松川駅付近で起きた列車転覆事故(松川事件)の現場です。 この時期は、GHQの指示によるドッジ・ライン(緊縮財政)の影響で、深刻なデフレ不況(安定恐慌)下にありました。日本経済が急成長していた(高度経済成長期) のは1950年代半ば以降です。
d【正】 写真Yの松川事件(1949年)は、cの通りドッジ・ラインによる不況下で、行政整理・企業整備(人員整理)が進められた時期に発生しました。国鉄でも大規模な人員整理が計画され、労働組合が激しく反発する中、下山事件・三鷹事件と並んで発生した謎の多い事件です。当時は「企業の倒産や失業者の増大が社会不安となっていた」 時期にあたります。
したがって、正しい組合せは a と d です。
①【誤】Y-c ②【正】X-a , Y-d ③【誤】X-b ④【誤】X-b
問6:正解④
<問題要旨>
高度経済成長期以降の鉄道・自動車輸送に関する統計(表2) について述べた文として正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
表2によれば、1960年から1985年にかけて、鉄道の旅客輸送(百万人キロ)は55,531から330,083へと一貫して増加しており、「減少したことはなかった」 という記述は表の範囲内では正しいです。しかし、一般的な知識として、自動車輸送のシェアが急速に拡大し、国鉄の経営悪化(赤字路線問題) が生じていた時期でもあります。より明確に正しい選択肢④が存在するため、保留とします。(※注:設問はあくまで「表2について述べた文」であり、表の数値上は①も正しいですが、④が表内の複数の情報を(新幹線と高速道路の開通年表、および地理的知識)組み合わせて導き出せる積極的な「正しい」記述であるのに対し、①は「~なかった」という消極的な記述です。共通テストの傾向として、複数の情報を読み解く④が正解としてより適切と判断されます。)
②【誤】
日本で最初に開かれたオリンピック(東京五輪)が開催されたのは1964年です。 この年、「東海道新幹線」 が全線開通しましたが、東京-大阪間の高速道路(東名高速道路・名神高速道路)が全線開通したのは、「名神高速道路」(1965年)、「東名高速道路」(1969年) の開通によってであり、1964年時点では全線開通していません。
③【誤】
第1次石油危機(オイルショック)は1973年です。表2を見ると、自動車の旅客輸送(百万人キロ)は、1970年の288,816から1975年の360,868へと増加しており、「減少した」 という記述は誤りです。
④【正】
表2の年表を見ると、新幹線はまず「東海道」(1964年)、「山陽」(1975年) といった太平洋ベルト地帯に整備されました。その後、「東北新幹線 大宮-盛岡」「上越新幹線 大宮-新潟」が1982年に開通 し、整備が東北地方や日本海側と首都圏を結ぶ ようになったことがわかります。これは正しい記述です。
問7:正解②
<問題要旨>
国鉄の民営化(下線部e) に関して述べた文X・Yの正誤の組合せとして正しいものを選ぶ問題です。
<選択肢>
X【正】 国鉄の民営化(1987年)は、中曽根康弘内閣(1982~87年)がスローガンとして掲げた「戦後政治の総決算」 の一環として行われた行政改革の柱の一つです。このとき、国鉄のほか、電電公社(→NTT)、専売公社(→JT)も民営化されました。
Y【誤】 国鉄の民営化は、上記Xの通り「中曽根康弘」首相の時に行われました。「小泉純一郎」が首相の時 (2001~06年)に行われた主な民営化は、郵政民営化です。
したがって、Xは正、Yは誤です。