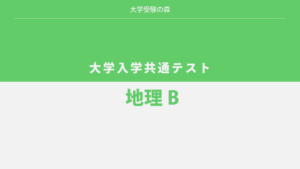解答
解説
第1問
問1:正解③
<問題要旨>
イギリスとニュージーランドの地形的特徴と土地利用の特徴を、それぞれグラフから読み取り、正しく組み合わせる問題です。両国の自然環境と農牧業に関する基本的な知識が問われています。
<選択肢>
①【誤】
ニュージーランドは環太平洋造山帯に位置し、険しい山脈が連なるため、国土の標高別面積割合はイのグラフに該当します。また、ニュージーランドは企業的牧畜が盛んで、国土に占める牧草地の割合が非常に高いです。AとBを比較すると、イギリスとニュージーランドの双方で高い割合を占めるAが牧草地と判断できます。したがって、牧草地はAです。
②【誤】
ニュージーランドに該当する図はイですが、牧草地に該当する凡例はAです。Bは森林と考えられます。イギリス、ニュージーランドともに森林がある程度広がっていますが、特にニュージーランドは国土の約4割が森林です。
③【正】
ニュージーランドは、南アルプス山脈に代表されるように、国土の多くを山地が占める国です。したがって、標高400m以上の割合が比較的高いイのグラフがニュージーランドを示します(一方、アは国土の大部分が標高200m未満の低平地であるイギリスを示します)。また、ニュージーランドは世界有数の羊・牛の飼育国であり、企業的牧畜が盛んです。土地利用を見ると、Aが国土の約4割を占めており、これは牧草地と判断できます。よって、ニュージーランド(イ)と牧草地(A)の組み合わせが正しいです。
④【誤】
牧草地に該当する凡例はAです。Bは森林と考えられます。
問2:正解③
<問題要旨>
北半球における永久凍土と氷河・氷床の緯度別分布を示したグラフを読み取り、その背景にある地理的な事象について正しく理解できているかを問う問題です。
<選択肢>
①【正】
北緯30度から45度は、全体的には温暖な気候帯ですが、グラフではわずかに永久凍土の存在が示されています。これは、チベット高原やヒマラヤ山脈、ロッキー山脈といった標高が非常に高い「高山地域」に分布する永久凍土(山地永久凍土)を反映していると考えられます。したがって、この記述は正しいです。
②【正】
北緯45度から70度にかけては、緯度が上がるにつれて太陽からの受熱量が減少し、年平均気温が著しく低下します。これにより、地中の温度が年間を通じて氷点下に保たれる永久凍土が分布しやすくなります。グラフでも、この緯度帯で永久凍土の割合が急増しており、記述の内容と一致します。
③【誤】
北緯60度から80度にかけて氷河・氷床の割合が増加するのは、気温が極めて低く、一度降った雪が融けずに万年雪となり、氷となって蓄積していくためです。しかし、これらの極地に近い高緯度地域は、寒気による高圧帯に覆われることが多く、大気中の水蒸気量も少ないため、降水量(降雪量)自体は非常に少ないのが特徴です。「降雪量が多くなること」が割合増加の主な原因であるとするこの記述は誤りです。
④【正】
北緯70度から80度のグラフを見ると、氷河・氷床の割合(破線)は80度に向けて急増しますが、100%には達していません。一方、永久凍土の割合(実線)も60%以上と高い値を示しています。これは、氷河・氷床に覆われていない陸地の大部分が永久凍土となっていることを意味します。したがって、この記述は正しいです。
問3:正解④
只今準備中です。しばらくお待ちください。
問4:正解④
<問題要旨>
複数の都市の1月と7月の日照時間のデータから、各都市の緯度や気候の特徴を推測し、ムンバイに該当するものを選ぶ問題です。日照時間が、季節による昼夜の長さの変化だけでなく、天候(特に乾季と雨季)によって大きく左右されることを理解しているかがポイントです。
<選択肢>
①【誤】
1月の日照時間が約1.5時間と極端に短く、7月は約8時間と長くなっています。冬と夏の日照時間の差が非常に大きいことから、北半球の高緯度に位置する都市と考えられます。これはオスロ(ノルウェー)に該当します。
②【誤】
7月の日照時間が10時間を超えて長く、1月も4時間程度あります。夏は高温乾燥で晴天が続く一方、冬は比較的降水がある地中海性気候の都市の特徴と考えられます。これはローマ(イタリア)に該当します。
③【誤】
1月の日照時間が約8時間と長く、7月の日照時間は約7時間とやや短くなっています。北半球とは逆に、1月(夏)の日照時間が7月(冬)よりも長いことから、南半球に位置する都市と判断できます。これはシドニー(オーストラリア)に該当します。
④【正】
1月の日照時間が約9時間と非常に長い一方、7月は約2.5時間と極端に短くなっています。ムンバイ(インド)は熱帯モンスーン気候に属し、1月は乾季で晴天が続くため日照時間が長く、7月は南西モンスーンの影響で雨季にあたり、曇りや雨の日が多いため日照時間が著しく短くなります。この特徴とグラフ④が一致します。
問5:正解④
<問題要旨>
南北アメリカ大陸の4カ国における洪水発生時期のデータから、各国の気候の特徴(雨季や融雪時期)を推測し、凡例の時期を特定する問題です。特に南半球では季節が北半球と逆になることを踏まえて考える必要があります。
<選択肢>
まず、各国の気候から洪水の発生しやすい時期を考え、凡例のサ~スを特定します。
・ボリビア:南半球に位置し、夏にあたる12月~2月頃が雨季となります。グラフを見ると「ス」の時期に洪水が集中しているため、スは12~2月と推定できます。
・コロンビア:赤道直下にあり、多くは年に2回雨季があります(4~5月頃と10~11月頃)。グラフでは「サ」の割合が最も高くなっています。これは10~11月の雨季に対応すると考えられ、サは9~11月と推定できます。
・カナダ:北半球の高緯度に位置し、春(3~5月)に気温が上昇して雪が融ける「融雪洪水」が起こりやすいのが特徴です。残ったシが3~5月と推定できます。
この推定をメキシコに当てはめて検証します。メキシコは夏から秋(6~11月)が雨季で、特にハリケーンの影響を受けやすいです。6~8月に加え、サ(9~11月)にも洪水が多いはずですが、グラフではシ(3~5月)のほうが多くなっています。このように一部の国では一般知識と異なるデータも見られますが、複数の国で説明がつく組み合わせを総合的に判断すると、上記の推定が最も妥当です。
したがって、「3~5月」がシ、「9~11月」がサ、「12~2月」がスという組み合わせになります。
①【誤】サは9~11月、シは3~5月です。
②【誤】サは9~11月、シは3~5月です。
③【誤】3~5月はシです。
④【正】上記の推論から、3~5月がシ、9~11月がサ、12~2月がスの組み合わせが正しいです。
⑤【誤】3~5月はシ、9~11月はサです。
⑥【誤】3~5月はシ、9~11月はサです。
問6:正解⑤
只今準備中です。しばらくお待ちください。
第2問
問1:正解⑤
<問題要旨>
世界の鉄鉱石の産出量・輸出量・輸入量について、それぞれ上位国を示した円の大小で表現された地図から、項目名と地図A~Cを正しく結びつける問題です。鉄鉱石をめぐる資源・貿易の基本的な知識が問われます。
<選択肢>
・地図B:中国の円が圧倒的に大きく、次いで日本、韓国、ヨーロッパ(ドイツなど)に円が見られます。これらは鉄鋼生産が盛んでありながら、国内の鉄鉱石資源が不足しているため、大量に輸入に頼っている国々です。したがって、Bは輸入量です。
・地図C:オーストラリアとブラジルが大きく、それに加えて中国、インド、ロシア、南アフリカなどにも円があります。これらは世界の鉄鉱石産出量の上位国と一致します。特に中国は産出量も世界トップクラスです。したがって、Cは産出量です。
・地図A:オーストラリアとブラジルが突出して大きく、他の国は小さいです。この2カ国は、豊富な資源を背景に世界へ向けて鉄鉱石を大量に輸出しています。したがって、Aは輸出量です。
以上の考察から、産出量がC、輸出量がA、輸入量がBとなります。
①【誤】産出量はC、輸出量はAです。
②【誤】輸出量はA、輸入量はBです。
③【誤】産出量はC、輸入量はBです。
④【誤】産出量はC、輸出量はA、輸入量はBです。
⑤【正】上記の推論から、産出量がC、輸出量がA、輸入量がBの組み合わせが正しいです。
⑥【誤】輸出量はA、輸入量はBです。
問2:正解②
<問題要旨>
日本の製鉄所の立地が時代とともにどのように変化してきたかを、地図と会話文から読み解き、誤りを含む記述を選ぶ問題です。工業立地論の変遷と日本の産業史を結びつけて考える必要があります。
<選択肢>
①【正】
鉄鋼業は、原料の鉄鉱石と燃料の石炭を大量に必要とします。製品の鉄鋼に比べて、これらの原料・燃料の総重量がはるかに大きいため(重量減損原料)、輸送費を削減するために原料・燃料の産地の近くに工場を立地させるのが合理的です。1910年の地図に見られるように、初期の製鉄所は国内の炭田や鉄山の近くに立地しました。この記述は正しいです。
②【誤】
1940年時点では、国内の石炭や鉄鉱石もまだ重要な資源として利用されており、「枯渇して」という表現は適切ではありません。原料・燃料の海外依存度が決定的に高まり、輸入に便利な臨海部への立地が主流となるのは、主に戦後の高度経済成長期(1950年代後半以降)です。1940年の段階での臨海部への立地は、大消費地である大都市への近接という要因も大きいです。したがって、この記述は誤りを含みます。
③【正】
1974年の地図を見ると、太平洋ベルト地帯の臨海部に多くの製鉄所が建設されています。これらは、海外から大型船で原料を輸入し、製品を国内外へ出荷するのに便利なように、港湾施設を備えた広大な埋立地に建設されたものです。この記述は正しいです。
④【正】
2022年の地図では、1974年に比べて製鉄所の数が減少しています。これは、安価な外国製品との競争激化や国内需要の変化などを背景に、日本の鉄鋼業界で企業の合併や再編が進み、非効率な工場の閉鎖など経営の合理化が行われた結果です。会話文の指摘は正しいです。
問3:正解③
<問題要旨>
日本の石炭輸入量の推移を示すグラフと、主要輸入相手国の石炭産業の特徴を述べた文章を正しく結びつける問題です。日本のエネルギー・資源輸入における相手国の変化とその背景を理解しているかが問われます。
<選択肢>
まず、グラフから国名を特定します。
・E:1970年から一貫して輸入量が多く、現在も日本の最大の石炭輸入相手国です。これはオーストラリアに該当します。
・F:1990年代後半から輸入量が急増し、近年ではオーストラリアに次ぐ輸入相手国となっています。これは主に発電用の一般炭を輸出しているインドネシアに該当します。
・G:かつては一定の輸入量がありましたが、現在は比較的少ないです。これはアメリカ合衆国に該当します。
次に、文章がどの国を説明しているか判断します。
・ア:「産出量が急増」「輸出量が増加」「国内でも消費量が増加」という記述は、近年の経済成長に伴い石炭の生産・輸出・国内消費がいずれも増加しているインドネシアの特徴と一致します。
・イ:「大規模な露天掘り」「国内市場は小さく、多くが輸出」という記述は、広大な国土で効率的な採掘を行い、国内人口が比較的少ないため生産量の多くを輸出に回しているオーストラリアの特徴と一致します。
・ウ:「確認埋蔵量は世界で最も多い」「国内における消費量も世界有数」という記述は、世界一の石炭埋蔵量を誇り、巨大な国内経済を背景に消費量も非常に多いアメリカ合衆国の特徴と一致します。
以上のことから、E-イ、F-ア、G-ウの組み合わせが正しいです。
①【誤】Eはイ、Fはアです。
②【誤】Eはイ、Gはウです。
③【正】上記の推論から、Eがイ、Fがア、Gがウの組み合わせが正しいです。
④【誤】Fはア、Gはウです。
⑤【誤】Eはイ、Fはア、Gはウです。
⑥【誤】Eはイ、Gはウです。
問4:正解③
<問題要旨>
4カ国の1990年と2018年における「人口1人当たりの製造業付加価値額」と「GDPに占める製造業の割合」の変化を示すグラフから、ドイツに該当するものを選ぶ問題です。各国の経済発展の段階や産業構造の特徴を理解している必要があります。
<選択肢>
①【誤】
1990年時点では両方の指標が非常に低く、2018年にかけて急速に成長していますが、まだ先進国には及ばないレベルです。これは改革開放以降、急速な工業化を進めた中国と考えられます。
②【誤】
1990年から2018年にかけて、「1人当たり付加価値額」は増加していますが、「GDPに占める製造業の割合」は上昇しています。これは、経済発展段階が比較的低く、これから工業化が進展していく国のパターンです。ドイモイ政策以降、工業化を進めるベトナムと考えられます。
③【正】
1990年時点で「1人当たり付加価値額」が非常に高く、2018年にかけてさらに微増しています。一方で「GDPに占める製造業の割合」は20%強で安定しています。これは、付加価値の高い工業製品の生産に強みを持ち、「マイスター制度」などに支えられた高い技術力で製造業の国際競争力を維持しているドイツの特徴と一致します。
④【誤】
1990年時点では「1人当たり付加価値額」も「GDPに占める製造業の割合」も比較的高かったですが、2018年にかけて両方の指標が低下しています。これは、世界で最初に産業革命を経験しましたが、その後、金融など第三次産業へのシフトが進み、製造業の比率が低下した(脱工業化)イギリスの特徴と一致します。
問5:正解①
<問題要旨>
1988年と2008年の空中写真を比較し、工場の跡地利用などに見られる日本の産業構造の変化や都市の変化について述べた文章から、適当でないものを選ぶ問題です。写真の読解力と、日本の経済地理に関する知識が問われます。
<選択肢>
①【誤】
1988年時点で操業していた繊維工場が、その後閉鎖されたとあります。この時期(1980年代後半から90年代以降)、日本の繊維工業は、国内の農村部へ移転するのではなく、より安価な労働力を求めて中国や東南アジアなど国外へ工場を移転する傾向が顕著になりました。したがって、「国内の農村部に工場が移転する傾向がみられた」という記述は、この時期の状況として適当ではありません。
②【正】
2008年の写真を見ると、工場の跡地に大規模な建物と広い駐車場が整備されています。これは大型複合商業施設と考えられ、多様な店舗が集積することで広域から集客することができます。単独のスーパーマーケットよりも商圏が広くなるのは一般的です。この記述は正しいです。
③【正】
1988年の写真で工場西側にあった空き地や古い建物が、2008年の写真では、碁盤の目状に区画整理され、同じような形の屋根が並ぶ戸建ての住宅地に変化していることが読み取れます。この記述は正しいです。
④【正】
大都市圏では、土地や人件費のコストが高いため、単純な生産機能は海外や地方に移転する一方、本社機能や研究開発(R&D)拠点、高付加価値製品の生産拠点などは、情報や人材が集積する大都市圏に残る傾向があります。この記述は正しいです。
問6:正解④
<問題要旨>
日本の製造業が盛んな地域が抱える課題と、それに対する新しい取組みを、「目的」と「具体例」で正しく結びつける問題です。現代日本の地域が直面する課題と、それに対する持続可能な地域づくりの考え方を理解しているかが問われます。
<選択肢>
それぞれの「目的」に合致する「具体的な取組み」を考えます。
・P:地域の魅力を高める
→ サ~スの中で、地域の資産(工場群)を新たな観光資源(夜景)として活用する「シ」が、地域の新たな魅力創出に直接つながります。
・Q:環境に配慮した社会を構築する
→ サ~スの中で、生ごみや間伐材といったバイオマス資源を利用して発電し、エネルギーの地産地消を目指す「ス」が、環境配慮や持続可能なエネルギー利用に該当します。
・R:企業城下町から脱却する
→ サ~スの中で、特定の大企業に依存するのではなく、地域の中小企業が連携して新たな産業分野に進出する「サ」が、多角的な産業構造を構築し、企業城下町からの脱却を目指す取組みに該当します。
したがって、P-シ、Q-ス、R-サの組み合わせが正しいです。
①【誤】Pはシ、Qはス、Rはサです。
②【誤】Pはシ、Rはサです。
③【誤】Qはス、Rはサです。
④【正】上記の推論から、Pがシ、Qがス、Rがサの組み合わせが正しいです。
⑤【誤】Pはシ、Qはス、Rはサです。
⑥【誤】Pはシ、Qはスです。
第3問
問1:正解⑤
<問題要旨>
日本の大都市圏における1960年代の景観写真(A~C)と、その後の変化を述べた文章(ア~ウ)を正しく結びつける問題です。都心、郊外、臨海地域の典型的な景観と、高度経済成長期以降の都市構造の変化を理解しているかが問われます。
<選択肢>
まず、写真がどの地域か判断します。
・A(臨海地域):煙突のある工場が密集しており、臨海部の工業地帯の景観です。
・B(都心):高層ビルが建設され、高速道路が走っており、大都市の都心部の景観です。
・C(郊外):丘陵地を造成した土地に、同じような形の中層集合住宅(団地)が立ち並んでおり、郊外の住宅地の景観です。
次に、文章がどの地域の変化か判断します。
・ア:「地価上昇で人口減少(ドーナツ化現象)」→「地価下落や利便性で見直され人口増加(都心回帰)」という流れは、都心の変化を説明しています。
・イ:「核家族の転入急増」→「高齢化」→「建て替えで新たな転入者」という流れは、高度経済成長期にニュータウンとして開発された郊外の住宅地の変化を説明しています。
・ウ:「多数の人々が働いていた」→「広大な空き地を利用してレジャー施設」という流れは、工場の海外移転などで衰退した臨海工業地域の跡地再開発の様子を説明しています。
以上のことから、A-ウ、B-ア、C-イの組み合わせが正しいです。
①【誤】Aはウ、Bはア、Cはイです。
②【誤】Bはア、Cはイです。
③【誤】Aはウ、Cはイです。
④【誤】Aはウ、Bはアです。
⑤【正】上記の推論から、Aがウ、Bがア、Cがイの組み合わせが正しいです。
⑥【誤】Bはアです。
問2:正解②
<問題要旨>
日本の4つの市区の昼夜間人口比率と通勤・通学交通手段のデータから、福岡市に該当するものを選ぶ問題です。各都市の性格(大都市の中心か、郊外都市か、地方都市か)と、それに伴う人口流動や交通事情の特徴を推測する力が求められます。
<選択肢>
各選択肢の都市の性格を考えます。
・① 東京都心の中央区:昼間には多くの人が働きに来るため、昼夜間人口比率が極端に高くなります(数100%)。交通手段は鉄道の割合が圧倒的に高いはずです。
・② 福岡市:九州地方の中心都市であり、周辺地域から多くの通勤・通学者を集めるため、昼夜間人口比率は100を超えます。大都市なので鉄道やバスの利用も多いですが、地方大都市であるため自家用車での通勤も一定数います。
・③ 秋田市:地方の中核都市ですが、大都市圏ほどの集積はないため、昼夜間人口比率は100をわずかに超える程度でしょう。交通手段は完全に車社会であり、自家用車の割合が非常に高いはずです。
・④ 東京郊外の調布市:都心へ通勤・通学する人が多いため、昼間人口が夜間人口より少なくなり、昼夜間人口比率は100を下回ります(ベッドタウン)。交通手段は都心へ向かう鉄道の割合が高いはずです。
次に、表のデータと照合します。
・①:昼夜間人口比率が456.1と異常に高く、鉄道利用率が91.6%と突出しています。これは東京都中央区です。
・②:昼夜間人口比率が109.8と100を超えており、中心都市の性格を示しています。交通手段は鉄道(33.2%)、バス(17.3%)、自家用車(30.0%)とバランスが取れています。これは福岡市の特徴と一致します。
・③:昼夜間人口比率は103.7。自家用車の割合が70.8%と極めて高いです。これは車社会である地方都市秋田市と考えられます。
・④:昼夜間人口比率が83.9と100を下回っており、ベッドタウンの性格を示しています。鉄道利用率が49.7%と高いです。これは調布市です。
問3:正解④
<問題要旨>
世界の都市圏人口の推移を示すグラフから凡例を特定し、発展途上国の都市における人口流入と人々の就業形態について正しく理解しているかを問う問題です。
<選択肢>
まず、凡例カとキを特定します。グラフは1990年から2015年にかけての人口増加を示しており、破線(y=x)より上にあるほど人口増加が大きいことを意味します。
・BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)諸国の都市は、この期間に著しい経済成長と人口増加を経験しました。
・先進国の都市は、既に成熟しており、人口増加は比較的緩やかです。
グラフを見ると、キ(□)はカ(●)に比べて、全体的に破線より上に大きく離れた点が多く、人口増加が著しいことがわかります。したがって、キはBRICS、カは先進国です。
次に、空欄Xを考えます。発展途上国の都市では、農村から流入した人々がすぐに安定した職に就けるとは限りません。多くは、特別な技術や資本を必要としない露天商などの小売業・サービス業(インフォーマルセクター)に従事して生計を立てます。高度な専門知識を要する金融業に従事するのは困難です。したがって、Xは小売業・サービス業です。
よって、キがBRICS、Xが小売業・サービス業の組み合わせが正しいです。
①【誤】キはBRICS、Xは小売業・サービス業です。
②【誤】キはBRICSです。
③【誤】Xは小売業・サービス業です。
④【正】上記の推論から、キがBRICS、Xが小売業・サービス業の組み合わせが正しいです。
問4:正解③
只今準備中です。しばらくお待ちください。
問5:正解④
<問題要旨>
アメリカのフィラデルフィアとメキシコのメキシコシティにおける貧困地区の分布図を比較し、その特徴に関する記述として適当でないものを選ぶ問題です。先進国と発展途上国の都市でみられる都市問題の違いを理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【正】
フィラデルフィアは、アメリカ北東部の「ラストベルト(錆びついた工業地帯)」に位置する都市です。かつては製造業で栄えましたが、産業構造の変化により衰退し、都心部(インナーシティ)では工場の閉鎖、失業者の増加、住宅の老朽化といった問題が深刻化しました。図でも貧困地区が都心部に集中しており、この記述と一致します。
②【正】
メキシコシティは発展途上国の巨大都市(メガシティ)であり、急激な人口増加に社会基盤(インフラ)の整備が追いついていません。特に、都市の周縁部に形成されたスラム(不良住宅地区)では、上下水道や電気、道路などが未整備な場合が多くみられます。図でも貧困地区が都市の郊外に広がっており、この記述と一致します。
③【正】
図を比較すると、フィラデルフィアでは貧困地区が黒く示された「都心地区」とその周辺に集中しています。一方、メキシコシティでは、貧困地区は都心部にも一部見られますが、主に市街地の外縁部に向かって広がっています。したがって、「フィラデルフィア都市圏の方が都市圏中心部に集中している」という記述は正しいです。
④【誤】
フィラデルフィアの貧困地区は都心部に塊状に分布しており、「高速道路に沿って放射状に」広がっているとは言えません。メキシコシティの貧困地区は郊外に広がっていますが、こちらも特定の高速道路に沿って放射状に分布しているというよりは、都市の周縁部を埋めるように広がっています。したがって、「両都市圏ともに」という記述は明らかに誤りです。
問6:正解②
只今準備中です。しばらくお待ちください。
第4問
問1:正解④
<問題要旨>
太平洋とその周辺の4つの測線に沿った海底地形の断面図から、ハワイ諸島付近を通る測線Bに該当するものを選ぶ問題です。プレートの動きによって生まれる多様な海底地形(海嶺、海溝、ホットスポットなど)の知識が問われます。
<選択肢>
各測線の特徴を考えます。
・A:日本の東方沖から太平洋プレートの中央部へ向かう線。日本海溝という非常に深い溝を通過します。
・B:太平洋のほぼ中央、ハワイ諸島を横切る線。ハワイ諸島はホットスポットによって形成された火山島で、海底から高くそびえる海山列(天皇海山列~ハワイ海山列)の一部です。
・C:南米沖の東太平洋海嶺(プレートが生まれる場所)からナスカプレートを横断する線。中央部に比較的緩やかな盛り上がり(海嶺)があり、その両側は深い海洋底が広がります。
・D:オーストラリアの東方沖。サンゴ礁(グレートバリアリーフ)や、太平洋プレートとインド・オーストラリアプレートの境界付近の複雑な地形が見られると考えられます。
次に、断面図と照合します。
・①:水深6000mを超える非常に深い溝(海溝)と、その近くの起伏の激しい地形が見られます。これは日本海溝を通過する測線Aに該当します。
・②:全体的に水深が浅く、3000m程度の比較的平坦な海底が続いています。これは東太平洋海嶺付近の測線Cの特徴とは異なります。また、ハワイのような巨大な海山も見られません。
・③:水深3000~4000m程度の平坦な海底が広がっています。これは典型的な大洋底の地形で、大きな起伏が見られません。
・④:水深4000m~5000mの海底から、海面近くまで達する巨大な海底火山(海山)がいくつもそびえ立っています。これは、ホットスポットによって形成されたハワイ諸島の海底地形の特徴と一致します。したがって、これが測線Bに該当します。
問2:正解③
<問題要旨>
3つの地点のハイサーグラフ(月平均気温と月降水量の関係図)と、その地域でみられる民族衣装の説明文を正しく結びつける問題です。ハイサーグラフから気候区を読み取り、その気候に適応した生活文化を推測する力が問われます。
<選択肢>
まず、ハイサーグラフから各地点の気候を読み取ります。
・F:最寒月平均気温が-10℃を下回り、最暖月が10℃を超える、年較差の非常に大きい気候です。降水量は年間通じて少なめです。これはシベリアなどで見られる冷帯(亜寒帯)気候(DwやDf)です。
・G:最寒月平均気温が10℃程度、最暖月が20℃強で、夏に降水量が少なく、冬にやや多い傾向があります。これは地中海性気候(Cs)です。
・H:年間を通じて気温が25℃以上と高く、ほとんど変化がありません。降水量は特定の時期に集中しており、雨季と乾季が明瞭です。これは熱帯気候(サバナ気候 Aw など)です。
次に、民族衣装の説明文と気候を結びつけます。
・ア:「アルパカの毛」「防寒性」という記述から、アンデス山脈の高地など、標高が高く冷涼な地域の衣装(ポンチョなど)とわかります。
・イ: 「トナカイの毛皮」「保温性と断熱性」という記述から、極めて寒冷な冷帯(亜寒帯)やツンドラ気候帯の衣装とわかります。
・ウ:「木綿」「通気性と吸湿性」「腰に巻く」という記述から、高温多湿な熱帯地域の衣装(サロンやパレオなど)とわかります。
F-イ、H-ウの組み合わせが確実です。Gは地中海性気候で、冬の防寒と夏の日差し対策が必要な服装が考えられます。アのアルパカは南米アンデス産なので、ペルーやボリビアの高地(高山気候)の衣装であり、どのハイサーグラフとも完全には一致しません。しかし、F-イ、H-ウの組み合わせから、消去法でG-アとなります。
設問の組合せを見ると、F-イ、G-ア、H-ウの組み合わせが求められます。
①【誤】Fはイ、Gはアです。
②【誤】Gはア、Hはウです。
③【正】上記の推論から、Fがイ、Gがア、Hがウの組み合わせが正しいです。
④【誤】Hはウです。
⑤【誤】Fはイ、Gはアです。
⑥【誤】Fはイ、Hはウです。
問3:正解③
<問題要旨>
日本、カナダ、ベトナム、チリの1人1日当たりのたんぱく質供給量の内訳データから、国名を特定する問題です。各国の食文化や産業(農牧業、水産業)の特徴を理解しているかが問われます。
<選択肢>
各国の食文化の特徴を考えます。
・日本:伝統的に魚を多く食べる文化があり、大豆製品(豆腐、味噌など)も豊富です。近年は食の欧米化で肉類の消費も増えていますが、魚や大豆の摂取量は他国に比べて多いと考えられます。
・カナダ:アメリカと同様、肉類や乳製品(牛乳)の消費量が非常に多い欧米型の食生活です。
・ベトナム:東南アジアの国で、米を主食とし、魚醤(ヌクマム)を使うなど魚介類をよく食べます。経済発展に伴い肉の消費も増えていますが、伝統的な食生活が中心です。牛乳を飲む習慣は欧米ほど一般的ではありません。
次に、データと照合します。
・カ:たんぱく質総量が107.1gと最も多く、特に肉(31.6g)と牛乳(17.2g)の数値が高いです。これは欧米型の食生活であるカナダと判断できます。
・キ:魚(16.7g)と大豆(8.2g)の数値が4カ国の中で突出して高いです。これは日本の食文化の特徴と一致します。
・ク:魚(11.2g)の割合が比較的高く、肉(17.3g)もそれなりにありますが、牛乳(2.0g)の数値が著しく低いです。これはベトナムの特徴と一致します。
・チリ(参考):肉(31.0g)が多く、南米の食文化を反映しています。
したがって、日本がキ、カナダがカ、ベトナムがクとなります。
①【誤】日本はキ、カナダはカです。
②【誤】日本はキ、ベトナムはクです。
③【正】上記の推論から、日本がキ、カナダがカ、ベトナムがクの組み合わせが正しいです。
④【誤】カナダはカ、ベトナムはクです。
⑤【誤】日本はキ、カナダはカ、ベトナムはクです。
⑥【誤】日本はキ、ベトナムはクです。
問4:正解②
<問題要旨>
太平洋の島嶼地域(グアム、ハワイ、フィジー)を訪れる観光客の出発地割合を示したグラフから、地名と凡例を特定する問題です。各観光地の地理的な位置と、主要な観光客の出身国との関係を理解しているかがポイントです。
<選択肢>
まず、各観光地の位置と主要な観光客層を考えます。
・グアム:日本や韓国から地理的に非常に近く、短期間の旅行先として人気です。したがって、アジアからの観光客が大多数を占めるはずです。
・ハワイ:アメリカ合衆国の州であり、アメリカ本土からの観光客が最も多いです。また、日本からの観光客も多いです。
・フィジー:オーストラリアやニュージーランドから地理的に近く、これらのオセアニア諸国からの観光客が中心です。
次に、凡例JとKがアジアかヨーロッパかを考えます。
・タヒチのグラフを見ると、Kが50%以上を占めています。タヒチはフランス領ポリネシアにあり、フランスをはじめとするヨーロッパからの観光客が多いことで知られています。したがって、Kはヨーロッパ、残ったJはアジアと判断できます。
最後に、グラフと地名を結びつけます。
・サ:J(アジア)からの観光客が80%以上を占めています。これは日本や韓国に近いグアムの特徴と一致します。
・シ:北アメリカからの観光客が70%以上を占め、J(アジア)も15%程度います。これはアメリカ本土と日本からの観光客が多いハワイの特徴と一致します。
・ス:オセアニアからの観光客が60%以上を占めています。これはフィジーの特徴と一致します。
設問で問われているのは、グアムとヨーロッパの組み合わせなので、サとKになります。
①【誤】ヨーロッパはKです。
②【正】上記の推論から、グアムがサ、ヨーロッパがKの組み合わせが正しいです。
③【誤】グアムはサです。
④【誤】グアムはサ、ヨーロッパはKです。
⑤【誤】グアムはサです。
⑥【誤】グアムはサ、ヨーロッパはKです。
問5:正解②
<問題要旨>
環太平洋の4カ国(アメリカ、オーストラリア、中国、ペルー)間の輸出額の変化を示した図から、中国に該当するものを選ぶ問題です。1999年から2019年にかけての世界経済、特に中国の急速な台頭を理解しているかが問われます。
<選択肢>
各国の経済的特徴と貿易関係を考えます。
・P:1999年、2019年ともに、他の3カ国すべてに対して太い線(多額の輸出)で結ばれています。これは、経済規模が大きく、世界各国と緊密な貿易関係を持つアメリカ合衆国と考えられます。
・Q:1999年時点では他国への輸出額は全体的に小さいですが、2019年には輸出元・輸出先ともに他の3カ国との間で極めて太い線で結ばれています。この20年間で貿易額が爆発的に増加したのは、急速な経済成長を遂げた中国の特徴と完全に一致します。
・R:P(アメリカ)やQ(中国)と太い線で結ばれています。資源国であり、特にアジア太平洋地域との結びつきが強いオーストラリアと考えられます。
・S:他の3カ国との貿易額が全体的に小さいです。これは経済規模が比較的小さいペルーと考えられます。
したがって、中国に該当するのはQです。
①【誤】Pはアメリカ合衆国です。
②【正】上記の推論から、Qが中国です。
③【誤】Rはオーストラリアです。
④【誤】Sはペルーです。
問6:正解④
<問題要旨>
環太平洋地域における日本企業の現地法人数の変化(1999年と2019年)を示した地図と、それに関する記述から、適当でないものを選ぶ問題です。日本企業の海外進出先の変化とその背景を読み取る必要があります。
<選択肢>
①【正】
1999年から2019年にかけて、アジア(特に中国や東南アジア)における円の大きさ(法人数)の増加は、北アメリカにおける円の増加に比べてはるかに顕著です。これは、安価な労働力や拡大する市場を求めて、日本企業のアジア進出が加速したことを示しています。この記述は正しいです。
②【正】
アジアの円の内訳を見ると、1999年時点では製造業(白色部分)の割合が高い国が多いですが、2019年には非製造業(灰色部分)の割合が多くの国で高まっています。これは、現地の所得水準向上に伴い、小売、金融、サービスといった非製造業の需要が高まったことを反映しています。この記述は正しいです。
③【正】
北アメリカ、特にアメリカでは、シリコンバレーなどに代表されるように、IT産業が高度に集積しています。日本の企業も、現地の技術や人材、市場を獲得するために、ソフトウェアやAI(人工知能)といった先端技術分野の研究開発拠点や関連企業を進出させています。この記述は正しいです。
④【誤】
日本の自動車企業が海外に進出する際、現地の部品メーカーから調達したり、日系の部品メーカーが共に進出したりして、サプライチェーンを構築するのが一般的です。進出先の単一の工場内で、部品の生産から完成車の組み立てまで「すべてを一貫して」行うことは稀です。多くの部品は外部から調達しています。したがって、この記述は誤りです。
第5問
問1:正解⑤
<問題要旨>
地図に示された3都市の1月の気候データ(日照時間、平均気温)から、各都市名を特定する問題です。日本海側と瀬戸内側、そして内陸盆地の冬の気候の違いを理解しているかが問われます。
<選択肢>
まず、各都市の冬の気候の特徴を考えます。
・浜田市:日本海に面しており、冬は北西からの季節風の影響で曇りや雪の日が多く、日照時間は短くなります。また、海に近いため気温の低下は比較的緩やかです(沿岸部)。
・広島市:中国山地にさえぎられるため、冬の季節風の影響を受けにくく、晴天の日が多いです。そのため、日照時間は長くなります。気温は浜田市と近いか、やや低くなる程度です。
・三次市:中国山地沿いの内陸盆地に位置するため、冬は放射冷却現象により、朝晩の冷え込みが非常に厳しくなります。平均気温は最も低くなります。積雪もありますが、山陰地方ほど日照時間は短くありません。
次に、表のデータと照合します。
・ア:日照時間が138.6時間と最も長く、平均気温も5.4℃と比較的温暖です。これは冬に晴天が多い広島市の特徴と一致します。
・イ:平均気温が1.9℃と最も低いです。これは内陸盆地で冷え込みが厳しい三次市の特徴と一致します。
・ウ:日照時間が64.2時間と最も短く、平均気温は6.2℃と最も高くなっています。日本海側で日照時間が短いという特徴と、対馬暖流の影響で気温が下がりにくいという特徴から浜田市と判断できます。
したがって、浜田市がウ、広島市がア、三次市がイとなります。
①【誤】浜田市はウ、広島市はア、三次市はイです。
②【誤】浜田市はウ、広島市はアです。
③【誤】浜田市はウ、三次市はイです。
④【誤】広島市はア、三次市はイです。
⑤【正】上記の推論から、浜田市がウ、広島市がア、三次市がイの組み合わせが正しいです。
⑥【誤】広島市はアです。
問2:正解⑥
<問題要旨>
石見地方の住民が、3種類の商品・サービス(衣料品、娯楽、食料品)をどこで購入・利用しているかを示した図から、項目名を特定する問題です。商品の専門性や買回り性(比較検討して購入するかどうか)によって、人々の購買行動範囲(商圏)がどう変わるかを考える問題です。
<選択肢>
商品・サービスの性質(専門性)と商圏の広さは、一般的に以下の関係にあります。
・高次(専門性が高い):衣料品・身回品、娯楽・レジャーなど。品揃えが豊富なより大きな都市へ遠出して購入・利用する傾向がある(商圏が広い)。
・低次(日常性が高い):食料品など。最寄りの店で頻繁に購入するため、地元での購入率が高い(商圏が狭い)。
これを踏まえて図を分析します。
・カ:多くの地区で、広島市や出雲市など、他地区への流出割合が非常に高くなっています(太い矢印が多い)。これは、より専門的で多様な選択肢を求めて遠出する傾向が最も強い商品・サービスです。旅行なども含まれる娯楽・レジャーと考えられます。
・キ:カほどではないものの、他地区への流出が見られます。特に旧浜田市域など都市部では地元での購入率(25%以上)が高いですが、周辺地域からは都市部へ買いに出る傾向があります。これは典型的な買回り品である衣料品・身回品と考えられます。
・ク:ほとんどの地区で地元での購入率が25%以上(濃い灰色)であり、他地区への流出が非常に少ないです。これは、日常的に購入する最寄り品である食料品の特徴と一致します。
したがって、衣料品・身回品がキ、娯楽・レジャーがカ、食料品がクとなります。
①【誤】衣料品はキ、娯楽はカ、食料品はクです。
②【誤】衣料品はキ、娯楽はカです。
③【誤】娯楽はカ、食料品はクです。
④【誤】衣料品はキ、娯楽はカ、食料品はクです。
⑤【誤】衣料品はキ、食料品はクです。
⑥【正】上記の推論から、衣料品・身回品がキ、娯楽・レジャーがカ、食料品がクの組み合わせが正しいです。
問3:正解④
<問題要旨>
浜田市の人口分布と、コンビニエンスストア、まちづくりセンターの立地を示した図を比較し、施設までの距離別人口割合のグラフと正しく組み合わせる問題です。施設の性質(営利目的か公共サービスか)と立地戦略の違いを読み解く必要があります。
<選択肢>
まず、2つの施設の立地特性を考えます。
・コンビニエンスストア(X or Y):営利企業であり、収益が見込める場所、つまり人口が密集している地域や幹線道路沿いに集中して立地する傾向があります。
・まちづくりセンター(X or Y):公共施設であり、市民サービスを提供するため、市内の各地域に、ある程度均等に配置される傾向があります。人口の少ない地域にも配置されます。
図3を見ると、●(コンビニ)は人口密集地であるa地区やb地区の中心部に集中しているのに対し、□(まちづくりセンター)はc地区のような人口の少ない地域も含め、市内全域に分散して配置されています。
次に、図4のグラフを分析します。これは、各地区の住民が、最寄りの施設までどれくらいの距離に住んでいるかを示しています。
・X:小学校区a(人口密集地)では、住民の多くが1km未満に住んでいますが、サやシの地区では、1km未満の住民が少なく、3km以上離れている住民の割合が高いです。これは、人口密集地に集中立地するコンビニエンスストアの状況を反映していると考えられます。
・Y:どの地区でも、比較的多くの住民が1km未満に住んでおり、3km以上離れている住民はほとんどいません。これは、市内各地域に分散配置されているまちづくりセンターの状況を反映しています。
したがって、まちづくりセンターはYです。
次に、小学校区bとcを特定します。
・小学校区b:市の西部に位置し、中心市街地からやや離れていますが、人口は比較的多く、まちづくりセンターも地区内に複数設置されています。
・小学校区c:市の東部に位置する山間地域で、人口が非常に少ないです。まちづくりセンターは地区内に1つだけです。
グラフYを見ると、サはシに比べて、施設(まちづくりセンター)から1km未満に住む住民の割合が高く、より利便性が高いことがわかります。人口が多く、施設も複数ある小学校区bがサに、人口が少なく施設へのアクセスが相対的に遠い住民もいる小学校区cがシに該当すると考えられます。
したがって、まちづくりセンターがY、小学校区bがサの組み合わせが正しいです。
①【誤】まちづくりセンターはY、小学校区bはサです。
②【誤】まちづくりセンターはYです。
③【誤】小学校区bはサです。
④【正】上記の推論から、まちづくりセンターがY、小学校区bがサの組み合わせが正しいです。
問4:正解②
<問題要旨>
地形図と現地の写真を見比べ、地域の景観や土地利用について述べた会話文から、誤りを含むものを選ぶ問題です。地形図の読解力と、写真から景観の特徴を読み取る力が問われます。
<選択肢>
①【正】
地点Eの写真は、周囲を丘に囲まれた穏やかな湾(入り江)を撮影したものです。地形図を見ても、Eが位置する浜田漁港は、陸地が深く入り込み、外海から直接波が打ちつけにくい地形になっていることがわかります。このような地形は、船を安全に停泊させるのに適しています。この記述は正しいです。
②【誤】
地点Fの写真は、道幅が狭く、昔ながらの建物が密集する街並みを撮影したものです。地形図で見ても、Fを通る道は曲がりくねっていて狭く、城下町の古い街道の面影を残しています。会話文では「モータリゼーションに対応した大規模な再開発がされている」とありますが、写真の景観は、自動車社会に対応する以前の古い街並みであり、再開発されている様子は見られません。したがって、この記述は誤りです。
③【正】
地点Gの写真は、港湾に面した広い土地に大きな建物が並んでいる様子を撮影したものです。地形図を見ると、Gが位置する一帯は、海岸線が人工的な直線になっており、広大な平地が広がっています。周辺の自然海岸線や山の迫り方から、この土地は海を埋め立てて造成された人工島(埋立地)であると判断できます。この記述は正しいです。
④【正】
地点Hは、山の斜面に位置する住宅地です。地形図の等高線を見ると、宅地造成のために等高線が不自然に途切れたり、急な崖(切土)や緩やかな斜面(盛土)を示す記号が見られたりします。これは、山を切り崩し、谷を埋めるなどして平坦な土地を造成したことを示しています。この記述は正しいです。
問5:正解③
<問題要旨>
江戸時代の浜田を中心とした商品流通の図と、石見焼の分布図から、当時の物流について考察した会話文の空欄を埋める問題です。近世日本の海上交通(特に北前船)と商品流通に関する歴史地理的な知識が問われます。
<選択肢>
・空欄タの考察
会話文では、瀬戸内海・大阪から北海道・東北・北陸へ向かうJの経路で、浜田に何が運ばれたかを問うています。この時代、日本の経済の中心であった上方(大阪周辺)からは、生活に必要な様々な物資が地方へ運ばれました。選択肢にある「砂糖・塩」は、当時の貴重な調味料や保存食であり、上方から日本海側の各地へ運ばれる主要な商品でした。一方、「米・昆布」は、主に北国(東北・北陸・北海道)の産物であり、上方へ運ばれる商品です。したがって、タには砂糖・塩が入ります。
・空欄チの考察
会話文では、浜田の特産品である石見焼が、東北・北陸地方へどのように運ばれたかを問うています。資料1の右の地図を見ると、石見焼が確認された地点は、日本海沿岸に集中しています。浜田から東北・北陸地方へは、陸路で行くには中国山地などの険しい山々を越えなければならず、甕(かめ)のような重くて壊れやすい陶器を大量に運ぶのは非常に困難です。一方、この時代には北前船に代表される日本海航路が物流の大動脈として発達していました。船を使えば、大量の物資を効率的に遠くまで運ぶことができます。したがって、チには海路が入ります。
以上のことから、タが「砂糖・塩」、チが「海路」の組み合わせが正しいです。
①【誤】タは砂糖・塩です。
②【誤】タは砂糖・塩、チは海路です。
③【正】上記の推論から、タが砂糖・塩、チが海路の組み合わせが正しいです。
④【誤】チは海路です。
問6:正解③
<問題要旨>
石見地方の過疎問題の解決に向けた取組みについて、目的(P~S)と具体例(①~④)を関連付け、特定の目的(P)に合致する具体例を選ぶ問題です。現代日本の地域課題とその対策について、正しく理解しているかが問われます。
<選択肢>
まず、それぞれの具体例がどの目的を主としているかを考えます。
・① 交通空白地域における乗合タクシーの運行
→ これは、高齢者など交通手段を持たない住民の移動を助け、買い物や通院といった日常生活の不便さを解消するものです。主な目的は**Q(日常生活における利便性の向上)です。
・② 地元で水揚げされる水産物のブランド化
→ これは、地域の特産品に付加価値をつけ、その魅力を高めて地域外にアピールし、販売を促進するものです。主な目的はS(魅力ある地域産品の宣伝)です。
・③ 伝統行事の保存・継承に対する支援
→ これは、地域に古くから伝わる文化を守り、次の世代に伝えていく活動です。これにより、地域住民のアイデンティティや、ふるさとへの誇り・愛着を育むことにつながります。主な目的はP(地域文化に対する愛着の醸成)です。
・④ 廃校を利用したサテライトオフィスの整備
→ これは、都市部の企業が地方に拠点を設けることを促し、移住者が働く場所を確保するものです。主な目的はR(移住者の働く場所の確保)**です。
設問では、P(地域文化に対する愛着の醸成)を主な目的とする具体例を問うているので、③が正解となります。