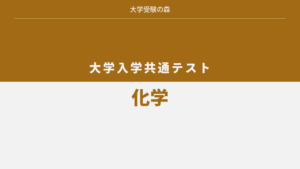解答
解説
第1問
問1:正解④
<問題要旨>
配位結合を含むイオンの判別に関する問題です。配位結合は、一方の原子が非共有電子対を供与し、他方の原子(またはイオン)がそれを受け取って形成される共有結合の一種です。
<選択肢>
①【誤】
アンモニウムイオン NH4+ は、アンモニア NH3の窒素原子 N が持つ非共有電子対を、水素イオン H+に供与して配位結合を形成することで生じます(NH3+H+→NH4+)。したがって、配位結合を含みます。
②【誤】
オキソニウムイオン H3O+は、水 H2O の酸素原子 O が持つ非共有電子対を、水素イオン H+ に供与して配位結合を形成することで生じます(H2O+H+→H3O+)。したがって、配位結合を含みます。
③【誤】
ジアンミン銀(I)イオン [Ag(NH3)2]+ は、銀イオン Ag+が、2分子のアンモニア NH3の窒素原子 N が持つ非共有電子対を受け取り、配位結合を形成して生じる錯イオンです(Ag++2NH3→[Ag(NH3)2]+)。したがって、配位結合を含みます。
④【正】
ギ酸イオン HCOO-は、ギ酸 HCOOH が電離して H+を放出した陰イオンです。イオン内の結合(C=O, C-O, C-H)はすべて共有結合(または共鳴構造)であり、非共有電子対を一方的に供与して形成された配位結合は含まれません。したがって、これが配位結合してできたイオンとして適当でないものです。
問2:正解①
<問題要旨>
液体の密度と気体の状態方程式を用いて、状態変化(液体→気体)に伴う体積変化(体積比)を計算する問題です。
<選択肢>
メタン CH4 の分子量は16 なので、16gのメタンは 16 g/16 g/mol=1.0 mol です。
- 液体の体積 Vliquid の計算
液体のメタンの密度は 0.42 g/cm3 です。
質量 m=16 g 、密度 d=0.42 g/cm3 なので、
Vliquid= m/d =16 g / 0.42 g/cm3 ≈ 38.095 cm3 ≈ 0.0381 L( 1 L=1000 cm3 ) - 気体の体積 Vgas の計算
気体の状態方程式 PV=nRT を用います。
P=1.0×105 Pa
n=1.0 mol
R=8.3×103 Pa⋅L/(K⋅mol)
T=300 K
Vgas = nRT / P = 1.0 mol×8.3×103 Pa⋅L/(K⋅mol)×300 K / 1.0×105 Pa = 24.9 L - 体積の比較(倍率の計算)
Vgas / Vliquid = 24.9 L / 0.038095 L ≈ 653.6 ≈ 6.5×102
したがって、体積は約 6.5×102 倍になります。
①【正】
上記の計算結果 6.5×102 と一致します。
②【誤】
計算結果と異なります。
③【誤】
計算結果と異なります。
④【誤】
計算結果と異なります。
問3:正解④
<問題要旨>
溶液、コロイド溶液、懸濁液の粒子径の違いと、ろ紙およびセロハン膜(半透膜)の透過性に関する問題です。粒子の大きさは一般に、溶液 < コロイド < 懸濁液 です。
<選択肢>
・グルコース:水に溶けて溶液となります。粒子は最小です。
・砂:水に溶けず、懸濁液となります。粒子は最大です。
・トリプシン:水中で分子コロイドとなります 。粒子は中間の大きさです。
・ろ紙:穴が比較的大きく、懸濁液の粒子(砂)は通しませんが、コロイド粒子(トリプシン)と溶液の粒子(グルコース)は通過させます。
・セロハン膜(半透膜):穴がろ紙より小さく、溶液の粒子(グルコース)は通過させますが、コロイド粒子(トリプシン)や懸濁液の粒子(砂)は通過させません。
したがって、
・ろ紙を通過できるもの:グルコース、トリプシン
・セロハンの膜を通過できるもの:グルコース
となります。この組合せは選択肢④です。
問4:(a)正解④ (b)正解③ (c)正解⑤
a:正解④
<問題要旨>
水の状態図(図1)の読解問題です。状態図の各領域(固体、液体、気体)と境界線(融解曲線、蒸気圧曲線、昇華曲線)、三重点の意味を理解しているかが問われます。
<選択肢>
①【正】
圧力 2×102 Pa は、三重点の圧力 6.11×102 Pa よりも低いです。状態図でこの圧力の水平線を見ると、固体領域と気体領域の境界(昇華曲線)と0℃ より低い温度で交わります。したがって、氷は0℃より低い温度で昇華します。
②【正】
状態図で温度 0℃ の垂線を見ると、 1.01×105 Pa は固体と液体の境界(融解曲線)上にあります。水の場合、融解曲線は圧力が上がると温度が下がる方向(左上)に傾いています。したがって、0℃で 1.01×105 Pa の氷にさらに圧力を加える(垂線を上に行く)と、液体の領域に入ります。これは氷が融解することを意味します。
③【正】
0.01℃ , 6.11×102 Pa の点は、状態図において固体、液体、気体の3つの領域が接する「三重点」です。三重点では、三つの状態が共存できます。
④【誤】
液体と気体の境界線(蒸気圧曲線)を見ると、圧力が 1.01×105 Pa のときに沸点は 100℃ です。圧力が 1.01×105 Pa よりも低い 9×104 Pa の場合、蒸気圧曲線と交わる温度は 100∘C よりも低くなります。したがって、水は 100℃ より「低い」温度で沸騰します。
b:正解③
<問題要旨>
氷と水の密度に関するグラフ(図2)の読解問題です。水の密度が約4℃で最大になること、氷の密度が水より小さいことなど、水の特異な性質を読み取ります。
<選択肢>
①【誤】
図2より、0℃ において、氷の密度(約 0.917 g/cm3 )は水の密度(約 1.000 g/cm3 )よりも小さいです。体積 V=質量/密度 なので、同じ質量1gでは、氷の体積は水の体積よりも大きくなります。「小さい」という記述は誤りです。
②【誤】
図2の氷の密度(左下の実線)を見ると、-4℃ から 0℃ にかけて密度はわずかに減少しています。0℃で最大にはなりません。
③【正】
図2から読み取ると、
・12℃ での水の密度(右上の実線):約 0.9995 g/cm3 (0.999 g/cm3 より上)
・-4℃ での過冷却水の密度(左上の破線):約 0.9985 g/cm3 (0.999 g/cm3 より下)
よって、12℃での水の密度は、-4℃での過冷却の状態の水の密度よりも大きいです。
④【誤】
水は4℃ で密度が最大(1.000 g/cm3)になります。4℃の水の液面を冷却すると、液面の水温は4℃より下がり、密度は小さくなります(例:3℃や2℃の水は4℃の水より軽い)。密度が小さい水は軽いため、下の方へは移動せず、液面に留まります。
c:正解⑤
<問題要旨>
融解熱を用いた熱化学計算と、密度を用いた体積計算の融合問題です。加えた熱量から融解した氷の物質量を求め、残った氷の質量を算出し、図2から読み取った密度を用いて体積を計算します。
<選択肢>
- 融解した氷の物質量・質量
水 H2O のモル質量は 1.0×2+16=18 g/mol です。
氷の融解熱は 6.0 kJ/mol です。
加えた熱量 6.0 kJ により融解した氷の物質量 nmelt は、
nmelt=6.0 kJ/6.0 kJ/mol=1.0 mol
融解した氷の質量 mmelt は、
mmelt=1.0 mol×18 g/mol=18 g - 残った氷の質量
はじめの氷の質量は 54 g でした。
残った氷の質量 mremain = 54 g−18 g = 36 g - 残った氷の体積
問題の条件は 1.01×105 Pa 、 0℃ の氷です。
図2より、0℃ における氷の密度 dice を読み取ります。グラフの左下の実線は、 0.917 g/cm3 の線よりわずかに上にあります。 0.917∼0.918 g/cm3 程度と読み取れます。
仮に dice=0.917 g/cm3 として計算します。
残った氷の体積 Vremain = mremain / dice = 36 g / 0.917 g/cm3 ≈ 39.26 cm3
(※ dice=0.918 g/cm3 としても Vremain = 36 g / 0.918 g/cm3 ≈ 39.22 cm3)
いずれの場合も、最も適当な数値は 39 cm3 です。
①【誤】18
②【誤】19
③【誤】20
④【誤】36(残った氷の質量(g)です)
⑤【正】39
⑥【誤】40
第2問
問1:正解①
<問題要旨>
吸熱反応と発熱反応のエネルギー図の理解を問う問題です。吸熱反応では、反応物よりも生成物の方がエネルギー準位が高くなります。
<選択肢>
硝酸アンモニウムの溶解は「吸熱反応」であると問題文に記載されています。
・反応物:NH4NO3(固)+aq (固体を水に入れる前の状態)
・生成物:NH4NO3 aq (水に溶解した状態)
吸熱反応なので、エネルギー準位は(生成物)>(反応物)となります。
また、矢印は反応の進行方向、すなわち反応物から生成物へ向かう必要があります。
したがって、エネルギー図は、低い位置にある NH4NO3(固)+aq から、高い位置にある NH4NO3 aq へ向かう上向きの矢印が描かれているものを選びます。
①【正】
反応物が低エネルギー側、生成物が高エネルギー側にあり、矢印は反応物から生成物へ向かう上向き(吸熱)です。正しい図です。
②【誤】
エネルギー準位は正しいですが、矢印が生成物から反応物へ向かっており、逆反応を示しています。
③【誤】
反応物が高エネルギー側、生成物が低エネルギー側にあり、発熱反応を示しています。
④【誤】
発熱反応の逆反応を示しています。
問2:正解③
<問題要旨>
化学平衡(ルシャトリエの原理)に関する問題です。生成物であるCOの物質量を増やす操作、すなわち平衡を正反応(右向き)に移動させる操作を選びます。
<選択肢>
反応式: CO2(気)+H2(気)⟺CO(気)+H2O(気)
条件:正反応は吸熱反応 、反応物・生成物はすべて気体 。
①【誤】
正反応は吸熱反応なので、温度を下げると平衡は熱を発生する方向、すなわち逆反応(左向き)に移動します。COは減少します。
②【誤】
この反応では、反応物(CO2+H2)の気体分子の総数(1+1=2 mol)と、生成物(CO+H2O)の気体分子の総数(1+1=2 mol)が等しいです。このように反応の前後で気体分子の総数が変化しない場合、圧力を変更しても平衡は移動しません。COの物質量は変化しません。
③【正】
反応物の一つである H2を加えると、ルシャトリエの原理により、 H2を消費する方向、すなわち正反応(右向き)に平衡が移動します。その結果、COの物質量は増加します。(温度と圧力を一定に保つためには、容積可変の容器が膨張しますが、 H2の濃度(分圧)増加の影響が支配的です。)
④【誤】
温度と圧力を一定に保ったまま、反応に関与しないアルゴンを加えると、容積可変の容器は膨張します。体積が増加するため、反応に関与する各気体の分圧は減少します。しかし、②で述べたように、この反応は気体分子の総数が変化しないため、分圧が変化しても平衡は移動しません。COの物質量は変化しません。
問3:正解④
<問題要旨>
各電池の反応式から、反応物の総質量 1kg あたりに流れる電子 e-の物質量を計算し、その大小を比較する問題です。流れる電気量 Q は、電子の物質量 ne に比例します(Q=ne×F、Fはファラデー定数)。
<選択肢>
各電池について、反応式で ne (mol) の電子が流れるときに消費される反応物の総質量 Mreact (g) を計算し、単位質量あたりの電子の物質量(ne/Mreact)を比較します。この値が大きいほど、1kgあたりの電気量 Q が大きくなります。式量は表1 を用います。
- アルカリマンガン乾電池 (式(2) )
2MnO2+Zn+2H2O→…
(負極 Zn→Zn(OH)2+2e-、正極 2MnO2+2H2O+2e-→2MnO(OH)+2OH-)
電子 ne=2 mol が流れます。
消費される反応物の総質量 Mreact(Mn)=(2×式量MnO2)+(1×式量Zn)+(2×式量H2O)
Mreact(Mn)=(2×87)+(1×65)+(2×18)=174+65+36=275 g
比 ne/Mreact=2/275≈0.00727 - 空気亜鉛電池 (式(3) )
O2+2 Zn⟶2 ZnO
(負極 2Zn→2Zn2++4e-、正極 O2+4e-(+2H2O)→4OH- または O2+4e-(+4H+)→2H2O)
電子 ne=4 mol が流れます。
消費される反応物の総質量 Mreact(Zn)=(1×式量O2)+(2×式量Zn)
Mreact(Zn)=(1×32)+(2×65)=32+130=162 g
比 ne/Mreact=4/162=2/81≈0.02469 - リチウム電池 (式(4) )
Li+MnO2⟶LiMnO2
(負極 Li→Li++e-、正極 MnO2+e-(+Li+)→LiMnO2)
電子 ne=1 mol が流れます。
消費される反応物の総質量 Mreact(Li)=(1×式量Li)+(1×式量MnO2)
Mreact(Li)=(1×6.9)+(1×87)=93.9 g
比 ne/Mreact=1/93.9≈0.01065 - 比較
ne/Mreact の値を比較すると、
空気亜鉛 (0.02469) > リチウム (0.01065) > アルカリマンガン (0.00727)
となります。
①【誤】
②【誤】
③【誤】
④【正】空気亜鉛電池 > リチウム電池 > アルカリマンガン乾電池
⑤【誤】
⑥【誤】
問4:(a)正解④ (b)正解② (c)正解④
a:正解④
<問題要旨>
弱酸の電離平衡における、モル濃度 c と電離度 α の関係(希釈の法則)を問う問題です。
<選択肢>
弱酸 HA の電離平衡 HA⟺H++ A- における電離定数 Ka は、 Ka=[H+][A-] / [HA] です。
各濃度を c,α で表すと [HA]=c(1−α), [H+]=cα, [A-]=cα となります。
Ka=(cα)(cα) / c(1−α) = cα2 / 1−α
α が1よりも十分小さい(α≪1)とき、1−α≈1 と近似できるため、
Ka≈cα2α≈√Ka/c=√Ka / √c
電離度 α は、モル濃度 c の平方根の逆数(1 /√c)に比例します。
これは、濃度 c が大きいほど α は小さく、濃度 c が小さいほど α は大きくなる(c の減少関数)ことを意味します。グラフ①、②、③は誤りです。
この関係(α∝1/√c)をグラフで確認します。
c=c0 のとき α=α0 です。
c=4c0 のとき、 α≈√Ka/√(4c0)=(1/2)√Ka/√c0=(1/2)a0
c=(1/4)c0 のとき、 α≈√Ka/√(c0/4)=2√Ka/√c0=2α0
グラフ④は、c=c0 で α=α0 、 c=4c0 で α≈α0/2 、 c≈c0/4 で α=2α0 となっており、この関係を正しく表しています。
グラフ⑤は、c=4c0 で α≈α0/4 となっており、 α∝1/c (反比例)に近い形で、 α∝1/√c よりも急激に減少しているため、誤りです。
①【誤】
②【誤】
③【誤】
④【正】
⑤【誤】
b:正解②
<問題要旨>
弱酸と強塩基の中和滴定において、緩衝溶液となっている時点での [H+] と [HA], [A−] の濃度から、弱酸の電離定数 Ka を求める問題です。
<選択肢>
電離定数 Ka=[H+][A-] /[HA]を用います。
NaOH水溶液の滴下量が 2.5 mL の時点での各濃度が必要です。
この時点での [H+]=8.1×10−5 mol/L です。
[HA] と [A-] の濃度は、中和反応 HA+OH-→A-+H2O によって決まります。
・はじめの HA: 0.10 mol/L×10.0 mL=1.0 mmol
・加えた NaOH (OH⁻): 0.10 mol/L×2.5 mL=0.25 mmol
反応により、HA が 0.25 mmol 消費され、A- が 0.25 mmol 生成します。
・反応後の HA: 1.0−0.25=0.75 mmol
・反応後の A-: 0+0.25=0.25 mmol
このときの溶液の総体積は 10.0 mL+2.5 mL=12.5 mL です。
[HA]=0.75 mmol/12.5 mL=0.060 mol/L
[A-]=0.25 mmol/12.5 mL=0.020 mol/L
(この値は図1のグラフの 2.5 mL 時点の [HA]=0.06 , [A-]=0.02 とも一致します。)
Ka を計算します。
Ka=[H+][A-] / [HA] = (8.1×10−5 mol/L)×(0.020 mol/L) / 0.060 mol/L
Ka=(8.1×10-5)×1/3 = 2.7×10-5 mol/L
①【誤】
②【正】
③【誤】
④【誤】
⑤【誤】
⑥【誤】
c:正解④
<問題要旨>
弱酸の中和滴定における濃度変化(滴定曲線)の解釈を問う問題です。電気的中性の原理、水のイオン積、中和反応、希釈効果などを理解しているかが問われます。
<選択肢>
当量点(中和点)は、HA 1.0 mmol が NaOH 1.0 mmol で中和される滴下量 10 mL の点です。
①【正】
水溶液中に存在するイオンは H+,Na+,A-,OH- です。水溶液は常に電気的に中性であるため、陽イオンの電荷の総和と陰イオンの電荷の総和は等しくなければなりません。すべてのイオンは1価なので、 [H+]+[Na+]=[A-]+[OH-] という関係(電気的中性の原理)が常に成り立ちます。下線部は正しいです。
②【正】
問題文より「水溶液の温度は変化しない」とあります。水のイオン積 Kw=[H+][OH-] は温度のみに依存する定数であるため、[H+] と [OH-] の積は滴下量によらず一定です。下線部は正しいです。
③【正】
滴下量が 10 mL 未満(当量点より前)では、NaOH (OH-) が加えられます。OH-が HA⟺H++A- の H+ と反応して H2O になるため、平衡は右に移動し [A-] が増加します。また、中和反応 HA+OH-→A-+H2O が進むこと自体によっても [A-] は増加します。図1のグラフでも 0〜10 mL で [A-] は増加しています。下線部は正しいです。
④【誤】
滴下量が 10 mL(当量点)より多い範囲では、HA はすべて A- になっており、中和反応は完結しています。この範囲で [A-] が減少する(図1のグラフ参照)のは、中和反応によるものではなく、NaOH水溶液が追加されることによる「希釈効果」(溶液の総体積が増加するため、[A-] = ( A- の物質量) / (総体積) が減少する)のためです。下線部の理由は誤りです。
第3問
問1:正解①③
<問題要旨>
化学実験における試薬の保存方法や取扱い、安全対策に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
ナトリウム Na は、空気中の酸素や水だけでなく、エタノール C2H5OH とも反応して水素を発生します(2Na+2C2H5OH→2C2H5ONa+H2)。したがって、エタノール中には保存できません。反応性のない石油(灯油)中に保存します。
②【正】
水酸化ナトリウムは強塩基で皮膚を腐食します。付着した場合は、ただちに多量の水で洗い流すのが第一の応急処置です。その後、可能であれば弱酸(酢酸やホウ酸水溶液)で中和し、さらに水で洗います。下線部は正しいです。
③【誤】
濃硫酸を水で希釈すると大きな溶解熱が発生します。「濃硫酸に水を加える」と、少量の水が突沸し、濃硫酸が飛び散る危険があります。必ず「多量の水に、濃硫酸を撹拌しながら少しずつ加える」ようにします。
④【正】
濃硝酸 HNO3 は、光によって分解し、有毒な NO2 を発生して褐色を帯びます(4HNO3光4NO2+O2+2H2O)。そのため、光を遮る褐色びんに保存します。下線部は正しいです。
⑤【正】
硫化水素 H2S は、腐卵臭を持つ有毒な気体です。実験で扱う際は、吸入しないよう通風の良い場所やドラフト(局所排気装置)内で行います。下線部は正しいです。
誤りを含むものは①と③です。
問2:正解④
<問題要旨>
ハロゲン(17族)元素の性質の周期性(族の傾向)に基づき、ヨウ素 (I) の下に位置するアスタチン (At) の性質を推測する問題です。
<選択肢>
ハロゲンの性質の傾向(F, Cl, Br, I の順):
・単体の融点・沸点:分子量が大きくなるため、高くなる(F2<Cl2<Br2<I2)。
・単体の水への溶解性:無極性分子のため、水に溶けにくい。
・ハロゲン化銀の溶解性:AgCl,AgBr,AgI は水に難溶(AgF は可溶)。
・単体の酸化力:原子番号が小さいほど強い(F2>Cl2>Br2>I2)。
①【正】
融点・沸点は、周期表で下に行くほど高くなる傾向(F2<Cl2<Br2<I2)があります。At は I の下なので、単体 At2 の融点・沸点はハロゲン中で最も高くなると推定されます。記述は適当です。
②【正】
他のハロゲン単体(特に Br2,I2)が無極性分子で水に溶けにくいことから、At2 も水に溶けにくいと推定されます。記述は適当です。
③【正】
ハロゲン化銀は AgCl,AgBr,AgI が難溶です。この傾向から AgAt も難溶であると推定されます。したがって、 NaAt 水溶液と AgNO3 水溶液を混ぜると AgAt の沈殿を生じると考えられます。記述は適当です。
④【誤】
ハロゲン単体の酸化力は Br2>I2 です。この傾向から、At の酸化力はさらに弱く、Br2>At2 であると推定されます。酸化力の強い単体(Br2)は、酸化力の弱い単体のイオン(At−)を酸化できます。
Br2+2At−→2Br−+At2
したがって、臭素水を NaAt 水溶液に加えると、上記の酸化還元反応が起こると推定されます。「反応は起こらない」という記述は適当でないと考えられます。
問3:正解③④
<問題要旨>
代表的な合金(ステンレス鋼)とめっき鋼板(トタン)の構成元素に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
・ステンレス鋼 :鉄 (Fe) を主成分とし、耐食性を高めるために クロム (Cr) を必須成分として含む合金です。ニッケル (Ni) を含むものも多いです。したがって、アは ③ Cr です。
・トタン :鉄 (Fe) の表面に 亜鉛 (Zn) をめっきしたものです。鉄よりイオン化傾向が大きい亜鉛が犠牲的に腐食することで、鉄本体を守ります(犠牲防食)。したがって、イは ④ Zn です。
(参考)
・ブリキ:鉄 (Fe) にスズ (Sn) をめっきしたもの。
・Al , Ti はこれらの主な構成元素ではありません。
問4:(a)正解③ (b)正解⑤ (c)正解②
a:正解③
<問題要旨>
酸化還元反応式において、各原子の酸化数の変化を調べ、酸化されたか還元されたかを判断する問題です。
<選択肢>
反応式(1): NiS+2 CuCl2⟶NiCl2+2 CuCl+S
各原子の酸化数を比較します。
・反応物:
NiS:S は -2、Ni は +2
CuCl2:Cl は -1、Cu は +2
・生成物:
NiCl2:Cl は -1、Ni は +2
CuCl:Cl は -1、Cu は +1
S:単体なので 0
酸化数の変化:
・ニッケル原子 (Ni): +2 → +2 (変化なし)
・硫黄原子 (S): -2 → 0 (酸化数増加 → 酸化された)
・銅原子 (Cu): +2 → +1 (酸化数減少 → 還元された)
・塩素原子 (Cl): -1 → -1 (変化なし)
したがって、「ニッケル原子」は「酸化も還元もされない」、「硫黄原子」は「酸化される」の③の組合せが正しいです。
b:正解⑤
<問題要旨>
複数の化学反応式(触媒的なプロセスを含む)を用いた物質量の計算問題です。
<選択肢>
反応(1)と(2)を足し合わせると、 CuCl2 と CuCl が消去され、全体の反応式が得られます。
(1) NiS+2CuCl2 → NiCl2+2CuCl+S
(2) 2CuCl+Cl2 → 2CuCl2
全体 NiS + Cl2 → NiCl2 + S
この全体の反応式から、NiS と Cl2 は 1 : 1 の物質量比で反応することがわかります。
CuCl2 は反応(1)で消費され、反応(2)で再生されるため、触媒のように働いています。
問題文に「すべてのニッケルがNiCl₂として水溶液中に溶解し」とあるので、NiS がすべて反応したことがわかります。
NiS のモル質量: 59(Ni)+32(S)=91 g/mol
反応した NiS の物質量:36.4 kg×1000 g/kg / 91 g/mol = 36400 / 91 mol = 400 mol
全体の反応式 NiS+Cl2⟶NiCl2+S より、NiS 400 mol がすべて反応するために必要な Cl2 の物質量も 400 mol です。(CuCl2 40.5 kg は 40500 g/135 g/mol=300 mol であり、反応を媒介するのに十分な量(または触媒量)として存在します。)
①【誤】150
②【誤】200
③【誤】300
④【誤】350
⑤【正】400
⑥【誤】500
⑦【誤】550
⑧【誤】700
c:正解②
<問題要旨>
電気分解において、陽極と陰極で流れた電子の総物質量が等しいこと(ファラデーの法則)を利用する計算問題です。陰極では複数の反応が同時に起こっています。
<選択肢>
- 各反応と電子 e− の物質量の関係
気体の状態方程式 PV=nRT より、気体 x の物質量 nx=PVx / RT です。
・陰極(3) (Ni析出): Ni2++2 e-⟶Ni
Ni の物質量を nNi とすると、流れた電子 ne(Ni)=2×nNi
Ni の質量 w=nNi×M より nNi=w/M
よって ne(Ni)=2w/M
・陰極(4) (H2発生): 2H++2 e-⟶H2
H2 の物質量 nH2=RTPVH2
流れた電子 ne(H2)=2×nH2=2PVH2 / RT
・陽極(5) (Cl2発生): 2 Cl-⟶Cl2+2 e-
Cl2 の物質量 nCl2=PVCl2 / RT
流れた電子 ne(Cl2)=2×nCl2=2PVCl2 / RT - 電子の物質量の保存
陽極で流れた電子の総量と、陰極で流れた電子の総量は等しいです。
ne(陽極)=ne(陰極)
ne(Cl2)=ne(Ni)+ne(H2) - w を求める
上記の関係式に、各 ne を代入します。
2PVCl2 / RT = M2w+2PVH2 / RT
両辺を 2 で割ります。
PVCl2 / RT = Mw+PVH2 / RT
w/M について整理します。
Mw=PVCl2 / RT−PVH2 / RT = P(VCl2−VH2) / RT
w について解くと、
w=MP(VCl2−VH2) / RT
第4問
問1:正解③
<問題要旨>
エチレン(エテン)の酸化反応に関する知識問題です。
<選択肢>
エチレン CH2=CH2 を PdCl2 と CuCl2 を触媒として酸素 O2 で酸化する と、アセトアルデヒド CH3−CHO が生成します。
2 CH2=CH2+O2→2 CH3−CHO
この工業的製法はワッカー法と呼ばれます。
①【誤】エタノール CH3−CH2−OH は、エチレンへの水の付加で得られます。
②【誤】ジメチルエーテル CH3−O−CH3 は、メタノールの分子間脱水で得られます。
③【正】アセトアルデヒド CH3−CHO が生成します。
④【誤】酢酸 CH3−COOH は、アセトアルデヒドをさらに酸化すると得られます。
問2:正解①
<問題要旨>
デンプン、合成繊維(アクリル)、ゴム、再生繊維(レーヨン)に関する基本的な知識を問う問題です。
<選択肢>
①【誤】
デンプンはアミロースとアミロペクチンからなります。アミロースは温水に溶けますが、アミロペクチン は分子量が非常に大きく、複雑な枝分かれ構造を持つため、冷水にも温水にも溶けにくい(膨潤する程度)です。したがって、「冷水に溶けやすい」 という記述は誤りです。
②【正】
アクリル繊維 は、アクリロニトリル CH2=CH−CN を付加重合させたポリアクリロニトリルを主成分とする合成繊維です。記述は正しいです。
③【正】
生ゴム(ポリイソプレン)に硫黄を加えて加熱する操作を「加硫」といいます。これにより、ゴム分子鎖間に硫黄原子による架橋構造 が形成され、弾性、強度、耐久性が向上します 。記述は正しいです。
④【正】
レーヨン は、木材パルプなどから得られたセルロース を、一度薬品(二硫化炭素や水酸化ナトリウムなど)に溶解 させてビスコースという溶液にし、それを再び繊維として再生させた 再生繊維です。記述は正しいです。
問3:正解⑦
<問題要旨>
タンパク質・アミノ酸の検出反応(ニンヒドリン、キサントプロテイン、ビウレット)が、どのような構造に対して陽性となるかを問う問題です。
<選択肢>
図1のトリペプチドは、チロシン(側鎖にベンゼン環)、アラニン、システインが結合したものです。
ア ニンヒドリン反応 :
アミノ基(−NH2)を持つアミノ酸やペプチドと反応し、青紫色を呈します。
図1のトリペプチドはN末端にアミノ基 を持つため、陽性です。
イ キサントプロテイン反応 :
ベンゼン環を持つアミノ酸(チロシンなど)と反応します。濃硝酸で黄色、アンモニア水で橙黄色になります。
図1のトリペプチドはチロシン残基(ベンゼン環)を持つため、陽性です。
ウ ビウレット反応 :
ペプチド結合(−CO−NH−)を2つ以上(つまりトリペプチド以上)持つ化合物と反応し、赤紫色を呈します。
図1の化合物はトリペプチドであり、ペプチド結合を2つ 持つため、陽性です。
以上より、ア、イ、ウのすべての反応で特有の変化(陽性反応)を示します。
問4:(a)正解② (b)正解② (c)正解⑤
a:正解②
<問題要旨>
サリシン、サリチル酸、および関連する糖類(グルコース)や芳香族カルボン酸の性質・製法に関する知識を問う問題です。
<選択肢>
①【正】
グリコシド結合 は、酸(希硫酸など)を触媒として加熱 したり、特定の酵素を用いたりすることで加水分解 されます。記述は正しいです。
②【誤】
銀鏡反応 は、アルデヒド基などの還元性官能基によって引き起こされます。サリシン は、サリチルアルコールとグルコースがグリコシド結合したものです 。図2の構造からわかるように、グルコースの還元性を示す部分(1位のヘミアセタール構造)がグリコシド結合 に使われているため、環状構造が開いてアルデヒド基になることができません。したがって、サリシンは還元性を示さず、銀鏡反応は陰性です。下線部は誤りです。
③【正】
サリチル酸 は、工業的にはコルベ・シュミット反応によって製造されます。これは、ナトリウムフェノキシドと二酸化炭素を高温・高圧で反応 させてサリチル酸ナトリウムとし、これを酸性にする ことでサリチル酸を得る方法です。記述は正しいです。
④【正】
サリチル酸(HOC6H4COOH)とメタノール(CH3OH)を反応 させてできるエステルは、サリチル酸メチル(HOC6H4COOCH3)です。これは消炎鎮痛剤 (外用薬)として用いられます。記述は正しいです。
b:正解②
<問題要旨>
アミノ酸の分子内脱水による環状アミド(ラクタム)の生成に関する問題です。β-ラクタム環は、β-アミノ酸から生成されます。
<選択肢>
β-ラクタム環は、リード文の図3や図4にあるように、アミド結合(-CO-NH-)を含む四員環構造です。
このような四員環アミドは、アミノ基(−NH2)とカルボキシ基(−COOH)が分子内脱水縮合して形成されます。
環を構成する原子が4つ(−CO−NH−Cβ−Cα−)であることから、アミノ基がカルボキシ基に対してβ位(隣の炭素がα位、その次がβ位)にあるアミノ酸、すなわちβ-アミノ酸が原料となります。
① H2N−αCH2−COOH(α-アミノ酸) → 三員環(不安定)
② H2N−βCH2−αCH2−COOH(β-アミノ酸) → 四員環(β-ラクタム)
③ H2N−γCH2−βCH2−αCH2−COOH(γ-アミノ酸) → 五員環(γ-ラクタム)
④ H2N−δCH2−…−COOH(δ-アミノ酸) → 六員環(δ-ラクタム)
⑤ H2N−ϵCH2−…−COOH(ε-アミノ酸) → 七員環(ε-カプロラクタム)
したがって、β-ラクタム環ができる化合物は②のβ-アミノ酸(β-アラニン)です。
c:正解⑤
<問題要旨>
芳香族化合物の合成経路に関する問題です。ニトロ化、側鎖の酸化、ニトロ基の還元、エステル化の各反応を正しい順序で理解しているかが問われます。
<選択肢>
図5の合成経路を順に追います。
・出発物質:トルエン (C6H5−CH3)
・トルエン → 化合物A
反応:濃 HNO3, 濃 H2SO4 → ニトロ化反応。メチル基はオルト・パラ配向性。
最終生成物がパラ体なので、化合物Aは p-ニトロトルエン (O2N−C6H4−CH3) です。
・化合物A → 化合物B
反応:KMnO4 → 側鎖(メチル基)の酸化。メチル基 −CH3 がカルボキシ基 −COOH に変わります。
化合物Bは p-ニトロ安息香酸 (O2N−C6H4−COOH) です。
・化合物B → 化合物C
反応:Sn, HCl → ニトロ基(−NO2)の還元。−NO2 がアミノ基 −NH2 に変わります。
化合物Cは p-アミノ安息香酸 (H2N−C6H4−COOH) です。
・化合物C → p-アミノ安息香酸エチル
反応:エタノール, 濃 H2SO4 → エステル化反応。−COOH が −COOCH2CH3 に変わります。
生成物は p-アミノ安息香酸エチル となり、経路と一致します。
問題は「化合物B」を問うているので、p-ニトロ安息香酸(選択肢⑤)が正解です。
①【誤】(p-トルイジン)
②【誤】(p-アミノベンズアルデヒド)
③【誤】(化合物C)
④【誤】(化合物A)
⑤【正】
⑥【誤】(p-ニトロ安息香酸エチル)
第5問
問1:正解④
<問題要旨>
質量分析の検量線(図1)を読み取り、試料中の物質量を比例計算する問題です。
<選択肢>
- 尿 3.0 mL 中のテストステロン質量を求める
図1のグラフは原点を通る直線であり、信号強度と質量は比例しています。
グラフから、信号強度 100 のとき、質量は 5.0×10−8 g (横軸の単位 ×10−8g に注意)であることが読み取れます。
ある選手の尿 3.0 mL の信号強度は 10 でした。このときの質量を m3.0 とすると、比例関係から、
m3.0 / 信号強度10 = 5.0×10-8 g / 信号強度100
m3.0=10 / 100×(5.0×10-8 g)=0.5×10-8 g=5.0×10-9 g - 尿 90 mL 中のテストステロン質量を求める
尿 3.0 mL 中に 5.0×10-9 g 含まれているので、尿 90 mL 中の質量 m90 は、その 90/3.0=30 倍です。
m90=m3.0×30=(5.0×10-9 g)×30
m90=150×10-9 g=1.5×10-7 g
問2:正解③
<問題要旨>
同位体希釈質量分析法を用いた物質量の決定問題です。試料中の銀(未知量、同位体比 50:50)と、スパイクとして加えた既知量の銀(107Ag 100%)を混合した後の同位体比(75:25)から、元の試料中の銀の物質量を計算します。
<選択肢>
実験Ⅰで調製した溶液 200 mL 中に含まれる Ag の総物質量を nX (mol) とします。(これが求める値です。)
実験Ⅱで用いたのは、この溶液 100 mL なので、これに含まれる Ag の物質量(試料由来)は nX/2 (mol) です。
- 試料由来(100 mL分)の各同位体の物質量
同位体比 107Ag:50.0%,109Ag:50.0%
107Ag: (nX/2)×0.500
109Ag: (nX/2)×0.500 - スパイク由来の各同位体の物質量
添加量 nspike=5.00×10-3 mol
同位体比 107Ag:100%
107Ag: 5.00×10-3 mol
109Ag: 0 mol - 混合溶液中の同位体比
実験Ⅱの混合溶液の同位体比は 107Ag:75.0%,109Ag:25.0% でした。
これは、 総107Ag 物質量 / 総109Ag 物質量 = 75.0 / 25.0 = 3/1 を意味します。 - 方程式を立てて nX を解く
((nX/2)×0.500)+(5.00×10-3) / ((nX/2)×0.500)+0 = 3/1
(nX/2)×0.500+5.00×10-3 = 3×((nX/2)×0.500)
5.00×10-3=2×((nX/2)×0.500)
5.00×10-3=nX×0.500
nX=5.00×10-3 / 0.500 = 10.0×10-3 mol = 1.00×10-2 mol
問3:(a)正解④ (b)正解② (c)正解①
a:正解④
<問題要旨>
同位体存在比を考慮した質量スペクトルの予測問題です。クロロメタン CH3Cl の分子イオンピークは、塩素の同位体 35Cl (存在比 3) と 37Cl (存在比 1) の影響を受けます。
<選択肢>
クロロメタン CH3Cl の分子イオンを考えます(Cは 12C, Hは 1H と仮定)。
・35Cl を含むイオン (M+): 12C1H335Cl+
相対質量: 12+(1×3)+35=50
相対強度: 35Cl の存在比に比例 ∝3
・37Cl を含むイオン (M+2): 12C1H337Cl+
相対質量: 12+(1×3)+37=52
相対強度: 37Cl の存在比に比例 ∝1
したがって、質量スペクトルでは、相対質量 50 のピークと相対質量 52 のピークが、約 3:1 の強度比で観測されるはずです。
選択肢のグラフの中で、相対質量 50 のピーク強度 (M) と 52 のピーク強度 (M+2) が M:(M+2)≈3:1 となっているものを探します。
① 51 が最大。
② 50 が最大だが、52 がほぼない。
③ 52 が最大。 50:52≈30:100≈0.3:1 。
④ 50 が最大。 50:52≈100:30≈3.3:1≈3:1 。
⑤ 50 と 52 がほぼ 1:1。
⑥ 52 が最大。 50:52≈35:100≈0.35:1 。
相対質量 50 と 52 のピーク比が約 $3:1$ となっているのは④です。
b:正解②
<問題要旨>
高分解能質量分析の概念を用いた問題です。質量数が同じ「28」でも、構成原子の精密な質量(12C=12.000, 1H=1.008, 14N=14.003, 16O=15.995 )の違いにより、分子イオンの精密な相対質量はわずかに異なります。この値を計算し、スペクトル(図4)と対応付けます。
<選択肢>
各分子イオンの精密な相対質量を計算します(12C=12.000 とします)。
- CO+
構成原子: 12C+16O
相対質量: 12.000+15.995=27.995 - C2H4+
構成原子: 2×12C+4×1H
相対質量: (2×12.000)+(4×1.008)=24.000+4.032=28.032 - N2+
構成原子: 2×14N
相対質量: 2×14.003=28.006
相対質量は、CO+(27.995)<N2+(28.006)<C2H4+(28.032) の順になります。
図4のスペクトルの横軸は左から右に相対質量が大きくなるので、
ア(最も小さい):CO+
イ(中間):N2+
ウ(最も大きい):C2H4+
と対応します。
①【誤】
②【正】ア=CO+, イ=N2+, ウ=C2H4+
③【誤】
④【誤】
⑤【誤】
⑥【誤】
c:正解①
<問題要旨>
質量分析における分子の開裂(フラグメンテーション)の予測問題です。分子イオンピークと、指定された位置(図5)で切断された場合に生じる特徴的な断片イオンのピークが、どの相対質量に現れるかを予測します。
<選択肢>
メチルビニルケトン CH3−CO−CH=CH2 の主なイオンの相対質量を計算します(C=12,H=1,O=16 )。
- 分子イオン (M+)
CH3COCH=CH2+
相対質量(分子量): 70
→ 相対質量 70 にピーク(分子イオンピーク)が予想されます。 - 断片イオン(左側 H3C−∣∣−CO… で切断)
・CH3+
相対質量: 12+3=15
・COCH=CH2+
相対質量: (12+16)+(12+1)+(12+2)=55
→ 相対質量 15 と 55 にピークが予想されます。 - 断片イオン(右側 …CO−∣∣−CH=CH2 で切断)
・CH3CO+ (アセチルイオン)
相対質量: (12+3)+12+16=43
・CH=CH2+
相対質量: (12+1)+(12+2)=27
→ 相対質量 43 と 27 にピークが予想されます。
したがって、主要なピークとして 15, (27), 43, 55, 70 にピークが現れると予想されます(強度は異なります)。
選択肢のスペクトル(強度が10未満は省略)を調べます。
① 15, 43, 55, 70 にピークあり。
② 15, 43, 70 にピークあり(55 がない)。
③ 15, 55, 70 にピークあり(43 がない)。
④ 15, 70 にピークあり(43 も 55 もない)。
予想される主要な断片イオン(15, 43, 55)と分子イオン(70)がすべて(10以上の強度で)存在するのは①のみです。