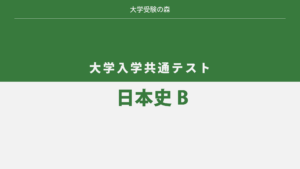解答
解説
第1問
問1:正解③
<問題要旨>
問題文に記述された奈良時代の人物が起こした兵乱の時期を、年表から特定する問題です。問題文の「光明皇太后と結びついて権力を握り太政大臣に相当する地位に就いた人物」とは藤原仲麻呂(恵美押勝)を指し、彼が起こした兵乱は764年の藤原仲麻呂の乱(恵美押勝の乱)です。この出来事が年表のa~dのどの期間に起こったかを判断します。
<選択肢>
①【誤】
aは、737年(藤原四子の死)から752年(大仏開眼供養会)までの期間です。藤原仲麻呂の乱(764年)はこの期間には含まれません。
②【誤】
bは、752年(大仏開眼供養会)から757年(養老律令の施行)までの期間です。藤原仲麻呂の乱(764年)はこの期間には含まれません。
③【正】
cは、757年(養老律令の施行)から766年(道鏡が法王になる)までの期間です。藤原仲麻呂の乱は764年に起きているため、この期間に含まれます。
④【誤】
dは、766年(道鏡が法王になる)から780年(伊治呰麻呂の乱)までの期間です。藤原仲麻呂の乱(764年)はこの期間には含まれません。
問2:正解⑤
<問題要旨>
中世から近世にかけての日本と朝鮮との関係を示す3つの出来事を、年代順に正しく配列する問題です。それぞれの出来事がいつ起こったかを特定する必要があります。
<選択肢>
Iの出来事は、1510年に朝鮮の三浦(さんぽ)で起きた日本人の反乱(三浦の乱)です。
IIの出来事は、豊臣秀吉による朝鮮侵略(文禄・慶長の役、1592~98年)の際に、朝鮮の金属活字が日本にもたらされたことを指します。
IIIの出来事は、1419年に朝鮮が倭寇の根拠地とみなした対馬を攻撃した事件(応永の外寇)です。
これらの出来事を年代順に並べると、
応永の外寇(1419年)→ III
三浦の乱(1510年)→ I
文禄・慶長の役(1592~98年)→ II
となるため、正しい順序はIII→I→IIです。
①【誤】I→II→IIIの順ではありません。
②【誤】I→III→IIの順ではありません。
③【誤】II→I→IIIの順ではありません。
④【誤】II→III→Iの順ではありません。
⑤【正】III→I→IIの順であり、正しい配列です。
⑥【誤】III→II→Iの順ではありません。
問3:正解④
<問題要旨>
戦国時代の商人や流通に関する二つの史料を読み解き、その内容に関する記述X・Yの正誤を判断する問題です。史料を正確に読解する能力が問われます。
<選択肢>
X:史料1は六角氏の命令です。「石寺新市」という特定の城下町では楽市(自由な商業活動)を認める一方、「濃州ならびに当国中」(美濃国と近江国の他の地域)では座に所属しない商人の活動を禁じ、その荷物を没収するとしています。つまり、楽市令は領内全域に出されたわけではなく、座の特権は石寺新市以外では保護されています。したがって、Xの「六角氏が治める近江国・美濃国には楽市令が出され」という記述は、適用範囲を誤解しており、誤りです。
Y:史料2は織田信長の命令です。「諸役あるべからず」とは、「(これまで通り)諸々の税を免除する」という意味です。つまり、大滝神郷紙座が持っていた税の免除特権を、信長が改めて認めた(安堵した)命令です。したがって、Yの「税免除の特権を撤廃した」という記述は、史料の内容と正反対であり、誤りです。
以上より、XもYも誤りです。
①【誤】X正 Y正ではありません。
②【誤】X正 Y誤ではありません。
③【誤】X誤 Y正ではありません。
④【正】X誤 Y誤であり、正しい組み合わせです。
問4:正解①
<問題要旨>
江戸時代初期の印刷技術と、徳川家康の出版事業に関する文章の空欄補充問題です。空欄アには活字印刷を伝えた主体、空欄イには家康が愛読した『吾妻鏡』の説明が入ります。
<選択肢>
①【正】
ア:16世紀後半にヨーロッパ式の活字印刷術を日本に伝えたのは、キリスト教の布教活動を行ったイエズス会の宣教師たちです。彼らが伝えた印刷機で印刷されたキリシタン版は、日本の印刷史において重要です。
イ:『吾妻鏡』は、鎌倉時代に幕府によって編纂された歴史書で、源頼朝の挙兵から鎌倉時代中期までの出来事を記しています。したがって、「鎌倉幕府の成立から中期までの時期を扱った史書である」という説明は正しいです。
よって、この組み合わせは正しいです。
②【誤】
イの『吾妻鏡』の説明が「鎌倉幕府の滅亡とその後の内乱を題材とした軍記物」となっていますが、これは『太平記』などの内容であり、誤りです。
③【誤】
アが「オランダ東インド会社の社員」となっています。オランダとの本格的な交易が始まるのは17世紀以降であり、16世紀後半に活字印刷を伝えた主体としては不適切です。
④【誤】
ア、イのいずれの説明も誤っています。
問5:正解①
<問題要旨>
江戸時代後期の学問や文芸で活躍した人物について、説明文X・Yと人名a~dを正しく組み合わせる問題です。
※本問は、大学入試センター発表の正解と、歴史的事実に基づく論理的な解答が食い違っています。ここでは歴史的事実に基づき、各選択肢の正誤を解説します。
説明文の分析:
X「江戸に蘭学塾の芝蘭堂を開いて門弟を育成し、蘭学の入門書である『蘭学階梯』を著した」人物は、大槻玄沢です。
Y「江戸町人の風俗や恋愛を描いた人情本で人気を博したが、天保の改革で処罰を受けた」人物は、為永春水です。
人名の分析:
aは緒方洪庵、bは大槻玄沢、cは為永春水、dは滝沢(曲亭)馬琴です。
<選択肢>
①【誤】(大学入試センターの発表では正解)
X-aの組み合わせは、X(大槻玄沢)とa(緒方洪庵)を結びつけており、誤りです。緒方洪庵は、大坂に蘭学塾の適塾を開いた人物です。Y-cの組み合わせは、Y(為永春水)とc(為永春水)であり、正しいです。しかし、X-aが誤りであるため、この選択肢は全体として誤りです。
②【誤】
X-aの組み合わせが誤りです。また、Y-dの組み合わせは、Y(為永春水)とd(滝沢馬琴)を結びつけており、誤りです。滝沢馬琴は読本作家として知られています。
③【正】(論理的に正しい選択肢)
X-bの組み合わせは、X(大槻玄沢)とb(大槻玄沢)であり、正しいです。Y-cの組み合わせは、Y(為永春水)とc(為永春水)であり、正しいです。両方の組み合わせが正しいため、これが論理的な正解となります。
④【誤】
X-bの組み合わせは正しいですが、Y-dの組み合わせが誤っています。
問6:正解②
<問題要旨>
明治時代の歴史書編纂事業に関する史料を読み、その内容と近代の印刷・出版に関する記述a~dの正しい組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
a【正】
史料3には、「活版印刷器械の便開け、著書はなはだ盛んなるがごときも、実は士族糊口のためにするに過ぎず」とあります。これは、活版印刷が普及して出版が盛んになり、士族が生活のために出版活動に関わっていたことを示しており、記述は正しいです。
b【誤】
史料3には、「修史の材料となるべき書に印本はなはだ少なし」「官撰官訳の書を除けば良書なし」とあり、歴史編纂の材料となる良質な書物が『群書類従』以外には乏しいと述べられています。したがって、記述は史料の内容と合致せず、誤りです。
c【誤】
円本や文庫本が広く普及し、大衆文化の形成に大きな影響を与えたのは、主に大正時代後期から昭和時代にかけてのことです。したがって、明治時代に関する記述としては不適切であり、誤りです。
d【正】
明治時代には、文明開化の中で知識や情報を伝えるメディアとして日刊新聞や雑誌が次々と創刊され、自由民権運動などを背景に民間の言論活動が活発化しました。記述は正しいです。
以上から、正しい記述はaとdです。
①【誤】cが誤りです。
②【正】aとdの組み合わせであり、正しいです。
③【誤】bとcが誤りです。
④【誤】bが誤りです。
第2問
問1:正解①
<問題要旨>
弥生時代から古墳時代にかけての調理に使われた土器、甕(かめ)と甑(こしき)の名称と用途を、写真から判断する問題です。それぞれの土器の特徴を理解しているかが問われます。
<選択肢>
X:写真2の土器は、丸い胴体を持ち、下部外面にすすが付着しています。これは、火にかけて煮炊きに用いたことを示す痕跡です。このような特徴を持つ土器は甕(かめ)と呼ばれます。したがって、「写真2の土器は甕で、食品を煮るために用いられた」という説明は正しいです。
Y:写真3の土器は、底部中央に穴が開けられています。これは、下の甕で沸かしたお湯の蒸気を通すための構造です。このような特徴を持つ土器は甑(こしき)と呼ばれ、米などを蒸すために用いられました。したがって、「写真3の土器は甑で、食品を蒸すために用いられた」という説明は正しいです。
以上より、XもYも正しい記述です。
①【正】X正 Y正であり、正しい組み合わせです。
②【誤】X正 Y誤ではありません。
③【誤】X誤 Y正ではありません。
④【誤】X誤 Y誤ではありません。
問2:正解①
<問題要旨>
『養老令』の条文と、平城宮跡から出土した木簡の情報を基に、8世紀の調(ちょう)として納められた塩に関する記述a~dの正しい組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
a【正】
史料1の『養老令』には、調として雑物を納める場合、塩は三斗と規定されています。表1の木簡の事例を見ると、若狭国、尾張国、紀伊国などからの納入量はすべて「3斗」となっており、令の規定通りの量が納入されていたことがわかります。したがって、この記述は正しいです。
b【誤】
調は、成人男性(正丁・次丁など)に課された税であり、女性は課税対象外でした。表1に見える納入者の名前もすべて男性名です。したがって、「男女が負担していた」という記述は誤りです。
c【正】
表1に挙げられている納入国(若狭国、尾張国、紀伊国、淡路国、備前国)は、すべて海に面しており、製塩が可能な地域です。塩が海に面した国々から納められていたと考えるのは自然であり、記述は正しいです。
d【誤】
表1の事例に「尾張国」があります。尾張国(現在の愛知県西部)は、都(平城京)から見て東側に位置します。したがって、「都より東側の国からは納入されなかった」という記述は誤りです。
以上から、正しい記述はaとcです。
①【正】aとcの組み合わせであり、正しいです。
②【誤】dが誤りです。
③【誤】bが誤りです。
④【誤】bとdが誤りです。
問3:正解②
<問題要旨>
古代日本の女性の服装に関する3つの事柄を、年代順に正しく配列する問題です。それぞれの事象がどの時代に対応するかを特定する必要があります。
<選択肢>
I:高松塚古墳の壁画は、飛鳥時代末期~奈良時代初頭(7世紀末~8世紀初頭)に描かれたものです。大陸(唐や高句麗)の文化的影響が色濃く見られます。
III:鳥毛立女屏風は、正倉院に収蔵されている奈良時代(8世紀)の文物です。描かれた女性の服装は、当時の唐の様式を反映しています。
II:寝殿造の邸宅や、裳(も)を長く引く女房装束(十二単)は、国風文化が栄えた平安時代中期(10~11世紀)を代表する貴族の住居と服装です。
これらの出来事を年代順に並べると、
高松塚古墳壁画の制作(7世紀末~8世紀初頭)→ I
鳥毛立女屏風の制作(8世紀)→ III
女房装束の着用(10世紀~)→ II
となるため、正しい順序はI→III→IIです。
①【誤】I→II→IIIの順ではありません。
②【正】I→III→IIの順であり、正しい配列です。
③【誤】II→I→IIIの順ではありません。
④【誤】II→III→Iの順ではありません。
⑤【誤】III→I→IIの順ではありません。
⑥【誤】III→II→Iの順ではありません。
問4:正解③
<問題要旨>
古代の乳製品である蘇(そ)について、会話文、木簡の写真、貴族の日記(史料2)の内容を踏まえ、誤っている記述を一つ選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
写真4の木簡には、出雲国から蘇が貢納されたことが記されています。会話文では、『延喜式』で蘇の貢納が免除されていた国々の中に、出雲国は含まれていません。したがって、出雲国が蘇を納めていたことは『延喜式』の規定と矛盾せず、この記述は正しいです。
②【正】
史料2では、西海道(九州地方)から蘇がまだ献上されていない、とあります。会話文では、『延喜式』の規定で「九州の国や島は大宰府を通じて納めていた」とあり、九州が蘇の貢納地であったことがわかります。両者の内容は合致しており、この記述は正しいです。
③【誤】
会話文によると、『延喜式』に定められた蘇の貢納期限は11月まででした。一方、史料2の出来事は永延2(988)年正月20日、つまり年が明けてからです。その時点で西海道からの蘇が「いまだ献ぜざる」状態であったことから、貢納期限が守られていなかったことがわかります。したがって、「貢納期限が守られていたことが読み取れる」というこの記述は明確に誤りです。
④【正】
史料2には、摂政・藤原兼家の宴会に際して、「内より」(天皇のもとから)蘇が下賜される予定であったことが記されています。これは、蘇の授受を通じて天皇と有力貴族との間に結びつきがあったことを示すものであり、この記述は正しいです。
問5:正解⑥
<問題要旨>
古代の食物に関する3つの資料(木簡、『日本三代実録』、『枕草子』)について、その特徴や内容を説明する空欄ア、イ、ウに当てはまる文の正しい組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
ア(木簡の特徴):木簡は荷札やメモとして使われた実用の品であり、一つ一つの情報量は少ないですが、書かれた内容は意図的に改変されることが少なく、当時の社会経済を知る上で史料的価値が高いとされています。したがって、b「1点ごとに含まれている情報の量は少ないが、意図的に内容が改変されていることは少ない」が適切です。
イ(『日本三代実録』の内容例):『日本三代実録』は六国史の一つで、858年から887年までの出来事を記した正史です。cの応天門の変(866年)で罰せられた伴善男の財産が没収された記事は、この年代に含まれる事件であり、正史の記述としてふさわしい内容です。一方、dの藤原陳忠の話は『今昔物語集』に収められた説話であり、『日本三代実録』の記述ではありません。したがって、cが適切です。
ウ(『枕草子』の時代背景):『枕草子』が書かれた平安時代中期(10世紀末~11世紀初頭)は、遣唐使が廃止(894年)された後であり、国家間の正式な朝貢関係はありませんでした。しかし、唐や宋の商人たちの来航による私的な交易は続いており、それらを通じて中国の文物がもたらされていました。したがって、f「唐・宋などの商人の来航」が当時の文化流入の背景として適切です。
以上より、正しい組み合わせはア-b、イ-c、ウ-fであり正解は⑥です。
第3問
問1:正解②
<問題要旨>
中世の朝廷に関する3つの出来事を、年代順に正しく配列する問題です。それぞれの出来事が鎌倉時代、南北朝時代、室町時代のいずれに属するかを判断します。
<選択肢>
I:朝廷が北面の武士に加えて西面の武士を設置し、幕府との戦いに踏み切ったのは、後鳥羽上皇が承久の乱(1221年)を起こした際の出来事です。これは鎌倉時代中期にあたります。
III:悪党は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけて、荘園や公領で年貢納入を拒否したり、武力で支配に抵抗したりした武士たちのことです。その活動が活発化した鎌倉時代後期に、朝廷がその取り締まりを幕府に要請しました。
II:朝廷が持っていた京都の支配権(市政権)や、諸国に段銭(たんせん)を課す権限が幕府の管轄下に置かれたのは、室町幕府、特に3代将軍足利義満の時代(14世紀後半)に幕府の権力が朝廷を圧倒していく過程での出来事です。
これらの出来事を年代順に並べると、
承久の乱(1221年)→ I
悪党の活動活発化(鎌倉時代後期)→ III
室町幕府の権力確立(14世紀後半)→ II
となるため、正しい順序はI→III→IIです。
よって正解は②です。
問2:正解③
<問題要旨>
鎌倉時代の永仁の徳政令(史料1)と、それを根拠とした南北朝時代の訴状(史料2)を読解し、関連する記述a~dの正しい組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
a【正】
史料1には「非御家人ならびに凡下の輩買得の地に至りては、年紀の遠近を謂わず、本主これを取り返すべし」とあります。これは、土地を買ったのが非御家人や庶民である場合、元の持ち主(本主)は、誰であっても、年数に関係なくその土地を無償で取り戻せる、と規定したものです。したがって、この記述は史料を正しく読み取っています。
b【誤】
史料1の条文では、元の持ち主を「本主」と記すのみで、「御家人であれば」という限定はありません。実際に、史料2では御家人ではない名主・百姓がこの法令を根拠にしています。したがって、「本主が御家人であれば」と限定するこの記述は誤りです。
c【誤】
史料2の下久世荘の名主・百姓は、徳政令の条文を根拠として、自分たちが売却地を取り戻した行為の正当性を主張しています。これは条文の規定を自分たちの状況に当てはめて適用したものであり、「読み換え」というよりは直接的な根拠としています。したがって、この記述は不適切です。
d【正】
史料2で、名主・百姓は「永仁五年三月六日に鎌倉幕府が立法した徳政令と、…指令書には、『非御家人…売主これを取り返すべし』と見えるからです」と述べ、徳政令の規定を明確な根拠として、訴えの棄却を求めています。したがって、この記述は正しいです。
以上から、正しい記述はaとdです。
①【誤】cが誤りです。
②【正】aとdの組み合わせであり、正しいです。
③【誤】bとcが誤りです。
④【誤】bが誤りです。
問3:正解①
<問題要旨>
南北朝時代の文化を担った人物について、説明文X・Yと人名a~dを正しく組み合わせる問題です。
説明文の分析:
X「南朝の立場から皇位継承の正統性を説いた『神皇正統記』を著した」人物は、南朝に仕えた公家の北畠親房です。
Y「連歌の規則書として『応安新式』を制定し、『菟玖波集』を編集した」人物は、室町幕府の有力者でもあった二条良基です。彼は連歌の大成者として知られます。
人名の分析:
aは北畠親房、bは一条兼良(室町中期の学者)、cは二条良基、dは宗祇(室町後期の連歌師)です。
<選択肢>
①【正】
X-aの組み合わせは、X(北畠親房)とa(北畠親房)で正しいです。Y-cの組み合わせは、Y(二条良基)とc(二条良基)で正しいです。したがって、この選択肢が正解です。
②【誤】
Y-dの組み合わせが誤りです。宗祇は『新撰菟玖波集』を編纂しましたが、『菟玖波集』や『応安新式』は二条良基によります。
③【誤】
X-bの組み合わせが誤りです。一条兼良は『公事根源』などを著しましたが、『神皇正統記』の著者ではありません。
④【誤】
X-b、Y-dのいずれの組み合わせも誤っています。
問4:正解④
<問題要旨>
戦国大名が制定した分国法(史料3~5)と、その内容を説明した文X・Yを正しく組み合わせる問題です。
史料の分析:
史料3(朝倉氏):有力な家臣は城下町(一乗谷)に集住させ、領国内に勝手に城を構えることを禁じています。これは家臣団の統制と中央集権化を目的としています。
史料4(今川氏):家臣が他国の者と勝手に婚姻関係を結ぶことを禁じています。これは、家臣が領国外の勢力と結びつき、自立化することを警戒したものです。
史料5(伊達氏):喧嘩は理由を問わず双方を処罰する(喧嘩両成敗)と定めています。これは、家臣同士が私的な武力で争うことを禁じ、大名による裁判で紛争を解決させることを目的としています。
説明文の分析:
X「この戦国大名は、家臣が領国外の武士と結びつくことを警戒した」は、史料4の内容に合致します。
Y「この戦国大名は、家臣同士が自らの武力で争うことを禁止した」は、史料5の喧嘩両成敗の規定に合致します。
<選択肢>
①【誤】X-史料3, Y-史料4の組み合わせではありません。
②【誤】X-史料3, Y-史料5の組み合わせではありません。
③【誤】X-史料4, Y-史料3の組み合わせではありません。
④【正】X-史料4, Y-史料5の組み合わせであり、正しいです。
⑤【誤】X-史料5, Y-史料3の組み合わせではありません。
⑥【誤】X-史料5, Y-史料4の組み合わせではありません。
問5:正解④
<問題要旨>
中世社会の特色として、「実力を行使して問題を解決しようとする事例」に最も当てはまるものを選択肢から選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
所領を一期分(一代限りの相続)にすることは、法的な相続の形態の一つであり、一族内の紛争を避けるための知恵ではありますが、直接的な武力や腕力といった「実力行使」にはあたりません。
②【誤】
地頭による荘園侵略に対して、荘園領主が幕府に下地中分(土地を分割して互いの支配権を確定させる方法)の裁定を求めることは、幕府の法秩序(公権力)に頼った解決方法であり、「実力行使」とは正反対の手段です。
③【誤】
戦国大名が、豊臣秀吉など天下人の発令した惣無事令(私的な戦闘の禁止)を受け入れることは、より大きな権威に従うことであり、自らの実力行使を放棄することを意味します。
④【正】
村同士の用水争いにおいて、相手の村の用水路の取水口を破壊し、自分たちの田に水を引こうとする行為は、法や話し合いによらず、直接的な物理的手段で目的を達成しようとするものであり、「実力を行使して問題を解決しようとする」典型的な事例です。
第4問
問1:正解②
<問題要旨>
室町時代から江戸時代にかけての貿易品や衣料の変化に関する文章の空欄ア、イ、ウに当てはまる語句の正しい組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
ア、イ:会話文に「庶民も、それ以前のようにイを使った衣料から、次第にアを使った衣料を着るようになっていった」とあります。中世までの庶民の衣料の主な素材は麻や苧(からむし)(イ)でしたが、近世になると、より肌触りが良く暖かい木綿(ア)が普及しました。木綿は朝鮮などから輸入されていましたが、江戸時代前期までに国内生産が盛んになりました。したがって、アは木綿、イは麻・苧です。
ウ:16世紀半ばから17世紀初めにかけて、日本は世界有数の鉱産物産出国でした。特に、中国産の生糸などを大量に輸入するための対価として、石見銀山などで増産された銀(ウ)が大量に輸出されました。
以上より、ア:木綿、イ:麻・苧、ウ:銀の組み合わせが正しいです。
①【誤】ウが金になっています。
②【正】ア:木綿、イ:麻・苧、ウ:銀の組み合わせであり、正しいです。
③【誤】アとイが逆になっています。
④【誤】アとイが逆で、ウも異なっています。
問2:正解⑤
<問題要旨>
江戸幕府がポルトガル船の来航を禁止する(1639年)に至るまでの、キリスト教禁止や貿易制限に関する出来事を年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
III:江戸幕府は、1612年に直轄地に対してキリスト教禁止令(禁教令)を出し、翌1613年にはこれを全国に拡大し、宣教師や信徒への迫害を始めました。これが一連の鎖国政策の初期段階となります。
I:1616年に、幕府はヨーロッパ船の寄港地を平戸と長崎の2港に限定しました。これはキリスト教の布教を伴う貿易を管理・制限するための措置です。
II:島原・天草一揆は、1637年から1638年にかけて起きた、キリシタン弾圧や重税に苦しむ農民らによる大規模な反乱です。幕府はこの反乱にキリスト教が深く関わっていると考え、禁教と貿易統制を一層強化しました。
これらの出来事を年代順に並べると、
キリスト教禁止令の発布(1612~13年)→ III
ヨーロッパ船の寄港地制限(1616年)→ I
島原・天草一揆(1637~38年)→ II
となるため、正しい順序はIII→I→IIです。
よって正解は⑤です。
問3:正解③
<問題要旨>
江戸時代の俵物(干しあわび、いりこ、ふかひれなど)の輸出に関する記述X・Yの正誤を判断する問題です。
<選択肢>
X【誤】
俵物の輸出が促進された背景には、金・銀などの貴金属の海外流出を防ぐ目的がありました。17世紀末から18世紀にかけて、長崎貿易では生糸や薬種などの輸入代価として多額の金銀が支払われ、国内の通貨供給に影響を及ぼすほどでした。そこで、幕府(特に徳川吉宗の享保の改革など)は、金銀に代わる輸出品として、中国で需要のあった俵物などの生産と輸出を奨励しました。「中国からの来航船が減り、貿易額も減少したため」ではなく、貿易の赤字(金銀の流出)を是正するためでした。したがって、この記述は誤りです。
Y【正】
俵物の主要な産品である干しあわびや、昆布などは、蝦夷地(現在の北海道)の重要な産物でした。俵物の輸出が奨励されたことで、松前藩や場所請負人による蝦夷地での海産物生産が活発化しました。したがって、この記述は正しいです。
以上より、Xは誤り、Yは正しい記述です。
①【誤】X正 Y正ではありません。
②【誤】X正 Y誤ではありません。
③【正】X誤 Y正であり、正しい組み合わせです。
④【誤】X誤 Y誤ではありません。
問4:正解④
<問題要旨>
江戸時代後期の風俗を記した『守貞謾稿』の砂糖に関する記述(史料1)を読み、その内容として最も適当なものを選択肢から選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
史料1には「長崎入舶の蘭」「支那よりは」とあり、砂糖が長崎経由でオランダや中国から輸入されていたことがわかります。江戸時代の対外貿易は、原則として長崎口、対馬口、薩摩口、松前口の四口に限定されていました。すべての藩が直接貿易を行っていたわけではないため、「異国と貿易を行っていたすべての藩を通じて」という記述は誤りです。
②【誤】
史料1は、砂糖の輸入元や国内の産地について述べたものであり、幕府の専売制やその改変については言及していません。したがって、この記述は史料からは読み取れません。
③【誤】
史料1には、黒糖について「薩摩より琉球産を渡すのみ」とあります。これは、琉球産の黒糖が薩摩経由で日本本土にもたらされていたことを意味します。薩摩から琉球へ輸出していたわけではないので、記述は誤りです。
④【正】
史料1には、国産の白糖の産地として「讃岐」「阿波」「駿河・遠江・三河・和泉」、黒糖の産地として「紀伊・土佐」などが挙げられています。これらは幕府領や様々な大名の藩領にまたがっています。したがって、「一部の藩領でも白砂糖や黒砂糖が生産されていた」という記述は、史料の内容と合致しており、正しいです。
問5:正解③
<問題要旨>
1835年時点の上野国桐生・下野国足利周辺の織物業に関する史料を読み、その地域の状況と社会背景に関する記述a~dの正しい組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
a【誤】
史料2には、この地域の織物業は「昔は農業の片手間に女性が蚕飼をして…生計を立てていた」とあり、当初は農家の副業であったことがわかります。その後、専業化が進んだとあるため、「江戸時代初期から織物を専業とする者が集住していた」という記述は史料の内容と合わず、誤りです。
b【正】
史料2が書かれたのは1835年(19世紀)です。その中で、「最近は…蚕飼などはやめて、…機織り屋はそれぞれ機織り女などを大勢抱えて生業としている」とあります。これは、農家の副業から、原料を他から仕入れ、労働者を雇用して生産する問屋制家内工業へと発展し、専業化が進んでいたことを示しています。記述は正しいです。
c【正】
史料2に描かれているような、農村における商品生産の発展は、江戸時代後期に広く見られた現象です。村役人などを務める有力な百姓(豪農)の中には、地主経営で得た富をもとに、酒・醤油の醸造や織物業などのマニュファクチュアを経営し、商品生産や流通の担い手として経済的に成長する者も現れました。記述は当時の社会経済状況として正しいです。
d【誤】
定免法は、過去数年間の収穫高を基準に年貢率を一定期間固定する制度で、主に享保の改革(18世紀前半)の際に幕府財政の安定化を目指して導入されました。史料が指す織物業の繁栄期(18世紀後半~19世紀)に「新たに」採用された年貢増徴策ではありません。したがって、記述は誤りです。
以上から、正しい記述はbとcです。
①【誤】aが誤りです。
②【誤】aとdが誤りです。
③【正】bとcの組み合わせであり、正しいです。
④【誤】dが誤りです。
第5問
問1:正解④
<問題要旨>
幕末から明治初期にかけての状況について述べた文章の空欄ア、イに当てはまる語句の正しい組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
ア:1858年の日米修好通商条約で開港が定められたのは、神奈川(横浜)、長崎、新潟、兵庫(神戸)、箱館の5港です。このうち、1859年に貿易が開始されたのは横浜、長崎、箱館の3港でした。したがって、空欄アには箱館が入ります。
イ:明治時代になると、まず官吏(役人)や軍人が制服として洋服を着用することが義務付けられました。これをきっかけに、次第に洋装が社会に広まっていきました。したがって、空欄イには官吏や軍人が入ります。
以上より、ア:箱館、イ:官吏や軍人の組み合わせが正しいです。
①【誤】アが兵庫、イが官営模範工場の工女になっています。
②【誤】アが兵庫になっています。
③【誤】イが官営模範工場の工女になっています。
④【正】ア:箱館、イ:官吏や軍人の組み合わせであり、正しいです。
問2:正解②
<問題要旨>
幕末の1865年と1867年における日本の輸入品目に関する2つのグラフを比較し、それに関する記述X・Yの正誤を判断する問題です。
<選択肢>
X【正】
グラフ1(1865年)とグラフ2(1867年)を比較すると、輸入総額は1,514万ドルから2,167万ドルへと増加しています。「艦船」の割合は6.27%から7.83%に、「小銃などの武器類」は7.04%から13.28%に上昇しています。輸入総額と割合が共に増加していることから、武器類の輸入額が大きく増えたことがわかります。これは、幕府や諸藩が軍備の西洋化を急いでいた幕末期の国内情勢を反映しており、記述は正しいです。
Y【誤】
グラフ1から2にかけて輸入総額が増加した背景には、国内の政治的対立の激化に伴う武器輸入の増大などがあります。一方、「関税率が引き上げられた」のであれば、輸入品の価格が上昇し、輸入量はむしろ減少しようとします。実際に、幕末に結ばれた不平等条約では、日本に関税自主権がなく、関税率は低く抑えられていました。その後、1866年の改税約書で関税率はさらに引き下げられました。したがって、記述は誤りです。
以上より、Xは正しく、Yは誤りです。
①【誤】Yが誤りです。
②【正】X正 Y誤であり、正しい組み合わせです。
③【誤】Xが正しく、Yが誤りです。
④【誤】Xが正しいです。
問3:正解④
<問題要旨>
明治初期に設立された国立銀行に関する史料を読み、その内容と合致する記述を選ぶ問題です。
<選択肢>
①【誤】
当初の国立銀行条例(1872年)では、アメリカの制度にならい、国立銀行が発行する銀行券(紙幣)は正貨(金貨)との兌換(だかん)が義務付けられていました(兌換銀行券)。しかし、この規定が厳しく、銀行設立が進まなかったため、後に条例が改正されます。したがって、記述は誤りです。
②【誤】
国立銀行は、条例に基づいて設立された民間の銀行で、それぞれが紙幣発行権を持っていました。史料にも、金禄公債をもとに「国立銀行設立を申請する者夥しく」「多数の乱立をみたり」とあり、多くの国立銀行が設立され、それぞれが紙幣を発行したことがわかります。紙幣発行権が第一国立銀行だけに与えられていたわけではありません。記述は誤りです。
③【誤】
史料には、「政府の命令同様の慫慂にて、三井組、小野組発起し、…これを第一国立銀行とす」とあります。これは、政府が三井組や小野組といった有力な商人に働きかけて第一国立銀行を設立させたことを意味します。彼らに対抗するためではありません。記述は誤りです。
④【正】
史料には、1876年の秩禄処分で華族・士族に交付された金禄公債について、「この公債証書をもって、国立銀行設立を申請する者夥しく(おびただしく)」とあります。これは、秩禄を失った華族・士族が、受け取った公債を資本金として国立銀行を設立し、新たな収入源を得ようとした動きを示しています。記述は史料の内容と合致しており、正しいです。
問4:正解②
<問題要旨>
明治時代の文化活動について、「西洋文明の影響を受けつつ、同時に日本の伝統を引き継いでいる」という視点から、正しい記述の組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
a【正】
アメリカから来日したフェノロサは、岡倉天心らとともに、西洋美術偏重の風潮の中で見捨てられかけていた日本の伝統美術の価値を再評価し、その保護・復興に尽力しました。これは西洋人の視点から日本の伝統が再評価された例であり、記述は正しいです。
b【誤】
政教社は、三宅雪嶺、志賀重昂らが結成した団体で、雑誌『日本人』を発行し、国粋主義の立場から政府の欧化政策を批判しました。洋学者の加藤弘之は、社会進化論を唱えるなど、欧化主義的な立場の人物であり、政教社には参加していません。記述は誤りです。
c【誤】
1890年に公布された民法(旧民法)は、家父長権が弱いなど日本の伝統的な家制度にそぐわないと批判され、施行が延期されました(民法典論争)。この旧民法が模範としたのは、ドイツ民法ではなくフランス民法でした。したがって、記述は誤りです。
d【正】
明治政府は1872年に、西洋にならって太陽暦を採用し、それまでの太陰太陽暦(旧暦)を廃止しました。しかし、農業など季節と密接に関わる農村部では、旧暦に基づく年中行事や生活習慣が長く根強く残りました。これは、西洋の制度と日本の伝統的慣習が併存した例であり、記述は正しいです。
以上から、正しい記述はaとdです。
①【誤】cが誤りです。
②【正】aとdの組み合わせであり、正しいです。
③【誤】bとcが誤りです。
④【誤】bが誤りです。
第6問
問1:正解⑤
<問題要旨>
第一次世界大戦後の国際条約に関する三つの史料を読み、ワシントン会議(1921~22年)で調印された条約(X)と、廃棄された条約(Y)を正しく特定する問題です。
<選択肢>
史料1:「両締盟国」(二国間)が、一方が攻撃された場合には「協同して戦闘に当り」、講和も合意の上で行うという内容の軍事同盟です。これは、1902年に結ばれ、ワシントン会議で失効した日英同盟の条文の特徴を示しています。
史料2:「国際紛争を解決する手段としての戦争を、放棄する」という趣旨の多国間条約です。これは、第一次世界大戦後のパリ講和会議で設立が合意された国際連盟の規約の内容です。
史料3:「主力艦建造計画を廃止」し、建造できるトン数に制限を設けるという内容です。これは、ワシントン会議で調印された海軍軍備制限条約(主力艦の保有比率を米・英・日・仏・伊で定めたもの)の条文です。
したがって、
X(ワシントン会議で調印された条約)は史料3(ワシントン海軍軍縮条約)です。
Y(ワシントン会議で廃棄された条約)は史料1(日英同盟)です。
よって正解は⑤です。
問2:正解④
<問題要旨>
不戦条約(1928年)に調印した日本の内閣に関する正しい記述を選ぶ問題です。不戦条約に調印したのは、田中義一内閣です。
<選択肢>
①【誤】
幣原喜重郎を外相に起用し協調外交を展開したのは加藤高明内閣です。日ソ基本条約を結びソ連との国交を樹立したのも加藤高明内閣の時(1925年)です。
②【誤】
虎の門事件(1923年)の責任をとって総辞職したのは、山本権兵衛内閣です。
③【誤】
シベリア出兵(1918年)を決定したのは、寺内正毅内閣です。
④【正】
1925年に成立した普通選挙法に基づく最初の総選挙(第1回普通選挙)は、1928年に田中義一内閣のもとで実施されました。不戦条約調印も同年の出来事であり、この記述は正しいです。
問3:正解③
<問題要旨>
満州事変勃発後の1932年1月に、日本の海軍省・陸軍省・外務省が作成した中国問題処理の方針(史料4)を読み、その内容に関する記述X・Yの正誤を判断する問題です。
<選択肢>
X【誤】
史料4には、「満蒙の治安維持及び満鉄以外の鉄道保護は、主として中国側の警察ないし警察的軍隊に当たらせる」とあります。これは、満鉄の警備は引き続き日本側(関東軍)が行うことを意味しています。したがって、「関東軍の行動に制限を加え、満鉄の警備を中国側に任せる」という記述は、史料の内容と合致せず、誤りです。
Y【正】
史料4の末尾に、「つとめて国際法ないし国際条約抵触を避け、特に満蒙政権問題に関する措置は九カ国条約などの関係上、できる限り中国側の自主的発意に基づいたような形式にするを可とす」とあります。これは、満州に新国家を樹立するにあたり、中国の領土保全などを定めた九カ国条約に違反しているとの国際的非難を避けるため、形式を整えようとしていたことを示しています。したがって、「日本政府内では…既存の条約などに違反しない方針が検討されていた」という記述は正しいです。
以上より、Xは誤り、Yは正しい記述です。
①【誤】X正 Y正ではありません。
②【誤】X正 Y誤ではありません。
③【正】X誤 Y正であり、正しい組み合わせです。
④【誤】X誤 Y誤ではありません。
問4:正解①
<問題要旨>
満州事変後、日本が国際的に孤立を深めていく時期(1930年代~日中戦争期)の外交に関する記述a~dの正しい組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
a【正】
1933年に国際連盟を脱退した日本は、同じくヴェルサイユ体制に不満を持つドイツやイタリアに接近し、1936年に日独防共協定、1937年に日独伊三国防共協定、そして1940年には日独伊三国同盟を締結しました。記述は正しいです。
b【誤】
1938年の第一次近衛声明で、近衛文麿内閣は、交渉相手としてきた蔣介石の国民政府を「対手とせず」と発表し、和平交渉の道を自ら閉ざしました。これは日中関係を改善するものではなく、戦争を長期化させる原因となりました。記述は誤りです。
c【正】
日本は、ドイツのヨーロッパでの快進撃を背景に、援蔣ルートの遮断や南方資源の獲得を目指す南進政策を進めました。その際、背後(北方)の脅威であるソ連との衝突を避けるため、1941年に日ソ中立条約を締結しました。記述は正しいです。
d【誤】
日米通商航海条約の廃棄を通告したのは、日本ではなくアメリカ側です。1939年、アメリカは日本の中国侵略に抗議して同条約の廃棄を通告し、日本の南進を経済的に牽制しました。記述は主語が誤っており、誤りです。
以上から、正しい記述はaとcです。
①【正】aとcの組み合わせであり、正しいです。
②【誤】dが誤りです。
③【誤】bが誤りです。
④【誤】bとdが誤りです。
問5:正解③
<問題要旨>
第二次世界大戦後、連合国軍(GHQ)の占領下にあった時期(1945~1952年)の日本の社会や文化について、誤っている記述を一つ選ぶ問題です。
<選択肢>
①【正】
GHQの指令により、戦争指導者や協力者と見なされた軍人・政治家・官僚・思想家などが公職から追放されました(公職追放)。記述は正しいです。
②【正】
アメリカ教育使節団の勧告を受けて、教育勅語に代わる理念として教育基本法が制定され、教育の機会均等、男女共学、六・三・三・四制の学校体系などが定められました。記述は正しいです。
③【誤】
戦時中の抑圧的な文化統制は終わり、占領期には自由な文化活動が活発になりました。特に、戦後の解放感や明るさを歌った歌謡曲(「リンゴの唄」など)は大流行しました。日本政府によって歌謡曲が規制されたという事実はありません。記述は誤りです。
④【正】
戦時中の言論統制は撤廃され、新聞や雑誌では自由な言論活動、特に戦前の体制や政府に対する批判が盛んになりました。一方で、GHQによる占領政策への批判はプレス=コードによって厳しく制限され、検閲の対象となりました。記述は正しいです。
問6:正解④
<問題要旨>
第二次世界大戦後に日本がアメリカとの間で結んだ3つの条約・協定を、年代順に正しく配列する問題です。
<選択肢>
II:MSA協定(日米相互防衛援助協定)は1954年に締結されました。これは、アメリカから経済的・軍事的援助を受ける見返りに、日本が自衛力の増強義務を負うことを定めたものです。
III:1960年に、旧安保条約が改定され、新日米安全保障条約が締結されました。この新条約では、在日米軍の配置や装備の重要な変更、日本からの戦闘作戦行動について、日米間の事前協議を行うことが定められました。
I:沖縄返還協定は1971年に調印され、1972年に沖縄の施政権が日本に返還されました。アメリカが「琉球諸島」の施政権を放棄する内容です。
これらの出来事を年代順に並べると、
MSA協定(1954年)→ II
新安保条約(1960年)→ III
沖縄返還協定(1971年)→ I
となるため、正しい順序はII→III→Iです。
よって正解は④です。
問7:正解②
<問題要旨>
サンフランシスコ平和条約以後の日本の外交関係に関する文章の空欄ア、イに当てはまる語句の正しい組み合わせを選ぶ問題です。
<選択肢>
ア:1951年のサンフランシスコ講和会議には、ソ連は参加しましたが、条約の内容に反対して調印を拒否しました。インドは、会議自体に招かれましたが、条約がソ連や中華人民共和国を排除していることなどを理由に参加しませんでした。したがって、空欄アにはソ連が入ります。
イ:1972年、田中角栄首相が訪中し、中華人民共和国との国交正常化が実現しました。この際に両国間で調印されたのは、日中共同声明です。この声明で、日本は中華人民共和国を中国の唯一の合法政府と承認し、両国間の「不正常な状態」の終結を宣言しました。日中平和友好条約が締結されるのは、1978年のことです。
以上より、ア:ソ連、イ:日中共同声明の組み合わせが正しいです。
①【誤】イが日中平和友好条約になっています。
②【正】ア:ソ連、イ:日中共同声明の組み合わせであり、正しいです。
③【誤】アがインド、イが日中平和友好条約になっています。
④【誤】アがインドになっています。